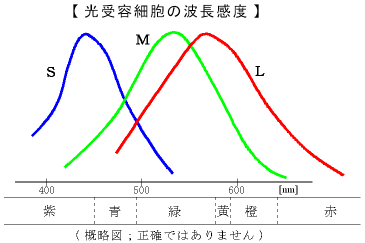1905年にアインシュタインが特殊相対論に関する最初の論文を発表したとき、彼は、操作的な方法論を援用しています。例えば、同時性を定義するときには、正確な時計を用意し、観測者同士が光による交信を行って時計の読みを比較するというやり方を示しています。また、運動する物体の長さも、観測を行う座標系において、ある時刻に物体の両端がどこに位置していたかによって決められると主張しました。こうした操作的な方法論は、物理学に詳しくない人にもとっつきやすく、ローレンツ収縮のような相対論特有の現象を簡単に導けるため、多くの相対論入門書でも使われてきました。このため、相対論と言えば、「運動する時計は遅れる」「運動する物体は縮む」と単純にイメージされることが少なくありません。
1905年論文では、操作的な方法論でローレンツ変換の式を導いた後、これを使って、マクスウェル方程式の変換公式やローレンツ力の本性(電荷に固定した座標系では電場から受ける力に等しい)を論じています。論文のタイトルが「運動物体の電気力学について」ですから、操作的な方法論に基づく前半の議論は、あくまでヒューリスティックなものであり、論文の主眼は後半にあったとも考えられます。しかし、後半の議論はやや平板な演繹的論法に終始しており、前半ほど迫力がないのも事実です。やはり、当時のアインシュタインは、特殊相対論を、操作的方法論によって構築される理論として捉えていたと言うべきでしょう。
私は、こうしたアインシュタインの解釈は、特殊相対論の本質に到達したものではないと考えます。(私の考えでは)特殊相対論の本当の意味は、1908年に、アインシュタインの大学時代の師であるミンコフスキによって明らかにされました。彼は、3次元空間に時間を加えた4次元時空(ミンコフスキ空間)の枠組みを使うと、相対論の多くの公式が直観的に理解できることを示しました。この枠組みによれば、時間も空間と同様の“拡がり”となり、「質点の運動」は「4次元時空内部の世界線」として表されます。相対論を時空の幾何学と見なすことに対して、アインシュタインは、初めのうちは難色を示していたようですが、一般相対論の研究に打ち込む1910年代前半には、時間と空間を統一した4次元座標で記述することに馴染んでいます。
ミンコフスキの議論では、4次元時空の枠組みは「天下り的な仮定(postulate)」として扱われていますが、現在では、相対論を理解する最も自然な方法論として捉えられています。例えば、「基礎物理法則は全ての座標系で同じ形で表される」という相対論の主張は、「ミンコフスキ空間には特権的な方位が存在しない」ことの直接的な帰結と解釈されます。「運動物体は縮む」といった操作的な方法論に基づく理解は、入門段階では受け入れやすいかもしれませんが、特殊相対論の意味を深く理解し、一般相対論へと進んでいくためには、あまり適切なものとは言えません。質問の最後にあるように、時間座標・空間座標の変換として捉える方が正しいと言えます。
「運動する時計の遅れ」「運動する物体の短縮」をミンコフスキ空間の幾何学としてどのように理解すれば良いかは、すでに、次のような質問に対する回答として示しています。参考にしてください。
【Q&A目次に戻る】

ハッブル宇宙望遠鏡は、天体観測のために特化した装置であり、地上観測には向いていません。口径2.4mの反射望遠鏡は長さ4mのシールドで覆われていますが、これは、真空中をまっすぐに進む微弱な光を集めるのに有効です。極端に暗い遠方の銀河については、センサを使って望遠鏡の向きを正確に調べ、その上で、天球上の同じ位置からのものと同定されるデータを重ね合わせることにより、鮮明な画像を作り上げています。しかし、この望遠鏡を地上に向けても、空気密度の揺らぎに起因する屈折や、エアロゾル・水滴などによるランダムな散乱のせいで、情報が不可逆的に失われているため、宇宙空間で実現されるような解像度は得られません。
軍事用の偵察衛星は、充分な解像度を確保するため、高度350km以下(場合によっては100km程度)の低軌道で目標物に近づき、ピンポイント撮影を行うのが一般的です。一方、長さ13m、重さ11トンもある巨大なハッブル宇宙望遠鏡は、大気との摩擦が小さい高度600kmの軌道を周回しています。ここから宇宙に望遠鏡を向けると、大気に邪魔されない鮮明な画像が得られますが、地上にある物体を観測するには少し高すぎます。無理に軌道を下げると、短期間で地上に落下してしまいます。打ち上げコストも考えると、偵察衛星は、口径があまり大きくない望遠鏡を搭載した比較的小型のものに限られるでしょう。
現在使用されている偵察衛星の分解能に関しては、
別の回答で触れています。
【Q&A目次に戻る】
 ある回答
ある回答で「ブラックホールがホーキング輻射で蒸発した後に、何が残るか分からない」とありますが、平坦な時空だけが残るという解釈はきわめて素人的でしょうか? ブラックホールに取り込まれた情報がどうなるかという議論と関係があるのでしょうか?【現代物理】

ブラックホールの蒸発に関するホーキングの理論は、一般相対論と場の量子論を折衷したもので、蒸発の最終段階まできちんと計算しているわけではありません。時空の量子論が完成された段階で、この理論がどのような修正を受けるかは、いまだ明らかではないのです。
ブラックホールには、「事象の地平面」と呼ばれる“後戻り不可能な地点”が存在します。ホーキングは、地平面近くの曲がった空間における量子効果を考察し、対生成によって生じた粒子・反粒子の一方が無限遠に遠ざかる確率を計算しました。その結果、粒子/反粒子がブラックホールからエネルギーを奪って彼方に飛び去る確率が、(ブラックホールからは何も放出されないという予想に反して)有限の値として求められたのです。これをもとに、孤立したブラックホールがどのような割合でエネルギーを放出し質量を失うかを計算したところ、質量が天体規模のときはごくわずかしかエネルギーを放出しないが、質量が小さくなるにつれて放射率が高まり、最終的には残ったエネルギーを爆発的に放出してしまうことがわかりました。これが、ブラックホールの蒸発と呼ばれる現象です(電荷や磁荷を持つブラックホールが存在すれば、蒸発は途中で止まると言われています)。
こうした計算は、あくまで「通常の素粒子に関する量子論的な計算を曲がった空間内部で行う」という方法論に基づいています。このとき、曲がった空間は、固定されたバックグラウンドとして扱われています。しかし、重力がきわめて強くなると、時間・空間そのものが量子論的な揺らぎを示すと考えられており、この方法は使えません。アインシュタイン方程式のブラックホール解には、時空の歪みが無限大になる特異点が含まれていますが、現実のブラックホールでは、時空の量子論的な揺らぎがきわめて大きくなって、時空の歪み方すら確定したものとして扱えなくなります。ホーキング放射の最終段階では、事象の地平面はきわめて小さくなるので、中心部から地平面まで含めたブラックホール全体に量子論を適用する必要があります。しかし、時空の量子論は、まだ完成されたと言うには程遠い状態です。
時空の歪みを含めたあらゆる物理現象を量子論的に扱う理論として注目されているのが、超ひも理論(弦理論)、あるいは、その発展形であるM理論です。超ひも理論によると、ブラックホールは多数のひもが絡み合った塊として解釈できるようですし、M理論では、次元数の高いブレーンを使ってブラックホールを記述することが可能だそうです
(「科学の回廊」で書いたように、私は超ひも理論が嫌いなので、あまり詳しく勉強していません)。こうした理論を使えば、蒸発の最終段階まできちんと解明できる(おそらく、ブラックホールは完全に蒸発して平坦な時空が残ることが示される)のかもしれませんが、数学的にきわめて難しいため、今のところ、特殊な解をいじくり回しているだけのように思われます。
ホーキングは、ブラックホールの蒸発を論じた研究の2年後に、ブラックホールに取り込まれた情報が跡形もなく消えてしまうことを証明する論文を発表しています。そこで使われた論拠は、ホーキング放射がランダムに起こるため、取り込まれた情報と何の相関もないというものです。しかし、この議論も、一般相対論と量子論をつぎはぎした方法論に基づいているため、完全とは言えません。一方、超ひも理論の研究者は、ブラックホールの内部に蓄えられていた情報がホーキング放射に乗って送り出されるので、情報の喪失は起きないという主張を展開しています(ホーキング自身も、2004年に自説を撤回して、情報は保存されるという見方に傾いています)。ただし、こうした主張は、検証されていない多くの仮説の上に導かれたものです。超ひも理論の正当性も含めて、最終的にどのような結論に落ち着くかを見届けるには、まだかなり時間がかかりそうです。
【Q&A目次に戻る】

においの元になるのは、物質から放出された「におい分子」です。におい分子は、比較的分子量の小さい有機または無機の化合物で、バニリン(バニラ臭)やジャスミン(ジャスミン臭)などが有名です。においの知覚は、空気中を浮遊してきたにおい分子が嗅上皮にある嗅細胞に吸着され、神経興奮を引き起こすことによってもたらされます。人間が感応するにおい分子は数万〜数十万種類に上ると言われており、さまざまなにおい分子の組み合わせによって多様なにおいが実現されています。
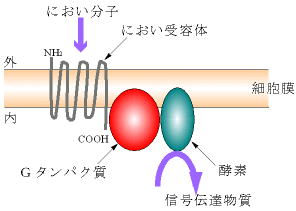
におい分子が嗅細胞で神経興奮を引き起こす具体的なメカニズムは、2004年度ノーベル医学生理学賞の対象となったアクセルとバックの研究(1991)が契機となって、ここ15年ほどの間に急速に解明されてきました。その概略は、次のようなものです:
嗅細胞には、細胞膜を7回貫通する構造をした「におい受容体」が存在しています。人間やラットには、少しずつ構造の異なるにおい受容体が1000種類ほどあると言われていますが、1つの嗅細胞には1種類のにおい受容体しかありません。この受容体ににおい分子が結合すると、一連の反応
(Gタンパク質を介した酵素反応の活性化→信号伝達物質の産生→イオンチャネルの開口)を通じて神経興奮をもたらす活動電位が発生し、嗅細胞の軸索を通って嗅球と呼ばれる脳の部位に信号が送られます。1種類のにおい受容体は、複数のにおい分子に異なる感度で反応するため、約600万個ある嗅細胞から送られてくる信号のパターンによって、数千から1万種類のにおいを嗅ぎ分けることが可能になっています。
人間の体からもさまざまなにおい分子が放出されていますが、「いいにおい」と感じられる体臭があるかどうか、はっきりとわかっていません。多くの哺乳類は、汗や尿の中に異性を惹きつける性フェロモンを分泌しており、通常の嗅覚系とは異なる鋤鼻器(じょびき)と呼ばれる器官で感知しています。しかし、人間の成人では鋤鼻器は痕跡化しており、フェロモンが何らかの役割を果たしているかは不明です。イノシシに対してフェロモン効果を持っており、人間の汗や尿にも含まれているアンドロステノンが、人間に対してもフェロモンとして作用するという説はかなり有力ですが、科学的に確定した結論は得られていません。アンドロステノンのにおいは、尿や汗に似た嫌なにおいだとも、花の香りに似た良いにおいだとも言われており、感じ方に個人差があるようです。また、何パーセントかの人は生まれつきアンドロステノンのにおいを感じる能力を持っていませんが、繰り返し嗅がせているうちににおいを感じるようになるとの実験結果もあり、感受性が後天的に変化すると考えられています。
『源氏物語』に登場する薫中将は、女性をうっとりさせる体臭を放つ特異体質の持ち主として描かれていますが、こうした効果をもたらす神経機構が解明されれば、イグノーベル賞くらいは受賞できそうです。
【参考文献】大瀧丈二著『嗅覚系の分子神経生物学』(フレグランスジャーナル社)
【Q&A目次に戻る】

色の知覚は、3種類の錐体が可視光線を吸収することに始まります。L錐体・M錐体・S錐体と呼ばれるこれらの光受容細胞は、特定の波長に対する感度が異なっている(下図)ため、それぞれの錐体が作り出す信号を組み合わせることによって、色の識別が可能になるのです。逆に言えば、光受容細胞が3種類しかないため、分光学的に見て異なる光刺激でも、同じ色の知覚をもたらすこすことがあります。例えば、6W の 540nm光と 25W の 650nm光を混合したものは、10W の 580nm光と同じ応答を引き起こすため、視覚上は全く区別できません。
錐体信号は、まず、外側膝状体において、L-M と S-(L+M) という組み合わせで処理され、続いて、1次視覚野でさらに複雑に加工されることが知られています。このとき重要なのは、大脳皮質での応答が入力された信号に対して線形でないという点です。線形応答であるならば、L-M の値が連続的に変化するにつれて、知覚される色も連続的に変わるはずです。しかし、実際には、ある閾値より入力が小さいときにはほとんど応答せず、この値を超えると急にはっきりと応答するといった非線形な変化が見られます。この非線形性が、知覚されるスペクトルの色変化がなだらかではなく、いくつかの色に分離して見える理由です。
ただし、「虹は7色」というのは、世界共通の認識ではありません。日本では、紫・藍・青・緑・黄・橙・赤の7色とするのが一般的ですが、アメリカやイギリスでは紫と藍を区別せず、単に紫と呼ぶことが多いようです。世界的に見ると、虹の色数は 4〜7 までばらついています(3色とか8色とする民族もあるらしい)。「学術的には7色」と記される場合もありますが、これは、分光学を確立したニュートンが、プリズムによって得られたスペクトルに7つの色名を当てたことに倣ったものと思われます。日本では、明治時代の学校教育でニュートン流の「7色のスペクトル」という知識を移入したため、「虹は7色」という常識が定着したのでしょう。
【Q&A目次に戻る】
 別の回答
別の回答で書きましたが、潮汐力は、作用する物体の大きさを r、月と地球の距離を R とすると、月からの重力に 2r/R という項を乗じられた値になるので、海のように広い範囲で重力の作用を受ける場合に限って、その効果が表面化します。生物個体が潮汐力を感知できるとは考えられません(温度・湿度が一定である鉱山の坑道に生息する洞窟コオロギが、潮汐リズムと同期した行動パターンを示すという報告もありますが、これが潮汐力を感知した結果だと考える生物学者は、ほとんどいません)。また、潮汐力による地磁気の変化といった2次的な効果も、生物が捉えるには微弱すぎます。
多くの場合、生物の行動を潮汐リズムと同期させるのは、体内時計の作用だと考えられています。体内時計としては、ほぼ24時間の周期性を示す概日時計が有名ですが、潮汐の影響を受ける貝やカニなどの生物には、12.4時間という潮の干満の周期に同期した生物時計も存在することが知られています。概日時計に関しては、「時計分子」と呼ばれる一群のタンパク質と「時計遺伝子」の相互作用によってタンパク質の合成量が1日周期で増減するというメカニズムが、かなりの程度まで解明されています。概潮汐時計の研究は始まったばかりで、不明な点が多いものの、同じようなメカニズムが働いていると考えて良いでしょう。
生物時計は、分子反応に基づく内因性のリズムを持っていますが、必ずしも正確ではないため、環境からの情報に基づいて時計を同調させる必要があります。概潮汐時計の場合、波による機械的な刺激のほか、温度・塩分・水圧の変化が同調因子として作用していることが判明しています。シオマネキを用いた研究によると、ひとたび同調された概潮汐時計は、照度・温度が一定という条件下でも、ほぼ2ヶ月にわたって行動パターンを支配したそうです。
概日リズムより長い周期の生物時計については、あまり良くわかっていません。大潮・小潮の周期と同期した半月周期の生物リズムの存在も知られていますが、これは、内因性の生物時計によるものではなく、24時間周期の概日時計と12.4時間周期の概潮汐時計が、15日ごとに同位相になることを利用していると考えられています。
人間には、光刺激を同調因子とする概日時計が視床下部に備わっていますが、潮汐や月の満ち欠けと同期する内因性の生物時計が存在する証拠はありません。女性の月経は、ほぼ1ヶ月の周期を持つことから、月の満ち欠け(あるいは大潮・小潮)と関係するという説もありますが、月経が見られる他のサル下目では人間よりも周期が長く、月の変化と同期していないので、偶然の一致にすぎないという見方が有力です。満月の夜に行動パターンが変化するのは、単純に明るさの差によるものか、明るく丸い物体の存在が引き起こす心理的効果でしょう。
【参考文献】富岡憲治ほか著『時間生物学の基礎』(裳華房)
【Q&A目次に戻る】

原子核の構造や変動は、最新鋭のコンピュータを使っても、分子の場合のようにはうまく計算できません。これは、分子と原子核とでは、次のような質的な差があるためです:
- 分子を構成する電子と原子核(またはイオン)は、質量に1000倍以上の開きがあり、原子核の運動速度は電子に比べるときわめて遅いので、それぞれの運動を分離して扱うことが可能です。例えば、「グラファイトが水素を吸着してメタンを生成する」というような比較的簡単な化学反応の場合は、原子核のある配置に対して電子の密度分布と全エネルギーを計算し、その結果をフィードバックして原子の運動を求めることにより、時間とともに刻々と原子の位置が移動する様子が可視化できます。しかし、原子核を構成する陽子・中性子に関しては、こうした運動の分離が行えません。
- 分子の動力学を支配している電磁相互作用は、比較的弱い相互作用であるため、さまざまな逐次近似法が使えます。分子軌道法では、出発点となる波動関数を適当な方法で選び、厳密な解との差を小さくするように段階的に計算を進めていきます。しかし、陽子・中性子を結びつけている核力は、別名「強い相互作用」と呼ばれていることからも分かるように、力が大きすぎて逐次近似法が使えません(段階的に計算しようとしても、補正の方が元の値より大きくなったりします)。
- 分子の場合、電子と原子核という構成要素が途中で別の粒子に変化することはありません。しかし、原子核内部では、「陽子がπ中間子を放出して中性子に変わる」といった反応が生じています。このように粒子が変化する過程を扱うためには、相対論的な量子力学(場の量子論)を用いなければなりませんが、数学的に難しく近似的な計算ですら容易に行えません。また、この理論は、反応が起きる確率を求めるものであり、個々の粒子の変化を追跡することはできません。
- 原子核の内部にある陽子や中性子は、粒子としてのアイデンティティを持っておらず、「陽子がπ中間子を放出して中性子に変化する」という過程を(原子核のα崩壊のように)具体的にイメージすることは、適切ではありません。
原子核反応を分子動力学と似た手法を使って計算することは、1990年代から何人かの物理学者によって試みられています。例えば、核子を波束(波が狭い範囲に集中したもの)として表し、半古典的な近似を使って波束が従う方程式を与えるという方法が提案されており、2つの原子核(2個の
12C や
40Ca など)が高速で衝突していくつかの原子核に壊れる過程が、実際に計算されています。しかし、きわめて粗っぽい近似に基づいており、どこまで信頼できる計算か判然としません。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
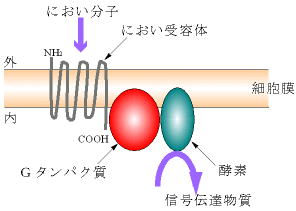 におい分子が嗅細胞で神経興奮を引き起こす具体的なメカニズムは、2004年度ノーベル医学生理学賞の対象となったアクセルとバックの研究(1991)が契機となって、ここ15年ほどの間に急速に解明されてきました。その概略は、次のようなものです:
におい分子が嗅細胞で神経興奮を引き起こす具体的なメカニズムは、2004年度ノーベル医学生理学賞の対象となったアクセルとバックの研究(1991)が契機となって、ここ15年ほどの間に急速に解明されてきました。その概略は、次のようなものです: