
ボーアは、前期量子論の立て役者として、いくつかの重要な関係式を導きましたが、物質の振舞いを記述する基礎方程式には到達できませんでした。一方、シュレディンガーは、あらゆる物理現象を記述する波動方程式を発見したものの、波動関数そのものを物理的実在と見なしたため、正統的な量子力学の立場からすると異端者だったと言えるでしょう。
ボーアの理論の出発点になるのは、原子の安定性とスペクトルを説明するために、プランクの量子仮説に基づいて1913年に提唱された水素原子のモデルです。ここでは、原子核の周りを回る1個の電子に対して、軌道を制限するような量子条件が課せられることが(ほとんど天下り的に)主張されています。この条件は、同じ年に発表された第2論文で、角運動量の量子化として、
J = nh/2π (h:プランク定数)
という形を与えられました。古典力学の範囲で原子の周りで円運動をしている電子の角運動量やエネルギーを計算し、それにこの条件を付け加えると、電子はとびとびの軌道しか許されないことになります。さらに、エネルギー量子hνを吸収・放出しながら軌道間を遷移(量子飛躍)すると考えると、水素原子のスペクトルを完全に説明できます。このように、ボーアの理論は、従来の物理学では説明不可能だった観測データに合致するモデルを与えるものではありますが、束縛された電子以外のケースにどのように拡張したら良いかがわからず、普遍性がありません。あくまで、特定の現象を説明するために、古典論をベースにしながら、古典論では説明の付かない新しい関係式を付け加えて作り出した折衷的な理論だと言えます。
ボーアの理論の一般化は、その後、多くの物理学者によって成し遂げられました。特に、定常状態については、ゾンマーフェルトによって、作用変数の量子化:

という見通しの良い条件式が与えられました。この条件式を元に、ボーアを中心とする物理学者は、元素の周期律を説明することにかなりの程度まで成功します。しかし、電磁場との相互作用に関して満足のいく理論は構築できず、古典論を部分的に援用する折衷的な性格を拭い去ることはできませんでした。突破口が開かれるのは、ハイゼンベルグが、作用変数の量子化条件を行列式で書き直すことによって、pとqという2つの行列の間に交換関係が成立することを見いだす1925年になってからです。
ボーアの理論では、非定常的な変化は量子飛躍として突然起きるとされていましたが、これとは逆に、原子レベルの現象を波動として理解しようとする研究者たちがいました。その嚆矢となったのが1924年のド・ブロイの物質波仮説で、運動量pの電子は波長h/pという波として振舞うと主張されていました。シュレディンガーは、この素朴な物質波仮説を数学的に発展させ、1926年に発表した一連の論文で波動力学を一気に構築します。この理論では、物理現象の根底には波動関数ψで記述される実体的な振動過程があるとされ、定常状態についてのボーア=ゾンマーフェルトの量子化条件は、この波が定常波を形成するという条件から導くことができます。さらに、量子飛躍は、電磁場との持続的相互作用に起因するある振動モードから他のモードへの連続的な変化と見なされ、理論から不連続性を追放してしまいました。
シュレディンガーの理論は、あらゆる現象を波動の連続的変化として記述するもので、ボーア理論やその正統な後継者であるハイゼンベルグの行列力学に比べて理解しやすく、また、理論の解釈に古典論を必要しないという点で一貫性も有しています。ただし、ψψ
*が荷電分布を与えるという当初の主張は、孤立した自由電子という最も単純なケースに対しても当てはまらないことが明らかになり、現象の根底に波動関数で記述される実体が存在するというシュレディンガーの解釈は、根拠のないものとして斥けられました。その結果、波動関数は、直観的にはわかりにくい確率振幅として再解釈され、波動力学そのものは、いくつかの波動関数を基底ベクトルとする関数空間という概念を梃子にして、ハイゼンベルグの行列力学と合体させられることになりました。こうしてできあがったのが、いわゆる量子力学です。
さらに詳しい説明は、量子力学史の参考書をご覧ください。
【Q&A目次に戻る】

上の考え方は、基本的な筋道は正しいのですが、具体的な部分で誤っています。
良く知られているように、二重スリットに光子(あるいは電子)を多数照射すると、背後のスクリーンに光子(電子)が到達したことを表すドットが縞模様(フリンジ)を形成します(上図)。こうした縞模様は、波動特有の干渉現象で、同一波源から出た波が分かれて2つのスリットを通過し、スクリーン上で再び一緒になったことを示します。しかし、光子や電子は、しばしばボールのように宙を飛んでくる粒子として扱われるので、どちらか一方のスリットを通過したと考えるのが素直です。この波動−粒子の二重性が、物理学者の悩みの種でした。
質問にあるように、この問題を解決する鍵は、光子や電子の伝播を「粒子が飛んでくる」と見なさないことです。1929年にハイゼンベルグとパウリによって基本的な枠組みが与えられた場の量子論では、光子(電子)は電磁場(電子場)の励起状態であり、粒子描像が成り立つのは、摂動論近似が使える一部の現象でしかありません。二重スリットの実験では、電磁場(電子場)の変動がスリットを通して伝播しているのであって、1個の粒子が飛んでいる過程として記述されることはありません。
ただし、これを電線内部を電流が流れる過程と類比的に考えるのは、あまり適切ではありません。電線の素材となる銅などの金属には、金属中を(ほぼ)自由に動き回れる伝導電子が存在しており、電線内部に電場が加えられると、これらの運動に電場の逆方向への偏りが生じて電流となるわけです(電子同士がドツキあっているのではありません)。一般に、電子間の相互作用は(超伝導などの特殊な現象以外では)近似的に無視できます。また、電子の平均移動速度は、電子が動く速度の2乗平均よりも遥かに小さくなっています。これに対して、二重スリット周辺の電磁場や電子場には、粒子状態として記述されるような伝導光子や伝導電子はなく、あくまで非粒子的な中間状態として考えるべきです。
さらに、場の量子論は、伝導電子の理論と決定的に異なる性質を持っています。それは、理論で用いられる状態関数が、そのまま系の物理的状態を表すとは言えない点です。状態関数は、特定の現象が生起する確率を正しく与えるものの、電磁場(電子場)が現実にどのように変動しているかを記述してはいません。このため、現在の理論の枠組みの中では、場の変動が実際に波のように伝わっているかすら、明らかにできないのです。場の量子論を超えた根元的な物理学理論を構築しようとする試みは、全くと言って良いほど成功していません。
【Q&A目次に戻る】

プラズマ(自由運動できる正負の荷電粒子を含んだ物質の状態)を利用した技術には、蛍光灯やアークなど古くから日常的に用いられているものがあり、必ずしも最近になって急にもてはやされるようになったわけではありません。むしろ、プラズマ物理学の最大の応用技術であった核融合発電に関しては、1999年に国際熱核融合炉(ITER)計画から米国が撤退し21世紀中の実用化に黄信号が灯ったこともあって、開発への熱意が急速に萎んできています
(もっとも、巨大プロジェクトに伴うおこぼれにありつこうと、ITERを日本に誘致しようという動きもありますが)。
ここ数年、一般の人が「プラズマ」という言葉を目にする機会が増えたのは、小型で性能の良いプラズマ発生装置が開発され、これを内蔵した家電製品が市場に投入されたためでしょう。最も知られているのが、画素の1つ1つが微細な蛍光灯になっているPDP(プラズマディスプレイパネル)で、すでに大画面薄型ディスプレイとして実用化されています(PDPの原理に関しては、
別の項目をご覧ください)。また、クラスターイオン(正負イオンの集合体)を用いた空気清浄機も実用化されており、一部のエアコンや冷蔵庫などに搭載されています。このタイプの製品は、空気中に浮遊するカビや有害物質を分解できるというので、清潔志向の強い消費者の人気を集めているようです。
このほか、反応性に富んだ物質を含むプラズマ雰囲気中で行う表面加工や、プラズマアークを使ったごみ焼却のように、さまざまな産業における新たな応用分野も切り開かれています。
【Q&A目次に戻る】

自転車やバイクのような2輪車は、停止中には支えていないとすぐに倒れてしまうのに、走行中は(よほど下手な乗り手でない限り)長時間にわたって安定した状態を保つことができます。このように、走っている2輪車が転倒しないのは、2つの異なるメカニズムが働いているためです。
車輪の回転モーメントが小さく回転速度が遅い場合は、主に、乗り手のリアルタイム制御によって転倒が防がれています。この効果は、自転車をゆっくり走らせようとすると、実感することができます。このとき、自転車の乗り手は、体勢が不安定になるたびに傾いた側にこまめにハンドルを切り、慣性の法則によって反対側に重心移動して体勢を立て直します(自転車自体にも、傾いた側に首を振る工夫がなされています)。逆に、ハンドルが固定された自転車に乗ろうとしても、すぐに倒れて数メートルも走れないでしょう。
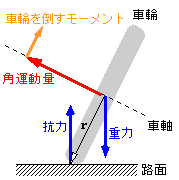
一方、車輪の回転モーメントが大きく回転速度が速い場合には、コマと同じようにジャイロ効果が効いてきます。自転車やバイクを高速で走らせるとき、あまりハンドルを切らなくても安定走行できるのは、このおかげです(ハンドルが固定された自転車でも、あらかじめスピードを付けておけば、ある程度は倒れずに走れるはずです)。これは、外力によるモーメントが作用しないときには角運動量が保存する──例えば、宇宙空間に孤立する天体は一定の角運動量で自転し続ける──という力学法則に由来する効果です。車輪の場合、角速度ωのときの角運動量
M(太字はベクトルであることを表す)は車軸方向を向いており、その大きさは、回転モーメント(全質量mが半径rの円周上に集中している理想的な車輪の場合、mr
2)をIとすると、
M=Iω
で与えられます。
Mの(ベクトルとしての)時間変化は、力のモーメントに等しく、
d
M/dt=Σ
r×f(
×はベクトル積)
となります。自転車やバイクが直進しているとき、
Mは水平方向を向いています。車輪が傾いたとき、力のモーメントが
Mをいっそう傾かせるように作用するならば、すぐに倒れてしまうはずですが、(中心と接地点を通る断面に関して対称と見なせる)理想的な車輪の場合は、その向きにモーメントは作用しないので、車輪は進む向きを変えるだけで倒れることはないのです(右図)。
【Q&A目次に戻る】

絶対零度以上の全ての物体が、その温度に応じてエネルギーを放射することは、19世紀末の熱力学の法則によって明らかにされました。中性子星や白色矮星も、有限の温度を持っているので、熱放射を行って次第にエネルギーを失っていき、最終的には、宇宙空間と同じ温度(現在は絶対温度で3度)にまで冷えて熱平衡状態に到達するはずです。
それでは、ブラックホールは熱放射を行うのでしょうか。古典物理学の範囲では、ブラックホールからは光すら出て来られないはずなので、熱放射をしない絶対零度の物体のようにも思えます。しかし、これは少し奇妙な話です。恒星が重力崩壊を起こしてブラックホールを形成する過程で、それまで高温だった物体が、突然、熱力学の定理で到達不可能とされていた絶対零度に飛躍してしまうのですから。この難点を克服するため、1970年代初頭にはブラックホールに何とか熱力学を適用しようとする物理学者が現れます。中でも独創的だったのがベケンシュタインで、彼は、類推を元にして、ブラックホールの質量の逆数が温度に、事象の地平面の面積がエントロピーに相当すると主張しました。温度を式で表すと、
温度T[K] = 1.2×10
26/M
(M:ブラックホールの質量[g])
となります。このアイデアが正しければ、ブラックホールは有限の温度(太陽質量の10倍のブラックホールでは6×10
-9[K]という極低温)を持ち、当然、熱放射をすることになります。でも、どうやって?
多くの物理学者がお手上げだったこの問いに挑んだのが、車椅子の天才物理学者ホーキングでした。厳密な重力の量子論が構築されていなかった当時(今も)、彼は、「曲がった時空上の量子論」という折衷理論を使って、ブラックホール周辺の場のゆらぎを計算しました。平坦な空間でも、真空は何も存在しない“虚空”ではなく、光子や電子の場が量子論的に揺らいでおり、仮想的な粒子(virtual particle)が存在しています。ただし、エネルギー保存の法則があるために、こうした仮想粒子が真空から飛び出してくることはなく、仮想的な粒子と反粒子がペアで生成されるや否や、再びペアで消滅してしまいます(真空はエネルギーの基準状態であり、粒子が飛び出す状態は、これに対してプラスのエネルギーを持っているのですから)。ところが、ブラックホール周辺で真空から粒子が飛び出してくる確率を(折衷理論によって)計算すると、零でない答えがでてくるのです。これは、真空で対生成された粒子のうち一方が事象の地平面の内側に落ち込んでしまい、他方が対消滅するパートナーを失って外に飛び出してくる(ホーキング放射)ことを意味します。
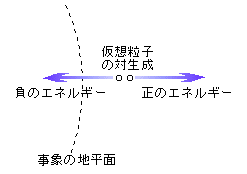
このとき、飛び出す粒子は、重力ポテンシャルの低い状態に落ち込む「予定の」相棒からエネルギーをもらって(仮想粒子のペアだからそんな器用なことができるのです)、正のエネルギーを外部に持ち去ります(右図)。したがって、ブラックホールには負のエネルギーが流れ込むことになり、ホールの質量は減少していきます。ところが、上の式で示したように、ブラックホールの温度は質量に反比例するわけですから、ホーキング放射をして質量が減少すればするほど高温になっていくはずです。恒星規模のブラックホールの温度は宇宙空間(3K)よりも低温なので、ホーキング放射するよりも外から流れ込むエネルギーの方が常に大きくなりますが、ビッグバン直後に存在したと予想されるミニ・ブラックホールでは、この効果は顕著に現れます。ホーキングの計算が正しければ、はじめに質量1億トン程度(温度1兆度)だった“小さな”ブラックホールは、ホーキング放射の効果で1億年程度をかけて徐々に質量を失っていき、最後の10分の1秒間に10
23[J]のエネルギーを放出して“蒸発”します。その後に何が残るか(あるいは何も残らないか)は、わかっていません。
ブラックホールがホーキング放射を行うという結果は、曲がった時空上の量子論という折衷理論で積分を行う際に、特異点を避けて時間が虚数となる領域に解析接続することによって得られます。仮想粒子ペアの一方がホールに落ち込むのは、物質が重力に引き寄せられるという通常の物理過程ではなく、時空構造に特異性があることの帰結であり、したがって、ホーキング放射はブラックホールだけで生じます。もっとも、折衷理論に基づく計算法が果たして正しいのか、現時点ではまだ結論が出ていません(ホーキングがノーベル賞をもらえない理由です)。一部の学者(超ひも理論の発展形である膜理論の研究者など)は、この計算結果は厳密な理論が持つ性質を近似的にうまく取り入れたもので、世界の根底にある数学的秩序を反映していると考えています。しかし、(私を含めた)多くの学者は、あまりに難しい理論なので正否の判定をためらっています。
【Q&A目次に戻る】

初等的な解釈で良ければ、光子のアイデアを使った光量子論の考え方がわかりやすいと思います。この理論によれば、光は、光子と呼ばれるエネルギーの固まり(粒子)と解釈され、1個の光子が持つエネルギーEは、波長をλ、プランク定数をhとすると、
E=h/λ
で与えられ、波長が短いほどエネルギーが高くなっています。一方、光の強度とは光子の密度と関係しており、強度の高い光とは、単位体積あたりの光子数がより多くなっている光だと考えられます。したがって、長波長光の強度を高めると、1個1個のエネルギーは小さい光子がたくさん飛んでくることになります。光化学反応が起きるかどうかは、光子が持つエネルギーによって決まるので、例えば、長波長の赤外線をいくら浴びたとしても、短波長の紫外線を照射されたときのように日焼けするということはないのです。
…と簡単に説明しましたが、上の描像は厳密には正しくありません。光子は位置や個数を決められる電子・陽子などの粒子とは異なり、どこに何個あるかを決定することはできません(波長が1mの光子が1個飛んでくるとしたら、それはどこにあるのでしょうか)。光の振舞いを正しく記述するのは、量子電磁気学と呼ばれる高度に数学的な理論であり、光子描像が近似的に適用できるのは、エネルギーや関与する反応が特定の範囲の現象に限られます。もっとも、物理学の専門家以外には、こうした本格的な議論は必要ないでしょう。
【Q&A目次に戻る】

ごく単純化して言えば、プロダクトイノベーションとは、それまで存在しなかった全く新しい製品を生み出すことであり、プロセスイノベーションは、生産手段の修正・改善を通じて生産性の大幅な向上を実現することです。前者が、少数の天才的な科学者・技術者が実現する飛躍的な変化で、多くの場合、新しい市場と関連産業の創出を伴うのに対して、後者は、協調的な技術者集団の手になる漸進的・累積的な変化として達成され、既に存在する市場の規模を拡大する効果があります。
1960〜70年代の高度成長期において、日本の製造業は、欧米で開発された製品を生産するに当たり、QC運動などを通じてコスト低下・品質改善を押し進め、プロセスイノベーションに基づく高度成長を成し遂げました。しかし、80年代に入ってもこの手法をそのまま継承してコストと品質にこだわった結果、プロダクトイノベーションへの積極的な取り組みが後回しとなり、90年代にアメリカの先進的な企業が実現したITやバイオの技術革新の前に、日本企業は苦戦を強いられています。こうした中で、「プロセスイノベーションよりプロダクトイノベーションを」といった標語が産業界で口にされるようになってきました。
プロダクトイノベーションは、画期的な新製品を生み出す“技術”革新と考えられます。もちろん、別の分野で実用化されていた既存の技術をうまく組み合わせて、新たなマーケットを創出する新製品を開発することも可能でしょう(携帯電話やカーナビなど)。しかし、産業の流れを大きく変える力を持っているのは、宇宙船内部という極限的な閉鎖空間で発電を可能にする燃料電池や、戦時下にあっても通信の途絶を極力回避できるインターネットのように、全く新しい発想に基づいて開発された革新的技術を伴う製品です。また、ゲノムデータに基づいて開発された医薬品や、ナノテクノロジーが生み出すテーラーメード素材のように、製品そのものよりも、開発に当たっての基本的なコンセプトが革新的なケースもあります。こうした革新的技術の開発には、しばしば莫大な先行投資が必要となり、しかも途中で挫折するケースが少なくないため、投資効率はあまり高くありません。このため、独創的な科学者・技術者とともに、長期的視野を持った経営者の存在が不可欠となります。製品開発に成功した暁には、特許権を活用してマーケットを独占し、巨大な利益を得ることも可能です(ゼロックス社による複写機やポラロイド社によるインスタント・カメラなど)。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
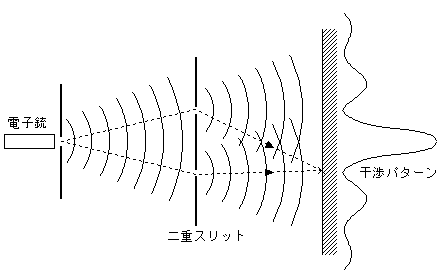
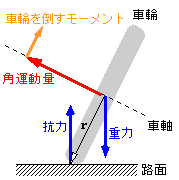 一方、車輪の回転モーメントが大きく回転速度が速い場合には、コマと同じようにジャイロ効果が効いてきます。自転車やバイクを高速で走らせるとき、あまりハンドルを切らなくても安定走行できるのは、このおかげです(ハンドルが固定された自転車でも、あらかじめスピードを付けておけば、ある程度は倒れずに走れるはずです)。これは、外力によるモーメントが作用しないときには角運動量が保存する──例えば、宇宙空間に孤立する天体は一定の角運動量で自転し続ける──という力学法則に由来する効果です。車輪の場合、角速度ωのときの角運動量M(太字はベクトルであることを表す)は車軸方向を向いており、その大きさは、回転モーメント(全質量mが半径rの円周上に集中している理想的な車輪の場合、mr2)をIとすると、
一方、車輪の回転モーメントが大きく回転速度が速い場合には、コマと同じようにジャイロ効果が効いてきます。自転車やバイクを高速で走らせるとき、あまりハンドルを切らなくても安定走行できるのは、このおかげです(ハンドルが固定された自転車でも、あらかじめスピードを付けておけば、ある程度は倒れずに走れるはずです)。これは、外力によるモーメントが作用しないときには角運動量が保存する──例えば、宇宙空間に孤立する天体は一定の角運動量で自転し続ける──という力学法則に由来する効果です。車輪の場合、角速度ωのときの角運動量M(太字はベクトルであることを表す)は車軸方向を向いており、その大きさは、回転モーメント(全質量mが半径rの円周上に集中している理想的な車輪の場合、mr2)をIとすると、
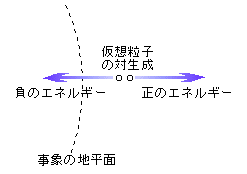 このとき、飛び出す粒子は、重力ポテンシャルの低い状態に落ち込む「予定の」相棒からエネルギーをもらって(仮想粒子のペアだからそんな器用なことができるのです)、正のエネルギーを外部に持ち去ります(右図)。したがって、ブラックホールには負のエネルギーが流れ込むことになり、ホールの質量は減少していきます。ところが、上の式で示したように、ブラックホールの温度は質量に反比例するわけですから、ホーキング放射をして質量が減少すればするほど高温になっていくはずです。恒星規模のブラックホールの温度は宇宙空間(3K)よりも低温なので、ホーキング放射するよりも外から流れ込むエネルギーの方が常に大きくなりますが、ビッグバン直後に存在したと予想されるミニ・ブラックホールでは、この効果は顕著に現れます。ホーキングの計算が正しければ、はじめに質量1億トン程度(温度1兆度)だった“小さな”ブラックホールは、ホーキング放射の効果で1億年程度をかけて徐々に質量を失っていき、最後の10分の1秒間に1023[J]のエネルギーを放出して“蒸発”します。その後に何が残るか(あるいは何も残らないか)は、わかっていません。
このとき、飛び出す粒子は、重力ポテンシャルの低い状態に落ち込む「予定の」相棒からエネルギーをもらって(仮想粒子のペアだからそんな器用なことができるのです)、正のエネルギーを外部に持ち去ります(右図)。したがって、ブラックホールには負のエネルギーが流れ込むことになり、ホールの質量は減少していきます。ところが、上の式で示したように、ブラックホールの温度は質量に反比例するわけですから、ホーキング放射をして質量が減少すればするほど高温になっていくはずです。恒星規模のブラックホールの温度は宇宙空間(3K)よりも低温なので、ホーキング放射するよりも外から流れ込むエネルギーの方が常に大きくなりますが、ビッグバン直後に存在したと予想されるミニ・ブラックホールでは、この効果は顕著に現れます。ホーキングの計算が正しければ、はじめに質量1億トン程度(温度1兆度)だった“小さな”ブラックホールは、ホーキング放射の効果で1億年程度をかけて徐々に質量を失っていき、最後の10分の1秒間に1023[J]のエネルギーを放出して“蒸発”します。その後に何が残るか(あるいは何も残らないか)は、わかっていません。