
「波長の短い可視光線や紫外線を金属に照射すると電子が飛び出してくる」という光電効果は、すでに1887年に発見されており、光のエネルギーが電子に受け渡されたとして定性的に説明できることは早くから理解されていました。ところが、実験を進めていくうちに、次のような特徴が見いだされ、波の形でエネルギーが拡がっているとすると説明が付かなくなってきました。
- 紫外線を照射すると、1/1000秒以下のタイムラグで電子の放出が始まる。
(エネルギーが拡がっているならば、放出に必要なエネルギーが貯まるまで時間が掛かるはずです)
- 金属に固有の振動数ν0が定まっており、ν0以下の振動数の光では、どんなに強度(明るさ)を上げても電子の放出は生じない。
(波のエネルギーは強度に比例するので、充分に強度を上げれば電子が飛び出すのに必要なエネルギーを供給できると考えられます)
- 振動数νの光を照射したときに飛び出す電子の最大エネルギーは、光の強度によらず、ν−ν0に比例する。
(これも、強度に比例するエネルギーを持つ波の振舞いとしては、不可解です)
アインシュタインは、振動数νの光が、hνというエネルギーの固まり(エネルギー量子あるいは光子;hはプランク定数)の集まりだと解釈すると、こうした特徴を説明できることを示しました(アインシュタインは光の実体を粒子と見なしたわけではありませんが、ここでは、話を簡単にするために、「光=光子の集まり」としておきます)。光子が金属内部の電子に衝突すると、電子がエネルギーを吸収して直ちに金属の外部に飛び出すというわけです。また、光の強度は光子の密度を表しており、どんなに光子の数を増やしても、個々の光子が電子を金属の外に弾き出すだけのエネルギーを持っていなければ、光電効果を起こすことはできません。電子を金属から取り出すのに必要な最低限のエネルギーをhν
0と書くと、放出される電子の最大エネルギーは、
h(ν−ν
0) …(E)
になります。
実際に(E)式が成り立っていて係数がプランク定数と一致することは、1914年から16年に掛けてミリカンが精密実験によって確認しており、アインシュタインの仮説の正当性が実証されました。
もちろん、光子の概念を用いずに光電効果の特徴を説明できる理論があれば、アインシュタインの仮説に取って代わることができるはずです。しかし、数式も少なく直観的にもわかりやすい説明として、これ以上のものはないというのが実状です。ちなみに、こんにち採用されている物理学理論によると、電子も光子も場の励起状態として波動的に記述されるのですが、使われている数式が難しく、そのままでは直観的に理解できません。光電効果のような(干渉のない)低エネルギー現象に関しては、粒子が飛んできて相互作用するという描像が良い近似で成立する──摂動論の高次項が無視できる──ので、現在でも、議論の出発点として、エネルギーの固まりである光子が飛んでくるという説明が使われます。
【Q&A目次に戻る】

格子定数は、結晶軸の長さや軸間角度のことですから、膨張や変形によって値が変化するものであり、当然、温度や圧力に依存します。4桁以上の精度を必要とする精密測定の場合は、測定したときの試料の温度を論文に付記するのが一般的です。特に、有機化合物や金属錯体は、室温で相転移することもあり、温度に強く影響されます。もちろん、超高温/超低温でX線回折の実験を行う際にも、温度による結晶の変化を考慮することが必要です。
ただし、無機物の結晶の格子定数は、それほど敏感に温度に依存していないので、室温での実験の場合、高い精度が要求されない限り、格子定数の温度依存性を無視することが少なくありません。測定結果と理論値が異なっていたとすると、まずは温度以外に原因を求めた方が良いと思います。格子定数が理論値から少しずれる原因としては、装置の整備不良や測定ミスの他にも、不純物の影響が考えられます。試料が固溶体となっている場合、溶媒の格子間隔をa、溶質の格子間隔をbとすると、測定された格子間隔dは、
d = (1-x)a + xb
という形になります(xは溶質イオン濃度)。また、結晶水を含んでいる場合、その量によって格子定数が変化することもあります。
【Q&A目次に戻る】

人間の唾液はpH6.8〜7.5(刺激唾液)という値を示しており、唾液が充分に分泌されていれば、口中はほぼ中性に保たれます。しかし、歯垢中に棲息している細菌は糖を分解する過程で酸を作り出しているため、何らかの理由で唾液の分泌量が減少したり、食事によって糖が供給されたりすると、口の中は次第に酸性に傾き、同時に、口臭などの不快な症状が現れてきます。このとき、味覚の鋭敏な人は「口が酸っぱい」と感じるようです。また、高血糖などの病気の症状として、口中が酸性になることもあります。「口が酸っぱくなるほど」という言い回しは、もしかしたら、喋り続けていると口の中が乾燥して酸性化してくることを表しているのかもしれません。
もっとも、私自身、長時間にわたって話を続けた際にも、「口の中が酸っぱくなった」と実感した経験はありません。むしろ、舌を活発に動かすことによって、唾液の分泌が促進されるような気もします。この表現は「口が酸(す)くなる」という形で江戸時代の洒落本・戯作本に登場してきますが、この手の文学によく見られる比喩だったのではないでしょうか
(以下は、私の推測です)。「酸(す)い」の語源になっている「酢(す)」に対しては、米や酒が悪くなってできるということもあって、日本人は必ずしも良いイメージを抱いていません。「酢にする(無駄にする)」「酢の過ぎた(行き過ぎた)」「酢を買う(余計なことをする)」などの言い回しがあります。また、「酸(す)し」が転じた「鮨(すし)」も、もともとは魚貝類を塩や飯に漬け込んで発酵させた酸っぱい「なれ鮨」のことで、ここから、「馴れ馴れしく嫌みなこと」を表す「酸(すし)なり」という遊郭表現も派生しています(『角川古語大辞典』(角川書店)より)。ですから、理屈ではなく、「あまりに時間を掛けて話しているうちに(唾液が悪くなって)口の中で酢ができてしまう」という誇張した表現として、「口が酸っぱくなる」と言ったように思われます。
【Q&A目次に戻る】

体細胞クローンは核移植によって作るので、細胞核の遺伝子によって決定される形質に関しては全てのクローンで同一になりますが、後天的に変化し得る形質は必ずしも等しくなりません。そもそも遺伝子とは、生物の完全な設計図を与えるものではなく、個々の細胞が特定の環境に置かれたときにどのように応答するか──例えば、膜タンパク質にある化学物質が結合したときに、細胞内でどのような化学反応が開始されるか──を規定しているにすぎません。さらに、タンパク質・脂質分子への糖鎖の付き方や、新規な病原体にも対応できる抗体の産生の仕方など、生物には、核遺伝子の規制を受けずに自然に多様性を獲得するような仕組みも備わっています。したがって、クローン個体といえども、温度・日照といった物理的環境や摂取される栄養分など、さまざまな後天的な要因に応じて、相当のヴァリエーションを示すことになります。実際、日本に数多くいるクローン牛の実物を見ると、ホルスタイン種特有の白黒のブチ模様などは後天的なものであり、遺伝子が同一であっても外見はかなり違うことがわかります(この点は、私自身、「21世紀・夢の技術展」(2000年8月、東京ビッグサイト)に出展された2頭のクローン牛で確認しました)。
クローン人間の個体識別は、一卵性双生児の場合よりもむしろ容易だと推測されます(一卵性双生児は、二人ともほぼ同一の環境で育てられるため、類似性が非常に高くなっています)。指紋に関して言うと、渦状紋(日本人に多い)・弓状紋・蹄状紋のような大まかな模様は人種によって出現頻度が異なっており、遺伝の影響を受けていると考えられますが、個体識別に使う詳細パターン(線の切れ方や分岐の位置関係)は後天的で、クローン個体同士でも異なっています(ただし、「12の詳細パターンが一致すれば同一人物だと認められる」という経験則がクローン人間にも適用できるかどうかは知りません)。虹彩も詳細パターンを完全に調べれば、指紋と同じようにクローン個体を識別できるはずです。ただし、声紋はもともと識別水準が低く、口腔や声帯の構造が類似しているクローン個体を区別することはできないかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

具体的な話の方がわかりやすいと思いますので、強磁性体におけるスピン(個々の原子が持つ磁気モーメント)を例にして説明します。強磁性体が高温になっているとき、熱的な擾乱によって原子のスピンはバラバラになっていますが、温度を一定温度(キュリー温度)以下にすると、近くのスピン間で向きを揃えるような相互作用が働き、あるブロック内部でスピンがほぼ同じ方向を向くようになります。これが、相転移によって自発磁化を起こした状態です。高温状態では、特定の“向き”というものがなく、系全体を回転させても同じ状態になっていましたが、低温でスピンが配向しているときには、こうした回転対称性は“自発的に”(=外部から特定の向きになるように強制されずに)破れたことになります。
ここで、磁化の向きの周りに個々のスピンを歳差運動させることを考えます。もともと回転対称性があり、磁化がどの向きになるかは全くの偶然で決まったのですから、全てのスピンの向きをいっせいに変えても、系のエネルギーは変わりません。と言うことは、歳差運動の位相を少しずつずらした長波長の「スピン波」を作るのに必要なエネルギーも、きわめて小さくて済むはずです。こうしたスピン波は、波長が無限大になると振動数がゼロに漸近する──これは、振動せずにスピンがいっせいに向きを変えることに対応します──という特徴的な分散関係(波長と振動数の関係)を持っています。
量子力学的な系では、波動は量子化されて粒子のように振舞うことが知られています。スピン波を量子化した“準粒子”はマグノンと呼ばれており、磁化の温度変化などに関与しています。マグノンのエネルギーは、光子の場合と同様に、振動数をνとするとhνで与えられ、分散関係からわかるように、波長が無限大のものはエネルギーを加えずに生成することができます。このように、対称性の破れに伴って生じる励起エネルギーがきわめて小さい(極限ではゼロの)粒子のことを、南部=ゴールドストーン粒子と呼びます(こうした粒子の存在を最初に予言したのは南部陽一郎ですが、難解な南部理論をわかりやすく解説したゴールドストーンの名を冠して、欧米ではゴールドストーン粒子またはゴールドストンと呼ぶのが一般的です)。結晶振動を量子化したフォノンも、並進対称性が破れたことによって生まれるゴールドストーン粒子です。
ゴールドストーン粒子はきわめて小さなエネルギーで作ることができるため、適当な条件が整うと、無限個のゴールドストーン粒子が生成されて特別の状態(ボーズ=アインシュタイン凝縮の状態)を作ることがあります。こうした状態は、しばしば直観に反する独特の物理現象をもたらします。例えば、マグノンが凝縮した場合には、ある範囲で温度上昇とともに自発磁化が増加することがあります。
励起エネルギーがゼロの粒子が生じるという南部=ゴールドストーン機構は、物性論だけでなく素粒子論の分野でも重要な役割を果たしています。光子以外の素粒子が質量を持っているのは、このメカニズムによると考えられています。
【Q&A目次に戻る】

話を簡単にするために、まず、月と地球という2つの物体だけから成るシステムを考えましょう。月は、地球の1/81.3の質量を持つ(太陽系の中では異例と言って良い)巨大な衛星です。このため、月と地球は連星系を構成しており、それぞれが、地球の中心から赤道半径の70%ほど月寄りの所にある重心の周りをケプラー運動していると見なせます(太陽まで含めて考えた場合には、地球の公転軌道が、月からの重力を受けて、楕円軌道からフラフラとずれるように見えます)。地球を剛体とし、重心の周りのケプラー運動を円運動で近似すると、地球の全ての部分が同じ(半径4670km、周期27.5日の)円運動をしていることになり、地球に固定した座標系では、円運動に伴って、場所によらず一定の遠心力が生じます。この遠心力は、地球の中心では月からの重力と完全に打ち消しあいますが、地表付近では、月からの重力と遠心力の合力(=潮汐力)がゼロではなくなります(下図)。図からわかるように、潮汐力は月に最も近い地点で月方向に最大になり、最も遠い地点で(遠心力が効いて)逆向きに最大になります。海水は、この潮汐力を受けて移動するので、満潮は1日に2回訪れます。
図のA点で単位質量の物体に加わる潮汐力の大きさは、次のように計算できます。
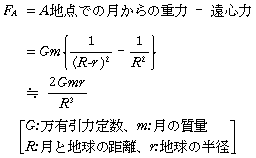
地表での重力加速度gを使うと、これは、
1.1×10
-7g
となり、10トンの海水に対して1g重程度の値になります。C地点での潮汐力の大きさはA地点と同じ、B,D地点では約半分です。
変形した海面の形は、地球の重力と潮汐力によるポテンシャルが一定になるという条件から求められます。導き方は省略しますが、(地球を剛体球として)赤道上での等ポテンシャル面の球面からのずれ h は、
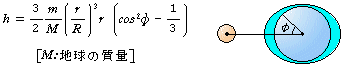
という形で与えられます。満潮になるのは、φ=0°,180°で h=35.7cm、干潮になるのは、φ=90°,270°で h=-17.9cm という値になります。
ただし、実際の海面変化は、上の議論では無視されているさまざまな効果のため、この値とはかなり異なっています。例えば、太陽による潮汐力は、月によるものの半分近く(0.515×10
-7g)にもなります。
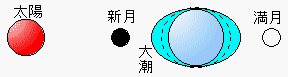
この結果、太陽と月が同じ方向にある満月・新月のときは干満の差が大きい大潮となり、そこから90°ずれた上弦・下弦の月のときには小潮になります。天文学的なパラメータとしては、このほかに、月の公転面に対する地球の自転軸の傾きや、月と太陽の公転面のずれを考慮する必要があります。また、地球上のパラメータでは、地形や潮流の影響が重要で、これらが複雑に絡んで、有明海などで見られるような数メートルに及ぶ干満の差をもたらすことがあります。
(【参考文献】『潮汐・潮流の話』(柳哲雄著,創風社出版)
【Q&A目次に戻る】

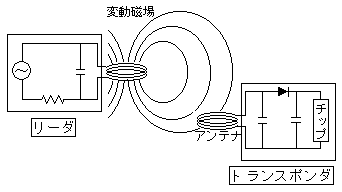
ICカードのシステムは、カードに埋め込まれたトランスポンダが、送信されたコマンドに対してどのように応答するかをリーダで読みとるという仕組みになっており、単純なシステムの場合、トランスポンダとリーダの間の信号のやり取りには、コイルの相互誘導が利用されます。こうしたシステムでは、リーダが発生させた一定周波数の変動磁場が、これと共振するトランスポンダの回路にエネルギーを供給して固有の電流を誘起する一方、その反作用としてリーダの内部抵抗における電圧が減少するので、この電圧変化を読み取ることで、トランスポンダの応答がわかるわけです。
コイル間の相互誘導を担う磁場は、コイルからの距離r に対して、1/r
3という距離依存性を持っています。大きさが無視できる微小ループアンテナに交流(対応する波長λ)を流した場合、距離r の地点での磁場は、次の公式で表されます(導き方は、アンテナに関する教科書を参照のこと):
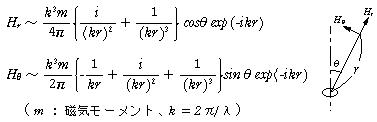
ここで、1/r
3に比例する項が相互誘導を引き起こす近傍界を表しているのに対して、1/rの項は、電場と対になって空間を伝播していく波動(電磁波)を意味します。電磁波は、ひとたびアンテナから放射されると、もはやリーダの側で制御することも反作用を測定することもできないため、ICカードのシステムで利用することは一般にできません(電磁波を利用するには、別のシステムが必要になります)。磁場の公式からわかるように、kr=1 (r=λ/2π)を境に、それより遠方では近傍界よりも電磁波の磁場の方が強く、相互誘導に基づいてトランスポンダからの応答を測定するのは難しくなるので、この距離が「電磁誘導システムでは克服できない制限」ということになります。
(【参考文献】『非接触ICカードの原理と応用』(K.Finkenzeller著,日刊工業新聞社)
【Q&A目次に戻る】

熱力学的に安定した混合状態が実現されている場合、物質の分離は自然には起こりません。何らかの人為的操作や環境との相互作用が伴っているはずです。こうした操作や相互作用の全てを包含するような一般論は存在せず、分離法に応じて個別に問題を設定していかなければなりません。
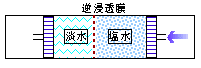
例えば、海水から淡水を作る方法として、分子半径の大きい電解質を通さない逆浸透膜を用意し、浸透圧に抗する力で海水を押し出していく方法があります。ここで、準静的・断熱的にピストンを押した場合、エントロピーが一定のまま水と電解質を分離することになります。溶液では(化学ポテンシャルなどの項があるので)少し難しいかもしれませんが、混合された2種類の理想気体を半透膜で分離する過程ならば、たいがいの熱力学の教科書で解説されています。
蒸留によって混合液体を分離する場合は、相変化に伴うエントロピーの増減を考慮する必要があります。ある成分だけが蒸発して他の成分が濃縮されていくとき、後者に関しては体積が収縮することによってエントロピーが減少しますが、前者が蒸発する際のエントロピー増大がこれを圧倒して、全体としてはエントロピー増大の過程になります。こうした過程を解析するに当たっては、熱を少しずつ断続的に流入させ、各段階での平衡条件を考えていけばわかりやすいでしょう。ただし、蒸発した成分だけを取り出す過程はしばしば不可逆であり、別途考察する必要があります。
溶液中で特定の成分が析出・沈殿する過程に関しては、溶媒の蒸発・温度の低下(環境への熱の流出)・薬品の添加による化学反応の進行など、その成分のエントロピー減少を補償する何らかの不可逆過程が先行しているはずであり、これらを化学熱力学的に正しく評価しなければなりません。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
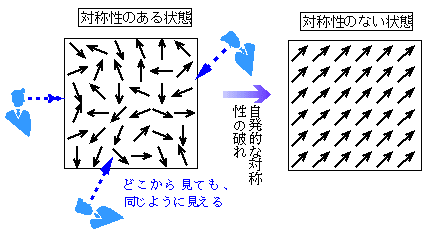
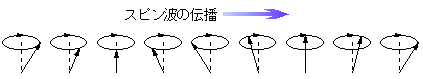
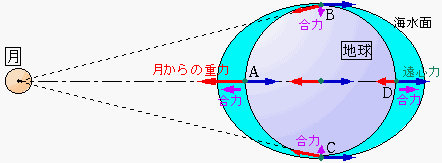
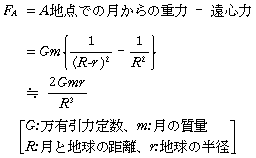
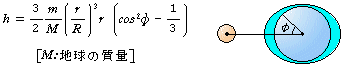
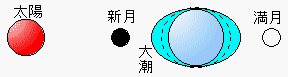 この結果、太陽と月が同じ方向にある満月・新月のときは干満の差が大きい大潮となり、そこから90°ずれた上弦・下弦の月のときには小潮になります。天文学的なパラメータとしては、このほかに、月の公転面に対する地球の自転軸の傾きや、月と太陽の公転面のずれを考慮する必要があります。また、地球上のパラメータでは、地形や潮流の影響が重要で、これらが複雑に絡んで、有明海などで見られるような数メートルに及ぶ干満の差をもたらすことがあります。
この結果、太陽と月が同じ方向にある満月・新月のときは干満の差が大きい大潮となり、そこから90°ずれた上弦・下弦の月のときには小潮になります。天文学的なパラメータとしては、このほかに、月の公転面に対する地球の自転軸の傾きや、月と太陽の公転面のずれを考慮する必要があります。また、地球上のパラメータでは、地形や潮流の影響が重要で、これらが複雑に絡んで、有明海などで見られるような数メートルに及ぶ干満の差をもたらすことがあります。
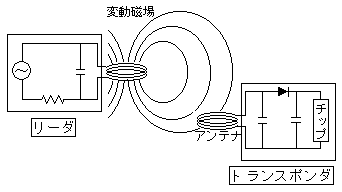 ICカードのシステムは、カードに埋め込まれたトランスポンダが、送信されたコマンドに対してどのように応答するかをリーダで読みとるという仕組みになっており、単純なシステムの場合、トランスポンダとリーダの間の信号のやり取りには、コイルの相互誘導が利用されます。こうしたシステムでは、リーダが発生させた一定周波数の変動磁場が、これと共振するトランスポンダの回路にエネルギーを供給して固有の電流を誘起する一方、その反作用としてリーダの内部抵抗における電圧が減少するので、この電圧変化を読み取ることで、トランスポンダの応答がわかるわけです。
ICカードのシステムは、カードに埋め込まれたトランスポンダが、送信されたコマンドに対してどのように応答するかをリーダで読みとるという仕組みになっており、単純なシステムの場合、トランスポンダとリーダの間の信号のやり取りには、コイルの相互誘導が利用されます。こうしたシステムでは、リーダが発生させた一定周波数の変動磁場が、これと共振するトランスポンダの回路にエネルギーを供給して固有の電流を誘起する一方、その反作用としてリーダの内部抵抗における電圧が減少するので、この電圧変化を読み取ることで、トランスポンダの応答がわかるわけです。
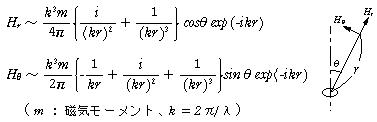
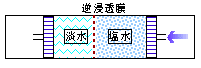 例えば、海水から淡水を作る方法として、分子半径の大きい電解質を通さない逆浸透膜を用意し、浸透圧に抗する力で海水を押し出していく方法があります。ここで、準静的・断熱的にピストンを押した場合、エントロピーが一定のまま水と電解質を分離することになります。溶液では(化学ポテンシャルなどの項があるので)少し難しいかもしれませんが、混合された2種類の理想気体を半透膜で分離する過程ならば、たいがいの熱力学の教科書で解説されています。
例えば、海水から淡水を作る方法として、分子半径の大きい電解質を通さない逆浸透膜を用意し、浸透圧に抗する力で海水を押し出していく方法があります。ここで、準静的・断熱的にピストンを押した場合、エントロピーが一定のまま水と電解質を分離することになります。溶液では(化学ポテンシャルなどの項があるので)少し難しいかもしれませんが、混合された2種類の理想気体を半透膜で分離する過程ならば、たいがいの熱力学の教科書で解説されています。