
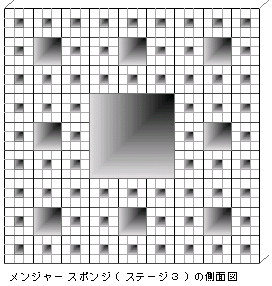
はじめに、フォトニックフラクタルについて説明します。
フォトニックフラクタルとは、大阪大学と信州大学の研究チームが電磁波を閉じ込める実験を行った誘電体のことです(ただし、トラップしたのはマイクロ波なので、“フォトニック”という呼称はあまり適切ではないでしょう)。具体的には、セラミック粉末を混合したエポキシ樹脂を、光造形の手法を使って、1辺27mmのメンジャースポンジ(ステージ3)
(*)に加工したものが利用されました。フラクタル構造を持つ空洞内部で特殊な局在波が形成されるという予測は1990年代初頭に提出されており、アメリカの研究者によって音波に関する数値計算などが行われていましたが、フラクタル構造を持つ誘電体を実作して電磁波を閉じ込めるという実験は、今回が初めてです。
(*)ある立方体を3×3×3=27個の立方体に分割し、側面の中央に位置する立方体を取り除くと、ステージ1のメンジャースポンジとなる。残った部分立方体を同様に27個に分割し、側面の中央を除いたものがステージ2で、以下、同じ作業を続けていくと、ステージ3、ステージ4…のメンジャースポンジが得られる。
この実験では、メンジャースポンジ型の誘電体にギガヘルツ帯の電磁波を照射したところ、8GHzの付近で透過ないし反射する電磁波が1万分の1まで急激に減衰する現象が見られました。そこで、誘電体内部の空洞にアンテナを挿入して測定したところ、内部に電磁波が局在していることが確かめられたとのことです。閉じ込め時間は約1千万分の1秒で、局在が観測されたのも波長の長いマイクロ波ですから、すぐに何かの役に立つものではありませんが、理論的にはたいへん興味深い現象です(一部新聞報道は、応用面がかなり誇張されています)。
なぜフラクタル誘電体の内部に電磁波が閉じ込められたのか、正直な話、よくわかりません。8GHzの電磁波の波長が37.5mmなのに対して、最大の立方体ブロックは1辺が9mmなので、単純な空洞共振とは異なります。実験データを見ると、吸収スペクトルがかなり鋭くなっており、基本的な局在モードが励起されたと考えざるを得ないのですが、どのようなモードなのかは、今後の理論的研究を待たなければなりません。
質問では、八木アンテナとのアナロジーについて言及されていますが、アンテナ素子は入射波と共振しやすい半波長程度の長さであり、また、誘起電流による2次電磁場による干渉を利用しているので、フォトニックフラクタルと直接的な関係はありません。しかし、いくつかの素子を並べたときに、相互の干渉によって特定の向きで利得が大きくなるという八木アンテナの基本的な性質が、イメージの上でつながりを持つことは、充分にあり得ます。
八木アンテナ開発当初は、マクスウェル方程式を手計算で近似的に解かなければならなかったため、設計するのがたいへんでした。しかし、現在では、パソコン用のソフトを使って、最適な反射器や導波器の長さ・間隔、そのときの利得の理論値などを簡単に計算することができます。
【参考文献】大阪大学宮本研究室のホームページ
【Q&A目次に戻る】

宇宙空間が生物の生存に不適切である最大の理由は、きわめて真空に近いことです。大気は地表から離れるとともに急激に減少し、高度15km程度で肺胞における酸素交換が困難になります。さらに、0.05気圧となる高度20kmでは、体液が沸騰するという現象が見られます。これは、急減圧の効果として、ちょうどサイダーの栓を抜いたときと同じように体液中に細かな気泡が発生するもので、この気泡が細い血管に詰まると、空気塞栓と呼ばれる症状を引き起こします。似たような症状は、水に潜っていた人が急浮上したときにも見られますが、真空に放り出された場合には、はるかに激越で、数秒から10秒程度で意識を喪失し、短時間で死に至ると言われています(少し残酷ですが、犬などを用いた動物実験が行われています)。ただし、安手のSF小説に描かれたように、体が破裂したり内臓が口から飛び出したりすることはありません。
圧力服などによって空気塞栓や窒息を免れたとしても、こんどは、温度の問題に直面します。大気がないために、宇宙空間で物質は恒星からの放射によって直接加熱されます。このため、地球周回軌道上では、太陽光にさらされた部分は100℃以上に、日陰になった部分は-100℃以下になります。いずれにせよ、数分も生きられる環境ではないのです。
このほか、放射線(銀河宇宙線・太陽放射線・捕捉放射線など)の問題もあります。放射線の強度は場所によって異なっており、高度400km程度の低高度周回軌道上では、ヴァンアレン帯が低く落ち込んでいる領域を除くと、急性放射線障害で死亡するほど放射線は強くありませんが、それでも、ガンや白内障などの病気の原因になります。
【Q&A目次に戻る】

はじめに明言しておきますが、マゲイジョのVSL(
Varying
Speed of
Light)理論は、巷に溢れる「相対論は間違っていた」なる主張とは、一線を画するものです。相対論の批判者たちが、ローレンツ不変性──特に、同時刻の相対性──に異議を唱えるのに対して、VSL理論では、局所的なローレンツ不変性は保たれており、時間的・空間的に狭い範囲で見る限り、特殊相対論はそのまま成り立っているからです。この理論は、宇宙論的な規模で考えたときに、光速が可変であることを主張するものです。
宇宙論の謎の1つに「地平線問題」があります。観測可能な極限である宇宙の地平線付近は、どの方向でもほぼ同じ状態になっています。例えば、地平面における天の北極Nと南極Sとでは、エネルギー分布などに差は見られません。ところが、ビッグバン直後には、この2点は、もはや相互作用することのない(すなわち、相手から発射された光はいくら待っても届かない)地点まで離れているため、緩和過程によって均質化されて「ほぼ同じ状態」になるはずがないのです。この問題を解決する(暫定的な)“定説”となっているのが、インフレーション理論です。この理論によると、NとSは、ビッグバンの直後には相互作用できるほど近くにあったにもかかわらず、過冷却状態の時期に宇宙全体が急膨張したため、相手から出た光が届かないほど引き離されて現在に至ったということになります。マゲイジョのVSL理論は、この“定説”の対抗馬として提出されたもので、初期の宇宙では、光速は現在の理論で想定されているよりも大きく、NとSは(インフレーションのない)ビッグバン理論で示されるほど離れていたにもかかわらず、互いに相互作用して均質化されたというのです。
カール・ポパーが正しく指摘したように、科学的な理論は、反証可能でなければなりません。マルクス経済学やフロイトの精神分析学は、信奉者の手に掛かれば、どんな社会的・心理的現象も見事に説明してしまい、当の学説が「間違っている」ことを立証するのは不可能です。これに対して、科学的な理論は、その理論を信じているいないにかかわらず、演繹的な手続きによって検証可能な“予言(prediction)”を導き出せることが要請されます。対抗理論とは異なる予言が提出され、実験・観測によって予言の妥当性が否定された場合、理論自体が棄却されることになります。さまざまな理論を提出しては、検証を通じて最適な理論を選び出す作業が継続的に行われることが、科学の信頼性を保証する根拠になっています。この観点からすると、VSL理論は、間違いなく正当な科学的理論の1つであると言えます。
それでは、多くの宇宙論研究者がVSL理論を真剣に検討しているかというと、そうでもありません。この理論には、いくつかの弱点があり、必ずしも信憑性の高い理論とは言えないからです。
ここで考えなければならないのは、「物理定数」とは何かという問題です。一般的な理解では、物理定数は2種類に分けられます。
- 単位を決めるための換算定数:プランク定数、ボルツマン定数、アボガドロ数、熱の仕事等量…etc
- 物理的な定数
- 万有引力定数またはプランク長
- 電気素量または微細構造定数(および他のゲージ結合定数)
- 電子質量(および他の素粒子の質量と混合角、ヒッグス理論ではヒッグス結合定数)
「物理的な定数」に分類したものの大半は、相転移などのダイナミカルな過程を通じて派生的に定まった2次定数だと考えられていますが、これらを導く理論は、まだ完成していません。
理論物理学において特に重要なのが、時間と空間の単位を結びつける定数です。時空を幾何学的な多様体と見なす立場からすると、時間と空間の拡がりは同じ単位で表すのが“自然”なのですが、歴史的な理由で[sec]と[m]のように異なる単位が使われるため、この2つを換算する定数として、c(=3×10
8[m/sec])が必要になります。
標準的な理論では、真空中の光は速度cで伝播するので、cはしばしば「光速」と呼ばれていますが、厳密に言えば、cと光速は別のものです。
VSL理論の初期バージョンでは、cと光速が同一視されており、方程式のあちこちに現れるcが、全て可変になるものとして扱われていたようです。しかし、『光速より速い光』の中で皮肉たっぷりに述べられているように、Physical Review Letter の査読者(この人は、マゲイジョが言うほど無能ではありません)に問題点を指摘され、形式的にローレンツ不変性を保つ(すなわち、単なる換算定数を分離した)「保守的なVSL理論」に改訂されました。この改訂版では、後で光速に等しいことが示される量 c' が、
ψ = log(c'/c
0) (c
0 : 現在の光速)
という場の量を介してダイナミカルな相互作用をすることになっています(J. Magueijo, gr-qc/0007036)。ψを導入した結果、相互作用項はやたらに複雑なものとなり、煩雑な計算を経て方程式を解いた結果として、光が c
0 より大きな c' で伝播することが導かれます。cは換算定数にすぎないという常識的な観点からすると、この「やたらに複雑な」形式が、VSL理論の本当の姿であるはずです。さらに、改訂版のVSL理論は、単に形式が複雑だというだけではなく、初期バージョンが持っていた革新性をも失っています。すなわち、光速がc
0より大きくなるのは、相対論の要請に反する現象ではなく、新たな場であるψの影響で電磁場などの伝播速度が変化してきたことを意味するにすぎません。改訂版のVSL理論を宇宙論に適用する試みは、まだ充分に展開されていないようですが、仮に初期バージョンと同程度の成功を収めるとすれば、標準理論ではともにcに等しいとされる重力場と電磁場の伝播速度が一致せず、ψとの相互作用によって重力が光より遅れて伝わるという内容になるはずです。
インフレーション理論が高く評価されるのは、アド=ホックな仮定を(あまり)置かずに地平線問題などが解決されるからです。これに対して、マゲイジョのVSL理論は、問題を解決するために相互作用の形式を大幅に変更しており、その分だけ説得力に欠けると言わざるを得ません。光速がcと異なる理論は、古典的なド=ブロイの理論をはじめとして、いくつも提唱されていますが、ほとんどが泡沫理論として泡のように消え去っています。多くの物理学者は、VSL理論も同じ運命を辿ると考えて、黙殺を決め込んでいるのでしょう(“黙殺”とは、研究するに値しないと思われる理論に対する明確な意思表明です)。
学界の実状に疎い人にはわかりにくいでしょうが、理論物理学の現場では、VSL理論並に非常識な理論が無数に考案されています。最先端分野を研究する物理学者にとって、ちょっとした思いつきに基づく新理論は遊ぶのに手頃な“おもちゃ”であり、少し計算してものになりそうか試してみるのは、日常的なことです(ちなみに、私も大学院生時代に、重力場のラグランジアン密度を R ではなく 1/R にすると、無限の過去から、はじめのうちはゆっくりと、次第に加速するように膨張する宇宙になるというムチャクチャな理論を考案したことがあります)。マゲイジョは、自分の発見がいかにも斬新であるかのように書いていますが、おそらく、多くの物理学者が似たようなことを思いつき、少し煮詰めてから、あまりエレガントでないとして放棄したのではないでしょうか。
【Q&A目次に戻る】

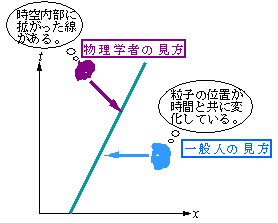
特殊相対論に関する質問は後を絶ちませんが、多くの人は、空間の中を時間の経過に従って物体が移動することを“運動”と解釈しているために、理論の本質が理解できずにいるようです。相対論の要諦は、空間と時間とを一体化し、4次元のミンコフスキ時空として扱うことにあるのです。人間は、通常、物体を時間から切り離し、空間の内部に拡がって存在するものとして認識しますが、相対論的な世界観の下では、全ての物体が時間と空間の双方に拡がりを持つことになります。例えば、一般的な認識で「粒子が空間の中を一定速度で運動している」と把握される状況は、物理学的な記述では、「時空内部に一定の傾きを持った直線がある」となります。この見方によれば、「絶対運動・絶対静止がない」という良く知られた相対論の主張は、「ミンコフスキ空間では絶対的な傾きがない」となります。周囲に何もない宇宙空間に浮かんでいる一本の棒が、真っ直ぐなのか傾いているのか決めることができないのと同じように、ミンコフスキ空間での傾きも、何らかの基準に対して相対的に定義するしかないのです。
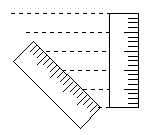
ユークリッド空間と同様に、ミンコフスキ空間でも、物理現象を記述する枠組みとしての“直交”座標系を、無数に定義することができます。ある座標系を「静止座標系」と呼ぶことにすると、それに対して傾いている座標系は「運動座標系」となりますが、もちろん、この呼称は、あくまで相対的なものです。こうした座標系の目盛りは、物理現象の普遍性によって決定できます。例えば、時間方向の目盛りは、その座標系で静止している原子時計によって、空間方向の目盛りは、単位時間に真空中で光が進む距離によって、それぞれ決めることができます。ただし、異なる座標系の間で目盛りは一致していません。これは、ある物差しとそれに対して傾いている物差しとでは、目盛りが重ならないのと同じです。各座標間の目盛り(座標)の関係は、ローレンツ変換の公式で与えられます。
ローレンツ変換によると、ある座標系に対して一定の角度で傾いた座標系の目盛りは、常に一定の割合(ローレンツ因子=(1-(v/c)
2)
-1/2)で伸びています。時間軸の目盛りの伸びを“人間的な見方”で表現すれば、「運動している時計は遅れる」ということになりますが、自分に対して相対的に運動している時計は、常に手元にあるわけではないので、この主張は、あくまで自分が使っている座標系で記述された内容に関するものとなります。「振り子の質量が増えたために周期が長くなった」などと解釈するのは、根本的に誤っています。時間の遅れが「ウラシマ効果」として物理的に実測されるためには、加速度運動によって傾きを変えるなどの物理的にノントリヴィアルな過程が必要です。
傾いている座標の目盛りは常に伸びると言いましたが、それではなぜ「運動する物体は収縮する」のか疑問に思うかもしれません。その理由は、“人間的な見方”では、運動する物体の長さを、自分の座標系における同時刻で定義するという慣習があるからです。物体が静止している座標系で記述した場合、この定義では、物体の先端よりも時間的に遅れて後端の位置を測定することになり、測定している間に物体が進んだ効果が「収縮」として現れるのです。実際、亜光速で運動している宇宙船を目で見たとしても、扁平に見えるわけではありません。ある時刻に目に到達する光は、宇宙船のいろいろな部分から同時に発射されたものではないからです。
総じて言えば、等速度運動に関する限り、相対論的な現象は幾何学的に解釈することが可能です。従って、特殊相対論を理解できるか否かの分かれ目は、時間を空間と同様の拡がりと見なす発想を受け入れられるかどうかにあると言って良いでしょう。
【Q&A目次に戻る】

現在の理論によると、「光子の大きさ」というものを考えることはできません。陽子や中性子のような複合粒子の場合は、構成要素が相互作用している拡がりを測定することができますが、光子やクォークのような“素”粒子(として扱われるもの)には、「大きさはない」と言うしかないのです。「波長」という概念は、電磁波の伝播のように、無数の光子が集団で運動している場合に、物差しで測れるような空間内部の長さとして意味を持つのであって、素粒子反応の範囲では、空間的な拡がりと直接結びつけることはできません。これは、周波数の逆数として定義される「周期」が、光子の時間的な拡がりを表していないのと同じです。
そもそも、光子を粒子のようにイメージすることが、混乱の元なのではないでしょうか。電子のような質量を持つフェルミオン(スピンが半奇数の素粒子)の自由状態は、個数が確定していて1個2個…と数えることができるので、あたかも粒子であるかのようにイメージすることが許されます。しかし、質量ゼロのボソンである光子は、一般に個数が確定しておらず、粒子描像はあまり適当ではありません。例えば、真空中を伝播する電磁波は、光子の個数が1個から無限個までの状態が重ね合わされたものであり、どんなに薄く拡がっても、「1個の光子が飛んでいる状態」にはなりません。粒子描像によって簡単に記述できるのは、光電効果やコンプトン散乱のように、摂動論の最低次が良い近似になっている場合に限られます。
【Q&A目次に戻る】

確かに、人間も光を浴びただけで生きるのに必要な栄養が作れるなれば、飢餓の恐怖がなくなって素晴らしいのですが、現実問題としては、かなり難しそうです。
体内で光合成を行うためには、葉緑体をオルガネラ(細胞内器官)として持つことが必要でしょう(サンゴ虫のように、光合成を行う藻類と共生するという方法もありますが、藻類を増殖させる場所をどう確保するかが問題になります)。葉緑体は、太古の昔にシアノバクテリアが単細胞真核生物の細胞内に取り込まれて形成されたとする説(共生起源説)が有力であり、形態的に見て独立性の高いオルガネラです。ただし、バクテリア時代に持っていた多くの遺伝子が、進化の過程で核染色体に移行しており、自己増殖機能はありません。クロロフィルやカロチノイドを合成するのに必要な酵素の大半は核染色体にコードされており、葉緑体は、出来上がった酵素をオルガネラ内部に取り込んで活動しているだけです。従って、人間の細胞内で葉緑体を増殖・機能させるためには、植物の核染色体が持つ遺伝子の多くを、遺伝子操作によって人間の染色体に組み込まなければなりません。
こうした人体大改造を行って葉緑体を持つ身体になったとしても、人間が独立栄養生物になれるわけではありません。決定的なのは、表面積が不足しているという点です。ミドリムシのような単細胞生物ならば、鞭毛を動かすのに必要なエネルギーを光合成で得ることもできますが、骨格や筋肉によって動き回るような大型動物の身体を、エネルギー密度の低い太陽光で維持することは不可能です。これは、体のスケールがn倍になると、体積はn
3倍になるのに、表面積はn
2でしか増えないことの帰結です。細胞内部に葉緑体を持つ人間を作ったとしても、身体活動を維持するのに必要な栄養(必須タンパク質やミネラルも含む)の大半は口から摂取せざるを得ず、皮膚表面での光合成は、ごく僅かな補助的栄養源となるにすぎません。エネルギー効率の観点からすると、地球上の生き物が、太陽光が照射される地域でほとんど動かずに繁殖する大量の植物と、移動しながら栄養を摂取する少数の動物に分かれているのは、自然な成り行きなのです。
【Q&A目次に戻る】

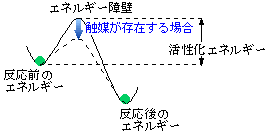
自然に進行する化学反応とは、エネルギーが極小状態にある(すなわち、外からエネルギーを加えなければ状態を変えないような)いくつかの物質が、より低い別の極小状態へと変化する過程です。こうした変化が実現されるためには、反応系が、途中にあるエネルギーの高い状態を通り抜けなければなりません。熱運動の揺らぎによって、この“エネルギー障壁”を乗り越えるのに必要なエネルギー(=活性化エネルギー)を偶然に得ることがありますが、エネルギー障壁が高い場合、その確率はきわめて低くなり、反応はゆっくりとしか進行しません。触媒とは、一般に、こうした化学反応の途中に関与して、活性化エネルギーを小さくする役割を果たす物質のことです。反応の前後で触媒は変化していませんが、反応の途中では他の物質と何らかの形で結合しているのがふつうです。
過酸化水素が分解されて酸素を放出する過程は、化学式では、次のように表されます:
2H
2O
2 → 2H
2O + O
2
この反応は、常温ではゆっくりとしか進みませんが、適量の二酸化マンガン(硫化銅や塩化第二鉄でも可)を加えると、過酸化水素水が激しく泡立つように見えるほど急速に進行することが知られています。二酸化マンガンの結晶は水に溶けないため、こうした触媒反応は、溶媒中に浮遊する何個かの分子やイオンがぶつかって起きる通常の化学反応とは異なり、過酸化水素分子が結晶表面に吸着されて起きる「接触分解」の反応になります。固体表面で生じる触媒反応は、不均一触媒反応と呼ばれており、具体的な反応過程が完全に解明されているわけではありませんが、一般に、(1)反応物(この場合はH
2O
2)の吸着、(2)表面上での化学変化、(3)生成物(H
2O と O
2)の解離──という順序で進みます。複数の原子が分子としてまとまっていられるのは、分子内部の電子が特定の軌道状態にあるからですが、この分子が結晶表面に吸着されると、結晶の電子の一部が分子に入り込んで軌道の混成が生じ、結合エネルギーが変化します。二酸化マンガンに吸着された過酸化水素分子の場合は、酸素原子を結合する力が弱くなり、最終的に、水分子と酸素分子に分解されるわけです。なお、二酸化マンガンの場合は、吸着した原子を全て放出するので、反応の前後で見るとそれ自身は変化していませんが、硫酸第一鉄を使って同じような実験を行うと、過酸化水素の分解速度は速くなるものの、鉄自身が酸化されて第二鉄になってしまうので、触媒とは言えません。
不均一触媒反応は、合成や改質を行うために化学工業でさかんに利用されていますが、その具体的なプロセスが解明されるようになったのは、ここ20年ほどのことです。例えば、鉄を触媒として水素と窒素からアンモニアを合成するハーバー法は1914年に実用化されましたが、実際に鉄の表面でどのような反応が起きているか明らかにされたのは1984年です。X線光電子分光法などを利用した原子間力の測定実験の結果、鉄の表面に吸着された窒素の分子は、結晶から電子が入り込むことによって結合エネルギーが変化し、原子間の結合の強さは、
水素-窒素 > 窒素-鉄 > 窒素-窒素
の順序になることがわかりました。このため、鉄の表面にくっついた窒素原子は、周囲にある水素原子と結合してアンモニア分子(NH
4)になり、鉄から離れていくことができるのです。
【Q&A目次に戻る】

地磁気は、大気とともに宇宙線の進入を防ぐバリアとなっています。したがって、地磁気が失われると、生態系や人間の健康にもさまざまな影響が生じます。
太陽や他の銀河などから飛来する放射線の一種の「宇宙線」は、主に高エネルギー荷電粒子の流れであり、磁場内部に進入すると、フレミングの左手の法則に従って方向を変えます。他の粒子との相互作用がなくエネルギーが失われないと仮定すると、磁場境界面に垂直に入射した粒子は、円軌道を描いて向きを反転させ、宇宙空間に跳ね返されます。実際には、荷電粒子の一部は大気との相互作用でエネルギーを失い、磁力線に巻き付くように運動して滞留するため、高エネルギー荷電粒子が閉じこめられた放射線ベルト(ヴァンアレン帯)が形成されています。
磁場の弱い高緯度地方では、跳ね返されずに地表に到達する宇宙線の割合が多くなります。アメリカでのデータによると、メキシコ国境に比べてカナダ国境付近では、腎臓ガンによる死亡率が30-40%高くなっていますが、これは、宇宙からの放射線量が多いためだと考えられています。このほか、乳ガンや先天性異常による胎児死亡率も、高緯度地方の方が高くなります。地磁気が弱くなると、宇宙線によるガンの増加や生殖能力の低下などが、低緯度地方にも及ぶようになるはずです。
古代の岩石に閉じこめられた磁性鉱物を調べた結果、過去5億年の間に地磁気の極性が20万年に1回の割合で反転したことが判明しています。地磁気が反転するメカニズムはまだ解明されていませんが、アフリカ最南端に地磁気が周囲と逆向きになっている領域が見つかっており、こうした反転領域が拡大して最終的には全球的に地磁気が逆になると考えられます。反転が起きる時期は予測不能ですが、現在の地球は反転期にあるらしく、地磁気は急速に弱まりつつあり、このペースで進むと、西暦3000年代の早い時期に完全に失われてしまう可能性があります。
最近公開された『コア』というアメリカ映画では、地磁気の喪失に伴う放射線量の増大によって人類が存亡の危機に立たされるという状況が描かれていました。しかし、実際には、それほど深刻な事態にはならないと考えられます。われわれが地表で浴びている放射線のうち、宇宙線に由来するものは、1/8程度にすぎません。しかも、宇宙線の大部分は大気によって遮蔽されるので、地磁気がなくなっても、放射線の増加は、大規模な絶滅を引き起こすほどのものにはならないはずです。渡り鳥のように地磁気を利用している生物には大きな影響が出るものの、それ以外では、おそらく、支配種の交代といった生態系の部分的な変動が見られるだけにとどまるでしょう。
【Q&A目次に戻る】

色彩の知覚をもたらす生化学的反応は、網膜にある光受容タンパク質が特定波長の光を受けて立体構造を変化させることに始まります。物体から反射される光のスペクトル(波長と強度の関係)は物理的に与えられていますし、光受容タンパク質の構造は遺伝子によって決定されていますから、この反応には、ほとんど個人差はありません(遺伝的な変異で光受容タンパク質の構造が通常と異なっているために、色覚異常が生じるケースもありますが、ここでは考えないことにします)。「赤と緑を異なる色として区別する」といった基本的な色彩識別能力は、人種や文化によらず、万人にほぼ共通していると言えるでしょう。しかし、網膜からの信号が脳の視覚野に送られた後で生じる神経興奮の過程は、後天的な要素が関与するため、誰もが同じセンセーションを感じているとは限りません。
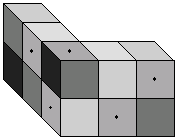
色彩の知覚が、網膜に入力された光の物理的性質をそのまま表象したものでないことは、錯視の実験で明らかにされています。例えば、右の図形は5段階の明るさで塗り分けられていますが、中間の明るさで描かれているのは、真ん中に黒い点を付けた5つの四辺形です。おそらく、左側上面の四辺形と左側面の四辺形は異なる明るさに見えていると思いますが、これは、脳が“照明の当たり方”を判断し、本来あるべき色を推定しているからです(色に関する錯視は、
別の回答でも紹介しています)。このように、目に見えているままと思われがちな色彩でも、脳の神経回路における複雑な情報処理を経て知覚されているので、たとえ物理的に同一スペクトルの光であっても、神経回路の構成が異なっている場合は、全く違うセンセーションを引き起こすことがあり得ます。
神経回路の基本的な構成は、発生初期に急速に増殖した神経細胞のうち、不適切な配線のものが“間引かれる”という過程を通じて、胎児の段階でできあがってしまうので、だいたい似たり寄ったりのものになっているはずです(上の図形についても、ほとんどの人が同じ錯覚に陥ります)。しかし、時には、配線ミスとでも言えそうなケースが生じることが知られています。例えば、“共感覚”と呼ばれる特殊な感覚の持ち主は、「ピアノのド音が青い色として感じられる」とか「数字の2が赤く見える」という不思議な体験をします。これは、単に「ピアノの音を聴くと色のイメージが付随して現れる」ということではなく、聴覚入力が視覚情報を処理する部位に送られるように神経が配線されてしまい、音そのものが青く見えることだと考えられています
(V.S.ラマチャンドラン/E.M.ハバード「数字に色を見る人たち」(日経サイエンス、2003年8月号p.42))。“共感覚”は、既知の2つの知覚が混じりあうタイプの異常なので、問診などを通じて何を感じているかを推測することが可能ですが、1つの知覚が全般的に変容している場合は、他人がそのセンセーションを推し量ることは困難でしょう。識別に関して見解の相違が生じない限り、海の色を苦味として、砂糖の味を薄紅色として感じている人がいたとしても、外からはわかりませんし、そもそも、「苦味」とか「薄紅色」といった概念自体が、何を指示しているのか不明になります。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
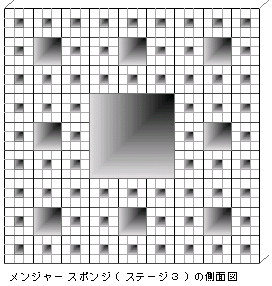 はじめに、フォトニックフラクタルについて説明します。
はじめに、フォトニックフラクタルについて説明します。
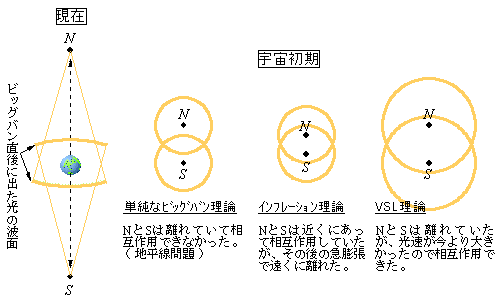
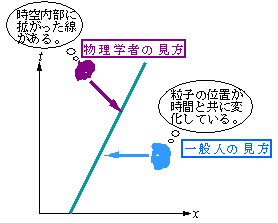 特殊相対論に関する質問は後を絶ちませんが、多くの人は、空間の中を時間の経過に従って物体が移動することを“運動”と解釈しているために、理論の本質が理解できずにいるようです。相対論の要諦は、空間と時間とを一体化し、4次元のミンコフスキ時空として扱うことにあるのです。人間は、通常、物体を時間から切り離し、空間の内部に拡がって存在するものとして認識しますが、相対論的な世界観の下では、全ての物体が時間と空間の双方に拡がりを持つことになります。例えば、一般的な認識で「粒子が空間の中を一定速度で運動している」と把握される状況は、物理学的な記述では、「時空内部に一定の傾きを持った直線がある」となります。この見方によれば、「絶対運動・絶対静止がない」という良く知られた相対論の主張は、「ミンコフスキ空間では絶対的な傾きがない」となります。周囲に何もない宇宙空間に浮かんでいる一本の棒が、真っ直ぐなのか傾いているのか決めることができないのと同じように、ミンコフスキ空間での傾きも、何らかの基準に対して相対的に定義するしかないのです。
特殊相対論に関する質問は後を絶ちませんが、多くの人は、空間の中を時間の経過に従って物体が移動することを“運動”と解釈しているために、理論の本質が理解できずにいるようです。相対論の要諦は、空間と時間とを一体化し、4次元のミンコフスキ時空として扱うことにあるのです。人間は、通常、物体を時間から切り離し、空間の内部に拡がって存在するものとして認識しますが、相対論的な世界観の下では、全ての物体が時間と空間の双方に拡がりを持つことになります。例えば、一般的な認識で「粒子が空間の中を一定速度で運動している」と把握される状況は、物理学的な記述では、「時空内部に一定の傾きを持った直線がある」となります。この見方によれば、「絶対運動・絶対静止がない」という良く知られた相対論の主張は、「ミンコフスキ空間では絶対的な傾きがない」となります。周囲に何もない宇宙空間に浮かんでいる一本の棒が、真っ直ぐなのか傾いているのか決めることができないのと同じように、ミンコフスキ空間での傾きも、何らかの基準に対して相対的に定義するしかないのです。
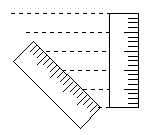 ユークリッド空間と同様に、ミンコフスキ空間でも、物理現象を記述する枠組みとしての“直交”座標系を、無数に定義することができます。ある座標系を「静止座標系」と呼ぶことにすると、それに対して傾いている座標系は「運動座標系」となりますが、もちろん、この呼称は、あくまで相対的なものです。こうした座標系の目盛りは、物理現象の普遍性によって決定できます。例えば、時間方向の目盛りは、その座標系で静止している原子時計によって、空間方向の目盛りは、単位時間に真空中で光が進む距離によって、それぞれ決めることができます。ただし、異なる座標系の間で目盛りは一致していません。これは、ある物差しとそれに対して傾いている物差しとでは、目盛りが重ならないのと同じです。各座標間の目盛り(座標)の関係は、ローレンツ変換の公式で与えられます。
ユークリッド空間と同様に、ミンコフスキ空間でも、物理現象を記述する枠組みとしての“直交”座標系を、無数に定義することができます。ある座標系を「静止座標系」と呼ぶことにすると、それに対して傾いている座標系は「運動座標系」となりますが、もちろん、この呼称は、あくまで相対的なものです。こうした座標系の目盛りは、物理現象の普遍性によって決定できます。例えば、時間方向の目盛りは、その座標系で静止している原子時計によって、空間方向の目盛りは、単位時間に真空中で光が進む距離によって、それぞれ決めることができます。ただし、異なる座標系の間で目盛りは一致していません。これは、ある物差しとそれに対して傾いている物差しとでは、目盛りが重ならないのと同じです。各座標間の目盛り(座標)の関係は、ローレンツ変換の公式で与えられます。
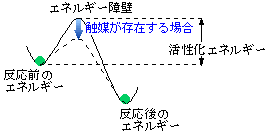 自然に進行する化学反応とは、エネルギーが極小状態にある(すなわち、外からエネルギーを加えなければ状態を変えないような)いくつかの物質が、より低い別の極小状態へと変化する過程です。こうした変化が実現されるためには、反応系が、途中にあるエネルギーの高い状態を通り抜けなければなりません。熱運動の揺らぎによって、この“エネルギー障壁”を乗り越えるのに必要なエネルギー(=活性化エネルギー)を偶然に得ることがありますが、エネルギー障壁が高い場合、その確率はきわめて低くなり、反応はゆっくりとしか進行しません。触媒とは、一般に、こうした化学反応の途中に関与して、活性化エネルギーを小さくする役割を果たす物質のことです。反応の前後で触媒は変化していませんが、反応の途中では他の物質と何らかの形で結合しているのがふつうです。
自然に進行する化学反応とは、エネルギーが極小状態にある(すなわち、外からエネルギーを加えなければ状態を変えないような)いくつかの物質が、より低い別の極小状態へと変化する過程です。こうした変化が実現されるためには、反応系が、途中にあるエネルギーの高い状態を通り抜けなければなりません。熱運動の揺らぎによって、この“エネルギー障壁”を乗り越えるのに必要なエネルギー(=活性化エネルギー)を偶然に得ることがありますが、エネルギー障壁が高い場合、その確率はきわめて低くなり、反応はゆっくりとしか進行しません。触媒とは、一般に、こうした化学反応の途中に関与して、活性化エネルギーを小さくする役割を果たす物質のことです。反応の前後で触媒は変化していませんが、反応の途中では他の物質と何らかの形で結合しているのがふつうです。
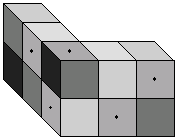 色彩の知覚が、網膜に入力された光の物理的性質をそのまま表象したものでないことは、錯視の実験で明らかにされています。例えば、右の図形は5段階の明るさで塗り分けられていますが、中間の明るさで描かれているのは、真ん中に黒い点を付けた5つの四辺形です。おそらく、左側上面の四辺形と左側面の四辺形は異なる明るさに見えていると思いますが、これは、脳が“照明の当たり方”を判断し、本来あるべき色を推定しているからです(色に関する錯視は、別の回答でも紹介しています)。このように、目に見えているままと思われがちな色彩でも、脳の神経回路における複雑な情報処理を経て知覚されているので、たとえ物理的に同一スペクトルの光であっても、神経回路の構成が異なっている場合は、全く違うセンセーションを引き起こすことがあり得ます。
色彩の知覚が、網膜に入力された光の物理的性質をそのまま表象したものでないことは、錯視の実験で明らかにされています。例えば、右の図形は5段階の明るさで塗り分けられていますが、中間の明るさで描かれているのは、真ん中に黒い点を付けた5つの四辺形です。おそらく、左側上面の四辺形と左側面の四辺形は異なる明るさに見えていると思いますが、これは、脳が“照明の当たり方”を判断し、本来あるべき色を推定しているからです(色に関する錯視は、別の回答でも紹介しています)。このように、目に見えているままと思われがちな色彩でも、脳の神経回路における複雑な情報処理を経て知覚されているので、たとえ物理的に同一スペクトルの光であっても、神経回路の構成が異なっている場合は、全く違うセンセーションを引き起こすことがあり得ます。