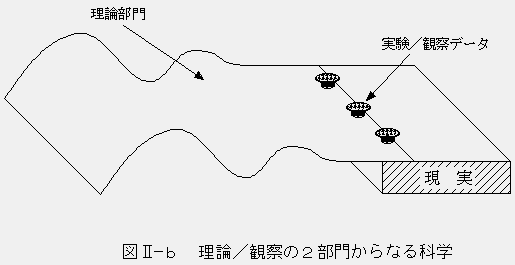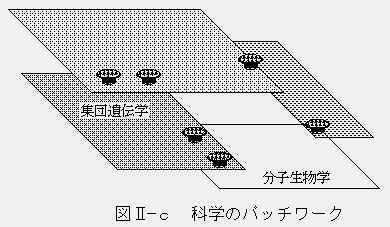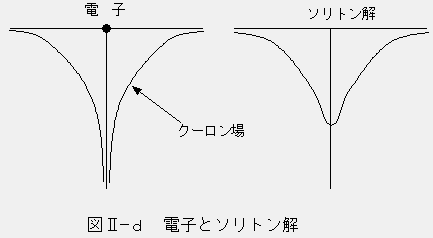II−2 《科学的実在論》の主張
機能主義的な現代科学の背後に隠されている《科学的実在論》の正体を探る
ためには,研究動向の全体像に関する考察が不可欠となる。この節では,はじ
めに科学的成果の体系について略述し,それに基づいて,現代科学が内包する
《実在論》の主張を明らかにしていく。
科学的成果のバッチワーク
仮に,科学の全体系が,中心を占める理論的記述の領域と周縁部に位置する
観察的記述の領域に大別されると仮定すると,科学理論が《実在》の状態を反
映している度合いは,必ずしも高いものではないと予想される。なぜなら,こ
の場合,理論的な議論の中で現実という強固な“土台”に立脚しているのは,
実証的な実験/観察データを引用しているマージナルな領域に限られることに
なり,それ以外の純理論的な記述は,足場を持たない空理空論に陥る虞れが大
きいからである(図II−b)。しかし,幸いなことに,実際の科学は,理論
と観察の2つの領域に大別されるのではなく,いくつかの理論がクラスターを
形成し,各クラスターごとに実証的な部門が用意されるという構成をとってい
る。例えば,集団遺伝学のクラスタ−には,交配関係についての野外観察や,(個
体ごとに保有する遺伝子の種類を特定する)DNAフットプリンティングを
用いた遺伝子の追跡調査を行う部門が,さまざまな理論の有効性を判定するた
めの実証部門としてあらかじめ設定されているのである。しかも,ここで使用
される実験/観察のデータは,実証すべき個々の理論からは(理論的予測値と
比較できるという意味で)独立しているため,(DNAフットプリンティング
のデータが集団遺伝学だけでなく分子生物学にも応用できるように)異なるク
ラスターで実証部門を共有することが可能である。こうした状況は,互いに少
しずつ重複する複数のクラスターが,ちょうどバッチワークのように,実験/
観察データという“鋲”で自然現象の回りに固定されているというイメージを
生み出す(図II−c)。この構造を,いささか野暮ったい感もあるが,科学
の「パッチワーク構造」と呼ぼう。
科学がバッチワーク構造をとることは,体系全体の安定性を保つ上で有用で
ある。実際,従来の理論で説明できない新しい現象が発見されたとしても,到
るところで“現実”と接点を持っているバッチワークは,全体としてきわめて
丈夫であるため,歪みが派生する部分のバッチ(=理論のクラスター)だけに
手を加えれば良いようになっている。こうしたバッチワーク構造の利点を生か
すためにさまざまな配慮がなされているが,特に,理論が(実験/観察デ一タ
が存する領域を離れて)あまり拡大解釈されないようにクラスターごとに規制
されている点は,(フロイトが自分の精神病理学の理論を無節操に拡張したの
と比べて)科学の信頼性を高める上で効果が大きい。比喩的に言えば,科学の
バッチワークでは,ひらひらする端切れは切り捨てられるのである。
科学のバッチワーク構造に対して投げかけられる疑問として予想されるのは,
バッチワークの“鋲”の役割を果たす実験/観察データが,はたして理論から
独立しているかという問題だろう。確かに,現代科学においては,目で見たま
まの素朴な観察結果が特定の理論を検証するということはあり得ず,最先端技
術を駆使した精密測定や統計数学に基づくデータ処理の積み重ねを経て,はじ
めて理論と比較できる段階に達するため,いかなるデータといえども,何らか
の理論に依存しているはずである。その結果として,データそれ自体が背後に
ある理論によって“汚染”され,現実と直接に結び付いているとは主張できな
いケースも出てこよう。しかし,幸いなことに,こんにちでは科学の分業体制
が進んでおり,実験/観察の手段となる測定技術や数学的技法が,他の科学理
識とは独立に与えられていることがほとんどである。生化学理論の研究者が顕
微鏡を覗く場合にしても,前世紀の研究者が自身の試行錯誤の上に実験方法を
創出したのとは異なり,正確な結果が得られるように懇切丁寧に解説してある
マニュアル通りに操作すれば済むようになっている。こうした事情から,理論
によってデータが歪められる危険は,現在では最小限に抑えられている。
科学の体系と実在の関係
科学のバッチワーク構造を認めた上で,科学と《実在》の関係として,次の
ようなイメージを提出したい:
- 「科学のバッチワークは,(唯一の)《実在》の一部を覆っている」
「唯一の」という語に括弧を付けたのは,この点について,必ずしも全ての
科学者が同意するとは限らないからである。もちろん,上の一文の表すところ
は単なるイメージであって,学術的な命題ではない。しかし,《科学的実在論》
と呼ばれるものは,このイメージによって最も適切に表されるのではないかと
思われる。
科学のバッチワークが《実在》を覆うためには,実験/観察データを共有し
ない理論クラスターがばらばらに離反しないように,近隣関係にあるクラス
タ−同士の間隙を埋めて互いに紫がりを持たせる“準”科学的な知識がなけれ
ぼならない。実際,動物行動学を研究している者は,理論を展開する上で直接
引用することがなくても,個々の生物個体を観察するときの“倍率”を連続的
に上げていけば,動物の体を構成する細胞が見えるようになるはずだという確
固たる知識は身に付けている。もちろん,動物行動学と細胞学を橋渡しするよ
うな科学的な理論の枠組みはいまだ存在せず,両者を結ぶのは,あくまで直観
的な関係付け以上のものではない。にもかかわらず,特定クラスター周辺では,
こうした「知識の曇(かさ)」は一般に高いコンセンサスを得ており,学際研
究という形で(細胞レベルでの反応がある種の行動を制御するというような)
新しい理論を建設する道が常に開かれている点は,注目に値する。
こうした曇状の知識に関する(クラスタ−周辺での)コンセンサスの高さを
示す例として,近代的な医学/生理学に収まりきらない“俗説”を受容あるい
は拒否する際に見られる・医学者の「足並みの揃い方」を指摘しておきたい。
こんにちでは,その作用機序が充分に解明されていないにもかかわらず,鍛麻
酔は,いくつかの病院で実地に使用され始めており,その信憑性はかなりの程
度で認められている。このように,鍼麻酔の技法が,医学/生理学の体系の外
にあってこれらと併存できるのは,(中国医学者による実践的なデモンストレー
ションが効を奏したことに加えて)既存の科学に付随する知識と矛盾していな
い点が大きいと推測される。すなわち,神経ペプチドによる自己麻酔作用や多
数の神経系が関与する協調的活動の存在が生理学の知見として既に認められて
いるため,「多数の神経の働きを統括する“ツボ”の神経があって,ここから
の刺激が自己麻酔をもたらす」と考えさえすれば,鍼の効果は現代科学の手の
届かない神秘的なものではなくなり,これを受容することに対する心理的な障
壁が取り除けるのである。一方,(「血液型A型の人は几帳面だ」などと主張
する)血液型性格診断のように,現代医学の範囲では決定的な否定材料が得ら
れていないものの,(銭麻酔と違って)ほとんどの医学者から拒否されている
説もあるが,こうした態度をとらせる原因は,(科学的方法論に則っていない
という点と共に)曇状知識との組艦に求められる。実際,科学的命題として洗
練されてはいないが,一般に「人間の性格は,きわめて多様な要素が絡み合っ
て形成される」というコンセンサスがあり,単純な凝集素反応や(血液型遺伝
子とリンクする)少数の遺伝子の作用が性格決定に大きく関与するという発想
とは相入れないのである。
当然のことながら,個々の科学者が抱懐する知識の畳は,当人の専門領域か
ら遠ざかるにつれて曖昧なものになり,学者間での見解の相違も増大する。脳
神経科学の世界的権威が,物理学の基礎について根本的な思い連いをしてい
る――などという話は,よく聞くところである。しかし,特定のクラスター周
辺に限ればこうした曖昧さはかなり抑えられているため,各クラスター近傍の
知識の章を基本とし,より遠方からの知識についてはこれと矛盾のない部分だ
けを選び出すという方式で,緩やかに統一された「科学の体系」を作ることが
可能である。こうした「体系」は,科学的方法論に裏打ちされた堅牢さに欠く
ため,近代の合理主義者が期待したような科学の「エンサイクロペディア」に
は程遠いが,《科学的実在論》を議論するための叩き台としては,何かと有用
である。そこで,以下では,この体系を「拡張されたバッチワーク」と呼んで,
その性質を調べることにする。
無矛盾性と稠密性の要求
拡張されたバッチワークが《実在》の性質を反映していると考えられるのは,
体系としてのく無矛盾性>と<稠密性>が期待される点である。ただし。ここ
で調う所の<無矛盾性>とは,相互の連関性をもとに理論クラスターを組み合
わせていったとき,バッチワークとしての辻棲が合わなくなるという事態が起
こらないことを保証する性質である。矛盾の具体例としては,演繹的手法によっ
てトップダウン式に求めた結論と,帰納的手法によってボトムアップ式に求め
た結論が食い違う状況を思い描けば良いだろう。また,く稠密性>とは,いか
なる科学理論も適用できないような現象が存在しない――すなわち,理論ク
ラスタ−同士の間隙に「隙間」がないことを要求する。いずれも,直観的には
明らかだが,《実在論》との絡みで論じられることは少ないので,それぞれに
ついて,簡単に解説しておこう。
はじめに,く無矛盾性>について取り上げる。もし,科学が人間の都合によっ
て読えられた虚構ならば,各部分が互いに整合的である必要はなく,(ちょう
ど古代ヘブライ人が一神教の教義の下にそれまでの部族信仰を強引にまとめた
ため旧約聖書のあちこちに軋みが見られたように)科学においても体系として
の破綻が生じて不思議はない。一方,拡張されたバッチワークが確固たる《実
在》を覆うようにアレンジされているとすれば,体系全体の破局をもたらすよ
うな構造上の矛盾が生じることはないはずである。この2つの対立する体系観
のうち,現代科学では後者の見解が採用されているが,その理由はかなり戦略
的である。確かに,現実の世界は,科学的方法論で体系化した範囲内では,ほ
とんど矛盾がないような現れ方をしている。もし,占星術が驚くべき確率で的
中したり,サイコキネシスを持つ超能力者が現れたりすると,たちまち科学的
世界像は破綻をきたし,物理法則の《実在性》すら危うくなってしまうが,そ
うした危機は現実化していないと信じて良いだろう。しかし,こうした(ほと
んど)矛盾のない世界像は,決して「現実がそうだから」という単純な理由で
実現されている訳ではなく,むしろ科学者が意図的に配慮した結果と見なすべ
きである。
そのように考えられる根拠として,次の2点を指摘しよう。第1に,占星術
や超能力など,その存在が科学の体系にとって脅威になるものは,科学的方法
論に則って学説としての有効性が検討される以前に,量状の知識との整合性な
どをもとにして研究対象たる資格がないと判断され,言わば「門前払い」を食
わされてしまうという事実がある。もっとも,(科学にとって幸いなことに)
こうした似非科学的主張の大半は,子細に検討すれば科学的命題を生成する能
力が乏しいことがわかり,厳格な科学的判断としてその無効性を宣告できる。
しかし,ほぼ全ての科学者はそこまで踏み込まずに論争を回避しており,無矛
盾性の要請を前面に立てて受容を拒絶していると考えられる。第2に,人間の
心理や社会現象のように合理的な体系を作りにくいジャンルには,科学的な議
論があまり進出していかない点を挙げておこう。こうした錯綜した現象をも射
程に捉えた理論は,明らかに,既存の体系に整合しないという危険を多分に宇
んでおり,無矛盾性を確保するのが難しい。したがって,科学が人文/社会的
現象の方面に進出を図る場合は,(自動翻訳機のような確かな応用を抱えた)
言語工学や(情報科学との接点を持つ)認知心理学など,周辺の扱いやすい分
野から取り崩していくのが一般的である。
なお,体系としての無矛盾性への期待は,個々のクラスター内部における矛
盾の発生を禁じるものでないことを付言しておく。実際,科学史のどの截断面
においても,正当性を巡る係争が跡を絶たない以上,互いに相入れない理論の
併存という意味での矛盾は,常に存在する。だが,現代科学は,論争をあくま
で局所的な領域に押し込めることにより,矛盾点を体系にとって無害なものに
している。例えば,現代物理学の大きな柱である量子力学と一般相対論は,前
者が因果的決定誇を排した確率的記述を行うのに対して,後者が因果的に結び
ついた多様体上での事象の連鎖を考えるという点で,根本的に互いに排斥し合
う理論である。ところが,(アインシュタインやボ−アのような)19世紀的な
科学者ならば世界観にかかわる論争を生んだはずの事態を前にしても,多くの
現代科学者は実に冷やかであり,量子力学はミクロな物性の理論として,―般
相対論はマクロな宇宙構造の理論として,異なる領域で使い分けている。その
背後には,因果的な記述を採用するか否かは,あくまで個々の理論を実地に適
用するときの「使用上の注意」にすぎず,これを客観的世界一般に当てはめて
も,「知識の曇」内部における科学的裏付けのない議論にしかならないという
認識がある。もちろん,宇宙創世直後などきわめて強い重力場の状態を記述す
るためには,新たに「量子重力理論」を開発する必要があるが,量子力学と一
般相対論の相克は,このクラスター固有の難点として内部的に処理されること
になる。このように,現代科学に存在する矛盾は,あくまで特定のクラスタ−
の内部もしくはその近傍での手直しによって解消されるものとして取り扱われ
ており,科学全体のバッチワークの辻棲が合わなくなるような構造的な歪みは
見つかっていない。
次に,く稠密性>について簡単に触れよう。改めて述べるまでもないことだ
が,こんにちの科学的知識は全く「スカスカ」であって,特に,人体のような
複雑なシステムについては,ほとんど何もわかっていないというのが実状であ
る。科学が単に与えられた問題を解決するための手段以上のものでなく,その
場限りで通用すれば充分だという立場からすれば,こうした状況も致し方ない
かもしれない。しかし,もし科学が一枚岩たる《実在》の性質を如実に反映し
ているならば,現在は曇状の知識が満ちているこうした空隙は,より厳格な理
論クラスターで埋められなければならない。現場の科学者の多くは,こうした
2つの立場のうち,後者の見解を良しとするはずである。このことは,過去に
おいて,分子運動論と流体力学,認知科学と脳神経科学の間に,科学者がどの
ような学際的理論を建設してきたかを見れば明らかだろう。そればかりか,現
在進行形の研究にとっても,体系の隙間を埋める作業が重要な意味を持ってい
る。例えば,医学/生理学の分野には,互いの関係が必ずしも科学的に解明さ
れていないin vitro(試験管内)とin vivo(生体内)の2通りの研究手法が
あり,(in vitroではウィルスを破壊する能力のある試薬がin vivoでは効き目
を失うというように)しばしば一致しない結果を与えるが,多くの医学者は,
生体内分子環境などのより詳細な理論を構築することにより,両者の間の懸隔
は埋められるはずだと考えて努力している。
《科学的実在論》の基本主張
<無矛盾性>と<稠密性>を期待するような動向を見ると,現代科学が方法
論的には有効性をキーワードとする機能主義を貫いていながら,その背後に,
確固たる《実在論》の発想を隠していることが明らかになる。ただし,上に見
たように,この2つの性質は現時点で全く満たされていないばかりか,いつの
日か満足されるという可能性もまずない。したがって,過去から未来に及ぶ科
学史のどの一断面を見ても,<無矛盾性>と<桐密性>を求めて変化し続ける
科学の姿が浮かんでくることになり,科学と実在のスタティックな関係を与え
る《科学的実在論》を定義することは困難となる。こうして,次の結論が得ら
れる:
-
「《科学的実在論》とは,特定の科学的命題に含意される見解ではなく,
科学の時間的発展に一定の方向性を主張する立場の根拠である」
なお,《科学的実在論》を科学の時間的変化の中に定位する見解に対しては,「特
定の科学的命題や概念が《実在》に直接的に対応するはずだ」という根強い反
対意見が予想される。この意見については,科学の機能主義的な側面を理解し
ていないことを理由に黙殺する手もあるが,ここでは,議論をより明確なもの
にするために,いかにも実在的に見える命題や概念も常にその虚構性が暴かれ
る可能性があることを示す方針で臨みたい。
多くの人は,科学的言説に現れる諸命題の中で,実験/観察のデータとより
適切に合致するものほど,実在性が高いと考えがちである。例えば,「動物の
行動は本能によって規定される」という主張は,<本能>概念の曖昧さや規定
される範囲/程度の不明確さがあるため,データとの一致は不満足なものにな
り,こうした法則はあまり実在的でないと結論される。これに対して。「孤立
系のエネルギーは保存する」という主張になると,(19世紀に提唱された当初
はあくまで帰納的な命題だったにもかかわらず)きわめて良い精度で実験データ
と一致するばかりか,いくつかの特殊なケースではより信懸性の高い理論か
ら演繹できることも知られているため,現代物理学の進展に疎い人には,エネ
ルギー保存則が《実在》の何らかの性質を直接に反映していると思われるかも
しれない。しかし,ハミルトン形式で表した力学理論によれば,エネルギーと
は,微小な時間が経過した後の系の状態を決定する量であり,その値は時間座
標の取り方に依存することが知られている。したがって,一様に流れる絶対時
間の枠組みと,常に保存するエネルギーとが,それぞれ独立に存在する訳では
なく,両者を“込み”にした統一的な法則を考えなければならないのである。
けだし,人間にとっては,時間が伸び縮みしない座標の方が対象認識に好都合
なため,知覚情報を一様な時間座標に投影して表象する能力が形成され,結果
的にエネルギー保存則が派生したのであろう。このように,エネルギー保存則
という基本的な物理法則ですら人間の作り上げた虚構である以上,単にデータ
との一致の良さをもとにして科学的命題の実在性を判定するのは,ほとんど不
可能であることがわかる。
より一般的に,ある命題の実在性を判断する基準として,当該命題を消去し
ても体系が意味を失わないかどうかを見れば良いとする主張がある。確かに,
実在的でないことが簡単にわかる場合は;この基準は役に立つ。例えば,砂に
描かれた三角形を見てこれを認知する場合,「人間が簡単な図形の認定をする
ときには,数個の特徴を既存の鋳型と照らし合わせるだけで済む」という知識
さえ持っていれば,「砂の上に三角形が(実際に)存在する」という命題を仮
定しなくても視覚情報に基づいた三角形の認知が説明できるので,三角形の存
在は説明のための作業仮説にすぎないことがわかる。しかし,虚構であると直
ちに判明しないケースでは,当該命題がはたして将来とも不要にならないかど
うかは,保証の限りではない。それどころか,<電子>のように現代物理学の
中で確固たる地歩を占めている対象ですら,明日にもその存在命題が消去可能
になるかもしれないのである。実際に電子の存在を必要としない2つの理論を
示しておく:
- (i)電子をはじめとする荷電粒子は,電磁場を介して他の物体と相互作用
する。簡単のため,特に静電作用に限定して考えよう。このとき,他の物
体は電子そのものに“触れる”ことはできず,その回りのクーロン場を媒
介として電子の存在を感知する。ところが,もし(電磁場の従う方程式が
線型でなく)エネルギーが1点に集中するソリトン解が存在したとすると,
中心に電子という“芯”のないクーロン場として振舞い,外部から見る限
り,これと電子を区別することは困難である(図II−d)。したがって,
電子の相互作用に関する従前の知識にほとんど変更を加えることなく,電
子自体の存在を消去することができる。
- (ii)通常,量子力学によって電子の振舞いを記述するとき,電子の“粒子性”
は境界条件の中に含まれており,観測によって波東が収縮したとされると
きにはじめてあらわになる。しかるに,もし波束の収縮が起きずに波動関
数の因果的な変化だけで状態が記述されるとすると,こうした境界条件が
不要になるため,電子を粒子と見なす根拠がなくなる。量子力学のこうし
た取り扱いは《多世界解釈》と呼ばれ,少なくとも論理的な矛盾がないこ
とが知られている。
以上の議論は,科学的な理論の命題や諸概念に関する《実在性》を判定する
ことの困難さを示している。いささか無責任な比喩を使って表現すれば,科学
と《実在》との関係は,ピカソの肖像画とそのモデルの関係である。確かに。
何らかの繋がりはあるはずだが,絵を見ている限り,断定的なことは何も言え
ないのである。
“弱い”科学的実在論
そもそも命題を通じて直接に《実在》の何たるかを語ることのない科学にと
て,《実在論》が積極的な発言を行う領域はあるのだろうか。この問いかけに
対する解答は,一意的に与えられるものではなく,科学をどれほど信頼してい
るかによって大きく異なってくる。はじめに,《実在論》を最も弱い意味で解
釈した場合の帰結について,見ていくことにしよう。
既に述べたように,《科学的実在論》とは,方法論的には有効性を重視する
機能主義的な立場を貫いているはずの科学が,結果的にく無矛盾性>とく稠密
性>を獲得する方向へ進むことを期待する主張の論拠である。そこで,“弱い”
意味での《実在論》として,こうした時間的発展の局所的な性質のみを語る立
場を考えることは,妥当だろう。ごく常識的な観点から,理想的な(すなわち
期待が実現されるケースでの)科学的発展の法則として,次のようなものを挙
げることができる:
- (i)適用範囲が大きく重なる複数の異なった理論クラスターは,これらを
導き出すような。より根底的なクラスターに吸収ないし置換される(無矛
盾性の志向)。
- (ii)既存の理論クラスター近傍の空隙には,新しい理論クラスターが構築
される(稠密性の志向)。
もっとも,このリストの内容は,相当に理想化されたもので,必ずしも現実
的ではない。実際の場面で考えても,動物の行動に関する観察データの回りに
は,ローレンツ流の動物行動学やダーウィニズムに基づく行動進化論,さらに
は筋肉反応などを調べる行動生理学から新興の神経行動学に到るまで,あまり
有効性の高くない(つまり,的確な予言を提出できない)理論クラスターがい
くつも折り重なっているが,これらを包摂するような根底的な学説が近い将来
に提出されるとは期待できない。もちろん,科学における発展の法則として,
もう少し現実に近いようなリストを作成することもできるが,そうした作業は
決して面白いものでもなければ,学問的に有益でもないだろう。要するに,“弱
い”意味での《科学的実在論》とは,その程度に無内容であり,それゆえ反駁
されることもないものである。
素朴に考えれば,従来よりも有効性の高いー―すなわち,実験/観察デー
タとの整合性が向上した科学的命題を以前よりも少数の仮定から生成する理論
を構築できた場合,新理論の内容は従前のものよりも《実在》の性質を正しく
表していると期待される。しかし,(有効性の高さは必ずしも実在性の高さと
相関しないとする先の主張から予想されるように)事態はそれほど単純ではな
い。この問題は,量子力学を考えると理解しやすいだろう。量子力学が誕生す
る以前には,物質の化学反応を記述する応用的な理論としては,いくつかの性
質にっいて反応前後での数量的関係を与える化学量論しか存在せず,当時は原
理的な理論として期待されていた古典力学や電磁気学は,数学的に厳密だが物
質の安定性を保てないため,化学反応に関しては無力であった。これに対して,
量子力学はまさにこの2っの理論を統一するものであり,プランク定数を零に
する近似で古典理論が再現できる一方,原子の化学的な性質を数学的に厳密な
手法によって解明する手段を与えることに成功した。したがって,うっかりす
ると,量子力学に現れる諸概念の方が,それ以前のものより《実在》の性質を
的確に表現するものと思いたくなる。しかし,量子力学は,そもそも<状態>
という(粗視化過程を含意する)概念を前提として構成されているため,個々
の自由度についての厳密な記述が当初から放棄される一方で,確率振幅のよう
な固有の物理量を導入する必要が生じたのである。この点を誤解して,古典力
学的な確定記述よりも量子力学的な確率記述の方が《実在》の性質をより適切
に表現していると見なすと,(ちょうど,粒子像よりも波動像の方が光の実体
を正しく表すと考えた19世紀の物理学者のように)科学の発展に「しっペ返し」
を食らうことになりかねない。以上の議論は,科学の命題/概念が《実在》の
性質と直接に対応していないという先の結論を,理論の局所的な変化の場にお
“強い”相学的実在論
“弱い”意味での《科学的実在論》が科学的発展の局所的な動向にしか目を向
けていないのに対して,“強い”《実在論》は,科学が発展する最終段階まで
射程に収めようとする立場である。もちろん,科学が常に累積的に前進すると
は限らず,知識の喪失と再発見を繰り返す無限ループに陥ったり,(マヤ文明
のように)特定の応用技術に関する知識のみが突出して他が失われる可能性は,
決して小さくない。しかし,こうした事情をあえて無視して,順調に発展した
と仮定した場合に科学が漸近するであろう体系について考察することは,人間
の思考能力と《実在》との原理的な関係を明らかにすると期待され,哲学的に
も無価値ではない。したがって,ここでは,その正当性はさておいて,“強い”
意味での《科学的実在論》の主張を見ることから始めよう。
科学的な知見が,何らかの形で《実在》の性質を反映させたものであるとし
ても,いつか《実在》を完全に記述するような理論が現れることは,原理的に
不可能だと考える。その理由は,人間が対象を認識する過程で,外界の実態に
は必ずしも対応しない特定の形式を採用しているからである。もちろん,そう
した認識形式を意識化できる場合は,批判的な分析に基づいてその橿桔から逃
れることも可能だろうが,多くの認識形式は意識的な分析すら許さないほど,
思考の根幹に関わっている。一般相対論を例にとって説明しよう。一般相対論
では,座標の選択に任意性があることから,元来は座標が指定されていない4
次元時空が存在し,これを認識するために座標という形式を付与したと解釈す
ることができる。このとき,座標表現が認識の形式にすぎないという事情は,
明確に意識化されている。ところが,そもそも座標を選択する以前の段階で,
4次元時空に対して微分多様体としての諸々の性質を付与するという作業を
行っていながら,こちらの方にはほとんど気がついていない。しかも,押し付
けられた性質の中には,連続性や欄密性などの意識化しやすい性質だけでな
く,「異なる2点は厳密に区別される」のように,自然界に必ず備わっている
とは期待できないにもかかわらず,その性質を持たない数学的モデルを考案す
ることがほとんど困難なものも含まれている。このように,意識的な分析が不
可能な特定の形式に縛られている以上,科学が「完全なる知識」に到達するこ
とは有り得ないと結論できる。
それでは,こうした「不完全さ」を脱け出せないままに前進を続けていった
として,人類の科学は,最終的にどのような体系に到達できるのだろうか。も
ちろん,この問い自体が雲を掴むようなものなので,このままでは具体的な議
論を進めることはできない。しかし,<自我>と<外界>の関係を明らかにす
るという《実在論》の最終日標を念頭に置くならば,体系の全体的な統一性に
論点を絞ることが許されよう。すなわち,<外界>に関する記述がく自我>の
記述と同一の地平の中に収まるか否かを推測することによって,科学の体系に
よって「覆われる」実在の構造を考察する地歩が固められるのである。
統一性という観点から大きく分けると,最終段階に到った科学は,
(i)全ての領域にわたる知識が連結された統一的な体系
または,
(ii)互いに連結されていない。いくつかの部分の集合から成る分裂した体系
のうち,いずれかに収敗すると仮定される。さらに,それぞれの場合について,
体系の統一または分立という事態が,《実在》の構造を(ことばの素朴な意味
で)“反映”しているのか,あるいは人間の認識能力の限界に由来するかを基
準にして,細分することも可能である。こうして,理想的な科学の最終局面と
して,次の4つのケースを想定することができる。
- (i)−(イ)可知的一元論 《実在》の一元的な性質を反映して,科学の体系
も統一的なものとなるケース。具体的には,精神科学と自然科学の知識が,
可能な限り無矛盾で稠密な体系において,ほぼ同一のステイタスを獲得す
るに到った状況を考えれば良い。このケースは,《実在》の構造から「―
元論」と呼ばれるべきものであり,かつ,その一元性が人間に知られ得る
という意味で「可知的」と形容される。
- (i)−(ロ)不可知的多元論 《実在》は統一されていないにもかかわらず,
人間がそれを単一の局面からしか見ないため,統一的な体系として表され
るケース。最もありそうなのは,精神現象に関する経験的な知識が,機能
的なモデルを構築できない“俗説”ないし単純な“錯覚”として科学の中
に組み込まれずに終わってしまい,正統科学の枠内ではく外界>に関する
記述しか取り扱わない狭義の唯物論に堕す場合である。このケースは,《実
在》の側は「多元論」的であるにもかかわらず,人間の知的能力の限界の
ためにそれと察知できないことから,「不可知的」と呼ばれる。
- (ii)−(イ)可知的多元論 《実在》の多元的な性質を反映して,科学の体系
も分立的なものとなるケースで,デカルト的な二元論を思い浮かべれば良
いだろう。こうした体系が実現される可能性としては,(「彼は〜と感じ
たから〜という行動をとった」と主張するような)俗流の心理学が科学に
昇格しながら,既存の客観的知識との間に一致点が見いだせないまま孤立
した学説にとどまる場合が考えられる。なお,この範隠には,《実在》の
多元性の一部分しか科学に反映されていない場合も含める。
- (ii)−(ロ)不可知的一元論 《実在》は統一されているのに対して,人間に
その全体像を見わたす視座が与えられておらず,いくつかの局面から接近
するしか手だてがないため,結果的に分裂した体系によって記述されると
いう「群盲象を撫でる」のケース。
以上の分類は(一元論的な《実在》の一面だけを唯物論的に曲解するケース
を落としているなど)決して厳密なものではなく,大まかな方向性を述べたに
すぎない。のみならず,実際の科学が最終的にどのようなコースを辿るか,現
時点では科学的な客観性をもって予測するのは全く困難であり,「科学はいっ
か世界の本質を統一的に理解できるようになるはずだ」とか「この世には人知
で計り知れないものがある」といった粗雑な見通しを語るのが精いっぱいだろ
う。そもそも,科学の時間的発展をもとに《実在》を論じる《科学的実在論》
の立場からは,これ以上の内容を含んだ発言を期待するのが無理なのである。
しかし,哲学的な興味からは,この段階で議論を放擲するのはいかにも消化不
良の感を免れず,やはり何らかの見通しを得たいというのが真情だろう。そこ
で,次なるステップとして,科学的な厳密性をある程度まで犠牲にしながら,
哲学的興味に則って《実在》の問題に挑戦する道を模索してみたい。すなわ
ち,《哲学的実在論》の検討である。
©Nobuo YOSHIDA