第III章 哲学的実在論の挑戦
「この世界は本当は何なのか」という問いは,人類が<外界>と<自我>の
間に存在する本質的な懸崖に気づいて以来,知を愛する者にとって常に気がか
りの種であった。残念ながら,外界について論じるときにはきわめて有効な知
的ツールとして威力を発揮した科学も,この問題に関しては,どうひいき目に
見たところで,不明瞭に口篭り的外れとしか思えない解答を与えるのが精いっ
ばいだろう。科学とは,元来,有効な科学的命題を生成することを目的として
おり,《実在》や《真理》のような「哲学的な」話題は関知しないのである。
とは言っても,科学的方法論が,複雑に絡み合った物事を筋道立てて考察する
ために人類が考案した最強の方法論であることは間違いなく,これを放棄して
まで何らかの結論を得ようとするのは,知性の自殺行為である。この観点から
すれば,《実在》にっいて論じる手段として残されているのは,「哲学的な」
動機の下に《科学的実在論》を徹底させる道しかあるまい。
既に述べたように,“強い”意味での《科学的実在論》は,<無矛盾性>と
<調密性>を満たすように科学が理想的な発展を遂げた場合,最終的には《実
在》の一元性ないし多元性を(そのまま,あるいは異なる形で)反映した体系
に漸近するという主張であり,科学的な命題のいずれかが《実在》に直接に対
応することを含意しない。このため,《科学的実在論》に立脚する議論は,そ
の形式をさまざまに制限されることになる。特に,<観念>の措定を前提とす
る「〜が実在する」という(素朴な実在論者が期待する)形式での存在命題が
許されないばかりか,科学的な理論の枠内で「《実在》は〜の性質を示す」と
主張することすら正当化できない。該当する性質が,(量子力学におけるく状
態>のように)道具としての理論の使い勝手を向上させるための虚構ではない
かどうか,誰にもわからないからである。さらに困ったことに,科学的発展の
最終段階が現実に到達できるものではなく,せいぜい漸進的に接近していくだ
けの仮想的な段階と考えられる以上,(過去/未来を問わず)いかなる時代の
科学者といえども,その時点での科学体系をもとにして(―元論/多元論のよ
うな)《実在》の体制について何らかの断定的な主張を行う権利は持っていな
い。しかも,仮に人類にとっての究極的な科学体系が実現されたとしても,人
間の認識能力にどのような欠陥があるか知れたものではなく,「科学体系の一
元(多元)性は《実在》の体制とは無関係なのではないか」という疑念を払拭
することはできない。こうした制約があるだけに,《科学的実在論》とは,何
ら意味のあることを語れない無能な見解であるように思われるかもしれない。
しかし,一見無能と思える《科学的実在論》も,<自我>とく外界>との間
に横たわる深い溝に何らかの説明を与えたいという動機に基づいて,その適用
範囲を純然たる科学の領域から拡張することにより,哲学的に意味のある発言
が可能になるものと思われる。この点について,述べていきたい。
確かに,人間の認識能力に何らかの限界が存在すると予想される以上,科学
的体系の一元性をもとに直ちに《実在》が一元的であると結論することはでき
ない。しかし,もし科学の一元的な体系が<外界>と<自我>を統合すること
によって得られたものである場合は,《実在》に潜む他の本質的な部分が(認
識の仮定で)切り捨てられた「見かけの」一元論にすぎないとしても,積年の
謎を解決したという点で,哲学的には有益だろう。逆に,科学の体系がいかに
見事な統一体として構築されようとも,その中に<自我>にっいての記述が含
まれなければ,《実在》の一元性については何の確証も得られないばかりか,
むしろ科学的記述の対象となる<外界>とそうでない<自我>との二元論の方
がもっともらしく感じられるはずである。このように,哲学的に動機づけられ
た《実在論》にとっては,<外界>と<自我>が統合できるか否かが最大の関
心事であり,議論をこの点に絞っても構わない。すなわち,《哲学的実在論》
の根本は心身問題にあると喝破されるのであり,この領域に限って科学的方法
論を適用すれば,有効な考察ができると期待される。
これまでの議論で明らかになっているように,科学的な《実在》は,歴史の
相においてのみその姿を表す。このため,上で述べた意味での《哲学的実在論》
を実行するためには,<自我>および<外界>それぞれを記述する理論が,科
学発展の最終段階でどのような関係になるかを推測する作業が必要になる。こ
こで,<外界>に関しては,現行の物理学が充分に利用できるモデルを提供し
てくれるので問題はない。ところが,現行の科学は(内観としての)<自我>
について記述することを完全に放棄しているため,既存の科学的知見を《実在
論》の議論に援用する道が閉ざされている。誤解のないように付け加えておく
が,各種の心理学で導入されている自我のモデルは,あくまで観察可能な心理
機能をシミュレートするという特定の目的を果たすために案出されたもの
で,《実在》一般を問題とする議論には役に立たない。したがって,科学的方
法論に則って何らかの結論を得るためには,く自我>についての擬似科学的な
記述を構成し,その上で仮想的未来における科学の時間発展を予測するという
手法を採用しなければならないだろう。ここで,あえて「擬似」科学と断わっ
たのは,現行の科学理論と同程度に洗練されたモデルを構築するのは現実問題
として困難であり,<自我>を特徴づける本質的な要素のいくつかだけをピッ
クアップした「おもちゃモデル」を使って,科学発展のプロセスを模擬的にな
ぞるのが精いっぱいだからである。以下の議論では,こうした(おもちゃのよ
うな)く自我>のモデルが,原理的に<外界>と統合可能かどうかを見ること
によって,両者を統一した一元的な《実在論》が得られるかを検討したい。
このような方針の下では,認識能力の限界のため多元的な世界が一元論的に
見えるく不可知的多元論>はとりあえず無視することができるので,哲学的な
興味は,統合が完遂される(少なくとも見かけの上での)<可知的一元論>と,
分裂が解消されないく可知的多元論>または<不可知的一元論>のいずれが正
当性を主張できるかという点に集約されるだろう。ただし,後二者については,
すぐに述べるように,その立論を支持しがたいいくつかの理由があり,その内
容を子細に検討する必要性が見いだせない。したがって,ここでの議論は,可
知的一元論に加担する立場に立って,主に原理的な統合を実現させる手法を模
索する方向で進めていき,最終的には,統合の可能性を強く示唆する結論を導
く。こうした結論が有効かどうかは,<自我>についての(擬似科学的な)モ
デルの妥当性に依存するが,少なくとも,今後の議論の叩き台としては通用す
るものだと考える。
可知的多元論/不可知的一元論の問題点
本題の可知的一元論についての論考に移る前に,筆者が快く思わない「分裂
した体系」について触れておきたい。
はじめに,可知的多元論――すなわち,《実在》が統一的でない体制をとっ
ているのに呼応して,科学の体系も最後まで分裂したままで終わるケースを取
り上げよう。特に,心身問題との関連で言えば,<外界>と<自我>が相入れ
ない別個の《実在》として捉えられる「心身二元論」が議論の対象となる。と
ころが,心身二元論を学問的に取り扱おうとすると,多くの観念的困難に直面
せざるを得ない。何よりも,二元論の立場を徹底させるならば,心と身体(あ
るいはその他の物体)は全く別個な存在様式を与えられるため,互いに相手の
状態を変化させるような相互作用をするとは考えられず,(ポジトロン放出な
どを使って現実に観測されている)脳内部の生理学的過程と意識現象の相関を
説明することは不可能になってしまう。
―方,「《実在》はただ1つでありながら,人間がそれを異なる局面からし
か見ることができないために,いつまで経っても統一的な科学の体系は実現さ
れない」という不可知的一元論は,学者の態度としてあまりに敗北主義的であ
る。歴史的にみても,この種の不可知論が学問の発展にプラスの貢献をした例
は見あたらない。例えば,ポーアは「相補性原理」を提唱して量子力学的二面
性についての不可知論を展開しているが,この見解がその後の量子力学の発展
において積極的な役割を果たした証拠はなく,むしろ,波動性/粒子性の起源
を明らかにしようとする研究にとってイドラ以外の何物でもなかった。こうし
たことから,確固たる論拠が得られない限り不可知論を排する立場を採用する
方が,学問的に見て建設的な態度と言えるだろう。
<自我>の科学的モデル
く自我>の(擬似)科学的モデルを構築するためには,何よりもまず,<自
我>を<外界>から峻別する本質的な要素を剔抉し,その上で,この要素から
構成される「基本モデル」を設定することから始めなければならない。もちろ
ん,人間の内面に生起する事象の大部分はこのモデルには含まれないが。これ
らについては,基本モデルに付加的な条件を課すことによって得られる付随的
な要素と考える。こうした階層的なモデルの導入は,物質の性質によらない(量
子力学や場の理論のような)基本理論を設定した上で,具体的な物性を導入す
るという物理学の手法を範とするものである。もし基本モデルにく自我>と<外
界>の質的な相違を全て集約することに成功したとすると,精神現象を再現す
るために後から付加される条件は,(モデルの構成から明らかなように)<外
界>の性質と矛盾するものではないため,<自我>と<外界>の統合を図る場
合に本質的な役割を演じるとは考えられない。したがって,統合可能性を論じ
る文脈においては,基本モデルのみを考察の対象とすれば充分である。
基本モデルを設定することの重要性を示すために,これを用いない議論の欠
陥を指摘しておこう。こんにち心身問題の解決法として最も期待されている「心
身同一説」の立場からは,人間の<自我>は大脳における生理学的過程と同一
視できると主張されている。ところが,この説で「心」として想定されている
のは,さまざまな精神現象における客観的な作用だけを抽出した「機能モデル」
以外の何物でもなく,く自我>が持っている「独裁的」「求心的」性格につい
ては実質的に黙殺されている。例えば,何らかの「怒り」がいろいろな心的活
動を惹起する作用は,これを特定の神経興奮のバターンと同定するだけでも説
明がつくが,その「怒り」が自分のものか否かによって<自我>における現れ
方が本質的に異なる理由を明らかにすることはできない。当然のことながら。
いわゆる「数の矛盾」――唯一の<外界>と多数の<自我>をどのように結び
付けるか――については,解決の糸口すら提示されていないのである。「同一
説」の立論にこのような欠陥が生じた理由は,く自我>とく外界>との相違を
際だたせるためのモデル化を怠り,客観的な事象を分析するのと同じ手法で精
神現象を取り扱おうとした結果,その機能面だけが強調される事態を招来した
ためと理解される。
それでは,具体的に<自我>の基本モデルを構築する作業に移ろう。
はじめに,人間の精神現象の中で,知的思考や感情,自由意思が,<自我>
を<外界>から区別する本質的な要素ではなf、ことを示す。その論法は,こう
した精神現象をもたらす機能が,いずれも客観的に規定された情報処理系にお
いてシミュレートできる(という蓋然性が高い)ことを指摘するもので,<外
界>に属するシステムを使って真似できるからには,これらがく自我>の本質
的な要素ではないとする発想に依拠している。
(1)知 的 思 考
対象認識を中心とする知的思考は,基本的には知覚ないし記憶の情報を機械
的に処理する過程として記述できる。視覚的な対象物を見てその形態や運動に
ついて認知する過程を例に取ると,網膜で結ばれた像から得られた信号は,後
頭葉に投射されて(コヒーレントな運動をする部分が同一物として抜き出され
るなど)さまざまな特徴分析を受け,いくつかのバターンに分解されてから,
頭頂葉に送られて他の感覚信号や記憶内容との連合が成立する。こうした特徴
分析を軸とするバターン認識は,多層バーセプトロンのような単純なシステム
によって基本的な機能が再現できるので,機械的な情報処理の過程と見なして
も,さしたる支障はない。より複雑な認識――例えば,顔を見て誰かを判断
するような――については,これほど確実な理論的根拠がある訳ではない。
しかし,学習能力を持つニューロ。コンピューターを使ったシミュレーション
を行った結果,適切な「教師」があらかじめ与えられているシステムでは,連
想記憶の形成は必ずしも困難でないという結論が得られており,充分に能力の
ある情報処理系ならば,人間が行っている思考過程を再現するのは不可能では
ない。以上のことから,知的思考は<外界>のシステムで模擬できるので,く自
我>の本質的な要素でないと言える。
(2)感 情
しばしば,感情の存在こそは人間固有の性質であり,コンピューターでは再
現できないものと主張される。しかし,諸々の感情から「自分が感じている」
という要素を捨象してしまうと,残るのは心的素材を処理するときの傾向性と
して解釈できる過程のみである。「愛情」を例に取って説明しよう。各人の体
験に照らし合わせれば明らかなように,「人を愛する」ときの心的過程は常に
愛情の対象を巡って進行し,何を見ても愛する者を思わずにはいられない心境
になる。このような精神状態は,機能的には,恋人についての情報が中枢系の
キャッシュメモリーに納められていて,僅かなキューが提示されるだけで即座
に呼び出されるという状況に等しい。しかも,特定の思考バターンを強要する
単純な強迫症の場合とは異なって,恋人の情報は,多くの具象的なイメージを
喚起し,これらを合目的的に構成する作用があるため,精神内容は豊かな多様
性をもって展開されることになる。―般に,人間は構成的な認識過程の促通を
「快」と感じる性向があるため,こうした愛情の直感は,当人にとって生理的
に心地良いものとなる。このように,愛情のような高度に人間的な感情も,機
能的な側面から見ると,情報処理の傾向性として理解することが可能なのであ
る。
(3)自 由 意 志
精神が物質と本質的に異なっている点として,厳格な因果法則の規制を逃れ
て創発的に行動を選択できる自由があることを挙げる論者は少なくない。しか
し,このような「自由意志」が,本当に過去の状態に束縛されない自発性を持っ
ているのか,外面的な観察だけからでは何とも言えないはずである。確かに,
意識野に現れる内容に限れば,いったんアイディアの種が蒔かれると,時間と
共に当該事項に関する情報量が一方的に増大するという(エントロピーの法則
に矛盾するような)過程が観察されることは事実である。しかし,思考の本体
は識閾下で行われていて,その一部だけが意識野に投射されると仮定すれば,
こうした意識内容の時間的発展を物理法則の枠内で説明することも不可能では
ない。こう考えると,自由意志の発現と思われた現象も,実は,中枢系における情
報の流れが特定の様式に従っていることの現れと解釈する方が素直である。
以上の議論によって明らかなように,知的思考/感情/自由意志は,いずれ
も<自我>を<外界>から隔てる本質的な構成要素とは言えない。この結論は,(思
考や感情のような)心理的な機能に着目している限り<自我>の特徴を抽出で
きないことを示唆する。そこで,次なるステップとして,より現象学的な視点
から<自我>の実態を分析する方向に進もう。
<自我>の最も重要な特徴は,それが他の誰のものでもない「自分の世界」
だと認められる明確な主体性を持っている点である。ところで,<外界>に登
場する人間(およびその他の知的存在)は全て「自分だけの(主観的)世界」
を備えていると信じて良いので,客観的な世界の背後には膨大な数のく自我>
が現に存在しており,その中のどれか1つが「この」自分に相当するという構
図が描かれることになる。ただし,このような構図を直観的に理解するために,
自己と他者を峻別する契機として「自己同一性」を担う実体を想定しても,論
理的な矛盾のない世界像を構成するのは難しいだろう。実際,民間信仰に見ら
れるように,「太郎の魂」という特定の固有名詞を付される実体が,それ自体
は無名性を保っている肉体と結び付くことによって,自分を「太郎」と自覚す
る人間が現れると仮定してみても,その存在様式が本質的に異なる魂と肉体が
どのように相互作用するのか全く理解できない。また,相互作用を頭ごなしに
仮定して,多くの魂が(肉体を含む)物質的世界と結合した複合体を構成して
いると考えると,複合体全体が特定の中心を持たない統一的なシステムとして
取り扱えるようになるため,それぞれの魂が「自分こそが世界の中心である」
と感じる根拠が不明になってしまう。こうして,実体を仮定する論法を採用す
る限り,く自我>が特定の主体に帰属する理由を説明できないと結論される。
それでは,自己同一性を担った実体が存在しないにもかかわらず,<自我>
が主体性を備えているという事実は,何を意味するのだろうか。議論のポイン
トを明らかにするために,「この(主観的な)世界は自分のものだ」とする直
感を現象学的に分析してみよう。直ちに言えることは,自己への帰属感が意識
のすみずみにまで行き渡っていて,「自分のものではない」異質の存在が主観
的世界の中に侵入してこないという点である。断わっておくが,ここで「異質
の存在」として想定されているのは,自己とは独立に存在する文字どおりの<他
我>であって,単なる他者性を帯びた幻聴や妄想は含まれない。確かに,精神
分裂病の症状として現れる幻聴は,まるで心の中で他人が囁いているかのよう
に現れるが,それでも「自分が聞いている幻聴」としての自己への帰属感は保
持されており,自己から完全に切り離された「他者の聞く幻聴」は主観的世界
に入り込むべくもないのである。自己に帰属しない何者かが意識内部に現れる
ことは現実には起こり得ないので,そうした事態を想像するのは難しいが,<外
界>とのアナロジーを使えば何とか理解可能になるだろう。一般的に言って,
客観的な世界においては,「自分の身体」も「他人の身体」も同じ存在資格で
併存して何の不思議もないのに対して,主観的世界では,「自分の意識」と「他
人の意識」が並んで現れる余地が完全に排除されているのである。このように
主観的世界がそれ自体で閉じていて自分に帰属しない異質な要素の侵入を許さ
ない状況を,世界の<完結性>と呼ぶことにしよう。さて,特定の主観的世界
が<完結性>を示す場合は,この世界に対応するく自我>にとっては,<他我>
と境界線争いを繰り広げるまでもなく,はじめから世界全体が「自分のもの」
としてのまとまりを備えている。したがって,「この世界は自分に属する」と
自覚するく自我>の主体性とは,自己の版図を宣言する積極的な主張ではなく,
単に,当の主観的世界の<完結性>に起因するものと言えよう。
こうした主観的世界の<完結性>は,<自我>と<外界>を区別する上で決
定的な役割を演じている。この点について説明しよう。うっかりすると,く外
界>に登場する個々の人間(ないしその脳)に自己完結した意識が備わってい
ると考えることに,何の不都合も感じられないかもしれない。事実,精神現象
を脳内過程と同一視する立場の人は,「太郎の脳」には自分を「太郎」と自覚
する意識が付随しており,この意識が他者の意識と混じり合わないのは脳が物
理的な境界を持つからだと単純に考えている。しかし,ここで注意しなければ
ならないのは,客観的世界に現れる多くの事象の中から「太郎」や「次郎」に
着目し,これを個別的な対象として分節的に把握するのは,あくまで当の世界
を認識している主体の能動的操作なのであって,物質的な世界の側にこうした
分節の契機がある訳ではないという点である。実際,認識過程を分析すれば明
らかなように,「太郎の脳が意識を持つ」と主張するためには,事前に「太郎」
なる人物の<観念>を措定することによって,認識の上で他の人間との差別化
を図っておかなければならない。こうした認識レベルでの操作を中止して客観
的世界の現象をありのままに眺める立場を取れば,全ての人間が存在資格の上
で同等と見なされ,その中の誰かを特別視して自己完結的な意識を割り当てる
作業が不可能になる。簡単に言えば,く外界>は基本的に平等な世界であり,
ここに特権的な<完結性>を備えた主体を導入することが,そもそも無理なの
である。あえて客観的世界の登場人物に意識を与えようとすると,多くの<自
我>が単一の世界の内部に併存することになるため,自我と非自我を分かつよ
うな意識の境界線が必要となり,<完結性>の要求と矛盾する。逆に意識のく完
結性>を基本原理として要請すれば,完結した意識を多くの個人に分配するこ
とが困難である以上,客観的世界全体に拡がった統一的な意識を想定しなけれ
ばなるまい。このように考えれば,<自我>と<外界>を峻別する本質的な契
機として<完結性>を指摘することは,当を得た判断だろう。
ここまでの議論を総合すれば,<自我>の基本モデルは<完結性>を備えて
いることが要請される。ただし,ここで謂う所の<完結性>とは,その内部で
世界が自足しており,自己と認められないような異質な要素が入り込む余地の
ないことを意味する。なお,部分的には<完結性>に包含される性質として,<自
我>の<均一性>と<内部連関性>を挙げておこう。前者は,客観的な世界が
(粒子や場のような)種々の構成要素を含んでいる(ように見える)のに対し
て,主観的世界は意識として同質的な素材から成り立っていることを主張する。
また,後者は,意識内容が連想などを通じて互いに連関しあっていることを意
味するが,より積極的に「意識の中心に密な観念連合があり,周辺部に行くに
従って疎になる」という求心性の主張だと解しても良いだろう。こうして,「互
いに連関性のある均一な素材が構成する自己完結した世界」が,<自我>を記
述する基本モデルとしての資格を備えていることになる。
<自我>の具体的表現
上に与えた基本モデルは現象学的な考察に立脚するものであり,く自我>の
擬似科学的モデルとしては不充分である。したがって,ここでは,客観的世界
に属する存在者の中でく自我>を備えていると想定される人間ないし脳の活動
に注目し,これらに関する科学的知見を援用しながら,より具体的にモデルの
内容を詰めていくことにする。
はじめに,<自我>が特定の実体や機能に還元できないという(既にモデル
作成の際に示した)結論が,科学的な考察によっても確認できることを指摘し
ておこう《zτ》。主体的な意識の担い手となる実体が存在しないことは,脳神経
系の構成要素をさまざまな階層で分析することによって,具体的に確かめられ
る。例えば,分子反応の階層で見いだされる生化学的素材は,脂質二重層にし
ても調節タンバク質にしても,細胞の安定化や化学反応の促通など特定の機能
を担当する物質として一般の体組織にごくふつうに含まれており,これらが意
識を支えている基礎物質である蓋然性はきわめて小さい。また,神経細胞の興
奮が離散的な状態として近似できるならば,脳の機能はテュ−リング・マシン
によって完全にシミュレートできるはずだが,0と1の数列が記入できるテー
プと数字の読み取り/書き込みを行うへッドから構成されるテューリング。マ
シンが,「自分の世界」を実感する<自我>を備えているとは考えられないの
で,く自我>の本質は機能以外の所に存することがわかる。
それでは,科学的知見に従えば,客観的世界におけるいかなる状況が<自我>
と結び付けられるのだろうか。実験心理学や大脳生理学の成果から知られてい
るように,自意識が成立するためには,1OOミリ秒以上の時間的持続と大脳と同
程度の空間的拡がりを持った神経系の興奮が必要となる。したがって,特定の
実体や機能にこだわらずに,神経興奮という「現象」そのものを<自我>と同
定するのが,発想としては素直だろう。ただし,神経細胞は単に電気化学的な
信号を伝える機能的な組織なので,「神経が」興奮することが重要なのではな
く,興奮の性質それ自体に本質的な要素が含まれているはずである。直ちに指
摘できることは,神経興奮が(駆動機構が別個に用意されているテューリング
・マシンなどとは異なって)外部からの制御を必要としない(ほとんど)自律
的な活動だという点である。しかも(初等力学の教科書に登場するような)単
純な自励力学系ではなく,多数の神経細胞が互いに協調しあって秩序ある興奮
バターンを生み出す<協同現象>としての性格を見落とすことができない。こ
うした証拠をもとに,(神経系での)<協同現象>こそが,客観的世界におけ
る<自我>の顕現だと解釈して良いだろう。
<協同現象>を<自我>と結び付ける発想は,先に示した基本モデルに照ら
し合わせると,きわめて合理的であることがわかる。なぜなら,現象を表現す
る変数を適当に選ぶことによって,<協同現象>は<自我>の本質的な性質と
見なされた<完結性>をあらわに示すことになり,物理的な表現形式のままで
<自我>の基本モデルと同定できるからである。<協同現象>がこうした性質
を備えていることは,次のようにして示される。物理学が教える所によれば,(神
経系などの)システムを完全に記述するのに必要な自由度のうち,<協同現象>
を直接に表すのは秩序バラメーターと呼ばれる一群の変数であり,それ以外は
非本質的な隷従バラメーターに分類される。詳細は物理学ないし数学の参考書
に譲るものとして,ごく単純なケースを考えると,系のグローバルな性質は秩
序バラメーターのみに支配され,隷従バラメーターは実現されている秩序の陰
に隠れた(多くの場合微細な)振舞いを記述することになる。例えば,水槽の
中で渦が発生しているとき,水の支配的な運動は渦の位置や角速度などを表す
少数のバラメーターによって規定され,個々の水分子は,このバラメーターの
値が定める束縛条件の下で,渦の流れに相対的な運動を表す変数によって記述
される。このような変数を用いると,<協同現象>の主要な特徴は,秩序バラ
メーターが張る部分位相空間の内部に集約され,隷従バラメーターによって張
られる他の空間を参照する必要がなくなる。しかも,(遠方に存在する別の渦
がある場合のように)物理的に相互作用のない複数の<協同現象>が実現され
ている場合は,それぞれの現象が直交した部分空間の内部で表現されるため,
互いに相手の領域を侵犯することはない。すなわち,<協同現象>は秩序バラ
メーターの部分空間で完結していると主張され,<自我>の基本モデルとして
の資格を備えていることがわかる。
<自我>とく外界>の統合
く自我>の基本モデルとして,秩序バラメーターによって記述される(神経
系の)<協同現象>を採用すると,本章の目的である<外界>との統合は,単
純な数学的操作によって実現される可能性が生まれる。このことを以下に示そ
う。ただし,く外界>については(必ずしも万人に認められている訳ではない
が)物理学のモデルによって完全に記述されるものと仮定する。
一般に,物理学的モデルは,(一般相対論や場の理論などのように)時空座
標の上にさまざまな事象が生起するという形式で表現されている。したがって,
この形式の延長線上に人間存在に関するモデルを構築しようとする限り,(現
象が生起する共通の土俵としての)時空多様体の上に多数の人間が平等に存在
することになってしまい,個人の内部に自己完結的な世界が備わっていると主
張することはできない。時空という外的世界の単一性と意識という内的世界の
多数性の間の矛盾を克服し得ないからである。しかし,多くの科学者が認めて
いるように,物理学の理論には時空多様体を用いなければならないという原理
的な要請はなく,数学的に等価な全ての形式が自然界を記述する道具として同
等の資格を持っているはずである。現に,古典力学の場合は,ニュートン流の
微分方程式による局所的形式とラグランジュ流の作用積分による非局所的形式
が完全に同等であるため,解くべき問題に応じて利用しやすい方を選ぶ自由が
ある。したがって,もし自然界の根源的な法則が古典力学によって記述される
と仮定すると,この世界は,(例えば)N個の質点が運動する4次元時空なの
か,または,(各質点ごとに位置と運動量を定める)6N次元の位相空間にお
けるある軌道なのかを峻別することは不可能となる。また,量子力学について
も,シュレディンガーによる波動力学とハイゼンべルグによる行列力学が数学
的な同値変換によって結ばれているため,どちらを利用するかは現場の物理学
者の裁量に委ねられており,いずれか一方に《実在》の表現としての優位性を
付与することはできない。優劣が生じるのは,科学の進展によって,従前の理
論を包摂する。より総合的な理論が提出された段階においてである。この見解
に従うと,現在の科学的知見の範囲内では,(質点系における位置と運動量の
ような)物理的自由度によって張られる位相空間での記述が,座標空間内部の
運動という“真の”表現から形式的な変換によって得られた数学的な虚構と見
なされる根拠が存在しないばかりか,むしろ,自然の実態に即した表現である
可能性も生まれてくる。
ここで,さらに一歩進めて,位相空間が座標空間よりも《実在》に“近い”
という可能性を積極的に認める立場を採用し,「この」宇宙を記述するのに必
要な全自由度によって張られる位相空間の中で世界を眺めることにしよう。た
だし,ここで調うところの位相空間とは,(質点系の古典力学における位置と
運動量のような)物理的な自由度を座標軸として持つ数学的な空間を意味し,
場の理論のように全ての時空点に物理的自由度が与えられている場合,その次
元数は(オーダーとしてはこの世界の拡がりを空間/時間の最小単位で表した
量になるため)想像を絶する巨大な数になる。適当な数学的形式を用いると,
現実に生起するあらゆる物理現象が,この(きわめて巨大な次元数を持つ)空
間の中で表現できると予想される(z8》。とは言っても,われわれが認識するさ
まざまな個別的事象を考えるに当たって,こうした巨大空間の全体を参照しな
ければならない訳ではない。特に,物理学的な意味で「秩序ある」現象が観察
される場合は,その現象を記述するのに必要な諸要素は,次元数が比較的少な
い部分空間の内部に「閉じ込められる」ことが知られている。例えば,水の中
に渦が発生しているとき,渦の運動を記述するためには,全ての水分子の自由
度を考慮しなくても,渦の強さや位置を表す秩序バラメーターが張る部分空間
だけを考えれば,(ほぼ)充分である。したがって,位相空間の内部で世界を
眺めると,秩序を示す現象が,いくつかの(懸け離れた,あるいは入れ子状に
なっている)部分空間に納まって生起しているように見えるはずである。
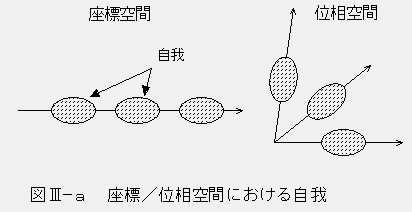 従来の科学哲学的な常識では,こうした位相空間における表現形式は,あく
まで“本来の”時空多様体上の表現に従属する数学的な虚構と見なされていた。
しかし,位相空間内部で生起する現象の中に,意識活動を成り立たせている脳
神経系内部の<協同現象>も含まれていると考えると,事態は一変する。なぜな
ら,位相空間での記述においては,<自我>と同定される<協同現象>は,秩
序バラメーターによって張られる・互いに直交した部分空間に分配されて表現
されることになり,それぞれの空間内部での自己完結性が,何らの作為なしに
自然に導かれるからである。この性質は,座標空間に依拠する記述において,
いくつかのく協同現象>が時空内部に併存するため,個々のく自我》に自己完
結的な性格を与えられないことと鋭い対照をなす。直観的に示すならば,座標
空間内部のく自我>は座標軸上に複数個並んで存在するのに対して,位相空間
においては,互いに直交する座標軸に振り分けられることになる(図III−a)。
序論で述べたように,主観的世界に見られる直接的な所与は,《実在》の
概念を規定する際に本質的な役割を果たしており,その表れ方は《実在》と(素
朴な意味で)親しい関係にあると予想される。したがって,主観的世界たる<自
我>の基本的な性質である<完結性>が自然に満たされている表現形式は,そ
うでないものに比べて,《実在》の表現として優位にあると考えられる。この
場合,時空を枠組みとして持つ<外界>は,従来の見解とは逆に,位相空間の
表現から数学的な変換操作によって再構成された結果と見なされる。一般に人
間が「時空間内部に物体が存在する」という形式で客観的な世界を認識するの
は,認知過程において(脳がコンピューターのような数学的操作を遂行し)位
相空間から座標空間への変換を実行しているためと想像される。以上の見解を
正当なものと認めると,「求心性」を示す<自我>と「並列性」を示す<外界>
が同一の概念枠の中で統合されたことになる。
従来の科学哲学的な常識では,こうした位相空間における表現形式は,あく
まで“本来の”時空多様体上の表現に従属する数学的な虚構と見なされていた。
しかし,位相空間内部で生起する現象の中に,意識活動を成り立たせている脳
神経系内部の<協同現象>も含まれていると考えると,事態は一変する。なぜな
ら,位相空間での記述においては,<自我>と同定される<協同現象>は,秩
序バラメーターによって張られる・互いに直交した部分空間に分配されて表現
されることになり,それぞれの空間内部での自己完結性が,何らの作為なしに
自然に導かれるからである。この性質は,座標空間に依拠する記述において,
いくつかのく協同現象>が時空内部に併存するため,個々のく自我》に自己完
結的な性格を与えられないことと鋭い対照をなす。直観的に示すならば,座標
空間内部のく自我>は座標軸上に複数個並んで存在するのに対して,位相空間
においては,互いに直交する座標軸に振り分けられることになる(図III−a)。
序論で述べたように,主観的世界に見られる直接的な所与は,《実在》の
概念を規定する際に本質的な役割を果たしており,その表れ方は《実在》と(素
朴な意味で)親しい関係にあると予想される。したがって,主観的世界たる<自
我>の基本的な性質である<完結性>が自然に満たされている表現形式は,そ
うでないものに比べて,《実在》の表現として優位にあると考えられる。この
場合,時空を枠組みとして持つ<外界>は,従来の見解とは逆に,位相空間の
表現から数学的な変換操作によって再構成された結果と見なされる。一般に人
間が「時空間内部に物体が存在する」という形式で客観的な世界を認識するの
は,認知過程において(脳がコンピューターのような数学的操作を遂行し)位
相空間から座標空間への変換を実行しているためと想像される。以上の見解を
正当なものと認めると,「求心性」を示す<自我>と「並列性」を示す<外界>
が同一の概念枠の中で統合されたことになる。
もっとも,上で述べたような統合の作業を実際に遂行しようとしても,こん
にちの科学的理解の範囲ではほとんど乗り越えられない難問に直面することに
なる。第1に,こんにち信じられている物理学理論は基本的に「場の理論」で
あるため,各時空点上に割り当てられた無限の自由度を取り扱わねばならない。
しかも,場の方程式は時空に関する微分を含んでいるため,時空を消去して位
相空間の表現に移るためには,理論全体を根底から変革しなければならない。
第2に,位相空間を出発点とする立場から<協同現象>に合理的な定義を与え
るのが,骨の折れる作業となる。古典力学的な理論に限定できるならば,位相
空間内部での古典的な軌道を考え,これを任意の部分空間に射影したときの振
舞いに基づいて,形式的に<協同現象>を特定することも不可能ではあるまい。
しかし,量子力学的な議論が必要になった場合は,現在の物理学の知見では全
くお手上げになる。第3に,純粋に形式的な議論の範囲内では,神経興奮のく協
同現象>とそれ以外のものを弁別する手段がないため,磁性体の自発磁化や水
槽の渦のような単純な現象にまで,自己完結的な世界が付随することを認めな
ければならない。すなわち,秩序を示すあらゆる現象は,意識水準に差はあれ,
全てく自我>を有するものと解釈されることになる。ただし,この点は深く考
えるとそれほど奇妙ではなく,むしろ,従来の<自我>概念があまりに「人間」
の側に偏していたことを改めるものだろう。
このように多くの問題が積み残されたままになっているため,本章の議論に
価値を認められない人も少なくないだろう。しかし,筆者にしてみれば,確実
だが当り前の結論を得るよりも,ほとんど解決不能と思える哲学的なアポリア
にあえて挑戦し,解決のための糸口を指摘する方が,はるかに価値のある仕事
だと思われる。こうした思いを込めて,この研究の今後を,科学哲学を信じる
多くの研究者に託したい。
©Nobuo YOSHIDA
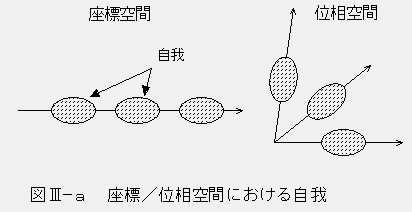 従来の科学哲学的な常識では,こうした位相空間における表現形式は,あく
まで“本来の”時空多様体上の表現に従属する数学的な虚構と見なされていた。
しかし,位相空間内部で生起する現象の中に,意識活動を成り立たせている脳
神経系内部の<協同現象>も含まれていると考えると,事態は一変する。なぜな
ら,位相空間での記述においては,<自我>と同定される<協同現象>は,秩
序バラメーターによって張られる・互いに直交した部分空間に分配されて表現
されることになり,それぞれの空間内部での自己完結性が,何らの作為なしに
自然に導かれるからである。この性質は,座標空間に依拠する記述において,
いくつかのく協同現象>が時空内部に併存するため,個々のく自我》に自己完
結的な性格を与えられないことと鋭い対照をなす。直観的に示すならば,座標
空間内部のく自我>は座標軸上に複数個並んで存在するのに対して,位相空間
においては,互いに直交する座標軸に振り分けられることになる(図III−a)。
序論で述べたように,主観的世界に見られる直接的な所与は,《実在》の
概念を規定する際に本質的な役割を果たしており,その表れ方は《実在》と(素
朴な意味で)親しい関係にあると予想される。したがって,主観的世界たる<自
我>の基本的な性質である<完結性>が自然に満たされている表現形式は,そ
うでないものに比べて,《実在》の表現として優位にあると考えられる。この
場合,時空を枠組みとして持つ<外界>は,従来の見解とは逆に,位相空間の
表現から数学的な変換操作によって再構成された結果と見なされる。一般に人
間が「時空間内部に物体が存在する」という形式で客観的な世界を認識するの
は,認知過程において(脳がコンピューターのような数学的操作を遂行し)位
相空間から座標空間への変換を実行しているためと想像される。以上の見解を
正当なものと認めると,「求心性」を示す<自我>と「並列性」を示す<外界>
が同一の概念枠の中で統合されたことになる。
従来の科学哲学的な常識では,こうした位相空間における表現形式は,あく
まで“本来の”時空多様体上の表現に従属する数学的な虚構と見なされていた。
しかし,位相空間内部で生起する現象の中に,意識活動を成り立たせている脳
神経系内部の<協同現象>も含まれていると考えると,事態は一変する。なぜな
ら,位相空間での記述においては,<自我>と同定される<協同現象>は,秩
序バラメーターによって張られる・互いに直交した部分空間に分配されて表現
されることになり,それぞれの空間内部での自己完結性が,何らの作為なしに
自然に導かれるからである。この性質は,座標空間に依拠する記述において,
いくつかのく協同現象>が時空内部に併存するため,個々のく自我》に自己完
結的な性格を与えられないことと鋭い対照をなす。直観的に示すならば,座標
空間内部のく自我>は座標軸上に複数個並んで存在するのに対して,位相空間
においては,互いに直交する座標軸に振り分けられることになる(図III−a)。
序論で述べたように,主観的世界に見られる直接的な所与は,《実在》の
概念を規定する際に本質的な役割を果たしており,その表れ方は《実在》と(素
朴な意味で)親しい関係にあると予想される。したがって,主観的世界たる<自
我>の基本的な性質である<完結性>が自然に満たされている表現形式は,そ
うでないものに比べて,《実在》の表現として優位にあると考えられる。この
場合,時空を枠組みとして持つ<外界>は,従来の見解とは逆に,位相空間の
表現から数学的な変換操作によって再構成された結果と見なされる。一般に人
間が「時空間内部に物体が存在する」という形式で客観的な世界を認識するの
は,認知過程において(脳がコンピューターのような数学的操作を遂行し)位
相空間から座標空間への変換を実行しているためと想像される。以上の見解を
正当なものと認めると,「求心性」を示す<自我>と「並列性」を示す<外界>
が同一の概念枠の中で統合されたことになる。