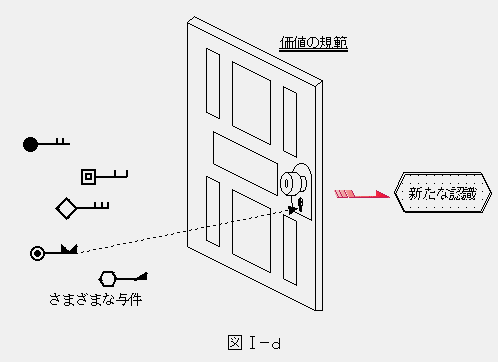I−2 価値基準としての範型
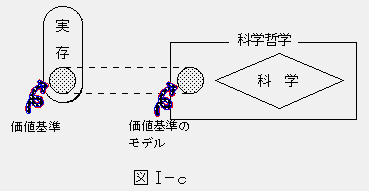 前節の結論は,科学の成果を踏まえた上で主体的な価値判断を遂行するため
には,あえて科学の内部に入り込んで価値論を展開しなければならないという
ものであった。このためには,元来は実存の内部に心理的な客体として存する
価値基準を,科学の概念体系と照合できるように,基本的な性質を不変に保ち
ながらモデル化しておく必要がある(図Iーc)。実際,モデル化しないま
まに「科学においても個人の人格を尊重するべきだ」などと提言されても,こ
の格率をどのように当てはめれば良いのかわからないため,科学への適用を目
指す価値基準としては使い物にならないのである。このような価値判断の手法
は,「その機能が明確に定義できるモデルを構築する」という科学的方法論に
準拠するもので,科学の懐に飛び込む以上は,当然のこととして採用しなけれ
ばならない。もちろん,いかに威勢の良い目標を掲げたとしても,それが
原理的に実行不可能ならば,単なる“お題目”で終わってしまうだろう。そこ
で,本節では,ある種の<価値>については,その基準をモデル化して科学的
な議論の対象にできることに力点を置いて論じていく。
前節の結論は,科学の成果を踏まえた上で主体的な価値判断を遂行するため
には,あえて科学の内部に入り込んで価値論を展開しなければならないという
ものであった。このためには,元来は実存の内部に心理的な客体として存する
価値基準を,科学の概念体系と照合できるように,基本的な性質を不変に保ち
ながらモデル化しておく必要がある(図Iーc)。実際,モデル化しないま
まに「科学においても個人の人格を尊重するべきだ」などと提言されても,こ
の格率をどのように当てはめれば良いのかわからないため,科学への適用を目
指す価値基準としては使い物にならないのである。このような価値判断の手法
は,「その機能が明確に定義できるモデルを構築する」という科学的方法論に
準拠するもので,科学の懐に飛び込む以上は,当然のこととして採用しなけれ
ばならない。もちろん,いかに威勢の良い目標を掲げたとしても,それが
原理的に実行不可能ならば,単なる“お題目”で終わってしまうだろう。そこ
で,本節では,ある種の<価値>については,その基準をモデル化して科学的
な議論の対象にできることに力点を置いて論じていく。
科学的方法論に基づく価値論の有効性
<価値>の議論も科学的方法論に準拠して行うという方針に対しては,いく
つかの批判が予想されるが,特に次の2つを取り上げよう:
- (i)<価値>とは,特定の社会体制に随伴する心理的虚構であり,科学的な
議論で取り扱われる客観的な対象とは繋がりを持たない。
- (ii)価値判断は個人の置かれた状況に敏感に依存する総合的判断であり,
還元的手法によって対象をモデル化する科学的方法論では取り扱えない。
いずれも<価値>の客観性/普遍性を否定する主張だが,その論拠を社会の
側に置くか個人の側に置くかという点で相違している。それぞれについてコメ
ントしておきたい。
(i)の見解は,<価値>の基準が判断主体の属する社会体制に応じて変動する
ため,客観的な議論の対象となるのはせいぜい個々の体制と価値観の相互関係
にとどまり,社会から切り離した一般的な<価値>について論じるのは無意味
だと主張するものである。確かに,道徳的な規範に代表されるように,価値判
断と呼ばれるものの多くが社会体制に依存していることは疑い得ない事実であ
り,ここから科学的方法論が<価値>の問題に馴染まないという結論を導くの
は一見もっともな論法である。しかし,それでは社会体制から独立しているは
ずの科学的な知識が価値判断に対して無色透明であるかと言えば,そうではあ
るまい。例えば,脳死を前提とした臓器移植を推し進めている医学者には,―
般に「脳の機能が不可逆的に喪失した人体には生きた人間としての価値は存在
しない」という発想が見られるが,このような人間観を育んだ土壌として,脳
の生理的な活動と主観的な精神現象が密接に結び付いているという科学的な知
見を軽視することはできないだろう。さらに,臓器移植の妥当性に関する意識
調査では,一般市民レベルで見ると欧米と日本の間に大きな意見の隔たりが見
られるのに比して,医学者の見解は移植推進の方向でかなり高いコンセンサス
を得ているが,この事実も(医学者は日欧米を問わず等質の社会的特権階級に
属していると考えるより)共通の科学的知識が同一の価値観を形成した結果と
解釈する方が素直である。このように,科学者集団の内部に必ずしも社会体制
に依存しない固有の価値観が成立し得る以上,価値基準をモデル化して非=社
会的に取り扱う方法論が価値論の領域でも通用する可能性があると考えてよい
だろう。
一方,(ii)の見解は,<価値>があまりに個人的なもので科学的な概念として
一般的に取り扱えない点を問題にしている。これも一面ではまさしく真実を言
い当てており,その限りでは批判の余地はない。他人からみると何の価値もな
い手紙や小石のようなガラクタが,当人にとってはかけがえのない値打ち物で
あるという事態は,誰しも体験したことがあるだろう。しかし,当然のことな
がら,<価値>のあらゆる側面が科学的手法の及ばない個人史の内側に属して
いる訳ではなく,価値判断の認識論的な形式のように一般的な法則が支配して
いる領域も存在するはずである。実際,感情の志向性を考えた場合,志向を喚
起するに到る動因は種々雑多だとしても,志向性に関与する諸要素の配置が同
一の形式を供えていることは充分に予想される。この点に,科学が楔を打ち込
む余地が残されていると言えよう。
上の考察が示しているように,科学的方法論は,日常的な用語法で表される
「価値」全般にわたって通用するのではなく,分析の対象を特定の領域に制限
して上で適用しなければならない。特に,<価値>の観念から社会的/個人的
要素を取り除いて「科学的な」議論を行うためには,分析のターゲットを,価
値判断を遂行する認識過程の形式的な側面に絞り込むのが妥当だろう。この観
点から,次に,認識論的な手法に基づいて一般的な価値判断の形式を論じてい
く。ただし,現時点では,科学的方法論を採用する手法が有効だと結論された
訳ではなく,あくまでその可能性が示されたにとどまっている。むしろ,議論
の範囲を限定したために,われわれが実感している<価値>の観念からあまり
に多くの特徴を捨象してしまうことは否めない。したがって,こうしたやり方
が<価値>の本質をどこまで解明するかは,最終的な結論の正当性によって判
定して頂きたい。
認識過程としての価値判断
価値判断を認識論的に分析する際に導きの糸になるのが,存在判断との比較
である。外界に存在する対象に眼差しを向けてこれを認識する過程において,
人間は,対象が持っている特徴を抽出して既存の知識と照合し,何らかの既知
の存在と同定する,あるいは未知のものと認定した上で知識体系を書き改め
る――という作業を行っている。ここで重要なのは,存在判断を完遂するた
めには,知識のネットワーク的な体系があらかじめ用意されているだけではな
く,判断を通じてこの体系があまり大幅に変更されてはならないという条件が
課せられている点である。実際,われわれが見慣れないものを目にしたとき,
その瞬間に既存の知識体系が音を立てて崩れてしまったのでは,以後の判断を
遂行することが不可能になるため,できるだけ知識の恒常性を保ちながら,部
分的な改変によって当該対象を体系内部に組み込むように計らっている。例え
ば,空中を移動するオレンジ色の光球を目撃した場合,自分に理解できない大
気現象の一種と見なすよりも,マージナルな知識として多くの人が抱いている
宇宙人のイメージと短絡的に結び付けてしまう方が,発想として容易なのであ
る。こうした点をもとに,(知識を多少は変更する場合があるものの)存在判
断をスタティックな過程と呼ぶことが許されよう。これに対して,価値判断は,
既存の体系を抜け出て新たな認識の地平を切り開いていく性質を有しているの
で,よりダイナミックな過程として特徴づけられる。すなわち,2種類の判断
の差異は,具体的な判断内容よりはむしろ認識論的な展開における動的性格に
存するのである。
このような主張に対して,価値判断は主として行為を規制する機能を担って
おり,この点で存在判断から区別されるはずだという批判がなされるかもしれ
ない。しかし,この批判は具体的な事例によって反駁される。例えば,鉄道の
チケットを手渡された場合,われわれが次の行動に移るための契機となるのは,
内省を通じて実感できるように,チケットの有用性に関する価値判断ではなく,
そのチケットが規定する路線ないし列車についての存在判断にすぎない。存在
判断による行為の規制が可能になるのは,意味ネットワークとしての知識体系
が,単に概念的な関係を記述しているだけではなく,行為に関する指示を含ん
でいるためである。表層的な意識の状況からすると,これらの指示は「ある条
件が満たされたときには特定の行動に移ることができる」あるいは「移るべき
である」という形式をとっており,個々の対象や事態に関する概念に随伴して
いると推定される。なお,ここから付随的に,当為命題が必ずしも価値判断に
由来している訳ではないという結論が導かれるが,社会的な“刷り込み”によ
る行動の制御が現実に行われていることを想起すれば,これはそれほど驚くべ
き事態ではないだろう。こうした機械的な規制に比べて,価値判断が惹起する
行為にははるかに豊かな自由が許されている。道すがらふと目にした野花があ
まりに美しく,一輪の花を摘み取ってきたとしよう。このとき,花に関する知
識の中に「これを摘み取るべし」という指示が含意されているとは到底考えら
れないので,この行為は,「美しい」という価値判断を契機として,認識過程
が既存の知識体系を越えて進展していった結果だと想定される。存在判断の場
合とは明らかに異なるダイナミックな展開こそ,価値判断の本質的な特色を表
すものである。
もっとも,認識活動のあらゆる局面において,価値判断と存在判断の外延が
裁然と規定されているとは言えない。例えば,菓子の「甘さ」を感得するのは
価値判断なのか存在判断なのか。「甘さ」を特定の味蕾からの味覚入力として
捉えれば、その認定は存在判断に他ならない。その一方で,血糖値が低下した
ときには甘さの味蕾を刺激する食物を欲するように生理的にプログラムされて
いるため,同じ入力が欲求の充足の契機として行動をさまざまに規制すること
から,価値判断としての色彩も濃厚である。このように,身体的な判断の中に
は身分の暖味な境界例が多数存するため,これらを含めて全ての判断を厳然と
区分できるような定義を導入することは,認識論的にあまり興味ある作業では
ない。したがって,ここでは,最も典型的な価値判断過程を,次のように形式
化して表現することで満足しよう:
-
(典型的な)価値判断とは,対象や事態などの認識与件があらかじめ用意
されている基準に合致するかどうかを判定し,肯定的な結論が得られた場
合は,それぞれの基準に応じて,与件に関する知識体系には含意されない
分野への展開が触発されるような判断である。
ここで,「基準に応じて」という条件を入れたのは,判定される価値の種類に
よって主体が何を感じ何をするかが連ってくるという日常的な常識を加味した
結果である。直観に訴える言い回しをすれば,価値を認定される対象/事態と
価値基準とは鍵と鍵穴の関係にあり,与件の中にこの鍵穴に適合する鍵があれ
ば,扉が開いて新たな認識の地平が拓けてくるのである(図I−d)。
価値判断を上のように定義すると,科学的方法論に準拠して<価値>を解明
するためのキーコンセプトとして,種々雑多な与件に対して適用される明確な
価値基準の存在が浮かび上がってくる。もし,社会体制や個人の生活史に依存
しない普遍的な価値の規範が存在し,これをモデル化して体系的な学説に組み
込むことができるならば,科学的な価値論を構築する可能性が見えてくるだろ
う。次に,この点を議論しよう。
普遍的な価値基準の可能性
日常的な経験によれば,価値判断の基準はあまりに複雑かつ精妙で,これを
モデルとして単純化することはとてもできない相談に思えるだろう。実際,か
なり鑑識眼があるはずの批評家達が,同一の美術作品に対して全く異なった評
価を下している例は,枚挙に暇がない。マルセル。デュシャンの『大ガラス』
を,ダダイズムの思想が結実した今世紀芸術の精華と褒め称える人もあれ
ば,(わたしのように)思いつきの意匠を並べ立てただけのガラクタだと姥め
る人もいる。このように,判断が一致しない事例があまりに多く見られるから
には,そもそも価値基準とは個人の体験や身辺状況に大きく影響されるもので
あって,普遍的な価値の規範など存在しないと言いたくなるかもしれない。
しかし,ここで次の点に注意されたい。価値判断においては,与えられた素
材に対して直ちに価値基準が適用されるのではなく,与件をさまざまな角度か
ら吟味/検討し,その内容に加工を施した上で基準との比較照合を行っている。
したがって,与件と判断の間に万人に共通する1対1の対応関係がないからと
いって,判断基準そのものが人によって大きく異なっているとは速断できない。
喜怒哀楽というバターン化された感情が多くの民族に共通していることからも
わかるように,一般に人間の認識過程には,与件に対する諸々の処理過程を経
るにっれて,(一般性の高いカテゴリーによって分類できるような)いくつか
の類型的な様態に収束していく傾向がある。したがって,この様態に対して適
用される判断基準が存在する場合は,社会体制や個人史によらない普遍性を有
している蓋然性が高い。この場合,価値判断の個人差は,主として収束先の相違
に由来し,価値基準そのものの差異を反映している訳ではないと考えられる。
例えば,人が美術作品を鑑賞する過程をこの枠組みの中で叙述すると,作品を
目にした瞬間に「美しい」と感じるのではなく,作品の主題や構図ないしは細
部のデザインに触発されてそれぞれの個人的体験に応じた連想を展開させ,そ
の結果として,生産的な観念連合を生みやすいセンシティヴな精神状態になっ
たとき,はじめて作品の美しさ一般を感得できるものと想定される。すなわ
ち,<美>の端緒は多様であるが,「美しい」と感じる瞬間には認識の統一が
実現されており,この統一が<美>の普遍性を保証しているのである。
「認識が統一された様態に収束した段階で(基準の適用という意味での)価
値判断が行われる」という如上の主張と対抗させて考察すべき仮説は,価値基
準との比較照合が多様な与件の段階で行われるとするものだろう。議論を単純
化するため,「多様な生(ナマ)の素材から加工された統一的様態へ」という
(必ずしも実在するとは限らない)仮想的な心理過程の軸を考えよう。ここで
取り上げた2つの仮説は,この過程のいずれかの極で価値判断が遂行されると
いうものだが,直ちにわかるように,これらは互いに排斥,し合う背反仮説では
なく,価値判断が行われる地点を「生のもの」と「加工されたもの」の両極間
の任意の位置に設定することによって,互いに漸進的に移行できる関係にある。
したがって,ここで取り掛かるべきは,具体的な価値判断のそれぞれについて,
上記の心理的座標軸のどの付近で価値基準の適用が行われているかを定める実
証的な作業だろう。この作業は,個人の内面的な観察を中心に,精神病理学や
文化人類学の知見を援用しながら行われる。
現実における価値基準の適用
はじめに,人間の本能的な側面に関与する価値判断の大部分が,多様な素材
そのものを相手にして行われていることを指摘しておく。すなわち,われわれ
は生活世界に登場する素材の姿を直接的に反映した<規範>を無数に抱いてお
り,この<規範>を与えられた素材とそのまま比較対照することによって価値
判断を下しているのである。このことは,既に例として挙げた「美人」の判定
を思い起こすとわかりやすいだろう。特定の社会に所属する男性は(各人の好
みに応じて多少の差異はあるものの)基本的にその文化によって規定される「美
人」の<規範>を後天的に獲得しているが,内省によってそれと知られるよう
に,このく規範>は,姿態や目鼻立ちなどの具体的な弁別要素を備えたテンプ
レートとして与えられている。このため,現実の女性を見て美醜の判断を下す
場合は,容姿についての知覚情報に複雑な処理を施す必要がなく,ほとんど生
の素材のまま「美人」の鋳型と比較できることになり,きわめて短時間で美し
いか否かが判定されるのである。このほかにも,身体的な快/不快の判断のよ
うに人間の本能的な行動決定の指針となる価値基準については,美醜の判定と
同様に「生の素材」の極近傍で判断が遂行されていることは見やすい。このタ
イプの価値判断は,日常生活で最も頻繁に観察される。
より社会的な価値判断――なかんづく,道徳的な善悪の判断については意
見が分かれるところだが,特定の社会体制を前提とするときのみその道徳性が
解釈されるような命題に関しては,素材にあまり手を加えずに判断を遂行して
いるケースが大半ではないかと推定される。このことは,主として日常的な体
験についての内省から察知されるが,いくつかの文化人類学的/精神病理学的
な証拠も存在する。
文化人類学的な事例としては,婚姻外の性行為に対してキリスト教文明圏で
見られる根強い道徳的反感を取り上げてみよう。改めて述べるまでもなく,カ
トリックの教義の下では,生殖を目的とする夫婦間の営み以外の性行為は厳し
く禁じられており,特に既婚者が配偶者以外と性交渉を持つことは重罪と見な
されている。ところが,こうした道徳的規範は,永続的な一夫一妻制という特
定の婚姻形態があってはじめて機能するものであり,異なる社会体制において
も有意味であるとは限らない。実際,(サハラ以南の)アフリカでは,多くの
成人はそのライフサイクルを通じて複数の経済的/性的バートナ−を持ち,そ
の結果として生じる血縁関係のネットワークの中で相互に協力し合う体制を作
り上げているが,こうした社会においては,当然のことながら,性行為を特定
の男女のペアに限定する道徳的規範は存在しない。社会学的な研究によれば,
一夫一妻制は,(分割が困難な地権や水利権などの)家督を相続させる嫡子を
差別化するための制度であり,自然環境が厳しく富の集中が起きにくい地域で
は,むしろネットワーク的な婚姻関係が成立しやすいことが知られている。こ
うした事情を勘案すれば,婚姻外の性行為に対する非難は,「夫婦間の永遠の
愛情」を尊重する高貴な倫理観に根ざすものではなく,より表層的な社会意識
に由来すると見なされる。したがって,道徳的な価値判断も,個々の行為を理
念化した上で一般的な「不道徳性」の烙印を押しているのではなく,「夫婦以
外の性行為」という具体的な物差しを振りかざしているだけだと考えるのが良
さそうである。
社会的な価値判断が生の素材を対象としていることを(それほど積極的では
ないが)支持する証拠は,精神病理学の領域にも見いだされる。ある精神分裂
病の患者は,症状が寛解して日常生活に不自由しなくなったため,バーティー
への出席が許されて,ほとんど健常者と区別できないほどそつなく振舞ってい
たが,会も終わる頃に人前で排尿するという粗相をしてしまった。ところが,
回りの人がその不作法さをいくら説いても,本人はどうしても納得できなかっ
たという。ここで,マナーの善し悪しに関する価値判断が,一般に行為内容を
抽象化した上で行われていると仮定すると,このケースを合理的に解釈するこ
とが難しくなる。なぜなら,抽象化された行為についての社会性や道徳性の判
定は,(当該行為が他者の感情を害しないかなどの)汎用的な基準を個別に適
用していく形式的な操作から成っているので,他の多くの行為を無難にこなし
ている一方で,特定の行為――ここでは,人前での排尿――のみについて選択
的にこの操作が不可能になるということは,いかにもありそうにないからであ
る。むしろ,人前での排尿が禁じられているのは,それが一般的な意味で不作
法と見なされるためではなく,具体的/個別的に当該行為を禁止する規定が(排
尿の仕方を規定するプログラムの“但し書”として)明記されている結果だと
解釈するのが妥当である。この観点からすれば,上記の分裂病患者においては,
この但し書を参照する能力が損なわれていたものと推測される。
普遍的な価値基準としての《範型》
ここまで述べてきた事例は,現実的な価値判断の多くが,認識内容が統一的
な様態に収束してからではなく,加工する前のほとんど生の素材に対して直接
的に遂行されていることを示唆している。もし,このような状況があらゆる価
値判断について妥当するものならば,<価値>の問題を科学哲学によって論じ
ることはきわめて困難になるだろう。なぜなら,その場合の価値の規範とは,
人間の精神的活動の諸原理を反映するものではなく,個々の社会体制に応じて
定着した偶然の産物にすぎないため,これをモデル化して機能主義的な学問体
系の中に組み込むという科学的方法論が援用できないからである。それでは,
全ての価値判断が現実に「生の素材」の極近傍で行われているのかと聞かれる
と,あながちそうだとも言えない。既に述べたように,美術作品を「美しい」
と評価する判断は,個別的な内観を信じれば,認識がある種の統一的な様態に
達した段階で下されている。このほかにも,ある人がとった行動が「人道的だ」
と評価されるときには,行動の具体的な内容よりも,より抽象的な目的意識や
図式化された対人関係が重視されている。こうした価値判断は,特定の社会体
制に依拠しないばかりか,さまざまな心理的加工を通じて与件の多様性が捨象
された「統一的な様態」の極で,普遍的な基準を用いて遂行されていると期待
される。そこで,このような価値の基準を,今まで述べてきたような生の素材
に適用する規範と区別するために,《範型》と呼ぶことにしよう。この名称は,
ウェーバーの’ideal typus’を念頭に置いたもので,価値を判定するための
「規範」ではあるが,具体的/即物的に内実が規定されずに一般的な「型」と
して機能することを含意している。科学哲学によって議論されるべき<価値>
の問題とは,この《範型》概念の妥当性である。
《範型》の概念をもとにして科学哲学的な価値論を展開することについて2
種類の批判が予想されるので,それらに対する反論を試みよう。第1に「なぜ,
価値全般を問題としないで議論の対象を《範型》に限定するのか」という批判
が寄せられるだろう。これに対しては,多くの規範が社会体制と個人の生活史
に由来する偶然的所産であって科学的方法論による分析が困難であるという事
実と共に,全ての価値を哲学的に規定することの危険性を指摘しておく。歴史
の体験が物語るように,過去の思想や宗教の中には,人々に一定の価値観を押
し付けようとして文化の画一化や反対者への弾圧を繰り返してきたものが数多
くある。その轍を踏まないためにも,価値論に関して哲学者は版図をあまり広
げないように自重すべきなのである。一方,これと正反対な第2の批判とし
て,「なぜ,全ての価値を相対的なものと考えず普遍的な《範型》の存在を認
めるのか」という声が上がることも予想される。残念ながら,いかなる価値判
断も何らかの社会的/個人的要素を多かれ少なかれ含んでいる以上,こうした
主張を完全に論駁することは困難である。この点にこそ,《範型》論を展開す
る上での最大の弱点がある。
《範型》の普遍性を巡るさまざまな疑念は,これが客観的世界の法則によっ
て裏打ちされた存在論的な概念ではないという事実に根ざしている。実際,そ
の定義から明らかなように,《範型》とは,統一された認識の様態に適用され
る主観的な基準以上の何物でもないのである。「人道性」という《範型》を例
にとって説明しよう。この《範型》は,見聞した行為を端緒とする認識過程が
特定の図式的関係を満たす状態に収束したとき,その諸関係全体の構図を判定
する際の基準としてのみ機能するもので,人道的な行為の外延を画定する客観
的な規範としては役に立たない。このため,同一の行動に対して人々の評価が
分かれるのはもちろん,そもそも「人道性」なる《範型》を適用できるのか原
理的に決定できないような境界事例も現れてくる。例えば,カレル。チャペッ
クは『山椒魚戦争』という小説に知能を持った山椒魚を登場させているが,こ
うした生物に対して「人道的」なる語を用いるべきかどうかは誰にもわからな
いだろう。こうなると,そもそも《範型》を普遍的な価値基準と見なして良い
のか,懐疑的にならざるを得ない。
一方,もともと《範型》それ自体が普遍的である必要はなく,これに基づく
行為の規制が社会的に何らかの効果を上げれば充分だと主張する人もあるだろ
う。例えば,<貴族>と<奴隷>とを峻別する言語体系を有していた社会にお
いて,各階層の成員が社会的なコンテクストで等価に扱われていることを評価
する「(人間の)平等性」なる《範型》が導入され,その結果として階級制撤
廃の方向に改革がなされたとすれば,たとえ「等しい価値を持つ人間一般」と
いう概念の定立に成功しなかったとしても,《範型》が社会的に有意義な役割
を果たしたと結論されるかもしれない。しかし,こうした見解は,当然のこと
ながら,<価値>を社会体制に従属させる相対主義へと後退を余儀なくされる
だろう。
こうした“普遍性論争”に終止符を打つ最も確実な手段は,その普遍性と有
用性が実証的に確認できるような《範型》を具体的に提示することである。こ
の方針に基づいて,次章では,人間にとって最も根源的だと思われる1つの《範
型》――すなわち,<創造的秩序>を取り上げることにする。
©Nobuo YOSHIDA
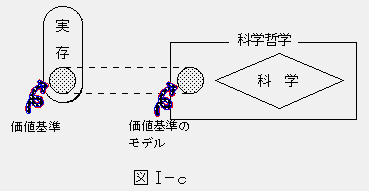 前節の結論は,科学の成果を踏まえた上で主体的な価値判断を遂行するため
には,あえて科学の内部に入り込んで価値論を展開しなければならないという
ものであった。このためには,元来は実存の内部に心理的な客体として存する
価値基準を,科学の概念体系と照合できるように,基本的な性質を不変に保ち
ながらモデル化しておく必要がある(図Iーc)。実際,モデル化しないま
まに「科学においても個人の人格を尊重するべきだ」などと提言されても,こ
の格率をどのように当てはめれば良いのかわからないため,科学への適用を目
指す価値基準としては使い物にならないのである。このような価値判断の手法
は,「その機能が明確に定義できるモデルを構築する」という科学的方法論に
準拠するもので,科学の懐に飛び込む以上は,当然のこととして採用しなけれ
ばならない。もちろん,いかに威勢の良い目標を掲げたとしても,それが
原理的に実行不可能ならば,単なる“お題目”で終わってしまうだろう。そこ
で,本節では,ある種の<価値>については,その基準をモデル化して科学的
な議論の対象にできることに力点を置いて論じていく。
前節の結論は,科学の成果を踏まえた上で主体的な価値判断を遂行するため
には,あえて科学の内部に入り込んで価値論を展開しなければならないという
ものであった。このためには,元来は実存の内部に心理的な客体として存する
価値基準を,科学の概念体系と照合できるように,基本的な性質を不変に保ち
ながらモデル化しておく必要がある(図Iーc)。実際,モデル化しないま
まに「科学においても個人の人格を尊重するべきだ」などと提言されても,こ
の格率をどのように当てはめれば良いのかわからないため,科学への適用を目
指す価値基準としては使い物にならないのである。このような価値判断の手法
は,「その機能が明確に定義できるモデルを構築する」という科学的方法論に
準拠するもので,科学の懐に飛び込む以上は,当然のこととして採用しなけれ
ばならない。もちろん,いかに威勢の良い目標を掲げたとしても,それが
原理的に実行不可能ならば,単なる“お題目”で終わってしまうだろう。そこ
で,本節では,ある種の<価値>については,その基準をモデル化して科学的
な議論の対象にできることに力点を置いて論じていく。