I−1 実存に基づく価値判断の限界
価値判断を実存にのみ立脚させることによって科学から切り離した場合,ど
のような不都合が派生するかを考える。
支援システムとしての科学
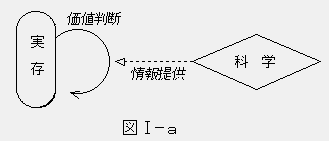 「価値論と科学はどのような関係にあるべきか」についての諸々の見解の中
で,最も保守的かつ穏健なものは,後者を前者の支援システムとして利用する
という意見だろう。これは,価値判断は基本的に自己の内面的認識に対して(「こ
れは良い」というように)行われると仮定した上で,その判断の根拠として科
学的知見が援用できることを主張するものである(図I−a)。この考え自
体には積極的に反対すべき理由はなく,おそらく大半の科学者もこれを支持す
ると予想される。ただし,もしこの関係が両者を繋ぐ唯一の紐帯であるとする
と,価値判断が「没価値的な」科学によって振り回され日和見主義に陥る危険
がある。この点について順を追って説明しよう。
「価値論と科学はどのような関係にあるべきか」についての諸々の見解の中
で,最も保守的かつ穏健なものは,後者を前者の支援システムとして利用する
という意見だろう。これは,価値判断は基本的に自己の内面的認識に対して(「こ
れは良い」というように)行われると仮定した上で,その判断の根拠として科
学的知見が援用できることを主張するものである(図I−a)。この考え自
体には積極的に反対すべき理由はなく,おそらく大半の科学者もこれを支持す
ると予想される。ただし,もしこの関係が両者を繋ぐ唯一の紐帯であるとする
と,価値判断が「没価値的な」科学によって振り回され日和見主義に陥る危険
がある。この点について順を追って説明しよう。
素朴に考えると,人間は「〜は価値がある/良い/善だ/好ましい/美しい」
といった価値判断を,純粋に個人的な直観に基づいて遂行しているようであり
科学的な知識が何の役に立つかと思われるかもしれない。しかし,心理学や文
化人類学の教えるところによれば,認識された対象/事態に対して下される価
値判断の基準は,多くの場合,社会的な規範として後天的に獲得されたもので
あり,こうした規範を与件と無意識のうちに比較することによって,一見個人
的な価値判断を遂行しているとされる。したがって,(単なる個人的直観では
ない)心理的な客体としての規範を分析する作業において,科学的な知見が有
用になるケースが多々ある。
価値判断の基準が後天的に獲得された心理的客体であることを端的に示す卑
近な例として,いわゆる「美人」の尺度を取り上げてみよう。大半の男性は,
女性の顔を見ただけで,ほとんど瞬間的に「美しい」か否かが判定できるはず
である。しかも,こうした美醜の判定は自分の個人的な嗜好に即して行われて
いると思っている人が多いのではなかろうか。ところが,このような素朴な考
えに対しては,文化人類学的な反論が提出されている。第1に,特定の文化圏
内部では,ある人が非常に美しいと感じる女性を別の男性が非常に醜いと評価
することは滅多にないが,「美人」の尺度が(美術作品の評価と同じく)単な
る個人的な「好み」の反映ならば,成員の間でこれほどまでに高いコンセンサ
スが得られる理由が判然としない。第2に,地方によっては肥満したり体の一
部が異常に発達したりしている女性が好まれる民族も存在しており,文化圏が
異なると「美人」を巡るコンセンサスを得にくい。こうしたデータをもとに,
それぞれの文化圏には女性の容姿を判定する固有の「物差し」があり,そこに
生活する人々は,無意識のうちにその基準を我が物として受け入れている――
と結論されよう。ただし,(労働力が不足している地域では多産型の体形が美
しく見られるというように)社会状況と美人の条件が必然的に結びついている
訳ではなく,さまざまな偶然的要素が絡み合って一定の嗜好を醸成しているよ
うである。
もし,全ての価値判断が個人の内的な直観に依拠しているとすれば,そこに
科学が容喙する余地はないだろう。だが,(上で見た「美人」の規範のように)
価値基準が外在的な社会状況に由来するものならば,両者の因果関係を分析す
る目的で,科学的な知識を援用することが可能となる。断わっておくが,ここ
でわたしが主張したいのは,<価値>が社会体制に依存するという相対主義の
見解ではない。科学が価値判断と無縁のものではなく,少なくとも,因習的な
謬見に惑わされないための判断材料を提供する役割は果たせることを提示する
のが主な目的である。この点について,1つだけ具体例を挙げておこう。近代
以前のヨーロッパでは,精神分裂病の患者はカーニバルなどで「見せ物」扱い
にされ,実質的にその人権が認められていなかった。しかし,クレッペリンを
はじめとする精神病理学者の研究を通じて,この症候群が(おそらく脳の器質
的病変に起因する)精神病の一種であり,抗精神病薬によって緩和させられる
ことが知られるようになるにつれて,身体的疾病に冒されている一般の病人と
同様に扱うべきだという意識が高まってきた。このように,倫理的な方針決定
を含む多くの判断に際して有益な情報を提供することが,価値論の領域で科学
の果たし得る最大の役割であると見ても誤りではないだろう。
ここまでの議論から示されるように,科学が価値論に有用な情報を提供する
支援システムとして機能することは承認しなければなるまい。しかし,科学が
単にそれだけの役割にとどまるとすると,価値判断が主体性を失って日和見主
義に堕す懸念を拭いがたい。そのように感じられる理由として,次の2点を挙
げておこう。
第1に,科学自身は独自の判断基準を持っていないため,常識的な価値観か
ら見ると好ましくない結論を支援するような理論が,政治的な理由によって財
政面/人材面で優遇された形で研究され暫定的に受容されるという事態は,充
分に予想される。このような場合,科学的知識は決して絶対的な正当性を主張
するものではなく,将来の研究成果によって覆される可能性を常に秘めている
にもかかわらず,「科学的に認められている」ことを根拠に,当の結論がごり
押しされる危険は避けられないだろう。
第2の問題として,科学を支援システムとして利用する場合に,科学的な知
見を日常生活で使われる概念体系の枠内に翻訳して用いるため,活用できる知
識の範囲が翻訳の容易な心理学や社会学など応用性の強いジャンルに限定され
がちな点が指摘できる。これらのジャンルは,もともと学問的な基礎づけが充
分にされておらずt物理学や神経生理学などの基礎科学に比べて理論的な概念
の定義に曖昧さを残している。このため,支援システムとして単に有効性が乏
しいだけではなく,日常的概念への翻訳の際に誤解を生じやすく,社会問題を
引き起こす心配がある。
この2つの危険性が同時にあらわになるのが,科学的知見が社会差別を正当
化する根拠として用いられるケースである。
アメリカで行われた調査によれば,人種/民族ごとのIQを比較した場合,
ユダヤ系や中国系の市民の値が高くなる一方,黒人やヒスバニックの値が有意
に低くなることが知られている。こうした「科学的なデータ」をもとに,
黒人など“知能の低い”民族に対して高等教育を施すことは投資の無駄になる
ので,学校に人種/民族別の入学定員枠を設けるべきだという差別思想が声高
に叫ばれた史実は,科学の誤った応用例として記憶にとどめておかなければな
らない。こうした過誤が生じた原因として,次の2点が指摘される:
- (i)IQについての研究は,もともと特殊学級に進学させるべき生徒を選別
する目的で(ビネーに委託されて)始められたため,当初から,長期間の
観察なしに簡単に実施でき,しかも被験者の間に数量的な差をつけられる
テストの開発に研究目標が偏っていた。
- (ii)知的能力の一部を測定するにすぎないIQが,日常的な意味での「頭の
良し悪し」に対応すると誤解されたまま一般に喧伝されてしまった。
これらが,先に述べた(支援システムとしての科学に見られる)危険性がその
まま表面化した結果であることは,論をまたない。
幸いなことに,IQが日常的な意味での「知能」を表す指標としては信憲性
に乏しいという事実は,(哲学的な価値論に頼らなくとも)科学的な議論によっ
て明らかにされる。具体的には,
- (i)IQは(ロボトミー手術などによって)前頭葉に傷害を受けても必ずし
も減退せず,ここで遂行される創発的な思考能力を充分に反映していない。
- (ii)IQ検査は,バターン変化の規則性を発見する単純な推論能力など,訓
練によって獲得しやすい後天的な能力を中心に評価するため,練習を積め
ば容易に得点を上げることができる。
- (iii)IQは幼児期の環境に左右されやすく,生活水準の低い家庭の子供は絵
本などの教育用具を活用できないため低い値になる傾向にある。
などの点が,IQの有用性の限界を明かにしている。しかし,こうした個別的
批判はあくまでIQに特有のものであって,社会的な差別を助長する各種の検
査に対して一般的に妥当する訳ではない。それどころか,科学的な反論が容易
に提出できず,そもそも差別するのが正当ではないかと思わせるケースすら現
れている。例えば,遺伝子調査の結果,犯罪者の間では性染色体がXYYと
なる異常が一般人よりも有意に高く観察されることが判明した。このデー
タをもとに,XYYの保有者は通常のXYの男性よりも反社会的な行動をとる
傾向性が高いという推測がなされ,新生児の段階でスクリーニングを行うべき
だという主張にまで発展している。これに対して,XYY保有者が刑務所内で
は必ずしも粗暴な傾向を持たない点を盾に反論する者もあるが,IQの場合ほ
ど説得力がないのが実状である。
以上の議論によって示されるように,科学的な知見を判断材料として受動的
に利用するだけでは,機能主義的な科学の営みに必然的に含意される「定説」
の揺らぎによって,主体的であるべき価値の判断が狂わされる危険が生じてく
る。したがって,科学の成果を射程に収めた価値論を展開するためには,より
主体の能動性を活用しなければならないと結論される。
異議申し立てのための哲学
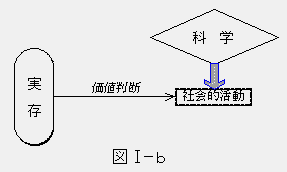 主体が能動的に<価値>を主張する方法として直ちに思い浮かぶのが,「科
学の名の下に」行われる社会的活動に対する異議申し立てである。直観的に言っ
てしまうと,科学の営為に何かキナ臭さを感じたときに,自己の実存を踏まえ
て「待った」を掛ける態度である(図I−b)。科学と価値論の関係として
科学を支援システムとして活用する方式が主に科学者に好まれるのに対して,
哲学者が是とするのは,この異議申し立てのやり方ではないかと思われる。し
かし,私はこの方法に共感は覚えない。確かに,歴史を回顧すると,哲学者に
よって科学的な活動に対する疑義が提出され,社会的な影響力を持ったことが
あるかもしれないが,現代にはこの方法は通用しないはずである。何よりも,
科学者が非=科学的な言説には耳を傾けようとしないことを忘れてはならない。
科学とは独自の理念に従う機能主義的なシステムであり,科学的方法論に従わ
ない命題が取り込めるようには組織されていないのである。
主体が能動的に<価値>を主張する方法として直ちに思い浮かぶのが,「科
学の名の下に」行われる社会的活動に対する異議申し立てである。直観的に言っ
てしまうと,科学の営為に何かキナ臭さを感じたときに,自己の実存を踏まえ
て「待った」を掛ける態度である(図I−b)。科学と価値論の関係として
科学を支援システムとして活用する方式が主に科学者に好まれるのに対して,
哲学者が是とするのは,この異議申し立てのやり方ではないかと思われる。し
かし,私はこの方法に共感は覚えない。確かに,歴史を回顧すると,哲学者に
よって科学的な活動に対する疑義が提出され,社会的な影響力を持ったことが
あるかもしれないが,現代にはこの方法は通用しないはずである。何よりも,
科学者が非=科学的な言説には耳を傾けようとしないことを忘れてはならない。
科学とは独自の理念に従う機能主義的なシステムであり,科学的方法論に従わ
ない命題が取り込めるようには組織されていないのである。
哲学に対して人々が期待するのは,時代の良心としてしなやかな感性を失わ
ずに体制を批判する能力かもしれない。だが,この姿勢をかたくなに把持しよ
うとすると,哲学は現代社会にとってもはや文学作品以上の影響力を持つこと
はできないだろう。その間にも,科学は圧倒的な力を社会に及ぼし続けるに違
いない。もし,哲学的な価値論に何らかの成果を期待するならば,自己の実存
にのみ立脚することを止めて,科学の内部に入り込んで実存から切り離された
価値基準を構成する道を模索しなければならない。この試みが,次節の課題と
なる。
©Nobuo YOSHIDA
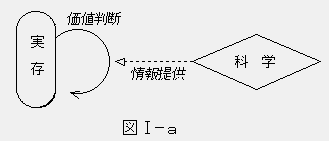 「価値論と科学はどのような関係にあるべきか」についての諸々の見解の中
で,最も保守的かつ穏健なものは,後者を前者の支援システムとして利用する
という意見だろう。これは,価値判断は基本的に自己の内面的認識に対して(「こ
れは良い」というように)行われると仮定した上で,その判断の根拠として科
学的知見が援用できることを主張するものである(図I−a)。この考え自
体には積極的に反対すべき理由はなく,おそらく大半の科学者もこれを支持す
ると予想される。ただし,もしこの関係が両者を繋ぐ唯一の紐帯であるとする
と,価値判断が「没価値的な」科学によって振り回され日和見主義に陥る危険
がある。この点について順を追って説明しよう。
「価値論と科学はどのような関係にあるべきか」についての諸々の見解の中
で,最も保守的かつ穏健なものは,後者を前者の支援システムとして利用する
という意見だろう。これは,価値判断は基本的に自己の内面的認識に対して(「こ
れは良い」というように)行われると仮定した上で,その判断の根拠として科
学的知見が援用できることを主張するものである(図I−a)。この考え自
体には積極的に反対すべき理由はなく,おそらく大半の科学者もこれを支持す
ると予想される。ただし,もしこの関係が両者を繋ぐ唯一の紐帯であるとする
と,価値判断が「没価値的な」科学によって振り回され日和見主義に陥る危険
がある。この点について順を追って説明しよう。
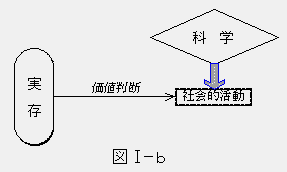 主体が能動的に<価値>を主張する方法として直ちに思い浮かぶのが,「科
学の名の下に」行われる社会的活動に対する異議申し立てである。直観的に言っ
てしまうと,科学の営為に何かキナ臭さを感じたときに,自己の実存を踏まえ
て「待った」を掛ける態度である(図I−b)。科学と価値論の関係として
科学を支援システムとして活用する方式が主に科学者に好まれるのに対して,
哲学者が是とするのは,この異議申し立てのやり方ではないかと思われる。し
かし,私はこの方法に共感は覚えない。確かに,歴史を回顧すると,哲学者に
よって科学的な活動に対する疑義が提出され,社会的な影響力を持ったことが
あるかもしれないが,現代にはこの方法は通用しないはずである。何よりも,
科学者が非=科学的な言説には耳を傾けようとしないことを忘れてはならない。
科学とは独自の理念に従う機能主義的なシステムであり,科学的方法論に従わ
ない命題が取り込めるようには組織されていないのである。
主体が能動的に<価値>を主張する方法として直ちに思い浮かぶのが,「科
学の名の下に」行われる社会的活動に対する異議申し立てである。直観的に言っ
てしまうと,科学の営為に何かキナ臭さを感じたときに,自己の実存を踏まえ
て「待った」を掛ける態度である(図I−b)。科学と価値論の関係として
科学を支援システムとして活用する方式が主に科学者に好まれるのに対して,
哲学者が是とするのは,この異議申し立てのやり方ではないかと思われる。し
かし,私はこの方法に共感は覚えない。確かに,歴史を回顧すると,哲学者に
よって科学的な活動に対する疑義が提出され,社会的な影響力を持ったことが
あるかもしれないが,現代にはこの方法は通用しないはずである。何よりも,
科学者が非=科学的な言説には耳を傾けようとしないことを忘れてはならない。
科学とは独自の理念に従う機能主義的なシステムであり,科学的方法論に従わ
ない命題が取り込めるようには組織されていないのである。