|
|
|
|
|
第4章.ビッグバン理論
〜何が空想を科学にするか〜 |
| 宇宙の年齢 | 宇宙の温度 | 物質の生成 | 元素合成 | |
| ビッグバン理論(オリジナル) | 20億年 | 初期:高温 現在:数K |
ビッグバンとともに | 全てビッグバン直後に |
| 〃 (改訂版) | 100〜150億年 | ビッグバンの直後に | ヘリウム以外は恒星内部で | |
| 定常宇宙論 | ∞ | 絶対零度 | 常に真空から生成 | 全て恒星内部で |
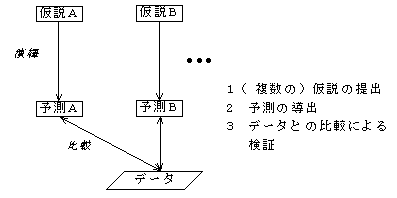
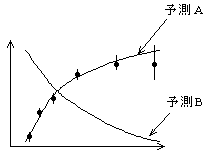 こうして仮説ごとに導き出された予測は、実験・観察によって得られた具体的データと比較され、データと合致しない予測を生成した仮説は、正当性を持たないとして棄却されてしまう(これを仮説の反証と言う)。もちろん、予測とデータが合致したとしても、直ちにその仮説が正当だと結論することはできないが、少なくとも段階的に信憑性を高めることにはなる。特に、学界を二分するような2つの対抗仮説があって、特定の現象について対照的な予測を導いている場合は、1つの「決定実験」によって雌雄が決し、勝利を納めた側が一挙に定説として認知されるケースもある(右の例で考えてほしい)。
こうして仮説ごとに導き出された予測は、実験・観察によって得られた具体的データと比較され、データと合致しない予測を生成した仮説は、正当性を持たないとして棄却されてしまう(これを仮説の反証と言う)。もちろん、予測とデータが合致したとしても、直ちにその仮説が正当だと結論することはできないが、少なくとも段階的に信憑性を高めることにはなる。特に、学界を二分するような2つの対抗仮説があって、特定の現象について対照的な予測を導いている場合は、1つの「決定実験」によって雌雄が決し、勝利を納めた側が一挙に定説として認知されるケースもある(右の例で考えてほしい)。
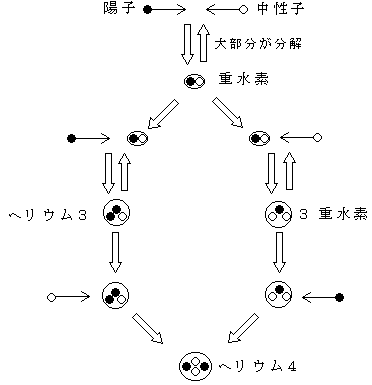 ビッグバン宇宙論によれば、ヘリウムの合成は、初期宇宙における高温・高密度状態で行われる(右図)。陽子と中性子が結合して元素を合成していくときの各粒子の「濃度」は、結合定数が与えられたときの化学反応の場合と同様にして計算することができる。最終的な水素とヘリウムの存在比がいくらになるかは、現在の宇宙の温度に依存するが、この値が絶対温度で5度程度(−268℃程度)のとき「水素:ヘリウム≒3:1」になることが導かれる。
ビッグバン宇宙論によれば、ヘリウムの合成は、初期宇宙における高温・高密度状態で行われる(右図)。陽子と中性子が結合して元素を合成していくときの各粒子の「濃度」は、結合定数が与えられたときの化学反応の場合と同様にして計算することができる。最終的な水素とヘリウムの存在比がいくらになるかは、現在の宇宙の温度に依存するが、この値が絶対温度で5度程度(−268℃程度)のとき「水素:ヘリウム≒3:1」になることが導かれる。
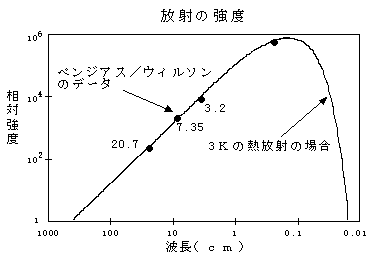 ところが、驚くべきことに、考えられる限りの電磁波の影響を除いていったにもかかわらず、最後までどうしてもその起源が明らかにできない電磁ノイズが残されたのである。この電磁ノイズは、全く日周変化を示さず、アンテナをどの方向に向けても同じ強度で測定された。したがって、その起源は、宇宙空間そのもの以外には考えられない。測定された強度を放射公式に当てはめると、絶対温度で3.3Kになる(上に、その後数年間に得られたデータと併せて示す)。1965年に発表されたこのデータは、定常宇宙論を完全に反証し、ビッグバン理論を強く支持するものだった。ところで、ペンジアスとウィルソンは、宇宙論について全く知識がなく、ピーブルスらが背景放射についての理論を発表した後になって、漸く自分たちが世紀の大発見をしていたことに気がついたという。彼らの業績に対して、1978年にノーベル賞が授与された。
ところが、驚くべきことに、考えられる限りの電磁波の影響を除いていったにもかかわらず、最後までどうしてもその起源が明らかにできない電磁ノイズが残されたのである。この電磁ノイズは、全く日周変化を示さず、アンテナをどの方向に向けても同じ強度で測定された。したがって、その起源は、宇宙空間そのもの以外には考えられない。測定された強度を放射公式に当てはめると、絶対温度で3.3Kになる(上に、その後数年間に得られたデータと併せて示す)。1965年に発表されたこのデータは、定常宇宙論を完全に反証し、ビッグバン理論を強く支持するものだった。ところで、ペンジアスとウィルソンは、宇宙論について全く知識がなく、ピーブルスらが背景放射についての理論を発表した後になって、漸く自分たちが世紀の大発見をしていたことに気がついたという。彼らの業績に対して、1978年にノーベル賞が授与された。
 最初の数分が過ぎると、重大な事件だけを記す「宇宙誌」のタイムスケールは、どんどんと引き延ばさざるを得なくなる(右図)。水素とヘリウムの原子核、それに光と電子だけを含んだままに膨張し続ける宇宙は、創成から数十万年を経て、やっと次の段階に入る。宇宙が始まってから30万年後に、水素の原子核に電子が捕まって、中性の水素原子が形成され始めるのだ。さらに、70万年を経て温度が3000度まで下がると、大半の電子が原子核と結合して、宇宙を構成する物質は、ほぼ中性化する。それまでは、電子に散乱されてまっすぐ進めなかった光は、邪魔な電子がいなくなって遠方にまで伝播できるようになる。この現象を「宇宙の晴れ上がり」と言い、こんにち観測可能な最も古い光は、この頃に発せられたものである。
最初の数分が過ぎると、重大な事件だけを記す「宇宙誌」のタイムスケールは、どんどんと引き延ばさざるを得なくなる(右図)。水素とヘリウムの原子核、それに光と電子だけを含んだままに膨張し続ける宇宙は、創成から数十万年を経て、やっと次の段階に入る。宇宙が始まってから30万年後に、水素の原子核に電子が捕まって、中性の水素原子が形成され始めるのだ。さらに、70万年を経て温度が3000度まで下がると、大半の電子が原子核と結合して、宇宙を構成する物質は、ほぼ中性化する。それまでは、電子に散乱されてまっすぐ進めなかった光は、邪魔な電子がいなくなって遠方にまで伝播できるようになる。この現象を「宇宙の晴れ上がり」と言い、こんにち観測可能な最も古い光は、この頃に発せられたものである。
©Nobuo YOSHIDA