フリードマン模型
-
アインシュタインの宇宙模型に理論的な欠陥があることを最初に正しく指摘したのは、ソ連の数理科学者・気象学者フリードマン(Alexander A. Friedmann)だった。当時のソ連は、漸く革命後の混乱を脱しつつあったが、理論物理学の水準は、まだイギリスやドイツに遠く及ばなかった。特に、技術的応用をほとんど持たない相対性理論は、労働者階級の利益とは無縁であるために、共産主義の教義とは相容れないものとして排斥される傾向にあった。こうした中で、若い頃から数学的才能を示していたフリードマンが、気象学という「実学」を担当したのは、やむを得ぬ選択だったと言える。しかし、宇宙論に強い興味を抱いていた彼は、ソ連の学界で孤立しながらも相対論の研究を続け、ついに、西欧の科学者が誰も予測し得なかった驚くべき結論を発見する。
-
フリードマンが採用した計算法は、従来のやり方に比べてはるかに現代的である。アインシュタインが、「この宇宙は4次元球の表面と同じ幾何学的構造を持つ」と(天下り的に)仮定したのに対して、フリードマンは、宇宙が一様・等方であること(これが「宇宙原理」の数学的表現である)だけを前提として計算を行ったのだ。具体的には、見通しが良いように極座標表示を採用し、空間の曲率や物質密度が場所によらずに時間だけの関数になるとして、式を簡略化してみせた(圧力の計算で多少の過ちを犯しているが、結論に本質的な影響はない)。こうして得られた方程式によると、(曲率が正という条件の下で)宇宙空間はアインシュタイン模型の場合と同じく球面状になるが、(アインシュタインが主張したように)宇宙が静的になるのは、いくつかのパラメータがきわめて特殊な関係式を満たしている場合に限られる。この関係式を満たさない一般のケースにおいて、「球の半径」Rは、時間を変数とする常微分方程式に従うことが示される。こうしてフリードマンは、宇宙のダイナミカルな変化を解明する「魔法の式」を手にしたのである。1922年に発表された第1論文で、彼は、動的宇宙観復活ののろしを上げる。
-
宇宙の半径Rが従っている方程式の解は、(フリードマンによれば)宇宙定数および全質量がどのような範囲にあるかによって、大きく3つのパターンに分けられる。これらは、横軸に時間、縦軸に半径Rをとったグラフを使って、下図のように表される。
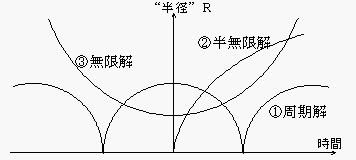
-
それぞれのパターンを言葉で説明すると次のようになる:
- 周期解:宇宙半径Rが0と最大値の間で振動するという解。当時得られていた物質密度のデータなどから、フリードマンは、振動の周期をおよそ100億年と推定している(この値は、現在のデータとは全く一致しない)。面白いことに、フリードマンは、Rが0になる振動の両端を同一時刻と見なすことが可能だと考えている。この考えによれば、宇宙は、大きさ0の「天地創造」の瞬間から膨張を始め、ある最大の大きさに達した後に収縮に転じて、再び大きさが0まで萎んでしまうが、この瞬間は取りも直さず最初の瞬間と同一だということになる。これは、まさに、ヘレニズム的な「循環する時間」の発想であり、いつまでも同じ歴史が繰り返されることを意味する。もちろん、フリードマンは、宇宙半径が0になるたびに新しい世界が繰り返し創造されるという通常の解釈も施している。
- 半無限解:過去のある瞬間に大きさ0の宇宙が創造され、そのまま無限に膨張を続けるという解。おそらく、「まともな」科学論文の中で、「世界の始まり(the beginning of the world)」とか「世界の創造(the creation of the world)」という語句が使われた初めてのケースだろう。ただし、当然のことながら、宇宙が始まる原因やエネルギーの起源については、いっさい言及していない。
- 無限解:無限の過去から収縮してきた宇宙が、ある時点で最小の半径をとった後に膨張に転じて、再び無限の未来へ向かって膨張を続けるという解。宇宙内の物質も、きわめて希薄な状態から始まって次第に凝集してある瞬間に最大密度に達するが、その後、再び拡散してバラバラになってしまう。
-
残念ながら、フリードマンが提唱した3つの解は、こんにちでは、いずれも受け入れられていない。(2)の半無限解と(3)の無限解が実現されるためには、宇宙定数λが充分に大きく、宇宙を膨張させる反重力の効果が天体間の引力を上回っていることが必要だが、現在の観測データによると、宇宙定数ははるかに小さい。一方、(1)の周期解は、1960年代までは支持する学者もいたが、ペンローズとホーキングによる特異点定理により、数学的にあり得ないことが示された。実は、フリードマンはかなりトリヴィアルな計算間違いをしており、実際には不可能な解を導いてしまったのである。数学に秀でていたはずの彼がなぜこうした間違いを犯したかは定かではないが、論文の中で半世紀以上も前の1866年のワイエルシュトラウスの古典的な著作を参考文献として引用していることから推測するに、文化的・経済的に立ち後れていた当時のソ連にあって、近代的微分方程式論の知見が充分に得られていなかったようである。現在では、(1)の1周期分が「閉じたフリードマン宇宙」と呼ばれ、この宇宙の実態を記述する有力なモデルの1つとなっている(下図)。このモデルによると、宇宙は過去のある瞬間に生まれ、しばらく膨張を続けて最大半径に達した後に収縮に転じ、未来のある瞬間に無限小に萎んで消えてしまう。
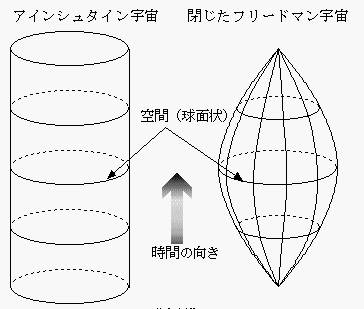
-
論文で示した解がそのままの形では受け入れられないとしても、宇宙論研究史−−と言うよりは、人類の世界観の変遷−−の中で、フリードマンの果たした役割は、実に巨大である。彼によって、初めて、宇宙が過去のある瞬間に創造されたという可能性が、科学的な理論の枠組みで論じられるようになった。現在では、彼の名は、アインシュタインやガモフとともに、科学史の殿堂で不朽の光芒を放っている。
-
しかし、時代の風は、フリードマンに対して冷たかった。Zeitshrift fur Physikという一流の学術雑誌に掲載されたにもかかわらず、相対論の研究者がほとんどいなかったソ連国内ではもちろん、西側諸国でも、彼の論文に注目した人は少なかった。指導的な立場にあるアインシュタインは、3ヶ月後に同じ雑誌に10行ほどの短いコメントを書いているが、宇宙の半径が時間に依存するという結果は重力場の方程式と矛盾していることを指摘するきわめて攻撃的なもので、相対論の計算に慣れていない研究者に、フリードマンの論文は読むに値しないと思いこませる内容になっていた。フリードマンによる抗議の手紙や他の学者からの指摘によって、間もなくアインシュタインの方が間違っていることが判明したが、それでも彼は、8ヶ月経ってから漸く誤りを認める6行のコメントを雑誌に発表しただけで、フリードマン模型の普及に力を貸すことはなかった。“御大”アインシュタインがかくも冷遇したこともあって、フリードマンの研究は、学界から完全に黙殺されてしまう。
-
これほど冷淡な扱いを受けながらも、フリードマンは、1924年の第2論文でさらなる展開を示す。第1論文で前提としていた「正曲率」という条件を撤廃し、曲率が負になったときの宇宙の幾何学的構造と時間的な振舞いを調べたのである。彼が得た結論は、またもや驚くべきものだった。負の曲率を持つ宇宙は、言わば鞍状の構造を持ち(下図)、無限に拡がるジョルダノ・ブルーノ的な世界になることが示されたからだ。もちろん、ユークリッド幾何学を前提して無限宇宙を定式化することはできる。しかし、ユークリッド的な無限宇宙は、天体間に作用する万有引力のため、安定な状態ではいられない。これに対して、フリードマンの無限宇宙は、動的な変化を通じて、その幾何学的な構造を維持することが可能になっている。
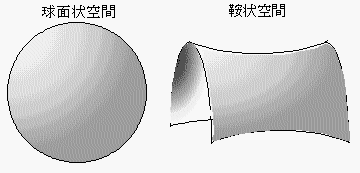
-
ここでもフリードマンは、第1論文の場合と同じく、宇宙全体のダイナミクスを記述する常微分方程式を導出し、その解の振舞いを議論している。ただし、球面状宇宙における“球の半径”のように宇宙の大きさを直接的に示す量がないため、一定の質量が含まれる領域の拡がりを表す量Rを(後世の命名法によれば)“スケール・パラメータ”Rとして定義し、その時間変化のパターンを調べた。フリードマンによれば、負の曲率を持つ宇宙には、(1)過去のある瞬間に生まれてRが無限に大きくなる半無限解と、(2)無限の過去からRが減少を続けた後に最小値に達し、その後は無限の増大へと転じる無限解の2つが存在する。このうち、(2)の無限解は観測データによって否定されたが、(1)の半無限解は、「開いたフリードマン宇宙」と呼ばれ、現在、観測データと矛盾しない宇宙模型として有望視されている。
-
宇宙論研究史にこれほど巨大な足跡を残しながら、フリードマンは、正当な評価を得られないまま、1925年、気象観測中に罹った風邪をこじらせ、38歳の若さで急逝した。彼が名声を得るのは、ハッブルの発見によって動的宇宙論の正当性が認められるようになる1930年代になってからである。
動的宇宙模型の展開
-
フリードマンと独立に宇宙の動的な振舞いを研究した学者の中でもその名が広く知られているのが、物理学者にして司祭でもあるルメートル(Abbe G. Lemaitre)である(彼が、科学的探求心とキリスト教への信仰心をいかに両立させていたかは興味あるところだが、ここでは問わないでおこう)。1927年の論文で、彼は、万有引力項と宇宙項が釣り合って膨張も収縮もせずに定常状態を保つというアインシュタインの宇宙模型が、わずかな摂動で膨張(ないし収縮)を始める不安定なものであることを示した。彼の計算によれば、アインシュタインの静的宇宙は、初めのうちはゆっくりと、次第に加速されながら、どこまでも膨張を続けることになる。この模型そのものは、宇宙定数の値が観測データと一致しないので現実的ではないが、宇宙にとっては静的な状態よりも動的な変化の方が自然であることを示す画期的な研究だった。
-
もっとも、ルメートルも(フリードマンほどではないが)学会では冷たくあしらわれていた。宇宙が動的に変化していることを明確に示す充分な観測データが得られていなかったからである。理論家たちが、膨張宇宙の模型を現実的なものと認めるためには、ハッブルが与えたような信頼できる観測データと、エディントンなどの“大物”学者による定式化が必要だった。
観測的宇宙論の成立
-
 宇宙全体がどのような構造をしているかを観測データを元に研究する「観測的宇宙論」が学問として成立するのは、今世紀に入ってからである。
宇宙全体がどのような構造をしているかを観測データを元に研究する「観測的宇宙論」が学問として成立するのは、今世紀に入ってからである。
-
すでに18世紀に、イギリスの天文学者ハーシェルは、観測される恒星の分布に基づいて、多数の恒星が円盤状に集まった銀河構造をなすことを発見していた。現在の知見では、銀河系は差し渡しが10万光年に及び、1000億個を越える恒星の集団である。しかし、銀河系が宇宙で唯一の天体の集団なのか、銀河系から遠ざかっていくと宇宙はどうなるのか−−といった「宇宙論的な」質問には、19世紀までの天文学者には答えるべくもなかった。
-
今世紀当初まで論争の種になっていたのが、「星雲」の位置づけである。光学望遠鏡ではぼんやりとしたシミのようにしか見えないこの天体が、銀河系内部/外部のいずれにあるかは、観測データに基づく具体的な立論が行えないだけに、各人の世界観をも反映して議論が紛糾した。星雲が銀河系と同等の「島宇宙」であるという主張は、古くは18世紀の哲学者カントや数学者ラプラスによって提唱されていたが、必ずしも有力視されていなかった。しかし、19世紀末からの観測技術の向上に伴って、アンドロメダ星雲などの「渦巻星雲」の光学像が得られるようになると、これらは(銀河系内のガス状星雲などとは異なって)多数の恒星が集まった「島宇宙」ではないかという見解が天文学者の間に拡がっていった。この論争は、1910年代前半にピークを迎え、宇宙には直径40万光年になんなんとする唯一の巨大銀河系が存在すると主張するシャプレーらと、銀河系と同等の島宇宙が無数に存在するというカーティスらが対峙する。
-
この論争に決着をつけたのは、やはり観測データだった。1914年、スライファーはアンドロメダ星雲のスペクトルが銀河系のものと類似していることを見いだし、両者が類縁関係にあると示唆した。さらに、1923年には、アメリカの天文学者ハッブルが、当時世界最大だったウィルソン山天文台の100インチ望遠鏡を使って、アンドロメダ星雲をはじめ、いくつかの星雲までの距離の測定に成功した。彼が利用したのは、セファイドと呼ばれる変光星である。セファイドは、星全体が変形することによって周期的に明るさを変えるが、表面積が大きく明るい星ほどゆっくり振動する性質がある。この変光周期と絶対光度の間の関係を元に、渦巻星雲内にあるセファイドの周期と見かけの光度のデータから、星雲までの距離を求めたのだ。ハッブルの計算によれば、アンドロメダ星雲までの距離は93万光年となり、シャプレーらが考えた巨大銀河系の領域よりもはるか遠方に位置する(アンドロメダ星雲までの距離は後に200万光年に修正される)。こうした観測データの集積により、この宇宙には、銀河系の他にも多数の島宇宙が存在することが明らかになった。
-
宇宙に多くの「島宇宙」(銀河系外星雲/渦巻星雲;以下では単に星雲と呼ぶ)が存在するならば、これらは、どのように分布しいかなる運動をしているのか。これが、観測天文学者に課せられた次のテーマとなる。もっとも、遠方の天体ほど観測データが得にくくなるため、宇宙論的な規模で星雲の分布を調べるのは、かなり困難である。理論家の観点に立てば、「宇宙原理」が成立しているかどうかはかなり気になるところであるが、とりあえず尤もらしい仮説の1つとして受け入れるしかなかった。深宇宙に関心を寄せる天文学者が尽力したのは、主として、星雲の運動速度の測定である。
-
星雲のように、決まった波長の光を発する物体の運動速度は、ドップラー効果を利用して測定することができる。ドップラー効果とは、波源が観測者から遠ざかるときに波長が引き伸ばされ、観測者に近づくときには逆に押し縮められる現象で、これを利用して、自動車の速度や気流の速さを測定することができる。一般に、観測者に対する波源の視線速度(視線方向の速度成分)をvとすると、静止しているときの波長λから、
-
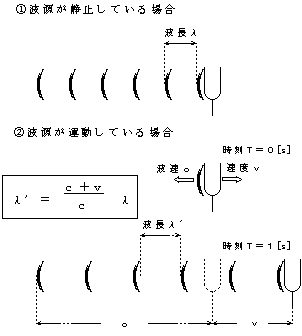 δλ=λ・v/c
δλ=λ・v/c
-
だけずれる(cは波の速さ)。星雲の場合、特定の振動数の光(原子スペクトル)を発していることがわかっているので、観測された波長を元に、視線速度を計算することができるはずである。
-
ドップラー効果を利用した星雲運動の測定は、1913年のスライファーによる先駆的研究に始まる。彼は、アンドロメダ星雲が地球に向かって300km/sで運動していると発表したが、測定誤差が大きく信頼は得られなかった。その後、シルバーシュタインやルンドマークらの観測データが提出されたが、いずれも正確なものとは言い難く、星雲運動の定性的な特徴すら掴めなかった。最大の障害は、星雲までの距離の測定法が確立されていなかったことで、セファイドを利用するハッブルの手法が紹介されるまでは、暗中模索の状況が続いた。また、星雲の運動とは別に、太陽自身が運動していることも問題を複雑にしていた。(適当に定義された)星雲系に対する太陽の運動速度をV、星雲と太陽の視線方向と太陽の運動の向きがなす角度をφとすると、ドップラー効果を元にして計算した速度
-
v=c・δλ/λ
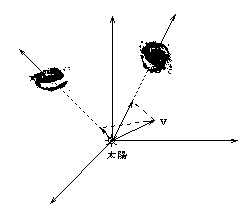
-
からVcosφを差し引いた値が星雲の固有運動の大きさを表す。ところが、太陽運動の向きと速さを求めるには、星雲との相対運動のデータを利用するしかなく、正確さは期しがたい。
-
こうした困難な状況下にあって、何人かのパイオニア達は、太陽運動の効果を除いた星雲の視線速度voが示す定性的な特徴として、銀河系からの距離rに依存する項があると主張し始めた。例えば、ルンドマークは、1920年頃から、
-
vo=k+lr+mr2
-
という式を使い始めた(k、l、mは定数)。また、ワイル、ルメートル、ロバートソンら理論家も、視線速度が距離依存性を持つ可能性を検討している(ただし、理論家の言う視線速度とは、星雲が実際に運動している速さというよりは、相対論的な効果によって生じる「見かけの」ドップラー効果に起因するものである)。しかし、いずれも、確固たる観測データに立脚していないため、机上の空論と言われても仕方のない内容だった。1929年にハッブルが提出したデータは、まさに、暗闇の中で人々が待望した曙光とでも言うべきものだったのである。
ハッブルが発見したもの
-
アンドロメダ星雲までの距離の測定ですでに名声を得ていたハッブルは、助手のフマーソンとともに、ウィルソン山天文台の100インチ反射望遠鏡を駆使して、星雲の視線速度と距離の関係を調べていた。当時の天体望遠鏡は、コンピュータ制御で自動的に鮮明な光学像を取得する現代のものとは異なって、手動で根気強く調整を続けなければならない。第1次大戦の勇士にしてプロ級の腕を持つボクサーだった(という“伝説”を持つ)ハッブルは、不屈の英雄精神をもって困難な作業に当たり、他の天文学者の追随を許さない詳細なデータを得た。ここでは、1929年に発表された有名な論文の抄訳を引用して、彼が行った研究の跡を辿りたい。
銀河系外星雲における距離と視線速度の関係
-
エドウィン・ハッブル(ウィルソン山天文台)
(1929年1月17日受理)
-
銀河系外星雲に対する太陽の運動を決定しようとすると、秒速数百km程度の不定項が現れる。本論文は、比較的信頼できる星雲までの距離のデータのみに基づいて、この問題を再検討するものである。
-
銀河系外星雲までの厳密な距離は、セファイドなど特定タイプの星の絶対光度をもとに求められる。ただし、この手法が適用できるのは、既存の観測機器によって解析できる数個の星雲に限られる。これらの星雲についての研究を通じて、後期渦巻型星雲((【注】ハッブルの星雲進化論による分類で、現在では使われない用語である)に含まれる星の最大光度はほぼ一定しており、絶対等級M=−6.3 となることが判明している。また、星雲自体の光度の平均値は、M=−15.2となる。
-
これまでに、46の銀河系外星雲の視線速度が観測されているが、そのうち距離が推定できるのものは24しかない。そのデータは、第1表(省略)にまとめられている。はじめの7つの距離は、星雲内に含まれる多くの星の綿密な観測によるもので、信頼性が高い(【注】これは、主として、星雲内のセファイドのデータに基づくもので、後に、正確な値の半分程度に見積もられていたことが判明する)。次の13の距離は、星の最大光度についての仮定に基づいており、相当の誤差も有り得るが、現時点では妥当な値だと信じられる(【注】後期渦巻型星雲に含まれる最も明るい星の絶対等級がM=−6.3とわかっているので、これと見かけの等級を比べることにより距離が求められる)。最後の4つの星雲は、おとめ座銀河団に属する。2×106パーセク(【注】1パーセク(pc)=3.26光年) という銀河団までの距離は、含まれる星雲の光度分布から求められたもので、ハーバード・グループの推定値とは数メガパーセク([注]1メガパーセク(Mpc)=100万パーセク) の差がある(【注】おとめ座銀河団に含まれる最も明るい星雲が観測されていると仮定し、他の銀河団に属する星雲の光度分布のデータと比較して距離を割り出している)。
-
表のデータは、距離rと視線速度vの間に線型関係があることを示唆する。そこで、次のように方程式を立てることにする。
-
Kr − Vcosφ = v
(V:太陽速度、φ:星雲の方向と太陽運動のなす角度)
-
24個の星雲を独立に取り扱った場合と、互いの方向や距離の近さをもとに9つのグループに分類した場合(【注】各グループに属する星団が同一の運動をしていると仮定する)のそれぞれについて、この方程式の解を求めたところ、次の結果を得た。
| |
24星雲 |
9グループ |
| K |
465±50 km/sec/Mpc |
513±60 |
| V |
306 km/sec |
247 |
-
この解を代入したvの値と観測値の差は、上の2つの場合について、それぞれ 150および100km/sec となるが、この値は、星雲またはグループの固有運動の平均値を表す(【注】ここでいう固有運動とは、線型関係からのずれを指す)。第1図(省略)に、観測値から太陽運動の値を除いた視線速度と距離の関係をプロットしておく。
-
以上の結果は、これまで視線速度が観測された星雲に関して、速度と距離が近似的な線型関係にあるという主張を確立するものである。より広範囲にわたってこの関係が成り立つかを調べるために、ウィルソン山天文台のヒューメイソン氏が、観測可能な最遠方の星雲の速度を決定する企画に着手している。最初に得られた NGC7619星雲のv=3779km/secという値は、線型関係と矛盾しない。太陽運動の効果を修正した速度は3910となり、K=500 とすると、7.8×106パーセクという距離に相当する。この星雲の見かけの等級は11.8なので、距離の換算を行えば、絶対等級は−17.65 になるが、この値は、銀河団に属する最も明るい星雲の平均的な光度に等しい。
-
こんにちの科学論文と比較すると、ハッブルの議論はかなり強引であり、統計的処理にも問題が多い。しかし、その自信に溢れた語り口には、つい説得されそうになる。この研究内容がアメリカ天文学会で発表されたとき、参加者はスタンディング・オベーションをもってハッブルを讃えたと伝えられるが、それほどまでに天文学者が渇望してやまなかったデータがここにあったと言えよう。ハッブルの発見は直ちに海を渡ってヨーロッパの学界にも伝えられ、ド・ジッターらの理論家に支持される。こうして、ハッブルは、天文学史上にガリレオに匹敵する名声を刻み込んだのである。彼は、フマーソンとともに視線速度と距離の関係を調べ続け、1931年には、より多くのデータに基づいて線型関係(いわゆる「ハッブルの法則」)を確固たるものにしている(ただし、セファイドに関するデータの誤りが原因となって、現在の観測値とはかなりのずれがある;下図)。
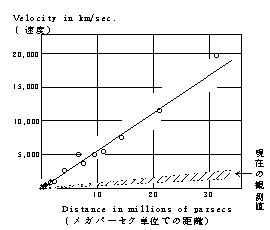
-
もっとも、ハッブル本人が、自分の発見したものの意味を当初から正しく理解していたわけではなかった。視線速度と距離の線型関係にしても、自然界の根底にある単純で美しい秩序の現れとして認識していたものの、必ずしも星雲が実際に後退運動しているとは解釈せず、他の物理的原因で光の振動数が低下し、その結果として「見かけの」ドップラー効果が生じたと考えたようである。1929年の論文で、彼は、こうした線型関係が生じる原因として2種類の「ド・ジッター効果」を紹介している。1番目は、ド・ジッター宇宙において遠方の原子の振動が(見かけ上)遅くなるというもので、時間の経過が場所によって異なるという相対論的な効果の一種である。2番目は、「物質粒子の散乱」に起因する効果と記されており、おそらくはコンプトン効果(すなわち、宇宙空間を伝播する過程で物質と相互作用して光がエネルギーを失い、アインシュタインの関係式E=hνに従って振動数も低下するというもの)を意味すると推測されるが、文章が曖昧で理解しづらい(そもそも、ド・ジッターが論じた現象ではない)。ハッブルは、確かに粘り強い観測家ではあったが、理論物理学についての理解力にはいささか欠如していたようである。いずれにしても、ハッブルが発見したものは、1929年時点では単なるデータに過ぎず、理論家による解釈が待たれた。
-
ハッブルが発見したデータを正当に解釈し、その物理的意味を市民に広めた功績は、イギリスの物理学者・天文学者エディントン卿(Arthur S. Eddington)に帰せられる。アインシュタインの友人で、天文学のみならず一般相対論や原子核理論にも通暁していた彼は、視線速度と距離の線型関係が持つ意味を直ちに理解することができた。
-
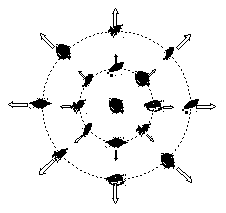 ハッブルの発見を銀河系外星雲の後退として素朴に解釈すると、われわれの住む天の川銀河が宇宙の中心に当たり、他の星雲がそこから離れるように遠ざかっていることになるが、これはいかにも不合理である。エディントンは、アンシュタインの球面状宇宙模型から出発して、これが動的に変化する可能性を考察した。エディントンの発想を直観的にイメージするには、膨らむ風船を思い浮かべればわかりやすいだろう。
ハッブルの発見を銀河系外星雲の後退として素朴に解釈すると、われわれの住む天の川銀河が宇宙の中心に当たり、他の星雲がそこから離れるように遠ざかっていることになるが、これはいかにも不合理である。エディントンは、アンシュタインの球面状宇宙模型から出発して、これが動的に変化する可能性を考察した。エディントンの発想を直観的にイメージするには、膨らむ風船を思い浮かべればわかりやすいだろう。

-
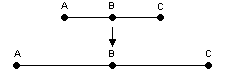 表面に一様な密度で点が描かれた風船を膨らませると、点と点との間隔は次第に拡大していくが、互いに遠ざかる速さは、離れた点同士の場合ほど大きい。例として、風船上で1直線(大円)上に一定の間隔rで並んだA,B,Cの3点を考えよう(右図)。時間Δtが経過して、AB間、BC間の間隔が2rになったとき、AC間の間隔は4rになる。つまり、Aから見ると、BはΔtの間にrだけ離れたのに対して、Cは2r離れたことになり、“後退速度”はBの2倍になっている。このように、宇宙という球面が一様に膨張する場合、その上に存在する星雲同士が互いに遠ざかる速さは、距離に比例するという「ハッブルの法則」が成り立つことになる。
表面に一様な密度で点が描かれた風船を膨らませると、点と点との間隔は次第に拡大していくが、互いに遠ざかる速さは、離れた点同士の場合ほど大きい。例として、風船上で1直線(大円)上に一定の間隔rで並んだA,B,Cの3点を考えよう(右図)。時間Δtが経過して、AB間、BC間の間隔が2rになったとき、AC間の間隔は4rになる。つまり、Aから見ると、BはΔtの間にrだけ離れたのに対して、Cは2r離れたことになり、“後退速度”はBの2倍になっている。このように、宇宙という球面が一様に膨張する場合、その上に存在する星雲同士が互いに遠ざかる速さは、距離に比例するという「ハッブルの法則」が成り立つことになる。
-
1930年の王立天文学会で発表されたエディントンの理論は、天文学者としての名声と直観的にわかりやすい説明法が奏功したためか、アインシュタインの宇宙模型とハッブルの観測データを結びつけた画期的な業績として、学界に速やかに受け入れられる。宇宙とは決して永劫不変のものではなく、その誕生と終焉をも視野に納めることが可能なダイナミックな存在であることが、明確な科学理論として初めて人々に受容されたのである。
-
ただし、いくつかの後日譚を付け加えておかなければ不公平だろう。エディントンは、実は以前にルメートルの1927年の論文を読んでいたのだが、それを忘れて、自分の学説として膨張宇宙論を提唱していたのだ。ルメートルからの手紙でそのことを思い出させられたエディントンは、素直に先達の業績を評価し、ヨーロッパではルメートルの名声が一気に高まることになる。フリードマンというさらなるパイオニアが再発見されるのは、もっと後の話である。
©Nobuo YOSHIDA
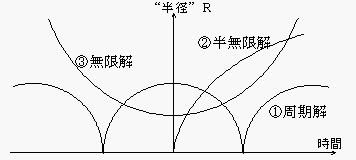
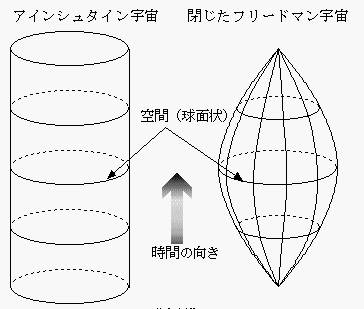
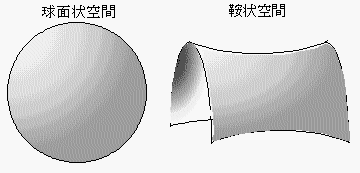
 宇宙全体がどのような構造をしているかを観測データを元に研究する「観測的宇宙論」が学問として成立するのは、今世紀に入ってからである。
宇宙全体がどのような構造をしているかを観測データを元に研究する「観測的宇宙論」が学問として成立するのは、今世紀に入ってからである。
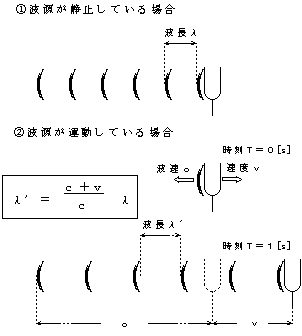 δλ=λ・v/c
δλ=λ・v/c
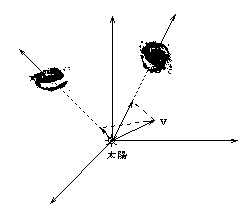
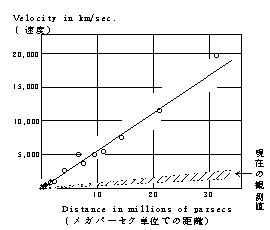
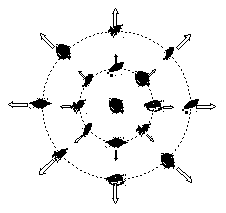 ハッブルの発見を銀河系外星雲の後退として素朴に解釈すると、われわれの住む天の川銀河が宇宙の中心に当たり、他の星雲がそこから離れるように遠ざかっていることになるが、これはいかにも不合理である。エディントンは、アンシュタインの球面状宇宙模型から出発して、これが動的に変化する可能性を考察した。エディントンの発想を直観的にイメージするには、膨らむ風船を思い浮かべればわかりやすいだろう。
ハッブルの発見を銀河系外星雲の後退として素朴に解釈すると、われわれの住む天の川銀河が宇宙の中心に当たり、他の星雲がそこから離れるように遠ざかっていることになるが、これはいかにも不合理である。エディントンは、アンシュタインの球面状宇宙模型から出発して、これが動的に変化する可能性を考察した。エディントンの発想を直観的にイメージするには、膨らむ風船を思い浮かべればわかりやすいだろう。

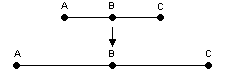 表面に一様な密度で点が描かれた風船を膨らませると、点と点との間隔は次第に拡大していくが、互いに遠ざかる速さは、離れた点同士の場合ほど大きい。例として、風船上で1直線(大円)上に一定の間隔rで並んだA,B,Cの3点を考えよう(右図)。時間Δtが経過して、AB間、BC間の間隔が2rになったとき、AC間の間隔は4rになる。つまり、Aから見ると、BはΔtの間にrだけ離れたのに対して、Cは2r離れたことになり、“後退速度”はBの2倍になっている。このように、宇宙という球面が一様に膨張する場合、その上に存在する星雲同士が互いに遠ざかる速さは、距離に比例するという「ハッブルの法則」が成り立つことになる。
表面に一様な密度で点が描かれた風船を膨らませると、点と点との間隔は次第に拡大していくが、互いに遠ざかる速さは、離れた点同士の場合ほど大きい。例として、風船上で1直線(大円)上に一定の間隔rで並んだA,B,Cの3点を考えよう(右図)。時間Δtが経過して、AB間、BC間の間隔が2rになったとき、AC間の間隔は4rになる。つまり、Aから見ると、BはΔtの間にrだけ離れたのに対して、Cは2r離れたことになり、“後退速度”はBの2倍になっている。このように、宇宙という球面が一様に膨張する場合、その上に存在する星雲同士が互いに遠ざかる速さは、距離に比例するという「ハッブルの法則」が成り立つことになる。