|
|
|
|
|
環境省は、67種類の物質を環境ホルモンとして指定していたが、生物への影響が不分明であるため、2004年に指定制度を廃止、約千種類の化学物質の中から内分泌攪乱作用のあるものを洗い直す作業に着手した。
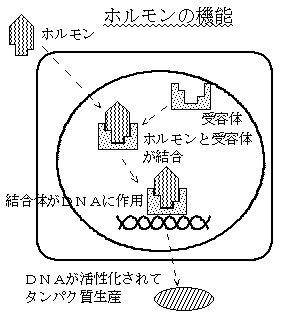
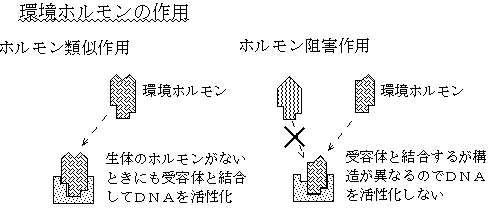
| 生 物 | 場 所 | 内分泌撹乱作用 | 推定原因物質 |
| イボニシ | 日本 | 雌のインポセックス | 船底塗料由来の有機スズ化合物 |
| サケ属 | 五大湖 | 甲状腺の過形成 | 未特定の甲状腺腫誘発物質 |
| カダヤシ | フロリダ | 雌の雄化 | 製紙工場の排水、化合物は未特定 |
| ローチ、ニジマス | イングランド | 精巣発育遅延 | ノニルフェノールか? |
| ミシシッピーワニ | フロリダ | 外性器形成不全、精巣機能不全、孵化率低下、個体数減少 | 湖内に流入したDDTなどの有機塩素系農薬とされる |
| ヤマシギ、ハイタカ、ミサゴ、ミヤマガラス、ヨーロッパヒメウなど | イギリス、北アメリカ | 産卵数減少、繁殖期遅延、産卵失敗、破損卵増加、卵の小型化、孵化率低下など | 野外観察および毒性試験よりDDTと推定される |
| セグロカモメ | 五大湖 | 甲状腺異常 | DDT説もあるが断定できない |
| ハクトウワシ | 五大湖 | 低孵化率 | PCB、DDTの可能性あり |
| アジサシ、カモメ | 五大湖 | オスの生殖器以上 | PCB、DDTの可能性あり |
| カワウソ、ミンク | 五大湖 | 繁殖激減 | PCBの可能性が高 |
| フロリダピューマ | フロリダ | オス:精子数減少、メス:不妊 | 有機塩素系農薬? |
| ゼニガタアザラシ | オランダ | 個体群の激減 | PCBの可能性が高い |
| シロイルカ | カナダ・ケベック | 個体数激減、卵巣異常、不妊 | PCB、ダイオキシンの可能性 |
| バンドーイルカ | 米国東海岸 | 大量死 | 特定できず |
©Nobuo YOSHIDA