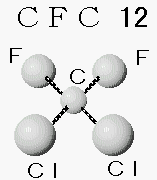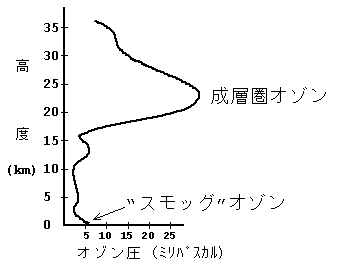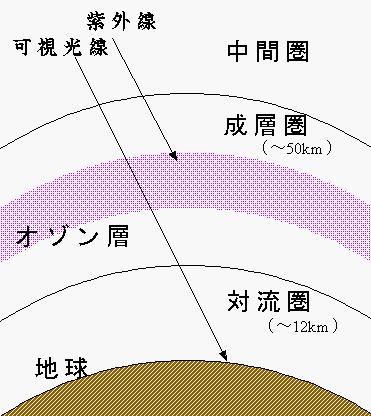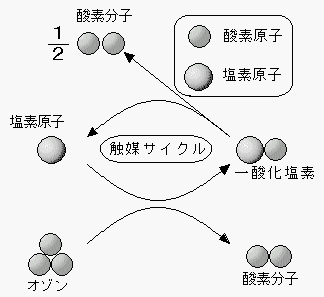§2.フロン
今世紀前半の工業の発展は、数多くの有害な物質を産み出してきた。戦後にはいると、各地で公害が多発するようになり、人間に対して毒性を持つ物質の規制が進められるようになる。この過程は、図式的にたいへんわかりやすい。昔は、公衆衛生の概念が曖昧だったために、毒でも平気で使っていたが、しだいにその危険性に対する意識が高まり、毒を社会から排除するようになったという訳である。しかし、世界はそれほど単純ではない。化学的な毒性がないにもかかわらず、さまざまな物質が人類を脅かしている。「毒性がない」からこそ安全だと考えた技術者は、何を見落としていたのか。ここでは、毒がないのに危険な物質の代表例であるフロンを例に考えてみよう。
フロンの開発
フロンとは、炭素、塩素、フッ素からなる化合物の総称で、各元素の結合の仕方に応じてさまざまな種類がある(下図はその1例)。フロンという呼称は日本独自のもので、諸外国では、クロロフルオロカーボン(塩化フッ化炭素)の頭文字をとってCFCs(終わりのsは種類が複数あることを示す)とか、デュポン社の商標のままフレオンとか呼ばれている。かつて「今世紀最大の発明」ともてはやされたこの物質が、いまや、オゾン層破壊の元凶として、世界的な規制の対象になっているとは、何とも皮肉な話である。
フロンは、1928年、GMの技術者トマス・ミッジリによって合成された。彼が、この物質を開発したのは、当時の冷蔵庫が持っていた欠陥を克服しようという明確な目的があった。
冷蔵庫を冷却するためには、適当な冷媒を気化させて気化熱を奪うのが一般的だが、この頃使われていた冷媒は、アンモニア・塩化メチル・二酸化イオウなどの有毒物質ばかりであり、冷蔵庫から漏れた冷媒によって、一家全員が中毒死するという悲劇も起きている。当時はまだ、冷蔵庫は一般家庭には普及していなかったが、これから多くの家庭で使用されるようになるはずの製品に有毒物質が含まれるというのでは、あまりに危険が多い。このため、毒性のない冷媒の開発が急がれていた。歴史的なエピソードとして有名な話だが、ともに天才的な物理学者として知られるアインシュタイン(若い頃に特許局で働いていたこともあって、発明に興味を持っていた)とシラード(当時は研究所助手で、研究費の不足を補うため特許使用料を欲していた)もこの問題に関心を持ち、新しいメカニズムに基づいて作動する冷蔵庫を案出して、共同で特許を取っている(もっとも、製造コストが高くつくため実用化はされなかった)。
ミッジリの研究は、彼らほど斬新なものではないが、化学的に安定な物質を冷媒として使用することによって冷蔵庫の安全性を高めようとする真っ当至極なものであった。周期律表を参照しながら研究を続けた結果、フッ素化合物こそ望む性質を有する物質であるとの確信を得、さらに研究対象をしぼって、遂にフロンへと到達する。その完璧なまでの無毒性に自信を持った彼は、公開実験で自らフロンガスを吸い込んで、安全性をアピールして見せた。
フロンの化学的特性
フロンに生体毒性がないのは、この物質が化学的にきわめて安定なことに起因する。多くの毒物は、生体内に侵入して何らかの化学反応をすることによって、その毒性を発揮する。例えば、一酸化炭素は、赤血球のヘモグロビンとの親和性が高く、肺でのガス交換の際に酸素より先に結合してしまうため、酸素運搬が阻害され脳の低酸素状態などを引き起こして中毒症状をもたらす。これに対して、フロンは化学的に安定で生体物質と結合しないので、直接吸い込んでも何の反応も起こさないまま吐き出される。フロン自体は、生物に対して直接的な悪影響を全く及ぼさないのだ。
化学的に安定だという特性は、単に生体毒性がないというだけではなく、工業的に応用する上で、次のような特長として現れる。
- 不要な化学反応を起こさない(洗浄剤として好都合である)
- 腐食性がない(フロン以前の冷媒はパイプなどを腐食する危険があった)
- 長期間の使用に耐える(冷蔵庫やエアコンなどの耐久財で使用できる)
- 不燃性がある(フロン規制後にスプレーで使用されているLPGに比べて安全である)
- 熱に対して安定で分解しにくい
PCBの項でも述べたように、「化学的に安定」な物質は、使用後に環境中に放出されると、いつまでも分解されずに残留する危険がある。すでに、1960年代に、PCBやDDTなど、残留性の高い化学物質による公害が広く知られるようになっており、フロンの潜在的危険性を指摘する声もないわけではなかった。しかし、化学者の大半は、「フロンは大丈夫だろう」という見方をしていた。何よりも、PCBやDDTと異なって生物に対して毒性が全くないため、環境中に蓄積されても生態系に何らかの影響を及ぼすとは考えにくい。さらに、フロンは気体なので大気中に拡散して十分に希薄になってしまい、生体濃縮を起こす心配もない。こうしたことから、フロンこそは、人類が造り上げた最も安全な化学物質だという認識が広まった。
化学的安定性に加えて、フロンには、次のような好ましい特徴がある。
- 加圧/減圧によって簡単に液化/気化する(液体としても気体としても利用可能)
- 無色・無臭である(スプレーで使用しても不快感を与えない)
- 不純物のない製品を合成できる(洗浄剤として使用できる)
こうしたフロンの有用性に気がついたデュポン社(アメリカ)は、権利を買い取って、1930年から「フレオン」という商品名で量産化に乗り出す。その思惑は見事に当たり、フロンは、冷蔵庫以外にもさまざまに利用されるようになり、20世紀の科学技術文明を支える重要な役割を果たすことになる。
フロンの用途
工業的に利用されるフロン(フロン11、フロン12など)は、次のようなさまざまな用途で使われていた。(括弧内は規制前の世界での頻度である)
- 洗浄溶媒(LSIやOA機器の洗浄、ドライクリーニングなどに使用)(19%)
- 冷媒剤(ビル空調用の大型装置や家庭用冷蔵庫、自動販売機、エアコン、カーエアコンなどに使用)(20%)
- 発泡剤(スポンジのような多孔質の樹脂の製造で利用)および断熱材(ポリウレタンフォームやポリスチレンフォームの内部に閉じこめて使用)(19%)
- スプレー噴射剤(ヘアースプレーや虫よけスプレーなどに使用)(25%)
日本では、半導体工場で洗浄用に用いられる割合が最も高かった。半導体はわずかでもホコリや不純物が残っていると不良品になりやすいので、丹念な洗浄が必要となるが、通常の水には、さまざまな不純物が溶け込んでいるので、洗浄剤としては好ましくない。また、多くの有機溶剤は可燃性物質で、工場で大量に使用するには危険性が伴う。これらに比べて、合成されたフロンには不純物がほとんど含まれず、化学的に安定で半導体基盤や金属・プラスチック部品を腐食することもない。さらに、表面張力が小さく僅かな隙間にも入り込む上、使用後は速やかに蒸発して後に残らないので、洗浄剤として理想的である。不燃・無毒なので安全性も高い。高品質の日本製半導体は、フロン洗浄なくしてはあり得ないと言われたほどである。
オゾン層と紫外線
環境に対するフロンの危険性が初めて科学的に指摘されるのは、1974年、アメリカのローランドとモリーナによって、成層圏のオゾン層を破壊するという警告が出されたときである。
オゾンは酸素原子が3つ結合した分子で、それ自体は、呼吸器の上皮細胞を傷害する有毒なガスである(「高原の空気にはオゾンが含まれていて健康に良い」という俗説は、真っ赤な嘘である)。地表付近には、排気ガスなどに含まれる“スモッグ”オゾンが多少ある(その増加は大気汚染として深刻な問題を引き起こす)だけだが、高度15〜35kmの上空では、多量のオゾンが層をなして存在している(上図)。これが、オゾン層と呼ばれるものである。
オゾン分子には、紫外線を吸収する作用があるため、オゾン層は、太陽から降り注がれる有害な紫外線を遮るバリアとなる(下図)。地球上で生物が繁栄していられるのは、この自然のバリアが存在しているからである。
紫外線は、細胞傷害性があり、特に、染色体上の遺伝子を傷つけ、生物の繁殖力を低下させたり、皮膚ガンを発症させる作用がある。強い太陽光を浴びると日焼けするのは、皮膚表面にメラニン色素を沈着させて、紫外線が体内深くまで侵入するのを防ごうとする生体防御反応の一種である。もしオゾン層が破壊されて紫外線が地表に降り注ぐようになると、次のような被害が発生することが予想される。
- 人間の健康 : 皮膚ガン、白内障、抗体異常の増加
- 農作物 : 不稔率の増加、病虫害に対する抵抗力の衰弱
- 水中の生態系 : 植物プランクトンの減少とこれに連なる食物連鎖系の崩壊
フロンによるオゾン層の破壊
フロンによるオゾン層の破壊が警告された当時、これを本気にする学者は少なかった。オゾンは成層圏で定常的に生成されているものである。大量のフロンが大気中に放出されているとは言っても、成層圏まで拡散していくのはごく僅かで、十分に希薄化されたフロンがオゾン分子を分解する程度では、オゾン層はびくともしないと考えられたのである。当時は、PCBをはじめ、人工的な物質による環境汚染に対する関心が高まっており、さまざまな物質に対して、勇み足気味に環境毒性を指弾する意見が次々と発表されていたので、学者の間でも「またか」という意識があったのかもしれない。また、オゾンの量が減少しているという報告も、どこからもなかった。
ところが、1985年に事態は一変する。イギリスの南極調査班がハレーベイ基地上空におけるオゾン層を測定したところ、春期オゾン層が7年間で40%以上も減少したことを発見したのである(下図;実は、日本の調査隊も、これより以前に同様の発見をしていたのだが、計器の故障を疑って発表をためらっているうちに、イギリス隊に先を越されたのである)。オゾンが極端に減少している領域(明確な境界を持つわけではない)は「オゾンホール」と呼ばれ、ここを通って南極の地表に達する紫外線量が増加していることは、近年の観測によって確かめられている。
人間が大量に使用しているとはいえ、自然界の大気の量と比較すると微々たるものにすぎないフロンが、なぜオゾン層を破壊することができるのか。そこには、科学者の予想を超えたメカニズムが作用していた。
化学的に安定なフロンは、大気の下層では光分解もせず水にも溶けないため、しだいに大気中の濃度が高まり、成層圏へと拡散していく。高度25〜35kmに達すると、さしものフロンも強力な紫外線を浴びて分解され、塩素原子(Cl)を放出する。この塩素原子は、オゾン(酸素原子が3つ結合したもの、O3)を次のような化学反応によって分解する。
Cl + O3 → ClO + O2
ただし、この反応だけで終わるならば、少量のフロンが少量のオゾンを分解するという、自然界にとってはさしたる影響もない些事で済むはずである。問題は、酸素と結合した塩素原子(一酸化塩素)が、極成層圏雲と呼ばれる雲に含まれる氷の結晶表面で、遊離酸素や別の一酸化塩素と反応して、また元の塩素原子に戻ってしまうことである。
ClO + O → Cl + O2
ここで自由になったClが再びオゾンを分解し、また酸素原子を離して自由なClに戻り……という過程をいつまでも繰り返すことになる。こうして、たった1個の塩素原子が、平均十万個のオゾン分子を、次から次へと分解していくのである。
化学的には、フロンから放出された塩素が触媒となって、それ自体は変化せずにオゾンを分解していくことになる。オゾンがいかに大量にあろうとも、これではたまったものではない。現在では、南極上空におけるオゾン層の減少が主としてフロンに起因することは、ほぼ確認されている。
なお、オゾンを殺菌などのために人工的に生成することは可能である(多くの工場からは公害物質としてオゾンが排出されている)ものの、生物に悪影響を及ぼさないように成層圏に機械を打ち上げて大量のオゾンを生成することは、技術的に困難である。
フロン対策の現状と将来
こうした事態に対して、紫外線をカットするメラニン色素が少ない白人を中心に、危機感が高まってきた。特に、南半球にあって白人の多いオーストラリアでは、深刻視されている。オゾン層破壊の効果がきわめて大きい「特定フロン」については、1989年に発効したモントリオール議定書によって、先進国では95年までに生産が中止されている。その効果が少しずつ現れ、大気中のフロン濃度は1999年頃をピークに減少傾向に転じた。特定フロンに代わってエアコンの冷媒や電子機器洗浄などに利用されている「代替フロン」の一部(HCFC)にも、特定フロンほどではないがオゾン層破壊の効果があるため、2020年までに廃止することが決まっている(最近では、特定フロン・代替フロンを併せて「フロン類」と呼ぶのが一般的である)。
しかし、事態は決して楽観できる状況にはない。現在進行中の二酸化炭素による地球温暖化の影響で、地表付近の温度が上昇する反動で南極上空の温度が低下し、その結果、氷の表面で化学反応が生じるオゾン層破壊の過程が促進されるため、フロン濃度が低下してもオゾンホールは拡大を続けると予想されている。1998年に国連環境計画・世界気象機関が発表した予測では、2020年頃にオゾンホールが最大になり、その後は回復に向かうものの、オゾンホールが消滅するのは2050年から21世紀末までになるとされている。さらに、特定フロンに代わって使い続けられる洗浄剤(PFCなど)や冷媒(HFCなど)の中には、地球温暖化を促進する効果が二酸化炭素の1万倍になるものもあり、オゾン層破壊とともに二重の環境破壊が続けられることになる。これらは、1998年に締結された京都議定書に従って段階的に削減されるはずだが、実際には、需要の高まりに応じて使用量は増大傾向にある。また、ノンフロン冷蔵庫の冷媒として使用される炭化水素(イソブタンなど)は、可燃性気体であるため、室内に漏れた場合には火災の危険が高まるという問題もある。
オゾン層破壊を少しでも和らげるためには、1995年以前に製造されたエアコンや冷蔵庫を廃棄する際に、その内部に封入されているフロンを適切に処理しなければならない。欧米諸国では、1990年代にフロン処理に関する法律が整備され、メーカーなどにフロン処理が義務づけられていたが、日本では法整備が遅れ、これまで大量のフロンが大気中に放出されるがままになっていた。1999年度の特定フロン回収率は、家庭用冷蔵庫27%、業務用エアコン56%、カーエアコン18%と低水準にとどまっている。こうした事態を改めるため、政府は、家電リサイクル法(2001年施行)・自動車リサイクル法(2004年施行予定)などを制定し、ユーザーの費用負担によってメーカーがフロンを回収することを義務づけた。例えば、家電リサイクル法によれば、ユーザーが冷蔵庫を廃棄処分するときには、処理費用(4600円+運送費)を支払って小売店経由でメーカーに搬送しなければならない。この費用が高すぎると不満を口にする人もいるが、大型冷蔵庫の場合、フロン回収などに手間が掛かるため処理には1万円程度を要しており、法律の趣旨に反して、費用をユーザーとメーカーが折半しているのが現状である。フロンの大量使用で豊かな生活を楽しんでいたら、後の世代にツケが回ってきた格好である。
安全な物質のチャンピオンと思われたフロンにして、この有様である。われわれは、安全と危険の基準について、根本的に見直すことを迫られているのかもしれない。
©Nobuo YOSHIDA