|
|
|
|
|
リサイクルに関しては、「リサイクルの現状と今後」を参照。
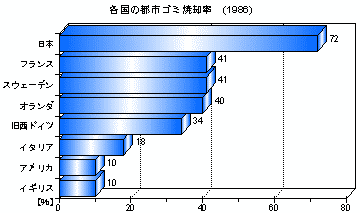 1970年代に世界で最も優れた脱硫技術を開発し、大気中のイオウ酸化物の大幅な削減に成功した日本が、なぜダイオキシン対策の面で欧米諸国に遅れを取ってしまったのか不思議な気もするが、発生源になっているのが世間の動向に疎く対応が遅い役所の管轄下にあるゴミ処理施設だったことに加えて、国民の間で、欧米ほどダイオキシンに対する恐怖感が強くなかったという事情が考えられる。1976年にイタリアのセベソで農薬工場が爆発してダイオキシンが周囲に飛散し、住民200人が皮膚炎を発症するなどの健康被害を受けたほか、ニワトリやウサギ数千匹が死ぬという事故が起きた。これをきっかけに、ヨーロッパではこの物質に対する反感が高まり、その後、ゴミ焼却場周辺でダイオキシン濃度が高くなっていることが判明して、焼却処理に反対する住民運動が盛り上がっていく。一方、アメリカは、1960年代のベトナム戦争の際に、密林に隠れるベトコンに手を焼いて、ダイオキシンを主成分とする「枯れ葉剤」を散布したところ、現地住民の間に奇形児の出産が相次ぐという結果を招いている。欧米が早くからダイオキシン対策を進め、プラスチックの焼却処理を抑制してきたのに対して、こうした恐怖体験を持たない日本では、90年代にはいるまで問題が看過されてしまったようだ。このことは、各国の都市ゴミの焼却率の差異に如実に現れている。
1970年代に世界で最も優れた脱硫技術を開発し、大気中のイオウ酸化物の大幅な削減に成功した日本が、なぜダイオキシン対策の面で欧米諸国に遅れを取ってしまったのか不思議な気もするが、発生源になっているのが世間の動向に疎く対応が遅い役所の管轄下にあるゴミ処理施設だったことに加えて、国民の間で、欧米ほどダイオキシンに対する恐怖感が強くなかったという事情が考えられる。1976年にイタリアのセベソで農薬工場が爆発してダイオキシンが周囲に飛散し、住民200人が皮膚炎を発症するなどの健康被害を受けたほか、ニワトリやウサギ数千匹が死ぬという事故が起きた。これをきっかけに、ヨーロッパではこの物質に対する反感が高まり、その後、ゴミ焼却場周辺でダイオキシン濃度が高くなっていることが判明して、焼却処理に反対する住民運動が盛り上がっていく。一方、アメリカは、1960年代のベトナム戦争の際に、密林に隠れるベトコンに手を焼いて、ダイオキシンを主成分とする「枯れ葉剤」を散布したところ、現地住民の間に奇形児の出産が相次ぐという結果を招いている。欧米が早くからダイオキシン対策を進め、プラスチックの焼却処理を抑制してきたのに対して、こうした恐怖体験を持たない日本では、90年代にはいるまで問題が看過されてしまったようだ。このことは、各国の都市ゴミの焼却率の差異に如実に現れている。
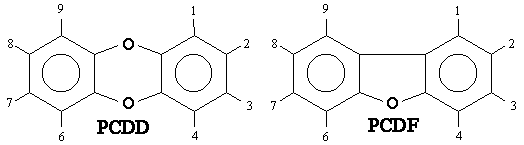
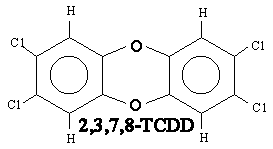 塩素の付き方によって多数の異性体が存在し、毒性も大きく異なるが、最も毒性が強いのが、図の2,3,7,8の位置に対称的に塩素が付いた2,3,7,8四塩化ジベンゾパラジオキシン(2,3,7,8-TCDD)で、他のダイオキシンの毒性は、この物質の何倍になるかという毒性等量を使って表す。報道などで見られる「ダイオキシンの量」とは、ダイオキシンの各異性体の量に、この毒性等量を掛けて足しあわせたものである。
塩素の付き方によって多数の異性体が存在し、毒性も大きく異なるが、最も毒性が強いのが、図の2,3,7,8の位置に対称的に塩素が付いた2,3,7,8四塩化ジベンゾパラジオキシン(2,3,7,8-TCDD)で、他のダイオキシンの毒性は、この物質の何倍になるかという毒性等量を使って表す。報道などで見られる「ダイオキシンの量」とは、ダイオキシンの各異性体の量に、この毒性等量を掛けて足しあわせたものである。
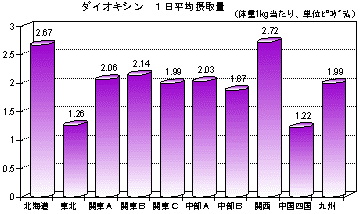
| 焼却炉排出規制 | 大気・土壌中の指針 | 食品基準 | 許容摂取量 | |
| 日本 | 100-5000(新設) 1000-10000(既設) |
大気0.8 土壌1000(住宅地) |
なし | 4 |
| オランダ | 100 | 土壌 10(放牧地) 1000(住宅地) |
6(乳製品) | 1(提案中) |
| 米国 | 100-300(新設) | 土壌1000(住宅地) | なし | 0.01(提案中) |
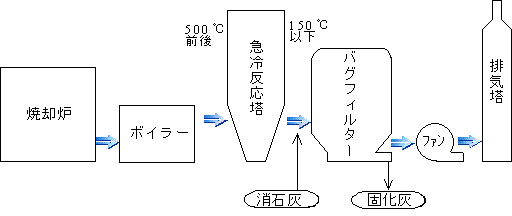
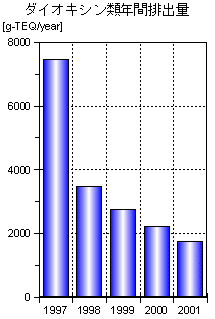 ゴミ焼却施設で対策を推し進めた結果、ダイオキシンの排出量は確実に減少している。年間排出量は、1997年には7348-7602グラムだったものが、2001年には1743-1762グラムに減っており(環境省報道発表資料より)、廃棄物処理法の改正などで排出削減を進めた効果が現れたと見られる。このペースでいけば、2003年3月までに1997年比で90%減らすという目標は達成確実である。ただし、この値は、年に1回、焼却炉が安定稼働してから測定するという国の基準に沿ったものであり、炉内が低温になって不完全燃焼したときに発生するダイオキシンの量を正しく表しているか、疑問視する向きもある。また、ダイオキシン規制を推進した結果、基準を達成できない多くの焼却施設が廃棄処分されるが、その内部に残されているダイオキシンの処理が適正に行われるという保証はない。
ゴミ焼却施設で対策を推し進めた結果、ダイオキシンの排出量は確実に減少している。年間排出量は、1997年には7348-7602グラムだったものが、2001年には1743-1762グラムに減っており(環境省報道発表資料より)、廃棄物処理法の改正などで排出削減を進めた効果が現れたと見られる。このペースでいけば、2003年3月までに1997年比で90%減らすという目標は達成確実である。ただし、この値は、年に1回、焼却炉が安定稼働してから測定するという国の基準に沿ったものであり、炉内が低温になって不完全燃焼したときに発生するダイオキシンの量を正しく表しているか、疑問視する向きもある。また、ダイオキシン規制を推進した結果、基準を達成できない多くの焼却施設が廃棄処分されるが、その内部に残されているダイオキシンの処理が適正に行われるという保証はない。
©Nobuo YOSHIDA