
これは、簡単には答えられない問題です。物理学の範囲は広範で、既知の公式を使ってコンピュータによるシミュレーションを繰り返すような分野から、数学的な能力よりも物理的な直観(それが何であるかはうまく言えませんが)を用いてモデルを構築する分野まで実にさまざまであり、各分野に応じて異なる能力が要求されます。強いて言えば、一つの目的に向かってたゆまずに研究を続ける持久力と、自分の立てた仮説が間違いだと気がついたときにそれを放棄できる潔さが必要でしょう。しかし、これは、物理学に限らず全ての学問(あるいは全ての仕事)に必要とされる能力かもしれません。
ミチオ・カクの“パラレルワールド”の話に興味を持ったとありますが、この分野の研究は、お勧めできません。この手の話は、誰かが専門的に探究しているというよりは、最先端理論を扱う素粒子物理学者が、一般人向けに研究成果をおもしろおかしく紹介しようとしたものが多く、必ずしも信憑性が高くありません。物理学者が思い描くパラレルワールドにはいくつか種類があり、ミチオ・カクが扱っているのは、究極の理論とされるM理論が予言する未知の次元に関するものですが、これも、M理論に対する少数の支持者(と言うより信者)だけが問題にしているマイナーな主張です。このほか、宇宙の多重生成や量子力学の多世界解釈などもパラレルワールドと絡んでいますが、これらに関しては、まだ定説が確立されていないというのが現状です。しかも、こうした理論を研究するには、ド難しい(M理論などは論文を読んでいるとひきつけを起こしそうになるほど難しい)数学の知識が要求されるので、業績を上げられるのは、ほんの一握りの超秀才(あえて天才とは言いません)だけです。多くの研究者が、あまりの難しさに頭脳を消耗したあげく、他の分野への転身を余儀なくされています。当事者たちはさまざまな成果が上がっていると主張していますが、少し冷静になって省みると、ここ数十年間でめぼしいと言える成果はごくわずかしかありません。学問としては、完全に停滞している分野なのです。
近年、学問的に進歩が著しいのは、これまで数学的手法の適用が難しいとされてきた複雑なシステムについての研究です。複雑なナノ構造を持つ新素材の物性や、超臨界状態にある液体の研究など、おもしろい発見が続いています。また、究極の課題として、生命や脳を物理学的に解明するというテーマもあります。こうしたホットな研究についても目を向けられてはいかがでしょうか。
【Q&A目次に戻る】

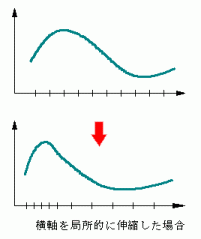
確かに、自然界に数学的な意味で無限小・無限大となる量は存在しないでしょう。しかし、だからと言って、無限を用いない数学理論を使えばうまくいくというわけではありません。
物理学で利用される実数体(あるいは複素数体)は、スケールを変換しても数学的な性質が変わらないという特徴を持っています。実数には 1.23… のように数値が割り振られていますが、この値を全て2倍や1/2にしても、あるいは数直線の一部分だけ(なめらかに)引き延ばしたり押し縮めたりしても、その上で定義された関数の微分可能性などの性質は変化しません。この「伸縮自在」という特徴のおかげで、物理学の記述はずいぶん簡単なものになっています。例えば、弾性体の振舞いを定式化するときに、結晶構造のような素材の細部について考慮する必要はありません。実数体に基づく理論を採用した段階で、スケールを伸縮させても物質定数が変わるだけで物理法則は変化しないことが暗黙の前提となっているからです。実数を用いた定式化が良い近似になっているという事実は、物理現象が、ある範囲のスケール変換に対して、ほぼ不変である(人間のスケールと原子・分子のスケールの間に何桁もの開きがある)ことに由来しています。
実数の伸縮自在性は、「どこまでも引き延ばせる(押し縮められる)」という形で、理論の中に無限の概念を忍び込ませます。しかし、これはそれほど深刻な問題ではありません。ちょうど、弾性体の理論を原子サイズの現象にまで当てはめるのが無理なように、どの理論にも有効範囲というものがあり、教科書には、その範囲を逸脱しないように一種の“注意書き”が記載されているからです。有効範囲を逸脱した領域を扱いたいときには、新たな理論を構築すれば良いのです(ここでは、相転移領域での比熱の発散のような定義の仕方に依存する形式的な無限大は論じません)。
場の量子論(素粒子論)には、短距離極限での相互作用に起因する「紫外発散の困難」があると言われています。しかし、これも有効範囲を逸脱したときにだけ表面化するもので、必ずしも深刻な困難とは見なされません。紫外発散とは、間隔が無限小になる領域まで相互作用を計算したときに現れる無限大のことですが、標準的な場の量子論に関しては、狭い領域での相互作用をひっくるめて物理定数の中に取り込んでしまう「くりこみの技法」が確立されており、長距離領域では無限大が現れないようにできるからです(古い教科書の中には、「くりこみ」を「無限大から無限大を引いて有限にする技法」として紹介しているものもありますが、これは誤りであり、1960年代に有限量だけを使ってくりこめることが証明されています)。もちろん、実際に短距離の極限でどのような現象が起きるかを既存の場の量子論で解明しようとしても、紫外発散のせいでどうしても行き詰まってしまいます。ただし、この問題を回避するためには、場の量子論を超える新しい理論を作らなければならないのであって、数学的に無限の扱いを変更することによって何とかなるものではないはずです。
無限大が現れない数学を利用する方法も、あることはあります。例えば、場の量子論では、時間・空間を実数体ではなく(結晶のような)格子で表す格子ゲージ理論が知られています。これを使うと、短距離極限といったものは存在せず、微分も差分に置き換えられるので、計算に無限大が現れることはありません。しかし、時空を格子化したことによって、光速が結晶軸の方向とそれ以外の方向で異なるといったさまざまな問題が持ち上がります。これを修正するのは、そう簡単なことではありません。そもそも、格子ゲージ理論とは、コンピュータ計算を行うためのモデルであって、現実の世界が格子状になっているとは(ごく一部の例外を除いて)誰も考えていません。
このほか、無限小・無限大を極限ではなく1つの数として扱うノンスタンダード・アナリシス(超準解析)を場の量子論に応用しようとする試みもあったようですが、成功を収めたという話は聞いていません。
現実の世界は、実数に見られるようなスケール変換に対する不変性を持っていないのでしょうが、それではどのような数学的構造をしているかは今もって全く不明ですし、これまで考案された数学理論で近似的に表せるようなものではないように思われます。
【Q&A目次に戻る】

航空機が飛ぶのは、翼の周りに生じる空気の流れによって揚力が発生するからです。最近、こうした科学的説明にクレームを付ける議論が見受けられます
(竹内薫著『99・9%は仮説』(光文社)などを参照)が、これは、従来の説明の誤りを指摘したというよりも、ベルヌイの法則を安易に援用することに対して警鐘を鳴らすものと言えるでしょう。ベルヌイの法則とは、流体におけるエネルギー保存則と言っても良い法則で、簡単に言えば、「流速が大きいほど圧力が低い」というものです。この法則を使って航空機が飛ぶ理由を説明すると、「翼は上に凸の形に湾曲しており、翼を通過する滑らかな定常流がある場合、上面で流れが速く下面で遅くなっているので、下から上に押し上げる圧力の方が強くなって揚力が作用する」となります。この説明自体は間違っていないのですが、問題は、これを、「翼の上面では下面より流速が速くなる」→「だから、揚力が作用する」という因果関係として解釈してしまいがちなことです。ベルヌイの法則は、「流速の違いが圧力の差を生み出す」という原因と結果の関係を述べているのではなく、「流速と圧力の間には一定の関係がある」ことを示しているにすぎません。そもそも、翼の上面で流れが速くなることは自明ではなく、説明を要する現象です。揚力の発生で重要なのは、翼の周囲でどのような流速分布になっているかという点であり、ベルヌイの法則を使ってわかった気になってはいけない−−というのが、この議論の教訓でしょう。
物体の周りの流れは、理論的には、流体の運動に関するナヴィエ=ストークスの方程式を適当な境界条件の下で解けばわかるはずです。しかし、この計算は容易ではありません。物体を通過する流れがある場合、表面の摩擦によって流体が引きずられ、その結果として、解析の難しい乱流(不安定な乱れた流れ)が発生するからです。乱流は、フラッター(振動)などを引き起こし、安定な飛行を妨げる好ましくない現象でもあります。コンピュータによる数値計算では、乱流が生じる臨界条件はわかっても、発生した乱流がどのような影響を及ぼすかを正確に求めることはできないのです。こうした(実用上および計算上の)乱流の問題を回避するため、流体中を高速で移動する機体は、先端部が丸く膨らみ後部で滑らかに細くなるような形−−いわゆる流線型に設計されるのが一般的です。航空機の翼の断面も流線型をしており、乱流は後端のごく狭い領域に限られます。ベルヌイの法則を用いた揚力の説明は、乱流の影響が小さく、翼の周りに流速に差のある滑らかな流れがある場合にだけ使えるものです。
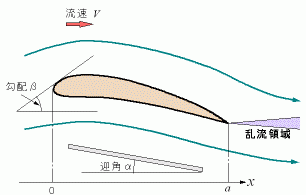
こんにちでは、滑らかな流れが生み出す揚力はコンピュータを使って計算できますが、いくつかの近似を採用すれば、一定の断面を持つ翼に作用する揚力を簡単な式で表すことができます。流体の密度をρ、全体の流速(静止した流体中を動いている翼の速度としても良い)をV とすると、単位長さあたりの揚力F は、
F = ρV (Γ
1 - Γ
2)
で与えられます(ジューコフスキーの定理)。ここで、Γ
1 は、流体の速度を翼の上面に沿って積分した値、Γ
2 は下面に沿って積分した値で、積分路は、物体に引きずられる境界層から少し離れた地点で、翼の後端に生じる乱流領域を除くように選びます。流速の大小から揚力が求められていることでわかるように、この式は、ベルヌイの法則と密接な関係があります。さらに、翼が薄いなどいくつかの仮定を置くと、
Γ
1 - Γ
2
= - V ∫dx (β
1(x)+β
2(x)) (x/(a-x))
1/2
と求められます(求め方は、流体力学の教科書を読んでください)。β
1,2は翼の上下面の勾配、積分範囲は0 からa までです(x座標の取り方は図の通り)。面白いことに、この式によると、翼の断面は上に凸の曲線である必要はなく、薄い平らな板が流れに向かうような傾き(迎角)αになっているだけで、揚力
F = παaρV
2
が発生することがわかります(上下で流速に差があるので、ベルヌイの法則を使った説明も可能です)。もっとも、この近似が成り立つのは、板の先端が丸く後端が尖った流線型になっていて、乱流の影響が小さい場合に限られます。迎角が少し大きくなるだけで、流れを先端の小さな丸みで受け流すことができなくなり、乱流領域が大きくなって、上の近似は破綻してしまいます。平らな翼で飛ぼうとしても、すぐに失速して墜落するわけです。通常の翼は、先端部の丸い領域が大きく、全体として表面が後ろに傾むくように、前寄りの位置に凸部がある曲面として設計されています。この形状だと、乱流が発生しにくいことに加えて、Γの計算でプラスの寄与を与える範囲が大きくなり、プラスの迎角を持つことと等しくなります。
このように、翼の周囲に生じる流れとそれが生み出す揚力は、乱流の発生が抑えられているという条件下で、かなり正確に計算できます。ただし、翼長が有限で細かな凹凸を持つ現実の翼で、実際に乱流の影響が小さくなるかどうかは、そう簡単にはわかりません。また、こうした議論は、あくまで乱流が抑制されている場合にどのような定常流が存在するかを示すもので、流れが変化する際のダイナミックな過程は、必ずしも解明されていません。航空機の設計において、コンピュータによる計算だけではなく、巨大な風洞を用いた実験が欠かせないのは、そのためです。こうした状況を、「しっかりと説明ができていない」と呼ぶかどうかは、好みの問題です。
【Q&A目次に戻る】

脳に微小電極を刺し込んで電気刺激を与え、反応を観察するという実験は、現実に行われています。ただし、大半は、ラット・ネコ・サルなどの動物を用いた実験です。人間の脳に電気刺激を与えるのは、脳神経系疾患に対する治療目的に限られています。パーキンソン病(運動を司る神経細胞の変性・脱落によって生じる)の治療のために電極を持つ脳刺激装置を埋め込む外科手術を行うケースなどがそれで、脳刺激装置の位置が適正かどうかを確認するために、手術中にモニター用電極を刺し込んで刺激に対する反応を見るといった作業が繰り返されます。こうした実験は、当然のことながら、あくまで治療本位であり、患者本人の同意を得て行います。以前には、研究目的で脳のあちこちに電気刺激を与える実験が行われたこともありましたが、健康被害が生じる心配があるため、最近では、治療に必要でない部位にブスブスと電極を刺すことは控えられています。
脳への電気刺激が臨死体験ないし幽体離脱に似た感覚をもたらすことは、側頭葉てんかんの患者を対象とした実験で示されています(O.Blanke et al., Nature 419 (2002) 269 )。これは、てんかん治療のために脳の一部を切除する前に、切除部位が言語中枢でないことを確認するために行った作業で、シルビウス裂の周辺にある角回に電極を刺入して電気刺激を与えた後、言語機能(物品呼称や復唱など)の評価を行うというものです。このとき、言語機能評価とは別に、患者の主観的体験が報告されました。それによると、2〜3mAの刺激に対しては、「ベッドに沈んでいく」「高所から落下する」といった感覚が生じ、刺激を3.5mAにすると、「自分自身がベッドに横たわっているのを上から見ている」と答えたそうです。ただし、見ることのできない自分の顔を視認したのではなく、(上から見下ろしているはずなのに)確認できるのは下半身だけだったということです。つまり、実際に幽体離脱をしたのではなく、知覚情報と身体像の関係を適切に結びつけることができなくなった結果だと解釈されます。
こうした報告は数が少ないので、直ちに臨死体験などに関する明確な主張が行えるわけではありません。上の(擬似)幽体離脱体験にしても、側頭葉てんかんの患者に特徴的なものか、健常者にも見られる現象かは、まだわかっていないのです。しかし、脳の電気刺激によって主観が変容する可能性があることだけは、ほぼ確実な事実だと言えるでしょう。
【Q&A目次に戻る】

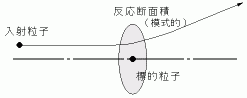
加速される粒子自体はきわめて小さいのですが、ビームを正確に制御することによって反応が起きる確率を高めています。
粒子同士の衝突実験では、一方の粒子から見て、相手の粒子を中心とするある円内に入るように近づいたときに、粒子間の反応(電子−陽電子の対消滅反応や中性子による原子核の核分裂反応など)が起きると考えることができます。この円の面積を反応断面積と言います(正確に言うと、反応後に粒子がある方角に飛び去る割合として微分断面積を定義し、これを積分して断面積を求めるので、反応が起きる範囲が幾何学的な円になるわけではありません)。
加速器実験には、静止している標的にビームを照射する場合と、ビーム同士を交差させる場合があります。ここでは、後者のケースを考え、2つのビームをビーム1、ビーム2と呼ぶことにしましょう。ビーム1(粒子数N
1)に属する粒子からビーム2(粒子数
2)を見ると、ビームの断面積A の中に反応断面積σを持つ粒子がN
2個存在しているように見えます。反応断面積の部分に粒子が入れば反応が起きるのですから、1回の衝突でビーム1内の1個の粒子がビーム2内の粒子と反応する確率は、N
2σ/A 、反応の総数は、
N
1N
2σ/A
で与えられます。サイクロトロンのようなリング状の加速器では、ビームをリング内で周回させて何度も衝突させるので、上の値に1秒あたりの衝突回数fを乗じた
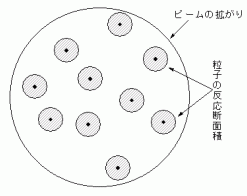
fN
1N
2σ/A
が1秒あたりの反応数になります。この式で、反応断面積σは、反応の種類によって決まります(一般に衝突エネルギーの関数になります)。σの係数になる
L = fN
1N
2/A
はルミノシティと呼ばれ、加速器の性能を表す指標になります。ルミノシティを向上させるには、(1)ビーム断面積A を小さくする、(2)粒子数 N
1、N
2 を大きくする、(3)衝突回数f を大きくする−−という方法があります。
高エネルギー加速器研究機構のKEKB加速器は、加速した電子と陽電子を衝突させてB中間子とその反粒子をたくさん作り出す装置ですが、そのルミノシティは、世界最高レベルの10
34[/cm
2s] に達しています。この高いルミノシティは、次のような技術によって実現されました:
- 電子と陽電子のビーム(KEKB加速器では、リング全周にわたって数メートルおきにバンチと呼ばれる粒子集団となっている)の拡がりは、縦2ミクロン、横100ミクロンと小さく(長さは7ミリ程度)、これを0.5ミクロン以下の誤差で正確に衝突させている。
A = 2×10-6[cm2]
- 1つのバンチは、電子または陽電子を500〜700億個含んでいる。
N1N2 = 3.5×1021
- バンチは1周3kmのリングをほぼ光速(秒速30万km)で周回しているので、毎秒10万回の割合で衝突ポイントを通過する。リング全体で1000個以上のバンチが連なっており、衝突ポイントではこれらが次々と衝突するので、
f = 108[/s]
となる。
- 電子(陽電子)同士の相互作用などによって軌道が不安定になるため、実際のルミノシティは、公式よりやや小さい値になる。
L = 1034[/cm2s]
このようにルミノシティL はきわめて大きな値になりますが、電子と陽電子が対消滅してハドロン(核子・中間子などの総称)になるときの反応断面積が 10
-33〜10
-32cm
2 程度であり、KEKB加速器の目標であるB中間子が生成される反応は1秒間に数回しか起こりません。
【Q&A目次に戻る】

質問にあるのは、ベンジャミン・リベットが行った古典的な認知心理学の実験のことでしょう。この実験では、脳波計を装着した被験者は、次のような指示を受けます:
- 決められた時間内の任意の瞬間に簡単な動作(ボタンを押す、指を曲げるなど)を行う。
- 動作を行おうという心の動きを感じた瞬間に、目の前に置かれたオシロスコープの画面でドットがどの位置にあるか覚えておく。
オシロスコープのドットは一定の角速度で回転しているので、報告されたドットの位置から、被験者が動作しようと感じた時刻がわかります。平均すると、この時刻は実際に動作を開始した時刻の200ミリ秒前でした。ところが、脳波計の記録を調べると、動作開始の500ミリ秒前に大脳皮質の運動野で電位変化が始まっていたことが判明しました。動作だけでなく意識にも先立つこの電位は、準備電位(readiness potential )と呼ばれています。
この実験結果は、何を意味しているのでしょうか。「自由意志は存在しない」という乱暴な結論もあり得ますが、最も簡単な解釈は、「意志決定の初期過程は意識化されない」というものです。意識は脳で行われている膨大な情報処理のごく一部しか含んでいないので、意志決定に関与する神経活動の中に意識されない過程が含まれていたとしても、何ら不思議なことはありません。
指を曲げるといった簡単な動作の場合、意志決定を行う神経活動の大部分が無意識下でなされていることは、自分の行動を注意深く観察していれば、ごく当たり前の事態だと気がつくはずです。人間は、指を曲げるという決定を意識的に行うことはできません。自分の指に向かっていくら「曲がれ、曲がれ」と念じても曲がることはなく、指を曲げようという気持ちになったときに、自然に曲がるのです。どうして指を曲げようという気持ちになったかがわかるほど、人間の意識は支配的ではありません。
意識は、脳による情報制御の所産だと言っても良いでしょう。無意識的に決定された行動プランは、単に随意筋を動かすための指令として投射されるだけでなく、感覚器官から逐次入力される外部情報や、新たに想起された学習記憶などと突き合わされ、リアルタイムで修正されていきます。こうした行動プランの修正過程が意識の主要部分になっている−−というのが私の考えです。単純な動作の場合、意識は、常に行動プランの決定よりも遅れた事後的なものになります。しかし、(手を伸ばしノブをつかみドアを開けるといった)一連の目標を段階的に達成していく複雑な行動では、次の段階に入る前にフィードバック的に行動プランを修正しなければならないため、意識が動作に先行するようになります。こうした動作が、意志に基づく主意的な行動として自覚されるのです。
ただし、脳における神経活動と主観的な意識の関係は、今なお充分に解明されているとは言えません。最近では、fMRI(機能的磁気共鳴映像法)によって脳内の血流量や酸素代謝率の変化がリアルタイムで測定できるため、脳のどの部分が活性化しているか、時間を追って調べることが可能になっていますが、まだ時間的な解像度が低く、いかなる神経活動が意識の内容を作り上げているかは、今後の研究にゆだねられています。
ところで、意識されようとされまいと、人間の行動が物理法則に縛られていることには、変わりありません。しかし、だからと言って、われわれがどのように行動するかが、宇宙開闢の瞬間に決まっていたというわけではありません。陰極から放出された1個の電子の運動ですら、量子力学の不確定性ゆえに、初期条件だけで確定することはできないのです。まして人間の場合は…。デカルトの時代には、「物理法則に従う」とは「時計仕掛けのように動く」ことだと誤解されていたので、人間の価値を保証するために、物理法則に縛られない何かが必要だと考えられました。しかし、現在の科学的知識によれば、物理法則は意外なほどルースであり、人間の自由と相反するものではありません。
この質問に関連する内容は、「意志と行為の時間関係」および「意識とは何か−制御論的アプローチ」でも取り上げています。
【Q&A目次に戻る】

科学に「証明されるべき説」などありません。科学における学説の正当性(学説の正しさ)は、その学説が有効であると実証することによってのみ示されます(ここで、「有効性」とは、他の理論よりも正確に実験・観察のデータを予測できる、あるいは、より少ないパラメータによって同程度の予測を行える−−といったことです)。信頼できる学説がまだ確定していない最先端分野において、新しい学説を創造する独創性のない大多数の科学者たちが行っているのは、データとの比較や他領域への応用を通じて、どの理論が有効かを検討する作業です。現在のように大学でも企業でもシビアな業績評価が行われている状況下で、有効かどうかもわからない新理論を反証しようと考える能天気な科学者はいないでしょう。誰かが「自分の学説は、まだ有効性を実証する段階にはないが、究極的な真理だと信じる。間違っていると思うなら、反証してみたまえ」という態度を取ったとしても、単に無視されるだけです。
新理論に対する反論がどのように行われるか、具体的な例を通じて見ていきましょう。
1980年にアルヴァレらは白亜期末に恐竜が絶滅した原因として、直径10kmほどの小惑星が衝突して気候が激変したという新しい学説を提唱しました。これは、それまで支配的だった「漸進的な変化によって恐竜は絶滅した」とする学説と真っ向から対立するものだっただけに、大きな反響を引き起こしました
(詳しくは、「科学の回廊」−「アルヴァレらによる恐竜絶滅の新説はなぜ受容されたか?」を参照してください)。このとき、反対者たちが行ったのは、アルヴァレらが自説の有効性を実証すると考えた根拠に対して、批判を加えることでした。
小惑星衝突説の根拠になったのが、白亜紀と第三紀の地層の境界に、イリジウムを地表の平均値より有意に多く含有した薄い層が存在することです。アルヴァレらは、隕石には地表よりも多量のイリジウムが含まれることから、この境界層が、地上に激突して砕け散った隕石に由来するものと考えました。これに対して、衝突説に反対する科学者の一部は、キラウエア山のように地中深くからプリュームが上昇してくる火山ではイリジウムを多く含んだ溶岩が噴出することを指摘し、白亜期末に火山の大噴火があったとすると境界層の存在を説明できると主張しました。また、別の反対者グループは、アルヴァレらが陸生・海生の動植物の過半が小惑星衝突直後の短期間のうちに絶滅したと論じているにもかかわらず、白亜期末に向かうにつれて恐竜の種類が漸減している(ケラトプス類ばかりが増えている)こと、あるいは、境界層の上からもアンモナイトの化石が見つかっていることを指摘しました。これらの批判に対しては、衝突説に賛同する科学者から再反論が提出されています。
多くの場合、新しい学説に対する反論は、有効であるという根拠に対する批判(データが誤っている、別の学説によってもデータを説明できる、新学説では説明できないデータがある)を通じて行います。こうした反論が決定的ならば、学説は反証されたことになります。逆に言えば、有効性が示されていない学説に対しては、反論しようがありません。新しい学説を考案したのに誰も目を留めてくれないと嘆くアマチュア学者がいますが、そうした結果になるのは、往々にして有効性の根拠が薄弱だからです。
【Q&A目次に戻る】

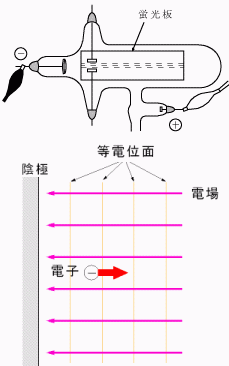
その実験で使われたのは、おそらく右図のような「放電管」だと思います。このマイナスの電極(陰極)から電子が放出され、管の内部をほぼ直進し、最終的にはプラスの電極(陽極)に到達します。
電子が陽極に向かって進まずに、図の真横に向かうのは、電子を加速する電場が陰極板に対して垂直になっているからです。金属のような導体が帯電した場合、その周辺の電場は導体表面に対して垂直な向きになることが知られています(等電位面は導体表面と平行です)。電子に比べると陰極板は無限大の平面と言っても良いので、陰極の近くでは、電場は陰極板に垂直にまっすぐ伸びていると見なせます。この電場から力を受けて加速されるので、電子は短時間のうちに陰極板に垂直な向きに猛烈なスピードで運動するようになります(単純計算によると、1Vの電位差で秒速600kmまで加速されます)。陰極から充分に離れたところでは電場は陽極に向かって曲がっていますが、その位置では、電子はすでに巨大な運動量を持っているので、運動方向をそらされるような力を受けても、軌道の向きはほとんど変わりません。ちょうど山頂から勢いづいて転がってきた岩が、少々のでこぼこも乗り越えて突進していくように、電子も放電管の内部をほぼ直進するのです。この電子は、そのまま反対側のガラス壁に激突して運動量を失い、そのままガラスに沿って陽極まで移動していきます。
極性を入れ替えたときにどのように電子が運動するかは、新たな陰極の形によって決まります。陰極が平面板と見なせる場合には、電子は表面に対して垂直に加速され、そのまま直進していきます。
【Q&A目次に戻る】

北極海を覆っている海氷は、たとえ全部溶けたとしても、アルキメデスの原理に従って、それまで排除していたのと同じ質量の水になるだけなので、海面上昇には寄与しません。溶けると海面上昇につながるのは、主に、南極大陸とグリーンランドにある氷床(陸地を覆う巨大な氷の層)です。スカンジナビア半島やカナダにある氷河も寄与しますが、ヨーロッパや北米の大陸氷河の大部分は前の氷河期が終了した1万年前までに溶けてしまったので、大した分量ではありません。地球温暖化による海面上昇を議論するときには、南極とグリーンランドの氷を総称して「極地の氷」と呼んでいます。これらの氷が全て溶けると、海面は72m上昇するとされていますが、そのうち65mが南極の氷、7mがグリーンランドの氷の寄与です
(環境省の資料より)。
実は、地球温暖化によってどの程度の海面上昇が起きるのか、現在なお、はっきりとはわかっていません。過去100年間に地球の平均気温は0.6℃ほど高くなり、これに伴って海面が10〜25cmほど上昇していますが、これは、極地の氷が溶けたためではなく、温度上昇による海水の膨張と、アルプスなどの小規模氷河の溶融が、ほぼ半々に寄与した結果だと考えられています。今後の気温上昇によって、極地の氷も少しずつ(数千年かけて)溶けていきますが、その一方で、海水面からの水の蒸発が盛んになり極地に降り積もる雪の量も増すため、南極の氷床は、しばらくの間は増大すると考えられます。実際、人工衛星を利用して氷床の動きを観測すると、西南極大陸で動きが遅くなっており、氷が厚く成長していることが示唆されます。ただし、南極半島の棚氷(陸地から海上に張り出した氷)の崩壊が予想以上のスピードで進んでいるとの報告もあり、氷床の変化には不明な点がいろいろと残されています。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、21世紀末までに、水の膨張を主たる原因として15〜95cm程度の海面上昇があると予測しています。この数値自体にもかなりの幅がありますが、この予測がさらに大きくはずれる可能性もあります。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
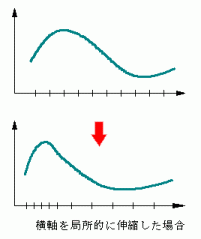 確かに、自然界に数学的な意味で無限小・無限大となる量は存在しないでしょう。しかし、だからと言って、無限を用いない数学理論を使えばうまくいくというわけではありません。
確かに、自然界に数学的な意味で無限小・無限大となる量は存在しないでしょう。しかし、だからと言って、無限を用いない数学理論を使えばうまくいくというわけではありません。
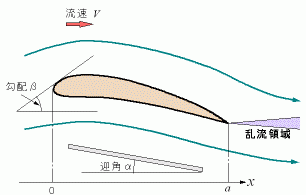 こんにちでは、滑らかな流れが生み出す揚力はコンピュータを使って計算できますが、いくつかの近似を採用すれば、一定の断面を持つ翼に作用する揚力を簡単な式で表すことができます。流体の密度をρ、全体の流速(静止した流体中を動いている翼の速度としても良い)をV とすると、単位長さあたりの揚力F は、
こんにちでは、滑らかな流れが生み出す揚力はコンピュータを使って計算できますが、いくつかの近似を採用すれば、一定の断面を持つ翼に作用する揚力を簡単な式で表すことができます。流体の密度をρ、全体の流速(静止した流体中を動いている翼の速度としても良い)をV とすると、単位長さあたりの揚力F は、
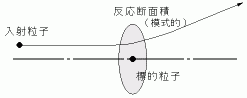 加速される粒子自体はきわめて小さいのですが、ビームを正確に制御することによって反応が起きる確率を高めています。
加速される粒子自体はきわめて小さいのですが、ビームを正確に制御することによって反応が起きる確率を高めています。
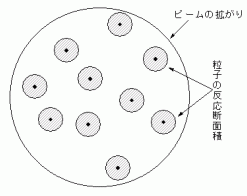 fN1N2σ/A
fN1N2σ/A
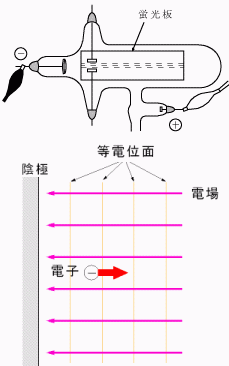 その実験で使われたのは、おそらく右図のような「放電管」だと思います。このマイナスの電極(陰極)から電子が放出され、管の内部をほぼ直進し、最終的にはプラスの電極(陽極)に到達します。
その実験で使われたのは、おそらく右図のような「放電管」だと思います。このマイナスの電極(陰極)から電子が放出され、管の内部をほぼ直進し、最終的にはプラスの電極(陽極)に到達します。