|
|
|
|
|
相対論が時間と空間についての古典的な見解を根本から覆したのに対して、物質の概念に変革を迫ったのが、場の量子論である。物質概念は、文化圏ごとに大幅に異なっているが、ヨーロッパ近代の自然観によると、物質とは、空間の中に自立的に存在し、同じ場所に同時に2つの物体が存在できない「相互不貫入」という性質を持つとされていた。さらに、ニュートン力学では、「指向性」のような内在力の概念を排し、物質と力を峻別することによって、物質は外部から(非物質的な)力を受けて運動するという基本的なテーゼが確立された。しかし、こうした物質概念は、19世紀に発達した電磁場の理論によって重大な修正を受け、20世紀の場の量子論によって根本的に書き換えられることになる。現代科学では、物質と力は場の相互作用という概念によって統合されており、将来的には、相対論的に統一された時空と一体化させられると期待されている。
ここでは、量子論に関する教科書的な知識を前提として、必ずしもオーソドックスでない定式化を試みる。
この節の議論は専門的な知識を踏まえて進められているので、初学者は、強調文字で書かれている要点だけをピックアップしながら、立論の方向性だけでも掴むようにして頂きたい。
【要約】 非相対論的な量子力学における概念的混乱は、理論が未完成であることに由来する。科学哲学的な観点から「物質とは何か」を考察するためには、場の量子論を援用しなければならない。
1920年代半ばに構築された(非相対論的な)量子力学は、現在なお、物質の振舞いを記述する理論として不動の地位を占めている。
しかし、この理論は、原子核や物性などの応用分野で驚異的な成功を収めているにもかかわらず、「物質とは何か」という基本的な問いかけに答えてくれるものとは言い難い。何よりも、理論を記述するに当たってしばしば古典的な概念を利用するため、電子を点状の粒子として導入しながら、その位置と運動量が不確定になるというような不可解な主張を行うことになり、混乱を招いている。この節では、こうした混乱が量子力学の概念的不備に由来することを指摘し、現代的な物質概念を明確にするためには、場の量子論を援用することが必須であることを強調したい。
通常の量子力学のフォーマリズムにおいては、質点系に関する古典的なハミルトニアンを書き下し、これに量子化の操作を施すことによって理論を構築する。だが、こうしたやり方では、出発点にあったはずの質点の概念が途中で雲散霧消してしまい、混乱の種となる。例えば、電子線を二重スリットに照射して後方のスクリーンに干渉像を結ばせるという有名な実験を考えてみよう(下図)。この実験では、干渉という形で電子の波動性が表に現れている限りは、電子がどちらのスリットを通過したかは確定できない。また、通過したスリットを特定できるような測定装置を取り付けると、こんどは、電子の粒子性が表面化して、干渉像が消滅する。しかも、波動性と粒子性は、必ずしも相互に排他的な性質ではない。電子と交換する運動量がより小さくなり、結果的に位置の測定により大きな誤差が生じるように実験装置をアレンジしていくと、しだいに「どちらのスリットを通過したか」という情報が曖昧になる一方で、背後のスクリーンに再び干渉像が現れてくる。こうした性質は、電子を古典的な点粒子のイメージで捉える限り、どうしても理解できないはずである。

二重スリット実験に関しては、アインシュタインとボーアが興味深い論争を闘わせている。次の項目を参照されたい。
実は、こうした混乱の多くが、非相対論的量子力学が質点力学の記法を部分的に借用していることに起因している。そもそも、量子論的なハミルトニアンに現れる位置qは、古典力学において質点が特定の時刻に存在する地点を表す位置座標とは、本質的に異なる。非相対論的量子力学は、相対論的量子力学──いわゆる場の量子論──の近似理論であり、そこで扱われる電子や陽子は、場の励起状態が示す集団運動の標識的表現にすぎない。したがって、「電子の位置をqで表す」とは、電子が存在する地点の座標をq(の期待値)で表しているのではなく、電子場の集団運動を変数qで代表させるという意味である。実際、非相対論的量子力学が電子の運動に適用されるのは、電子の質量エネルギー(約0.5MeV)よりも充分に小さい低エネルギーの事象の場合に限られている。こうした条件下では、測定にかかるような長寿命の電子−陽電子の対生成が抑制されており、電子場の集団運動は、漸近領域(相互作用領域から充分に遠ざかった領域)において1粒子運動と類似した振舞いを示すことになる。この近似的に1粒子運動と見なせる状態を、質点力学の用語法を援用しながら強引に記述しようとすると、「1個の粒子として存在するが、不確定性原理によって古典的な軌道が描けない」という不可解な描像ができあがる訳である。
科学理論としての量子力学の正当性は、1920年代から30年代にかけて、実験と理論が見事に一致するという実証的な研究によって確かめられていった。しかし、不確定性関係や非因果性などの量子力学の基本的な考え方が、物理学者たちに理解された訳ではない。当代一流の学者の中に、量子力学は自然界の記述としては不完全であり、あくまで暫定的に使われるべき理論にすぎないと主張した人は、決して稀ではない。
例えば、アインシュタインは、ポドルスキーおよびローゼンとの共同論文で、次のような論法で量子力学の不完全性を示そうとした:「物理理論についてなにか真剣な考察をするとき、理論といっさい関係のない客観的実在と、理論がそれを用いる物理概念との区別を考慮に入れなければならない。これらの概念は、客観的実在と対応することを意図されたものであり、われわれは、これらの概念を使って、客観的実在を自らのために描写するのである。…量子力学では、波動関数が、それに対応する状態にある系の物理的実在の完全な記述を、まさに表していると仮定されている。…だが、われわれは、この仮定が、…矛盾を導くことを示そう」(アインシュタインほか「物理的実在についての量子力学的記述は完全か」(*)より)。また、量子力学の建設者の一人であるシュレディンガーも、量子力学が持つ哲学的な制約に不満を漏らしている:「量子力学の支配的教義は、認識論への逃避によって、(何が実在するかという)このきわめて困難なジレンマから自ら…を救おうとする。すなわち、自然対象の現実の状態と、それについて私が知っていること、あるいは、より適切には、私が努力さえすれば知り得ることの間にはなんら区別されるべきものがない、というわけである」(シュレディンガー「量子力学の現状」(+)より)。
(*)A.Einstein, B.Podolsky and N.Rosen, Phys.Rev.47(1935)777
(+)E.Schrodinger, Naturwissenschaften 23(1935)807
こうした批判が行われる理由として、量子力学が、「自然界には何が実在しているか」という基本的な問いに対してあらわに答えていないことを指摘しておくべきだろう。量子力学による記述に使われる「波動関数」にしても、ニュートン力学に登場する「質点」やマクスウェルの電磁気学に現れる「電磁場」のような(たとえ近似的であるにせよ)実在性を付与されておらず、あくまでも、理論的な予測を行うための道具でしかない。量子力学は、例えば、「ウラン235に中性子を照射するとどの程度の確率で分裂が起きるか」とか「超伝導状態になった金属に磁場を加えたとき、磁力線はどのような分布になるか」といった問いに答えることのできる「役に立つ」理論ではあるが、「この世界は何からできているのか」と悩む哲学者にとっては、全く解答を与えてくれない。少なくとも、量子力学を発展させた場の量子論(素粒子論)が登場するまでは。量子力学は、自然の謎を解明することを目的とするロマンチックな古典科学が、技術的応用を果たすための道具としてこき使われる現代科学へと変貌するきっかけを作った理論と言えるかもしれない。
もちろん、場の量子論が公理的定式化の可能な無矛盾な理論として完成されているとは言い難い。いわゆる「紫外発散の困難」を始めとして、多くの疑問が未解決のまま残されている。しかし、場の量子論を用いれば、少なくとも、非相対論的量子論に見られるような用語法に起因する混乱は避けられるはずである。
以下では、実用上の諸問題にはいっさい触れず、場の量子論のフォーマリズムを哲学的観点から眺めることにする。
【要約】 場の量子論において、物質と力は統合され、可能な物質/事象は全て、高次元φ空間内部の過程として記述することができる。
場の量子論をどのように定式化すべきかは、その目的に依存する。初学者のための教科書は、スカラー場の量子化から始めてゲージ理論へと進んで行くだろうし、理論の公理化を試みる論文では、演算子積や積分測度に対して、数学的に正当な定義を与えることを最初に行うだろう。ここでは、「物質とは何か」というきわめて哲学的なテーマを論じているので、物理学的な厳密さは犠牲にして、あくまで直観的にイメージしやすい論法を採用したい。
場の量子論について予備知識の全くない人は、次の参照項目を読んであらかじめイメージを作っておいていただきたい。
場の量子論で最も基本になる物理的自由度は、場の変数φ(…)である。変数φは、非相対論的な量子力学における位置演算子qに相当するもので、最も規範的な場の理論においては、共役運動量π(…)との間に正準交換関係が成り立つ。
現実的な場の量子論では、物質として振舞うクォークやレプトンなどのフェルミオン場(半奇数スピン)と、さまざまな力を媒介するゲージボソン場(整数スピン)が存在するが、ここでは、スピノルやベクトルの添え字を省略し、あたかも単成分スカラー場φだけがあるかのような記法を用いる。これは、表現の上でのいたずらな煩雑化を避け、議論の道筋を明確にするための便法である。ただし、(直観的なイメージを別にすると)以下の議論にスカラー場の特性はあらわに用いていないので、フェルミオンやゲージボソンに拡張する場合のみならず、将来において理論の枠組みが大幅に変更され、スピノルやベクトル以外の場の量が導入されたときにも、議論に本質的な変更を加えずにそのまま使えると期待される。
場の変数を識別するインデックス(…)として、最も簡単な定式化においては、時空点xが選ばれる。すなわち、時空をメッシュに切って、離散的な座標の組x=(x,y,z,t)で指定される有限な領域に分割し、各領域に場の量を割り当てていく手法である。このやりかたは、ハイゼンベルグとパウリによる場の量子論の原典(1929)ですでに採用されたもので、その後、さまざまな改良が加えられて数学的な厳密性を増し、こんにちに至っている。
 時空の各点に場の変数φが存在するとは、各点が運動の自由度を持つことを意味する。きわめて素朴なイメージを用いると、時空のあらゆる地点にバネのような「運動する物体」が存在することになる(右図)。このとき、φはバネの伸び縮みの変位を表す。このような仮想バネが運動する“スペース”は、φという“座標軸”によって張られる数学的空間になり、変数φの状態関数はφを引数とする関数の形で表される(実際には、φもインデックスを持つので状態関数はφの汎関数になる)。
時空の各点に場の変数φが存在するとは、各点が運動の自由度を持つことを意味する。きわめて素朴なイメージを用いると、時空のあらゆる地点にバネのような「運動する物体」が存在することになる(右図)。このとき、φはバネの伸び縮みの変位を表す。このような仮想バネが運動する“スペース”は、φという“座標軸”によって張られる数学的空間になり、変数φの状態関数はφを引数とする関数の形で表される(実際には、φもインデックスを持つので状態関数はφの汎関数になる)。
現在、「標準模型」として多くの素粒子反応を記述するのに使われるゲージ理論の場合は、空間をジャングルジムのような格子で表現し、結節点に相当する格子点上にクォークやレプトンなどの“物質”を表すフェルミオン場を、格子点と格子点を結ぶリンク上に“力”を媒介するゲージボソン場を、それぞれ配するのが、一般的である(下図)。

時空点xをインデックスとして選ぶことは、絶対的な要請ではない。例えば、この世のあらゆる物理現象を世界の根源的な構成要素たる弦の運動に還元しようとする理論(超ひも理論)では、時空多様体上に固定された点よりも、弦の振動のモードの方が、物理的な自由度を識別するためのインデックスとして、実態に即したものとされる。しかし、こうしたインデックスの選び方は、特定の理論への依存性が大きく、たとえ現実的であるとしても、議論の一般性が失われるというデメリットがあり、さらには、学界で支持されていた学説の消長によって、流行遅れになる危険も孕んでいる。こうした問題を避けるために、本論では、時空を離散化して各領域に場の変数を配するといういささか古典的な手法を墨守する。
もちろん、離散化した時空点を引数とするφ(x)という記法が、議論の有効性を著しく制限することがあってはならない。素朴に考えると、時空をメッシュに切ることによって、長距離領域で明らかに存在しているローレンツ不変性──特に、空間における回転対称性と、慣性系の同等性をもたらす狭い意味での相対性──が成り立つかどうか、疑わしくなりそうである。しかし、この問題に対しては、技術的な解決法がある。すなわち、隣接する時空点上の場の変数同士が相互作用する際、作用の強さを表す結合係数を、全時空で不変な定数ではなく、ある一定値の回りを変動する不定数として扱うやりかたである。これは、格子場の理論においては、隣接する格子点間の間隔がばらついていることを意味する。このように格子間隔が一定でない“結晶”は、一定の結晶軸を持たないアモルファス(無定形)な状態になり、適切な条件が満たされれば、長距離でのローレンツ不変性が近似的に回復できる。以下の議論は、こうした「技術的解決」が暗に前提されているものとし、ローレンツ不変性の成立性について、いちいち断ることはしない。
 場の量子論において、場の変数φは確定した値を取らない。ある時刻──正確に言えば、ある空間的な超平面σ上──で系の状態は、その時刻──ないし超平面──で定義されるφの汎関数Ψ[φ;σ]として表される。Ψ[φ;σ]は、非相対論的な量子力学における波動関数ψ(q,t)を場の理論に拡張したものである。φの値が不確定になることは、非相対論的な量子力学において、電子が特定の位置に局在せずにぼんやりと拡がった状態として表されることに相当する。時空各点にバネが存在するという先の素朴なイメージを利用すれば、バネの変位が量子論的に揺らいでいることになる(下図)。非相対論的な量子力学では、電子の位置qがあたかも空間座標であるかのように記述されるために、量子論的な揺らぎの物理的な意味が判然とせず、点粒子でありながら位置が不確定になるという了解不能な命題が語られることもあったが、このような模式的な描像を用いれば、場の量子論における量子揺らぎ(quantum fluctuation)が、φという座標軸を持つ空間内部において場の変数が拡がった状態になることだと了解されるだろう。
場の量子論において、場の変数φは確定した値を取らない。ある時刻──正確に言えば、ある空間的な超平面σ上──で系の状態は、その時刻──ないし超平面──で定義されるφの汎関数Ψ[φ;σ]として表される。Ψ[φ;σ]は、非相対論的な量子力学における波動関数ψ(q,t)を場の理論に拡張したものである。φの値が不確定になることは、非相対論的な量子力学において、電子が特定の位置に局在せずにぼんやりと拡がった状態として表されることに相当する。時空各点にバネが存在するという先の素朴なイメージを利用すれば、バネの変位が量子論的に揺らいでいることになる(下図)。非相対論的な量子力学では、電子の位置qがあたかも空間座標であるかのように記述されるために、量子論的な揺らぎの物理的な意味が判然とせず、点粒子でありながら位置が不確定になるという了解不能な命題が語られることもあったが、このような模式的な描像を用いれば、場の量子論における量子揺らぎ(quantum fluctuation)が、φという座標軸を持つ空間内部において場の変数が拡がった状態になることだと了解されるだろう。

量子論的な揺らぎを、場の変数が時間と共に激しく振動していると誤解してはならない。揺らぎは、各時空点において存在するものであり、時間的な変動とは無関係である。また、量子揺らぎは、状態関数を用いることによって生まれた理論的な虚構ではなく、現実に物理的な効果をもたらすリアリスティックな現象である。このことは、原子が量子揺らぎによって安定性を保っている──すなわち、電子が量子揺らぎのせいで空間的に拡がるために原子核に吸収されない──などの事例から明らかである。
場の変数の相互作用を規定するダイナミクスは、一般に、ラグランジアンLによって定義される。ラグランジアンLの具体的な表式を与えることが、具体的な理論的モデルを指定することに相当する。電子と電磁場に関するハイゼンベルグ/パウリの古典的なモデルに始まり、湯川による中間子モデルや、ゲルマンの量子色力学モデル、ワインバーグ/サラムの電磁弱統一理論など、多くの理論がラグランジアンを与えることによって定義されている。ここでは、哲学的な興味に基づいて物質と力に関する一般論を考察しているので、ラグランジアンの形は特定しない。
なお、通常の連続理論では、ラグランジアンは、場の変数φとその微分dφを引数とするような汎関数として定義されるが、上で述べたように時空を離散化する場合は、微分は差分で置き換えられるので、φだけの汎関数L[φ]を考えれば充分である。このほか、離散系でのラグランジアンに関する条件はいろいろあるが、いずれも専門的になるので、比較的わかりやすいものだけを、次の項目でまとめて紹介するにとどめたい。
遠隔力を介して相互作用する古典的な質点系の力学では、ラグランジアンは、質点の運動を記述する運動項Kと、質点に加わる力を規定する相互作用項U(保存力の場合はポテンシャル項)が明確に分離され、L=K−Uという形式になっている。しかし、場の理論では、運動項と相互作用項を截然と区別することはできない。場に外部から力が加わるのではなく、場が自分自身と相互作用しながら変化するという形で、系の時間発展が表される。こうした特性は、水の表面にできる波の運動を思い浮かべればわかりやすいだろう。水の表面に“波”という自立的な物体があって、これが外部から力を受けて運動しているのではなく、水全体が自分自身と相互作用することによって、表面波の伝播という現象が生起するのである。
従来の物質概念を根本から覆すと言われる場の量子論の特性は、古典的には波動しか生み出せないはずの場が、量子効果によって粒子的な振舞いを示すという点に集約される。一般に、量子効果は、特定の条件を満たす離散的な(とびとびの)状態を安定化する傾向性を持つ。例えば、水素原子(固定された水素原子核によって1個の電子が束縛される系)の場合、古典理論の範囲では、電子が持つエネルギーは連続的に変化し得るが、(非相対論的な)量子力学で計算すると、1s状態や2p状態のようにとびとびのエネルギーを持つ離散的な状態しか安定的に存在できないことがわかる。場の量子論においては、こうした量子効果が、粒子的な励起状態を生み出すように作用する。もちろん、場の中に点状の粒子が突如として出現するのではなく、あたかも粒子が存在するかのような形で相互作用が行われる訳である。
細かいことを言えば、場が生み出す粒子的な励起状態の性質は、クォークや電子のようなフェルミオンと、グルーオンや光子のようなゲージボソンとでは、かなり異なっている。前者の方が粒子数が保存する──1個の電子を表す状態はいつまでも1個の状態であり続ける──ため、固体や液体などの物質を構成する要素となる。これに対して、後者は、通常は粒子数が一定しない状態をとっており、古典的な粒子としてはイメージしにくい(光子の場合も、光電効果やコンプトン効果のように、1光子交換で近似できるような過程以外は、あまり粒子的に振舞わない)。このため、一般人向けの解説では、フェルミオンを“物質”、ゲージボソンを“力”として峻別することも少なくない。だが、この差異は、量子効果によって粒子性が生じた場が持つ二次的な性質であり、哲学的な“物質”と“力”の概念を変革するほどのものではないので、ここではあえて深入りはしない。
具体的にどのような量子効果が生じるかを調べるには、ラグランジアンによってダイナミクスが定義された系を、経路積分法にしたがって量子化しなければならない。経路積分法とは、1940年代後半にファインマンが開発した量子化の手法である。それ以前には、1929年にハイゼンベルグとパウリが案出した正準理論にしたがって、場の変数とその共役運動量の間に正準交換関係を仮定し、そこから微小な時間差に対する状態発展の方程式を導き出す方法が一般的だった。しかし、計算が煩雑な上に見通しの悪い正準理論に比べて、経路積分法は、より簡単でわかりやすく、そして(おそらくは)物理的な実態により即したものであるため、こんにちでは、正準理論に代わって広く利用されている。
経路積分による量子化とは、ある状態から別の状態への遷移確率を計算するにあたって、さまざまな経路からの寄与を足しあげる(積分する)手法である。
議論を簡単にするため、まず、非相対論的な量子力学の枠組みで説明しよう。ある質点が、位置QiからQfに移動する過程を考える。経路積分法によると、こうした移動が生じる確率振幅T──その絶対値の2乗が確率になる──は、QiからQfに至る全ての“経路”に、exp(iS)という重みを乗じて足しあわせたものになる。ただし、Sはこの経路に関する作用積分で、ラグランジアンLを、QiからQfまでの経路に沿って積分したものである。ここで、作用積分Sが最小になるような経路は、古典力学における軌道に対応する(最小作用の法則)。経路積分は、古典軌道以外の経路も状態の遷移に寄与することを表しており、量子論で質点が確定した軌道を辿って移動するのではないことが如実になる。

場の量子論での経路積分は、基本的には、非相対論的量子力学の式を場の変数を使って書き換えたものになっている。すなわち、始状態Ψi[φ;σi]から終状態Ψf[φ;σf ]へ遷移するときの確率振幅Tは、遷移の過程で通過し得る全ての“経路”に、exp(iS) という重みを乗じて足しあわせたものになる。ただし、作用積分Sは、ラグランジアンLを、始状態と終状態で挟まれた時空領域で積分したものである。

場の量子論(素粒子論)において、経路積分の計算をもとに実用的な結果を得るためには、上のような単純な計算で済むはずもなく、実際には、さまざまなテクニックを駆使しなければならない。例えば、考慮すべき過程に応じて、始状態/終状態の形を適切に与える必要がある(素粒子の散乱の場合には、一般に、散乱ポイントから離れるにつれて個々の素粒子が自由粒子として振舞うようになるという「LSZ漸近状態」が選ばれる)。また、きわめて狭い領域での状態のミクロな変動は大局的な結果に影響を及ぼさないので、その効果を取り除く「くりこみ」の手続き(朝永−ファインマン−シュヴィンガーの理論)を施さなければならない。このほかにも、ゲージ理論などで束縛条件を満たすためのゴースト場の導入、フェルミ統計に従う粒子を扱うためのグラスマン数の利用など、現実に経路積分の計算を行うためには、きわめて高度な数学的手法が要求される。しかし、これらはいずれも実用のためのテクニックであり、哲学的な議論においては、あえて考慮する必要はないだろう。
遷移確率を計算するときに、複数の経路の和を取らなければならないという点は、経路(=軌道)が一意的に定まる古典物理学と基本的に異なる量子論の特徴である。この結果、量子力学的な状態Ψ[φ;σ]は、始状態から終状態に至る遷移過程の全ての段階で、φの値が確定する古典的な経路に束縛されず、φを座標軸とする空間の内部に拡がって存在している。ニュートン力学に基づいて質点の運動を考えると、ある時刻における位置q(t)はただ1つの値に定まるため、q(t)を座標軸とするような数学的抽象空間において、1点を除いては現実の過程とは対応しない領域になるので、q空間全体は数学的な虚構と言わざるを得ない。運動全体を問題にするならば、q空間内部に無数に存在する軌道(trajectory)の中で、現実の運動に対応するただ1つの軌道以外は、全て仮想的・非現実的なものであり、古典物理学におけるq空間は、そうした非現実的軌道を表現するための単なる道具でしかないのである。しかし、量子力学の場合、あらゆる物理的な現象は、φ(…)が張る空間の中で拡がった(=量子揺らぎを伴った)状態としてのみ記述されるので、φ空間は、単なる数学的虚構ではなく、状態の拡がりを実現するためのリアリティを持っていると見なすべきである。φ空間にリアリティを認めることは、次章以降の立論において本質的な重要性を持つ。
量子論を実際の現象に応用している研究者・技術者ならば、量子揺らぎが、人間が計算のために導入した仮想的な過程ではなく、物理系の振舞いに不可避的に伴うリアルなものであることを実感しているはずである。例えば、sp混成軌道による共有結合といった量子論に固有の振舞いを実現している電子を考えるとき、これを、量子揺らぎのない(=φ空間で拡がりのない)存在物としてイメージすることは、不可能である。さらに、量子揺らぎがリアルであるならば、それが実現される“スペース”もリアルだと考えるのが妥当だと考える。状態の“拡がり”と“拡がりのスペース”を別々に扱うのは冗長であり、両者を統合すべきだとの見解もあり得るが、通常の認知形式では“対象”と“対象の枠組み”とを峻別するのは困難であり、数学的にもφとΨ[φ]という別個の表記で指定されるので、ここでは、「φ空間内部に拡がった状態Ψが実現されている」というように、両者を別のものとして扱う。
なお、φ空間という呼称は、必ずしも一般的なものでない。経路積分を行う抽象空間を仮にそう呼んだだけであり、理論によっては、固有の呼び名が付けられていることもある。また、クォークや電子などのフェルミオンの場合、反可換数(グラスマン数)の空間になって単一成分での拡がりは存在しないため、スピノル空間での回転自由度による拡がりを想定した方がイメージしやすいだろう。
量子論的に記述可能な全ての現象は、経路積分の中に含まれるため、考えている時空領域の座標をインデックスとするφ(x)の汎関数として記述される。これを日常的な用語で言い換えると、「あらゆる物質とあらゆる事象は、φ空間の内部に存在/生起する」──と表現される。ここで「物質と事象」「存在と生起」という対概念を併記したが、これらの対概念は、日常的な認識論の範囲では峻別されるものの、物理現象として理論的に記述した場合は、いずれもφ(x)の汎関数として表される状態であり、時間的な変動の程度に関する量的な差異しか認められない。
ただし、通常の量子論の定式化において用いられる(シュレディンガー方程式の解としての)波動関数は、現実に存在/生起する物質/事象を表す汎関数そのものではなく、可能な汎関数にある重みをつけて加え併せたもので、あくまで、対象とする物理系の確率的な振舞いしか表していない。このため、量子力学の定式化に若干の変更を加えて、波動関数から確率情報を分離しなければならない。
【要約】 起こり得る過程の総体としてのΘは、互いに干渉しない量子過程Θrに分割される。われわれが生きている「この」世界は、1つの具現化された量子過程Θrである。
現実的であるかどうか別にして、理論的に生起し得る過程の総体は、1つのシンボルΘで表すことができる。これは、すべての場の変数φによって張られる高次元空間内部における実現可能な経路の一つ一つに、確率振幅を「測度」として付与したものである。初期状態だけを与えたときのΘは、その状態から出発して、その系で生起し得る全ての過程を含んでいる。これは、エヴァレット流の多世界解釈(*)における多世界全体を指すものである。特に、始状態Ψiをビッグバンとし、終状態を特に指定しないようなΘは、この宇宙における可能な歴史の総体である。
(*)H.Everett III, Rev.Mod.Phys.29(1957)462. この論文は原典としてしばしば引用されるが、多世界解釈そのものは、Everettの議論を発展させた de Witt らによって主張された。
ただし、現実の世界は、起こり得る過程の総体としてでなく、その中の一つの歴史として実現されているはずである。したがって、Θを全ての可能な歴史に分割し、その一つ一つを物理学的に峻別することができなければならない。この場合、量子力学の際だった特徴とされる(不確定性ではない)は、始状態を指定しても、どの歴史が具現化されるかわからないという点に集約される。この不確実性は、物理学の未熟さに起因するのではなく、そもそも時間発展は一意的ではないという自然界における非因果性の現れと考えられる。
旧来の解釈では、波動関数が冗長性(redundancy)を含まない対象記述になるのは、観測を通じて系の状態が(オブザーバブルの固有状態として)確定した場合だけであり、それ以外の過程については、現実と対応づけられるような量子状態を書き下すことは不可能だとされていた。量子力学とは、確率的な予測を行うための理論であって、理論的記述と実際の現象と結びつけるためには、観測という人為的な作業を行わなければならないというのだ。この見方によれば、波動関数は「単なる」確率振幅であって、古典物理学のように現実に関する直接的知見を与えるものではないことになる。
 これに対して、人為的行為としての観測を量子力学の定式化から排し、波動関数の冗長性なしに対象を記述する方法が、開発されつつある。ここで鍵となるのが、デコヒーレンス(decoherence) という概念である。デコヒーレンスとは、ある初期状態Ψiがシュレディンガー方程式にしたがって時間発展していく過程で、自発的(spontaneous) に(すなわち、外部から人間が関与することなしに)互いに干渉しない状態に分岐していくことである(右図)。「シュレディンガーの猫」(下の項目参照)が生きているか否かというような観測によって識別される状態は、互いにデコヒーレントになっていると考えられる。現実に生起しているのは、互いにデコヒーレントになった状態の1つ(猫が生きているか死んでいるかのどちらか)であり、こうしたデコヒーレント状態の連鎖が、現実の世界の歴史を記述することになる。
これに対して、人為的行為としての観測を量子力学の定式化から排し、波動関数の冗長性なしに対象を記述する方法が、開発されつつある。ここで鍵となるのが、デコヒーレンス(decoherence) という概念である。デコヒーレンスとは、ある初期状態Ψiがシュレディンガー方程式にしたがって時間発展していく過程で、自発的(spontaneous) に(すなわち、外部から人間が関与することなしに)互いに干渉しない状態に分岐していくことである(右図)。「シュレディンガーの猫」(下の項目参照)が生きているか否かというような観測によって識別される状態は、互いにデコヒーレントになっていると考えられる。現実に生起しているのは、互いにデコヒーレントになった状態の1つ(猫が生きているか死んでいるかのどちらか)であり、こうしたデコヒーレント状態の連鎖が、現実の世界の歴史を記述することになる。

デコヒーレンスに関しては、いまだ完全な理論が構築されている訳ではない。状態Ψiが、シュレディンガー方程式に則って時間発展を行い、ΨaとΨbの重ね合わせに変化したとすると、ΨaとΨbがデコヒーレントであるための・充分条件・は、任意のオブザーバブルAに対して、量子力学的な干渉効果を表す非対角項がゼロになる、すなわち、
<Ψa|A|Ψb> + <Ψb|A|Ψa> = 0
が満たされることである。しかし、ノントリヴィアルな系で、この条件式の成立が厳密に証明されたケースはない。せいぜい、きわめて単純なモデルで、状態を分割する際にきわめて小さな量として導入したパラメータεをゼロに近づける極限で、干渉効果を表すある項が〜O(ε)の微小量になることが示されただけである。厳密な論証が難しいのは、完全なデコヒーレンスはきわめて多数の自由度を持つ系でしか起きないからである。こうしたシステムでは、非対角項への寄与として多自由度にわたる積分が現れるが、その被積分項がゼロの回りで振動することによってプラスとマイナスが打ち消しあい、デコヒーレンスが実現されと予想される。しかし、これを数学的にきちんと証明するのは、至難の業である。
さらに、デコヒーレンスが既知の量子力学の枠内で実現されることを疑問視する学者も一部にいる。干渉効果がゼロになることはあり得ず、必ずO(ε)の“お釣り”が残ってしまうという主張である。この見解を採用するならば、状態の“完全な”(=相互干渉が全く生じない)分岐を実現するためには、量子力学の理論体系に何らかの「切断」(理論の適用限界をあらわに設定し、その範囲外のプロセスについては、適当な条件を付けて補うこと)を導入しなければならない。量子力学は、それだけでは現実を過不足なく記述することが原理的に困難な理論であり、これを近似として含むような包括的な理論を構築して、初めてデコヒーレンスが解明されることになるというのだ。ただし、量子力学を超克する包括的な理論がどのようなものになるかは、見当もつかない。
こうした問題があるものの、デコヒーレンスのアイデアは、もっともらしい推量(conjecture) として多くの学者に受容されていると言って良いだろう。ここでは、これを承認されたものとして、話を進めることにする。
デコヒーレンス理論を採用すると、あるシステムが逐次的に取る状態の系列を指定することが可能になる。これは、互いにデコヒーレントな状態の間では無矛盾条件が成立して干渉項が相殺されるため、量子過程を互いに干渉しない部分に分割することが可能になるからである(詳しくは、次の項目を参照)。
初期状態Ψiから出発して、逐次的に実現されるデコヒーレントな状態を、順にΨ1,Ψ2…と書くことにすると、
Ψi→Ψ1→Ψ2→…
という量子過程は、Ψiに始まる全量子過程Θの中の一つの具現化(realization) Θrと見なすことができる。それぞれの状態をつなぐ遷移過程は、経路積分の形で与えられる。すなわち、Ψi,Ψ1,Ψ2…を境界条件とし、これらで挟まれた領域の中で、さまざまな経路に重みを付けて足しあわせたものになる。これは、次のような模式図で表される。
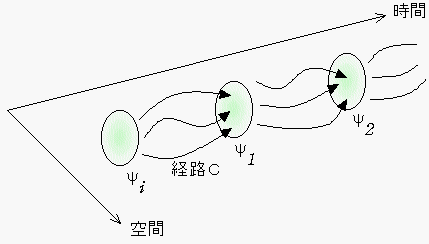
具現化Θrには、経路積分の積分値(を規格化したもの)という形で、先験的な確率振幅が付与されている。この確率(=確率振幅の絶対値の2乗)が、可能な歴史の総体Θを母集団として、そこから1つの具現化Θrを選び出すときの相対確率だとすれば、量子力学の確率解釈は正当化される。しかし、「誰が」「いかなる方法で」一つの歴史を選び出しているかを問うことは、量子力学の範囲では無意味であり、これを超克する理論を案出しなければならない。
厳密に言えば、具現化された量子過程Θrに冗長性が現れないようにするためには、もう少し細かく分割を進めなければならない。そのためには、2つのデコヒーレント状態ΨkとΨk+1に挟まれた中間状態の中から、いわゆる「無矛盾条件」を満たすセットを選び出して、各中間状態を通過する過程を別個の具現化とする必要がある。こうした分割を可能な限り進めた結果として得られるのが、冗長性の全くない「真の」歴史表現Θrである。この点に関しては、次の項目(かなり専門的なので、一般の読者には勧めない)を参照してほしい。
既に述べたように、可能な歴史の総体であるΘが、ある初期状態を与えれば、シュレディンガー方程式の解として一意的に与えられるのに対して、具現化された量子過程Θrにおいては、物理学的な意味での因果律が成立していない。ニュートン力学をはじめとする古典物理学では、初期条件を与えることによって、いかなる物理的な過程が実現されるかが完全に決定される。言うなれば、“神の一撃”として初期条件が与えられる瞬間だけが、唯一無二の事実という歴史の特殊性に関わる時刻であり、それ以外の時間は、この初期条件から機械的に導き出される従属的な立場にある。しかし、量子過程Θrには、そうした特権的な瞬間──物理法則を適用すべき境界条件が与えられる超平面──は存在しない。あらゆる部分が同等であり、法則によって厳格に規定されない非因果的な内部変化が生じているのである。
われわれが住む「この」世界とは、具現化された1つの量子過程Θrである。高次元φ空間の中で生起する時間的・空間的に拡がったこの過程において、「物質が力を受けて運動する」という描像は全く成り立たない。あらゆる物質とあらゆる事象が、物理法則の実現という形で、量子過程に一元化されているのである。こうした科学的世界観をベースに、「この世界についての仮説」を語っていくことにしよう。
|
|
|
|
|
©Nobuo YOSHIDA