第2の問題.時間はなぜ1次元か
これまでの議論では、時間と空間とともに多様体上に定義だれた座標として対称的に取り扱ってきた。本節では、時間が空間と決定的に異なっている点――すなわち、その1次元性を論じていくことにする。
時間が1次元であるということは、「流れ」という時間に特有の性質を与える大きな要素となっている。空間には、回転という連続変換に対する自由度があるため、回転不変性を破る特殊な境界条件をとらない限り、系に特定の向きを指定することはできなかった。ところが、時間は過去あるいは未来の二つの向きしか取り得ないため、離散的な変換操作である時間反転に対する不変性を破りさえすれば、一方向へ流れる時間の向きが与えられるのである。
現行の物理理論では、ほとんどの場合、時間の1次元性はモデルを構成する際の前提条件と見なされており、なぜ1次元になるかの説明が試みられることは稀である。しかし、この性質が時間の本質的な特性を定めるのに関与している以上、科学哲学的な立場から、何らかの方法で理由付けを行わねばなるまい。以下では、はじめに現在知られている二つの説明原理を持ち出していずれも否定し、時空構造の大域的性質を再検討する必要性を示唆する。ただし、最終的結論には到達できない。
物理的に時間の1次元性を説明する一つの方法は、自発的コンパクト化の議論を援用するものである。すなわち、時間はもともと任意の多数次元であったと仮定し、このうち余分な次元はきわめて小さな広がりしか持たないと解釈すれば、観測される時間は1次元となる〔12〕。もう少しわかりやすく、素朴なアナロジーを使って解説しよう。綱渡りの芸人にとって、ロープは進むか退くかという一方向の運動の自由度しか持たないが、ロープの上を這う虫にとっては、その周囲を回る自由度を含めて2次元の拡がりがあることになる。このロープの周囲という小さな拡がりが余剰次元に対応し、ロープの軸方向の延長が実際に観測される時間の1次元に当たる。こうした描像は、小さくなっている次元が現在の観測限界(直接的な実験では10-17メートル程度)を十分下回り、なおかついくつかの困難(宇宙の平均的な曲率がきわめて小さくなっているという観測事実との矛盾など)を克服できれば、現時点での宇宙像としての正当性を主張できる。
問題となるのは、余分な次元がコンパクトになる理由を、「自然に」与えられるかという点である。この問題を解明しようとする立場からすると、単に、余分な次元が小さくなる解が存在する模型を提出するだけでは、説明として不十分である。実際、現実の時間の性質と合致するためには、こうした模型において、ただ一つの次元だけが収縮せずに最低数百億年の延長を持つ持つに到る必要があり、そのために特別な条件(パラメータの微細な調節やその次元のみを非対称に扱う境界条件など)を課さなければならないとするならば、時間の1次元性の「自然な」説明原理として採用することはできない。この問題は、対象となるのが空間でなく時間であるがゆえに、いっそう困難な色彩を帯びてくる。空間に関しては、張力が働いて全体として収縮する傾向にありながら、エネルギーなどの保存則によって一つの次元だけが膨張するという理論を作ることは不可能ではないと思われる。しかし、時間座標の場合は、時間の経過と共に力学的に収縮していく訳ではなく、方程式系の無矛盾の解としてコンパクト化された時間と延長を持つ時間の差を出さねばならないので、空間のような保存則を利用することができず、多数の時間次元があるときに一つだけを特別扱いする理由が存在しない。…(具体的な議論省略)…こうして、時空のコンパクト化の議論を用いても、時間が1次元である理由は説明できないことになる。
時間の1次元性を説明するのに、人間原理を持ち出すことも可能だろう。人間原理とは、自然法則にさまざまな形式があり得るとしても、それが認識されるのは、当該法則が知的生命の存在を許す場合に限られるという原理である〔14〕。例えば、重力が斥力である世界では、安定した星系が形成されないために生命が発生することができず、たとえそのような世界が実在したとしても、斥力としての重力を物理法則と見なす学問は存在できないのである。論理実証主義的な表現を用いれば、観測されない世界について語ることは無意味なのである。この人間原理は、ある法則がなぜそのような形式をとっているかを説明する数少ない原理であるため、最近はいささか乱用されるきらいがあるが、これをもって時間の1次元性が説明できないか、見ていくことにしよう。
人間原理が援用できるためには、時間が2次元以上になると、知的生命が存在できなくなることが証明されなければならない。当然のことながら、知的生命が発生するための必要条件は知られていないので、議論は推測の域を出ないが、次の点は前提としても良いだろう。すなわち、(i)1次元時間で見られるパターン形成などの物理現象は、極座標表示で周方向の自由度を縮約すれば多次元の時間でも実現されるので、空間内部に設定する(知的過程を遂行するための)物理的装置は1次元時間のときと同様のものを用い、(ii)その内部で意識に相当するものが存在できるかを検討課題とする。ただし、意識に関する議論は、技術上の理由から神経回路理論のごく初歩のみを援用するにとどめ、本格的な研究は見送ることにする。
はじめに、2次元の時間で意識が存在できなくなる可能性を考察しよう。ここでは、意識を神経回路の興奮のパターンが初期条件に応じて特定の状態に収束する過程と仮定する。この過程は、意識が常に「何かについての意識」であり、感覚あるいは記憶に由来する予見から展開して(準)定常状態に到るという経験的事実に依拠している。ここで、意識が成立しない条件は、神経細胞の状態が2つの時間について収束しないことである。具体的には、時刻(t1,t2)でのある神経細胞の状態をx(t1,t2)で表すと、
-
lim(t1→∞)lim(t2→∞)x(t1,t2) ≠ lim(t2→∞)lim(t1→∞)x(t1,t2)
となる場合に、安定した意識は成り立たない。物理学的に見てこの式が成立するためには、t1を固定したままt2を変化させることによって与えられるt1のいろいろな初期条件に対して、t1の時間発展が各状態ごとに全く異なった経過を辿ることが必要である。しかし、こうした条件は、一般に、1次元時間系で収束が成立するモデルと同じものを使った場合は成立しない。なぜなら、一つの時間について収束する以上、
-
∃T:∀ε:|x(t1,t2)−X|<ε for t2>T
となるため、充分に大きなt2に対してはt1の始状態はきわめて近接しており、そこからt1について時間発展させても充分に近い終状態へ収束するはずだからである。
それでは、1次元時間と同じように発展する神経回路は存在するのだろうか。簡単なモデルから考えていこう。
最も簡単な神経回路のモデルとして知られているのは、マクロック/ピッツのモデルである〔15〕。このモデルでは、時間がτ単位で離散化されており、1または0の2値をとる神経細胞iの時刻tにおける状態をxi(t)と表せば、時間発展についての状態方程式は、
-
xi(t+τ)=θ(wijxj(t)−ξi)
で与えられる。ただし、θはヘヴィサイド関数、wは細胞jから細胞iへの結合係数、ξは閾値である。これを2次元の時間に拡張することは容易であり、二つの時間変数t1,t2を用いて、
-
xi(t1+τ,t2t+τ)
-
=θ(wijxj(t1+τ,t2)
+ w'ijxj(t1,t2+τ)
− ξi)
とすれば良い。この神経回路の終状態がどうなるかは境界条件に依存するが、特に簡単な境界条件、例えば、t1>0,t2=0 および t1=0,t2>0 のとき、それぞれ{xi}(i=1,2,…N)が定数ベクトルになるとすると、t1,t2が充分大きい領域では、{xi}は二つの時間それぞれに関して定常的または周期的になることが簡単に証明でききる。
さらに、カイエニエッロに従って、上のモデルに発火の不応期と学習による結合係数の時間変化の考えを導入して複雑化しても、事情は大差ない〔15〕。このとき、興奮性の結合係数の時間変化を記述する記憶方程式は、実質的に次式で与えられる。
-
gradwij={Σt'α(t',t)xj(t')xj(t)−β}・(wij−w0ij)
× θ(wij−Wij)
ただし、記号tで2つの時間を表しており、gradは2次元の時間に関する傾き、α(t',t)はt'がtより過去の場合に値をもつ2次元の重み関数である。このとき、t2<0ですべての神経細胞が静止状態にあるとすると、t1軸上でのwの変化は、1次元の時間の場合に等しくなり、特に一定の興奮パターンが(t1について)繰り返し現れる場合は、対応する結合係数が次第に増大し、最終的に一定の値Wijに固定されて永久記憶となる。
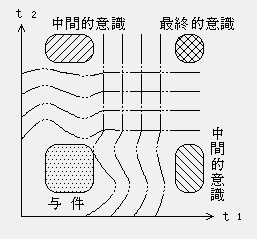 このようなモデルにおいてどのような「意識」が発生するかは、興味深いテーマである。明らかに、一方の時間を固定したときの他方の発展は、(固定された時間が充分に大きくその微小な変動に対して重み関数があまり変化しない場合は)1次元時間のときとほぼ等しくなるので、それぞれの時間軸上に中間的な「意識」が形成されることになる。こうした中間的意識から出発して、今度は固定されていた時間の向きに系を発展させていけば、最終的にある意識に到達するはずである(右図)。既に述べた2つの時間についての極限値の同一性より、この最終意識は、時間の中でどのような経路を辿っていっても等しいものになるはずである。こうした結果から、2次元時間に棲む知的生物は、時間の2次元的拡がりを覚知するものと予想される。
このようなモデルにおいてどのような「意識」が発生するかは、興味深いテーマである。明らかに、一方の時間を固定したときの他方の発展は、(固定された時間が充分に大きくその微小な変動に対して重み関数があまり変化しない場合は)1次元時間のときとほぼ等しくなるので、それぞれの時間軸上に中間的な「意識」が形成されることになる。こうした中間的意識から出発して、今度は固定されていた時間の向きに系を発展させていけば、最終的にある意識に到達するはずである(右図)。既に述べた2つの時間についての極限値の同一性より、この最終意識は、時間の中でどのような経路を辿っていっても等しいものになるはずである。こうした結果から、2次元時間に棲む知的生物は、時間の2次元的拡がりを覚知するものと予想される。
以上の議論は、時間が2次元になっても1次元のときと同様に神経回路のモデルを構築することができ、ある境界条件の下では興奮のパターンについての学習が成立する場合もあることを意味する。従って、もし、現在の神経回路理論の延長線上に、思考や意識に関する理論が樹立されるならば、同時に2次元時間における思考過程の可能性も確証されることになろう。このような予測を受け入れるならば、多次元の時間を持つ世界に知的生命が発生できないという命題は否定され、人間原理をもって時間の1次元性を説明することは、不可能になる。
これまでの論述では、時間が多次元になってもかまわないとの前提の元で、そのような世界は、余剰次元が縮約される、あるいは知的生命が発生しないという理由で認識対象とならないことを主張しようとし、いずれも所期の結論を得られなかった。そこで、そもそも時間が原理的に1次元でしかあり得ない宇宙モデルは存在しないかを、次に考えてみよう。ただし、確固たる議論を行うには今日通用している多くの科学理論を書き改めねばならないので、ここでは可能性を示唆するにとどめる。
一般にN次元多様体で―つの座標軸が特別になるのは、他の方向には存在する対称性が当該軸方向で破れている場合である。例えば、定ベクトル場のある世界では、ベクトルの方向を含む面内での回転不変性が破れており、その方向に時間を定義すると、時間座標のみが他の座標と区別される形で運動方程式中に現れることになる。この例では、多様体全体にわたって対称性を破らなければならないため、モデルとしては不自然である。ところが、1次元のみを特別扱いするためには、簡単な方法があることが知られている。すなわち、多様体上の1点に広い意味での特異点をとり、これを原点とする極座標を使えば、接線方向に存在する対称性が動径方向で破れていることになり、この方向だけが特殊な軸になる。さらに、動径方向の座標が(原点からの距産に等しい)正の値しかとり得ないという性質は、現実の宇宙において、時間が百数十億年前のビッグバンから始まったとする理論的・実験的結果に合致しており、多様体上に特異点を与えて時間の原点とするというモデルが有望であることを示唆している。
このモデルを前提とするとき解決しなければならないのは、時間と空間をいかにして分離するかという問題である。時間と空間の相違は、形式的には計量における符号の違いであり、事実的には境界条件の差が大きく関与している。このうち、後者については、特異点を原点とする極座標モデルと矛盾しない。実際、―般に利用される境界条件、空間については無限遠で状態が定常になる、または空間が有限で周期的になるとし、時間についてはある時刻におけるコーシー条件{位置と運動量のデータを与える)、あるいは二つの時刻におけるディリクレ条件(位置のデータを与える)を課すものであるが、極座標の場合は、空間の周期性は自然に導入され、時間には特異点近傍でのコーシー的な初期条件が与えられれば良い(時間の初期条件については次節で論じる)。従って、少なくとも境界条件に関しては、このモデルが現実と矛盾することはない。
しかし、計量の符号の差を「自然に」与えることは、現在の理論では不可能である。もちろん、符号を変えるだけなら、状態が解析関数で表現されていることを仮定して、半径座標rをit(iは虚数単位)と置き換える(いわゆるパウリ計量に対応する)のみで実現される.しかし、この書き換えは、物理的実在性の概念に新たな問題を提起する.この解釈に従えば、exp(−iωt)の時間依存性をもつと観測される現象が、実は exp(−r)の形で単調に減少する過程であり、振動に見えたのは人間が思考過程で虚軸に解析接続して認識したための錯覚であることになる。しかし、直観的にはもとより、科学的に見ても、この解釈はいかにも信じ難い.実際、多くの物理学者は、パウリ計量は単なる数学的トリックに過ぎないと考えている.従って、計量の符号に関するこの本質的な困難を克服しない限り、極座標モデルによって時間の1次元性を説明することはできない.この問題の解決は、今後の研究に委ねられている.
©Nobuo YOSHIDA
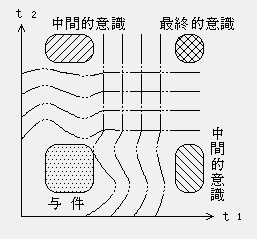 このようなモデルにおいてどのような「意識」が発生するかは、興味深いテーマである。明らかに、一方の時間を固定したときの他方の発展は、(固定された時間が充分に大きくその微小な変動に対して重み関数があまり変化しない場合は)1次元時間のときとほぼ等しくなるので、それぞれの時間軸上に中間的な「意識」が形成されることになる。こうした中間的意識から出発して、今度は固定されていた時間の向きに系を発展させていけば、最終的にある意識に到達するはずである(右図)。既に述べた2つの時間についての極限値の同一性より、この最終意識は、時間の中でどのような経路を辿っていっても等しいものになるはずである。こうした結果から、2次元時間に棲む知的生物は、時間の2次元的拡がりを覚知するものと予想される。
このようなモデルにおいてどのような「意識」が発生するかは、興味深いテーマである。明らかに、一方の時間を固定したときの他方の発展は、(固定された時間が充分に大きくその微小な変動に対して重み関数があまり変化しない場合は)1次元時間のときとほぼ等しくなるので、それぞれの時間軸上に中間的な「意識」が形成されることになる。こうした中間的意識から出発して、今度は固定されていた時間の向きに系を発展させていけば、最終的にある意識に到達するはずである(右図)。既に述べた2つの時間についての極限値の同一性より、この最終意識は、時間の中でどのような経路を辿っていっても等しいものになるはずである。こうした結果から、2次元時間に棲む知的生物は、時間の2次元的拡がりを覚知するものと予想される。