II−1 <自由>の直感と脳の情報処理
はじめに,人間の<意識>にかかわる問題を脳の生理的活動と結びつける立
論の妥当性に関して,筆者の基本的な見解を明らかにしておく。
意識化された精神的営為が大脳の活動と密接に結びついていることは,意識
内容と(脳波計や微小電極によって測定される)特定部位での神経興奮や(ポ
ジトロン放出を使って調べられる)血流量の増減が強く相関しているなどの実
験結果から明らかだが,果して意識を神経興奮の過程と同一視できるかどうか
は,現在の脳神経科学の知見だけでは決め手がない。人間の大脳皮質はきわめ
て複雑な組織で,その物理的過程を全て追跡するのは困難なため,その活動を
どのようにモデル化しようとも,非物質的な精神作用によって一定の神経興奮
が喚起される可能性が常に残るからである。しかし,次に掲げるような理由に
より,大脳皮質における物理的な神経興奮のバターンを<意識>そのものと等
置する仮説は,充分な妥当性を持っていると見なされる。
第1に,神経活動とそれに随伴する意識内容の形式的相似性はかなりの程度
まで定量的に検証されており,観察事実を説明する上で脳神経系とは別個に意
識の源泉を想定しなければならない必然性は見あたらない。1つだけ例を挙げ
よう。「異なる振動数の音を識別し低音のシグナルのときにある行動を起こせ」
という課題を与えたとき,シグナルを知覚してから行動を開始するまでの問に。
頭頂連合野での脳波にはいくつかのピークをもつ微小な変動が現れる。こ
の変動電位のうち,シグナルを提示してから約300ミリ秒後に現れるピークは,
行動を起こす必要のないダミーの高音刺激に対しては一般に発生しないが,シ
グナルの振動数を接近させて識別を困難にすると――おそらく,シグナルの高
低を判定するサンプルとして利用する目的で,高音についても音程を短期的に
記憶する作業が必要になるためだろう――このピークが再び観察されるよう
になる。提示した刺激に対するこうした反応から,この電位変動をもたらす神経
活動は,識別された刺激を記憶内容と比較しながら記憶の活性化や更新を遂行
する情報処理過程に対応するものと考えられる。ところが,刺激の提示から電
位変動がピークに達するまでの約300ミリ秒という時間は,<意識の流れ>にお
いて「このシグナルは低音だから行動に移らなければ」と感じる際の反応潜時
にほぼ等しい大きさである。したがって,変動電位を伴う神経活動と非物質的
な精神的作用を分離して「一方が引金となって他方が惹起された」と見なすに
は,両者が作用を及ぼし合うのに要する時間が(通常の神経興奮が伝播する過
程と比べて)かなり短いものと想定しなければならず,きわめて不自然である。
第2に,<意識>を物質的過程とは本質的に異なったものとして取り扱う認
識論的な操作が,実は,人間が認識を構成する際の心理的方略と軌を一にする
ものであり,必ずしも自然界に両者を峻別する根拠がある訳ではない点を指摘
しておかなければならない。この間の事情は次のように説明される。内観をも
とに<意識>の担い手として措定される<自我>と,認知された外界に登場す
るく他我>とは,前者が,あらゆる表象がその回りで求心的な構図をとりなが
ら配置される唯一の“世界中心”であるのに対し,後者は,同一の存在資格を
持って現れる多数の<身体>を(僅かな形貌の差異や所属する環境をもとに)
区別するための“仮想的標識”に過ぎないという点で,全く異質のものである。
もし,この相違が自然の側に由来すると仮定すれば,<意識>が属する精神と
<身体>が属する物質が,互いに排斥し合う世界を構成しているという物/心
の二元論に陥らざるを得ない。しかし,<意識>と<身体>(あるいは<自
我>とく他我>)の違いは,むしろ認識が成立する過程での情報処理の形式的
な差に起因するものと思われる。実際,人間が感覚器官を通じて獲得した情報
を分析する際には,形状や性質が安定に保たれる領域を<物>として対象化し,
その背景を全てのく物>に共通の<空間>として取り扱う性向がある。この結
果,「人間の目に映る」外界は,空虚な器たるく空間>の内部にいくつかのく物
体>が並存するという“劇場的”な様相を呈することになり,必然的に,安定
な――アメーバーのように変形や分裂をしない――身体を示す他者も,この
性向に従ってく個人>として分節される。く他我>の概念は,これを名指すた
めの虚構的な標識として導入されたものと考えられる。これに対して,
<自我>の回りに求心的に構成される<意識>は,明らかに視覚や聴覚などの
知覚情報処理のフィルターを通しておらず,その(デカルト的懐疑を許さない)
絶対的な性格を鑑みれば,より直接的に「なまの」物質的過程の形相的側面を
表すと解釈すべきだろう。したがって,<意識>がその現れ方において
<身体>と質的に異なるとしても,それは実体に根ざすというよりも認識の形
式に由来すると見なされる。ただし,<意識>をもたらす物理現象は,その特
性を再現するためのいくつかの要件を備えている必要があるため,現行の物理
学の枠組みでは記述しきれない。詳しい議論は別の機会に譲ることにして,こ
こでは,この過程が大脳皮質で生じる“密な”く協同現象>と理解できるとだ
け述べておきたい。
以上の議識をもとにすると,大脳皮質で神経興奮があるバターンをとってい
るとき,そこに一定の<意識>が生じていると仮定するのは充分に根拠のある
見解である。この考えをさらに押し進めれば,<意識>の内部で感じられるく気
分>はこのパターンの全体像を反映しており,ある形式に則って神経活動の連
鎖が生起することが,すなわち人間にとっての特定のく気分>に相当すると主
張できるはずである。したがって,く気分>の一種である<自由感>も,何ら
かの神経興奮のパターン――ないし(より一般化して)情報処理の形式――に
よってもたらされると考えて良いだろう。本章の課題は,この形式を求めるこ
とにある。
この問題設定がわかりにくいと感じられるならば,次のような素朴な例を思
い浮かべられたい。
物理的/生理的に可能で文化的な規制のない行為――例えば,(人のいない
場所で)指を伸ばしたり曲げたりするような――は,本人の<自由意志>に
よって任意に遂行できると主張する者もあるかもしれない。しかし,ためしに
指を曲げてみれば明らかなように,いくら「指よ,曲がれI」と念じても曲げ
ようというく気分>にならなければ指が曲がるはずもなく,また,自己を意図
的に「その気」にさせるのは一般に困難なはずである。にもかかわらず,多く
の人がこうした行為を自在に実行していると感じるのは,1つには,(同一条
件下での再現性や予言可能性が成り立つ)物理的な事象とは異なって,当該行
為が実行されるか否かを事前に予想できない――果して指を曲げる気になる
かどうか前もってはわからない――ことに起因する。実際,特定の行為を選
択するまでのプロセスが完全に覆い隠されているならば,各人にとっては意志
決定の結果が自分の内奥から卒然と湧き上がってきたかのように感じられても
さほど不思議はないのである。これを敷術して考えれば,意志決定の<自由>
は,必ずしも物理的な非決定論に根ざしているとは限らず,むしろ,決断の契
機が個人の意識から秘匿されていることをその必要条件としていると予想され
る。この予想は,
- (i)催眠術を施している間に無意識の領野に刷り込まれた指示を機械的に
履行した場合でも,多くの人はそれが自分の意志によることを疑わない。
- (ii)右脳と左脳を繋ぐ脳梁が切断された患者では,たとえ右脳の指示によっ
てある行為が為された場合でも,優位半球たる左脳はそれを自分の意志に
よるものだと主張する。
などの観察事実によって補強される。ここで,情報の流れという点に着目する
と,上に述べた決断過程の秘匿性は,「遂行すべき行為が識闘下で決定される
際に,その情報が意識野に提示されない」という形式的な状況に対応している
ため,これが<自由>を感じるための必要条件だとする主張は,<自由感>は
脳内部での情報処理の形式に由来すると見なす前段の結論をサポートする重要
な根拠となる。
もちろん,こうした秘匿性のみでは<自由感>をもたらすのに不足であり,
より詳細に情報の流れを分析する必要がある。この観点から,さらに議論を進
めていこう。
「不自由な」情報処理の形式
<自由感>を解明する手がかりを得るために,はじめに<自由>を感じられ
ない精神活動を分析し,そこで行われている情報処理の形式を明らかにしてみ
よう。
直観的にも自明なことだが,与えられた刺激から出発した信号が,いくつか
の処理系を連鎖的に経由し,筋収縮の反応をもたらして終結する反射弓におい
ては<自由感>が発生する余地はない。具体的に,指先に激しい痛みを覚えた
ときに無意識的に手を引っ込めるといった機械的な動作を支配する<脊髄反射>
を考えれば明らかなように,そこに<自由意志>が介在していないことは日常
体験を通じて知られる。それでは,こうした「不自由な」反射弓で観察される
情報処理の形式的特徴はどのようなものだろうか。脊髄反射の場合は,知覚信
号がほとんど加工されることなく脊髄に到達し,ここで刺激−反応の一種の“対
応表”に基づいてしかるべき応答が送り返されている。これをもう少し一般化
すると,
- (i)はじめに,各種の受容器から得られた信号がさまざまに組み合わされ
て処理系への入力となる。
- (ii)次に,与えられた入力信号が引金になって,学習や遺伝によって物理
的に規定されているいくっかの処理系の間で連鎖反応的に情報の受け渡し
が生じる。
- (iii)最終処理系から遠心的な出力信号が身体の各部位に投射される。
という情報の流れになっている。この過程で本質的なのは,情報の流れがいわ
ゆる樹構造をとって定方向的に展開している点にある。ただし,樹構造とは,
ちょうど枝振りの良い大樹のように,幹を中心にして枝と根が両方向に分岐し
ていきながらも,途中に(異なる枝先が合体してできる)ループが現れないよ
うな回路のトポロジーを指す。さて,ここで情報処理の形式をく気分>と等置
する先の議論を援用すれば,樹構造を持つ機械的/定方向的な反射弓において
は一般に<自由感>が生じないと主張できるはずである。もちろん,大脳皮質
に知覚情報が投射されない脊髄反射の観察をもとにこうした主張を引き出すの
は議論に飛躍があるが,(次に示すような)他の観察事実と突き合わせると,
この論旨はそれほど不自然ではない。
大脳皮質を経由する樹構造の反射弓が<不自由感>を現にもたらしている実
例と考えられるのが,精神病理学の領野でよく知られた<神経症>の症例であ
る。
心因性の疾患として知られる神経症(不安神経症,ヒステリー,恐怖症など)
は,器質的な精神障害とは異なって,総合的な状況判断がべースになって症状
が現れる点に特徴がある。具体的には,自分が置かれているのが発症の引金に
なる状況――例えば,大勢の視線が自分に向けられているとか,不潔な物に
手を触れてしまったというような――であることがひとたび認知されれば,
その後は機械的に諸症状を構成する反応のセットが(おそらく旧皮質に属す
る)“神経症発症”系から引き出されてくる。臨床的に観察される神経症的反
応には(四肢が硬直する,特定のホルモンの分泌が促進されるなどのような)
身体症状と(激しい不快感を覚える,ある儀式的行動をとらないと落ち着かな
いなど)精神症状が存在するが,各症状が(「恐怖感」のような)特定のカテ
ゴリーで包括できることから,“発症”系からの出力は,もともとごく単純な
信号として脳の各部位へ投射され,そこで症状がさまざまに“増幅”されて複
雑な表現型をとるに到ったと考えられる。したがって,強迫神経症の発症に本
質的な役割を果たしている情報処理の過程において,(状況を認知する)入力
部と(症状が増幅される)出力部ではかなり込み入った作業が行われているも
のの,両者を繋ぐ“発症”系の部分では,脊髄反射に似た機械的な変換操作が
実行されていると考えて良い。こうした状況を念頭に置けば,不安神経症の患
者が「心配する必要がないことは頭ではわかっていても,どうしても不安になっ
てしまう」と訴えるなど,自由意志の力ではどうにもならない強迫感が生じる
のは,“発症”系での機械的/定方向的な入−出力変換に原因があると推定す
るのが自然である。
“発症”系の性質を調べるには,動物行動学の知見が有益である。ここでは,
恐怖症を例に取るのがわかりやすいだろう。例えば,シマウマの子供は,ライ
オンの恐ろしさを学習するのに,実際に襲われるという(種の存続を危うくし
かねない)体験を必要としている訳ではない。そうではなく,何が恐怖の引金
となるかが“空白欄”になっている刷り込み機構が生まれつき備わっており,
親シマウマが特定の行動パターンをとったときにこの機構が解発されて,その
とき目にした対象に「待ったなしの恐怖」を感じるようになると想定される。
シマウマのように比較的安定した生活圏を確保している動物では,このメカニ
ズムはそれほどの破綻もなく機能する。ところが,生活体験があまりに複雑に
入り組んでいる人類に同様の機構が備わっていると,生存する上で必ずしも怯
える必要のない対象が,何かのミスで「恐るべきもの」として刷り込まれるケー
スも充分に予想される。これが,神経症的な恐怖症の発生の機序であろう。ー
般に,“神経症発症”系は一種の刷り込みのメカニズムを担当するシステムで
あり,神経症に見られる<不自由感>は,刷り込まれている本能が状況を顧慮
しないまま機械的に発現することに起因するものと思われる。
以上の議論は,「不自由な」意識が機械的/定方向的に情報が処理される場
合に派生することを示していた。これを逆に考えれば,意識の中で<自由>の
感触を得るためには,情報の流れに再帰的なループが存在し,ある情報処理系
からいったん他の部位に投射された情報が,何らかの加工を施された上で再び
元の処理系に帰還されるというプロセスが必要になると想像される。このよう
なループをもつ情報処理形式として直ちに思い起こされるのが,フィードバッ
クによる制御系である。そこで,手始めとしてフィードバック系に内在する意
識が果して<自由>かどうかを考察してみよう。
簡単にわかるように,設定された目標と実現された結果との差異に基づいて
出力を調節し直すという単純なフィードバックは,明らかに<自由感>とは縁
遠いものであり,脳で行われている情報処理の形式ともかなり相違している。
例えば,眼前のコップを手に取ろうとする際に視覚情報をもとに手の位置を
フィードバック調節しようとすると,両者の位置を目で確認してはじめて筋張
力の値が計算されるため,情報の流れとしては,外部由来の情報によって(手
の動きを与える)出力が制御されることになり,システムに内在する自律性の
範囲はきわめて狭小なものになる。―般に,フィードバック系での制御におい
て,目標値の変化に対する出力調整がスムーズに実行され,設定された出力が
常に目標値に近い結果を与える場合は,システム全体は実質的に外部情報に駆
動される他律系となる。逆に,誤差情報の帰還がすみやかに行われないときは,
しばしば目標値を通り過ぎるオーバーシュートや目標値のまわりでの振動を生
じてしまう。いずれにせよ,当該システムが系自身に内在する法則に基づいて
作動するという意味での<自律性>は期待できず,実質的に「不自由な」系で
しかない。
とは言うものの,<自由>を享受できるシステムとして,ある種の制御系を
想定するのは,基本的に正しい発想だと思われる。ここでいうところの制御系
とは,
- (i)外界に対して開かれており情報の出入りがある。
- (ii)出力信号の発生器や誤差の検出器など複数のサプ=システムを有する。
- (iii)ある部分から送り出された情報の流れが他の部分からの信号によって
制御される。
などの性質を示す情報処理システムである。思弁哲学によれば,外界から遮断
された内部で自律的に状態変化を行う閉鎖系での“純粋思惟”を想定すること
も可能だろうが,現実に,こうした非制御的なシステムで自由な思索が行われ
ているとは考えられない。意識を担った非制御系に近い例として(睡眠中にみ
る)<夢>を取り上げてみよう。<夢>の起原はいまだに判然としていないが,
睡眠によって知覚情報が途絶えている問に,皮質下からのランダムな入力が(お
そらく長期記憶の定着を図って)活動中の皮質部位に流れ込み,記憶を主な素
材とする自由な連想を生み出したものと推定される。また,<夢>の中で思い
描かれる運動のイメージが実際の筋収縮をもたらすと何かと不都合なので,レ
ム睡眠中は運動ニューロンに抑制が掛けられている。したがって,<夢>を生
成するシステムは,入出力系が実質的に遮断された閉鎖系を構成しており,信
号の制御は極端に抑えられた状態にある。ところが,経験的に知られるように,
人間は<夢>の中では<自由意志>を行使することはできず,与えられた状況
に従順に服さざるを得ない。この事実は,外界と情報をやりとりしながらその
流れを制御するという機能が,<自由>の享受のために重要な役割を果たして
おり,この機能を喪失すると<自由感>も同時に失われることを示唆する。も
ちろん,<夢>の中での不自由さが単に覚醒レベルの低さに起因する可能性も
あるが,傷病によって意識活動が低下しても自発的な意志が失われない患者が
存在することを思い起こせば,その蓋然性は低いと言えるだろう。
小脳のフィ−ドフォワード制御
フィードバック系以外で<自由感>を生み出す制御機構を探るに当たっては,
大脳に比べて比較的簡単な構造を持ちながら,随意的運動を制御する際に重要
な役割を果たす小脳が,おそらく最良のサンプルを提供してくれる素材である。
以下では,小脳が遂行している制御機構に焦点を絞って議論を進めたい。
小脳は,身体各部の受容器や大脳からの信号を受け取り,これをもとにして
延髄の前庭神経核や反射中枢である小脳核に運動を制御する信号を投射する器
官である。その主たる機能は,複数の筋活動の相互関係を計算して協調的な運
動を実現させることにあり,小脳の障害は,運動における推尺の異常――た
とえば,物を取ろうとして目標の手前や先を掴むような症状――や各種の運動
失調を惹起する。
小脳による運動制御の特徴は,(負荷が加わったときに筋張力を与える)伸
張反射などとは異なって,閉ループをもつフィードバック制御ではないという
点である。実際,多数の筋肉が関与する複雑な運動の場合,いちいち出力を検
出しながら発生したエラーを操作器の側に帰還させていたのでは,迅速な行動
が実現できないばかりか,信号伝達の遅れに起因するオーバーシュートが生じ
て(行き過ぎたり戻り過ぎたりの)病的な振戦を引き起こしかねない。こうし
た問題を回避して協調的な運動の制御を図るため,小脳では,あらかじめ筋張
力などの目標値を設定し,これに基づいて信号を一方的に投射する<フィード
フォワード制御>が実現されている。
小脳がフィードフォワード的な運動制御をしている例としてよく知られてい
るのが,前庭動眼反射弓と呼ばれる制御システムである。これは,物体を注視
しているときに(受動的または能動的な運動によって)頭の位置が変化した場
合,その動きに応じて眼球の方向を調節することによって,視野にプレが生じ
ないようにするものである。このシステムでは,頭の動きに関する情報は,頭
位の運動を検出する平衡器官から小脳を経由して前庭神経核に送られ,ここで
さらに動眼神経細胞に興奮/抑制を指示する信号に変換されて眼の動きを調節
するのに使われるが,眼球の運動によって視野のプレが補償されたかどうかの
情報は,中枢神経系には送られるものの,これを前庭神経核へと伝達する経路
は存在せず,負のフィードバック制御が行われている訳ではない。にもかかわ
らず,正常人ならば対象物体から視線を外さずに正しく注視し続けられるのは,
頭部がどれだけ動いたかという情報をもとに,視線を一定に保つのに必要な眼
球の回転角を小脳で計算し,この目標値に向かって運動筋をフィードフォワー
ド的に制御しているからである。このとき,小脳は(三半規管から得られた回
転速度に関するデータを積分するなど)目標値を求めるための一種のコン
ピューターとして機能しており,この計算に必要なさまざまなバラメーターは,
介在するニューロンにおけるシナプス結合数や後シナプス電位の形で,学習を
通じて小脳内部にインプットされている。
こうしたフィードフォワード制御は,単に小脳のみを介した機械的な動きに
便われているだけではなく,大脳連合野からの指令によって随意運動が遂行さ
れる場合にも利用されていると思われる。連合野が随意運動の指令を発すると
き,指令信号は運動野を経て小脳に送られる一方,小脳からの出力が大脳運動
野に接続する錐体路のニューロンに投射されるようになり,結果的に運動が実
行される以前に小脳と大脳の間でループが形成される。この過程で小脳が果た
している機能についてはいまなお不明な点が多いが,小脳が運動を制御する“コ
ンビューター”であることを考慮すれば,おそらく,運動を(部分的に)シミュ
レートしながら必要な筋張力の値を計算し,これをもとにそれぞれの筋肉を支
配する大脳運動野の各部位に適切な“準備”をさせていると推測される。ここ
で言う“準備”とは,生理学的には,運動に数百ミリ秒ほど先だって大脳運動野
に運動準備電位を誘起する過程を指し,これが小脳からの情報に基づいている
ことは,小脳を除去したサルで準備電位が著しく減少するという実験結果から
確かめられる。準備電位が誘起された状態では,筋張力それ自体は変化してい
ないが,これから行おうとしている運動で収縮する筋では,伸張に対する脊髄
反射が増幅し,逆に弛緩する筋の反射は減少することが判明しており,まさに
運動の“準備”が整えられていると言って良い。このように,運動の実行
以前にその状況を予測してしかるべき目標を設定するというフォーマットは,
フィードフォワード制御の典型である。
さて,現実そのものではなく“来たるべき”状況を想定しながら身体制御を
行う場合,目標となる身体の状態は,無意識の領域に完全に秘匿されるのでは
なく,具体的な<身体像>としてかなりの程度まで直観的にイメージされてい
ると考えられる。このことは,日常生活においてしばしば実感するところであ
る。具体的には,階段を急ぎ足に駆け上がって行った場合,最後にもう一段あ
ると思って足を出したものの実際には段がなかったときの。ガクッと崩れるよ
うな心理的衝撃を思い浮かべれば良いだろう。この例の場合は,まさに着地せ
んとする足のイメージが,階段との位置関係とともに前もって脳裏に描かれて
おり,この<身体像>に基づく(いまに着地の感触が訪れるという)予測が裏
切られたときには,短時間で新たな目標値を再設定しなければならないため,
脳が過負荷状態になって一時的なバニックが起きるのである。注意深い観察者
ならば、この瞬間に,思い描いていた階段のイメージが“崩壊していく”過程
が意識できるはずである。
いささか飛躍した想像かもしれないが,われわれが日常的に意識している自
己の身体についてのイメージも,実質的には,フィードフォワードされている
目標値がその主要部分を構成しているのではないだろうか。人はうっかりする
と,自分がいまどのような姿勢をしているかを主として視覚によって察知する
と誤解しがちだが,そうでないことは,目を閉じて視覚的情報を遮断しても,
自己の<身体像>が急激に失われないばかりか,身体の相互位置を判定して(指
で鼻の先を指示するような)簡単な動作をできるという事実から知られる。し
かも,こうした「視覚に頼らない」動作が,小脳が傷害されると一般にきわめ
て拙劣になることから,小脳による筋張力などの目標値の計算が,日常的な<身
体像>を構成する上で重要な役割を果たしていると予想される。もちろん,こ
の程度の“状況証拠”だけでは,認識される<身体像>が(知覚のみならず運
動の履歴に関する記憶を含めた)複雑に絡み合った多数の情報に裏打ちされて
いる以上,その構成過程を推断するのには不充分である。だが,必ずしも科学
的に厳密でない個人的な観察例で良ければ,簡単な実験を通じて,自己の身体
が単なる<知覚像>ではなく,より能動的な<行動体>として意識されている
ことが比較的容易に確認できる。具体的には,目を閉じてから全身の力を抜き,
その状態で自分がどのような姿勢をとっているかを判断して頂きたい。おそら
く,筋肉が完全に弛緩したままでは自己の<身体像>はあまりはっきりと思い
描けず,手足などが能動的に動かせることを意識した段階で,はじめて自分の
姿勢をそれと知るだろう。ただし,ここで言う「動かせる」状態とは,意識内
部でのシミュレーションによって確認できるような単なる<可能態>を指し,
実際に筋肉を緊張させて可動性をチェックする必要はない。感覚的には,運動
の際に使用される筋肉内部に,あたかもこれから運動を始めるかのような。緊
張感に似たかすかな知覚が生じるはずである。直接的な証拠はないが,この状
態は,大脳運動野に誘起される準備電位と密接に結びっいていると考えられ,
遂行すべき目標値によって構成された<身体像>が意識されたものと解釈でき
る。
一般に,外部知覚が残存している状態でこれに基づいて――例えば,目を
閉じる以前に観察しておいた視覚情報を利用したり,体を移動したときの運動
知覚を積算したりするような方法で――姿勢を判定できる場合は,空間内部
に定位されている身体が視覚的なイメージとして現れることが多いが,このイ
メージは,身体の<能動性>の意識と重ね合わされてはじめて<自己>への帰
属感を生むもので,それだけでは幻覚ないしは夢に近い“虚像”に過ぎない。
いささか文学的な言い方をすれば,目に映る像としては自分の手もすぐ前にあ
るペンと何ら変わることなく,ペンを手に取ろうと意識してはじめて掴む側と
掴まれる側との差から手が<自己>に属するものだと知るのである。視覚的イ
メージが自己の<身体像>を覚知する上で必ずしも第一義的な役割を果たして
いないと信じて良い理由は,日常体験の中にいくらでも見いだされる:
- (i)寝起きに目を閉じたまま半睡半醒の状態にあるとき,身体の姿勢が視
覚的イメージとして捉えられず,筋感覚が呼び覚まされるにつれて次第に
自分の姿が“見えてくる”ことからわかるように,視覚的な<身体像>は
筋感覚に依存して構成されるもので,これに先行することはない。
- (ii)白昼夢的な空想などにおいて観察されるように,視覚的イメージは意
識的/無意識的に容易に変形され,外部知覚に基づくコントロールがない
限り現実の身体状態から離反していってしまう。
人間の<身体像>が,現に自己がある状態についての知覚ではなく,能動的
に行動する際の目標値であるという仮説は,<自由>を論じるときに基本的な
役割を果たす。実際,われわれが肉体を自在に操っていると感じるのは,各瞬
間における行動が物理的因果法則を逸脱しているか否かではなく,身体が言わ
ば「自分の側に」あって自主的に企図された行為を遂行する場合である。逆に
考えれば、われわれにとっての<身体>が知覚される状態そのものであるなら
ば,(受容器レベルでの錯覚がない限り)これを積極的に変更するのは困難で
あるため,そこに<自由感>が生まれるとはなかなか理解しがたい。以下では,
こうした仮説をさらに押し進めて,単に運動機能にとどまらない。より高次の
認識活動においても,フィードフォワード的な目標値の設定が<自由感>の成
立に大きく関与していることを示しながら,人間にとっての<自由>の本質に
追っていきたい。
高次機能における機能分担とフィードフォワード
肉体的な運動の場合は,連合野から出された指令をもとに小脳で筋張力の目
標値が計算され,これが大脳運動野に送られて<身体像>のべースになると考
えられた。それでは,運動を伴わない純粋に内面的な思索の場合にはどうなる
のだろうか。もし,特定の思考を喚起するリリーサ−――『失われた時を求め
て』のマドレーヌ菓子のような――が与えられたとき,その時点における脳
細胞の興奮状態や記憶痕跡の配置に従って大脳の特定部位で一定の形式に則っ
て機械的に思考が進行するならば,その過程で人が<自由感>を覚えることは
ないだろう。運動制御のアナロジーを使って推測すれば,内面的思索に関して
も,大脳連合野がその大枠に関する指令を発してから,脳の異なる部位で思索
すべき内容についての目標値と見なされるべきもの――あるいは,厳密な目
標値ではない点を顧慮した・カギ付きの「目標値」――が設定されると考える
のが自然である。この点に関しては,心理学/生理学に基づく実験デ一夕が乏
しいために直接の検証は行えないが,間接的な傍証を積み重ねて正当性を認め
る方向で議論を進めていこう。
内面的思索の過程でフィードフォワードに似た制御方式が採用されていると
しても,その形式は,小脳を介した運動の調節とはかなり異なっているはずで
ある。特に,制御の実行および投射部位に関して,次のような点が指摘できる。
第1に,大脳で行われる思索では利用に供される素材が(種々の知覚や記憶な
ど)多方面にわたるため,「目標値」の計算は小脳のような限局された器官で
は不充分であり,主題に即して大脳のさまざまな部位で分担されていると考え
るべきである。第2に,「目標値」が投射されるのは,その複雑な情報を処理
した上でさらに思考を続ける必要から,主として再び大脳になると予想される。
とすれば,一見したところ,大脳内部で全ての情報が処理されることになり,
フィードフォワード制御が行われているとは考えにくいかもしれない。しかし,
既に多くの証拠によって確認されているように,人間の大脳皮質は部位に応じ
てその機能が裁然と分かれており,各部位の間で制御情報の交換をしながら活
動の調節がなされることは充分に可能である。大脳皮質内部には,もっばら投
射された制御情報に従って機械的に活動する“受身”の部位や,より自律的に
機能して他への指令を発する部位も存するだろうが,おそらく,連合野など意
識的思考と結びついている大脳の主要部分は,状況に応じて受動的/能動的な
振舞いを使い分けているのではないかと思われる。
思考の制御に関する上記の仮説を(部分的に)傍証する興味深い例として,「10
回クイズ」と呼ばれる子供の遊びを取り上げよう。このクイズにはいくつかの
ヴァリエーションがあるが,最も典型的なのは,次のようなものである:
- 相手に「ピザ,ピザ……」と10回繰り返して早口で唱えさせる。唱え終
わったところで,即座に自分の肘(ヒジ)を指さして「これは何か」と問
いかけると,ほとんどの人は(―瞬,逸巡してから)「膝(ヒザ)」と答
えてしまう。
このクイズの面白さは,自分が誤った答えをすることが充分に予期されなが
ら,なお正しく答えられないことを通じて,発話のような知的活動ですらも決
して意志の自由にならずに,ある種の機械的な制約を受けている事実を思い知
らされる点にある。このケースで人を誤りに導くメカニズムは,<保続傾向>
と呼ばれる人間(および高等動物)の心理特性のうちに見いだされる。<保続
傾向>とは,比較的汎用性のある類型的な応答の様式をいつまでも保持したが
る性質を指すもので,多くの場合,前頭葉障害の患者に神経心理学的な症状と
して見られる――例えば,この種の患者に筆記体のπとmが繰り返して現れ
る長い文字の列を転写させると,いつのまにか(πとmの区別をつけずに)
波状の模様を書くようになる――が,必ずしも病的な性向ではなく,一般
人にも多かれ少なかれ備わっている。上の10回クイズでは,最初のステップで
強く印象づけられた「ピザ」という音韻バターンがそのまま<保続的に>把持
されていたために,引き続く質問に対しても,これと類似した古型をもつ「ヒ
ザ」なる語が他に優先して想起されたと考えられる。この過程をより詳細にみ
れば,
- (i)「ピザ」という語を繰り返して唱えている間に音韻に関する中枢神経系
(聴覚性または口頭運動性の言語中枢)が“活性化”される。
- (ii)そこでバターンの特徴分析がなされ,この結果に基づいて類似したバ
ターンの連想が行われる。
- (iii)引き続く思考の展開に際しては,連想されている事項が優先的に援用
される。
という段階を経ている。ここで重要なのは,“活性化”されている部位でのバ
ターン連想が,意識的な精神活動を司っている大脳連合野から独立しているだ
けでなく,意識される思考が次にどの方向に進むかを無意識のうちに「前もっ
て」用意している点である。すなわち,10回クイズに見られるような人間の基
本的な<保続傾向>は,意識野の活動を大脳の他の部位がフィードフォワード
的に制御していることを示唆する。
上の見解に対しては,多くの反論が予想されるが,特に,代表的と思われる
二つの意見を取り上げよう。
第1に,(「ピザ」から「ヒザ」を思い浮かべるような)バターンの類似性
に基づく連想は,意識的思考を次のステップに進めるために記憶庫を探索する
よう指示が出された段階ではじめて実行に移されるのであって,決して「前もっ
て」目標値を提出しているのではないと主張されるかもしれない。しかし,こ
の反論は,反応潜時の測定を通じて実証的に覆すことができる。具体的には,
2つの単語を提出して両方とも有意味な語かどうかを判定させるとき,両方と
も有意味な場合は(nurse/butterのような)無関係な単語対よりも(bread/
butterのような)互いに関連した単語対の方が回答に要する時間が短くて済
む。この結果から,最初の単語が提示された時点で,その関連記憶が自動
的に探索され,該当する語が無意識のうちに頭に浮かんでくるというフィード
フォワード的な機能の存在が予想される。
第2の反論として考えられるのが,内面的思考の場合には(四肢の制御と異
なって)想起されたパターンが必ずしも次の思考を強制的に規定しない――10
回クイズの例では,保続傾向を振り切って正しく「ヒジ」と回答する余地が残
されている――一ことから,この連想は,単に(思考を円滑にするために)意
識野に対して複数の選択肢を提供する作業にすぎず,最終的な決断はより主体
的な意識活動に委ねられているとする主張である。確かに,一般的な思考過程
に現れるさまざまな連想は――例えば,食べ物の匂いをかいだときに料理や
食事のイメージが想起されても,思考がそのままこの主題に固定されるとは限
らないように――一必ずしもそれ以後の発想を規制するものでない。しかし,
上の主張が「意識活動がフィードフォワード的に制御されている」という命題
に対する反論として成立するためには,最終的な選択がなされる過程が意識内
部に主体性を持って現れてこなければならない。ところが,自分の意識を省察
してみればわかるように,想起されたパターンの連鎖を断ち切ったり複数の候
補から特定のものを選び出したりするには,数百ミリ秒から数秒のタイムラグが
必要であり,この間に,次に進むべき思考内容が(それと意識されないうちに)
識閥下から提示されるのである。この過程は,明らかに意識による主体的な活
動ではなく,むしろ無意識的な情報処理を通じて新たな「目標値」が再設定さ
れたものと解釈される。このように,状況に応じて強制力に差があるものの,
思考の流れは,パターンの連想や関連記憶の呼び出しなどを通じて,広い意味
でのフィードフォワード制御を受けていると考えて良いだろう。
内面的な思考における情報制御のプロセスを分かりやすくするために,いわ
ゆる実働記憶(working memory)の概念を導入しよう。ここで,実働記憶
とは,他の部位からの指令を受けたとき優先的に呼び出される状態にある記憶
内容の総称で,記憶を司る神経細胞の一部が自励的な反響回路を構成して言わ
ば“過敏な”状態になったことに起因する。実働記憶は,神経細胞の“配線”
として物理的に固定されている記憶痕跡とは異なって,必要に応じて直ちに用
立てられるように手元に置いておくもので,人工知能のアナロジーを用いれば,
レジスターに収納されて即座に呼び出せる状態にある“キャッシュ・メモリー”
と同一視できる。どのような事項を実働記憶に取り込むかについての調節は,
おそらく前頭連合野の一部である前頭前野あるいは頭頂連合野が司っており,
該当事項を記憶している部位を活性化する指令を出すものと思われるが,実質
的なことは何も分かっていない。しかし,その機能を考慮すれば,実働記憶の
内容が思考の次のステップを方向づけることになるため,フィードフォワード
される「目標値」はここに供給されると見るのが妥当である。
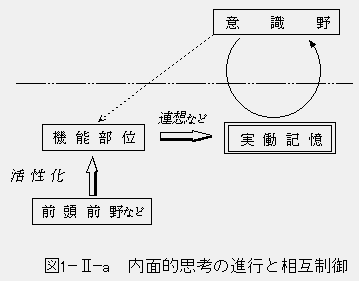 さて,内面的思考が進行する場合の相互的な制御は,きわめて単純化したモ
デルにおいては,実働記憶を中心に次のように構成されていると想定できる(図
1ーII−a)。すなわち,思考内容に傾向性を与える状況――例えば,(10回ク
イズのように)同一の興奮バターンの繰り返しや,(プル−ストにとってのマ
ドレーヌ菓子など)あらかじめ強化されていた応答を引き起こす刺激の提示の
ような――が生じた場合,この傾向に沿った記憶をもつ機能部位が(前頭前
野などの指令によって)活性化され,その内容が実働記憶に加えられる。意識
的な思考は,主としてこの実働記憶を呼び出しながら進行するため,その基本
的な方向性は,思考そのものに先だって構成される実働記憶の内容に大きく依
存することになる。こうした過程全体は,活性化される機能部位を小脳に,実
働記憶を大脳運動野に誘起される準備電位に読み換えれば,先に見た身体にお
ける運動制御と本質的に同じ制御様式であることがわかる。したがって,設定
された目標値が標的部位(=筋肉)に強制的な指令として送られるか,標的部
位(=大脳連合野)に到る途中に多くのサプシステムが介在して直接な規制力
が失われるかという相違はあるものの,大枠においてフィードフォワード制御
の形式を踏まえていることがわかる。
さて,内面的思考が進行する場合の相互的な制御は,きわめて単純化したモ
デルにおいては,実働記憶を中心に次のように構成されていると想定できる(図
1ーII−a)。すなわち,思考内容に傾向性を与える状況――例えば,(10回ク
イズのように)同一の興奮バターンの繰り返しや,(プル−ストにとってのマ
ドレーヌ菓子など)あらかじめ強化されていた応答を引き起こす刺激の提示の
ような――が生じた場合,この傾向に沿った記憶をもつ機能部位が(前頭前
野などの指令によって)活性化され,その内容が実働記憶に加えられる。意識
的な思考は,主としてこの実働記憶を呼び出しながら進行するため,その基本
的な方向性は,思考そのものに先だって構成される実働記憶の内容に大きく依
存することになる。こうした過程全体は,活性化される機能部位を小脳に,実
働記憶を大脳運動野に誘起される準備電位に読み換えれば,先に見た身体にお
ける運動制御と本質的に同じ制御様式であることがわかる。したがって,設定
された目標値が標的部位(=筋肉)に強制的な指令として送られるか,標的部
位(=大脳連合野)に到る途中に多くのサプシステムが介在して直接な規制力
が失われるかという相違はあるものの,大枠においてフィードフォワード制御
の形式を踏まえていることがわかる。
人間の<自由感>と情報制御の形式
おそらく,全ての(人間らしい生活を送っている)人間は,自分が物理法則
に完全に支配されておらず,何らかの意味で物理学の理論を超克した存在とし
て自由を享受していると感じているだろう。しかし,この<自由感>が何に起
因しているかは,必ずしも明確でない。既に述べたように,自分の指に対して
すら「曲がれI」と念じてもその気にならなければ曲がらないからである。こ
こでは,人間にとっての<自由感>―一すなわち,自分の思索が誰からも強制
されていないという信念の由来を探るに当たって,最も人間らしい精神活動で
ある言語的思考を議論の中心に据えるることにしよう。以下では,特に発話の
場面に絞って,人間が感じる思考の<自由>の本質について考えてみたい。
人が言葉を口にするとき,文法に適合した文章をはじめから意識している
ケースは稀であり,一般に,概括的な内容を念頭に置きながら逐次的に文を作っ
ていくはずである。にもかかわらず,通常は,あまり極端に文法から逸脱しな
い,あるいは,少なくとも発話された文から適格文を再構築できる程度の文を
話せるのは,無意識のうちに文法に基づいて文章を構成する作業を行っている
からである。この作業を段階的に説明すると,次のようになる:
- (i)はじめに,基幹となる事項を中心に文の基本的構図が指定される。具
体的に言えば,「きのう私はメアリーにバラを贈った」という文章を「バ
ラ」に力点を置いて述べる場合,この「バラ」にまつわるさまざまの関連
事項が意味のネットワークを構成しているが,その中から,自己の能動的
行為を軸とする部分が文章に変換されるべき対象と定められる。この発話
内容を記号で書けば,
S:(能動的行為)→バラ
となるが,ここで現れる「バラ」はいまだ言語化される以前の(意味ネッ
トワークのノードを構成する)イメージに過ぎない。
- (ii)次に,Sに関連する事項についての連想を進めて,文章に含まれるこ
とになる語を探索し,適当なものを実働記憶に加える。この段階で,(「バ
ラ」や「メアリー」などの)いくつかの言語概念が引き出される。
- (iii)これとほぼ同時に,指定されている基本的構図をもとに,各語に統語
論的な機能を付与する。この作業には,助詞や前置詞の付加,あるいは文
法機能を有する語尾変化や語順の決定などが含まれる。
- (iv)以上をまとめて,適格と思われる文を構成して発話する。ただし,発
話されている文は常にフィードバックされるため,発話の途中で文法的に
破格な,あるいは基本的構図に合致しない単語列を発見して言い改めるこ
とも可能である。
ここで述べたような発話作業は,ことばを口にする際の心理過程を注意深く
省察することによってもある程度は窺い知られるが,その具体的過程が最も端
的に現れるのは,言い間違いや言い淀みの局面においてである。上の例を再び
引用すれば,「バラ」を中心に語ろうとするときに,まず「バラをね」と言い
始めてから暫し次の句に詰まり,ややあって「贈ったんだよ,きのうメアリー
に」と続ける場合がある。こうした言い淀みが生じたのは,(i)の段階で「バ
ラ」のイメージを先行的に言語化して口に出してしまったため,関連事項を概
念的に整理して適格な文章を構成するのに手間取ったからである。ときには,
文法的な格構造を決定する前にロを開いて「バラが」と言い始めてしまい,直
ちに(主格から目的格へと)訂正を余儀なくされることもあるだろう。また,
関連事項を言語化する余裕がないまま,「アレを」とか「ナニが」のようなダ
ミーを含んだ文を口にするケースも稀ではない。このような破格の文が生成さ
れる理由は,人間が発話を決意するのが上の(i)から(ii)の段階であり,往々に
して(iii)の構文決定に到る以前に口を開いてしまうためと推測される。
このような発話の過程を考えると,その情報処理の形式が,小脳を介した運
動制御にきわめて類似していることに,いやでも気づかざるを得ない。人間は,
何かを話し始めるとき中心となる概念やテーマを意識するが,その関連事項の
選択や統語論的な構造の決定は無意識のうちに行っている。したがって,情報
の流れを考えると,意識野に発話のテーマが提示された後,それが大脳の適当
な機能部位に送られてから,長期/短期記憶との比較検討に基づく関連事項の
喚起を経て,発話される文の全体ないし適当な部分の句構造が出来上がるまで
の間は,識闘下で情報処理が進められ,その過程が意識野にフィードバックさ
れることはない。むしろ,適格と思われる文の構造がまとまってはじめて,こ
れが口や舌の運動命令に変換されて運動野に投射されるのと平行して,文の“素
型”として意識野に送られ,その適格性の検討がなされているようである。実
際,発話のときに注意するとかなりはっきりと分かるように,われわれは口に
出す直前に統語論的な構造を整えた形での文を意識しており,文法的または社
会的に不適当な部分があれば,その段階で訂正することも可能である。形式的
な考察から分かるように,このく文素型>――と呼ばせて頂く――は,運動
制御における<身体像>と次の各点で類似している。
- (i)いずれも意識を担う大脳連合野の指令に基づいて識閾下で構成されて
いる。
- (ii)大脳運動野に投射され,運動命令として一方的に(制御のために再び
大脳にフィードバックされることなく)身体に送られる。
- (iii)これと同時に,実現されようとしている行動のイメージとして大脳連
合野で意識化される。
このように,発話というきわめて高次の精神活動においても,基本的には
フィードフォワード的な制御が行われていることは注目に値する。
さて,ほとんどの人は,発話において人間は<自由>を享受していると感じ
ているようだが,その根拠はどこにあるのだろうか。素朴に考えれば,そもそ
も「何を発話するか」を選択するときに物理的束縛から逃れられているとし
て,く発想の自由>が結論されるだろう。だが,子細に検討するとその妥当性
は疑わしくなる。なぜなら,人が何かを語ろうという気になるとき,往々にし
て実に些細な事件がその契機になっているからである。例えば,眼前の美しい
「バラ」にふと目を止めたことをきっかけにして,自分がきのうメアリーに贈っ
たバラについて語り始める人もあるだろう。このケースでは,発話は自発的に
なされたというよりも,外界に由来する情報に導かれたと見なすべきである。
これに対して,「なるほど,知覚情報は思考の流れに影響を及ぼしたかもし
れないが,そこから派生したさまざまな想念の中で何を口にするかは当人の自
由にまかされている」と主張する者があるだろうが,次の点を注意してこの反
論をかわそう。確かに,発話の契機が与えられてから実際に口を開くに到る間
に膨大な知的作業が介在するため,この過程での自発性こそが人間の自由の本
質だと感じられるかもしれない。だが,この介在過程をいくつかの部分に分解
すると,各部分が開始される時点での自発性は,発話の場合と同様に必ずしも
明らかではない。具体例として,発話に到達する以前の段階として,内語のケー
スを取り上げよう。人間の思考には,受動的な知覚的イメージの連鎖から明確
に区別される過程として,言語概念を統語論的に構成する能動的な内語が存在
する。内語が実行されているときには,舌や口の筋肉を支配する大脳運動野が
活性化しており,声を出さない点を除けば通常の発話とほとんど変わるところ
がない。ところが,実際に自分がなぜある文を思い浮かべるに到ったかを反省
してみればわかるように,人間がどのような契機からイメージを言語化するか
は通常は偶然に委ねられており,意志的な操作が関与することはない。一般的
に言って,(イメージに基づく連想から内語による統語論的操作へというよう
に)知的方略を変更する際に,われわれの心理はその時点での知覚や想念の配
置によって形成される<気分>に支配されており,小さな事件をきっかけとし
て波紋が広がっていきながら,最後には有無を言わさない形である認識の体制
を取らざるを得ない心境になるはずである。
同じような<気分>の支配は,意志的に言語化の作業を継続するケースにも
見いだされる。例えば,懸命に物の名前を思いだそうとするとき,素朴な直観
では,意志の力でイメージの世界から言語の領域へと飛躍するように感じられ
るかもしれない。しかし,実際に行われているのは,言語記憶の体系の中でバ
ターンの比較に基づく探索を行いながら,類似したバターンの語を発見するた
びに意識野に戻して目的の語かどうかを判定し,その結果に応じて探索を継続
したり打ち切ったりするという・ごく機械的な作業である。しかも,なぜこの
ような作業を始めるかは,内語の場合と同様に純然たる気分の問題であって,
積極的な自発性に基づく訳ではない。
以上の考察から明らかなように,発話において人間に<自由>があるとして
も,それは「何を話すか」を選択する局面で発揮されるのではない。したがっ
て,ことばを発するときに人間が感じる<自由>の根拠を論じるためには,「い
かに話すか」という点に着目するのが妥当だろう。
結論から言えば,人が発話において<自由>を感得できるのは,ことばが意
識の中で,あたかも自己増殖するかのように豊かに拡大し整理されていくから
ではないかと思われる。例えば,自分が「バラ」を使って行った能動的行為に
ついて語ろうと思うだけで,無意識的な操作によって(「メアリ−」や「デバー
ト」などの)関連する事項が喚起され,自動的に統語論的な規則に適合した文
(「きのう私はメアリーにバラを贈った」)が“口を衝いて”出てくるのである。
この性質が<自由感>の根底にあることは,日常体験の内省を通じて確認でき
る。実際,発話する過程での意識内容に注意するとわかるように,人が自由な
会話を楽しむのは,いちいち文法規則や概念の想起に心を煩わされずに次々に
湧き上がってくることばの流れを味わうときだろう。このときの脳内部におけ
る情報の流れを考えると,はじめに発話のテーマが意識野に提示され,その後
は無意識的な活動を通じて実働記憶に加えられた関連語句が文素型として形を
整えられてから送り出されるという体制になっている。したがって,意識され
る範囲では,最初に与えられた発話の“タネ”が,外界の物理法則とは無関係
に,各人の記憶や性向を反映させながら成長していくように感じられるのであ
る。直観的に考えても,このような情報の自律的成長を<自由感>の根拠と見
なす見解は合理的なように思われる。
そこで,このアイディアを一般化して,人間にとっての<自由>とは,意識
野に示された(発話や内的思考を含めた広い意味での)行動の大綱が,無意識
的な活動を通じて関連する諸事項を取り込みながら豊かで実質的なものに練り
上げられ,しかるのち再び意識野に帰還されるという形式そのものに由来する
と仮定してみよう。この仮定は,上に示したように発話における<自由感>を
説明できるのみならず,これと形式的に類似していることから,小脳を介した
身体制御の場合にも当てはまるものである。それ以外の任意の認識や複雑な運
動については,この仮定の妥当性は直ちに確認できるものではないが,人間に
とって最も高次の精神的営為である言語活動で成り立っている以上,全ての精
神活動に敷術して論じることは充分に正当性が認められると思われる。
人間の<自由>が情報処理の形式に由来すると見なす立場からは,<自由>
が成立するための条件として,少なくとも,
- (i)情報処理系が,意識を担う部位と無意識的活動を行うそれ以外の部位
に階層化されている。
- (ii)無意識的な情報処理系で形成された情報を意識野に提出するための実
働記憶の機能が備わっている。
などの点が必要である。そこで,節を改めて,<自由>を感じられなくなった
精神病患者にどのような障害が生じているかを調べることによって,上の仮定
の妥当性を検証してみよう。
©Nobuo YOSHIDA
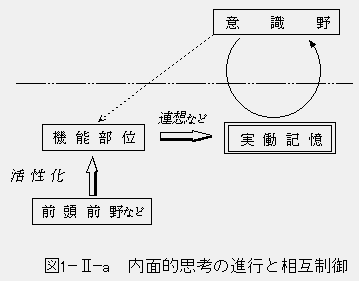 さて,内面的思考が進行する場合の相互的な制御は,きわめて単純化したモ
デルにおいては,実働記憶を中心に次のように構成されていると想定できる(図
1ーII−a)。すなわち,思考内容に傾向性を与える状況――例えば,(10回ク
イズのように)同一の興奮バターンの繰り返しや,(プル−ストにとってのマ
ドレーヌ菓子など)あらかじめ強化されていた応答を引き起こす刺激の提示の
ような――が生じた場合,この傾向に沿った記憶をもつ機能部位が(前頭前
野などの指令によって)活性化され,その内容が実働記憶に加えられる。意識
的な思考は,主としてこの実働記憶を呼び出しながら進行するため,その基本
的な方向性は,思考そのものに先だって構成される実働記憶の内容に大きく依
存することになる。こうした過程全体は,活性化される機能部位を小脳に,実
働記憶を大脳運動野に誘起される準備電位に読み換えれば,先に見た身体にお
ける運動制御と本質的に同じ制御様式であることがわかる。したがって,設定
された目標値が標的部位(=筋肉)に強制的な指令として送られるか,標的部
位(=大脳連合野)に到る途中に多くのサプシステムが介在して直接な規制力
が失われるかという相違はあるものの,大枠においてフィードフォワード制御
の形式を踏まえていることがわかる。
さて,内面的思考が進行する場合の相互的な制御は,きわめて単純化したモ
デルにおいては,実働記憶を中心に次のように構成されていると想定できる(図
1ーII−a)。すなわち,思考内容に傾向性を与える状況――例えば,(10回ク
イズのように)同一の興奮バターンの繰り返しや,(プル−ストにとってのマ
ドレーヌ菓子など)あらかじめ強化されていた応答を引き起こす刺激の提示の
ような――が生じた場合,この傾向に沿った記憶をもつ機能部位が(前頭前
野などの指令によって)活性化され,その内容が実働記憶に加えられる。意識
的な思考は,主としてこの実働記憶を呼び出しながら進行するため,その基本
的な方向性は,思考そのものに先だって構成される実働記憶の内容に大きく依
存することになる。こうした過程全体は,活性化される機能部位を小脳に,実
働記憶を大脳運動野に誘起される準備電位に読み換えれば,先に見た身体にお
ける運動制御と本質的に同じ制御様式であることがわかる。したがって,設定
された目標値が標的部位(=筋肉)に強制的な指令として送られるか,標的部
位(=大脳連合野)に到る途中に多くのサプシステムが介在して直接な規制力
が失われるかという相違はあるものの,大枠においてフィードフォワード制御
の形式を踏まえていることがわかる。