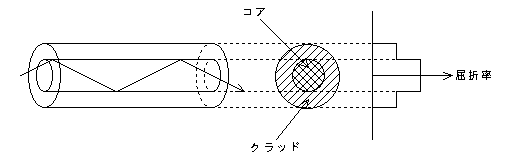○知的財産権とは何か
- こんにち、日本をはじめ、多くの国々では、自由主義経済が採用されている。
これは、市場原理に則って生産や流通をシフトさせる体制で、経済発展を実現するためにきわめて効果的である。
ところが、産業界に革新をもたらすような高度な技術に関しては、一定の条件の下に、その発明者(ないし権利を
譲渡された法人)に独占的な使用権を与える制度が実施されており、自由主義でありながら技術を勝手に使うことが
許されていない。これが、いわゆる特許制度であり、高度技術社会を維持する上で欠かすことのできない仕組みである。
- 自由主義体制に反するかのような特許権がなぜ認められているかは、次のような事情による。
- 現在のように技術の高度化が進むと、新しい技術の開発には、膨大な費用と長期の年月、それに有能な人材が必要となる。
例えば、通常の医薬品の開発には、俗に10年100億(円)がかかる(最近では、20年200億という声もある)と言われる。
こうした莫大な先行投資をしても、新しく開発した技術を他の会社に勝手に利用されてしまうと、資金の回収ができずに
経営に大きなダメージを受けてしまう。
こうした事態を避けるために、技術の開発者(発明者)に独占的な使用権を与えて制度的に保護しようと言うのが、特許の考え方である。
- 現在では、工業的な技術だけではなく、さまざまな知的財産に関して独占的な使用権を認める制度が導入されている。
こうした権利は、知的財産権(Intellectual Property Rights)と総称されており、特許権の他に、
工業所有権として実用新案権や意匠権、商標権など、文化的創作物に関する権利として著作権などがある。
ただし、以下では、技術問題を論じる上で最も重要な特許権に的を絞って議論を進めることにする。
- 日本の特許法には、次のような条文がある:
- (目的)この法律は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。(第1条)
- (定義)この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(第2条第1項)
- (要件:有用性、新規性)産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。(第29条第1項)
- 特許出願前に日本国内において公然知られた発明
- 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
- 特許出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明
- (要件:進歩性)特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が…容易に発明をすることができたときは、その発明については…特許を受けることができない。(第29条第2項)
- (効力)特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有する。(第68条)
- また、特許の出願から権利満了までには、次のような段階がある:
- 特許出願:次の書類を特許庁に提出
- 願書(出願人の住所・氏名、提出年月日、発明の名称)
- 明細書(発明の詳細な説明、特許請求の範囲〈クレーム〉)
- 必要な図面、要約書
- 出願公開:出願18ヶ月後に審査段階によらず明細書を公開
- *出願人に補償金請求権、先願としての地位が与えられる
- 審査請求:出願後7年以内に特許庁長官に出願審査を請求
- 審 査:資格を持つ特許庁審査官により審査
- *拒絶する場合は理由を通知、出願人は補正または反論できる
- 特許査定:拒絶する理由がない場合は特許査定を決定
- 特許登録:特許査定の決定後、登録料を支払えば登録される
- 権利満了:特許出願日から20年経つと権利消滅
- ここで重要なのは、特許制度が、単に、発明者を保護するだけでなく、技術の発展を促すという点である。
実際、特許制度があれば、研究・開発に多額の資金を要したとしても、新たに開発した技術を独占することによって莫大な利益を
手にする可能性も生まれる。技術が独創的で他の追随を許さないものであればあるほど、見返りも大きい。
こうして、特許制度は、すぐれた技術を生み出すインセンティブとなる。
- ただし、特許は、独占的使用権というきわめて強力な権利を発明者に与えるものだけに、おいそれと発行する訳にはいかない。
特許権に値する高度な技術かどうかについて、専門家による審査が行われるほか、
特許権が産業の育成のために有効に機能するように、さまざまな取り決めがなされている。
- 特に重要なのは、公開制度である。
中世ヨーロッパでは、技術の流出を防ぐためにギルド制度が生まれ、ギルドで承認された者のみに技術の伝達が行われた。
しかし、こうした閉鎖的なやり方では、技術の健全な発展は望めない。
特許制度は、独占的な権利を与える見返りとして、技術の中身を公開することを義務づけている。
日本の場合、出願後18ヶ月で、特許が成立しているか否かを問わず技術内容を詳述した明細書を公開しなければならない
(アメリカでは、特許が成立した後で初めて公開される)。
こうした技術の公開は、他社に企業戦略の手の内を明かすという危険もある。
実際、あるメーカーが新分野への事業展開を図ろうとすると、その方面への特許出願が多くなるので、
企業アナリストらに簡単に見破られてしまう。
だが、公開された特許内容に基づいて技術提携が画策されることもあり、産業育成の上で公開制度は好ましいものと言える。
- もう1つのポイントが、独占的な使用が許される範囲の画定である。
ここで言う「範囲」には、特許の継続期間と権利が認められる技術内容がある。
- 特許権の継続期間は、日本では、特許出願後20年となっている(他の多くの国も同じ)。
特許によって独占的な製造・販売を行っているメーカーは、しばしば類似技術による出願を繰り返して保護期間を長引かせようとする
(集積回路におけるテキサス・インスツルメンツやインスタント・カメラでのポラロイドなどの企業戦略である)。
しかし、特許になるような新しい技術をいつまでも編み出していくことは、どんな企業にとっても難しい。
かつてゼロックスは、多数の特許をもとに複写機の市場を完全に独占しており、
IBMなど他の企業がこの分野に進出することを拒んできた。
だが、70〜80年代に基本特許が次々と満了になると、さしものゼロックスも独占体制を維持できず、こんにちでは、
多くの企業が続々と参入しているが、それがかえって新機能の開発競争を促すというメリットも生んでいる。
医薬品の分野では、売れ筋商品の特許権が消滅すると、同じ成分を含んだ新薬がゾロゾロと現れる(いわゆる「ゾロ新」である)が、
特許使用料が含まれない分だけ安くなるため、医療費の高騰を防ぐ切り札と目されている。
- 継続期間が曖昧さなく定められるのに対して、しばしば紛争の種になるのが、保護が受けられる技術内容の範囲である。
発明者からすると、できるだけ広範囲にわたって特許が認められた方が利益を独占できるので好ましいが、
産業育成の観点からすると、範囲の過剰な拡大は、独占による産業の停滞を招く恐れがあるので、避けたいところである。
例えば、電信機を発明したマルコーニは、電磁波を利用した通信手段全般について特許を獲得しようとしたが、これは、産業への
影響があまりに大きいことから、審査で拒絶された。
特許権が認められるのは、産業を停滞させるほどには広くはないが、発明へのインセンティブがなくなるほど狭くはない程度に
定められた一定の範囲内であり、その内容は、公開される出願書類の明細書に記されている。
たとえ類似した技術であっても、この範囲から少しでもはみ出ていれば、特許による独占権の行使はできない。
だが、いくらことばや図でもって細かく説明しても、個々の製品に使われる技術を完全にカバーできるわけではない。
このため、「この製品は特許権を侵害している」「いや、していない」といった争いが後を絶たない。
こうした紛争は、最終的には、裁判の場で、問題となっている技術が、特許の明細書に記されたクレーム
(特許請求の範囲)に入るかどうかを判定することによって決着がつけられる。
○日米テクノロジー・ウォー
- 1980年代以降、日本とアメリカの間で、特許を巡る争いが頻発した。
特許侵害を認められた日本企業は、しばしば莫大な賠償金を支払わされ、経営面でも多大な影響を被ることになった。
- こうした動きの背景には、当時、構造不況への対処を迫られていたアメリカ政府が、基本特許を多く所有する国内企業からの声を受けて、
それまでのアンチパテント(特許冷遇)政策をプロパテント(特許優遇)政策へと転換したことがある。
この政策転換の流れの中で、米企業は、特許使用料の値上げや特許権侵害の訴訟を行い、多くの場合、
特許権保持者に有利な成果を上げている。
- ただし、プロパテント政策は、必ずしも、対米輸出で黒字を続けていた日本企業を狙い撃ちするものではなかった。
コダックとポラロイド、マイクロソフトとアップルのように米国企業同士が熾烈な裁判闘争を繰り広げたケースも少なくない。
この過程は、むしろ、アメリカ国内において、知的財産の重要性が認識されるようになり、名ばかりが喧伝されてなかなか実体が伴わなかった
情報化社会を現実のものとする動きが活発化したものと解釈することができる。
実際、プロパテント政策なくして、こんにちのマイクロソフトやインテルの繁栄はあり得ないと言っても良い。
- 特許紛争が、特に日米間で数多く起こったのは、特許についての基本的な考え方に差があったためである。
このことは、両国の産業発展のプロセスを考える上でも重要である。
- アメリカにおいて、特許は、何よりも、それまで誰も考えなかった革新的な発明を行ったパイオニアに与えられる権利である。
アメリカは、エジソンを生んだ発明大国であり、今世紀の産業構造を変えることになるジェネリック・テクノロジー
(その中には、電話、飛行機、トランジスタ、コンピュータ、原子力発電、レーザーなどがある)を作り上げてきた。
アメリカを世界のリーダーたらしめている活力の源が、他の追随を許さない技術開発力にあることを、アメリカ人自身がよく知っている。
エジソンに倣って、特許権を駆使して莫大な利潤をあげる個人発明家(レメルソンやハイヤットが有名)も数多い。
- このような伝統の下、アメリカでは、新しい産業を生み出せるようなパイオニア的な発明が高く評価され、具体的な製品の形になっていないアイデアの
段階でも積極的に特許権を与える傾向が強い。アメリカの企業が保有する基本特許の多くが、こうした「アイデア特許」である。
- さらに、特許侵害になるかどうかを考えるときも、明細書の文言そのものよりも、
特許のもとになっているアイデアを利用しているかどうかを判断基準とする。
これが、特許裁判においてアメリカの裁判所がしばしば採用する均等論(doctrine of equivalents, equivalent theory)で、
「実質的に(substantially)同一の方法/機能によって実質的に同一の結果を実現する発明は、等価(equivalent)と見なす」
主張である。
この法理がアイデアに基づく基本特許に適用されると、日本企業が考える以上に、特許の適用範囲が拡大されることになる。
- このほかにも、アメリカでは、パイオニアたることが期待される個人発明家を優遇する仕組みが、さまざまに盛り込まれている。
例えば、アメリカ以外のほぼすべての国が、同じ発明をした場合には先に出願した方が特許権を取得する先願主義を採用しているにもかかわらず、
アメリカでは、先に発明をした方に特許権が与えられる先発明主義がとられている。
どちらに特許権が与えられるかという争いになった場合は、発明過程を記したノート類などが証拠として使われる。
アメリカが先発明主義にこだわるのは、先願主義では、出願書類を制作する専門スタッフを雇える大企業が個人発明家に比べて有利になって
しまうからだとされる。
- アメリカが国内でジェネリック・テクノロジーを生み出すことによって産業を発展させたのに対して、日本は、
欧米に追いつき追い越せというムーブメントを通じて経済復興の道を歩んできた。
この場合、基本的な技術開発力は欧米企業が圧倒的に勝っているので、アイデアに基づく基本特許を広範に認めると、
日本のマーケットを欧米企業に独占されてしまう危険がある。
このため、基本特許の範囲をできるだけ制限し、従来技術よりも製品の機能や品質を向上させられるものに積極的に特許を与え、
もって国内産業の活性化を図ろうとした。
欧米製品よりも少しでも優れた製品を製造・輸出し、国際競争に互していこうとする国民意識の現れである。
こうして、日本では、いわゆる改良特許が重視されることになる。
- 改良特許を重視する考えは、到る所に現れている。
例えば、出願書類には、当該技術の具体的な実施例を書くことが求められる。
単なるアイデアだけでは、審査を通過することが難しい。
また、特許権の範囲も実施例に基づいて定められ、拡大解釈される余地を極端に減らしている。
裁判になった場合は、明細書に記された文言通りに特許権の範囲が解釈され、一部でも明細書と異なる技術が用いられている場合は、
特許侵害とは認められない。このように特許の範囲を狭く解釈する立場は、アメリカから厳しく批判され、近年、見直しの動きもあるが、
いまだにアメリカ流の考え方とは大きな隔たりがある。
- 特許制度は、いわゆる属地主義がとられており、アメリカでの紛争はアメリカの制度で、日本での紛争は日本の制度で
裁かれるため、日米の特許紛争では、どちらの国で争われたかが裁判結果に決定的な影響を与えている。
このことは、これから見ていく実例に、如実に現れている。
○特許紛争の実例I アメリカでの裁判
- 日本企業が製品をアメリカに輸出し、アメリカ企業がこれを特許侵害だと訴えた場合は、アメリカの特許制度が適用される。
こうした裁判例では、アメリカ企業が持つ特許の範囲が広範に解釈され、日本側が敗れるケースが多い。
特に有名な2つの事例を取り上げたい。
- コーニング 対 住友電工 「光ファイバ」
- 住友電工がアメリカに輸出した光ファイバが特許を侵害しているとして、輸入差し止めと損害賠償を求めて
コーニングが起こした訴訟。
途中で住友電工が特許無効を訴えて逆提訴するなど、裁判は二転三転したが、次のような過程を経て、最終的に住友電工側の敗訴となった。
- 1984.3. コーニング 国際貿易委員会(ITC)に住友電工の光ファイバが特許を侵害しているという理由で輸入差し止めを請求。
- 1984.8. 住電 コーニングの特許は無効だと提訴(ノースカロライナ州連邦地裁)。
- 1984.12.コーニング 住電に対し損害賠償訴訟(ニューヨーク連邦地裁)。
- 1985.4. ITC 住電製品は915特許侵害と認定。ただし、実質的な被害がないため輸入差し止め請求は却下。
- 1986.11.住電 コーニングが住電の製法特許を侵害していると逆提訴。
- 1987.10.ニューヨーク連邦地裁 住電はコーニングの製法特許は侵害していないが構造特許は侵害していると判決。
- 1989.2. 連邦巡回区控訴裁判所 住電の控訴を退ける。
- 1989.5. コーニングの特許権満了。
- 1989.12.住電 コーニングと和解(賠償金2500万ドル)。
- この裁判に敗れたことにより、住友電工はアメリカでの光ファイバ市場から全面撤退を余儀なくされた。
輸出開始直後の提訴なので売上額が少ない段階での撤退となり、傷は浅くて済んだとも言えるが、将来性のあるマーケットを
失ったことは住電にとっては遺憾な結果だったろう。
もっとも、この経験を通じて住電はアメリカ流の技術戦略を学んだらしく、1986年の高温超伝導騒動の際には大量の周辺特許を
出願して市場への足がかりを作ったほか、1989年の和解直後に、それまで争ってきたコーニングと新素材関連の技術提携することを発表
して周囲の日本人を驚かせた。
- この裁判で問題になったのは、1970年にアメリカで成立した2つの特許である。
- 1つは、光ファイバの製法に関する特許で、母材に含まれる水分を取り除く技法を記載している。
これは、コーニングが開発した独自の技術で、日本でも特許が成立したものだが、住友電工は、これとは異なる脱水技術を用いて
製品を製造しているので、特許侵害にはならないと判断された。
- 特許侵害になると認定されたのは、もう1つの構造に関する特許である。
これは、酸化ケイ素製の光ファイバの基本的な構造を記載したもので、きわめて広範な基本特許である。
いくつかのクレームを含むが、「純粋な酸化ケイ素(SiO2)からなるクラッドと、
15%以下の添加剤が入った酸化ケイ素からなるコアによって構成される光ファイバ」というのが、最も基本的な
クレームである。光ファイバは、屈折率の異なる内側のコアと外側のクラッドから構成され、両者の界面で
全反射を生じさせることにより、ファイバに沿って光を伝えるものである(下図参照)。
コーニングの構造特許は、屈折率の差をコアに添加剤を加えることによって与えるものだが、
その内容はきわめて一般的で、ガラスでできた光ファイバのほぼすべてが該当してしまう。
ちなみに、コーニングは日本でも特許を出願したが、あまりに広範すぎる内容のため審査で拒絶されている。
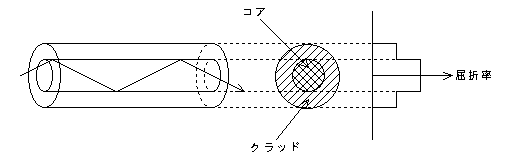
- 透明なファイバを用いて光を伝えるというアイデア自体は、かなり古くからある。
このため、必ずしも独創的でない発明に、あまりに広範な特許を認めているという批判もある。
しかし、不純物を適度に添加した酸化ケイ素を素材として用いるというコーニングの技術は画期的であり、
それ以前には何人もなしえなかった光ファイバの実用化に世界で初めて成功した事実は動かしがたい。
アメリカでは、こうしたパイオニア的な業績は特に高く評価される傾向があり、それが、
きわめて広範囲をカバーする基本特許の成立に結びついている。
- これほどの特許の障壁があるのに、住友電工は、なぜあえて光ファイバの輸出に踏み切ったのか。
そこには、特許侵害に当たらないとする確固たる論拠があった。
- コーニングの構造特許によると、コアとクラッドは次のような素材から作られている:
- クラッド=純粋なSiO2
- コア=SiO2+(15%以下の)添加剤
- これに対して、住友電工が輸出した製品は、次のような素材でできていた:
- クラッド=SiO2+添加剤
- コア=純粋なSiO2
- すなわち、コーニングが、コアに添加剤を加えて屈折率を上げたのに対して、
住友電工は、クラッドに添加剤を加えて屈折率を下げたのだ。
この組成は、明らかに、コーニングの特許に記載されているものとは異なる。
特許の範囲を明細書の文言通りに解釈するならば、住友電工製品は、コーニングの特許を侵害していない。
- しかし、裁判では住友電工の主張は認められなかった。
すでに述べたように、アメリカでは、均等論に基づいて、特許の範囲を出願書類の文言から拡大して解釈することが許される。
このケースでは、確かに添加剤を加える部分が異なってはいるが、
「酸化ケイ素に添加剤を加えたり加えなかったりすることによって屈折率に差をつける」という基本的な技術は
住友電工製品でも用いられており、「実質的に同一の方法で実質的に同一の結果を実現する技術」だと見なすことができる。
一方、文言に合致するか否かが重視される日本で同様の訴訟になったとき、住友電工が勝訴することはまず間違いない
(そもそも構造特許が成立しない)。
- ハネウェル 対 ミノルタ 「オートフォーカス装置」
- オートフォーカス(AF)機構を備えたカメラの歴史は、1977年の小西六(現コニカ)製品に始まるが、
このカメラに組み込まれていたのが、ハネウェル製のAFユニットである。
ミノルタは、当初、ハネウェルと技術開示契約を結んでAF技術の導入を行ったが、その後、独自技術の開発を進め、
1985年にはα-7000を発売する。
この製品は、焦点をあわせるスピードが従来品より格段に速くなった画期的製品として高く評価され、
ミノルタは、一躍、一眼レフ・カメラのトップに躍り出る。
- ところが、ハネウェルは1987年に、アメリカに輸出されたα-7000が特許侵害に当たると提訴する。
裁判は5年間にわたって争われるが、1992年2月、ニュージャージ州地裁で陪審員がミノルタ敗訴の評決を出した。
具体的には、侵害の有無が問われた4件の特許のうち、2件侵害、1件非侵害、1件は特許自体が無効と判断された。
賠償額は、特許侵害のあった製品の販売額の10%程度を目安に、9635万ドルと算出された。
最終的には、ミノルタがハネウェルとの和解に応じ、特許使用料込みで1億2750万ドルを支払うことになった。
- この裁判は、技術的な問題だけではなく、特許裁判におけるアメリカ独自の制度が窺われて興味深い。
- まず、日本ではなじみのない陪審員制が用いられたことに注目したい。
裁判結果が日本のマスコミで報じられたときは、技術面で優位に立って輸出攻勢を仕掛ける日本に対して、
陪審員が反感を抱いていたのではないかと疑問視する向きもあった。
また、高度に技術的な問題について、素人の陪審員の判断に委ねることの是非も論じられ
しかし、このケースに限ると、陪審員たちは、個々の特許の内容を具体的に検討した上で、どの特許に抵触するかを具体的に指摘しており、
単に日本憎しとの思いから評決を出したのではないことがわかる。
技術的な内容を含む裁判で陪審員制度を採用することには確かに問題も多いが、アメリカでは陪審員に選ばれることに誇りを持つ人は多く、
市民感覚に基づいて公正な判断を下してくれると期待しても良いのではないか。
- 日本との相違が際だつもう1つの点は、ハネウェルが持つ特許の1つが無効と判断されたことである。
日本では、資格を持った審査官が技術的な観点から審査して特許を付与している事実を重んじ、裁判所が特許無効の判断を下すことは
ほとんどない。
これに対して、アメリカでは、裁判所が第3者的な立場から特許の無効性を言い渡すケースは稀ではない。
密室の中で行われる審査に対して、市民の側から異議申し立てができるはずだというアメリカ的な発想の現れかもしれない。
- 技術的な観点からすると、この裁判結果は、パイオニア的な基本特許を重視するというアメリカ流の考え方に基づくものである。
- α-7000が侵害しているとされたAFに関する特許−−「ストーファー特許」−−は、位相差検出法の基本技術を述べたもので、
この分野ではきわめて先駆的であった。
簡単に言えば、被写体からの光を2つに分割して像を結ばせ、両者の強度分布に差があれば焦点が合っていないことがわかるという技法である。
ハネウェルの製品では、モーターを使ってレンズを少し動かしては焦点が合っているかどうかを調べるという作業を繰り返し、
最終的に焦点が合った状態を実現することになる。
- ミノルタの製品で画期的なのは、2つの像の強度分布の差をもとにレンズをどれだけ移動させれば焦点が合うかを
計算する機構を搭載していた点である。
この計算は、マイクロコンピュータによって瞬時に実行できるので、ハネウェル製品のように、レンズを少しずつ動かす手間をとらず、
きわめて短時間で焦点を合わせられる。
ミノルタ側は、この「改良」が、焦点が合っているか否かしか判定しないストーファー特許の技術を本質的に超えると考え、
特許侵害には当たらないと主張した。
- ミノルタの誤算は、アメリカにおける基本特許の地位が、日本で考えられている以上に高いことであった。
確かに、出願書類の文言には、焦点が合っているかどうかを指示する機構についてしか記載がない。
しかし、「光を分割して得られた像の強度分布の差をとる」という基本的なアイデアこそがストーファー特許の核心であり、
ミノルタの製品は、これを越えるものではない。
画期的ではあるが、基本技術の枠内での改良である。
こうした考えに基づいて、陪審員は特許侵害の評決を出した訳である。
- 住友電工もミノルタも、基本特許の場合、その適用範囲が明細書の文言よりも拡大されるという事実に疎かったわけだが、
これが、日本で行われる裁判ともなると、日米企業の立場が見事に逆転する。
次に、その例を見ていきたい。
○特許紛争の実例II 日本での裁判
- アメリカの企業が日本に製品を輸出したり、日本法人が製造・販売を行う場合は、当然のことながら、
日本の特許制度が適用される。
特許紛争で裁判になった場合は、日本での慣習に基づいてほぼ出願書類の文言通りに特許の範囲が認定されるため、
日本企業に有利な判決が出されることが多い。
ここでは、近年話題になったテキサス・インスツルメンツの事件を中心に解説する。
- テキサス・インスツルメンツ 対 富士通 「集積回路」
- アメリカ屈指の半導体企業であるテキサス・インスツルメンツ(TI)は、集積回路(IC)に関する基本特許を保有する
会社としても知られている。
今世紀最大の発明の1つに数えられるICの第1号は、1958年、TIに入社したばかりの研究員ジャック・キルビーが作った
簡単な位相発信器である。同じ頃、フェアチャイルドのロバート・ノイスも同様の発明をしており、後にクロスライセンス契約により
特許を分け合うことになる。
- TIは、キルビーの発明の重要性に早くから気づいており、巧妙な特許戦略を駆使して、そこから得られる利益を最大限に
享受することになる。
- ICに関する基本特許(キルビー特許)は、1959年2月、アメリカで「単一結晶の半導体薄板、能動回路素子、
受動回路素子からなる半導体装置」に関する特許として出願され、多くの利益をTIにもたらすが、1981年に満了している。
同じ特許は、日本では、1960年に出願されて65年に成立、80年に権利満了となった。
- 本来なら、キルビー特許に関してはこれで話が終わるはずだが、TIは、ここで実に巧みな方法を用いる。
日本の特許法では、出願中に2件以上の発明が含まれている場合、出願の一部を抜き出して分割出願できることになっている。
したがって、ICのようにきわめて応用範囲の広い基本発明は、用途や機能を限定することによって、分割出願の対象となるような新発明を
次々と派生させることも不可能ではない。
こうして、TIは、元の「キルビー特許」から8つの新しい発明をひねり出して1964年に出願する。
- あわてたのは日本企業である。これらの特許が認められると、日本の半導体市場でTIがあまりに強大な力を持つことになる。
TIの分割出願に片端から異議を申し立て、8件とも特許拒絶ない出願取り下げに持ち込んだ。
しかし、そのうち1件に関してTIはさらなる分割出願を行い、長期の審査を経て、1986年に遂に特許権取得に成功する。
- これがいわゆる「新キルビー特許」である。
1958年になされた古典的な発明に関する特許がいきなり成立し、世紀を越えて2001年までに継続することになったのだから、
日本企業としてはやりきれない思いだったに相違ない
(新キルビー特許は、特許法の改正により出願日からのシーリングが認められる以前のものなので、公告日から15年継続する)。
もっとも、TI側からすれば、日本側が特許に難色を示して審査を長引かせたのが悪いということになるのだろうが。
- ともあれ、新しく成立した「新キルビー特許」に基づいて、TIは、NECをはじめとする日本の半導体企業に、
年間で総額2000億円を超える使用量を要求してきた。
多くの会社はこれに従った(サンヨーは当該技術を使用していないということで支払いを回避した)が、
富士通だけが反旗を翻す。
1991年7月、東京地裁に、「特許侵害のないことの確認」を求める訴訟を起こす。
TIも富士通を逆提訴し、裁判の場で、決着がつけられることになった。
- 1994年8月に出された東京地裁の判決は、富士通勝訴というものだった。
- 問題になっている富士通製半導体メモリの構造は、特許書類に記されている古典的な回路とは似ても似つかぬものなので、
技術的な観点からすると妥当な判決とも言える。
しかし、裁判官が採用した判決の論拠を調べると、きわめて日本的な特許解釈がかいま見えて、実に興味深い。
- TIの訴えを斥けた根拠として、裁判官は、2つの点を指摘する(日経エレクトロニクス 1994.9.26.):
- 特許のクレームには「半導体基板内に複数の回路素子を含み」とあって、それ以外の素子について触れられていない。
従って、厳密に解釈すれば、基板の外に回路素子が1つでもあれば、特許に抵触しないことになる。
富士通製のメモリでは、いくつかの素子が3次元的に積み重ねられる形になっており、一部の素子はシリコン基板の外に置かれている
ことになるので、新キルビー特許の要件を満たしていない。
- クレームには、電気的な絶縁のために「各素子間は…互いに距離的に離間して形成され」という要件がある。
ところが、富士通のメモリでは、近接した素子の間に楔形の絶縁体を入れることによって絶縁しているので、この要件に該当しない。
- こうした主張から見て取れるように、ここでは、特許の範囲を出願書類の文言通りに限定しており、そこに書かれていない
部分が少しでもあると、特許侵害にならないという解釈が用いられている。
これが、日本流の文言主義的な特許解釈であり、特許の適用範囲をきわめて狭くとる点に特徴がある。
裁判所がこうした解釈を採用したことは、欧米製品の改良を通じて経済発展を実現していく上で、陰ながら重要な役割を果たしていたと考えられる。
-
※TIと富士通の間の訴訟は、2000年4月11日に最高裁が「新キルビー特許は事実上無効である」と認定し、富士通勝訴に終わった。
- ジェネンテック 対 東洋紡/住友製薬 「血栓溶解剤」
- 最後に、バイオテクノロジー絡みの事例として、TPA(ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子)の特許を巡る裁判を瞥見する。
- TPAは、もともと人間の体内にある生化学物質の一種で、遺伝子解読によってそのアミノ酸配列が解明されたものである。
ジェネンテックは、日本とアメリカでアミノ酸配列をクレームとする物質特許を取得、
その上で、遺伝子組み替え技術を使って合成したTPAを含む医薬品を、血栓溶解剤として販売していた。
ところが、日本で東洋紡と住友製薬が、ほぼ同じ成分を持つ医薬品の販売に踏み切ったため、両社を特許侵害の件で訴えたものである。
- 2つの裁判結果は、対照的であった。
- 東洋紡は一、二審とも敗訴したが、これは、同社の製品がジェネンテックが特許を持つTPAと全く同一の成分を含んでいるため、
やむを得ない結果と考えられる。
東洋紡は、「TPAはもともと自然界に存在するもので、特許に必要な新規性がない」と主張して特許の無効性を訴えていたが、
アメリカと異なって、専門家である審査官が与えた特許に対して裁判所が無効を宣告するケースがほとんどない日本では、
この主張が受け入れられる可能性はもともと小さかった。
- 一方、住友製薬は、1994年の大阪地裁での判決で、勝訴を勝ち得ている。
同社の製品では、459個あるアミノ酸の配列のうちのごく一部がジェネンテックの出願書類に書かれていたものと異なっていたため、
特許の範囲を文言通り解釈する立場をとれば、特許侵害に当たらないと判断された結果である。
実際には、生物活性という点でジェネンテックの製品とほとんど違わないのだが、特許権を狭くとる日本流の解釈が、
住友製薬に幸いしたと言える。
- こうした例を見てくると、日本とアメリカでは、同じ特許制度といっても、基本的な解釈に大きな相違があることがわかってくる。
どちらの制度がすぐれているかは一概には言えないが、産業構造を変革するジェネリック・テクノロジーを生み出すためにはアメリカ流の解釈が、
改良を積み重ねて高機能・高品質の製品を世に送り出すには日本流の解釈が、それぞれ有用であることは、指摘しておいて良いだろう。
©Nobuo YOSHIDA