|
|
|
|
|
| 第3章.細菌との闘いの果て |
| ウィルス(DNA/RNAウィルス) | 天然痘、インフルエンザ、ポリオ、狂犬病、流行性肝炎、エイズなど |
| リケッチア | 発疹チフス、つつがむし病など |
| 細菌(球菌、桿菌、ビブリオ、マイコプラズマ、スピロヘータ) | 結核、細菌性赤痢、ペスト、コレラ、梅毒、淋病、破傷風、敗血症、サルモネラ症など |
| 真菌 | カンジダ症、放線菌症など |
| 寄生生物(原虫、寄生虫) | マラリア、アメーバ赤痢、睡眠病、住血吸虫病など |
| その他(プリオンなど) | 狂牛病、クロイツフェルト=ヤコブ病など |
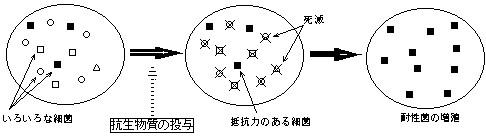
©Nobuo YOSHIDA