|
|
|
|
|
| 第1章.夢の物質を目指して |
| 用 途 | 製 品 と 使 用 場 所 |
| 絶縁油(トランス用) | ビル、病院、地下設備、電車、地下鉄、船舶などのトランス。 |
| 絶縁油(コンデンサー用) | 家庭用(冷暖房機、洗濯機、ドライヤー、電子レンジ、 冷蔵庫など)、安定器用(蛍光灯、水銀灯など)、モーター用に利用される各種コンデンサー。 |
| 熱 媒 体 | 各種化学工場、食品工場、合成樹脂工場、製紙工場などの行程の加熱と冷却。集中暖房やパネルヒーター。 |
| 潤 滑 油 | 高温用潤滑油、作動油、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤。 |
| 絶縁用可塑剤 | 電線やケーブルの被覆、絶縁テープ。 |
| 難燃用可塑剤 | ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ゴムに混合。 |
| その他の可塑剤 | 接着剤、ニス、ワックス、アスファルトに混合。 |
| 塗料・印刷インキ | 難燃性塗料、耐薬品塗料、耐水塗料、耐蝕性塗料、印刷インキ |
| そ の 他 | 陶器・ガラス器の着色、農薬の効力延長剤、紙などのコーティング |
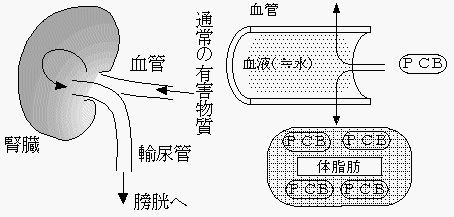
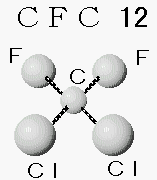 フロンとは、炭素、塩素、フッ素からなる化合物の総称で、多くの種類がある。フロンという呼称は日本独自のもので、諸外国では、クロロフルオロカーボン(塩化フッ化炭素)の頭文字をとってCFCs(終わりのsは種類が複数あることを示す)とか、デュポン社の商標のままフレオンとか呼ばれている。かつて「今世紀最大の発明」ともてはやされたこの物質が、いまや、オゾン層破壊の元凶として、世界的な規制の対象になっているとは、何とも皮肉な話である。
フロンとは、炭素、塩素、フッ素からなる化合物の総称で、多くの種類がある。フロンという呼称は日本独自のもので、諸外国では、クロロフルオロカーボン(塩化フッ化炭素)の頭文字をとってCFCs(終わりのsは種類が複数あることを示す)とか、デュポン社の商標のままフレオンとか呼ばれている。かつて「今世紀最大の発明」ともてはやされたこの物質が、いまや、オゾン層破壊の元凶として、世界的な規制の対象になっているとは、何とも皮肉な話である。

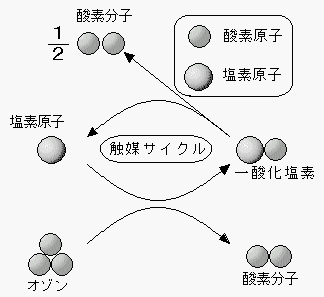
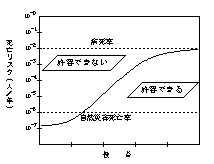
©Nobuo YOSHIDA