|
|
|
|
|
第1章.相対性理論
〜流れる時間への懐疑〜 |

| 通常の解釈に従えば、マクスウェルの電気力学を運動物体に当てはめた場合、現象の種類によらず、非対称的な議論が導かれる。例として、磁石とコイル(【注】原文には導体とあるがコイルと解釈した方がわかりやすい)のあいだに起こる電磁気的な相互作用を考えてみよう。このとき、観測される事象は、コイルと磁石の相対的な運動だけに依存する。ところが、従来の考えによると、2つの物体のどちらが運動しているかによって、はっきりした差異があることになる。磁石が運動し、コイルが静止しているときには、磁石の周りに一定のエネルギーをもつ電場が生じ、そのために、コイル内部に電流が流れる。その反対に、磁石が静止し、コイルが運動しているときには、磁石の周りに電場は生じない。そのかわり、コイルの中に、最初の場合の電場によって生じたのと等しい電流が流れる。…
このような例と、さらに“光の媒質”に対する地球の相対運動を発見しようという試みの失敗をあわせて考える(【注】アインシュタインはマイケルソンとモーレーの原論文は読んでおらず、装置の詳細なども知らなかったようだが、実験結果については承知していた)と、電気力学の現象は、力学の現象と同様に、絶対の静止という概念を正当化するような性質をもっていないように見える。むしろ、これらの事実から、力学の方程式が成り立つすべての座標系に対して、電気力学や光学の法則が、いつも同じ形で成り立つと考えられる。… このような推測を第一の要請と見なして、相対性原理と呼ぶことにする。 |
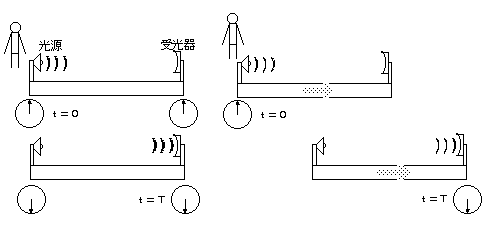
|
質点の運動を記述するには、その座標の値は、時間の関数として与えられる。ただし、ここで注意すべきことがある。こうした数学的な記述は、“時間”をどのように考えるかを明確にしない限り、物理的に無意味だという点である。一般に、時間が関与するすべての判断は、常に同時に起こる事件についての判断である。たとえば、私が「あの汽車はここに7時に到着する」というとき、それは、「私の時計の針が7時を指すことと、あの汽車の到着とは、同時に起こる事件である」という意味なのである。
“時間”の定義にまつわる困難は、“時間”の代わりに、それを“私の時計の針の位置”によって置き換えれば解決できると思われるかもしれない。事実、このような定義は、時計のある場所だけにおいては正しい。しかし、離れた場所で起こる2つの事件を時間を使って表そうとするときには、使えないのである。つまり、上記の定義は、違った場所でつぎつぎと違った時刻に起こる一連の事件を、1つの時間で表すときには、もはや正しくない。あるいは、同じことだが、時計から離れたいくつかの場所で起こるいくつかの事件の時間を計ろうとするときには、この定義は成り立たないのである… |

| 同時性という概念には、絶対的な意味を与えることはできない。2つの事件がある座標系から見て同時刻に起こったように見えても、その座標系に対して運動している別の座標系から見ると、もはや同時刻の事件とは言えなくなるのである。…… |
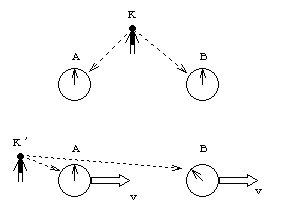
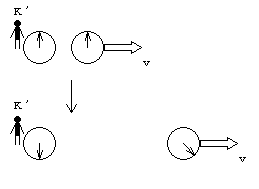

©Nobuo YOSHIDA