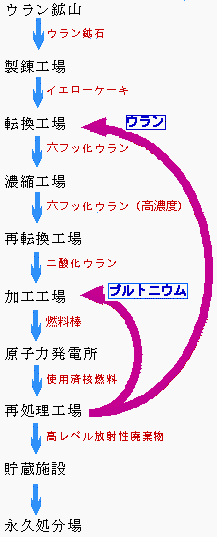§4.核燃料サイクルと放射性廃棄物

原子力発電の最大の問題は、使用済み核燃料の処理だと言われている。原子炉で核反応が進行する過程で、核燃料棒内部には、強い放射能を帯びた核分裂生成物(核のゴミ、俗に言う“死の灰”)と、ウラン238が中性子を吸収してできるプルトニウムが蓄積されてくる(右図;生成されたプルトニウムの一部は、原子炉内で分裂して核分裂生成物を作る)。この2つをどのように処理するかが、大きな課題である。日本では、使用済み核燃料から、核燃料として利用できる未分裂のウランとプルトニウムを再処理によって抽出し、残りを放射性廃棄物として処理するという核燃料サイクルが計画されている。この計画を巡っては、使用済み核燃料をそのまま埋設する直接処分に比べてコスト的に不利になる上、危険性の高いプルトニウムを保有することに対する懸念があり、批判が絶えない。また、どのような方法を採るにせよ、強い放射能を持つ放射性廃棄物を処分しなければならない。日本では、年間1000トンの使用済み核燃料が排出されており、各原子力発電所の敷地内に保管されているが、あと数年で満杯になる見込みなので、早急に処理方法を確立しなければならない。これらの問題について、簡単に見ていこう。
核燃料サイクル
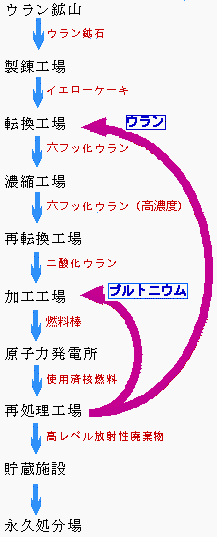
通常の原子力発電では、核燃料として中性子によって核分裂を起こすウラン235を利用している。ただし、ウラン235は製錬したウランの中に0.7%程度しか含まれていない微量成分であり、大部分は核分裂しないウラン238である。今後、アジア地域で原子力発電所の建設がさかんに行われると、ウラン235は21世紀中に枯渇する可能性もある。このため、使用済み核燃料の中に含まれている未分裂のウラン235と、一部のウラン238が中性子を吸収してできる核分裂性のプルトニウムを再処理工場で回収して再利用しようという計画が進められている。このような核燃料物質の循環を「核燃料サイクル」と呼ぶ。世界第2の原発大国で、電力の80%近くを原子力に依存しているフランスでは、積極的に再処理を推進しており、他国の使用済み核燃料も受け入れている。一方、アメリカやスウェーデンでは、再処理を行わずに使用済み核燃料を直ちに埋設する直接処分が行われている。
核燃料サイクルの概要を示そう(右図)。
- 製錬工場 : ウラン鉱石からウランを取り出し、イエローケーキと呼ばれる黄色の粉末にする。
- 転換工場 : 不純物を取り除きフッ素と化合させて六フッ化ウラン(UF6)にする。
- 濃縮工場 : 六フッ化ウランに0.7%程度しか含まれていない核分裂物質のウラン235を2〜4%まで濃縮する。この過程が、核燃料サイクルの中で最もエネルギーを消費する。
- 再転換工場 : 濃縮した六フッ化ウランを粉末状の二酸化ウランにする。
- 加工工場 : 二酸化ウランを焼き固めて円筒状のペレットに加工し、合金製の管に入れて燃料棒を作る。
- 原子力発電所 : 燃料棒の集合体を原子炉の中で使用し発電する。燃料は3〜4年ほど使用した後に新しい燃料と交換される。
- 再処理工場 : 使用済み燃料を化学的に処理し、分裂生成物を核のゴミとして取り出すとともに、核分裂しなかったウラン(ウラン235および238)や炉内で生成されたプルトニウムを回収する(下図;プルトニウムの回収が行われるのは一部の専用工場のみ)。回収されたウランは、再び濃縮して燃料とするため転換工場に送られる。プルトニウムは、プルサーマル発電(後述)に利用するMOX燃料に加工するため加工工場に送られる。日本では、青森県六ヶ所村に再処理工場を建設、2006年から操業する。
プルトニウムの利用
核分裂しないウラン238が炉内で中性子を吸収して生成されるプルトニウムは、ウラン235と同様に原子炉の核燃料として利用可能である。もともと燃料として使えなかったウラン238が核燃料に変化することになるため、見かけ上、エネルギー源の“増殖”が起きたことになる。一部のプルトニウムは、原子炉内でそのまま核分裂を起こすが、分裂しなかったものまで利用するには、専用の再処理工場で回収しなければならない。しかし、次のような理由で「悪魔の元素」と呼ばれるプルトニウムを、わざわざ取り出して輸送・加工を行うことへの批判は根強い:
- 半減期が長く(24000年)、人体に吸収されると骨髄に入り込んで傷害性の強いα線を放出し続けるため、発ガン性がきわめて強い。
- 再濃縮に高度な技術と膨大なエネルギーが要求されるウラン235に比べて、容易に爆発物を製造できる。爆縮レンズによって大規模な核爆発を引き起こすのは技術的に難しいが、小規模爆発により放射毒性のある未分裂プルトニウムが飛散するため、兵器として敵に与えるダメージは大きい。
プルトニウムを発電に利用する方法には、次の2つの種類がある。
-
◇高速増殖炉
-
プルトニウムを最も有効に利用できる原子炉。冷却材として液体ナトリウムを使うことにより、ウラン238が中性子を吸収しやすくなり、分裂するものよりも多くのプルトニウムが生成される(これが「増殖炉」と呼ばれる所以である)。理論通りに稼働すれば、利用可能なエネルギーの量は、ウラン235だけを利用する場合に比べて60倍にもなる。ただし、ナトリウムは空気中の水分と爆発的に反応するため、火災事故を引き起こしやすい。アメリカ・イギリス・ドイツは、技術的に実現困難だとして1990年代はじめまでに計画を断念した。フランスでは、実験炉として「スーパーフェニックス」が建設され、1985年から運転が始まっていたが、87年と90年にナトリウム漏れ事故を起こしたため、1998年に閉鎖が決定された。日本では、動力炉核燃料開発事業団(現・核燃料サイクル開発機構)が開発した高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)が、1995年12月に単純なミス(温度計の設計ミスおよび装着不備)によってナトリウム漏れ事故を起こし、開発が中断している。核燃機構は、運転を中止している「もんじゅ」の再開を目指しているが、2003年、地元住民らが原子炉設置許可の無効確認を求めた行政訴訟・控訴審で国側が敗訴し、先行きは不透明になっている。また、原子力委員会が高速増殖炉の実用化を断念、プルトニウムの利用はプルサーマルを軸とする方針を打ち出した。
-
◇プルサーマル
-
ウランとプルトニウムを酸化物の形で混合したMOX(Mixed Oxide)燃料を軽水炉(通常の原子力発電所で使用されている原子炉)で燃やす方式で、フランスなど一部の国で実施されている。MOX燃料はウラン燃料と比べると放射線量が高く発熱があるが、フランスでの運用実績によれば、安全性に著しい問題はないとされる。 ただし、エネルギーの増殖率は10%に過ぎず、ウランを10%節約するために高いコストをかけて再処理を行う価値があるとは考えにくい。日本では1997年にプルサーマルの導入を閣議了解し、99年から実施することにしていたが、関西電力高浜原発用にイギリスの加工工場から輸入したMOX燃料のデータに捏造があった(*)ため、計画が延期された。関西電力や九州電力などでは2006-07年にプルサーマルを開始する予定だが、東京電力では、計画は依然白紙のままである(2004年12月現在)。
(*)ペレットの大きさのばらつきを抜き取り検査していなかったにもかかわらず、別の測定データを添付して検査済みのように見せかけた。
再処理と直接処分
使用済み核燃料の処理方法としては、核燃料サイクルを実現するための再処理の他に、燃料棒をそのまま埋設する直接処分もある。2つの方法には、次のようなメリット・デメリットがある。
【再処理と直接処分】
| | 直接処分 | 再処理 |
| コスト | 割安
総額15兆円 | 割高(再処理工場の建設・運営が必要)
総額19兆円(電事連試算) |
| 放射性廃棄物 | 多い | 少ない(再処理で一部抽出するため) |
| 資源節約 | なし | あり
高速増殖炉 6000%
プルサーマル 10% |
| 最終処分場 | 数年以内に必要 | 30年程度の猶予あり |
日本では、2004年に原子力委員会で再処理の方針を転換して直接処分を行うべきではないかとの意見も出されたが、(1)最終処分場の建設が間に合わない、(2)すでに再処理のための施設を建設している、(3)直接処理を行うための技術の開発がなされていない──などの理由で、再処理継続の方針が決定された。
放射性廃棄物
使用済み核燃料には、大量の放射性廃棄物が含まれている。ウラン(ないしプルトニウム)が核分裂してできる分裂生成物は、ほとんどが強い放射能を帯びた有害物質であり、放射能が危険レベル以下になるには数万年かかるため、半永久的に人間や他の生物の生活圏から隔離した場所に保管しなければならない。この場所をどこにするかが、関係者の悩みの種となっている。放射性廃棄物には低レベルと高レベルのものがあり、前者の処理方法は一応は確立しているが、後者に関しては、いまだに日本を含む多くの国で最終処分場が決まっていないという有様である。
-
◇低レベル放射性廃棄物
-
原子力発電所からでる低レベルの放射性廃棄物のうち気体や液体のものは、専用の処理装置で放射性物質を取り除き、安全性を確認してから大気や海に放出する。使用済イオン交換樹脂等の固体廃棄物はセメント等で固めてドラム缶に密閉し、発電所内の貯蔵施設に一時的に保管、その後、一括して専用の処理施設(日本では青森県六ケ所村)で埋設処分する。
-
◇高レベル放射性廃棄物
-
再処理を行う場合、使用済み核燃料は、再処理工程で有用な資源(ウランとプルトニウム)と放射能レベルの高い廃液とに分けられ、後者は次の手順で処理される(直接処分の場合は、使用済み核燃料そのものが高レベル放射性廃棄物となる)。
- ガラス固化体に加工 : 放射性廃液を耐久性・耐熱性・安定性に優れているガラスと一緒に混ぜてステンレス製の丈夫な容器の中へ入れ、「ガラス固化体」(高さ約1.0m、直径約40cm)にする。
- 管理施設で一時保管 : ガラス固化体は、放射性崩壊による熱を発生するので、30〜50年間にわたって冷却のため専用の管理施設で貯蔵される。この施設は、厚さ1.5〜2メートルの鉄筋コンクリートの壁でおおわれ、放射性物質の漏出を防いでいる。日本では、青森県六ケ所村の管理施設に一時貯蔵されている。
- 最終処分 : 最終的には地下300メートル以上の深さの安定した地層に埋設処分される。高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体やそれを入れる金属製の容器、その周囲に詰められたた緩衝材の人工障壁と、これらを包む岩盤の天然障壁とで、人間の生活圏および生物圏から放射能が消える数万年にわたって隔離し続けられる。日本では、2027年に最終処分場の操業開始が予定されており、その準備として2000年5月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定された。それによると、電力会社は、処分場建設のために必要となる資金約3兆円を拠出しなければならないが、この負担を電気料金に上乗せすることが容認された。
-
◇最終処分
-
最終処分場の建設地が決定しているのは、2004年現在、アメリカとフィンランドの2カ国だけである。直接処分を行うために早急に処分場を決定しなければならなかったアメリカでは、2002年に上下院がユッカマウンテン(ネバダ州)を最終処分場として承認し、2010年の操業開始に向けて建設が進められている。ネバダ州知事は建設反対を表明していたが、原子力発電所に保管されている使用済み核燃料がダーティボムの原料としてテロリストに狙われることを心配した世論が、処分場決定の追い風となった。ここに7万7千トン分を収納する予定だが、米国内にはすでに4万トンの使用済み核燃料が蓄積されており、数十年で新たな処分場が必要になる見込み。フィンランドでは、世界に先駆けて、人口6千人の寒村ユーラオーキに処分場建設を決定、2020年の完成を目指す。また、スウェーデンでも最終候補地の絞り込みが進められている。
日本では、NUMO(原子力発電環境整備機構)が候補地を公募している段階であり、最終処分場の決定には至っていない。このほか、多くの国で最終処分場の選定に苦慮している。1999年に行われた核廃棄物に関する国際会議では、ロシアに処分を委託するという方式が提案され、関心を示す国もあった。ロシア政府は外貨獲得になる(核燃料1トンあたり150万ドル程度)として前向きだが、放射性物質の管理に不安があるとして、日本やヨーロッパ諸国は批判的である。
©Nobuo YOSHIDA