|
|
|
|
|
アイゼンハワー大統領が“Atom for Peace”講演(1953)を行って以降、アメリカでは原子力産業の育成が政策上の既定路線となっていた。このため、原子力委員会(AEC)が中心となって原子力発電の経済性・安全性をアピールし、多くの専門家・科学ジャーナリストもこれに同調した。1960年代後半から70年代の原発発注ブームも、このアピールに煽られた面がある。しかし、70年代半ば頃から、次第に原発の経済性・安全性に対する疑念が高まり、80年代にはいると世界的に反原発運動が起きるようになる。
1950年代から原子力産業の育成を画策していたAECは、政策的に原子力発電の経済性をアピールしていた。原発の発電コストがいかに安いかを強調する当時の有名な標語に、"too cheap to meter"というものがある。ウラン燃料がきわめて安価に入手できるので、「メーターで計れないほど電気料金が安い」という訳である。もちろん、現実には設備費が嵩むために火力発電に比べてそれほど安くはならないが、それでも、採算性の良さで原発に軍配が上がると主張されていた。
具体的な報告書としては、1966年にテネシー渓谷開発公社(TVA)が公表したものが有名である。TVAは、建設予定の発電所の入札結果を基に、原子力発電が同規模の火力発電より発電コストが低いことを示した。さらに、契約を結んだ業者に対して12年にわたる燃料の一括供給の保証を行うなど、原発優遇の施策を打ち出している。公共事業体であるTVAのこうした方針は、客観的な採算性の評価に基づくとされるが、AEC初代委員長リリエンソールがTVAの総裁だったことを思い合わせると、AECとTVAの親密な関係が窺える。
原子力発電が火力発電に比べて経済的だという報告がきっかけとなって、アメリカでは原発の発注ブームが起きる。しかし、間もなく、この見通しの甘さが明らかになってくる。
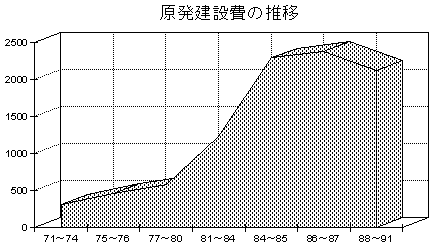 1970年代に入ると、発電所の建設コストが高騰し、原子力発電の採算性は急激に悪化していく。出力あたりの建設単価で比較すると、71〜74年に運転開始した発電所の平均が313ドルだったのに対して、88〜91年のものは2127ドルに急騰している(右図)。建設費高騰の理由は、70年代に入って原発の安全性に対する懸念が増大し、バックアップ装置の増設などで安全対策費が嵩んだこと、追加安全策や反対派住民の説得などによる工期の遅れから利子が増大したことにある。
1970年代に入ると、発電所の建設コストが高騰し、原子力発電の採算性は急激に悪化していく。出力あたりの建設単価で比較すると、71〜74年に運転開始した発電所の平均が313ドルだったのに対して、88〜91年のものは2127ドルに急騰している(右図)。建設費高騰の理由は、70年代に入って原発の安全性に対する懸念が増大し、バックアップ装置の増設などで安全対策費が嵩んだこと、追加安全策や反対派住民の説得などによる工期の遅れから利子が増大したことにある。
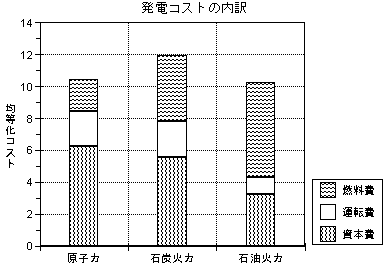 現在では、原子力と石油火力の発電コストは、ほぼ均衡していると言われている(左図)。しかし、今後、廃棄物処理費用や廃炉後の解体費用が加算されることを考えれば、原子力は必ずしも採算に合う発電方法とは言えないだろう。アメリカでは、電力自由化に伴って安価で電気を提供する中小電力会社(主に火力発電)が数多く現れたため、初期投資が巨額に上る原子力発電所を新規に建設しようという動きは、近年では全く見られない。逆に、1995年には、米会計検査院がTVAにおける原発コストの増大を批判、その結果、建設中の2基の完成が断念された。
現在では、原子力と石油火力の発電コストは、ほぼ均衡していると言われている(左図)。しかし、今後、廃棄物処理費用や廃炉後の解体費用が加算されることを考えれば、原子力は必ずしも採算に合う発電方法とは言えないだろう。アメリカでは、電力自由化に伴って安価で電気を提供する中小電力会社(主に火力発電)が数多く現れたため、初期投資が巨額に上る原子力発電所を新規に建設しようという動きは、近年では全く見られない。逆に、1995年には、米会計検査院がTVAにおける原発コストの増大を批判、その結果、建設中の2基の完成が断念された。
日本でも、後処理を含めた発電コストの試算が行われているが、結果にばらつきがあって、信頼性に欠ける。
2003年に電気事業連合会が発表した2005-87年に要する後処理の費用は、再処理工場の操業費9兆円、同工場の解体・処理費1兆6千億円、高レベル放射性廃棄物の処分費2兆5千億円など、総額で18兆9100億円となる。これを、単純に発電コストに上乗せすると、1kW当たり0.99-1.53円。従来求められていた原発の発電コストは、1kW当たり5.9円だが、この中には、一部再処理のコストも含まれていたため、その分を差し引いて、後処理を含めた原発の発電コストを計算すると、1kW当たり最大で6.4円となる。これは、石油火力(10.2円/kW)より割安で、石炭火力(6.5円/kW)、LNG火力(6.4円/kW)とほぼ同程度となる。約19兆円の後処理コストのうち、10兆円程度は電力会社が積み立てている引当金で回収できるが、残りは電気料金に上乗せされ、月300kWh消費する標準的な家庭では、年間1260〜1400円となる。
しかし、2004年に原子力委員会で行った試算によると、再処理の総コストは43兆円に達する。これは、電事連で考慮されなかった第2再処理工場の建設・操業費などを加えているためで、この数字を採用すると、原発の方が石炭・LNG火力よりかなり割高になる。また、1994年に通産省が行った試算によると、電気料金に上乗せされる後処理費用は電事連試算とかなり異なっているが、計算の根拠が明らかでない。
高レベルの放射性廃棄物が炉内に蓄積される原子力発電に対して、安全面から批判する声は商業化が進められる以前から少なくなかった。これに対して専門家グループによる安全性評価がたびたび行われているが、必ずしも信頼性は高くない。
◇ブルックヘブン報告
原子力発電所の安全性に関する最初の評価は、1955年にブルックヘブン・チームがまとめた「大規模原発における大事故の理論的可能性と結果」であろう。この時点で、商業的な原子炉は操業されておらず、多くの暫定的な仮定を含む不完全な内容ではあったが、それなりに示唆に富むものであった。この報告では、人口100万人の都市から50kmの地点にある10〜20万kwの原発が想定されており、核分裂生成物が放出される大事故の確率は1基あたり10万〜10億年に1回、最悪のケースでは、死者3400人、障害を受ける者4万3000人、被害総額70億ドルに上るとされている。
スリーマイル島原発やチェルノブイリ原発の事故を経験した現在では、この見積もりもやや楽観的であるように思われるが、当時としては充分に衝撃的な内容だった。事故確率の最大値である10万年に1回という数字は、かなり低いものに見えるかもしれないが、仮に世界中で1000基の原発が稼働しているとすると、世界のどこかで大事故が発生する確率は100年に1回となる。放出された放射性物質が国境を越えて世界中に飛散することを考えると、多くの人が、一生の間に1度は大規模原発事故に出会うというリスクは、決して小さいものではない。まして、その経済的な打撃が、アメリカの1つの州の財政を揺るがすほどの金額になれば、なおさらである。原子力委員会にとってあまり好ましくないこの報告内容は、長い間、公表されずにいた。
◇ラスムッセン報告
原子力を推進する立場から見て好ましい安全性評価は、1974年にラスムッセンに率いられたチームによる「原子炉安全性研究」において示された。この報告では、事故が起きる確立を、NASAで用いられた障害樹(fault tree)分析によって計算している。例えば、2つの安全装置が同時に故障しなければ起きないタイプの事故の発生確率は、それぞれの装置が故障する確率の積で与えられる。こうした計算法によると、大規模事故の確率は、原子炉1基あたり10億年に1回となり、ほとんど無視できることになる。この内容は、原子力発電の安全性を示すデータとして利用された。
ラスムッセン報告に対する批判は、1976年のウェッブらの研究など数多くあるが、何よりも、スリーマイル島原発の事故が、見事な反例になっている。このケースでは、原子炉内部で何が起きているかを示す表示がないまま次々と点灯するアラーム信号に動転した運転員が、コンピュータによって自動的に起動された安全装置のスイッチを手動で切ってしまい、事故の拡大を招いている。大事故とは、「ドミノ倒し」のように一連の出来事の連鎖として起きるものであり、2つの出来事が重なる確率がそれぞれの発生確率の積になるような独立事象の集まりではないのだ。
◇原子炉事故と反原発運動の高まり
ラスムッセン報告で「科学的に」安全性が実証されたにもかかわらず、その後、世界各地で原子力発電施設の事故が続き、反原発の動きが強まっていく。まず、1979年にスリーマイル島原発(米ペンシルバニア州)2号炉で炉心破損事故が発生し、原子力発電を支持してきたアメリカ国民に強い衝撃を与えた。さらに、1986年には、チェルノブイリ原発4号炉(旧ソ連・現ウクライナ)で暴走・爆発事故が起こり、大量の放射性物質が放出されるという「最悪事故」が現実のものとなった。また、規模は小さいものの、1995年の高速増殖炉もんじゅナトリウム漏出・火災事故、97年の再処理工場火災事故、99年の核燃料加工工場臨界事故と、日本で各施設の事故が相次ぎ、核への不安をかき立てることになった。
多くの国で政府主導の下に進められていた原発推進の動きに歯止めを掛けたのが、市民による反対運動である。欧米では原発の建設中止ないし運転停止を求める住民投票が相次ぎ、反原発派が勝利を収めるケースが増えている。興味深いのはアメリカにおける住民投票の結果で、スリーマイル島原発事故が起きた1979年前後から原発に対する風当たりが急に強くなったことが窺える。
| 年 | 地域 | 反原発票の割合 | 可決/否決 |
| 1976 | カリフォルニアほか7州 | 29〜42% | 否決 |
| 1978 | モンタナ州 | 60% | 可決 |
| 1980 | ミズーリ州/メーン州 | − | いずれも否決 |
| 1980〜82 | オレゴンほか3州 | 52〜66% | いずれも可決 |
欧米では、経済性・安全性に対する懸念が強まったことから原子力政策の見直しが進んでいるが、その一方で、アジアでは原子力発電の増強が行われている。以下では、特徴的な国/地域の現状をまとめておく:
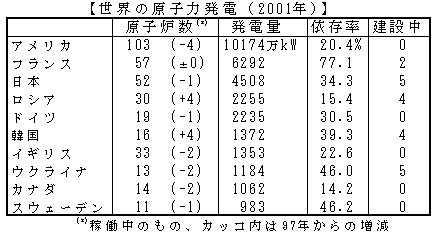
©Nobuo YOSHIDA