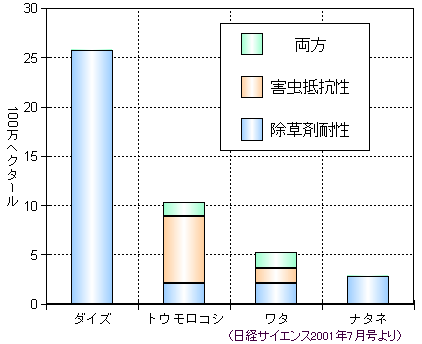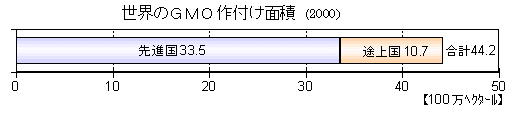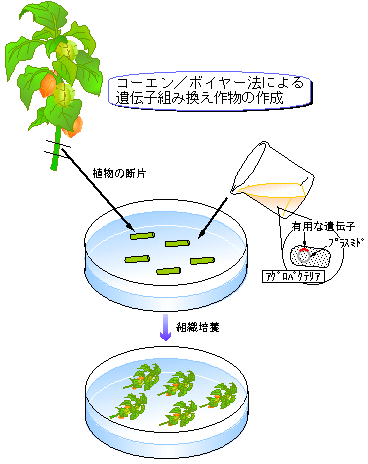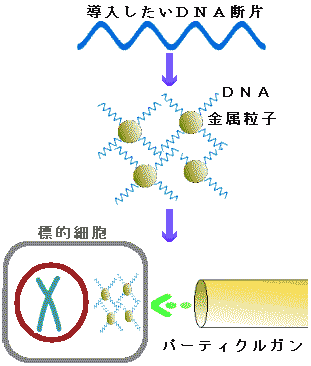§2.遺伝子組み換え作物
クローン技術が個体が持つ遺伝子情報のセットを丸ごと利用するのに対して、個々の遺伝子ごとに手を加えていこうとする技術が、「遺伝子組み換え(gene recombination)」である。
遺伝子組み換えの基本的技術は、1973年にコーエンとボイヤーによって完成された(コーエン/ボイヤー法)。ある生物に特定の形質を与えている遺伝子を、別の生物に組み込むというこの技術は、人類の未来を左右するほどの巨大な力を秘めたものとして、早くから科学者のみならず多くの知識人の注目を集めた。コーエンとボイヤーが特許使用料を低く抑えたこともあって、基礎的な研究が世界各地で活発に進められ、80年代からは、しだいに、医療や農業の分野での実用化が指向されるようになる。「リンゴの木に豚肉が生る」という当初のSF的予想は、遺伝子が機能する過程が明らかになるにつれて実現不可能であることがわかったものの、大腸菌にヒト成長ホルモンを合成させるなど、いくつかの実用的な成果を上げるに至った。
こうした流れの中で、遺伝子組み換えによって農作物の品種改良を行うという試みが、アメリカを中心に盛んになってきている。バイオテクノロジー先進国であると同時に農業大国でもある(選挙においても農民票の威力が大きい)アメリカは、自国で開発したこの技術を利用した営農戦略を、政策的に推進している。これは、食料の増産ないし安定供給を図るだけではなく、農作物に付加価値を与え、世界市場において有利な地位を獲得することを目標とするものである。中でも、東アジアの巨大市場があるコメに関しては、価格面の有利さでアメリカ米に勝利したタイ米を返り討ちにすべく、食味などに優れた商品を開発する試みが続けられている。
農業分野で遺伝子組み換え技術が実用段階に入ったことを告げたのは、1988年、米カルジーン社(後にモンサント社に吸収される)がメキシコで遺伝子組み換えトマトの野外試験を開始したというニュースである。環境団体は、こうした試みが自然界の生態系に悪影響を与えることへの懸念を表明したが、バイオテクノロジーによる農業技術の革新として歓迎する意見も少なくなかった。
数年間にわたる研究・開発の末、1994年にカルジーン社から発売された「風味の落ちにくいトマト」(FLAVR SAVR)を嚆矢として、アメリカの農家で遺伝子組み換え作物が続々と栽培されるようになる。これまでに、害虫に抵抗性を持つトウモロコシやワタ、特定の除草剤の影響を受けずに生育するダイズやナタネなど数十品目が商品化された。
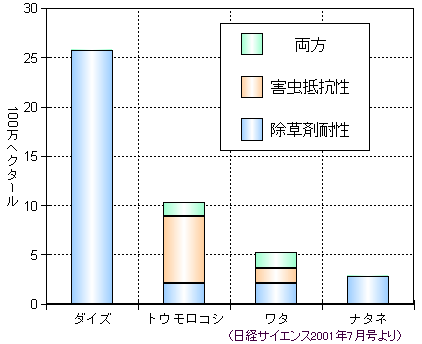
栽培地域は、主たる開発国であるアメリカが圧倒的に多く、作付け面積で遺伝子組み換え作物全体の68%を占める。以下、アルゼンチン(23%)・カナダ(7%)・中国(1%)などで栽培されており、開発途上国への産地のシフトも進んでいる(下図)。アメリカ農業ビジネスの戦略的商品として世界各地へ輸出されているが、ヨーロッパや日本では、安全面で不安があるとする声が強い。
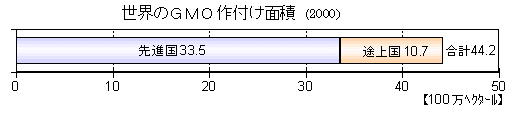
アメリカ国内の作付面積で見ると、2001年作付け面積で、ダイズの74%、トウモロコシの32%が組み換え品種となっており、遺伝子組み換えは、もはや「日常的な技術」になった感がある。将来的には、植物を一種の化学工場と考え、さまざまな薬用成分を含有した機能食品を作ることも検討されている。
遺伝子組み換え法
遺伝子組み換え作物は、次のような作業によって作り出される:
- 遺伝子の取り出し : 他の動植物や細菌から農業ビジネスにとって有用な形質を発現する遺伝子を見つけ、染色体からこの部分だけを制限酵素(DNAにおける特定の塩基配列の部分を切断する酵素)を使って切り出す。有用な遺伝子組み換え作物を作る際には、こうした「遺伝子探索」の作業が最も手間が掛かる作業となる。
- 遺伝子の導入 : 取り出した遺伝子を農作物の細胞核の中に導入する。導入方法には、次のようなものがある。
- アグロバクテリア法(コーエン/ボイヤー法) : 植物に寄生する細菌の一種であるアグロバクテリアは、プラスミドと呼ばれるリング状のDNAの一部を宿主の細胞内にもぐり込ませる性質を持つ。そこで、プラスミドから病原遺伝子を取り除き、かわりに有用な遺伝子をつなぎ合わせたアグロバクテリアを植物細胞に感染させることにより、遺伝子を導人することができる。この作業は、外来遺伝子を含むアグロバクテリアが入った溶液に植物組織(茎の一部など)を浸すだけなので、小規模な研究所で簡単に実行できる。
- パーティクルガン法 : アグロバクテリアが感染しない多くの単子葉植物(イネ・コムギ・トウモロコシなど)に遺伝子を導入するためにコーネル大学で開発された技術で、直径1〜2μの金やタングステンの微粒子に目的とする遺伝子をまぶし、これを火薬や高圧ガスで農作物の細胞の中に打ち込むものである。細胞膜の破損部分は短期間で修復され、細胞内に残存する金属球も植物の生育に悪影響を与えないため、効率的に遺伝子を導入できる。
- 電気パルス法 : 電気パルスで細胞膜に穴を開け、遺伝子を送り込む。
- 組み換え植物の選出 : 遺伝子が導入された細胞をガラス容器内部で組織培養して育てると、カルス(不定形の細胞塊)の段階を経て、茎や葉を持つ植物体が形成される。これは、遺伝子のオン/オフによって組織分化が進む動物と著しく異なった植物の特性である。こうしてできた多数の植物体の中から、望んだ形質が発現しているか、安定して遺伝するかなどをチェックして、目的に合ったものを選び出す。最終的には、遺伝子が組み込まれた種子を採取して、これを農家に販売することになる。
主な遺伝子組み換え作物
既に実用化された遺伝子組み換え作物では、次のような「有用な」形質が利用されている。
-
除草剤耐性の獲得
-
農作物に除草剤に対する耐性を与えることにより、大量の除草剤を散布して「雑草」を完全に撲滅し、農作物だけを効率的に育てる農法が可能になる。中でも注目されているのが、「ラウンドアップ」という除草剤である。この農薬は、動物に対する毒性がなく、環境中での残留性も小さいため、従来から多用されてはきたが、農作物への悪影響も皆無ではなく、どうしても使用量が制限されることになり、雑草を完全に駆除するのは難しかった。しかし、ラウンドアップの有効成分と結合してこれを無毒化する物質をコードする遺伝子をトマト・ダイズ・ワタ・ナタネなどに導入し、これらの作物に除草剤耐性を与えることにより、雑草を根絶やしにするまで心おきなくラウンドアップを散布できるようになったのである。遺伝子組み換えの最大手モンサントが遺伝子組み換え作物とのセット販売をしたこともあって、アメリカでは、ラウンドアップの消費量が急増しつつある。除草剤耐性を持つ作物は、農業の生産性を高める上できわめて有効で、農家からは特に歓迎されており、全遺伝子組み換え作物の81%が除草剤耐性のもので占められる。ただし、その反面、除草剤の散布量が増し、化学汚染を増悪し生態系の破壊につながるという批判も出されている。
-
殺虫物質の分泌
-
農作物自身に殺虫物質を分泌させて、害虫を駆除する方法も開発されている。殺虫剤を空中散布する場合に比べて、雨で流されることがないため効率的になるほか、植物体内に侵入する寄生虫の害を防ぐ効果が期待される。例えば、ヨーロピアン・コーンボーラーと呼ばれる害虫は、トウモロコシの茎や実の中に入り込んで内側から食い荒らすため、殺虫剤の空中散布では充分な殺傷効果が得られなかったが、遺伝子組み換えによって植物体自身が殺虫物質を分泌するようになると、比較的容易に駆除できるようになる。既に、遺伝子組み換えされたダイズ・ジャガイモ・トウモロコシなどが市販されている。
殺虫物質としては、土壌中に棲息するBt菌(Bacillus Thuringiensis)が作る毒素(Bt剤)が用いられることが多い。Bt剤は、鱗翅目の昆虫の消化管に存在する受容体に特異的に作用するので、人間を含む他の動物には無害だと信じられており、また、長期にわたって連用しても耐性を持つ昆虫が発生しにくいと言われている。ただし、間欠的に散布する場合と比べて、殺虫物質が常時分泌されるため、こうした環境に適応できる形質を備えた耐性昆虫がダーウィン流の選択によって増殖する危険性が高まるという批判もある(一部地域では、すでに耐性昆虫の発生が観察されている)。また、殺虫物質が植物体内に閉じこめられているので、これを食い荒らす害虫だけが影響を受けるとされていたが、周囲に飛散した花粉を食べた一般昆虫も被害を受けているというデータも提出された。さらに、殺虫物質は人間が食べる部分にも含有されるため、新たなアレルゲン(アレルギーの原因物質)になる可能性も指摘されている。
-
保存性の向上
-
世界で最初に市販された遺伝子組み換え作物(トマト)に導入された形質で、長期間にわたってみずみずしさを保つように操作されているため、流通・販売過程で腐って商品価値を失うものの割合を減殺できる。また、多くの果実は、流通過程で成熟が進むことを考慮して、完熟前に収穫する(トマトの場合は、まだ青くて堅いものが出荷される)ため、葉から供給される栄養分が完全に蓄積されていない憾みがあるが、この技術を用いれば、熟した果実を出荷することも可能になる。こうした日持ちの良い果実は、成熟を促進するエチレン(の前駆物質)を分解する酵素の遺伝子を組み込んだり、エチレンを合成する遺伝子を機能させないような「対抗」遺伝子(アンチセンスDNA)を組み込むことによって作り出す。購入後も風味が保持されて好ましいという意見が多いが、「変に堅いだけ」と批判する声も一部に聞かれる。
-
特定栄養素の産生
-
もともと農作物が持っていない栄養素を含有させて、商品価値を高めようという試みがある。すでに、コレステロール値を下げるオレイン酸を含んだダイズや、熱帯のヤシにしかないはずのラウリン酸を含有するナタネが作られている。さらに、タンパク質が少なく腎不全患者の食事に向いたイネ、鉄分を大量に含有して貧血予防の効果のあるトマトやレタス、リノール酸を含んでガン予防の効果が期待されるダイズなどが実用化に向けて開発中である。こうした食品は、健康志向が強まり、特定の栄養素を含んだ健康食品に対する需要が伸びているアメリカや日本では、歓迎される食品となるかもしれない。
ただし、やみくもに栄養素を加えていくと、大きなトラブルが生じかねない。実際、ピーナッツの成分をジャガイモに加えようとした試みに対しては、ピーナッツ・アレルギーの患者への配慮が欠けているという指摘がなされた。こうした患者はピーナッツを食べると激しいアレルギー反応を引き起こし、場合によっては死に至ることもあるため、自分で食生活を厳しく管理している。しかし、一般的な常識では、ジャガイモの中にピーナッツの成分が含まれているとは考えられないため、うっかり食べてアレルギーが発症する危険もある。このように、アレルギーを生じさせる可能性のある栄養素を含有させるときには、明確に表示することが米食品衛生局によって義務づけられている。また、不自然な遺伝子が機能していることが植物の生育にとって負担となり、かえって作物全体の栄養価が低下することを心配する意見もある
-
開発途上国向けのもの
-
開発途上国の生活を改善するために、遺伝子組み換え技術を利用しようという動きも見られる。特に期待されているのが、ベータカロチン(ビタミンAの前駆物質)を豊富に含有したイネ(コメが黄金色になることからゴールデンライスと呼ばれる)である。アジア・アフリカ・中南米では、ビタミンA欠乏症で免疫力が低下して死亡する子供が年間100万人を越えており、幼児の失明者も多い。こうした地域でゴールデンライスが食されるようになれば、栄養状態を改善する効果があるかもしれない。現在、実用化に向けて安全性のチェックが進められている。ただし、ビタミンA欠乏症を克服できるほどの大量生産が行われるか、ベータカロチンの摂取で病状が改善できるかなどの点を疑問視する向きもある。
感染症の予防に役立つ「食べるワクチン」の研究も進んでいる。開発途上国では、ワクチン注射を大規模に行うことは、衛生上の問題もあって難しい。そこで、遺伝子組み換え技術により、先進国でワクチンの成分を含む作物(バナナやトマトなど)の種子を作成し、これを途上国で栽培することによって、食べるだけでワクチン注射と同じ効果を生む果実が作れると期待される。途上国だけでなく、日本でも、花粉症の予防効果のあるイネが開発されているが、これは食品か医薬品かがはっきりしておらず、販売の目処は立っていない。
途上国向けの遺伝子組み換え作物としては、過剰な潅漑による塩類集積で作物が育たなくなった土地でも生育するトマト、石灰を含み強いアルカリ性を示す土壌でも育つイネ、酸性土壌でも豊かに実るトウモロコシなどの開発が進められている。
途上国向けの作物は、大きな利潤を生むとは考えにくいので、主に大学や国立研究所などで開発されている。
-
植物の品種改良
-
遺伝子組み換え作物に対して不安を感じる消費者が少なくない日本で、かなりの好評を博しているのが、サントリーが販売した「青色の花を咲かせるカーネーション」である(2001年まで日本で栽培される唯一の遺伝子組み換え作物だったが、2002年に作付けが中止された)。これは、カーネーションにペチュニアなどの青の色素の遺伝子を組み込んだものである。この技術を利用して、2004年には、不可能の代名詞だった「青いバラ」を誕生させた(パンジーの色素遺伝子が用いられたが、青というよりは淡い紫と言った方が良い)。
このほか、亜硫酸ガスなどの大気汚染物質に耐性のあるポプラ、パルプ収量の多いユーカリ、タバコモザイクウィルスに対して抵抗性のあるタバコなども開発中。
遺伝子組み換えと安全性
遺伝子組み換え作物は、ビジネスの観点から「有用」と判断された遺伝子を組み込んだ戦略的商品であり、生産性や商品価値を高めるというマーケッティング面でのメリットは否定できない。しかし、その一方で、「土壌生態系の中」ではなく「試験管内部」での品種改良によって生み出されてきた不自然な作物であり、生態系や人間の健康に悪影響を及ぼすのではないかという不安は拭いがたい。いくつかの不安要因を指摘しておきたい。
- 食品の安全性 : 遺伝子組み換え食品の安全性は、「実質的同等性」という概念に基づいて評価されている。すなわち、導入された遺伝子の起源や特性がよく知られており、植物が有するアルカロイドなどの自然毒に変化がなく、新たに産生されるタンパク質がアレルギーなどの有害反応を引き起こさない場合に、既存の食品と同等の安全性を持つと考えられる。すでに市販されている遺伝子組み換え作物は、この観点から安全性が認められたものである。しかし、人類が長い間の経験から安全な調理法・摂取法を探し出してきた――例えば、ジャガイモの芽にはソラニンという有毒物質が含まれているので、これを取り除いて調理する――自然食品と似て非なる遺伝子組み換え作物に対して、従来の経験則を適用することが妥当だという保証はない。安全面で特に懸念されているのは、新たなアレルゲン(アレルギーの原因物質)が含有されないかという点である。この点に関しては、導入した遺伝子によって作られる化学物質が、既知のアレルゲンと構造的な類似性があるかどうかを調べることによって安全性の確認を行っているが、植物の代謝系が全体的に変化している可能性もあり、完全なチェックとは言い難い。
2003年、国連の食品規格委員会は、アレルギー検査を中心とする安全性の国際指針を採択した。強制力はないものの、国際的な標準になると予想される。これまで、国レベルで認可された作物による健康被害の報告はないが、2001年に食用の輸入トウモロコシへの混入が問題となった飼料用GMコーンの「スターリンク」は、人間が食べるとアレルギーを引き起こす可能性があった。
- 植物の弱体化と栄養価の変化 : 遺伝子組み換えによって新たに生化学合成を行わされることになった植物は、通常よりも生育上の負担が増大していると考えられる。こうして植物が弱体化した結果として、農作物に含有される栄養素の配分が変化したり全体量が減少することは、充分に予想される事態である。また、代謝系が乱された植物が、特定の病気に対して著しく抵抗性を欠くようになる可能性も指摘できる。場合によっては、伝染病が拡がって農場が全滅することもあり得る。実験室で遺伝子組み換えを行った作物に、不稔性などの異常が生じるケースがあることは、すでに報告されている。
- 生態系への影響 : 殺虫成分を分泌する農作物に関しては、当該成分が常時含まれる状態に生態系が維持されるため、殺虫剤が間欠的に散布される場合よりも耐性を持った昆虫が発生しやすい。また、農作物を食する害虫に対してだけ殺虫効果を発揮すると言われていたが、花粉に含まれた状態で殺虫成分が外部に飛散するため、害虫以外の昆虫への影響も皆無ではない。
さらに、長い年月を掛けた育種とは異なり、不自然な形で(しばしば種の壁を越えて)導入された遺伝子が、生態系の中でどのような作用をするか誰にも予想できないことを指摘する意見も多い。例えば、作物に組み込まれた遺伝子が、花粉の飛散やバクテリアによる水平遺伝を介して環境中に解き放たれ、周辺の生物に何らかの影響を与える可能性もある。周囲の植物が除草剤耐性の遺伝子を含んだ花粉を受粉し、除草剤が効かない雑草が繁茂する結果になるかもしれない。こうした事態が実際に起きる確率はきわめて小さいが、遺伝子組み換え作物が広範囲で栽培されるようになった場合は、決して無視できないだろう。水平遺伝ではないが、カナダの農場では、除草剤耐性を持つナタネが小麦畑に侵入し、除草剤で駆除できずに農民を困らせているという。
- 化学汚染 : 除草剤に耐性を持つ農作物の場合は、雑草を根絶するために多量の除草剤を散布していることが多く、河川の汚染や食品への残留などが心配される。
各国の対応
- EU : 遺伝子組み換え食品に関しては、健康や環境に対する悪影響が懸念されることから、その是非を巡ってヨーロッパを中心に大きな議論が巻き起こっている。ヨーロッパの市民団体は、全体として遺伝子組み換え食品に対して批判的であり、"Frankenstein Food"と呼んで排斥運動を展開した。こうした流れを受けて、アメリカの要求の下にすでに一部製品の輸入を解禁していたEUでは、2000年から原料に遺伝子組み換え作物を1%以上使用する全製品で使用表示を義務化した。また、1998年には遺伝子組み換え作物の新規認可を凍結したが、アメリカからの批判もあって2001年に凍結解除を発表した。遺伝子組み換え食品に反対する動きは、主に安全性に敏感な市民団体によって進められているが、そこに、安全保障の考えに基づいて域内での食糧自給を目指すEUが、農業大国アメリカの戦略的商品である遺伝子組み換え作物を受け入れまいとする政治的配慮も絡んで、国際的に複雑な状況を生み出している。EUの政策を貿易障壁と受け止めるアメリカは、WTO(世界貿易機関)でこの問題を議題に乗せ、国際的な摩擦に発展した。
- アメリカ : ヨーロッパでは遺伝子組み換え作物の安全性が疑われているのに対し、アメリカの市民は、これを科学技術の成果として比較的好意的に見ているようである。アメリカでは、ダイズ・トウモロコシ・ジャガイモを中心に遺伝子組み換え作物が広く栽培されており、1999年には遺伝子組み換えダイズが全作付け面積の57%を占めた。EUや日本から非遺伝子組み換え作物の需要が増えていることもあって2000年には52%に減少したが、2001年には74%に増加している。
米科学アカデミーは、2000年4月にBtコーン(Bt剤を産生するトウモロコシ)などについて、各種の検査結果に基づいて「食べても安全」と結論づける報告書を提出した。ただし、2002年には、同アカデミーの専門委員会から、環境に対する影響評価が不十分であるとの勧告が提出されている。
- 日本 : 一方、アメリカから大量の農作物を輸入している日本では、政府や業者が対応に苦慮しているというのが実状である。日本の場合、輸入ダイズの75%、輸入トウモロコシの87%が米国産で、そのうち遺伝子組み換え作物の占める割合は、ダイズで27%、トウモロコシで23-34%と推定される(1998)。表示の義務化について、当初、厚生省は「その必要はない」という見解を示していたが、安全性を心配する声が高まったことから、農水省が乗り出し、2001年からダイズ・トウモロコシを原料とする24品目(豆腐・納豆・コーンスナック菓子など)について、
「組み換え」(遺伝子組み換え作物を原料に使用)
「不分別」(組み換え作物が混入している可能性がある)
という表示を義務づけた(ダイズの場合は、5%以上の混入が基準)。「組み換え」の商品は売れ行きが落ちると予想されるため、非組み換え原料を使用する業者が増えつつあるが、組み換え原料に比べてダイズで40%、トウモロコシで30%程度割高になるため、消費者の側も選択を迫られることになる。
事態をいっそう紛糾させたのは、輸入作物に未認可の組み換え品種が混入するという事件が相次いだことである。2000年末には、米国で飼料用にのみ認可され、日本では飼料用・食品用ともに未認可の遺伝子組み換えトウモロコシ「スターリンク」が食品用原料に混入していたとして、回収騒ぎに発展した。同様の事件は、2001年にジャガイモでも起きている。このため、食品業界では、米国における混入検査の強化や輸入元の変更などを行ったが、結果的にコストの上昇につながった。
- 国際社会 : 2000年1月、遺伝子組み換え技術を応用して作った動植物の国際取引を規制する「カルタヘナ議定書」が、生物多様性条約臨時締約国会議で130を越える締約国により採択された(日本は批准準備中、米国は生物多様性条約を批准しておらず公式には会議に参加していない)。この議定書の規定は、主に、環境に放出される恐れの少ない食品・飼料用の遺伝子組み換え作物を適切に管理することを目的としている。輸入国は、「バイオセイフティ情報センター」から必要な情報を入手でき、危険性を裏付ける証拠が不十分な場合でも輸入を止められる。また、遺伝子組み換え作物が混ざっている積み荷を区別することが義務づけられる。
遺伝子組み換えは高度な技術であり、安全性の問題に最終的な結論は出されていない。にもかかわらず、農業分野で覇権を握ろうとするアメリカの思惑に従って、急速に実用化されつつある。ここで必要なのは、われわれは、生命に関して、まだ十全な知識を獲得していないという基本的な認識を持つことであろう。現段階で行われている遺伝子操作は、ある物質をコードする遺伝子を生体に組み込む(というよりは単に細胞の中に入れる)作業でしかない。科学的に確認されているのは、その物質が産生されていること、およびその直接的な帰結(害虫抵抗性など)だけであり、代謝や免疫などの複雑な生体機能や、当該個体を含む生態系がどのように変動するかについて、科学はいまだ解明できていないのである。こうした全体系への視座を欠いたままで技術革新の成果に浮かれていると、後で手ひどいしっぺ返しを食らいかねないことは、肝に銘じておかなければならないだろう。
【参考】従来の品種改良との相違
産業としての農業において、社会からの求めに応じた「製品」の品質改善は、ビジネス・チャンスを拡大するために、当然成し遂げなければならないことである。ただし、単純な製造工程から構成されている工業製品の製造業と異なって、農業の場合、製品である農作物は、複雑な生態系の一部として他の多くの要素とリンクしており、品質改善(=品種改良)の試みが、農業の基盤となる環境そのものを改変する危険性を孕んでいる。20世紀半ばまでは、まだ「土壌生態系の中での品種改良」が主流であったため、環境への影響はそれほど大きくはなかった。しかし、バイオテクノロジーの助けを借りて、組織的な「試験管内(in vitro)での品種改良」の試みが続けられているこんにち、これが環境の改変を経て農業そのものへ打撃を与える可能性は、決して小さくない。
19世紀までの品種改良は、篤農家による優良品種の選別という形で行われてきた。先進的な農業活動家が優良な変種を発見すると、その種子を採取して栽培し、翌年、再度優良な形質が確認されれば、これを新品種として広めた。このようにして、収量や食味、病虫害への抵抗力などの点で問題のあった在来種を、少しずつ人間の要求に適ったものに置き換えていったのである。
20世紀にはいると、こうした優良品種の選別が、より系統的に行われるようになる。「純系分離法」と呼ばれる手法では、試験場で栽培される株ごとに種子を採取し、これを別々な系統として育てることを繰り返して、最も望ましい系統を選抜していく。このような手法によって、社会的に要求される特定の形質を持つ品種を、短期間で作り出すことが可能になった。日本でのコメ生産の場合、化学肥料の生産が開始されると耐肥性が、東アジアからの輸入米が増加すると食味が重視されるようになったが、こうした要求に応じて、農業試験場から次々と新しい品種が生み出さていったのである。
このような品種改良は、まだ土で作物を育てる過程を含んでいるため、人間に完全には制御できない土壌生態系の複雑さを踏まえた育種と言えるものだった。しかし、農業ビジネスに対する社会的要求は、しだいに、こうした悠長さを許さない段階まで高まってくる。
20世紀後半には、より科学的な育種法として、特定の品種を交配させて望ましい形質を持つ作物の種子を作るハイブリッド(一代雑種)の技法が実用化される。例えば、ハイブリッド米とは、自殖性(自家受精を行う性質)のイネを他殖性に変え、遠縁の品種(インディカ種とジャポニカ種など)を交配して雑種強勢をはかった一代雑種である。こうしたハイブリッド米の基礎技術は50年代に開発されるが、普及するのは、1976年に中国で多収米が採用されてからである。一代限りでしかないハイブリッドの種子は、農家が自分で調達することができないため、毎年、種苗会社から購入して作付けするという生産システムが定着することになる。
さらに、1970年代に入ると、バイオテクノロジーを利用した新しい育種法が開発される。組織培養法は、試験管内で細胞を培養し、人工種子を作成したり優良形質株を選び出すもので、植物を土壌生態系から切り離し、「生体マシン」として扱うという側面を持つ。また、細胞融合法は、プロトプラスト(細胞壁を除いた細胞)の融合により新品種を作り出そうとする技術で、1986年にハクサイとキャベツの細胞融合によって作り出された「バイオハクラン」が有名である。
こうした「試験管内(in vitro)での品種改良」は、しばらくの間は期待されたほどの成果を上げていなかったが、1990年代になって、遺伝子組み換え技術の応用により、植物の形質を人間が自由に操ることが可能になったわけである。
©Nobuo YOSHIDA