
原田氏の著書は、物理学の初歩も知らない人が書いた「相対論は間違いだった」というトンデモ本のたぐいとは一線を画しているように見えます。しかし、相対論的な現象の解釈が主流派とはっきりと異なっているにもかかわらず、その解釈を正当化するだけのしっかりした論拠がないばかりか、実験データの解釈や主流派への反論において不適切な内容が目に付きます。細かい点までチェックしていませんが、ざっと読んだ限りでは、あまり真剣に受け止めない方が良いタイプの本だと思います。ここでは、私が疑問に感じた点を挙げておきましょう。
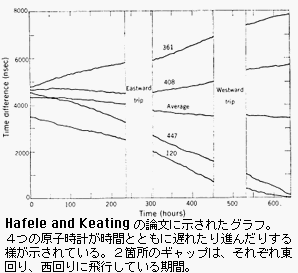
原田氏がことさら強調しているのが、「ヘイフリーとキーティングの実験は捏造だった」という主張です。この実験は1971年に行われたもので、商用ジェット機に4個のセシウム原子時計を積み込み、西回りと東回りで地球を周回したときに、時計の進み方にどの程度の変化が生じるかを測定しています(J. C. Hafele and R. E. Keating, Science 177 (1972) 166-168, 168-170)。時計に影響を与える効果として、(1)静止系に対する運動系での時間の遅れ(地表の時計に比べて東回りで遅れ西回りで進む)、(2)重力の作用による時間の遅れ(重力の強い地表の方が遅れる)の2つを考慮し、速度や高度の変化の影響を取り入れて理論的な予測値を計算すると、東回りで 40±23ナノ秒の遅れ(ナノ=10億分の1)、西回りで 275±21ナノ秒の進みとなりました。一方、4個の原子時計における時間変化の平均値は、東回りで 59±10ナノ秒の遅れ、西回りで 273±7ナノ秒の進みとなり、相対論の予測と巨視的な時計を使った実験結果が見事に一致した例として知られています。ところが、2000年になって、ヘイフリーとキーティングのデータには問題があるという論文が発表され、一部で注目を浴びました(A. G. Kelly, "Hafele & Keating Tests; Did They Prove Anything? ")。それによると、携帯用セシウム原子時計の進み方は不安定で、もともと1時間当たり数ナノ秒程度(最大で8.89ナノ秒)の狂いがあるが、ヘイフリーとキーティングは、その狂いを補正する際に理論的な予測値に近づけるようなデータ操作を行っているということです。
私は、ヘイフリーとキーティングの実験に対する批判は必ずしも正当だと思いません。彼らによる誤差の見積もり(測定値の±に続く部分)が小さすぎるのは確かですが、原論文のグラフを見ると、各時計の不安定性を考慮しても、東回りでは少し遅れ、西回りでは大きく進む傾向が読みとれるからです。しかし、それ以上に重要なのが、この実験が相対論の正当性を示す主たる根拠ではないということです。実験が行われた当時から、多くの物理学者は、これが相対論の正当性を調べる検証実験ではなく、原子時計の正確さをアピールするデモンストレーションだと受け取っていました。現在では、GPS(全地球測位システム)衛星に原子時計が搭載されており、その進み方の変化が相対論の予想と高い精度で一致することが確認されています。GPS衛星と地表では(上の(1)と(2)の効果を併せて)時間の進み方に100億分の1程度の差が生じるので、両者の時計は1時間の間に300ナノ秒程度はずれてきます。この違いを無視すると、電磁波による位置測定で(光速30万km/秒 × 300ナノ秒 =)100m程度の狂いが生じます。カーナビが1時間に100m、1日に2〜3kmも狂っていたのでは使い物になりませんが、現実のGPSでは相対論的効果による時刻のずれが補正されているので、充分に実用的な精度が確保できるのです。ヘイフリーとキーティングの実験データが正確かどうかはわかりませんが、われわれは、「カーナビが正しい位置を教えてくれるか」を確認することで、基本的に同じセットアップによる実験を日々行っており、1971年当時よりも遥かに高い精度でポジティブな結果を得ているわけです。
主流派に対する原田氏の批判にも、いくつかの問題点を指摘することができます。例えば、松田卓也・木下篤哉著『相対論の正しい間違え方』(パリティブックス)のある議論に対して、原田氏は、ローレンツ短縮が物質に加わる力によって生じるかのように説明していると批判します。しかし、『正しい間違え方』の該当する部分を読んでみると、何両か連結された車両を外部から見て一様に加速する場合を例にして、運動体に固定された座標系で見たときに各部分で加速のされ方が異なることを指摘し、一体であるためには連結部に応力が発生すると論じているだけです。原田氏の批判は、初歩的な誤解に基づくものです。こうした問題点があちこちに見られるので、「単位の相対性」のような新しい解釈に関しては、詳しく検討しようという気が起きません。
【Q&A目次に戻る】

現在では、光電効果やコンプトン効果に関しては精密な測定が行われており、その結果と完全に合致するのは、今のところ、光が粒子性を持つ理論(量子電磁気学、またはこれを含む理論)だけです。しかし、歴史的に見ると、光の粒子説が確立されるまでには、さまざまな紆余曲折がありました。
光が粒子的な振舞いをすることを最初に示したのは、1905年に発表されたアインシュタインの光量子論ですが、発表当初、この理論はほとんど見向きもされず、プランク、ローレンツ、ボーアといった名だたる物理学者もおしなべて批判的でした。光電効果におけるアインシュタインの予想を実証した1915年のミリカンの実験によって、その正当性を認める人が少しずつ増えていきますが、光量子論によってアインシュタインがノーベル賞を受賞した1921年になっても、批判者は後を絶ちませんでした。大半の物理学者が光量子論を受け容れざるを得なくなったきっかけは、1923年のコンプトン効果の発見です。光の粒子性を用いずにコンプトン効果を説明することは、きわめて困難だからです。しかし、ここに至るまで、光の粒子性を使わずに光電効果を説明しようとする理論がいくつも提案されました。
光電効果の特徴は、金属に光を照射したときに飛び出してくる光電子の最大運動エネルギーが、照射光の振動数だけに依存し、光の強度とは無関係な点です。もし、光の振動が金属内部の電子を揺さぶって外部に飛び出させているのならば、振幅の大きい光ほど大きな運動エネルギーを持った光電子を作り出すはずですが、そうなってはいません。
この特徴を説明するために考案されたのが、「誘発説」と呼ばれる理論です。これは、照射する光は電子が飛び出すための引き金になっているだけで、光電子の運動エネルギーの起源は金属の熱エネルギーだとするものです。しかし、この説は、金属の温度を変化させても光電子の運動エネルギーが変わらないことから、あっさりと否定されます。
次に提案されたのが、ゾンマーフェルトによる「共鳴説」(1911)です。当時、金属内部の電子は、ちょうどバネに取り付けられたおもりのように、平衡点からの距離に比例する復元力を受けると考えられていました。こうした電子は、バネのおもりと同じく一定の振動数νで振動しますが、νと同じ振動数を持つ電場が外部から加えられると、この電場の振動に共鳴して振幅がどこまでも大きくなっていきます。ただし、ニュートン力学に基づいて電子が持つエネルギーを計算しても、光電効果の特徴は再現できません。そこで、ゾンマーフェルトは、プランクによる量子仮説と組み合わせてみようと考えたのです。1900年、プランクは、電子の振動エネルギーは振動数νに定数hを乗じたものの整数倍に限られるとする理論を考案しました。これが、プランクの量子仮説で、hはプランク定数と呼ばれています。ゾンマーフェルトは、プランクの仮説を拡張する方法についてあれこれ考察していましたが、その1つとして、金属内部の電子が電場に共鳴するのは、プランクの量子仮説と良く似たある条件が満たされている場合に限られるという理論を提案しました(具体的な式の形は参考文献を見てください)。この仮定の下では、光電子が持つ最大運動エネルギーは、hνに小さな補正を加えたものになります。金属に振動数νの光を照射すると、金属内部に存在するさまざまな電子の中でνに共鳴する電子だけがエネルギーを吸収するものの、量子条件を満たさなければならないという制約から、運動エネルギーがhνになるというわけです。
ゾンマーフェルトの理論は、光電子の運動エネルギーが光の強度によらず、振動数に対して直線的な関係になるという現象を正しく説明することから、かなりの好意をもって迎えられましたが、間もなく問題が明らかになりました。1912年にコンプトンが、光電子の個数は照射光の強さに比例するという法則を見いだしますが、共鳴説では、これをうまく説明することができなかったのです。光電効果に関しては、この後もさまざまな泡沫理論が提案されては消えていきますが、1920年代には光量子論が定着し、さらに、1927年のディラックの光の放出と吸収に関する摂動論、1929年のハイゼンベルク=パウリの量子電磁気学によって、光の粒子性を含意する理論が確立されます。
【参考文献】西条敏美著『物理学史断章 : 現代物理学への十二の小径』(恒星社厚生閣)
【Q&A目次に戻る】

物理学者が空間と時間は連続的だと仮定するのには、2つの理由があります。1つは、連続的だとした方が計算に便利だから、もう1つは、今のところ非連続的だとする理論にうまくいくものがないからです。どちらも、それほど本質的ではなく、物理学者たちが空間・時間は連続的だと心底信じているわけではありません。
空間・時間は連続的だという仮定が便利なのは、解析学の手法が利用できるからです。流体力学のことを考えてみてください。物理学者は、気体や液体が分子・原子の集まりであることは百も承知でありながら、流体は連続的であるとしてナヴィエ=ストークスの方程式を立てます。実際、分子・原子の運動論を展開しても、計算がやたらと難しいばかりで、あまりめざましい成果は出てきません(気体の粘性抵抗など、計算できる量もあることはありますが)。それよりも、微分方程式論が専門の数学者と協力してナヴィエ=ストークス方程式を解いた方が、遥かに多くの結果が導けます。流体が実は非連続的であることの影響は、乱流のように解が発散するケースで顔を出しますが、そうした問題が生じる領域は限られているので、その領域だけ特別扱いすれば良いだけです。
ミクロの極限を扱う素粒子論では、留数定理や収束半径など解析学の手法をフルに活用していますが、これは、空間や時間が連続的であることを大前提としているわけではありません。実際、空間や時間が連続的だと理論がうまく定義できないことが多いので、まず空間や時間は非連続的だとして理論の枠組みを作り、しかる後に、非連続性が表に出ないように連続極限を取るというのが一般的な理論構成です。連続極限を取ることができれば、さまざまな物理量が空間・時間の連続関数として表されるので、解析的な計算が可能になります。連続関数による表現は、真の理論に対する近似にすぎませんが、ナヴィエ=ストークスの方程式が良い近似であるのと同じように充分に良い近似だと信じられるので、安心して解析学の定理を利用しているのです。
もしかしたら、空間や時間は連続的ではないかもしれません。しかし、非連続的な空間・時間を扱う理論は、いまだ実用的な段階には達していません。例えば、素粒子論で理論の枠組みを作る際に、空間・時間が格子状になっているというモデルを利用することがありますが、実際の世界がこれと同じような格子状の空間・時間から成り立っているのではないかと考えると、いろいろな支障が生じます。何よりも、結晶格子と同じように、結晶軸の方向とそれ以外の方向では物理的な性質が異なってしまい、伝播する方向によって光速が違うといった結果になってしまいます。こうした問題が表面化しないようにあれこれ取り繕うと、結局は連続極限を取るのと同じことになってしまい、非連続的なモデルを仮定することが無意味になります。
こうした事情があるので、取りあえずは連続的な空間・時間を扱っていますが、連続的であるべきだというこだわりはないはずです。
【Q&A目次に戻る】

質問にあるのは2003年に発表されたWMAP(ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機)の観測データですが、CMBの光源と地球の位置関係は、宇宙がどのように膨張してきたかを決める宇宙モデルに依存しており、観測データだけからは正確な数値は明言できません。
CMBの光がいつ放出されたかは、観測データと理論的なモデルを組み合わせることによって求めます。CMBは、電子が原子に吸収されて光が素通りできるようになった「宇宙の晴れ上がり」期に放出された光であり、その赤方偏移パラメータz は 1089±1 と正確に測定されています。しかし、この値から放出時期を求めるには、特定の宇宙モデルを仮定し、その膨張の変化を表す式に代入して計算しなければなりません。最も確からしいとされているのは、現在よりも137±2億年前、ビッグバンから37万9(+8/-7)千年という数値です(これは、他の観測データと突き合わせたときに最も辻褄の合う数値ですが、信憑性はかなり高いと思われます)。宇宙モデルを仮定しなければ計算ができないのは、膨張の速度が変化するとそれに応じて赤方偏移の値が変わり、観測された赤方偏移の値と過去の宇宙の状態を結びつけることができなくなるからです。
特に、空間的な位置に関して議論する際には、注意が必要です。CMBの場合、光が放出されたのは確かに137億年前ですが、光源(宇宙の晴れ上がりの瞬間に光がいた場所)までの距離が137億光年とは言えません。通常の宇宙論では、全ての銀河を平等に扱う座標系で距離を定義しますが、この座標系は宇宙で時間が経過するにつれて刻々と変化するため、「ある時刻での距離」という言い方しか意味がないからです。光の経路長も定義が曖昧です。数千万光年程度の比較的近い銀河ならば、現在の距離であろうと(光が出た)数千万年前の距離であろうとそれほどの差はありませんが、数十億年以上のタイムスケールでのイベントとなると、距離の定義はかなりややこしくなります。一般向けに発表される初期宇宙の観測データで、赤方偏移や宇宙時間だけが示されて距離の値が表記されないのは、そのためです。
CMBの光は、ちょうど動く歩道を逆向きに歩いている人のように、宇宙空間の膨張に逆らいながら進んできたものです。このため、137億年間にわたって空間を伝わっている間に、光源までの距離はどんどんと引き延ばされ、
現在 では、CMB の光源は、おそらく400億光年よりも彼方に位置しており、われわれから見て(と言っても、もう見えませんが)光速の50倍以上のスピードで遠ざかっています。それでは、光が放出された時刻での光源と地球(と言うか、将来、銀河系へと成長する密度揺らぎの位置)の距離はどの程度だったかとなると、もはや何とも言えません。膨張過程を宇宙初期にまで外挿する場合、計算に用いる宇宙モデルによって値が大きく異なるからです(質問にある1258万光年という数字は、「137億光年÷1089」という計算結果だと思いますが、それほど簡単に計算できることではないのです)。宇宙が現在より約1000分の1(正確に1089分の1だったわけではありません)の時代のことなので、距離のスケールが1千万光年単位になるとは思いますが、それよりも細かな数値を導くことは、現在の段階では困難でしょう。
【Q&A目次に戻る】

電子や陽子の個数が数えられるのは、これらの素粒子を含む反応が、個数の保存則とエネルギー保存則という2つの物理法則に従っているからです。光子の場合は、個数の保存則が存在しないので、原則的には個数は数えられません。
電子の場合について説明しましょう。電子は、近似的に「電子数の保存則」に従っています。この法則によれば、
電子数=電子の個数−陽電子の個数
は一定に保たれています。陽電子とは、電子の反粒子のことで、質量が等しく電荷の符号が反対の粒子です。電子と陽電子がペアで生成されれば、電子数を一定に保ったまま電子の個数を増やしていくことが可能です。しかし、あらゆる物質は、質量をmとすると mc
2 という質量エネルギーを持っているため、外部から少なくとも 2mc
2 という(電子と陽電子の質量エネルギーの和に相当する)エネルギーを注入しなければ、電子と陽電子をペアで作り出すことはできません。この値は、通常の化学反応で放出されるエネルギーの数十万倍にもなるため、超高温でもない限り、物質内部でいきなり電子・陽電子ペアが生み出されることはありません。特に、外部から作用を受けない自由電子は、最初の個数を保ったままでいます。ただし、巨大なエネルギーを持つ宇宙線が大気と相互作用すると、電子と陽電子のペアが数多く生成される電子シャワーと呼ばれる現象が生じることがあります。
「電子数の保存則」は近似的なものだと記しましたが、厳密に成り立っているのは「レプトン数の保存則」です。これによると、電子がWボソンを放出して電子ニュートリノに変わることが可能です。しかし、Wボソンは質量が電子の16万倍もあり、Wボソンが崩壊してできる素粒子も全て質量が電子より大きいため、エネルギーの保存則によって、電子の個数が変化するような反応は禁止されることになります。
電子や陽子とは異なり、光子に関しては、「光子数の保存則」という物理法則はありません。1個の光子がいつの間にか複数の光子に変化してしまうような反応は、「ゲージ不変性」と呼ばれる(個数の保存則とは別の)物理法則で禁止されています。しかし、個数の保存則がないために、光子の量子力学的な状態は、さまざまな個数の状態が重ね合わされたものになります。
個数の保存則がある場合、個数の異なる状態が量子力学的な意味で干渉することはこの保存則によって禁止されているので、素粒子は個数の固有状態(個数が定まった状態)で表されます。ところが、光子の場合は、個数の保存則がないために、個数の固有状態では表されません。例えば、荷電粒子が外部からの作用を受けて軌道が曲げられるときには、個数の定まらない光子群がバラバラと放出されることになります。同じような事情は、原子核内部で陽子と中性子を結合させているπ中間子にも当てはまります。原子核内部の陽子と中性子の個数は定まっていますが、π中間子が何個あるかは決まっていません(数えるための測定技術がないのではなく、個数自体が不定なのです)。
光子に質量があれば、光子の個数が増えるとそれだけ質量エネルギーが増すので、エネルギーの保存則によって個数が一定になりますが、光子には質量がないので、エネルギーの保存則で個数を定めることもできません。通常、個数の保存則に従わない質量ゼロの素粒子は、孤立した安定状態を取ることができませんが、光子の場合は、ゲージ不変性に守られる形で、自由に空間中を伝播することができるのです。
光子の個数は不定ですが、光子が関与する素粒子反応の中には、1つの光子の寄与が圧倒的に大きくなる場合があります。特に有名なのが、コンプトン散乱と光電効果です。この反応では、1つの光子が電子と相互作用したと仮定するだけで定量的な振舞いをほとんど説明できてしまい、2つ以上の光子の寄与は2桁以上も小さな値になります。これは、電子と光子の相互作用定数αの値が1/137と小さいためです。従って、コンプトン散乱や光電効果に関しては、1個の光子が飛来して電子と相互作用したと見なしてかまわないことになります。
【Q&A目次に戻る】

物理学者が次元数の世界を想定するのは、そうすることで現実に見られる秩序の起源が解明できると考えられるからです。つまり、高次元の世界というアイデアが先にあり、これを空間3次元という目に見える世界に「コンパクト化」する操作は、どちからかと言うと、理論と現実が合致するようにつじつまを合わせるためのものなのです。なぜ世界はコンパクト化されているのかという質問に対して、物理学者があまり胸を張って回答していないのは、そのせいです。
この世界が3次元よりも高い次元数を持つ空間からできているというアイデアは、1920年代に作られたカルーザ=クラインの理論にまで遡ります。アインシュタインの一般相対論は、4次元時空(時間1次元と空間3次元)を対象としていますが、カルーザ=クライン理論では時空は5次元となっています。「新たに加えられた次元における一般相対論の相互作用が、コンパクト化された4次元の世界では電磁気的相互作用として姿を現すと解釈できる」というのがカルーザとクラインの基本的な考えです(正確に言えば、カルーザは数学的に次元数を上げてみただけで、物理的な解釈を施したのがクラインです)。このように、次元数を上げることで、4次元の世界では説明不能な現象(例えば、なぜ電磁気的な相互作用が存在するのか)を解明しようというのが、高い次元数の世界を考える理由です。1970年代に入ってから、素粒子物理学で議論の対象となったのが、なぜ陽子と電子の電荷は大きさが同じで符号が反対なのかといった問題です。こうした問題を解決するには、数学的な対称性を考察する必要がありますが、4次元の時空では、観測事実をきちんと説明できる対称性を見いだせませんでした。そこで、次元数を増やして、より大きな世界での対称性を考える理論が流行するようになります。超ひも理論や(その発展形である)M理論なども、その流れの中にあります。
M理論では、11次元の時空を考えることにより、さまざまな電荷を持つ素粒子が存在する理由を統一的に説明しようとしています。ここまでは、数学的に美しいと言えなくもない理論です。しかし、この理論は明らかに観測事実とは合致していません。そこで、時空が4次元に見えるように余分な次元は全て縮こまっている(あるいは、拡がったままでいるけれども、4次元の世界とは目立った相互作用はしていない)と解釈し、コンパクト化という言い訳めいた便法を使っているのです。また、現実に見つかっていない素粒子が数多く存在することになってしまうので、見つからない理由をあれこれと考え出しています(見つかっていない素粒子の一部がいまだ解明されていない宇宙の暗黒物質だという便利な解釈もあります)。しかし、この辺りの議論は、それほどエレガントとは言えません。もしかしたら、そのうち全てをエレガントに説明できる理論が作り出されるのかもしれませんが、今の段階では、一部の物理学者が主張する理論をあまり真剣に受け取らない方が良いでしょう。
【Q&A目次に戻る】
 別の質問に対する回答
別の質問に対する回答でも述べましたが、記憶はニューロンのネットワークの中にコードされていると考えられています。ただし、単純に、結合のトポロジー(どのニューロン同士がつながっているかということ)だけではなく、シナプスと呼ばれる結合部分の立体構造や神経伝達物質の産生能力など、生理学的な詳細が記憶内容に深くかかわってきます。したがって、ニューロンの配置まで捉えられるような高精度のMRI(ないしはそれに類似する装置)が開発されて、ニューロン・ネットワークのトポロジーがデータとして記録できたとしても、記憶を保存したことにはなりません。少なくとも、シナプス結合の生理学的な性質まで突き止めなければ、データとしては不十分です(ネットワークのトポロジーとシナプスの性質さえわかれば記憶を再生できるのか、断定はできませんが)。人間の大脳皮質には100億個強のニューロンが存在しています。側頭葉の記憶にかかわる部分だけでも億単位になるので、ニューロン・ネットワークを探索・記録するだけでも至難の業ですが、さらに、ニューロンよりも2桁以上多いシナプスの生理学的な性質まで調べていくことは、人間の技術ではほぼ不可能と言って良いでしょう。
個人の人格がどのように決まっているかは、まだあまりわかっていませんが、ニューロンやシナプスの性質と密接に関連していることは確かです。例えば、ギャンブルが好きかどうかは人格にかかわる問題ですが、パーキンソン病の治療などで神経伝達物質の一種であるドーパミンの機能を補う薬を投与すると、ギャンブルへの嗜好が強まるという報告があります。したがって、将来的には、神経伝達物質の産生能力を調べることなどによって、その人の特徴(ギャンブルが好きかなど)をある程度まで推定することが可能になるとは思われますが、それでも、人格の再生とはほど遠い話です。
【Q&A目次に戻る】

私が知る限りでは、単なる偶然の一致でしかないようです。
太陽と月の直径・地球からの距離・直径/距離の値は、それぞれ次のようになります:
| | 直径 | 地球からの距離 | 直径/距離 |
| 太陽 | 139万2000km | 1億4960万km | 0.0093 |
| 月 | 3476km | 38万4400km | 0.0092 |
直径/距離の値が両者でほぼ等しいため、太陽と月が同じ大きさに見えるわけですが、そうなる物理的な理由は思い当たりません。
月は、46億年前、できかけの原始地球に火星ほどの大きさの微惑星が激突、飛び散った破片が凝集して形成されたと考えられています。月と地球の直径比は27%にもなり、太陽系にある衛星の多くが2〜3%でしかないのに比べて不釣り合いに巨大で、衛星と言うよりは、地球と連星系を構成する兄弟星と言った方が良いかもしれません。このため、他の惑星上から眺められる多くの衛星よりも見かけが大きく、神話や芸術を生み出す迫力ある天体となっています。
太陽系内の地球型惑星に属する衛星で発見されているのは、月以外には火星のフォボスとディモスだけですが、大きいフォボスでもわずか20kmほどで、地球から見る月の40%、火星から見る太陽の60%程度の大きさにしか見えません。木星型惑星の中には、直径で月より大きな衛星を持つものがあり、その中には、惑星上から見た太陽よりも大きく見えるものがあります。例えば、木星から見た太陽の見かけの大きさは、木星から太陽までの距離が地球−太陽間の 5.20倍であるため、地球から見た場合の 0.19倍となります。一方、最も低い軌道を回るガリレオ衛星のイオは、直径 3630kmと月とほぼ同じ大きさで、木星からの距離も 42万2000kmであるため、木星表面で天頂にあるイオを見上げると、月よりも大きく見えることになります(もちろん、月ほど明るくはありませんが)。大きさだけで比較すると、太陽よりも遥かに大きな衛星が夜空に浮かんでいるわけです。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
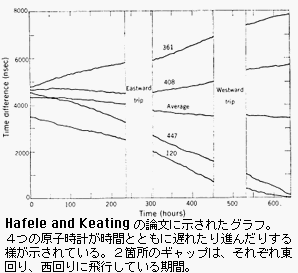 原田氏がことさら強調しているのが、「ヘイフリーとキーティングの実験は捏造だった」という主張です。この実験は1971年に行われたもので、商用ジェット機に4個のセシウム原子時計を積み込み、西回りと東回りで地球を周回したときに、時計の進み方にどの程度の変化が生じるかを測定しています(J. C. Hafele and R. E. Keating, Science 177 (1972) 166-168, 168-170)。時計に影響を与える効果として、(1)静止系に対する運動系での時間の遅れ(地表の時計に比べて東回りで遅れ西回りで進む)、(2)重力の作用による時間の遅れ(重力の強い地表の方が遅れる)の2つを考慮し、速度や高度の変化の影響を取り入れて理論的な予測値を計算すると、東回りで 40±23ナノ秒の遅れ(ナノ=10億分の1)、西回りで 275±21ナノ秒の進みとなりました。一方、4個の原子時計における時間変化の平均値は、東回りで 59±10ナノ秒の遅れ、西回りで 273±7ナノ秒の進みとなり、相対論の予測と巨視的な時計を使った実験結果が見事に一致した例として知られています。ところが、2000年になって、ヘイフリーとキーティングのデータには問題があるという論文が発表され、一部で注目を浴びました(A. G. Kelly, "Hafele & Keating Tests; Did They Prove Anything? ")。それによると、携帯用セシウム原子時計の進み方は不安定で、もともと1時間当たり数ナノ秒程度(最大で8.89ナノ秒)の狂いがあるが、ヘイフリーとキーティングは、その狂いを補正する際に理論的な予測値に近づけるようなデータ操作を行っているということです。
原田氏がことさら強調しているのが、「ヘイフリーとキーティングの実験は捏造だった」という主張です。この実験は1971年に行われたもので、商用ジェット機に4個のセシウム原子時計を積み込み、西回りと東回りで地球を周回したときに、時計の進み方にどの程度の変化が生じるかを測定しています(J. C. Hafele and R. E. Keating, Science 177 (1972) 166-168, 168-170)。時計に影響を与える効果として、(1)静止系に対する運動系での時間の遅れ(地表の時計に比べて東回りで遅れ西回りで進む)、(2)重力の作用による時間の遅れ(重力の強い地表の方が遅れる)の2つを考慮し、速度や高度の変化の影響を取り入れて理論的な予測値を計算すると、東回りで 40±23ナノ秒の遅れ(ナノ=10億分の1)、西回りで 275±21ナノ秒の進みとなりました。一方、4個の原子時計における時間変化の平均値は、東回りで 59±10ナノ秒の遅れ、西回りで 273±7ナノ秒の進みとなり、相対論の予測と巨視的な時計を使った実験結果が見事に一致した例として知られています。ところが、2000年になって、ヘイフリーとキーティングのデータには問題があるという論文が発表され、一部で注目を浴びました(A. G. Kelly, "Hafele & Keating Tests; Did They Prove Anything? ")。それによると、携帯用セシウム原子時計の進み方は不安定で、もともと1時間当たり数ナノ秒程度(最大で8.89ナノ秒)の狂いがあるが、ヘイフリーとキーティングは、その狂いを補正する際に理論的な予測値に近づけるようなデータ操作を行っているということです。