
記憶については、まだ良くわかっていないことが多々あります。しかし、大枠としては、ニューロン(神経細胞)が作るネットワークの中にコード化されているという考え方が受け容れられています。
印象的な体験の場合、そのときの視覚的・聴覚的体験を丸ごと記憶として貯えているように思えることがありますが、これは誤解です(そもそも、人間の脳には、それほどの記憶容量はありません)。いかなる体験も、まず1次投射野で感覚入力からさまざまな抽象的特徴が抽出され、それぞれの特徴に反応するニューロンを介して、複雑なパターンを持った神経興奮の集合として連合野に伝達されます。連合野では、こうしたパターンの組み合わせを通じて新たな興奮パターンが形成され、最終的には、記憶部位(海馬など)へ送られた後に記憶として定着します。
ここで重要なのは、記憶が抽象的な特徴の組み合わせから成り立っているということです。もし記憶がビデオテープのように出来事を丸ごと記録するものならば、それを収めるために莫大な容量が必要となりますし、ニューロンのネットワーク内にどのように記銘するのか理解不能です。しかし、抽象的な特徴の組み合わせだとすると、次のような形でネットワークへのコード化が可能になります。
まず、それぞれの特徴は、特定の興奮パターンが形成されやすい部分回路にコードされていると仮定します。ネットワークの節点に当たる部分(2つのニューロンの接触点)はシナプスと呼ばれていますが、「興奮パターンが形成されやすい」とは、興奮性シナプスのシグナル伝達効率が強化されていることで、こうしたシナプスの強化は、一般に、同じ入力が繰り返されることによって生じます。特徴をコードする部分回路では、該当する特徴を伝えるニューロンからの入力によって持続的に興奮するだけでなく、記憶内容の想起となる外部出力をもたらすと考えられます。新しい出来事を体験すると、そこに含まれる特徴に該当する部分回路内部の伝達効率が(入力の繰り返しによって)いっそう強化されることに加えて、特徴の新しい組み合わせ方もシナプスの強化を通じてコードされるでしょう。このような「さまざまな特徴の組み合わせ方の総体」をコードした神経ネットワークが記憶なのです。
上の仮説を人間の脳で確かめることは困難ですが、マウスを使った実験なら、遺伝操作技術で記憶力増強マウスを作り出したチェンによる面白い報告があります(J.Z.チェン「わかり始めた記憶の暗号」(日経サイエンス 2007年10月号 p.38))。まず、マウスに対して、垂直落下、大地震など必ずや記憶されるだろうシビアな出来事を、数時間以上の休憩を挟んで、都合7回体験させます。実験中および休憩時間中、海馬のCA1領域における260のニューロンの活動を記録し、パターン分析を行ったところ、それぞれの体験に特徴的な興奮パターンが浮かび上がってきました。特に重要なのは、抽象性の度合いの異なる特徴をコードしていると思われるニューロン群が発見されたことです。例えば、あるニューロン群は、すべてのびっくり体験に対して興奮しており、「びっくりする出来事」という特徴をコードしていると考えられました。さらに、垂直落下と大地震にだけ興奮する「動きの乱れ」をコードするニューロン群、大地震にだけ興奮する「揺れ」をコードするニューロン群、そして、2つの箱を使って大地震の体験をさせたとき一方の箱だけに興奮する「黒い箱の中での揺れ」をコードするニューロン群が見いだされました。このように、体験からさまざまな特徴を抽出して別々にニューロンのネットワークに記銘するという仕組みは、人間にも共通するものだと思われます。
【Q&A目次に戻る】

10の∞乗は自然数と同じ無限大(可算無限)ではありません。このことは、1891年にカントールが対角線論法と呼ばれる方法で証明しています。ここでは、そのあらましを簡単に述べておきます。
仮に、0.abc…という数が自然数と1対1対応できるとするならば、0以上1未満の実数全てに自然数の番号を振って数列を作ることができるはずです。この数列をα
1,α
2,α
3,…と表します。この数列の小数点以下の数字にも、添字を付けて表してみます。
| α1= | 0. | a1 | b1 | c1 | … |
| α2= | 0. | a2 | b2 | c2 | … |
| α3= | 0. | a3 | b3 | c3 | … |
| … | | | | | |
ここで、小数第1位がa
1とは異なる数(例えば、a
1が1ならば2、a
1が1以外なら1とする)であり、さらに、小数第2位がb
2と、小数第3位がc
3と異なるというように、小数第n位の数がα
nの小数第n位と異なっているような数βを考えます。βは、α
1,α
2,α
3,…とは必ずどこかで異なっているわけですから、αの数列には含まれていません。したがって、「0.abc…という形の数に自然数で番号を振ることができる」という前提が誤っていたことになり、実数は可算無限ではない(実数集合の濃度は自然数集合より大きい)と結論されます。
この証明はどこか変だ、騙されたみたいだ−−と感じる人は少なくないでしょう。それは、おそらく、無限というものの考え方の違いによるものです。一般の人は、無限とは「どこまでも行ってもその先がある」という“途切れない可能性”のイメージで捉えていると思います。そうした考え方からすると、対角線論法は確かに奇妙です。0.abc…という形の数に自然数で番号を振っていった場合、対角線論法に従えば、N番目までのどの数とも異なる小数を作ることはできます。しかし、N+1番目としてその小数を指定してしまえば、対角線論法は論破できそうにも見えます。ちょうどジャンケンのようなもので、先に数列を指定してしまった方が、相手の後出しによって必ず負けになるのです。
実は、集合論で無限を扱うときには、こうした“可能性としての無限”を考えているわけではありません。「自然数で番号を振る」とは、1から順番にどこまでも振っていくというのではなく、自然数から(0,1)区間の実数への写像を考えるという形で、無限個の数の対応をまとめて付けてしまうのです。このとき、無限は、可能性ではなく1つの数学的な実体として考えられています。対角線論法とは、「自然数から実数への写像が存在したと仮定すると矛盾が生じる」という背理法であり、無限集合から無限集合への写像を数学的実体として扱えることが前提となっています。この前提を否定して、「無限とは可能性のことだ」と主張するならば、確かに対角線論法は通用しませんが、それ以前に、集合論そのものの基礎が破綻してしまいます。
【Q&A目次に戻る】

質問にある研究は、イェール大学のミーゼンボックらが行ったもので、Cell誌上に発表されました("Remote control of behavior through genetically targeted photostimulation of neurons," Cell 121 (2005) 141-)。それによると、次のようにしてショウジョウバエの行動をコントロールしたそうです。
神経細胞に活動電位を生み出すイオンチャネルの中には、ある作用物質が結合したときにだけ活性化するものがあります。そこで、この作用物質に光分離できるような形で阻害剤をくっつけておき、これを神経細胞の周囲に用意しておけば、光を照射することによって解き放たれた作用物質がイオンチャネルに結合し、神経を興奮させられるはずです。ミーゼンボックらは、まず、ATPによって活性化されるイオンチャネルP2X
2を培養神経細胞に移入し、光刺激によって放出されたATPが神経興奮を引き起こすことを確認しました。
次に彼らが行ったのは、生きたショウジョウバエを使った実験です。ここで利用されたのが、遺伝子操作によってP2X
2がGF(giant fiber)と呼ばれる神経細胞に発現しているショウジョウバエです。GFとは、昆虫の中枢神経系に存在する単純な制御システムで、これが興奮するとジャンプなど定型的な逃避行動が引き起こされます。この遺伝子操作ショウジョウバエの中枢神経系に光分離可能な阻害剤をくっつけたATPを注入し、直径8mm・高さ2mmの円筒状の容器に閉じ込めた上で、波長355nmのレーザー光を150〜250ミリ秒間照射したところ、GFの興奮に誘起されたと推測される行動−−足の伸張、ジャンピング、細かな羽ばたきなど−−が観察されたそうです。容器が小さいため、実際に飛び立つことはありませんでした。2.5秒間隔でレーザー光を照射したところ、同じ反応が繰り返され、慣れは生じなかったということです。逃避行動の発現率は、2回の実験で63%と82%でしたが、これは、生理的な刺激を加えたときの逃避行動の発現率(34〜37%)よりは高く、GFを電気的に直接刺激したときよりは低い値です。
ミーゼンボックらは、このほかにも、ショウジョウバエのドーパミン作動性ニューロンにP2X
2を発現させ、光刺激でこれらを興奮させる実験を行っています。この成果は、ドーパミンの減少によって生じるパーキンソン病の治療に役立てられる可能性があります。
ところで、ショウジョウバエに対して行われた実験を、人間に応用することはできるでしょうか。上の実験内容からわかると思いますが、全く同じ方法を使うことはできません。まず、行動を制御したい相手に対して、標的となる神経細胞にイオンチャネルを発現させる遺伝子操作をあらかじめ行っておく必要がありますが、それは不可能です。さらに、光刺激を与える少し前(ショウジョウバエの場合は1時間前)に、脳にATPなどの作用物質を注入しなければなりません。また、たとえATPを脳に注入したとしても、人間にはショウジョウバエにない頭蓋骨があるので、光刺激が中枢神経系に到達しません。何よりも、ショウジョウバエのような昆虫に、特定の行動を誘発するGFのようなシステムが存在するのに対して、人間には、そうしたシステムがありません。せいぜい特定の筋肉をピクリと動かすことができる程度であり、一連の行動を引き起こすことはできないでしょう。
ただし、脳に微小電極を刺し入れて特定の神経細胞に電気刺激を与える装置が開発された場合、やり方によっては、人間の行動を制御することが可能になります。例えば、特定の行動を取ったときに電気刺激によって強い快感/不快感を与えることができるならば、この行動−刺激の操作を繰り返すことによって、自発的にその行動を促進/抑制するようになると予想されます。これは恐ろしいことですが、技術的に不可能ではないはずです。
【Q&A目次に戻る】

現在、地球温暖化が進行中であること、その主たる要因が人類の活動であることは、科学的にほぼ確認されています。政府や市民団体が推進している温暖化対策の中には効果の乏しいものもありますが、これという決め手の対策がないため、いろいろな分野で少しずつ手を打っていくしかないと考えられます。
地球温暖化への警告が発せられるようになった1980年代には、アメリカで高温が記録されたのに対してヨーロッパが寒冷化していたこともあって、温暖化そのものに疑いの目を向ける科学者も少なくありませんでした。しかし、その後に観測データが積み重ねられ、現在では、1906年〜2005年の100年間に全球での平均気温が0.74±0.18℃だけ上昇したことが確実視されています。近年には、10年あたり 0.13±0.03℃と、過去100年の2倍近いペースで温度上昇が続いています。気候モデルを用いた計算によると、その大部分は温室効果ガスの増大(および対流圏オゾンの増大)に起因するもので、一部で主張された太陽放射量増大の影響は、せいぜい1割程度しかないと考えられています。
温暖化の直接的な結果に、海水面の上昇があります。1993〜2003年に観測された海面上昇は 3.1±0.7mm/year ですが、このうち、1.6±0.5mm/year は温暖化による水の熱膨張の結果だとされます。ただし、熱膨張以外に関しては、不明な点が多くあります。1992年以降、南極で大規模な棚氷の崩壊が続いていますが、南極での氷の融解が海面上昇に大きく寄与しているとは考えられていません(推測では 0.21±0.35mm/year の寄与)。そもそも、南極の棚氷やアルプスなどの山岳氷河は、1万年前に氷河期が終了してからずっと溶け続けており、近年の地球温暖化によってどれだけ融解が加速されているかはわかっていません(海に浮かんでいる氷山が溶けても海面は上昇しないことは、
別の回答で説明しています)。
温暖化による気候変動は、全体的な傾向として現れつつあります。例えば、陸地の大部分で、最近100年間に降雨の傾向が大きく変化しています。南北アメリカの東部・ヨーロッパ北部・アジア北部と中部では降水量が増加し、サハラ砂漠南縁部・地中海地域・アフリカ南部や南アジアの一部は乾燥化しています。温暖化は、大気中の水蒸気量を増加させるため、もともと雨の多い地域ではさらに降雨量が増えると予想されていますが、観測されている降雨傾向の変化は、この予想と合致しています。また、温暖化によって土壌水分の蒸発が促進されますが、その予想通り、1970年代以降、熱帯・亜熱帯での干魃に拍車が掛かっています。
温暖化によって熱帯低気圧が強大化するという予測がありますが、現時点でその傾向が見られるかどうかははっきりしません。2005年にアメリカ史上最大級のハリケーンであるカテリーナが上陸したことから、ハリケーン強大化という主張が現実味を帯びてきましたが、データにばらつきが大きく、決定的なことはまだ言えません。ちなみに、人類史上最悪の被害をもたらしたのは、1970年にバングラデシュを襲ったサイクロンであり、温暖化とは無関係のようです。
まだ不明な点も多々ありますが、将来的に多大な影響を人類に与える地球温暖化が進行中であることは、まず間違いありません。それでは、こうした温暖化を防ぐには、何をすれば良いのでしょうか。こんにち、温暖化対策と言われるものの中に、あまり効果がないものが混じっていることは確かです。
植林をすれば木が育っている間に二酸化炭素を吸収しますが、老木になると光合成の能力が低下し、枯死すると(泥炭などを作らない限り)バクテリアに分解されて再び二酸化炭素を放出します。地球温暖化対策になるのは、老木を伐採した後に植林を行い、活発に光合成を行う若木を育てるという持続的な林業を興した場合であり、漫然と植林すれば良いというものではありません。
一般的に言って、循環型社会を実現すれば、二酸化炭素などの温室効果ガスの放出量は低減できるはずです。ただし、最も効果的なのは消費量の削減、次いで製品の再使用であり、素材リサイクルは必ずしも効果的ではありません。特に、プラスチックのリサイクルに関しては、よほど組織的に行わなければ、環境対策としてのメリットはあまりないでしょう(この点については、
別の回答で論じています)。
バイオエタノールを混入したバイオガソリンは、石油価格の高騰に対応するための商品で、サトウキビやトウモロコシのデンプンを利用している現状では、温暖化対策にはなりません。農業廃棄物となるセルロースからエタノールを生成する技術が実用化されて、初めて効果的な対策になります。
このように効果の乏しいものもありますが、全ての対策が無意味という訳ではありません。冷房の設定温度を28℃にするとか、30秒以上停車する場合はエンジンを停止するといった小さなことでも、全国民が進んで実行すれば、多少なりとも効果があるはずなので、手近なところから対策を始めれば良いと思います。
【Q&A目次に戻る】

物理学的には、過去に戻るタイムマシンの存在を禁止する法則はありません。一般相対論によれば、この世界とは、過去から未来まで拡がった時空多様体であり、その中に、未来から過去に戻るような部分的構造があってもおかしくないからです。問題は、そうした構造が現実に存在しているか、さらに、人間などの知的生命体がその構造を利用できるか−−という点です。
ソーンは、ワームホールを利用して「過去に戻る」タイムマシンを製造する方法を提案しています。しかし、ここで「過去に戻る」とは、ワームホールの両端に時間差を作り出して、未来側の端から入って過去側の端から出てくるということです。従って、戻ることができるのは、せいぜいワームホールが制御できるようになってから後の時間帯でしかありません。ソーンのワームホール・タイムマシンを使ったのでは、タイターのような未来人が、いまだワームホールを見つけてもいない現代にやってくることはできないのです。そもそも、ワームホールは負のエネルギーが存在しない限り一瞬のうちに潰れてしまうことが知られていますが、そうしたものが存在するかどうかは不明ですし(おそらく存在しない)、存在したとしても人類に制御できるとは思えません。
それでは、自然界にもともと存在しているワームホールか何かを利用して、過去に戻ることはできるでしょうか。質問にエルゴ領域という言葉が現れますが、これは、回転するブラックホール(カー・ブラックホール)の事象の地平面の外側に存在する領域のことです。この領域に放り込んだ物体をうまく分裂させて、片方を遠方に打ち出すことにより、ブラックホールの回転エネルギーを外部に取り出せると考えられています。ブラックホールをエネルギー源して利用できることから、ハードSFにはエルゴ領域の話題がしばしば登場しますが、あくまで地平面の外側の領域であり、そこにワームホールのような時空構造が形成されることはないので、タイムマシンとして利用することはできません。
原理的に禁止されていないとは言え、過去への回帰を可能にするような巨視的な時空構造は、近在の宇宙には存在しないと予想されます(素粒子レベルの微視的な構造なら、量子ゆらぎの効果として無数に存在するはずです)。もし、そうした構造が無視できない確率で形成されるならば、中間サイズのものを含めると至る所に過去へ抜け道が開いていることになり、未来は過去によって決定され、過去は未来に影響されないという因果法則が成り立たなくなってしまいます。時間が過去から未来へ整然と流れるようには感じられなくなり、因果的な歴史の存在に裏打ちされた文化も支持基盤を失います。逆に言えば、人類が歴史的な文化を維持できているという事実が、少なくともわれわれのの周辺に過去に回帰する時空構造が存在しないことを示唆しているのです。
ちなみに、タイターによれば、北京オリンピックは開催されなかったそうです。この点については、来年、確認が取れるはずです。
【Q&A目次に戻る】

この質問に対してピッタリの回答を与えてくれるのが、エドワード・ハリソン著『夜空はなぜ暗い?
オルバースのパラドックスと宇宙論の変遷』(地人書館 )という本です。ただ、歴史的な宇宙観の変化も含む多岐にわたる内容なので、ここでは、議論のポイントだけを簡単に紹介したいと思います。
現在の宇宙空間に存在する光のほぼ全ては、恒星から放出されたものです。光源となる恒星がなければ、この世界は漆黒の闇の中に沈むはずです。地球上の人間が受け取る光は、ほとんどが太陽からなので、太陽が地球の裏側に隠れてしまうと、大気による散乱光や月からの反射光以外の自然光は、もはや微弱な星の光しかありません。これだけでは夜空を明るくできないことは、次のように考えればわかります。
夜空に見える星の大部分は、銀河系に属する天体です。銀河系には、2000〜4000億個という膨大な数の恒星がありますが、差し渡し10万光年の円盤状の領域内部に広く分布しているので、平均すると、1辺が数光年の立方体内部に恒星1個の割合でしか存在しません(太陽に最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリまでの距離は4.2光年です)。恒星からの光はあらゆる方向に放出されるので、その強さは、恒星までの距離の2乗に反比例して弱くなります。地球と太陽の距離は約6万分の1光年なので、地球から1光年彼方にある太陽と同じ明るさ(絶対等級)の恒星は、見かけの明るさが太陽の36億分の1、100光年彼方では36兆分の1となります。したがって、銀河系にある数千億個の恒星をもってしても、太陽よりはるかに弱い光にしかなりません。
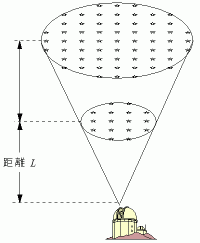
それでは、われわれの住む銀河系(天の川銀河)以外の銀河の光まで考えると、どうなるでしょうか。他の銀河までの距離は、天の川銀河の大きさよりもさらに巨大(アンドロメダ銀河までの距離は230万光年)なので、その光は問題にならないほど弱いと思えるかもしれません。しかし、無限大の宇宙空間に無限個の銀河があるとなると、話は別です。仮に、同じような銀河が空間内部に均一に分布しているとして、夜空の特定の方位を見た場合を考えましょう。地球から距離L(多少の幅を持たせます)に存在する銀河の個数がn個だとすると、距離2Lにある銀河は4n個になります(右図)。距離が2倍になったので、それぞれの銀河からやってくる光は、距離Lの地点にある銀河の4分の1に弱まっていますが、銀河の総数が4倍なので、距離2Lにある銀河からの光の総量は、距離Lからの銀河の光の総量と等しくなります。この性質は、距離が3倍、4倍…となっても同じなので、無限の彼方からの光まで積算されると、夜空の明るさは無限大になってしまうはずです(途中に光を吸収する星間物質がある場合は、議論を少し変更する必要がありますが、充分に長い時間が経つと、光を吸収した星間物質が熱くなって輝き始めるので、同じ結論に達します)。
このパラドクスを回避するためには、宇宙の歴史を考える必要があります。光は有限の速度で伝わるので、1億光年彼方にある銀河から放出された光が地球に達するまでには約1億年かかります(「約」を付けたのは、距離が大きくなると相対論的な効果が無視できなくなるからです)。現在の知見によれば、宇宙は137億年前にビッグバンと呼ばれる大爆発とともに生まれたと考えられています。したがって、137億年より前に放出された光は存在しないので、たとえ宇宙空間が無限大だとしても(無限大かどうかはわかっていません)、無限の彼方からの光まで積算されて夜空が輝くということはないのです。
ただし、1つ注意しなければならないことがあります。137億年前のビッグバンの際には、ちょうど溶鉱炉の鉄が白熱して輝くように、宇宙全体が高温になって輝いていたはずです。そのときの光が137億年後のこんにちも残っているならば、夜空を明るく輝かせるのではないかという疑問です。これに答えるには、「宇宙の膨張」に関する知識が必要です。宇宙が誕生した当初は、宇宙空間そのものが狭く、物質が高密度に詰まった高温状態になっていましたが、宇宙空間が急激に膨張し“スペース”が拡がっていくと、物質密度がどんどんと希薄になり、温度も下がっていきました。ビッグバンから30〜40万年経って温度が3000度ほどになった頃、光が物質の束縛を逃れて宇宙空間に解き放たれます。この光は今なお宇宙空間を飛び回っていますが、空間が当時からさらに1000倍にも膨れ上がったため、光の波長もそれにあわせて引き延ばされていきました。温度が3000度の原初の光は、波長1ミクロンの近赤外のところに強度の最大値を持つ赤っぽい光ですが、空間膨張とともに波長が1000倍になったので、強度の最大値も1ミリの遠赤外になり、目に見えない暗い光へと変化したのです(目に見える可視光線の波長は、0.4〜0.8ミクロンです)。この結果、ビッグバン当時の輝きは失せて、宇宙空間は、わずかな恒星による光を除いて、闇の中に閉ざされることになりました。
【Q&A目次に戻る】

ガリレオ以前と以降では、学問に求められるものが異なっていたと考えられます。それ以前には、自然を解明する学問は、「なぜ」という問いに答えることを主たる目標としていましたが、ガリレオの登場によって、「いかに」の追求へ方針が転換されたと言えるでしょう。
アリストテレスが求めたのは、「なぜ、重い物体は落下するのか」という問いに対する解答です。彼は、四元素説の信奉者であり、月の天球より下にある全ての存在は、土・火・水・空気の四元素が混じり合って作られると考えていました。さらに、彼の宇宙観によれば、宇宙の中心には土が球状に凝集して大地を構成しており、その周囲に、天体を載せて円運動する天球が存在するとされていました。こうした思想に基づいて、宇宙の中心は土が、天球の最外殻である恒星天は火が本来あるべき場所であり、土と火のエレメントは、自分のあるべき場所に向かって自然に動かされると主張したのです。一般の物体は、“重さ”をもたらす土のエレメントと“軽さ”をもたらす火のエレメントがどのように配合されるかに応じて、上下方向の運動の仕方が決まると見なされました。
アリストテレスは、「なぜ」という疑問に答えるのには熱心でしたが、「いかに」という問題意識は希薄だったようです。上のような議論は、「天体論」(『アリストテレス全集 第4巻」(岩波書店)に収録)に詳しく記されていますが、それでは運動速度が具体的にどのようになるかについては、ほとんど語られていません。
そもそも、「重さ」についての理解も、現代のものとかなり異なっています。例えば、「銅は羊毛より重い」という表現があるかと思えば、「銅の中では量の多い銅が重い」とも記されており、比重と重量の区別が厳密になされていません(「重さ」が比重の意味であるならば、空気抵抗があるので“重い”物体の方が早く落ちます)。物理的な量を明確に定義するという科学的な発想に欠けていたと言えるでしょう。ちなみに、アリストテレスのほぼ100年後に活躍したアルキメデスは、比重について正しく理解しています。
「重さ」と「落下速度」の関係となると、もっと曖昧になります。「量が多くなればなるほど…それだけ速く動く」という記述もありますが、これは、必ずしも「重量が大きいと落下速度が速くなる」という意味ではなく、「火のエレメントの量が多いと速く上昇する」ことも含意しています。さらに、「鉄板は水に(しばらく)浮くが、針は(速やかに)沈む」と記されており、物体の形が落下速度に影響を与えるという認識もありました。アリストテレスの誤りを明らかにする論法としてしばしば挙げられるのが、「1kgの銅球2個を糸で連結した物体は、2kgなのに1kgの銅球と同じ速さで落下するはずだ」というものです。しかし、形が落下速度を大幅に変えるとなると、「連結物体は球とは形が違うので落下速度が速くならなかった」と反論することも可能です。同じ大きさで2kgの球があれば速く落下すると考えられるからです。ただし、アリストテレスは、形がどう変化するとどれだけ落下速度が変わるかについて、全く触れていません。
アリストテレスの議論は、「なぜ」物体は落下するかを説明するものであっても、「いかに」落下するかを明らかにすることはできません。古代ギリシャから中世ヨーロッパに至るまで、いわゆる自然哲学は貴族の嗜みという性質が強かったため、それで事足りたのでしょう。しかし、土木技術が進歩して建築資材を持ち上げたり放り投げたりする機会が増えてくると、機材の強度などを決定する上で、物体の運動に関する定量的な議論が必要となってきます。ガリレオが「いかに」を追求する定量的な実験科学に着手した背景には、そうした社会的な状況があったのかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

光速に近い運動体が進行方向に潰れるという現象は、主に、静止系と運動系で同時性の定義が異なっているために生じます(それ以外のファクターもありますが、ここでは省略します)。
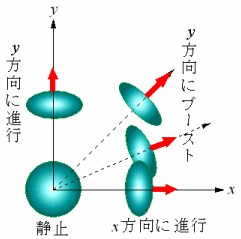
乗っている人から見ると、xy面で円盤型である宇宙船を考えます。この宇宙船の形は、宇宙船に対して静止している座標系で測定されたものです。ところが、宇宙船が動いている外部座標系では、時間の基準が船内座標系と異なっています。外部座標系では、宇宙船の各部分の位置を全て同じ時刻で測定してはずなのに、船内座標系からすると、宇宙船の後端の位置を測定する時刻は先端のときよりも遅いように見えます。つまり、船内にいる人からすると、外部座標系での測定は、後端が先端方向に少し進んだときに位置を測定したことになっています。外部の座標系で、運動する宇宙船が進行方向に潰れた形だと判定されるのは、そのせいです。決して宇宙船が押し潰されたわけではありません。
運動物体が潰れた形になるのが測定(より正確に言えば位置決定)時刻の違いによるのですから、形が潰れるのは必ず物体の進行方向になります。したがって、x方向に進んでいた円盤をy方向に(小さな加速度で)ブーストすると、楕円の短軸が進行方向に向くように回転していくはずです(このことは、実際にローレンツ変換の式を使って計算して確かめられます)。
なお、実際に円盤形の宇宙船を亜光速で飛ばしたとしても、必ずしも楕円形に潰れた形では見えません。楕円形になるのは、先端と後端の位置を同じ時刻で決めた場合ですが、同じ時刻に宇宙船表面から反射された光が一斉に目に到達するわけではないからです。
【Q&A目次に戻る】

恐竜絶滅の重力増加説なるもの、この質問で初めて知ってネット検索したところ、いくつかのページがヒットしましたが、運悪くコーヒーを飲みながら読んだために、噴いてしまいました。物的証拠に基づかず推測で作り上げた仮説なので、あまり真剣に検討する必要はないと思います。
この説の出発点になるのは、「恐竜がなぜあんなにも巨大になれたのか」という疑問です。これに対する解答として、まず「恐竜が巨大化した時期には現在よりも重力が弱かった」というアイデアが出され、さらに、「白亜期末に突然重力が増加し、自分の体重を支えきれなくなった恐竜が絶滅した」と話が発展したようです。しかし、地質学的な記録にも残らない形で重力が増加することがあるでしょうか。
重力増加説の信奉者が挙げているのが、地球の自転が急に遅くなり、遠心力が弱まったというものです。現在の遠心力は、赤道でも重力の0.3%にすぎませんが、地球の自転速度が今の10倍もあれば、(自転速度の2乗で増える)遠心力は重力の1/3ほどにもなり、生物の進化にも大きな影響を及ぼしたかもしれません。ところが、地球の自転速度はいろいろな方法で推測されており、約9億年前のカンブリア紀でも、現在より25%程度速かったにすぎないと考えられています。恐竜が生息していたジュラ紀〜白亜紀に、地球の自転速度が現在の何倍も速かったという主張は、地質学的なデータと矛盾します。また、地球が月を補足したために自転が遅くなったという説もありますが、そうした大変動が起きたにもかかわらず、月が現在のように円に近い公転軌道を描いている理由が説明できません。
そもそも、恐竜は、生物学的に理解できないほど巨大だと言えるでしょうか。現在、地上に生息する最も体重の重い動物はアフリカゾウであり、体高3メートル、体重5〜6トンほどです。ジュラ紀に生息していたブラキオサウルスは、肩までの高さがアフリカゾウの3倍弱ありますが、筋肉や骨の断面積が(面積は長さの2乗の単位を持つことより)この値の2乗で増加していたとすると、アフリカゾウの8倍程度の体重を支えられたと推定できます。かつては、ブラキオサウルスの体重は80トン以上と推測されていましたが、その後、恐竜には鳥類と同じように中空骨や気嚢など体を軽くする仕組みが存在すると判明し、現在では、せいぜい40〜50トン程度だと言われています。とすると、ちょうどアフリカゾウの8倍の体重であり、無理のない重さです。
恐竜(および魚竜や翼竜)の特徴は、地球上の多様な環境に見事に適応していたという点です。化石が少なかったので長らく見過ごされてきましたが、体重数百kg以下の小型恐竜も数多くいたことがわかっています。白亜期末には、こうした恐竜の仲間(鳥類に進化する分岐を除く)とアンモナイトが絶滅し、プランクトンや陸生植物が激減したのですから、体重が重すぎて死に絶えたという素朴な説では、この大絶滅の過程をとても説明できないでしょう。
【Q&A目次に戻る】

相対論について考えるときには、「ゆがんだり切れたりしない剛体」を想定すると話がおかしくなります。たとえナノチューブ製の(おそらく物質としては最強の)ワイヤーであっても、無理に引き上げようとすると必ずどこかで破断してしまい、シュヴァルツシルト半径の内側から何かを取り出すことはできません。
物体を1つにまとめているのは、電気的な力です。例えば、金属は、規則正しく並んでいる陽イオンと、その間を動き回る自由電子との間に作用する電気的な引力によって、1つの固体として存在しています。こうした物質内部の力を担っているのが電磁場であり、その変化はたかだか光速でしか伝わりません。ところが、シュヴァルツシルト半径の内側では、強い重力によって空間が大きくゆがみ、光ですらブラックホールの中心に近づく方向にしか進むことができなくなります。このため、シュヴァルツシルト半径を持つ球面(これを事象の地平面と言います)を横切るようにワイヤーを吊り下げた場合、面内の部分にどのような重力加速度が働いているかを外に伝えることができず、内側の部分を支えるのに必要な応力を発生させられません。このため、どうやっても面の内側からワイヤーを引き上げることは不可能です。
潮汐力を無視するという仮定も妥当ではありません。シュヴァルツシルト半径の外側を周回する宇宙船からワイヤーを吊り下げるとすると、宇宙船内部では遠心力と重力が釣り合って無重量になっていますが、ブラックホールにほんのわずか近づくだけで急激に重力が大きくなります。この重力の変化が潮汐力であり、これによってワイヤーが破断したり、宇宙船もろともブラックホールに飲み込まれたりするのです。ワイヤー全体を自由落下させた場合は、破断することなく事象の地平面を通り抜けられますが、ブラックホールの中心部に近づくにつれて潮汐力が無限に大きくなるので、落下する途中でワイヤーはバラバラになってしまいます。
【Q&A目次に戻る】

ブラックホールの融合は、銀河レベルの現象としてはきわめて激越で、銀河形成にも大きな影響を及ぼしますが、宇宙論のレベルで見ると、それほど凄まじいものではありません。
ブラックホールのエネルギー源は、その質量です。多くの銀河の中心部には、質量が太陽の百万倍から1億倍以上にもなる超巨大ブラックホールが存在し、周囲の物質を吸い込む過程で強力な電磁波やプラズマ流を放出していると考えられています。しかし、こうした超巨大ブラックホールでも、その質量は銀河全体の1%にもならず、宇宙の膨張に重要な役割を果たすほどではありません。宇宙論的なスケールで見ると、ブラックホールといえども「ちょっと大きめの天体」でしかないのです。
ブラックホールの融合が大きな意味を持つのは、銀河形成においてです。こんにち観測される無数の円盤形の銀河は、宇宙初期に存在していた球状星団クラスの小銀河が合体して巨大化したと考えられています。そうした小銀河の合体の過程で、内部にあるブラックホールも次々と融合し巨大になっていきますが、この融合過程がバルジ(銀河中央の膨らんだ部分)の形成などに寄与したという説が提出されています。
2005年に観測されたガンマ線バースト GRB 050509B は、27億光年離れた銀河の近くからやってきたもので、持続時間が50m秒ときわめて短いことから、ブラックホール同士の合体の際に生じた可能性が指摘されています(中性子星同士、または、中性子星とブラックホールの合体である可能性も大)。また、2003年には、2億6000万光年彼方にある銀河の中心部から噴出するジェットを観測することにより、2個の超巨大ブラックホールが1.05年の周期で直径0.3光年の楕円軌道を描いて運動していると判明しましたが、このブラックホールは、数万年後には融合を始めると予想されています。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
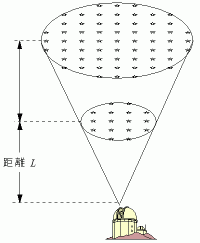 それでは、われわれの住む銀河系(天の川銀河)以外の銀河の光まで考えると、どうなるでしょうか。他の銀河までの距離は、天の川銀河の大きさよりもさらに巨大(アンドロメダ銀河までの距離は230万光年)なので、その光は問題にならないほど弱いと思えるかもしれません。しかし、無限大の宇宙空間に無限個の銀河があるとなると、話は別です。仮に、同じような銀河が空間内部に均一に分布しているとして、夜空の特定の方位を見た場合を考えましょう。地球から距離L(多少の幅を持たせます)に存在する銀河の個数がn個だとすると、距離2Lにある銀河は4n個になります(右図)。距離が2倍になったので、それぞれの銀河からやってくる光は、距離Lの地点にある銀河の4分の1に弱まっていますが、銀河の総数が4倍なので、距離2Lにある銀河からの光の総量は、距離Lからの銀河の光の総量と等しくなります。この性質は、距離が3倍、4倍…となっても同じなので、無限の彼方からの光まで積算されると、夜空の明るさは無限大になってしまうはずです(途中に光を吸収する星間物質がある場合は、議論を少し変更する必要がありますが、充分に長い時間が経つと、光を吸収した星間物質が熱くなって輝き始めるので、同じ結論に達します)。
それでは、われわれの住む銀河系(天の川銀河)以外の銀河の光まで考えると、どうなるでしょうか。他の銀河までの距離は、天の川銀河の大きさよりもさらに巨大(アンドロメダ銀河までの距離は230万光年)なので、その光は問題にならないほど弱いと思えるかもしれません。しかし、無限大の宇宙空間に無限個の銀河があるとなると、話は別です。仮に、同じような銀河が空間内部に均一に分布しているとして、夜空の特定の方位を見た場合を考えましょう。地球から距離L(多少の幅を持たせます)に存在する銀河の個数がn個だとすると、距離2Lにある銀河は4n個になります(右図)。距離が2倍になったので、それぞれの銀河からやってくる光は、距離Lの地点にある銀河の4分の1に弱まっていますが、銀河の総数が4倍なので、距離2Lにある銀河からの光の総量は、距離Lからの銀河の光の総量と等しくなります。この性質は、距離が3倍、4倍…となっても同じなので、無限の彼方からの光まで積算されると、夜空の明るさは無限大になってしまうはずです(途中に光を吸収する星間物質がある場合は、議論を少し変更する必要がありますが、充分に長い時間が経つと、光を吸収した星間物質が熱くなって輝き始めるので、同じ結論に達します)。
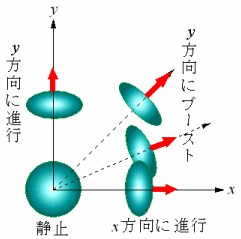 乗っている人から見ると、xy面で円盤型である宇宙船を考えます。この宇宙船の形は、宇宙船に対して静止している座標系で測定されたものです。ところが、宇宙船が動いている外部座標系では、時間の基準が船内座標系と異なっています。外部座標系では、宇宙船の各部分の位置を全て同じ時刻で測定してはずなのに、船内座標系からすると、宇宙船の後端の位置を測定する時刻は先端のときよりも遅いように見えます。つまり、船内にいる人からすると、外部座標系での測定は、後端が先端方向に少し進んだときに位置を測定したことになっています。外部の座標系で、運動する宇宙船が進行方向に潰れた形だと判定されるのは、そのせいです。決して宇宙船が押し潰されたわけではありません。
乗っている人から見ると、xy面で円盤型である宇宙船を考えます。この宇宙船の形は、宇宙船に対して静止している座標系で測定されたものです。ところが、宇宙船が動いている外部座標系では、時間の基準が船内座標系と異なっています。外部座標系では、宇宙船の各部分の位置を全て同じ時刻で測定してはずなのに、船内座標系からすると、宇宙船の後端の位置を測定する時刻は先端のときよりも遅いように見えます。つまり、船内にいる人からすると、外部座標系での測定は、後端が先端方向に少し進んだときに位置を測定したことになっています。外部の座標系で、運動する宇宙船が進行方向に潰れた形だと判定されるのは、そのせいです。決して宇宙船が押し潰されたわけではありません。