
オートポイエーシス(autopoiesis; 自己創出)の理論は、ベルタランフィに始まる一般システム論──心理や社会を含むさまざまな対象系を抽象的なシステムに関する一般概念で記述しようとする理論──の流れの中に位置づけられているようです。ただし、私には、どうにも受け入れられない代物です。
生命システムの特徴を抽出した「オートポイエティック・マシン」という概念は、神経システムの研究に基づいてマトゥラーナとヴァレラが提唱したもので、「自己を産出するプロセスのネットワークを絶えず再生産し実現する」ように有機的に構成されたハードウェアだと説明されています
(H.R.マトゥラーナ/F.J.ヴァレラ『オートポイエーシス 〜生命システムとは何か〜』(国文社))。良くわからない議論ではあるものの、例えば、細胞という1つのシステムを考えた場合、自己を構成する代謝産物の生成を含む細胞の全機能は、代謝産物の濃度に依存するような細胞内信号伝達のネットワークによって制御されているので、細胞がオートポイエーシス・システムだという主張は、何となく意味が通じるような気がします。しかし、著者らがこの概念を一般化し、社会制度に関する議論にも適用し始めると、もう付いていくことができません
(オートポイエーシス概念の一般化に関しては、マトゥラーナとヴァレラの間で見解の相違があったそうです)。細胞における自己制御の特性は、膜タンパク質の3次構造が代謝産物との結合によって非連続的に変化するといったハードウェア固有の性質に大きく依存しており、社会や心理にまで一般化することは、粗雑なアナロジーにしか見えないからです。
現在、実用的な学問の各分野で、研究内容が個人の思考能力のポテンシャルを上回っており、ある学説を検証するために、多数の学者が手分けして研究することが必要になっています。特に、学界で広く受容されていない最先端学説の場合は、信奉者がまだ多くないため、その学説を正当だと思っていない人にも研究に加わってもらわなければなりません。その際に採用されるのが、仮説−演繹という方法です。すなわち、
「仮にその学説が正しいとして、そこから何が導けるか」
を考えるのです。「その学説を応用するのに必要なスキルを身に付けた人ならば、たとえ信じていなくても演繹できる」──そんな結論が導かれたとすると、その結論を具体的なデータと比較することにより、学説の当否を検証することが可能になります(例えば、ビッグバン理論が正しいと仮定すると、水素とヘリウムの存在比が原子核理論に基づく計算によって導かれるため、宇宙空間での元素の存在比を観測することで学説の検証ができます)。こうした検証作業を多数の学者が協力しながら積み重ねていくことにより、学説はより洗練され、他のジャンルに応用可能な形で体系化されていきます。逆に、それを信じる人には弁舌をさわやかにする効能があっても、それ以外の人には何も導けないような単なる説明的な学説の場合、信奉者たちの独りよがりの道具に堕すばかりでなく、信奉者間でも見解の統一が取れずに、学派が分裂して衰退していく傾向が見られます。一般化されたオートポイエーシス理論について言えば、「社会や精神はこれこれの特徴を持つからオートポイエーシス・システムだ」ではなく、「オートポイエーシス・システムだと仮定すると何が演繹されるか」を考えることが、学問的な検証作業の出発点になります。
私は精神医学の分野に詳しくないので、こうした作業が実際に行われているかどうかは知りません。質問を受け取ってから、取りあえず、斎藤環氏の『ひきこもり文化論』(紀伊国屋書店)などを読んでみましたが、「システムの構成要素間に見られる有機的な産出関係」のようなマトゥラーナ流の議論はなく、オートポイエーシス理論の応用と言うよりは、持論の説明のために用語を拝借したという程度のものでしょう(本人は、「自己流にこの理論を応用した」と記していますが…)。「ひきこもり」の原因を器質や環境に一方的に求めるのではなく、高度な自律性を備えた自己と家族/社会の相互作用という文脈で考えていく中で、たまたま「オートポイエーシス」とか「デカップリング」といったことばが使いやすかったのだと思います。一般システム論の信奉者には物足りないでしょうが、「ストレス」のような工学的な用語を使うと心理学の説明がわかりやすくなるのと同じで、罪のない越境行為ではないでしょうか。
日本におけるオートポイエーシス理論の研究では、河本英夫氏や花村誠一氏が第一人者のようですが、彼らの論文は1〜2篇斜め読みしただけでめげたので、何とも言えません。
「何とも言えません」と言いながら付け加えるのも何ですが、仮説−演繹法による学問的な検証作業を遂行できない「単なる説明的な学説」を展開している著書には、次のような特徴があるような気がします。これは、あくまで個人的見解です。
- 不必要な引用が多い。科学技術系の論文に見られる引用が、具体的なモデルやデータを参照するためのものであるのに対して、抽象的な一般論が引用される。「これはまさにラカンが主張した××である」のように。
- 体系的な記述がなく一般論が“横滑り”する。特定の事例を徹底的に解明する論述を嫌い、一般論を展開する過程で、さまざまな事例が断片的に触れられていく。免疫系の自己−非自己の話が出たかと思うと、ベルーソフ・ザボチンスキー反応が紹介され、急に社会組織論に話題が移っていったりする。
- 科学的な用語を本来とは異なる意味で用いる。科学的な理論では、ある用語は特定のモデル内でのみ有意味になることが多いが、適用範囲を逸脱して使われるケースが少なくない。カオス理論における「予測不能性」は、少数自由度の完全決定系を仮定したときだけ明確な意味を持つ。「クラインの壺」は幾何学的な概念であり、社会システムに応用しても素朴な比喩にしかならない。……
【Q&A目次に戻る】

電磁気学などで複素数を使うと計算が楽になる理由は、次のように説明できます。
実数を数直線で表し、絶対値を原点からの距離、正負の符号を原点に対する向きと考えると、「負数を乗じる」というかけ算では、数直線上の向きは、かけられる数と逆になります。容易にわかるように、2乗して負数になる実数は存在しないことになり、実数は、代数演算に関して閉じていません。この難点を逃れるために数学者が考案したのが、2乗すると -1 になる虚数単位i であり、2つの実数x,yを使って
z = x + iy
と表される複素数を定義すれば、これを使うことによって任意の代数方程式が解を持つことが示されます。しかし、なぜ2乗すると負になる数を導入しなければならないのか、また、これを使うとなぜ計算が楽になるのか、どうにもしっくりしません。
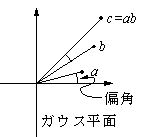
複素数の導入に当たって、こうした代数的な解釈をするよりも、はじめからガウス平面上で考えた方が、素直ではないでしょうか。実数では、「向き」という離散量と「大きさ」という連続量を変える演算としてかけ算を定義していましたが、この定義を改めて、かけ算とは、そもそも「角度」と「大きさ」という2つの連続量についての演算だと考え直すことにするのです。偏角に関しては、ガウス平面上でかける数の偏角の分だけ回転させる操作として「かけ算」を定義すれば、数直線上での向きを逆転させるといった離散的な操作は不必要になり、任意の代数方程式が解を持つことも納得できるはずです(任意の多項式 f(z) で z の偏角や絶対値を連続的に変化させると、f(z) の偏角や絶対値も連続的に変化することを考えてみてください)。実数から出発して訳の分からない虚数単位を導入するのではなく、「ガウス平面で回転させる演算としてかけ算を定義するのが複素数だ」と考えると、物理現象とのつながりが見えてきます。
複素数の特色は、周期関数が簡単に与えられる点にあります。実数では、三角関数という厄介な代物を扱わなければなりませんが、複素数の場合、絶対値が 1 で偏角が x という単純な数の実部と虚部が(x を増すとガウス平面上の円周上をぐるぐる回るように変化するので)xの周期関数になっています。この複素数をxの関数として g(x) と表すと、複素数における「かけ算」の定義より、
g(x+y) = g(x)g(y)
g(x+dx) = (1+idx)g(x) (g'(x) = ig(x))
などの簡単な関係式を満たしていることがわかります。周期関数が、このように簡単で性質の良い関数で表されることが、複素数を使うと物理現象が扱いやすくなる最大の理由です(もちろん、g(x) とは e
ix のことです)。
重要な物理現象の多くは、振動過程を含んでいます。仮に、この世界とは異なる物理法則に支配されている世界が存在したとしても、そこで振動や波動のような過程が生起せず、摂動が指数関数的に減衰する緩和過程しか見られないとすると、生命が発生することは困難でしょう。何らかの事情で生まれた変化が振動によって維持され、あるいは、波動によって伝達されるようなプロセスがあって、はじめて、生命体のような複雑な秩序が形成されるのです。当然のことながら、そうした世界での物理現象を記述する科学において、振動を数式で表すことがきわめて重要になります。振動の記述には周期関数が使われますが、複素数は、数学的に扱いやすい周期関数を提供してくれる最も単純な数の体系だと考えられます(複素数より複雑な数論も存在しますが、通常の物理現象を記述する上では不必要です)。交流や電磁波などさまざまな振動・波動を扱う電磁気学の分野では、複素数の威力は圧倒的です。
もっとも、本当のことを言うと、物理数学で複素数が役に立つ理由が、単に「周期関数を扱いやすい」という技術的な点だけなのかどうか、私自身にもわかっていません。実際、量子力学では、それを使わずに物理法則を記述することが不可能なほど、複素数は物理理論と密接な関係を持つようになります。もしかしたら、もっと深いところで複素数を必要とする本質的な理由があるのかもしれませんが、今の時点では、これ以上のことは言えません。
【Q&A目次に戻る】
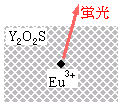
一般的な蛍光体は、母材(母体結晶)と呼ばれる結晶内部に、付活材と呼ばれる物質を注入して薄く分散させた構造になっています。例えば、ブラウン管などで用いられる赤色蛍光体 Y
2O
2S:Eu
3+ は、母材となる Y
2O
2S 結晶の所々に Eu
3+ が入り込んだものです。規則正しく配列した母材の結晶の中に付活材のイオンが入り込むと、結晶格子が歪んで電子のエネルギー状態が変化し、伝導バンドと荷電子バンドの間に新たなエネルギー準位が現れます。蛍光とは、通常、この準位から(あるいは、この準位へ)の遷移の際に放出される光子のことです。蛍光の波長λは、遷移する準位間のエネルギー差をΔEとすると、
hc/λ = ΔE
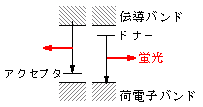
で与えられます。ここで、母材が一定の構造を持つ無限に拡がった完全結晶であり、付活材の密度も充分に低いとすると、エネルギー準位はシュレディンガー方程式によって完全に決定されるため、スペクトルの形は理論的に決まるはずです。
ただし、母材と付活材の種類が同じでも、次のような場合には、製造方法によってスペクトルが変化することがあります。
- 焼成条件などで付活材のイオンの価数が変化する場合。例えば、Euを含む結晶を作るときに、酸素を含む雰囲気で焼成すると3価のイオンが多くなって赤色の蛍光になり、酸素を含まない雰囲気や水素などの還元ガス中で焼成すると2価になり青色の蛍光になります。
- 母材が複数の結晶構造を取り得る場合、あるいは、格子欠陥や微量不純物の存在が無視できない場合は、結晶構造の違いに応じてスペクトルが変化します。こうした変化が見られるのは、母材の結晶構造に敏感な外殻電子軌道が発光に関与している場合に限られます。
- 蛍光体がナノスケールで薄膜や粉体に加工されている場合、表面効果によって発光特性が大きく変わり得ます。大きさが数ナノメートル程度のナノ粒子半導体では、バンドギャップが粒径に応じて変化するため、粒子サイズによって蛍光の波長を制御することができるそうです。また、蛍光体の結晶が超格子構造を取っている場合、母材の組成が同一であっても、焼成条件などによって超格子構造が変化し、発光スペクトルが変化することがあります。
最初の回答の誤りを指摘してくださった山嵜氏に感謝します。
【Q&A目次に戻る】

地球が自転し続けているのは、外部から力が働かない物体に関して「角運動量保存則」(回転運動に関する慣性の法則のようなもの)が成り立っているからです。ある軸の周りを半径r、角速度ωで回転している質量mの物体の角運動量は mr
2ω 、多数の物体がある場合は、その総和 Σm
ir
i2ω
i で全角運動量が与えられます。地球は、宇宙空間に浮かぶ微惑星が凝集して形成されたものですが、太陽やその他の天体からの引力が充分に小さいとすると、元になった微惑星が持つ全角運動量は一定に保たれます。このため、微惑星が近づいて上式の r
i が小さくなるにつれて角速度 ω
i が次第に大きくなり、1個の天体としてまとまったときには、相当に大きな角速度で自転するようになったのです。
もし、地球が宇宙空間に孤立しているならば、角運動量保存則が成り立つため、いつまでも一定の角速度で自転を続けることになりますが、実際には、他の天体からの相互作用があるため、自転の角速度は少しずつ遅くなっています。特に大きな影響を与えているのは、地球にとって不釣り合いに巨大な衛星である月との間の潮汐摩擦です。この点に関しては、
月と地球の距離についてや
月の公転・自転周期のシンクロについての回答でも触れましたが、この潮汐摩擦のために、月の公転周期と自転周期がシンクロして月は常に同じ面を地球に向けるようになり、さらに、月は地球から遠ざかり、地球の自転は少しずつ遅くなっています。また、太陽との潮汐摩擦も地球の自転を減速する作用があり、太陽が永遠に輝き続けるならば、いつかは、地球も公転と自転の周期がシンクロして、太陽に常に同じ面を向けるようになるはずです。ただし、太陽の寿命は有限であり、主系列星として輝いている間には、こうした事態は起こらないでしょう。現在、地球の自転は年に0.000015秒の割合で遅くなっていますが、このペースでいくと、太陽が赤色巨星となって太陽系が滅亡する50億年後には、地球の1日は40数時間になるはずです(実際には、減速のペースはダウンします)。
【Q&A目次に戻る】

気功の中でも「内気」と呼ばれる体内の気の流れは、完全に解明されていないものの、(神経興奮やホルモンの分泌などの)生理学的な基盤があると考えられています。しかし、気を外部に発する「外気」に対しては、多くの科学者は懐疑的です。「人の気配を感じる」という言い方がありますが、これは、かすかな物音や状況の変化(虫が急に鳴き止むなど)を総合的に判断したものと推測されます。気功師が患部に手をかざすと痛みが和らいだという報告は、体温の熱放射や空気の動きが引き起こした生理的反応か、安心感に由来するプラシボ効果ではないでしょうか。いずれにしても、身体から(熱以外の)何かが放射されたと考えるだけの根拠は見あたりません。
身体の内部では、神経興奮のような電気的反応がさかんに起きているので、周囲に生体電磁場が生じています。また、皮膚近くでの化学反応によって、きわめて微弱な(人間の目には全く見えない)可視光が発せられることもあります。しかし、これらは、いわゆるオーラとは無関係でしょう。オーラ写真と呼ばれることもあるキルリアン写真は、電圧を加えた状態でフィルムに生体を接触させたとき、体を通して放電した様子が現像されたもので、純粋に電気化学的な現象です。精神状態によって画像が変化しますが、これは、主に発汗の差によるものと考えられます。
【Q&A目次に戻る】

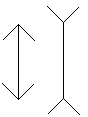
こうした唯我論は昔からあり、完全に反駁することは不可能です。しかし、次のように考えてみてください。「自分だけが存在する(あるいは、自分だけが意識を持つ)」と主張できるほど、自分のことがわかっているのかと。
人間の自己認識は、さまざまな知覚や記憶に基づいて形成されています。深く自省すればそれと知れることですが、身体についてのイメージも、直接的な与件ではなく、多種多様な知覚情報が混ざっている2次的な構成物でしかありません。目を閉じてだらしなく横になっているとき、どんな姿勢をしているのかわからなくなることがあるのも、そのせいです。身体イメージすら間接的であるのに、自分だけは特別だと思いなし、同じように間接的な情報から構成されている他者の意識に対してだけ懐疑的になるのは、いささか片手落ちでしょう。
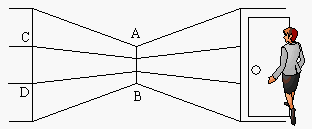
われわれは、単に感覚入力によって得られる情報だけで客観的な認識を構築しているのではなく、膨大な言語情報を使って、世界に関するモデルを作り上げています。こうしたモデルは、一般的に、感覚のみに頼る世界よりも合理的・整合的だと思われます。例えば、上の図で、2つの線分が同じ長さなのに、右側の方が長く見えるという錯視は、誰しもが実感できることだと思います。しかし、なぜそのように見えるか、感覚的な議論では明らかにできないでしょう。下の図を見ればわかるように、実は、この“錯視”は、幾何学的な遠近感を作り出す上で、重要な役割を果たしているのです。図の線分ABは線分CDと同じ長さであるにもかかわらず、長く見えるはずです。これは、遠近法に従えばABの方が遠くにあると推測されるので、「網膜から入力された視覚データが同じならば、実際には遠くにある方が大きい」という前提の下に、脳が表象される内容を補正していると解釈されています。こうした補正能力は、直線的なエッジが多く存在する現代的な環境での実体験を通じて獲得したと考えられ、「脳における視覚データの情報処理は、線の向きや大きさなどの単純な特徴を抽出した上で、脳の異なる部位で分析的に遂行される」という認知科学の知見と合致しています。感覚の世界では「なぜかそう見える」としか言いようがなかったのに比べて、この解釈が、より整合的で「腑に落ちる」ならば、“外部”から提供される言語情報は、それなりに信頼性が高いと考えても良いのではないでしょうか。
こうした信頼性の高い情報は、人間と呼ばれる個体が、きわめて類似した解剖学的組織を有しており、体内で生起するさまざまな生化学的反応も特定の類型に属していることを主張しています。とすれば、他の人間も、自分と同様な内面世界を持っていると推測するのが整合的でしょう。
それでも懐疑の念を打ち消せないならば、最終的には、パスカルのいわゆる“賭け”の議論を持ち出すしかありません。他者に意識があるかどうか、決定的な証拠がないことは確かです。しかし、どちらかに賭けるとするならば、意識があると仮定した場合の方が、他者に好意を寄せられるという快い利得があり、意識がないと仮定した場合よりも期待値(確率×利得)が大きくなるので、こちらに賭ける方が得策でしょう(ちなみに、パスカルは神の存在に関して賭けの議論を適用しています)。
【Q&A目次に戻る】

紙切れが舞い落ちる過程を物理学的に解析するのは、かなりの難問です。紙の形状や空気の流れによって、結果が全く異なったものになるからです。
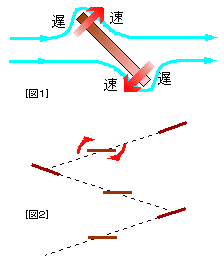
薄い板や紙が流体中に置かれている場合、流れに対して面が垂直になる向きに力が働きます。これは、面に沿って流れる流速に図1のような遅い・速いの差が生じ、ベルヌーイの定理に従って、流速の遅い部分の方が速い部分よりも圧力が高くなったためです。紙切れや木の葉が空気中を舞い落ちるときには、まず空気抵抗が少ない面に平行な向きに落下し始めますが、間もなく、この力のために回転し、その結果として抵抗が大きくなって急速に速度が遅くなります。すると、再び面と平行な向きへの落下に転じます。空気の流れがない理想的な状況下では、これを繰り返すことになり、ヒラリヒラリと往復運動を続けていきます(図2)。往復運動の周期や振幅は、落下物体の形状などに依存しますが、条件が同じならば、往復する幅の間のどこかに落下します。水中に硬貨を落としたときも、同じように往復運動しながらゆっくりと沈んでいくので、客に投げてもらった硬貨を海に潜ってキャッチするといった芸当も可能になります。
落下するのが細長い紙片などの場合は、往復運動にならずに、くるくると回転を続けながら一方向にドリフトしていくことがあります。このときは、紙片の形状などに依存するドリフト速度によって落下地点が決まります。
【参考文献】近角聡信著『日常の物理事典』(東京堂出版)p.45
【Q&A目次に戻る】

光関連技術は、現在、急速に発展しており、表示装置に使われる発光ダイオードや有機ELなどの技術をはじめとして、多くの応用が社会の至る所で見られます。
間もなく重要な社会的インフラになると予想されるのが、光ネットワークです。動画や音楽などのデータ交換が盛んになるにつえて、通信容量に対する要求水準が高まり、近い将来、ネットワークの基幹回線には毎秒1京ビット以上の容量が必要になると考えられています。回線部分に関してなら、光ファイバの改良によって要求に応えられるでしょうが、回線の切り替えに既存のデジタル交換機を使っていたのでは、信号品質の劣化と時間のロスが生じてしまいます。このため、「エレクトロニクス(電子工学)」に頼らずにすむように、「フォトニクス(光工学)」の研究が急ピッチで進められており、ミクロンサイズの鏡を利用した光スイッチを作ることも、夢物語ではなくなっています。こうした装置が低コストで製造できるようになれば、超高速光ネットの普及が進み、一般家庭でも高品位動画のオンライン視聴が可能になるほか、多数のパソコンをネットで結合した「メタコンピューティング」も実現されるでしょう。
フォトニクス技術は、さらに多くの可能性を秘めています。多くの科学者が注目しているのが、フォトニック結晶と呼ばれる人工的な結晶で、これを使えば、ちょうど半導体によって電子の流れを制御するように、光の流れを自在に操ることが可能になります。光集積回路の開発も視野に納められており、将来的には、こんにち電子を使って実現されている技術のかなりの部分が、光に取って代わられるかもしれません。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
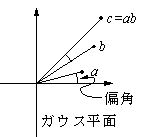 複素数の導入に当たって、こうした代数的な解釈をするよりも、はじめからガウス平面上で考えた方が、素直ではないでしょうか。実数では、「向き」という離散量と「大きさ」という連続量を変える演算としてかけ算を定義していましたが、この定義を改めて、かけ算とは、そもそも「角度」と「大きさ」という2つの連続量についての演算だと考え直すことにするのです。偏角に関しては、ガウス平面上でかける数の偏角の分だけ回転させる操作として「かけ算」を定義すれば、数直線上での向きを逆転させるといった離散的な操作は不必要になり、任意の代数方程式が解を持つことも納得できるはずです(任意の多項式 f(z) で z の偏角や絶対値を連続的に変化させると、f(z) の偏角や絶対値も連続的に変化することを考えてみてください)。実数から出発して訳の分からない虚数単位を導入するのではなく、「ガウス平面で回転させる演算としてかけ算を定義するのが複素数だ」と考えると、物理現象とのつながりが見えてきます。
複素数の導入に当たって、こうした代数的な解釈をするよりも、はじめからガウス平面上で考えた方が、素直ではないでしょうか。実数では、「向き」という離散量と「大きさ」という連続量を変える演算としてかけ算を定義していましたが、この定義を改めて、かけ算とは、そもそも「角度」と「大きさ」という2つの連続量についての演算だと考え直すことにするのです。偏角に関しては、ガウス平面上でかける数の偏角の分だけ回転させる操作として「かけ算」を定義すれば、数直線上での向きを逆転させるといった離散的な操作は不必要になり、任意の代数方程式が解を持つことも納得できるはずです(任意の多項式 f(z) で z の偏角や絶対値を連続的に変化させると、f(z) の偏角や絶対値も連続的に変化することを考えてみてください)。実数から出発して訳の分からない虚数単位を導入するのではなく、「ガウス平面で回転させる演算としてかけ算を定義するのが複素数だ」と考えると、物理現象とのつながりが見えてきます。
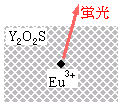 一般的な蛍光体は、母材(母体結晶)と呼ばれる結晶内部に、付活材と呼ばれる物質を注入して薄く分散させた構造になっています。例えば、ブラウン管などで用いられる赤色蛍光体 Y2O2S:Eu3+ は、母材となる Y2O2S 結晶の所々に Eu3+ が入り込んだものです。規則正しく配列した母材の結晶の中に付活材のイオンが入り込むと、結晶格子が歪んで電子のエネルギー状態が変化し、伝導バンドと荷電子バンドの間に新たなエネルギー準位が現れます。蛍光とは、通常、この準位から(あるいは、この準位へ)の遷移の際に放出される光子のことです。蛍光の波長λは、遷移する準位間のエネルギー差をΔEとすると、
一般的な蛍光体は、母材(母体結晶)と呼ばれる結晶内部に、付活材と呼ばれる物質を注入して薄く分散させた構造になっています。例えば、ブラウン管などで用いられる赤色蛍光体 Y2O2S:Eu3+ は、母材となる Y2O2S 結晶の所々に Eu3+ が入り込んだものです。規則正しく配列した母材の結晶の中に付活材のイオンが入り込むと、結晶格子が歪んで電子のエネルギー状態が変化し、伝導バンドと荷電子バンドの間に新たなエネルギー準位が現れます。蛍光とは、通常、この準位から(あるいは、この準位へ)の遷移の際に放出される光子のことです。蛍光の波長λは、遷移する準位間のエネルギー差をΔEとすると、
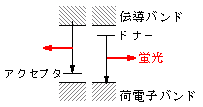 で与えられます。ここで、母材が一定の構造を持つ無限に拡がった完全結晶であり、付活材の密度も充分に低いとすると、エネルギー準位はシュレディンガー方程式によって完全に決定されるため、スペクトルの形は理論的に決まるはずです。
で与えられます。ここで、母材が一定の構造を持つ無限に拡がった完全結晶であり、付活材の密度も充分に低いとすると、エネルギー準位はシュレディンガー方程式によって完全に決定されるため、スペクトルの形は理論的に決まるはずです。
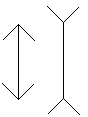 こうした唯我論は昔からあり、完全に反駁することは不可能です。しかし、次のように考えてみてください。「自分だけが存在する(あるいは、自分だけが意識を持つ)」と主張できるほど、自分のことがわかっているのかと。
こうした唯我論は昔からあり、完全に反駁することは不可能です。しかし、次のように考えてみてください。「自分だけが存在する(あるいは、自分だけが意識を持つ)」と主張できるほど、自分のことがわかっているのかと。
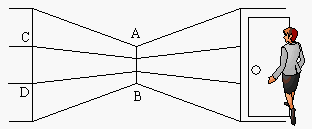 われわれは、単に感覚入力によって得られる情報だけで客観的な認識を構築しているのではなく、膨大な言語情報を使って、世界に関するモデルを作り上げています。こうしたモデルは、一般的に、感覚のみに頼る世界よりも合理的・整合的だと思われます。例えば、上の図で、2つの線分が同じ長さなのに、右側の方が長く見えるという錯視は、誰しもが実感できることだと思います。しかし、なぜそのように見えるか、感覚的な議論では明らかにできないでしょう。下の図を見ればわかるように、実は、この“錯視”は、幾何学的な遠近感を作り出す上で、重要な役割を果たしているのです。図の線分ABは線分CDと同じ長さであるにもかかわらず、長く見えるはずです。これは、遠近法に従えばABの方が遠くにあると推測されるので、「網膜から入力された視覚データが同じならば、実際には遠くにある方が大きい」という前提の下に、脳が表象される内容を補正していると解釈されています。こうした補正能力は、直線的なエッジが多く存在する現代的な環境での実体験を通じて獲得したと考えられ、「脳における視覚データの情報処理は、線の向きや大きさなどの単純な特徴を抽出した上で、脳の異なる部位で分析的に遂行される」という認知科学の知見と合致しています。感覚の世界では「なぜかそう見える」としか言いようがなかったのに比べて、この解釈が、より整合的で「腑に落ちる」ならば、“外部”から提供される言語情報は、それなりに信頼性が高いと考えても良いのではないでしょうか。
われわれは、単に感覚入力によって得られる情報だけで客観的な認識を構築しているのではなく、膨大な言語情報を使って、世界に関するモデルを作り上げています。こうしたモデルは、一般的に、感覚のみに頼る世界よりも合理的・整合的だと思われます。例えば、上の図で、2つの線分が同じ長さなのに、右側の方が長く見えるという錯視は、誰しもが実感できることだと思います。しかし、なぜそのように見えるか、感覚的な議論では明らかにできないでしょう。下の図を見ればわかるように、実は、この“錯視”は、幾何学的な遠近感を作り出す上で、重要な役割を果たしているのです。図の線分ABは線分CDと同じ長さであるにもかかわらず、長く見えるはずです。これは、遠近法に従えばABの方が遠くにあると推測されるので、「網膜から入力された視覚データが同じならば、実際には遠くにある方が大きい」という前提の下に、脳が表象される内容を補正していると解釈されています。こうした補正能力は、直線的なエッジが多く存在する現代的な環境での実体験を通じて獲得したと考えられ、「脳における視覚データの情報処理は、線の向きや大きさなどの単純な特徴を抽出した上で、脳の異なる部位で分析的に遂行される」という認知科学の知見と合致しています。感覚の世界では「なぜかそう見える」としか言いようがなかったのに比べて、この解釈が、より整合的で「腑に落ちる」ならば、“外部”から提供される言語情報は、それなりに信頼性が高いと考えても良いのではないでしょうか。
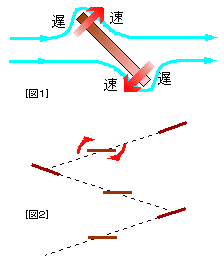 薄い板や紙が流体中に置かれている場合、流れに対して面が垂直になる向きに力が働きます。これは、面に沿って流れる流速に図1のような遅い・速いの差が生じ、ベルヌーイの定理に従って、流速の遅い部分の方が速い部分よりも圧力が高くなったためです。紙切れや木の葉が空気中を舞い落ちるときには、まず空気抵抗が少ない面に平行な向きに落下し始めますが、間もなく、この力のために回転し、その結果として抵抗が大きくなって急速に速度が遅くなります。すると、再び面と平行な向きへの落下に転じます。空気の流れがない理想的な状況下では、これを繰り返すことになり、ヒラリヒラリと往復運動を続けていきます(図2)。往復運動の周期や振幅は、落下物体の形状などに依存しますが、条件が同じならば、往復する幅の間のどこかに落下します。水中に硬貨を落としたときも、同じように往復運動しながらゆっくりと沈んでいくので、客に投げてもらった硬貨を海に潜ってキャッチするといった芸当も可能になります。
薄い板や紙が流体中に置かれている場合、流れに対して面が垂直になる向きに力が働きます。これは、面に沿って流れる流速に図1のような遅い・速いの差が生じ、ベルヌーイの定理に従って、流速の遅い部分の方が速い部分よりも圧力が高くなったためです。紙切れや木の葉が空気中を舞い落ちるときには、まず空気抵抗が少ない面に平行な向きに落下し始めますが、間もなく、この力のために回転し、その結果として抵抗が大きくなって急速に速度が遅くなります。すると、再び面と平行な向きへの落下に転じます。空気の流れがない理想的な状況下では、これを繰り返すことになり、ヒラリヒラリと往復運動を続けていきます(図2)。往復運動の周期や振幅は、落下物体の形状などに依存しますが、条件が同じならば、往復する幅の間のどこかに落下します。水中に硬貨を落としたときも、同じように往復運動しながらゆっくりと沈んでいくので、客に投げてもらった硬貨を海に潜ってキャッチするといった芸当も可能になります。