
恐竜絶滅に関する小惑星衝突説は、「
科学の回廊」−「
アルヴァレらによる恐竜絶滅の新説はなぜ受容されたか? 」の中でも書いたように、あくまで有力な仮説の1つに過ぎません。この説を反証しようとする論文は、これまでに何本も発表されていますし、これからもそうでしょう。しかし、現時点で、多くのデータと整合する最も信憑性の高い説であることは間違いありません。
今回、問題となっているのは、ケラーらプリンストン大学のグループが米科学アカデミー紀要に発表した次の論文です:
G. Keller et al., 'Chicxulub impact predates the K-T boundary mass extinction' (PNAS, 101(2004)3753)
オンライン版のアブストラクト(www.pnas.orgで閲読可能)によると、これまで恐竜絶滅をもたらした小惑星の衝突跡と考えられてきたユカタン半島のチチュラブ・クレータが、白亜紀−第三紀境界より30万年も前のものであることが判明したとのことです。研究グループは、クレータ内から削りだした試料を使って、堆積学(sedimentology)・生層位学(biostratigraphy)・磁気地層学(magnetostratigraphy)などに基づく分析を行い、結論を導き出したそうです。
この結論に対する解釈としては、次のようなものが考えられます。
- 分析結果は誤っており、チチュラブ衝突は白亜紀−第三紀境界に起きた。学術論文の中には、「実験・観測によって〜であることが実証された」と唱いながら、後に誤りであることが判明したものが、驚くほど(一般の人が心底驚愕するほど)たくさんあります。このため、理論系の科学者は、実験系の科学者の言うことを鵜呑みにせず、追試が行われるまで態度を保留することも少なくありません。実際、白亜紀−第三紀境界層より上の地層からアンモナイトの化石が発見されたという報告が提出されたこともありますが、これは、褶曲などによって地層の上下が入れ替わったせいだと判明しています。小惑星の衝突地点では、大量の土砂が噴出した後に再び舞い降りて堆積しているため、分析を誤りやすいと推測されます。
- チチュラブ衝突の30万年後に再び小惑星の衝突が起きた。白亜紀−第三紀境界層には地表には少ないイリジウムが集積しており、その時点で小惑星の衝突が起きたと考えるのが一般的です。ケラーらの分析が正しいとすると、白亜紀の生物たちは、わずか30万年の間に立て続けに起きた天災によって滅びたことになります。ただし、直径10km以上の巨大隕石の衝突は1億年に1回程度と推定されており、確率的には起こりそうにない話です。
- チチュラブ衝突の30万年後に火山の大噴火が起きた。イリジウムはマントルにも多く含まれているので、世界規模で大噴火が起きれば、白亜紀−第三紀境界層でのイリジウム集積を説明できます。ただし、これほどの天変地異が30万年の間に独立した(互いに無関係の)出来事として起きる確率は、かなり小さいはずです。巨大隕石の衝突が火山噴火の引き金になることが示せるならば、一応は整合的な説となるのですが、30万年という間隔は、いかにも長すぎるような気がします。
- チチュラブ衝突の30万年後に未知の大事件が起きた??
チチュラブ衝突が白亜紀−第三紀境界層と恐竜の絶滅をもたらしたという仮説は、世界各地で得られた多くのデータと良く一致しているため、1地点で採取された試料の分析だけで覆すことはできません。今のところは、1番目の解釈が最も妥当だと思われます。しかし、今後の研究によって状況が一変し、「やはり小惑星衝突説は間違っていた」という展開になるかもしれません。それはそれで、面白い話です。
科学という学問の要諦は、個人が持つ知能の限界を自覚することです。科学以外のジャンルでは、圧倒的な能力を誇る天才がいて、その人にお伺いを立てれば何でもわかるということがあり得ます。しかし、現代科学の総体は、個人の知的ポテンシャルを遥かに上回っており、どんなに天才的な科学者でも、1人で完成された学説を作り上げることはできません。大勢の科学者が「ああでもないこうでもない」とアイデアを出し合っていくうちに、だんだんと定説となる学説が練り上げられていくのです。科学的研究がこうしたものである以上、有力な仮説に反対するヘソ曲がりの存在は必要不可欠です。彼らの反論に揉まれているうちに、学説の完成度が高くなっていくからです。ケラーらの研究は、そうした反論の1つであり、おそらくは、小惑星衝突説の完成度を高めるステップとして利用されることになるでしょう。
【Q&A目次に戻る】

人間の思考は、厳密に論理的であるとは言えません。しかし、世界が論理的でない以上、非論理性は、適切な理解を得るために必要なことです。
世界は法則に則って変化していますが、最も根元的な法則は、人間の認識能力の埒外にあると言わざるを得ません。人間は、世界を近似的に表すモデルを案出し、このモデルに基づいて、未来予測や状況判断を行っています。こうしたモデルの中には、その変動が厳密に定義されているものもあり、コンピュータ・シミュレーションを行えば、将来にわたる振舞いが完全に解明できるものもあります。仮に、このモデルが世界を完璧に表現しているならば、人間の智慧よりもコンピュータ計算の方が信頼できることになるでしょう。しかし、モデルには常に適用限界があり、どこまでモデルが利用できるかを決めるには、必ずしも論理的でない人間の経験知に頼らざるを得ないのです。
例えば、近年の経済学者は、利潤を求める企業家やステータスに応じて商品を購入する消費者の行動をモデル化し、コンピュータによる経済動向の予測を行っています。こうした予測は、経済が比較的安定しているときには、かなりの精度で的中しますが、株価が異常に高騰したり、世情が不穏になってきたりすると、人間の経済行動はモデルから逸脱し始め、予測精度は一気に低下します。アメリカにおけるITバブル崩壊の背景には、経済モデルへの過信があったとも言われていますが、真に賢明な人間は、「そろそろこのモデルは使えなくなるな」と感じて投資を引き上げていたのではないでしょうか。
日常的な世界でも、われわれは、モデルに基づいて物事を理解することが多々あります。コップを手で持とうとするとき、これを3次元空間内に定位された滑らかな形状の物体としてモデル化し、その把持に必要な筋出力を素早く(主に小脳で)計算します。単純な作業に関しては、モデルに基づく思考はかなりの程度まで論理的ですし、場合によっては、脳にコンピュータを埋め込んだ方が思考の効率は上がるかもしれません。しかし、他者とのコミュニケーションを含む社会的な行動を開始すると、単純なモデルは通用しなくなります。「1+1=2」とは論理的世界の必然なのでしょうが、「何が1個の対象とされるのか」が必ずしも判然としていない人間社会において、この必然は成立しません。孤立した2人と協力しあうカップルが、本質的に異なるということもあるからです。
厳密な論理が通用するのは適切に定義されたモデルの世界であり、そうしたモデルによって精度の良い近似が行える状況は、論理的に理解することが可能でしょう。しかし、現実の世界はモデルによって記述しきれない面を必ず持っています。適用モデルの限界を知ることは、論理を越える人間独自の思考であるはずです。
【Q&A目次に戻る】

現代物理学において、真空とは、何も存在しない空っぽの“虚空”ではなく、素粒子の場が許された最低のエネルギーを持つ「基底状態」だと解釈されています。こうした基底状態では、次のような形で素粒子が登場します:
- 零点振動に相当する反応。真空中でも、粒子・反粒子の対生成・対消滅が絶え間なく生じており、通りかかった他の素粒子と相互作用して真空偏極などを引き起こす。
- 真空中への凝縮。真空と同じ量子数を持つ場は、空間全体に瀰漫するように凝縮することがある。ヒッグス粒子と呼ばれるスカラー粒子が真空中に凝縮すると、電子やクォークの通行を妨害するために、慣性質量を生み出す。
- 超長波長の場。光子のように質量がない素粒子の場合、超長波長状態のエネルギーは限りなくゼロに近くなるため、真空状態と厳密に区別することができない。
このうち、3番目のケースでは、宇宙の膨張とともに超長波長の場の強度は弱まっていきますが、残りの2つでは、元の真空と同じ状態の空間が拡がっていくことになります。
仮に素粒子を1個2個…と数えられる粒子だと考えると、宇宙の膨張・収縮によって真空中にある素粒子の個数が増大・減少することになり、かなり奇妙な感じを受けるでしょう。しかし、実は、真空における素粒子は、ビリヤード球のように個数が数えられる粒子ではありません。素粒子の本来の姿は、電磁場のような“場”であり、これが特定の“励起状態”になると、粒子的に振舞うようになるのです。素粒子論を啓蒙的に解説した書物に、「真空では電子と陽電子が対になって生成消滅を繰り返す」と説明されることがありますが、これもあまり正確な記述ではなく、真空状態を、電子や陽電子の状態で書き換えた(数学的に言えば、摂動論展開を行った)ときの一部分(展開項の1つ)を、そう述べているだけのことで、実際には、粒子としてイメージできるような電子・陽電子が現れるわけではありません。
真空に凝縮している場についても、同様です。こうした凝縮場は、粒子というよりも古典的な場に近い状態にあるので、膨張とともに凝集している粒子の個数が増えるということはなく、一定の強度を保ったまま宇宙とともに場が拡がっていくと考えてかまいません。
ただし、粒子数の増減という問題が解消されたとしても、宇宙空間が膨張する過程でミクロな世界に何が起きるか完全に解明されたわけではありません。連続的な場で自然界を記述する現在の理論では、ある状態を保ったまま場が拡がっていくことは、さして不自然ではないでしょう。しかし、おそらく時空は連続的なものではなく、より根元的な理論においては、時空の最小単位というものを考えなければならないはずです(最新の量子ループ理論で、そうした試みが始まっています)。宇宙が膨張するとき時空の最小単位がどのように変化していくかは、今なお研究途上にあると言えます。
【Q&A目次に戻る】

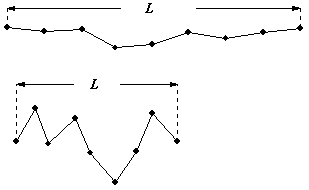
伸ばしたゴムを加熱すると縮もうとする、あるいは、ゴムを急に伸ばすと発熱することは、19世紀の初めにゴフ(Gough)が発見し、後にジュールが詳しく研究したことから、ゴフ=ジュール効果と呼ばれています。この性質は、ゴムの弾性が、金属バネなどとは異なり、エントロピー弾性と呼ばれる統計熱力学的な効果であることに由来しています。
ゴムは、多数の鎖状高分子が絡み合ったものです。フックの法則に従う小さな伸張においては、この鎖状高分子が、クネクネ曲がった状態からより真っ直ぐな状態へと変化したと見なすことができます(大変形の場合は、高分子間の相互作用を考慮する必要があります)。簡単のため、鎖状高分子を剛体棒が連結されたモデルで表し、連結部で折れ曲がるときの角度はいくつかの離散的な値しか取らず、全体のエネルギーは折れ曲がり方に寄らないと仮定します。この場合、鎖全体の長さL が小さいほど、(各連結部がどの角度で曲がるかという)折れ曲がり方のパターン数Ωは多くなります(図参照)。最大の長さになるのは、剛体棒が全て真っ直ぐに連なったときで、パターン数は1つに限られます。こうしたパターン数の多寡は、乱雑さの度合いを表すと考えられます。長さL が小さい場合は、各連結部でどのように折れ曲がっているか推測しにくい乱雑な状態であり、L が大きいほど、パターンがほぼ決まった乱雑さの少ない状態になります。一般に、あるシステムは、温度が上昇すると、より乱雑な状態に移行する傾向があります。ゴムを加熱した場合は、より乱雑に折れ曲がったL の小さい状態へと変化しようとするのです。
こうした性質を理論的に説明するのが統計熱力学で、エントロピーと呼ばれる量を使って定式化します。エントロピーS は、パターン数(より一般的には状態数)Ωを使って、次のように定義されます:
S = k log
e Ω (k : ボルツマン定数)
詳しい説明は統計熱力学の教科書に譲りますが、鎖状高分子の場合、全体を一定の長さに保のに必要な力f は、近似的に次の公式で与えられることが知られています:
f = - T (∂S/∂x)
T (x : 全体の長さ)
一般の場合にS を計算するのはたいへんなので、1次元鎖の場合を考えましょう。1次元鎖では、各連結部を真っ直ぐに伸ばすか、180°折り曲げるかかという2つの選択肢しかありません。真っ直ぐな連結部の個数をn
+、180°折り曲げた連結部の個数をn
-とすると、
n
+ = ( n + Δ)/2
n
- = ( n - Δ)/2
x = aΔ
ただし、n : 連結部の総数、a : 個々の棒の長さ、x : 全体の長さ
となります(nはきわめて大きいので、±1程度の差は無視します)。x を一定にしたときのパターン数は、n個の連結部からn
+個の真っ直ぐな連結箇所を選び出す場合の数になるので、
Ω = n!/n
+!n
-!
で与えられます。スターリングの公式:
log
e n! = n log
e n - n
を適用すれば、エントロピーS= k log
eΩ は簡単に計算できて、
S = (定数)- kn {(1+x/na)log
e(1+x/na) + (1-x/na)log
e(1-x/na)}/2
となります。x が na に比べて小さいと仮定すれば、対数項を展開して、
S ∝ x
2
が得られます。したがって、
f = - T (∂S/∂x) ∝ Tx
となり、係数が絶対温度に比例するフックの法則が成立することがわかります。この式によって、加熱すると伸ばしたゴムが縮もうとするというゴフ=ジュール効果が説明できます。
【Q&A目次に戻る】

消泡剤の作用を理解するためには、まず、なぜ泡構造が安定するかを理解する必要があります。
水をはじめとする多くの液体は、純粋なときにはほとんど泡立たないのに、他の物質を混ぜると泡立ちやすくなるという性質を示します。理由の1つは、石けんなどの起泡剤を混ぜたときに、起泡剤分子の働きで、膜の一部が薄くなったときに元に戻すという「膜弾性」が生じるからです。親水基と親油基を持つ起泡剤分子が混入している水が膜状になった場合、起泡剤分子は親水基を内側にして膜の表面にほぼ一定の面密度で分布します。ここに外力が加わって膜の一部が薄く引き延ばされると、起泡剤分子がまばらになるため、元の分布に戻ろうとする作用が生じます
(図1)。この作用が、膜が簡単に破れない原因になると考えられています。
消泡剤の中には、液体表面に存在する起泡剤分子の分布を変えることによって消泡効果を発揮するものがあります。例えば、ある種の有機液体は、膜の表面に付着したときに起泡剤分子の層を押しのけることによって、膜弾性を低下させます(境界面に分布する有機液体の分子は、膜が伸張して分布がまばらになっても、液体の側から新たな分子が供給されるため、膜弾性をもたらしません)
(図2)。このため、泡は薄くなったときに元に戻るという性質を失い、不安定になって破壊されます。こうした消泡剤が効果的に作用するためには、泡を作る液体に溶けない、泡表面に薄く拡がる性質がある(拡散性が高い)──などの化学的特性が要求されるため、泡を作る液体によって、有効性が大きく異なります。
シリカのような疎水性粉末も消泡効果を持っていますが、これは、膜表面に分布していた分子をくっつけたまま内部に沈み込むためです
(図3)。この効果も、親油基が粉末にうまくくっつくかどうかに依存しており、水の泡で効果的だからといって、親油基の方に親和性がある油の対して有効とは限りません。
【参考文献】『消泡剤の応用』(佐々木恒孝監修、シーエムシー)
【Q&A目次に戻る】

プラスチックなどの高分子素材の大半は絶縁体ですが、一部の物質は電気を通すことができます。こうした物質が、導電性高分子と呼ばれています。
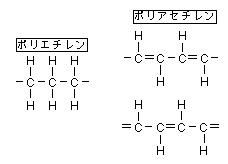
通常の高分子が電気を通さないのは、電子が特定の原子に束縛された結合電子(σ電子)になっていて、自由に動けないからです。例えば、ポリエチレンの場合、炭素原子の外側にある4つの電子は、いずれも隣り合う原子(2個の炭素原子、2個の水素原子)と共有されて原子をつなぎ止める役割を果たしています。これらの電子は自由に動くことができないので、ポリエチレンの電気伝導度はきわめて低く、絶縁体となります。これに対して、ポリアセチレンの炭素原子は、4つの電子のうちの2つが隣の炭素原子との二重結合に使われています。こうした二重結合は、炭素骨格で1つおきに現れますが、ある炭素原子のどちら側に二重結合ができるか決まっているわけではなく、図の2つの結合状態が混じった(縮退した)状態が実現されています。つまり、二重結合に関与している電子の1つは、炭素原子のどちら側にも存在できることになるのですが、炭素原子間の電子は一方の炭素に“所有”されているわけではなく、両方に“共有”されているのですから、結局、炭素骨格のどこにでも存在できるような可動性を持っているのです。こうした電子はπ電子と呼ばれ、導電性をもたらす鍵となっています。
ただし、純粋なポリアセチレンは、ほとんど電気を通しません。全ての軌道にπ電子が詰まっており、(パウリの排他率によって)動き回るためのスペースがないためです。このスペースを作るために利用されるのが、ヨウ素のような電子を奪う物質(p型ドーパント)です。ポリアセチレンにヨウ素をドーピングしてやると、電子が動くスペースができる(より正確に言えば、電子の抜けた“穴”が移動する)ために、電気伝導度は1000億倍にもなって、金属並の導電性が実現されたのです。
導電性高分子の利点は、高い電気伝導度を持ちながら、容易に加工できる点です。身近な応用例としてよく目にするのは、導電性高分子をシート状に加工したタッチパネルで、指で触れた位置が電気的信号となって伝えられています。このほか、帯電防止トレイや機能性コンデンサとしても利用されています。最近では、ある種の導電性高分子(ポリフェニレンビニレンなど)が電気を通すと光を発する性質を持っていることを利用して、消費電力が少なく折り曲げることもできる有機ELディスプレイの素材に使おうという動きもあります。
【Q&A目次に戻る】

太陽系惑星の放射平衡とは、太陽からの放射によるエネルギー収入と、惑星から宇宙空間に放射されるエネルギー支出が等しくなっている状態で、内部からの発熱が無視できる地球型惑星で近似的に成立しています(木星型惑星では、内部からの熱が無視できないほど大きくなります)。
惑星に照射されるエネルギーは、太陽までの平均距離によって決まります。地球の公転軌道上における単位時間・単位面積当たりの平均放射エネルギーは、太陽定数と呼ばれており、その値は、
1370 W/m
2
です。火星の公転半径は、天文単位(地球の公転軌道の長半径を基準とする長さの単位)で1.5237 AUであり、太陽からの放射エネルギーは(球面状に拡がるため)距離の逆2乗で減少するので、火星軌道上での太陽放射エネルギーFは、
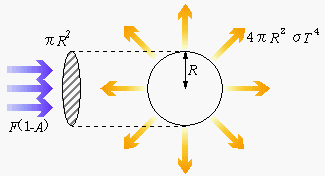
F = (太陽定数)×(1/1.5237)
2 = 590 W/m
2
になります。この入射エネルギーのうち、一部は惑星に吸収されずに宇宙空間に反射されてしまいます。惑星全体で見たとき入射されるエネルギーに対する全反射エネルギーの値は、アルベド(ボンドアルベド)と呼ばれており、地球は0.30、火星は0.16 です(地球のアルベドが大きいのは、雲の上面で多く反射されるためです)。太陽放射をF、アルベドをA と表すと、惑星に吸収される(正味の)太陽放射は F(1-A) であり、地球と火星で、それぞれ次の値になります:
地球 959.0 W/m
2
火星 495.7 W/m
2
放射平衡温度とは、惑星が吸収する太陽放射の全エネルギーと、惑星が完全黒体であると仮定したときに放出される熱放射エネルギーが等しくなるときの黒体の温度のことです。惑星が吸収するエネルギーは、惑星の半径を R とすると、
F(1-A)πR
2 …(1)
で与えられます(図参照)。一方、温度T の黒体の熱放射は、ステファン・ボルツマンの放射法則より、単位時間・単位面積あたり、
σT
4
になることが知られています。ただし、σはステファン・ボルツマン定数で、
σ = 5.67×10-8 W/m
2K
4
です。惑星全体からの熱放射は、
4πR
2σT
4 …(2)
となり、(1)と(2)が等しいという条件から、放射平衡温度T を求めるための公式:
F(1-A) = 4σT
4
が得られます。この式に数値を代入して放射平衡温度を求めると、
地球 255 K
火星 216 K
となります。地球表面の実際の平均温度は 288K と上の値よりかなり高くなっていますが、これは、地球の大気による温室効果の結果です。一方、火星表面の平均温度は、230K 程度であり、温室効果は地球の場合ほど効いていません。
【Q&A目次に戻る】

20世紀半ばまで、網膜上の視覚情報は、そのまま脳の視覚連合野に送られ、この情報から対象についてのデータを探索していると考えられていました。しかし、実験技術の進歩とともに、視覚情報を処理する機能は、はるかに専門分化していることが判明します。最初に視覚情報が送られるのは、後頭葉にある1次視覚野ですが、この段階で、全視野の情報が属性ごとに分けられ、それぞれが、異なる皮質に投射されます。送り先には、運動の処理系(V5野)、色の処理系(V4野)、形の処理系(色と関係した形を処理するV4野と運動する対象の形を処理するV3野)があり、各部位が担当する属性だけを分析します。最終的な視覚像が認識されるのは、属性ごとに分析されたデータを視覚連合野で統合してからです。われわれは、視覚的な光景を連続的な拡がりのように感じていますが、実際には、細切れにされたデータの集積なのです。一酸化炭素中毒で運動と形の処理系が傷害された患者に関する臨床記録によると、この人は、色の処理だけで視覚を構成しようとするため、青い色の対象を見ると、全て海だと誤認するそうです。
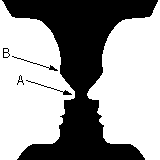
各属性を処理するシステムでは、成長過程で獲得されたいくつかのテンプレートが用意されており、これと比較しながら特徴を捉える作業が行われています。したがって、統合された視覚的認識に含まれるデータの総量は、それほど多くはないはずです。にもかかわらず、複雑な世界の状況全体を直観的に把握していると感じられるのは、絶え間なく視覚情報の処理が続けられているからです。例えば、ルビンの杯のように、2通りの見え方をする図形がありますが、これが、同時に2つの顔と西洋風の杯に見えることはありません。われわれは、それと意識せずに細かく視線を動かしており、エッジの曲率が極大になるところを見つけると、通常は、そこが出っ張っているものと仮定して形の分析を進めていきます。このため、まず図のAの部分に着目すると、そこが出っ張っているものと見なすので人間の顔が見えてきますし、Bの部分に着目すると杯に見えるはずです(見え方には個人差があります)。こうした作業が常に続けられているので、処理される情報量は全体として膨大なものとなり、世界が隅々まで見えているように感じられるのでしょう。
【Q&A目次に戻る】

力学を力・質量・加速度の関係として定式化したのはニュートンですが、彼の主著『プリンキピア』においても、質量が物質固有の保存量として、加速度が位置の時間変化として、それぞれ明確に定義されるのに対して、力の定義には曖昧さが残されています。例えば、複数の物体に取り囲まれている質点には、各物体からの万有引力が別々に作用し、その合力によって運動が決定されるのか、それとも、本当に作用しているのは合力だけなのか、実験によって決定することはできません。このため、質問者と同様に、力は実体的なものではなく、運動方程式 f=ma によって便宜的に定義されるにすぎないと考える哲学者もいました。
しかしながら、ニュートンが導入した力の概念は、単に便宜的なものとは言えない要素をいろいろと含んでいます。何よりも、「物質が持つ内在的な性質の現れ」ではなく、「他の物体からの作用」として非物質的に捉えた点が重要です。物体が落下するのは、地球の中心に向かう性質があるからではなく、地球から物体に万有引力が作用するからだ──というわけです。さらに、作用・反作用の法則に従って、地球が物体に及ぼすのと同じ力が物体から地球に及ぼされることが示されます。こうした物体間相互作用が全て理論から与えられるならば、力の概念が持っていた曖昧さは払拭されることになります。
19世紀までは、摩擦力や抗力のように、物体の運動を通じてしか大きさを決められない力が数多く残されていたため、力の何たるかを解明することはできませんでした。しかし、その後、万有引力以外の力の大半が電磁気的な相互作用であることが明らかになり、“場”を介しての相互作用という定式化が可能になります。電磁気的相互作用の場合は、粒子が電磁場を作り出し、電磁場が粒子に作用を及ぼすという場と粒子の2元論で記述されます。さらに、万有引力も重力場の理論としてまとめられ、ニュートン力学に内包されていた力の曖昧さは、
(「全ての力が解明されたわけではない」、「量子論特有の困難が残されている」などの問題を別にすると)ほぼ完全に解消されました。例えば、複数の物体に取り囲まれた質点に働くのは、周囲の物体によって作られた重力場からの作用であり、各物体に向かうようなベクトルで表される力が“実際に”作用しているわけではありません
(自己相互作用の問題は、ここでは触れません)。
なお、人工衛星内部の無重量状態と、あらゆる天体から遠く離れた領域における無重力状態が実質的に等価であることには、深い物理的意味があります。簡単に言えば、重力と(遠心力などの)慣性力は原理的に区別できないものであり、運動を記述する座標系の定義から見直す必要がある──ということになるのですが、詳しい説明は、一般相対論に関する教科書などを参照してください。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
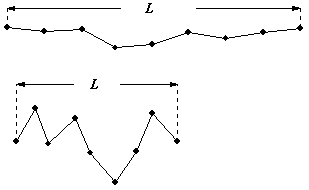 伸ばしたゴムを加熱すると縮もうとする、あるいは、ゴムを急に伸ばすと発熱することは、19世紀の初めにゴフ(Gough)が発見し、後にジュールが詳しく研究したことから、ゴフ=ジュール効果と呼ばれています。この性質は、ゴムの弾性が、金属バネなどとは異なり、エントロピー弾性と呼ばれる統計熱力学的な効果であることに由来しています。
伸ばしたゴムを加熱すると縮もうとする、あるいは、ゴムを急に伸ばすと発熱することは、19世紀の初めにゴフ(Gough)が発見し、後にジュールが詳しく研究したことから、ゴフ=ジュール効果と呼ばれています。この性質は、ゴムの弾性が、金属バネなどとは異なり、エントロピー弾性と呼ばれる統計熱力学的な効果であることに由来しています。
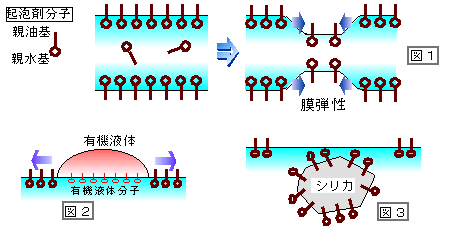
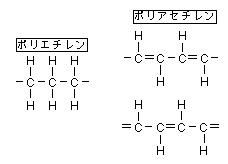 通常の高分子が電気を通さないのは、電子が特定の原子に束縛された結合電子(σ電子)になっていて、自由に動けないからです。例えば、ポリエチレンの場合、炭素原子の外側にある4つの電子は、いずれも隣り合う原子(2個の炭素原子、2個の水素原子)と共有されて原子をつなぎ止める役割を果たしています。これらの電子は自由に動くことができないので、ポリエチレンの電気伝導度はきわめて低く、絶縁体となります。これに対して、ポリアセチレンの炭素原子は、4つの電子のうちの2つが隣の炭素原子との二重結合に使われています。こうした二重結合は、炭素骨格で1つおきに現れますが、ある炭素原子のどちら側に二重結合ができるか決まっているわけではなく、図の2つの結合状態が混じった(縮退した)状態が実現されています。つまり、二重結合に関与している電子の1つは、炭素原子のどちら側にも存在できることになるのですが、炭素原子間の電子は一方の炭素に“所有”されているわけではなく、両方に“共有”されているのですから、結局、炭素骨格のどこにでも存在できるような可動性を持っているのです。こうした電子はπ電子と呼ばれ、導電性をもたらす鍵となっています。
通常の高分子が電気を通さないのは、電子が特定の原子に束縛された結合電子(σ電子)になっていて、自由に動けないからです。例えば、ポリエチレンの場合、炭素原子の外側にある4つの電子は、いずれも隣り合う原子(2個の炭素原子、2個の水素原子)と共有されて原子をつなぎ止める役割を果たしています。これらの電子は自由に動くことができないので、ポリエチレンの電気伝導度はきわめて低く、絶縁体となります。これに対して、ポリアセチレンの炭素原子は、4つの電子のうちの2つが隣の炭素原子との二重結合に使われています。こうした二重結合は、炭素骨格で1つおきに現れますが、ある炭素原子のどちら側に二重結合ができるか決まっているわけではなく、図の2つの結合状態が混じった(縮退した)状態が実現されています。つまり、二重結合に関与している電子の1つは、炭素原子のどちら側にも存在できることになるのですが、炭素原子間の電子は一方の炭素に“所有”されているわけではなく、両方に“共有”されているのですから、結局、炭素骨格のどこにでも存在できるような可動性を持っているのです。こうした電子はπ電子と呼ばれ、導電性をもたらす鍵となっています。
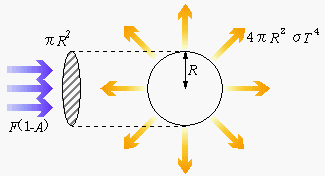
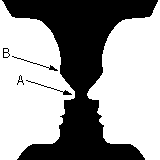 各属性を処理するシステムでは、成長過程で獲得されたいくつかのテンプレートが用意されており、これと比較しながら特徴を捉える作業が行われています。したがって、統合された視覚的認識に含まれるデータの総量は、それほど多くはないはずです。にもかかわらず、複雑な世界の状況全体を直観的に把握していると感じられるのは、絶え間なく視覚情報の処理が続けられているからです。例えば、ルビンの杯のように、2通りの見え方をする図形がありますが、これが、同時に2つの顔と西洋風の杯に見えることはありません。われわれは、それと意識せずに細かく視線を動かしており、エッジの曲率が極大になるところを見つけると、通常は、そこが出っ張っているものと仮定して形の分析を進めていきます。このため、まず図のAの部分に着目すると、そこが出っ張っているものと見なすので人間の顔が見えてきますし、Bの部分に着目すると杯に見えるはずです(見え方には個人差があります)。こうした作業が常に続けられているので、処理される情報量は全体として膨大なものとなり、世界が隅々まで見えているように感じられるのでしょう。
各属性を処理するシステムでは、成長過程で獲得されたいくつかのテンプレートが用意されており、これと比較しながら特徴を捉える作業が行われています。したがって、統合された視覚的認識に含まれるデータの総量は、それほど多くはないはずです。にもかかわらず、複雑な世界の状況全体を直観的に把握していると感じられるのは、絶え間なく視覚情報の処理が続けられているからです。例えば、ルビンの杯のように、2通りの見え方をする図形がありますが、これが、同時に2つの顔と西洋風の杯に見えることはありません。われわれは、それと意識せずに細かく視線を動かしており、エッジの曲率が極大になるところを見つけると、通常は、そこが出っ張っているものと仮定して形の分析を進めていきます。このため、まず図のAの部分に着目すると、そこが出っ張っているものと見なすので人間の顔が見えてきますし、Bの部分に着目すると杯に見えるはずです(見え方には個人差があります)。こうした作業が常に続けられているので、処理される情報量は全体として膨大なものとなり、世界が隅々まで見えているように感じられるのでしょう。