
相対性理論によって、全宇宙で同じように時間が刻まれているのではないことが明らかになって以来、時間軸上を自由に行き来する仮想的な機械──いわゆるタイムマシンの存在を原理的に否定する根拠はなくなりました。実際、何人かの物理学者は、タイムマシンを実作する方法について、まじめな論文を発表しています。しかし、これらはいずれも、現実にはありそうもない状況を想定するものであり、近い将来(あるいは遠い将来にも)、タイムマシンが作られる可能性はほとんどなさそうです。
時間移動を可能にする手段としては、重力場を利用する方法と、宇宙のトポロジー(位相構造)を利用する方法とがあります。一般相対論によると、強い重力場の中では時間はゆっくり進むことが知られています。従って、人工的に重力場を発生させたり、宇宙船を加速度運動させたりすると、そこにいる人間にとって、時間は外部の人よりもゆっくりと経過します。宇宙船内部で10年経つ間に外部で20年が経過したとすると、実質的に、10年後の未来にタイムトラベルしたことになるわけです。しかし、この例のように外部の半分の時間しか経過しないようにするためには、(地球表面の重力を1Gとして)20億Gの重力場の中に入らなければなりません(即死します)。また、未来に行くことはできても、過去には戻れません。
宇宙が周期的境界条件を満たすようなトポロジーを持っているならば、ロケットで宇宙を1周すると、出発点に帰ってきたときウラシマ効果によって残っていた人より若いままでいられる──つまり、未来に行ったことになります(このことに関しては、「科学の回廊−
周期的空間における双子のパラドクス」参照)。しかし、銀河系近傍の数億光年を見る限り、こうしたトポロジーはなさそうです。
ホイーラーら何人かの物理学者がタイムマシンとして使えると指摘しているのが、ワームホールです。ワームホールとは、宇宙のある地点と別の地点を直に結ぶような一般相対論の特殊解で、通常とは異なるトポロジーを持っています。もし、ワームホールの両端で時刻が異なっていれば、未来の側からワームホールに入って過去の側に出ることにより、過去への旅も可能になるはずです(逆のルートを辿れば未来に行けます)。ただし、理論的な計算では、ワームホールは巨大な重力のために一瞬のうちに潰れてしまうという結果が出ています。崩壊を防ぐためには、マイナスのエネルギーを持った何かで支えなければならないのですが、そんなものが宇宙のどこかに存在するとは思えません。これまでの常識が覆されるような大発見がない限り、ワームホールを使った時間旅行は夢物語に終わりそうです。
この他にも、宇宙ひもと呼ばれる重力場の歪みを利用したタイムマシンも提案されていますが、やはり実現は困難のようです。
【Q&A目次に戻る】

遺伝子はしばしば“生命の設計図”を与えると言われますが、実際にはそれほど大局的な情報を含んだものではなく、ある状態の細胞が特定の環境下に置かれたときに引き起こされる一連の反応中の一部を規定しているにすぎません。たとえ、それがアミノ酸配列の決定という最も重要な部分であるにしても、遺伝子の機能はそれ以上のものではないはずです。遺伝子について理解するためには、この点を正しく認識する必要があります。
遺伝子そのものが持つ情報は、アデニン・チミン・グアニン・シトシンの塩基配列に集約されています。しかし、塩基配列だけが遺伝情報を担っているのではありません。例えば、DNA分子上で遺伝子と遺伝子の間隙に当たるイントロンの部分は、かつては機能を持たない単なる“つなぎ”にすぎないと思われていましたが、近年、遺伝子の発現や転写活性を調整したり、合成されるタンパク質の修飾に関与していることが明らかになりました。また、転写されたRNAが何通りかのスプライシングを行うによって、1つの遺伝子から数種類のタンパク質が作られる場合がありますが、この過程には、RNAとタンパク質の複合体が寄与しています。さらに、生体内におけるタンパク質の機能は、糖や脂質などを付加する分子修飾によって変わってきますが、遺伝子が修飾の仕方まで決めている訳ではありません。この他にも、タンパク質やRNAの輸送、受容体との相互作用など、遺伝子の発現から引き起こされる一連の反応には、実にさまざまの因子が絡んでいます。
このように、遺伝子と発現形質の間には単純な対応関係がないため、遺伝子情報の解釈は一筋縄ではいきません。現在、バイオインフォマティクスと呼ばれる学問分野が急成長していますが、これは、ゲノム解読などで明らかになった遺伝子やイントロンについての膨大なデータと、これまた膨大な量になる発現形質に関するデータを、コンピュータによる力業で突き合わせ、両者の相関関係を解明しようというものです。ここで用いられるのは、リレーショナル・データベースを記述するプログラミング言語であり、そのままでは人間に理解できる代物ではありません。例えば、胃ガン細胞と正常細胞との間で数千に及ぶ遺伝子に関して発現の有無を比較した研究によると、10個ほどの遺伝子に関して発現パターンが逆になる傾向が強いことが判明していますが、それが何を意味するかは、今後の研究に委ねられています。
バイオインフォマティクスの研究をいくら積み重ねても、なかなか生物個体の理解には到達できないので、もう少し間接的な手法が用いられることもあります。良く利用されるのが、遺伝子操作によって特定の遺伝子が機能しなくなったノックアウト・マウスで、その発育過程や形態異常などを観察することによって、当該遺伝子の“機能”がある程度は推定できます。また、特定の表現形質を持つグループとそうでないグループの遺伝子検査を行い、この形質と相関を持つ遺伝子を探索することもあります。ただし、こうした研究でわかるのは、あくまでルーズな相関であって、「この遺伝子の働きはこうだ」と直截的に表現することは一般に不適切です。実際にあった研究報告に、「第6染色体にあるIGF2Rの遺伝子型とIQの間に相関があり、遺伝子型が5型の人はIQが高くなる傾向にある」というものがありますが、これを「知能の遺伝子が見つかった」と言ってしまうと、大きな誤りを犯したことになります。
【Q&A目次に戻る】

「人間原理」とは、もともとは、宇宙モデルを構想する際にアインシュタインが採用した「宇宙原理(cosmological principle)」のアンチテーゼとなるものです。“地動説の宇宙版”とでも言うべき「宇宙原理」では、「宇宙は全体としてほぼ一様であり、人間がいる場所は(宇宙の中心のような)特別な地点ではない」と主張されています。これに対して、「人間原理」では、「人間がいるのは、生命が発生しやすい特異な場所だ」とされており、(大局的な視座から世界を見ている「宇宙原理」とは矛盾しないものの)宇宙における人間の位置づけを改めるものです。
こうした「人間原理」が問題なく適用できるのは、母集団が充分に大きい場合です。例えば、1つの惑星としての地球は、(1)水という電気モーメントが異常に大きい物質を地表面に大量に蓄えている、(2)全球の平均気温が水の融点と沸点の間にある、(3)地軸が適度に傾いているために穏やかな季節変動がある──などの著しい特徴を有していますが、これは、偶然の出来事ではなく、1000億もの恒星を有する銀河系が少なくとも100億以上はあるというこの大宇宙の中で、こうした条件を満たす惑星に知的生命が発生する確率が相対的に高いという事情に由来しています。
ところが、カーターの提唱した「強い人間原理」の議論では、しばしば、母集団の推定ができない領域にまで適用範囲が拡張されています。こうした拡張が行われるのは、現代科学が中途半端に発展し、「
この宇宙」とは異なる宇宙について具体的に論じることが可能になりながら、なぜ「
この宇宙」なのかが説明できないという苛立たしい状況があるからだと思われます。一般相対論を使えば、空間が100次元であろうと1000次元であろうと、理論的なモデルを構築することは簡単です。しかし、「それでは現実の宇宙空間はなぜ3次元なのか?」と問われても、まともには答えられません。敢えて答えようとしたとき、すがるべきワラとして「人間原理」が持ち出されるのでしょう。さらに、カーター流の“半”科学的な議論に乗っかる形で、一知半解な哲学者が“非”科学的な主張をしたため、「人間原理」という用語の意味するところすら混乱しているようです。
ここでは、“半”科学的な「人間原理」に限定して、いくつかの応用例の妥当性を簡単に見ていきます:
- 空間の次元数 : 宇宙空間が3次元である理由は、いまだわかっていません。あらゆる自然現象を説明する有力な理論として期待されているM理論によれば、空間はもともと10次元であり、そこから(ダイナミクスのよくわかっていない)コンパクト化と呼ばれるプロセスによっていくつかの次元が小さく潰れてしまうと考えられています(Dブレインと呼ばれる特殊な膜を持ち出す説明もあります)。この理論が正当だとすると、(8次元が潰れた)2次元空間や(3次元だけ潰れた)7次元空間の宇宙も存在し得るはずですが、こうした宇宙には知的生命は発生しにくいと考えられるため、「この宇宙」が3次元であるのは、ごく自然だということになります。しかし、M理論はまだ完成にはほど遠い状態であり、「潰れやすい次元数があるか」という基本的なことすらわかっていません。現時点では、「人間原理」を持ち出す前に、M理論のダイナミクスを明らかにするのが先決課題でしょう。また、M理論のようにもともとの次元数を限定する理論を援用しない場合は、原理的に無限次元まで許されるので「3次元空間」が実現される確率はゼロになり、「人間原理」を使うことはできません。
- 宇宙の一様性 : ビッグバン直後の宇宙では物質やエネルギーの分布がほぼ均一で、ブラックホールもほとんど存在していなかったと考えられています。こうした初期の一様性が過去と未来を区別する「時間の矢」の起源になっていることは、先見的な科学者によって早くから指摘されていますが、なぜ宇宙の始まりがかくも一様だったのか、理由は謎のままです(インフレーション理論でも完全には解決されていません)。ホーキングは、一つの解答として、一様でない宇宙は、ビッグバン直後にすぐに潰れてしまうため、内部にその宇宙を観測する生命が発生できないからだという「人間原理」に則った説明法を編み出しました。ただし、物質の偏った宇宙がどのような頻度で出現するかという母集団に関する分布則を提示できなかったので、説得力はあまりないと言わざるを得ません。
- 素粒子の種類/物理定数の値 : 電子やクォークなど低エネルギー領域で観測される素粒子の種類や、微細構造定数(=1/137.036…)・陽子と電子の質量比(=1836.1…)といった物理定数は、かなりの程度まで、宇宙初期における相転移の仕方に左右されています。従って、マザーユニバースから多数の宇宙が発生するという(一部の宇宙物理学者が主張する)多重発生仮説が正しいとすると、これらは個々の宇宙で大きく異なっている可能性もあり、内部の知的生命によって観測される宇宙は、素粒子の種類や物理定数の値が生命発生に好都合な範囲にあるものだけという「人間原理」が妥当することになります。もっとも、「宇宙の多重発生」という仮説はいまだ定説にはなっていません(そもそもマザーユニバースはなぜしかじかの性質を持っているかわからない)し、相転移に依存しない部分もかなりあるため、定量的な議論を進めることは困難です。
- 生命の存在可能期間 : 現在、宇宙が開闢してからたったの100億年しか経っておらず、熱死を迎えるまで1030〜1040年はあるとされる全寿命を考えると、人間は、まさにビッグバン直後に生きていることになります。これは(おそらく)偶然によるものではなく、宇宙に生命が満ち溢れているのは、若い恒星が短波長光を放ってエントロピーが急増する最初の一瞬だけで、あと数千億年も経つと、中性子星やブラックホールが支配する“生命の存在しにくい世界”になってしまうからだと推測されます。この例は、宇宙論に「人間原理」が適用できる数少ないケースの1つです。
科学者が承認するような「人間原理」は、「知的生命が存在する理由」を積極的に説明するものではなく、「生命が発生しにくい世界ではない」ことをかろうじて理由づけるものでしかありません。実際、知的生命の存在理由を「人間原理」に求めるのは、無理があります。詳しくは説明しませんが、私の考えによると、知的生命が意識を持っているのは、高次元状態空間において強い相関を持つ量子論的な状態が実現されているからです。従って、意識を持った知的生命が存在する上で鍵となるのは、その世界で量子論が成り立つかどうかのはずです。ところが、現代科学では、量子論以外の基本法則に従う世界を想定していません。母集団の中に量子論の妥当しない宇宙が含まれていない以上、「
この宇宙」が「人間のような知的生命の存在を許す特殊な宇宙」であると積極的に主張するのはあまり意味がないでしょう。
残念ながら人間は、「この宇宙になぜ知的生命が存在するか」という問いに答えるだけの知的段階には達していないようです。しかし、答えてみたいという知的欲求を押し殺すことはできませんし、敢えて答えようとするチャレンジも必要なのかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

ガソリンには数百の成分が含まれており、その割合は製法によって大きく異なりますが、大半が炭化水素(炭素と水素から成る化合物)であり、アルコール(炭化水素の水素原子を水酸基OHで置換したもの)はほとんど含まれていません。原油を蒸留して得られる直留ガソリンにはパラフィン(一般式C
nH
2n+2を持つ飽和鎖式炭化水素)が、また、蒸留の残りを接触分解法でガソリン化した接触分解ガソリンにはオレフィン(一般式C
nH
2nで表され二重結合を1つ持つ不飽和鎖式炭化水素)が多く含まれています。
あまり一般的ではありませんが、アンチノック剤としてガソリンにブチルアルコールを数%ブレンドすることもあります。また、第二次大戦前には、石油の節約と余剰アルコールの消費のために、ガソリンに5〜6%のアルコールを混ぜたGasoholが使われたこともあるそうです。
(それにしても、意表を付かれた質問でした)
【Q&A目次に戻る】

物質をシュヴァルツシルト半径より小さな領域に閉じこめると、重力崩壊を起こしてブラックホールになることが知られていますが、これは、あくまで天体のような孤立した物質の場合です。ビッグバンの直後には、宇宙全体を物質と放射がほぼ一様に満たしており、ある領域の物質には、収縮しようとする自身の重力の他に、周囲の物質から引っ張る力も作用します。この2つの力がうまく均衡してくれれば、部分的な重力崩壊を起こすことはありません。
ただし、2つの力が均衡するのは、物質やエネルギーが一様に分布している場合に限ります。ビッグバン直後の物質分布に大きな揺らぎがあり、特定領域の密度が周囲より高くなっていると、その部分の物質だけが急速に凝集してブラックホールを形成してしまいます。宇宙史初期にブラックホールが数多く形成されたとしても、ブラックホールの分布がほぼ一様ならば宇宙全体が膨張することは可能ですが、多数の超巨大ブラックホールが支配する宇宙では、恒星系が誕生して惑星上で生命が発生する確率は絶望的なまでに低くなります。また、物質分布が宇宙全体にわたって偏っている場合は、膨張せずにすぐに潰れてしまうのが一般的です。
宇宙の初期に物質やエネルギーの分布がきわめて高い一様性を持っている理由は、よくわかっていません。宇宙の“種”は無数に存在し、その中で物質分布が一様な宇宙だけがうまく膨張して生命を宿すことになるという説もありますが、あまり説得力があるとは思えません。この問題は、宇宙論における最大の謎の一つであり、いまだに解決されていないので、一般人向けの解説書にはあえて書かないのでしょう。
【Q&A目次に戻る】

この現象には、いくつかの要因が絡んでいます。
まず、泥の抵抗が大きいことが挙げられます(このほかにも、泥には密度が大きいという特徴がありますが、これは大きな浮力を生んで長靴を抜けやすくするので、ここでは関係ありません)。希薄溶液の場合は、アインシュタインの粘性法則:
μ = μ
0(1 + 2.5C)
(μ
0:溶媒の粘性率、C:容積濃度)
が成立し、溶媒の粘性率に小さな変化項を加えた値になりますが、泥のように粘土やコロイド分を多量に含有する溶液では、粒子間の結合力により、溶媒に比べて粘性がきわめて高くなります。こうした物質の性質を定量的に議論するには、通常の流体力学は使えず、レオロジーと呼ばれる分野の知識が必要になりますが、ここでは、専門的な議論は避けて、あくまで定性的な見積もりをすることにします。
粘性率μの通常の流体では、半径rの球を速さvで動かすときの抵抗Dが、
D = 6πμrv
で与えられます(ストークスの法則)。泥の場合、この公式はそのままの形では成り立ちませんが、定性的な振舞いは共通しています。すなわち、粘性の高い(μが大きい)泥の中で、長靴のような比較的大きな(rが大きい)物体を、慌てて(大きなvで)動かそうとすると、非常に大きな抵抗が生じるのです。長靴が抜けなくなるのは、主にこのためです。
このほかにも、長靴を引き抜くための力を加えにくいという事情があります。泥の上に足を下ろした場合、それとは意識せずに数十kgWの体重を加えるために、長靴は泥の中に簡単にめり込みます。しかし、これを引き抜こうとしても、同じ大きさの上向きの力を加えるのは容易なことではありません。もう片方の足も泥の上にあるときには、足場が不安定なため、なかなか踏ん張ることができません。また、人間の足は、前進するために後ろに蹴る力が強く出るように腿やふくらはぎに筋肉が付いていますが、前に持ち上げる筋肉はあまり強くありません。しかも、抵抗を減らそうと足先を下に向けるようにすると、長靴を泥の中に残して足だけがスポンと抜けてしまうので、足先が下がらないように持ち上げなければなりません。これは、ふだん使わない筋肉を働かせることになり、かなり苦しい体勢です。こうした要因が重なって、大きな抵抗に逆らって長靴を引き抜くのが困難になるのです。
【Q&A目次に戻る】

n型半導体において、一定の外部電場
Eを加えたときの電子の古典的な運動方程式は、
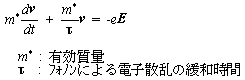
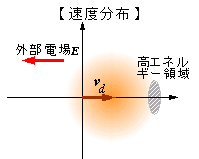
となり、外部電場がないときに比べて、速度が
vd = -
eEτ/
m*
だけシフトした方程式に従っていることがわかります。外部電場が弱いときには、速度の統計分布を考えたときにも同様で、電場がないときのマクスウェル−ボルツマン分布から
vdだけシフトした速度分布になり、平均速度(=ドリフト速度)は
vdとなります(右図;概略図です)。
vdの形からわかるように、緩和時間が定数ならば、ドリフト速度は外部電場に比例します。
外部電場を強くすると、速度分布のテール部分により大きな運動エネルギーを持つ電子が現れるようになりますが、こうした高エネルギー電子とフォノンの相互作用は、低エネルギー電子とは異なっています。低エネルギー電子は、主に音響フォノン(隣り合う格子点が同位相で振動するフォノン)によって弾性散乱され、(速度をシフトして評価した)運動エネルギーは散逸されません。これに対して、高エネルギー電子は光学フォノン(隣り合う格子点が逆位相で振動するフォノン)によって非弾性的に散乱されます。この結果、速度分布の高エネルギー領域に含まれる電子は、エネルギーを失って低エネルギー領域に遷移することになります。こうしたエネルギー散逸の効果によって、外部電場をある臨界値以上に強くしても、速度分布はそれ以上シフトせずに、ドリフト速度が“飽和”するわけです。
ドリフト速度が飽和する場合でも、
vd = -
eEτ/
m*
という関係は形式的に成り立ちますが、電場が強いほど高エネルギーまで加速される電子が増え、それとともに光学フォノンによる散乱も増加するので、(光学フォノンとの相互作用における)緩和時間τは
Eに反比例する形で減少します。飽和ドリフト速度の大きさは、外部電場が供給するエネルギー
eEv
dと、光学フォノンとの散乱で失われるエネルギーを等しいと置くことによって評価できます。後者は、光学フォノンのエネルギーを
Koとすると、
Ko/τ
のオーダーになります。従って、先のv
dの式と比較することにより、
v
d〜(
Ko/
m*)
1/2
が得られます。この結果には、(もはや定数ではない)τは含まれていません。多くのn型半導体では、
Ko〜40meV
m*〜0.1
me
となるので、この数値をv
dに代入すると、
v
d〜10
7[cm/s]
が得られます。
(【参考文献】『半導体の基礎』(P.Y.ユー/M.カルドナ著、シュプリンガー))
【Q&A目次に戻る】

標語的に言えば、ネクローシスは細胞の事故死、アポトーシスは自殺となるでしょう。
ネクローシス(壊死)は、細胞が傷害を受けたことによって引き起こされる受動的な死です。その原因には、動脈の血流停止による酸素不足、熱・放射線などによる物理的傷害、細胞毒性を持つ化学物質の作用、溶解性ウイルス感染、免疫系からの攻撃(補体攻撃)などがあります。ネクローシスは、傷害を受けた組織内で一斉に発現し、非可逆的に進行していきます。
ネクローシスにおける細胞の変化は、細胞質内の小器官、特に、ミトコンドリアや小胞体から始まります。ミトコンドリアの場合、まず形態的に膨大化し、リン酸カルシウムが沈着して、エネルギーの元になるATPを充分に作り出せなくなります。この結果、ATPを使って能動的に細胞膜内外のイオン濃度を調整していた輸送システムが崩壊、浸透圧を制御することが困難になり、Na
+や水が流入して細胞が膨潤し最終的には溶解を起こします。この過程で、細胞核は膨潤しますが、アポトーシスとは異なり、クロマチン(タンパク質と会合しているDNA)の大きな変化は見られません。
細胞が溶解すると、細胞の内容物が流出します。すると、そこに含まれる誘因物質に惹かれて、近くの血管からマクロファージなどの白血球が浸潤し、傷ついた組織を貪食し始めます。これは、傷ついた組織を取り除いて新しく作り直すための作業ですが、この過程で分泌されるサイトカインなどの作用によって炎症反応が引き起こされ、周辺の正常細胞を傷つけることもあります。また、壊死した細胞内部から流出するタンパク質分解酵素も、周辺細胞に悪影響を及ぼします。
上に述べたのは典型的なネクローシスのケースであり、実際には、さまざまなパターンがあります。例えば、心筋梗塞の場合には、細胞の外形が保たれる凝固性壊死を示すことが多いのに対して、脳梗塞では、壊死した組織が溶融してドロドロになってしまいます。また、糖尿病の患者では、足指の先端などで虚血と感染が重なって、壊疽性の壊死が見られることがあります。
ネクローシスが受動的な細胞死であるのに対して、アポトーシスは、遺伝子によって制御された能動的な細胞死です。ここでは、ネクローシスと対比する形で、その特徴を表にまとめておきます:
| アポトーシス | ネクローシス |
| 範囲 | 個々の細胞 | 周辺組織まで含む |
| 引き金 | 細胞内外からのシグナル・傷害 | 傷害 |
| 最初の変化 | 細胞サイズの縮小 | 細胞内器官の機能不全 |
| 細胞サイズ | 縮小 | 膨潤 |
| 水分 | 流出 | 流入 |
| 細胞質 | 小胞形成 | − |
| 細胞核 | 凝縮 | 膨潤 |
| クロマチン | 凝集・断片化 | − |
| ミトコンドリア | 膜透過性の増大・内容物の放出 | 膨大化 |
| 細胞膜 | 微絨毛の消失 | − |
| 最終段階 | アポトーシス小体に断片化 | 細胞溶解 |
| 死後の処理 | 近隣細胞による貪食 | マクロファージによる貪食 |
| 炎症の有無 | なし | あり |
アポトーシス・ネクローシスいずれに関しても、近年、数多くの専門書が出版されていますので、詳しくは、そちらをご覧ください。
【Q&A目次に戻る】

この問いは、歴史的には、「宇宙は(明るいはずなのに)なぜ明るくないのか」というオルバースのパラドクスとして知られているものです。
まず、宇宙はユークリッド空間だと仮定しましょう。この場合、ある時刻に観測点に到達するのは、r/c秒前(c:光速)にr[m]だけ離れた地点にいた恒星から発せられた光です。恒星は、観測点から見て等方的(isotropic)に分布していると仮定し、毎秒L[J]のエネルギーを放出する恒星の平均密度を
n(L,r,t) (r:観測点からの距離、t:観測時刻)
と表すことにすると、観測点からr〜r+drの距離に存在して時刻tに光を到達させた恒星の総数は、
4πr
2n(L,r,t−r/c)dr
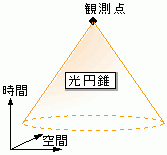
で与えられます。時刻がt−r/cで置き換わっているので、3次元空間に時間軸を加えた4次元で見ると、観測点を頂点とする過去に開いた4次元光円錐の表面にある恒星から光がやってくることになります。エネルギーは(特殊な例外を除いて)等方的に放射されると考えられるので、観測点に到達する光のエネルギーは、恒星1個につき、単位面積あたり単位時間に
L/4πr
2
となります。従って、任意の距離にある恒星からから観測点に送られた光の全エネルギーは、
∫dr L・n(L,r,t−r/c)
です。積分領域が無限大で、かつrが大きい地点でnがゼロになる(あるいは、充分に速くゼロに漸近する)ことがなければ、到達する光のエネルギーは無限大になってしまいます。これでは、空全体がギラギラと明るく輝く(どころか無限大のエネルギーで焼き殺されてしまう)はずです。
恒星と観測点の間に光を吸収する物質があったとしても、本質的な変化はありません。この場合は、物質が光を吸収して高温になり、放射の法則(空洞放射に対するプランクの放射法則など)に従って光を発し始めます。このため、光のスペクトルはずれますが、観測点に達する放射エネルギーが無限大になるという点は同じです。
この問題に最初に気がついたのは、惑星運動の法則で知られるケプラーだと言われています。彼は、宇宙空間が有限である(すなわち、rの範囲はある値以下に限られる)と仮定することによって、この謎は解決できると考えたようです。
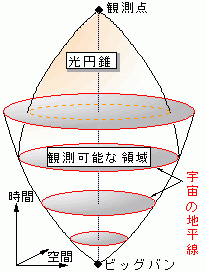
現在では、ビッグバン宇宙論に基づいて解決を図るのが一般的です。この理論によれば、宇宙は約150億年前に生まれて、今なお急激な膨張を続けているとされます。膨張による相対速度は、観測点からの距離rに(ほぼ)比例しており、相対速度が光速になる地点は、それ以遠の領域とはいかなる方法をもってしても交信できない(従って、そこから光もやって来ない)「宇宙の地平線」となります(相対速度が光速になるといっても、同じ点ですれ違うわけではないので、相対論とは矛盾しません)。全宇宙の大きさは無限大かもしれませんが、観測点にやってくる光は、宇宙の地平線よりも内側の領域(観測可能な領域)からやってくるものに限られます(右図)。
宇宙の地平線は、ビッグバン直後は観測点の近くにありましたが、その後は光速で遠ざかっています。従って、ある時刻に観測点に到達する光は、観測点を頂点とする過去に開いた光円錐の表面にあって、宇宙の地平線と交わる手前の領域に存在する恒星が発したものに限られます
(*)。この条件を満たす恒星の数は、全天を明るく照らすほど多くはないので、宇宙は暗くなってしまうのです。
(*)空間が膨張しているので、光円錐は幾何学的な4次元の円錐ではなく、時間方向に丸みを帯びた曲面になります(図はかなり杜撰に描いています)。また、厳密に言えば、宇宙の地平線とは交わらずに漸近する曲面になりますが、地平線近傍からの光は観測点にはほとんど到達しないので、地平線から離れた地点での曲面をそのまま延長して考えてもかまいません。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
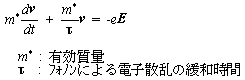
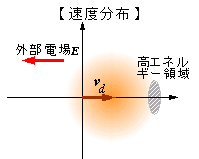 となり、外部電場がないときに比べて、速度が
となり、外部電場がないときに比べて、速度が
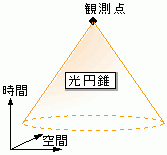 で与えられます。時刻がt−r/cで置き換わっているので、3次元空間に時間軸を加えた4次元で見ると、観測点を頂点とする過去に開いた4次元光円錐の表面にある恒星から光がやってくることになります。エネルギーは(特殊な例外を除いて)等方的に放射されると考えられるので、観測点に到達する光のエネルギーは、恒星1個につき、単位面積あたり単位時間に
で与えられます。時刻がt−r/cで置き換わっているので、3次元空間に時間軸を加えた4次元で見ると、観測点を頂点とする過去に開いた4次元光円錐の表面にある恒星から光がやってくることになります。エネルギーは(特殊な例外を除いて)等方的に放射されると考えられるので、観測点に到達する光のエネルギーは、恒星1個につき、単位面積あたり単位時間に
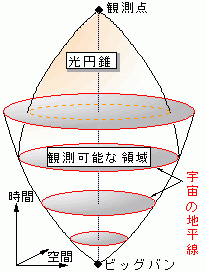 現在では、ビッグバン宇宙論に基づいて解決を図るのが一般的です。この理論によれば、宇宙は約150億年前に生まれて、今なお急激な膨張を続けているとされます。膨張による相対速度は、観測点からの距離rに(ほぼ)比例しており、相対速度が光速になる地点は、それ以遠の領域とはいかなる方法をもってしても交信できない(従って、そこから光もやって来ない)「宇宙の地平線」となります(相対速度が光速になるといっても、同じ点ですれ違うわけではないので、相対論とは矛盾しません)。全宇宙の大きさは無限大かもしれませんが、観測点にやってくる光は、宇宙の地平線よりも内側の領域(観測可能な領域)からやってくるものに限られます(右図)。
現在では、ビッグバン宇宙論に基づいて解決を図るのが一般的です。この理論によれば、宇宙は約150億年前に生まれて、今なお急激な膨張を続けているとされます。膨張による相対速度は、観測点からの距離rに(ほぼ)比例しており、相対速度が光速になる地点は、それ以遠の領域とはいかなる方法をもってしても交信できない(従って、そこから光もやって来ない)「宇宙の地平線」となります(相対速度が光速になるといっても、同じ点ですれ違うわけではないので、相対論とは矛盾しません)。全宇宙の大きさは無限大かもしれませんが、観測点にやってくる光は、宇宙の地平線よりも内側の領域(観測可能な領域)からやってくるものに限られます(右図)。