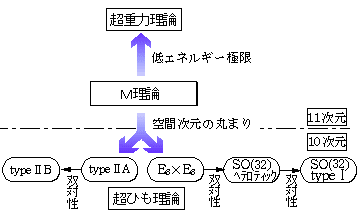現在、標準的とされている宇宙模型は、「ビッグバン/インフレーション模型」です。約150億年前に高温・高圧状態の宇宙が誕生し、10
-30秒ほどの短いインフレーション期(宇宙全体が指数関数的に急膨張する時期)を経て、平坦なフリードマン宇宙に近い現在の状態になったというものですが、この標準模型には、次のような欠点があります:
- 宇宙全体の振舞いを記述するアインシュタイン方程式を使ってビッグバンの瞬間にまで遡ると、温度・圧力が無限大になって物理法則が破綻してしまう(特異点問題)。
- インフレーション理論の予想に反して、
(1)物質密度が臨界値の1/3程度しかない
(2)膨張が加速している
という観測データが得られている。
"Cyclic Universe" 仮説は、こうした問題点を克服するものとして、P.J.Steinhardt と N.Turok によって提唱されました。この仮説がベースにしているのは、M理論と呼ばれる基本的な理論で、われわれが観測しているこの宇宙は、10次元空間に存在する3次元の“膜”だというものです(M理論についての簡単な解説は、
別の項目にあります)。通常は、10次元空間の6つの次元は小さく丸まっていると仮定されますが、たとえ膜の外に巨視的な拡がりがあったとしても、膜の励起状態として定義される物質粒子は、この膜から離れられないため、膜上に住んでいる知的生物は膜の外を観測する方法がなく、この3次元膜を唯一の世界と感じるはずです。"Cyclic Universe" 仮説では、M理論の低エネルギー近似として、4次元空間に3次元の膜が浮かんでいる状況を想定し、(それ自体が1つの宇宙であるような)2つの膜が相互作用する過程が考察されています。
"Cyclic Universe" に先立つ仮説として Steinhardt らが提唱したのが、"Ekpyrotic Universe" というアイデアです(ekpyrosis とは、世界の破滅と再生をもたらす劫火のことです)。基底状態にある膜は、エネルギーのない宇宙、すなわち、空っぽのミンコフスキ時空になっていますが、"Ekpyrotic Universe" 仮説では、この状態にある2つの膜が衝突、膜全体の運動エネルギーが膜内部のエネルギーに転換され、高温・高圧のビッグバン状態となって膨張し始めるとされています。もともと平坦なミンコフスキ時空だったものが外部からエネルギーを得て膨張を開始するため、標準模型と異なって、物質密度が臨界値より小さくても宇宙は平坦になるというわけで、観測データとうまく合致しています。
"Cyclic Universe" 仮説は、"Ekpyrotic Universe" 仮説を発展させたもので、2つの膜の間に間隔パラメータφ(衝突するときにはφ→−∞)の関数として表されるポテンシャルエネルギーV(φ)があると仮定し、その作用によって、膜同士が近づいては衝突し、跳ね返ってはまた近づき始めるという運動を無限に繰り返すと主張するものです。膜が跳ね返って少し経つと、φがある臨界値を超えてV(φ)が正値になり、その作用は「暗黒エネルギー」として膜宇宙の加速膨張を引き起こします。著者たちによれば、この加速膨張の期間に膜宇宙は再び物質の存在しない空っぽで滑らかな状態に戻り、宇宙全体がリフレッシュされるということです。その後、φは最大値に達してから減少し始めます。φが臨界値を下回ったところでV(φ)が負になって宇宙は減速膨張に、さらには収縮に転じ、ついにはφ→−∞の再衝突(ビッグクランチ)に至ります。
ここで興味深いのは、膜同士が衝突する過程で、特異点が現れないという点です。膜同士の相互作用を考慮すると、物質と重力場の結合項にβ(φ)
2という係数が掛かることになります。標準模型では、物質密度をρ、宇宙の大きさを表すスケール因子をaと表すと、物質の運動方程式は、

となり、a→0 のとき ρ∝a
-3 となって、密度無限大の特異点が生じます。ところが、βを含んだ方程式は、上の式でaがa'=aβで置き換わった形になることが導かれます。ここで、a→0 ,φ→−∞ のときβがうまい具合に無限大になってくれると、a'は有限の値に留まり、密度ρも発散することはありません。こうして、物理法則を破綻させずに「ビッグクランチ→ビッグバン」の過程を記述することができるのです。
このように、"Cyclic Universe" 仮説は、特異点問題を回避し、インフレーション模型では説明できない観測データとも合致させられるという長所を持っています………がしかし、だからと言って、宇宙論研究者が諸手を挙げて賛成しているかというと、そうではありません。この仮説は、さまざまな欠点を抱えているのです。
まず指摘できるのが、多くのアド=ホックな仮定を積み重ねているという点です。宇宙が周期的になるためには、ポテンシャルV(φ)が特定の形をしていなければなりませんが、それがM理論から演繹的に導かれるというわけではありません。M理論は数学的にきわめて難しいため、いくつかの簡単なモデルをもとに、φ→−∞での漸近的な振舞いを調べる程度のことしかできません。むしろ、「周期解が存在するように」V(φ)の形を決めているというのが、本当のところです。膜の衝突過程においても、さまざまな仮定を置いて周期性が壊れないようにしています。M理論から自然に周期的な解が導けることが示されて、初めて仮説に信憑性が生まれると言えるでしょう。
宇宙のエントロピーに関する議論も、あまり納得できません。宇宙におけるエントロピーの溜まり場はブラックホールであり、「ビッグバン直後にブラックホールが少ない」という事実が、「宇宙はビッグバンで始まる」という熱力学的な時間の向きを決定しています。エントロピー増大の法則が確かならば、ビッグバンがビッグクランチに引き続いて実現されるはずがないのです。"Cyclic Universe" 仮説では、エントロピー増大の法則に従ってブラックホールが形成されていくものの、加速膨張期にブラックホールの密度が充分に低くなるため、収縮後もエントロピーの小さい滑らかな状態に落ち着くとされていますが、これは、言うなれば、膜にブラックホールの傷がたくさん付いても、いくらでも引き延ばして「傷のほとんどない状態」に戻せるというもので、手品師に騙されたような印象を受けます。膜の大きさが無限大であることと、膜が膨張した分だけ物理的自由度が増えていくことを利用した数学的なトリックであり、M理論の熱力学が完成された暁に再考すべき点だと思われます。
何よりも問題なのは、そもそもM理論が科学者の信頼を獲得していないという点です。これを熱狂的に支持する物理学者のグループ(それも有能な人ばかり)がいるのは事実ですが、彼らの莫大な努力をもってしても、実験や観測のデータを定量的に再現することはおろか、「もともとの空間が10次元なのに、この世界はなぜ3次元なのか」といった基本的なことすら説明できていません。M理論を応用したとされる研究も、単純化したモデルで大ざっぱな議論を行うものが大半で、定量的な検証にはほど遠い状況です。私を含む多くの科学者にとって、M理論はまだ「突飛なアイデア」ないし「物理学者のおもちゃ」の域を出ておらず、もう少し“物証”が集まるまでは、眉に唾を付けて様子見を決め込みたいところです。
【Q&A目次に戻る】

物理的システムにおいて“自発的”とか“自律的”と言う場合は、問題としている過程が外部からの強制的な作用によって実現されたのではないことを意味しています。「自発磁化」を例にとって説明しましょう。

鉄のような強磁性体を冷却していくと、ある温度T
c(キュリー温度)以下になったとき、外部から磁場を加えなくても磁化が生じるようになります。これは、量子力学的な相互作用によって、隣り合う原子の持つ磁気モーメントが同じ向きに揃う方がエネルギーが低くなるためで、温度が高いときは熱による擾乱のせいで磁気モーメントはバラバラの方向を向いていますが、温度がT
c以下になると、磁気モーメント間の相互作用が熱の擾乱作用を上回ってモーメントが同じ向きに整列するわけです。ただし、「磁気モーメントが整列する」ことはわかっても、外部磁場がないときには、「どの向きに整列するか」をあらかじめ知ることは困難です。温度分布や個々のモーメントの状態に応じて、さまざまな向きに磁化が生じることになります。外部から磁化の向きを強制されていないので、「自発磁化」と呼ばれるのです。
“自発的”な過程では途中の状態を完全に記述できないのに対して、“自律的”なシステムでは、変数の時間的変化を方程式の解として表すことが可能になります。一般に、あるシステムが“自律的”であるとは、系の状態を与える内部変数{q
i}の変化が、外部状態に依存しない関数F
iによって決定される、すなわち、
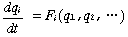
と書かれることを意味します。例えば、神経興奮の大まかな過程を記述するホジキン・ハックスリ方程式は、イオンチャネルの活性度や溶液中のイオン濃度を変数とする自律系の方程式となっています。つまり、神経細胞は、コンピュータ内部の半導体素子のように外部電源によって電気的状態を強制的に決定されるのではなく、膜電位がある臨界値に達すると自律的に興奮する能動的素子なのです。
物理学で“自”の付くさまざまな理論(自発的対称性の破れ、自励振動、自律的形態形成など)が発展するのは1960年代に入ってからであり、比較的新しい分野なので馴染みが薄いかもしれませんが、脳を含む複雑系の振舞いを解明する上で不可欠であると考えられています。
ただし、慎重な科学者は、“自発的”ないし“自律的”な物理過程が“自覚的”な意識と結び付いていると(露骨に)主張することはありません。その部分は、私の憶測です。
【Q&A目次に戻る】
 自分が時間や量子論について興味をもつようになった「ホ−キング、未来を語る」という本によれば、近い将来(今世紀中にも)、コンピュ−タが人間の脳と同じくらいの大規模並列処理ができるようになるとか…
自分が時間や量子論について興味をもつようになった「ホ−キング、未来を語る」という本によれば、近い将来(今世紀中にも)、コンピュ−タが人間の脳と同じくらいの大規模並列処理ができるようになるとか…
そこで質問です。
- そうなると、コンピュ−タにも、感情や欲望が生まれるのでしょうか?
- 元々、その感情や欲望が発生するメカニズムはどこから来てるんでしょう? 単純に、脳の処理のメカニズムとは関係ないのでしょうか?
- もし、そういったコンピュ−タが実現できたとして、(例えば、自分の意志で自分の複製を作ったり、自己修復するなど)悪い感情まで抑えきれるのでしょうか? ある人が言ってた「コンピュ−タは人間に危害を加えてはいけない!」と、そこまで都合よく感情をコントロ−ルできるのでしょうか? 感情をもつ=人間を滅ぼそうと思う・支配しようと思う意識も生まれる可能性があるのでは!?
- そこまで技術が進むと、将来的には、人間の脳を完全にコンピュ−タに移植できるのでは!? そうなると、永久に生き続ける(?)みたいな事が可能となるのでしょうか? 生きる定義が変わる時代が来るのでしょうか? 体自体は、何ら意味をもたなくなるというか、「コンピュ−タの中で生きてる人」みたいな事があり得るのでしょうか? もちろん、これは倫理的な問題はあるでしょうね。【その他】

こんにち利用されているノイマン型コンピュータは、人間の脳とは決定的な相違があります。それは、脳が神経系の自律的な協同現象を通じて機能しているのに対して、コンピュータは、常に“外部から”駆動されているという点です。脳の場合、プログラムに相当するのは、シナプス結合を通じて形成される神経細胞のネットワークであり、入力される刺激の頻度や神経興奮のパターンに応じて自律的に再編されていきます。ところが、コンピュータは、“外部で”作成されたプログラムの指示通りに処理を行うしか能がありません。また、神経細胞での信号伝達が、「膜電位の変化に誘起された自励発振」という自律的な現象であるのに対して、コンピュータにおいては、外部電源によって電荷移動が行われているだけです。既定のハードウェアの上で入力されたプログラムに従って動いているコンピュータが、人間と同じような能力を持つとは、とうてい考えられません。
「コンピュータが脳と同じような処理を行う」とは、あくまで、脳が行っている処理を明確に定義できるいくつかのプロセスに分割し、各プロセスをコンピュータによってシミュレートさせるという意味です。認知心理学の進歩によって、脳が行っている情報処理の一部は、単純なプロセスの組み合わせに還元できることが明らかになってきました。例えば、人間が「顔を見て誰だか判断する」際には、顔の輪郭やパーツの部分的な特徴を抽出して個別にパターン・マッチングを行っていることが知られています。こうした知見を利用すれば、CCDカメラの“眼”を使って人の顔を見分けるコンピュータを作成することは、それほど難しくはないでしょう。しかし、シミュレーションの結果が脳と同じだったとしても、コンピュータ内部で行われていることは、人が鈴木さんの顔を見て「あ!鈴木さんだ」と感じる過程とは、ずいぶん異なっているはずです。
ペットロボットのAIBOやゲームの「シーマン」の例が示しているように、コンピュータがあたかも感情や欲望を持っているかのようにプログラムすることは、技術的に可能です。人間が心地よいと感じるのが 1/f 揺らぎを持つ音であることを利用して、モーツァルトの音楽に「良い曲だ」と反応し、ガラスを爪でひっかく音に顔をしかめるロボットを作ることは、それほど難しくないでしょう。また、プログラムのあちこちに、発生させた乱数の値に応じて分岐先を変えるような条件分岐を挿入しておけば、コンピュータがいかにも気まぐれに振舞っているように見えるはずです。しかし、これは、あくまでシミュレーションであって、感情や欲望そのものではありません。
自発的な感情や欲望の源泉は、おそらく脳における自律的な協同現象です。読み込んだプログラム通りに動くのではなく、状況に応じて“配線”そのものを自律的に変化させるようなハードウェアが制作できれば、自覚的な意識や感情・欲望を持つコンピュータが実現できる可能性があります。しかし、こうした技術は、シリコンデバイスを用いる現在のエレクトロニクスの延長線上にはないでしょう。考えられるのは、バイオテクノロジーを駆使して、シリコンではなく生体物質から成る人工の脳を作ってしまう方法です。こうした人工脳を脳梁を介して人間脳と接続すると、2つの脳にまたがる意識が生まれるかもしれません。しかし、こうした技術が現実のものとなるのは、早くとも来世紀以降でしょう。
【Q&A目次に戻る】

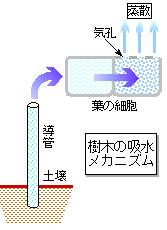
樹木の吸水メカニズムはかなり複雑ですが、ここでは単純化して、湿潤土壌に水を通す細い管(導管)が突き刺さっているものとして考えます。導管内部の水に加わる単位面積あたりの重力は、水柱1mにつき約10
4[N/m
2] = 0.1bar なので、導管の上部を真空にして大気圧(〜1bar)で水を押し上げても、せいぜい10mまでしか上がりません。また、毛管現象(管の内側に付着した薄膜の表面張力によって水が引き上げられる現象)の効果も限られています。数十mの巨木の先端にまで水が行き届くのは、実は、水柱の上端に位置する葉の細胞で浸透圧に起因する張力(陰圧)が発生し、水全体を引っ張り上げているからです。言うなれば、「根が水を吸い上げている」のではなく、「葉が水を引き上げている」のです。水分子は大きな電気モーメントを持っており互いに強く引き合う性質があるため、水全体を持ち上げるほどの張力で引っ張っても、水柱が断裂することはまずありません。
導管内の水に働く張力は、一般的には数bar〜十数bar、最大で 30bar 以上になります。従って、重力(1m当たり0.1bar)との釣り合いだけを考えれば、高さ300mを越す樹木も可能なはずですが、世界で最も高い樹木は、せいぜい120m程度に過ぎません。これは、導管表面の吸着力などによる抵抗に抗して水を引き上げるのに、かなりの力が必要となるからです。
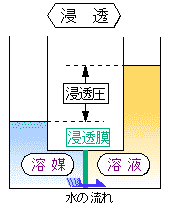
張力の源になっている浸透圧とは、溶媒(水)と溶液が浸透膜(溶媒は通すが溶質は通さない膜)を介して接しているときに生じるものです。このとき、溶液の側へと溶媒(水)が移動して最終的には平衡状態に達しますが、溶質が溶け込んでいることによる化学エネルギーの差を補償するために、圧力は等しくなりません。この圧力の差を浸透圧と言います(右図)。植物の場合、気孔から継続的に水分が蒸散していくので、水が細胞内に浸透しても平衡状態には達せず、葉の細胞はいつまでも水を引っ張り続けることになります。このとき、水の流れを生み出すエネルギー源となっているのは、蒸散を促して濃度の差を生み出すもの──すなわち、太陽光線です。
【参考文献】H.Mohr, P.Schopfer著『植物生理学』(シュプリンガー・フェアラーク東京)
【Q&A目次に戻る】

どんな原子核でも、充分に大きなエネルギーを与えることができれば、必然的に分裂します(軽い核では核破砕と呼びます)。連鎖反応を実現するためには、中性子捕獲によって核分裂を誘発しなければならないので、中性子が核分裂に必要なエネルギー──ウランでは 約6MeV──を与えられるかどうかが問題になります。ウランやプルトニウムの場合、あまり高速の中性子は捕獲できない(反応断面積が小さくすり抜けてしまう)という性質があり、連鎖反応が起きるほど高い確率で核分裂させるには、1eV 以下まで減速された中性子を用いなければなりません。ところが、こうした中性子は、運動エネルギーを核内にほとんど持ち込まないので、中性子が核内に入ったことによって解放されるエネルギー(中性子の結合エネルギー)の多寡が、核分裂の成否を決定することになります。
ここで標的核の中性子数が問題となります。重い原子核の内部では、同種の核子がペアとなって固く結合することが知られています(詳しい説明は省きますが、角運動量の特定成分を打ち消すようなペアを作ります)。これが、陽子・中性子とも偶数個の原子核(偶−偶核)が、どちらか(あるいは両方)が奇数個の原子核よりも安定な理由です。中性子が奇数個の原子核に熱中性子が捕獲されると、それまで相手のいなかった核内中性子が捕獲された中性子とペアを組んでエネルギーの低い状態に落ち込むため、ペアの結合エネルギーが原子核内部に解放されて、原子核は全体が変形するような大振幅の集団運動を始めます。この集団運動のエネルギーが核分裂のしきい値を超えるほど大きければ、原子核は分裂することになります(大きくなければ、ガンマ線などを放出して基底状態に遷移します)。
ウラン238(中性子:偶数)が熱中性子を捕獲したときに核内に解放されるエネルギーが 4.8MeV なのに対して、ウラン235(中性子:奇数)では 6.4MeV になりますが、この差は、主に、捕獲中性子が新たにペアを組むかどうかによって生じます。ウランの場合、核分裂に必要なエネルギーが約6MeV ですから、ウラン235はウラン238と違って熱中性子で核分裂させることができるわけです。ウラン238も高速の(1.2MeV以上の)中性子をヒットさせれば分裂しますが、ヒットの確率が小さいので、連鎖反応には至りません。
偶−奇核の方が偶−偶核より中性子捕獲による核分裂を起こしやすいわけは、以上のような議論で示せますが、分裂片の質量分布が非対称になる理由は、今もって完全には解明されていません。核分裂の振舞いを定性的に記述する古典的な液滴模型では、分裂は対称に生じるので、何らかの量子論的な効果が関与していることは明らかです。大ざっぱに言えば、変形中にクーロン力と表面張力が釣り合う辺りで両者の効果が相殺し、核子が安定状態を形成しようと集合する動きが核内部で不均一に見られるようになって、非対称性が成長するというわけですが、これをきちんと記述するような数学的モデルは、いまだ完成していません。
【Q&A目次に戻る】

人間の網膜には3種類の光受容タンパク質があり、それぞれ、赤・緑・青の光に最も強く反応します。「ある色が見える」とは、この3種類のタンパク質のいくつかが光を吸収して変形し、一定の刺激を視神経に伝えることに起因します。
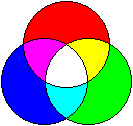
例えば、波長が550〜590nm程度の光が目に入ってきたときには、赤と緑に対応する光受容タンパク質が反応し、その結果として「黄色が見える」ことになります。このように、光受容タンパク質の反応における組み合わせが、「3原色」から構成される7色の光を決定します。
太陽光は、黄色に対応する波長で強度が最大になるスペクトル分布をしているので、その光を反射する月も、本来は黄色く見えるはずです。ところが、昼間に月を見上げたとき、目に入るのは月からの光だけではありません。大気中では太陽光の中で波長の短い青色の光が散乱され、空全体から降り注いでくるからです(これが、空が青く見える理由です)。その結果、月からの黄色と空からの青が重なって網膜に達し、3種類の光受容タンパク質が全て反応してしまうため、昼間の月は白っぽく見えるのです。
【Q&A目次に戻る】

はじめに、ハワイ大学の研究チームが「153億年前」という数値をどのようにして求めたかを、簡単に説明しておきます。
遠方の天体を観測することによって得られる確実なデータは、特定の元素が発する明るい光(輝線スペクトル)の波長が本来の値からどれほど長くなっているかという「赤方偏移」の値だけであり、銀河の年代などを求めるためには、これを適当な宇宙モデルに当てはめる必要があります。ケック望遠鏡を使ったハワイ大学チームの観測では、主に水素のライマンα線のデータが集められ、赤方偏移の大きさを示すz因子が z=6.56 と測定されました。この数値から銀河の年代を求めるのにハワイ大学チームが採用したのは、近年の観測で支持されている「加速膨張モデル」で、宇宙の膨張速度がだんだんと速くなっているというものです。このモデルを使うと、万有引力の効果で膨張が遅くなってくる従来のモデルに比べて、宇宙の年齢が大きく算定されるという特徴があり(初めのうちはゆっくり膨張し、長い時間に渡って加速されて現在の膨張速度になったというわけです)、ビッグバンが起きたのは、従来モデルによる140億年前ではなく160億年前になります。赤方偏移の値 z=6.56 を加速膨張モデルに当てはめると、観測された銀河は、ビッグバンから7億年が経過した153億年前のものと算出されました。これは、天体が存在しない「宇宙の暗黒時代」が終わりを告げ、低温のガスが集まって原始的な銀河が次々と形成されていた時期に当たります。
このように、「153億年前の銀河が観測された」という主張は、もともと膨張宇宙モデルから導かれたものですから、ビッグバン宇宙論と矛盾することはありません。奇妙に感じられるのは、次の2つの点で誤解があるからでしょう:
- 153億年前に発射された光が現在の地球に到達したからと言って、153億年前に銀河が153億光年彼方にあったとは言えません。宇宙が膨張しているため、光は、発射された時点での地球−銀河間の距離よりも長い道のりを進んでこなければならないからです。時刻t1に発射された光が時刻t0に観測された場合、時刻t1の基準座標系(光速度c=1とする)で測った光源までの距離r1は、公式:
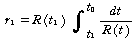
で与えられます。ただし、R(t)は膨張宇宙のスケールを与えるスケール因子で、ビッグバンの瞬間の R(0)=0 から単調に大きくなって、現在の R(t0)=1 になっています。加速膨張モデルにおける R(t) の表式は少し複雑ですので、最も簡単なフリードマンの「平坦宇宙モデル」を使って(ビッグバンが160億年前だったという仮定の下で)153億年前の銀河までの距離r1を計算してみると、手元の電卓によれば
r1 = 38億光年
になりました。
- ビッグバンから7億年後の宇宙は、差し渡し7億光年程度しかなかったかというと、そんなことはありません。宇宙は(特殊相対論には矛盾しない形で)超光速で膨張していますし、また、フリードマンの「平坦宇宙モデル」や「開いた宇宙モデル」では、もともと宇宙の大きさは無限大とされています。さらに、現在の標準的な宇宙モデルによれば、ビッグバン直後のごく短い間に、宇宙が超超…超光速となる猛烈な勢いで膨れ上がったインフレーション期があったとされています。いずれにせよ、物質が形成される遥か以前から、宇宙空間は途轍もなく巨大だったということです。
宇宙論を紹介する一般向けの書物では、せいぜい10億光年程度までの天体を扱うことが多いので、上のような問題はめったに取り上げられませんが、ビッグバンから現在までの歴史の96%を閲した銀河を考えるときには、さすがに相対論的効果を評価することが必要になります。
【Q&A目次に戻る】

M理論は、5種類の超ひも(超弦)理論と超重力理論を発展的に統合するものとして1995年にウィッテンが提唱した理論的枠組みで、あらゆる現象を記述する根源的な理論だと期待する物理学者も少なくありません。ちなみに、“M理論”という名称は、シュバルツの論文 "The Power of M Theory"(1995) でウィッテン自身が提案したものとして紹介されていますが、“M”が何の頭文字かは明らかにされておらず、膜(
Membrane)・魔法(
Magic)・神秘(
Mystery)などいろいろな含みを持つものと了解されています。
クォークやゲージボソンなどの「粒子」を世界の基本的な構成要素と見なす「素粒子理論」は、1960年代にその標準的な枠組みが完成しますが、(1)自然界にさまざまな種類の粒子が存在する理由を説明できない、(2)ミクロの極限で物理量を計算しようとすると答えが無限大になってしまう、(3)観測されている4種類の力(強い力・弱い力・電磁気力・重力)のうち重力を同じ理論的枠組みで記述できない──といった問題を抱えていました。こうした問題を解決する画期的な理論として1970年代の終わり頃から積極的に研究されたのが、「万物の理論 (Theory Of Everything; TOE)」──これは揶揄する表現です──とも言われる超ひも理論です。
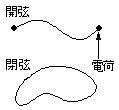
超ひも理論によれば、世界の構成要素は、量子力学に従って運動する太さのない「ひも」であり、この「ひも」(右図のような開弦と閉弦があります)が回転や振動を行う励起状態は、現象の細部が見えないマクロな視点からすると、あたかも粒子であるかのように観測されることになります。ただし、こうした「ひも」の理論を通常の4次元時空で作ろうとすると、「量子異常」と呼ばれる現象が起きて理論を破綻させてしまいます。研究の結果、整合的な理論が構成できるのは、時空が10次元の場合だけであることが判明しました。実際に観測されているのは4次元の世界ですから、10次元のうちの6つの空間次元は小さく丸まってしまって観測できないと解釈されています。超ひも理論は、開弦と閉弦が両方とも存在するか、閉弦を伝わる右向きの波と左向きの波を区別するか──などによって5種類に分類されますが、M理論が出るまでは、この5つの理論が互いにどのような関係にあるのかなど、多くの不明な点が残されていました。
物理学者にとってもう1つの謎だったのが、超ひも理論と超重力理論の関係です。超重力理論は、点粒子の考えに基づいて4種類の力を統一しようとするもので、「超対称性」と呼ばれる制限を理論に課す点が超ひも理論と共通しています。超重力理論によると、時空が11次元のときに理論が最も美しく整合的になるのですが、これと10次元の超ひも理論の間に何らかの関係があるのか、どうもはっきりしなかったのです。
1980年代の終わりに、超ひも理論を越える1つのアイデアが提案されます。それは、1次元の「ひも」ではなくて2次元の「膜 (membrane)」の運動を考えるというものです(超対称性を課すので超膜となります)。
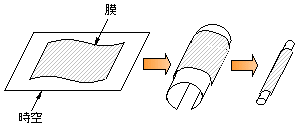
特に興味深い発見は、膜が拡がっている空間次元が丸まってしまった場合、「膜」は「ひも」のように見えるということでした(右図)。従って、11次元の「超膜理論」において、ある空間次元が小さく丸まってしまうと、10次元の「超ひも理論」になることが予想されます。1980年代の終わりには、11次元超重力理論に超膜解が存在することが判明し、「膜」を架け橋として超重力理論と超ひも理論を結びつける可能性が見えてきました。
1995年のウィッテンの論文は、こうした理論的発展を総合し、全体を俯瞰するきわめて見通しの良い視座を提供するものでした。この論文では、超膜理論を発展させた11次元の理論が提案されており、そこで1つの空間次元が小さく丸まってしまうと、あるタイプの超ひも理論に還元されることが示されています。さらに、この理論は低エネルギー極限で11次元超重力理論と一致すること、また、残りの超ひも理論は、相対性 (duality) と呼ばれる関係で結びつけられることも明らかにされました。こうして、超ひも理論の発展形として、M理論が誕生したのです。
M理論は、その後も「Dブレーン」などの新しいアイデアを取り込みながら(さらにド難しい理論へと)発展しています。例えば、「Dpブレーン」とは、p次元の空間的な拡がりを持つ物体で、細い突起を出して互いに結合し、複雑なトポロジーを形成すると考えられています。
この理論が、物理学者の長年の夢を実現する究極の理論なのか、あるいは、数学好きの科学者がひねり出した知的なおもちゃにすぎないのかは、あと10年以上経たないとわからないでしょう。
【参考文献】風間洋一「M理論とは何か」(日本物理学会誌 56(2001)242-)
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
 鉄のような強磁性体を冷却していくと、ある温度Tc(キュリー温度)以下になったとき、外部から磁場を加えなくても磁化が生じるようになります。これは、量子力学的な相互作用によって、隣り合う原子の持つ磁気モーメントが同じ向きに揃う方がエネルギーが低くなるためで、温度が高いときは熱による擾乱のせいで磁気モーメントはバラバラの方向を向いていますが、温度がTc以下になると、磁気モーメント間の相互作用が熱の擾乱作用を上回ってモーメントが同じ向きに整列するわけです。ただし、「磁気モーメントが整列する」ことはわかっても、外部磁場がないときには、「どの向きに整列するか」をあらかじめ知ることは困難です。温度分布や個々のモーメントの状態に応じて、さまざまな向きに磁化が生じることになります。外部から磁化の向きを強制されていないので、「自発磁化」と呼ばれるのです。
鉄のような強磁性体を冷却していくと、ある温度Tc(キュリー温度)以下になったとき、外部から磁場を加えなくても磁化が生じるようになります。これは、量子力学的な相互作用によって、隣り合う原子の持つ磁気モーメントが同じ向きに揃う方がエネルギーが低くなるためで、温度が高いときは熱による擾乱のせいで磁気モーメントはバラバラの方向を向いていますが、温度がTc以下になると、磁気モーメント間の相互作用が熱の擾乱作用を上回ってモーメントが同じ向きに整列するわけです。ただし、「磁気モーメントが整列する」ことはわかっても、外部磁場がないときには、「どの向きに整列するか」をあらかじめ知ることは困難です。温度分布や個々のモーメントの状態に応じて、さまざまな向きに磁化が生じることになります。外部から磁化の向きを強制されていないので、「自発磁化」と呼ばれるのです。
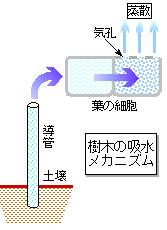 樹木の吸水メカニズムはかなり複雑ですが、ここでは単純化して、湿潤土壌に水を通す細い管(導管)が突き刺さっているものとして考えます。導管内部の水に加わる単位面積あたりの重力は、水柱1mにつき約104[N/m2] = 0.1bar なので、導管の上部を真空にして大気圧(〜1bar)で水を押し上げても、せいぜい10mまでしか上がりません。また、毛管現象(管の内側に付着した薄膜の表面張力によって水が引き上げられる現象)の効果も限られています。数十mの巨木の先端にまで水が行き届くのは、実は、水柱の上端に位置する葉の細胞で浸透圧に起因する張力(陰圧)が発生し、水全体を引っ張り上げているからです。言うなれば、「根が水を吸い上げている」のではなく、「葉が水を引き上げている」のです。水分子は大きな電気モーメントを持っており互いに強く引き合う性質があるため、水全体を持ち上げるほどの張力で引っ張っても、水柱が断裂することはまずありません。
樹木の吸水メカニズムはかなり複雑ですが、ここでは単純化して、湿潤土壌に水を通す細い管(導管)が突き刺さっているものとして考えます。導管内部の水に加わる単位面積あたりの重力は、水柱1mにつき約104[N/m2] = 0.1bar なので、導管の上部を真空にして大気圧(〜1bar)で水を押し上げても、せいぜい10mまでしか上がりません。また、毛管現象(管の内側に付着した薄膜の表面張力によって水が引き上げられる現象)の効果も限られています。数十mの巨木の先端にまで水が行き届くのは、実は、水柱の上端に位置する葉の細胞で浸透圧に起因する張力(陰圧)が発生し、水全体を引っ張り上げているからです。言うなれば、「根が水を吸い上げている」のではなく、「葉が水を引き上げている」のです。水分子は大きな電気モーメントを持っており互いに強く引き合う性質があるため、水全体を持ち上げるほどの張力で引っ張っても、水柱が断裂することはまずありません。
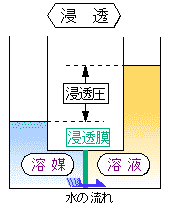 張力の源になっている浸透圧とは、溶媒(水)と溶液が浸透膜(溶媒は通すが溶質は通さない膜)を介して接しているときに生じるものです。このとき、溶液の側へと溶媒(水)が移動して最終的には平衡状態に達しますが、溶質が溶け込んでいることによる化学エネルギーの差を補償するために、圧力は等しくなりません。この圧力の差を浸透圧と言います(右図)。植物の場合、気孔から継続的に水分が蒸散していくので、水が細胞内に浸透しても平衡状態には達せず、葉の細胞はいつまでも水を引っ張り続けることになります。このとき、水の流れを生み出すエネルギー源となっているのは、蒸散を促して濃度の差を生み出すもの──すなわち、太陽光線です。
張力の源になっている浸透圧とは、溶媒(水)と溶液が浸透膜(溶媒は通すが溶質は通さない膜)を介して接しているときに生じるものです。このとき、溶液の側へと溶媒(水)が移動して最終的には平衡状態に達しますが、溶質が溶け込んでいることによる化学エネルギーの差を補償するために、圧力は等しくなりません。この圧力の差を浸透圧と言います(右図)。植物の場合、気孔から継続的に水分が蒸散していくので、水が細胞内に浸透しても平衡状態には達せず、葉の細胞はいつまでも水を引っ張り続けることになります。このとき、水の流れを生み出すエネルギー源となっているのは、蒸散を促して濃度の差を生み出すもの──すなわち、太陽光線です。
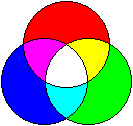 例えば、波長が550〜590nm程度の光が目に入ってきたときには、赤と緑に対応する光受容タンパク質が反応し、その結果として「黄色が見える」ことになります。このように、光受容タンパク質の反応における組み合わせが、「3原色」から構成される7色の光を決定します。
例えば、波長が550〜590nm程度の光が目に入ってきたときには、赤と緑に対応する光受容タンパク質が反応し、その結果として「黄色が見える」ことになります。このように、光受容タンパク質の反応における組み合わせが、「3原色」から構成される7色の光を決定します。
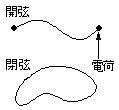 超ひも理論によれば、世界の構成要素は、量子力学に従って運動する太さのない「ひも」であり、この「ひも」(右図のような開弦と閉弦があります)が回転や振動を行う励起状態は、現象の細部が見えないマクロな視点からすると、あたかも粒子であるかのように観測されることになります。ただし、こうした「ひも」の理論を通常の4次元時空で作ろうとすると、「量子異常」と呼ばれる現象が起きて理論を破綻させてしまいます。研究の結果、整合的な理論が構成できるのは、時空が10次元の場合だけであることが判明しました。実際に観測されているのは4次元の世界ですから、10次元のうちの6つの空間次元は小さく丸まってしまって観測できないと解釈されています。超ひも理論は、開弦と閉弦が両方とも存在するか、閉弦を伝わる右向きの波と左向きの波を区別するか──などによって5種類に分類されますが、M理論が出るまでは、この5つの理論が互いにどのような関係にあるのかなど、多くの不明な点が残されていました。
超ひも理論によれば、世界の構成要素は、量子力学に従って運動する太さのない「ひも」であり、この「ひも」(右図のような開弦と閉弦があります)が回転や振動を行う励起状態は、現象の細部が見えないマクロな視点からすると、あたかも粒子であるかのように観測されることになります。ただし、こうした「ひも」の理論を通常の4次元時空で作ろうとすると、「量子異常」と呼ばれる現象が起きて理論を破綻させてしまいます。研究の結果、整合的な理論が構成できるのは、時空が10次元の場合だけであることが判明しました。実際に観測されているのは4次元の世界ですから、10次元のうちの6つの空間次元は小さく丸まってしまって観測できないと解釈されています。超ひも理論は、開弦と閉弦が両方とも存在するか、閉弦を伝わる右向きの波と左向きの波を区別するか──などによって5種類に分類されますが、M理論が出るまでは、この5つの理論が互いにどのような関係にあるのかなど、多くの不明な点が残されていました。
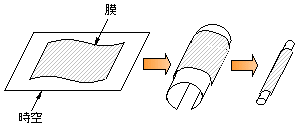 特に興味深い発見は、膜が拡がっている空間次元が丸まってしまった場合、「膜」は「ひも」のように見えるということでした(右図)。従って、11次元の「超膜理論」において、ある空間次元が小さく丸まってしまうと、10次元の「超ひも理論」になることが予想されます。1980年代の終わりには、11次元超重力理論に超膜解が存在することが判明し、「膜」を架け橋として超重力理論と超ひも理論を結びつける可能性が見えてきました。
特に興味深い発見は、膜が拡がっている空間次元が丸まってしまった場合、「膜」は「ひも」のように見えるということでした(右図)。従って、11次元の「超膜理論」において、ある空間次元が小さく丸まってしまうと、10次元の「超ひも理論」になることが予想されます。1980年代の終わりには、11次元超重力理論に超膜解が存在することが判明し、「膜」を架け橋として超重力理論と超ひも理論を結びつける可能性が見えてきました。