 樹木の吸水メカニズムのQ&A
樹木の吸水メカニズムのQ&Aを読みましたが、「根が水を吸い上げているのではなく、葉が水を引き上げている」という箇所に疑問があります。これによると、樹木頂部の導管内圧力が0気圧にある場合、100メートルの樹木では根の部分の圧力は水頭圧により10気圧近くになる計算になりますが、このような高圧において根が水を吸い上げたり水を吹き出さないのは何故でしょうか。【その他】

幹内部の導管においては、細胞間の膜が消失して底部から頂部に至る水柱が形成されており、そこに加わる単位面積あたりの力は、最大で30気圧にもなります(ただし、葉の側から浸透圧で引き上げているので、頂部の方により大きな力が加わります)。樹木の場合、この力によって細胞が破壊されないように、さまざまな自然の工夫がなされています。
当然のことながら、細胞膜を介して一方のコンパートメントが30気圧、他方が1気圧になると、圧力差によって膜が破壊されてしまいます。そうしたことのないように、導管の水柱から外部までの間には、多数の細胞が介在して圧力差を分散させています。特に、幹から葉に至る水の経路は数多く枝分かれしており、個々の経路の終端では水を引っ張る力が小さくて済むようになっています(幹の頂部に巨大な1枚の葉が付いているような樹木は、構造力学的にあり得ないでしょう)。
また、樹木を構成する細胞は、巨大な力に破壊されないように生化学的に補強されています。例えば、木質部の細胞壁にはリグニンと呼ばれる物質が沈着し、強固な構造を作っています。
樹木が水を引き上げる力は、一般の人が想像する以上に巨大なものです。朝、太陽光線が差し込んで光合成が始まると、葉から水の蒸散が行われて水の吸い上げが始まりますが、このとき、まず葉に近い幹の頂部に陰圧が作用するため、夜間に比べて幹の大きさがわずかに細くなることが観察されているほどです。
【Q&A目次に戻る】

電子ビーム溶接とは、加速した電子を標的に照射して瞬時に溶融・接合する技術です。電子という質量の小さい荷電粒子を用いるため、電場があればビームは簡単に曲げられてしまいます。
私は、電子ビーム溶接の実態ついての知識はなく、異種金属の溶接の際にビームがどのように曲がるのか知りませんが、そうした現象が実際に見られるとすると、接触電位差の影響が考えられます。2つの異なる導体を接触させると、電荷の移動を阻止するような電位差が生じるまで、一方から他方へと電荷が移っていきます。この電位差が接触電位差で、移動した電荷は、接触部近くの導体表面に分布することになります。導体内部から熱力学的に可逆なやり方で電子を取り出すのに必要なエネルギーを仕事関数Wとおくと、2つの金属a,bの間の接触電位差φ
abは、
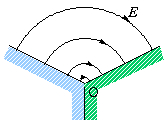
φ
ab = W
b − W
a
で与えられます。ただし、仕事関数Wは、金属の種類だけではなく、表面の状態(表面加工の有無や汚染物質の付着)にも依存するため、具体的な値は簡単にはわかりません。
表面が平面の2つの金属がある角度で交わっているという単純なケースでは、電場は交点Oを中心とする円弧に沿った向きで、Oからの距離に逆比例する大きさになります。
【Q&A目次に戻る】
 真空の空間であっても、その内部で常に対生成・対消滅を繰り返しているという話を聞きました。
真空の空間であっても、その内部で常に対生成・対消滅を繰り返しているという話を聞きました。
1) その場合、短い時間であっても物質と反物質が存在しているので、真空も質量を持っていることになるのでしょうか?
2) 物質/反物質の対称性の破れがあるとすれば、全ての場所で、低い確率にせよ、対消滅が起こらず、物質のみが残る現象が発生しているのでしょうか?
3) 2)が正しいとすると、現在より過去の方が物質の絶対量が少ないことになるのでしょうか?
【現代物理】

現代物理学の成果として明らかになったのは、真空が何もない“虚空”ではなく、粒子と反粒子の対生成・対消滅が繰り広げられるダイナミックな相互作用の場だという驚くべき事実でした。ただし、こうした真空内部の相互作用は、巨視的な世界にはほとんど影響を与えません。それは、真空内部に存在している粒子・反粒子のペアは、あくまで仮想状態(virtual state)として存在しているのであって、いつまでも空間内部に存在して影響を及ぼし続けることができないからです。例えば、こうした仮想的な粒子・反粒子ペアと重力場との相互作用を摂動論によって計算すると、真空が重力を生み出すような項は、全てゼロになるこが知られています。物理学では、外部との相互作用に基づいて質量を定義しているので、重力場などに永続的な影響を及ぼさない仮想的な粒子が質量を作り出すことはありません(ただし、真空凝縮と呼ばれる特殊な現象が生じる場合は、宇宙項という形で真空がエネルギーを持つことになります)。
この宇宙に反物質よりも物質の方が圧倒的に多い理由として、物質/反物質間の対称性が破れているためだという理論がありますが、これは、ビッグバンの莫大なエネルギーによって生み出された多数の物質/反物質のうち、前者がほんのわずか多くなって、その後の冷却過程で物質と反物質が対消滅で消えていく中で物質だけが生き残るというものです。物質/反物質の対称性が破れていたとしても、エネルギーの保存則があるため、通常の物理理論の枠内では、真空から物質が生成されることはありません。ただし、ホイルの定常宇宙論のように“通常でない”理論の中には、真空から物質が湧き出してくる可能性を示すものもあります。もしこうした理論が正しいとすると、時間が経つに従って宇宙全体の物質量は増加の一途を辿ることになりますが、残念ながら、これを支持する研究者は、ごく少数にとどまっています。
【Q&A目次に戻る】

携帯電話のカラー表示としても利用が始まっている有機EL(Electro Luminescence)パネルは、バックライトを必要とする液晶パネルとは異なり、それ自体が発光するディスプレイとして高い利用価値を持っています。
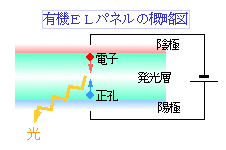
その構造は、蛍光性有機素材で作られた発光層を電極で挟むだけというきわめて単純なもので、電極から送り込まれた電子と正孔が発光層で合体して光を作り出します(右図)。ここで、発光層の素材として、ベースとなる有機素材に別の物質を微量に加えたものを使うと、白・赤・青などさまざまな色に発色するため、フルカラー画像を表示することが可能になります。
有機ELパネルは、蛍光面に高エネルギーの電子をぶつけて(X線や紫外線を含む)多量の電磁波を発生させるブラウン管とは異なり、低電力で特定の波長の光だけを作り出せるため、漏洩電磁波による健康被害を心配する必要はほとんどありません。さらに、それ自体が発光するので、一部の液晶パネルのようにバックライトとして水銀入りの蛍光灯を用いる必要がなく、環境負荷は比較的小さいと考えられています(蛍光灯の持つ潜在的危険性を排除するために、日常的な照明も、有機ELで製造した方が良いという意見があるほどです)。強いて言えば、短いライフサイクルを終えて廃棄される素材が何らかの悪影響を及ぼす可能性がありますが、基盤としては主にガラスが用いられているので、これも敢えて問題にするほどではないでしょう。
【Q&A目次に戻る】

1900年にプランクが、後にプランク定数hと表されることになる量を導入した際には、エネルギーの量子化という考えがベースになっていました。彼は、物質と電磁場との間で交換されるエネルギーが連続的ではなく、hν(ν:振動数)という離散的な値で行われると仮定すると、実験的に得られたスペクトルが見事に説明できることを示しました。このアイデアは、エネルギーhνを持つ光量子や運動量hk(k:波数)を持つ電子の理論へと発展されます。このように、量子論黎明期において、プランク定数hは、物理量の離散化を特徴づける特徴づける量として、また、古典論的な粒子描像に基づく物理量と量子論的な波動描像に基づく物理量を結びつける一種の換算定数として、理論の中に顔を出していました。
しかし、量子力学が発展するにつれ、こうした素朴な理解では収まらなくなります。古典的な世界像はあくまで近似的なものにすぎず、物理現象は全て量子論的に記述されるとの見方が一般的なものとなり、プランク定数の物理的な意味も、量子力学の枠内で解釈しなければならないからです。最も一般的な量子化の手法は、正準量子化と呼ばれるもので、物理系を支配する互いに共役な一般化座標Q
iとP
iとの間に、次の正準交換関係が成り立つことを要請します:
[Q
i, P
j] = iδ
ijh/2π
[A,B] は2つの演算子の交換子 AB-BA を表します。上式の右辺をゼロと置くと、全ての物理量は(量子ゆらぎを記述する演算子ではなく)確定した数値で表される古典的な量になるので、プランク定数h は、古典近似には含まれない量子ゆらぎの程度を表していると言えます。このことは、上の交換関係を変形して得られる不確定性関係の式:
ΔQ
i・ΔP
i≧h/4π
に端的に表されます。ただし、こうした量子ゆらぎの振舞いは、単に古典近似からのズレだけではなく、量子論固有の現象に関しても見られます。
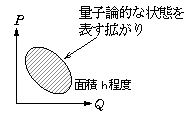
プランク定数の持つ意味を直観的に把握するためには、一般化座標の張る位相空間をイメージするとわかりやすいでしょう。古典論では、ある瞬間の物理系の状態は位相空間内部の1点で表されますが、量子論の場合、量子ゆらぎのために拡がりを持つことになります。系の量子論的な状態を表す拡がりは、時間とともにさまざまに変形しますが、その面積は、不確定性関係のために決してh/4π以下になることはありません。
【Q&A目次に戻る】

電子などの荷電粒子が自転しているのではないかというアイデアは、物質の磁性を説明するために20世紀の初頭にコンプトンによって提出されました。実際、電荷が球状粒子の表面に分布した状態で回転すると、円形電流によって磁気モーメントが生じるので、強磁性の原因になりそうに見えます。しかし、電子のような小さい(理論的には点として扱われる)粒子が自転すると、その表面速度は光速を超えて相対論に矛盾しそうですし、何よりも、古典的な粒子概念を否定する量子論の枠組みにも馴染みません。こうした理由から、1925年にパウリがスピンに相当する物理的自由度を導入した際には、「粒子の自転」という見方をいっさい行わず、「量子論固有の自由度」と解釈していました。その後、ウーレンベックとハウトシュミットが、“若気の至り”から、自由度の実体として電子の自転を想定することができるという論文を発表します。この論文で示された「スピン=素粒子の自転」という解釈に対しては、さまざまな批判が寄せられましたが、少なくとも古典論の用語法をそのまま使える便利さがあり、量子論の入門書には、そのまま取り入れられることもあります。
現代物理学において、素粒子のスピンは、もともとのパウリの解釈通り、量子論だけに見られる内部自由度として扱われています。数学的には、スピン状態はスピノルと呼ばれる量で表され、電子のようなスピン1/2の粒子の状態は、それぞれ粒子と反粒子の2つのカイラリティを表す4成分スピノルで記述されます。磁場を加えるなどしてスピン状態ごとにエネルギーが異なるようにすると、(「スピンがアップ状態の電子」などの)1成分だけが値を持つスピノルが固有状態を表します。通常の物理量は、空間を360°回転させると元の値の戻りますが、スピノルには、360°の回転に対して符号が変化する(ψが-ψになる)という著しい特徴があります。
スピンは、古典論では説明できない量子論固有の内部自由度を表しているものの、“回転”という古典的な操作と密接な関係を持っています。外部と相互作用を行っていない孤立した系の場合、「空間全体を回転させても物理法則は変化しない」という条件から角運動量の保存則が導かれますが、系を構成する粒子がスピンを持っている場合は、粒子の運動に伴う角運動量(軌道角運動量)だけでは保存則は成り立たず、これにスピンに起因する角運動量(スピン角運動量)をベクトル的に足し併せた「全角運動量」が保存されることになります。ちょうど太陽系などで公転の角運動量と各天体の自転の角運動量を加えた全角運動量が保存される場合と同様であり、「スピン=素粒子の自転」というアナロジーが成立するようにも見えます。しかし、これはおそらく本末転倒の解釈でしょう。われわれは、空間における物体の移動や回転を直観的に理解したつもりでいますが、現代物理学では、移動や回転という操作自体が、場の変動を伴う非直観的なプロセスであると考えられています。内部自由度としてのスピンがより根元的な姿であり、これを物体の自転と類比的にイメージできるのは、そのように巨視的な世界の方が組み立てられていると解釈するのが妥当だと思われます。
【Q&A目次に戻る】

プロペラやジェットエンジンで空気の流れを生み出すことによって飛行している飛行機と異なり、真空中を飛ぶロケットの場合は、ニュートンの作用反作用の法則を使い、進行方向と逆向きに物質を噴射することによって推進力を生み出さなければなりません(例外として、太陽風を帆に受けて進む宇宙帆船があります)。通常は、化学反応で熱せられたガスを噴射していますが、これでは単位質量あたりのエネルギーが小さく、太陽系内で航行するだけでも膨大な量の化学燃料を搭載しなければなりません。化学エンジンに代わるものとして、核分裂の熱で高温のガス流を作って噴射する原子力エンジンとともに期待されているのが、電磁気を使ってプラズマを加速するプラズマエンジンです。
プラズマエンジンは、次のようなステップを経て推進力を作り出します:
(1)中性のガスを、(電子レンジと同じ原理によって)高周波で数万度に加熱して、イオン化ガス(プラズマ)を作る。
(2)プラズマに定磁場とそれに直交する振動電場を加えることによって、イオンにサイクロトロン運動を起こさせる。この過程でプラズマは加熱され、1000万度の高温プラズマになる。
(3)高温プラズマの流れを磁場でコントロールしながらノズルから噴出させ、推進力とする。
プラズマエンジンの場合、高速のプラズマ流を利用するので、燃焼温度の低い(数千度)化学燃料に比べて噴射の際の運動量(質量×速度)が大きくなり、それだけ推進力も大きくなります。ただし、惑星探査ロケットで利用するには、10MW(=1万kW)の電力を必要とするので、かなり強力な電源を開発しなければなりません。
プラズマエンジンはNASAなどで研究されており、太陽電池を電力源とする小型の実験機を2004年頃に打ち上げようという計画もあります。
【参考文献】F.R.チャン・ディアス「惑星旅行を身近にする新型ロケット」(日経サイエンス、2001年2月号、p.92-)
【Q&A目次に戻る】

アインシュタインの重力理論をはじめ、一般共変性を満たす物理理論は、
F
μν… = 0
という形の方程式によって記述されます。通常の4次元時空では、添字のμやνは0〜3の値を取り、0が時間次元、1〜3が空間次元を表すとされますが、3を上限とすることについて「現実にそうだから」という以外に物理的な根拠はなく、添字が0からd-1までを動くd次元時空(1次元時間、d-1次元空間)の理論を考えてもかまわないはずです。高次元の理論が簡単に作れるにもかかわらず、観測されている世界が4次元である理由は、現在なお解明されていません。
この問題に対するアプローチには、いくつかの方法があります。まず、この世界が“本当に”4次元であるかを確認しなければなりません。ニュートンの重力法則をd次元時空に拡張した場合、距離rだけ離れた2質点間に作用する重力の強さは、1/r
(d-2)に比例するはずです(4次元の世界では逆2乗則になる)。実験・観測によると、重力の強さは、宇宙論のスケールから10
-13mまで d=4 の式にフィットしているとのことなので、この世界は4次元であると強く示唆されます。しかし、確かにそうだと断言できるわけではありません。
実際、物理学者は、「この世界は5次元だ」という1920年代のカルーザ−クライン理論を嚆矢として、この世界が5次元以上である可能性をいろいろと考察してきました。ここ20年ほどは、理論を量子化したときに異常な振舞い(アノマリー)を示さない「数学的に美しい」理論として、d=10,11,26次元などの高次元時空の理論(超ひも理論やM理論)が人気を集めています。その場合、3次元より大きい余分な空間次元は、10
-13m以下(おそらくは10
-35m程度)に小さく丸まってしまうか、あるいは、物質や重力の力線が侵入できない不可測領域になっていると想像されています。
ただし、高次元理論を考える場合でも、「なぜ4次元か」という謎は残ります。余分な空間次元が小さく丸まってしまうとしても、3次元空間だけ生き残る必然性はないからです。仮に「空間次元がさまざまに丸まった宇宙がたくさん生成される」とすると、空間次元が2次元以下の宇宙には知的生命は生息できない
(→別の項目を参照)ことが知られているので、「われわれが存在する」という条件から「
この 宇宙は4次元以上でなければならない」という結論は導けます。しかし、5次元以上の宇宙の生成が抑制される何らかの理由がない限り、「なぜ4次元か」という問いの答えにはなりません。
物理学者の中には、この世界が4次元であることに数学的な根拠があると考える人もいます。d次元のユークリッド幾何学を調べると、d=3〜5の辺りは、かなり特殊な世界であることがわかります。例えば、d次元単位球(半径1)の体積は、2次元ではπ、3次元では4π/3と、5次元までは次元数とともに増えていきますが、6次元からは減り始め、それ以後は次元を無限大にする極限で0に漸近します。また、正多面体の数は、3次元が5種類、4次元が6種類なのに対して、5次元以上は3種類となっています。多次元の多様体論で特に注目されるのが、質問にもある微分構造に関する定理で、d次元ユークリッド空間(R
d)においては、他では微分構造が1種類しかないのに対して、4次元だけ無限個存在することが示されました(ドナルドソン,1982)。ただし、この性質が「この世界が4次元擬リーマン多様体として観測される」こととどのように関わっているのか、私自身が不勉強でもあり、よくわかりません。ちなみに、ドナルドソンの難解な証明を物理学者向けにわかりやすく手直ししたのが超ひも理論やM理論の推進者にして当代最高の数理物理学者であるウィッテンですから、当然、何かを狙っていると思われるのですが…
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
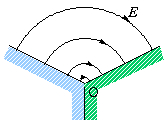
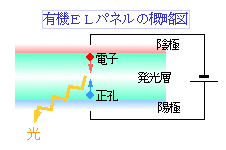 その構造は、蛍光性有機素材で作られた発光層を電極で挟むだけというきわめて単純なもので、電極から送り込まれた電子と正孔が発光層で合体して光を作り出します(右図)。ここで、発光層の素材として、ベースとなる有機素材に別の物質を微量に加えたものを使うと、白・赤・青などさまざまな色に発色するため、フルカラー画像を表示することが可能になります。
その構造は、蛍光性有機素材で作られた発光層を電極で挟むだけというきわめて単純なもので、電極から送り込まれた電子と正孔が発光層で合体して光を作り出します(右図)。ここで、発光層の素材として、ベースとなる有機素材に別の物質を微量に加えたものを使うと、白・赤・青などさまざまな色に発色するため、フルカラー画像を表示することが可能になります。
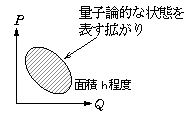 プランク定数の持つ意味を直観的に把握するためには、一般化座標の張る位相空間をイメージするとわかりやすいでしょう。古典論では、ある瞬間の物理系の状態は位相空間内部の1点で表されますが、量子論の場合、量子ゆらぎのために拡がりを持つことになります。系の量子論的な状態を表す拡がりは、時間とともにさまざまに変形しますが、その面積は、不確定性関係のために決してh/4π以下になることはありません。
プランク定数の持つ意味を直観的に把握するためには、一般化座標の張る位相空間をイメージするとわかりやすいでしょう。古典論では、ある瞬間の物理系の状態は位相空間内部の1点で表されますが、量子論の場合、量子ゆらぎのために拡がりを持つことになります。系の量子論的な状態を表す拡がりは、時間とともにさまざまに変形しますが、その面積は、不確定性関係のために決してh/4π以下になることはありません。