
色が3原色の組み合わせに還元できるという事実は、人間の視覚の特性に由来しており、電磁波の物理的な性質とは関係ありません。
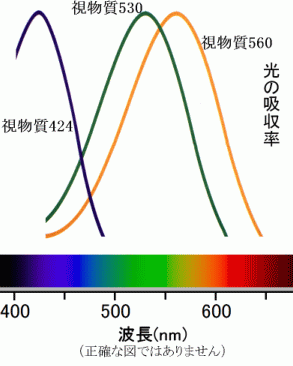
人間の視細胞(錐体細胞)には、ある範囲の波長の光を吸収して構造変化を起こす視物質(光受容タンパク質)が3種類存在しています。最も強く反応するのは、波長がそれぞれ560nm、530nm、424nmの光であり、それに応じて視物質560などと呼ばれますが、この波長だけに反応する訳ではありません。可視領域の広い範囲にわたって、2つ以上の視物質が反応します(図参照)。こうした反応は視神経を介して大脳視覚野に伝えられますが、このとき、各視物質がどの程度の割合で反応したかという組み合わせによって、色の知覚が成立します。例えば、500nmの光が眼に入射したとき、視物質424はほとんど反応せず、視物質530は光の吸収率が最大になる波長に比べて80%程度、視物質560は50%程度反応します(ここで言う吸収率とは、網膜に多数存在する視物質の中で、光を吸収して構造変化を起こすものの割合だと考えてかまいません)。この反応の組み合わせが、500nmの光に対する青緑という知覚を引き起こします。
異なる波長の光が同時に入射した場合には、視物質の反応の組み合わせが等しくなる波長の光と同一の色に見えます。赤い光に対しては、視物質560が他の2つに比べて強く反応します。また、緑の光に対しては、視物質530の相対的な吸収率がやや高く、視物質560は低くなります。赤と緑の光が同時に入射すると、それぞれの効果が重畳され、視物質560が相対的に強く視物質530がやや弱いという反応の組み合わせになりますが、これは、黄色の光が入射したときの組み合わせと同じです。したがって、実際には赤と緑という2種類の光が入射しているにもかかわらず、人間の目には黄色に見えるのです。
赤・青・緑の光が同時に入射すると、3つの視物質が全て反応しますが、これは、単一波長の光が入射したときには起こり得ない現象です。この結果、光のスペクトルのどこにもない白という知覚が生み出されます。
ちなみに、脊椎動物はもともと4種類の光受容タンパク質による4色型色覚を進化させていました。鳥類や多くの爬虫類、魚類は、今なおこの4色型色覚を備えています。これに対して、恐竜の全盛期に陰でこそこそ動き回る夜行性動物だった哺乳類では、暗闇ではあまり重要ではない色の知覚が衰え、赤タイプと青タイプの2種類の光受容タンパク質しか存在しなくなりました。その後、過去4000万年の間に旧世界霊長類(アカゲザルなどを含む狭鼻猿類)の祖先の視覚システムで、赤タイプの光受容タンパク質が2つのタイプに変異したため、人間は3色型の色覚を持っていると言われています。
【Q&A目次に戻る】

常識的なことばの定義に基づけば、原子力発電用の原子炉が核爆発を起こすことはありません。少し言い訳めいた表現を用いましたが、核分裂の連鎖反応において、どこまでが単なる核暴走でどこからが核爆発になるかという明確な定義がないので、こうした言い方をせざるを得ないのです。
ウランやプルトニウムが核分裂する際には、中性子が2〜3個飛び出します。この中性子のうち、平均して1個以上が他のウランやプルトニウムの原子核に衝突して分裂を引き起こすと、分裂する原子核の個数が指数関数的に増大し、最終段階では膨大な数の原子核がいっせいに分裂することになります。この過程がある程度以上の規模になったときに核爆発と呼ばれますが、では「ある程度」とはどの程度かとなると、はっきりしません。広島に投下されたウラン爆弾は、数十万分の1秒の間にTNT火薬換算で15キロトン相当のエネルギーを放出したので間違いなく核爆発ですが、2006年に北朝鮮が行った核実験では、その10分の1程度のエネルギーしか放出されておらず、不完全核爆発だと言われています。常識的に言って、核反応の規模がこれより何桁も小さければ、核爆発ではないと言って差し支えないと思います。
短時間に多量のエネルギーが放出されるためは、高い増大率で核分裂が持続することが必要です。ところが、発電用原子炉は、そうした過程が起きないように設計されています。まず、核燃料の濃度が核爆弾の場合よりも大幅に低いので、核分裂の際に飛び出した中性子が他の原子核に衝突するまでに長い距離を進まなければならず、核反応の進行速度が遅くなる上に、途中で吸収されてしまう確率が高くなって、核分裂の増大率が抑えられます。さらに、核反応が進みすぎて高温になると、自動的に核反応が抑制されるという仕組みもあります。核分裂を引き起こすには、飛び出した中性子の速度を少し遅くしなければなりません(速いままでは核分裂の確率が低くなります)。ところが、通常の原子炉ではそのための減速材として水を用いているので、高温になると気泡のせいで減速効果が失われてしまい、核分裂を起こしにくくなるのです。
これまでに起きた最悪の原子力災害は、1986年の
チェルノブイリ原子力発電所事故です。ソ連製の原子炉は気泡による核反応の抑制効果がない(正確に言うと、低出力時に促進効果が抑制効果を上回る)ために、制御棒を抜き過ぎたせいで始まった原子炉の暴走を止められず、急激に出力が増大したというものです。しかし、このときも数秒間で出力が定格の100倍以上に増大したというレベルで、核爆発に比べれば核分裂の増大率は何桁も小さかったと考えられます。屋根を吹き飛ばしたのは、高温になった燃料管の被覆が破裂し周囲の冷却水内部に飛び散ったことで生じた水蒸気爆発でしょう。
もっとも、たとえ核爆発が起きなくとも、炉内に蓄積されている核分裂生成物(死の灰)が飛散すれば甚大な被害をもたらすので、原子力発電所の事故が恐ろしいことに変わりはありませんが。
【Q&A目次に戻る】

進化をもたらすDNAの変異には、最も頻繁に起きる点突然変異(DNAの1つの塩基が別の塩基に置き換わる変異)のほか、遺伝子(あるいは特定の塩基配列)の欠失・挿入・重複、調節領域の変異などがあります。人間のDNAの場合、ヒトゲノム計画などによって確立された標準配列に対する異同がコンピュータを駆使して調査されており、通常のゲノムで、1塩基置換が約300万ヶ所(1000塩基対当たり1ヶ所の変異)、長めのDNAの欠失・挿入が数百ヶ所で見られます。さらに、異なる種の間で塩基配列がどれだけ違っているかを調べれば、種間の「遺伝的距離」がわかります。例えば、ヒトとチンパンジーのDNA配列は99%が一致していますが、ヒトとアカゲザルの一致率は97.5%程度であり、アカゲザルの系統がヒト/チンパンジーの共通の祖先から先に分岐したことが伺えます。
系統樹の分岐がいつ生じたかを決定するには、遺伝的距離の解析に加えて、変異の発生率に関する仮定が必要になります。点突然変異は、環境要因とは無関係に一定の割合で生じると推測されますが、変異によって個体の生存率が上下する可能性があるので、変異した遺伝子が集団内に定着するかどうかはケースバイケースです。おおざっぱに言って、ヘモグロビンやチトクロムのような巨大分子の場合、塩基の置換はそれぞれの分子ごとにほぼ一定の速度で定着している(分子構造や機能の違いのため、ヘモグロビンの方がチトクロムより大きい)ことが判明しているので、変異した塩基を変異数の定着速度で割れば、理論的には分岐年代が推定できるはずです。この手法(「分子時計」による年代推定法と呼ばれています)によって、ヒトとチンパンジーの分岐は、今から400〜500万年前に起きたと割り出されました。もっとも、分子時計は必ずしも正確ではなく、大幅な誤差を覚悟しておかなければなりません。化石試料や地質学のデータと突き合わせて検討することが必要でしょう。化石の解析からは、ヒトとチンパンジーの分岐年代は500万年よりも以前だとされています。
質問にある哺乳類と超大陸の関係は、東京工業大学の岡田典弘教授らによって今年提唱された新説で、レトロポゾンについての研究がベースとなっています。
H. Nishihara, S. Maruyama, and N. Okada, 'Retroposon analysis and recent geological data suggest near-simultaneous divergence of the three superorders of mammals,' (PNAS published online before print March 13, 2009)
レトロポゾンは自分自身を複製して DNA のあちこちに挿入する性質を持った塩基配列で、ヒトゲノムでは全体の 1/3 がレトロポゾンで占められています。一度挿入されたレトロポゾンは失われにくく、また、偶然同じ場所に挿入される確率は小さいので、レトロポゾンが特定遺伝子に挿入されているかどうかを見ることで、分岐の順番を推定することが可能です。例えば、SINE (
short
interspersed
repetitive
element) と呼ばれる300塩基ほどの配列について調べることで、クジラがカバの近縁種である(ウシとカバよりもクジラとカバの方が近い)と判明しました(これも岡田教授の業績です)。
哺乳類(カモノハシと有袋類を除く)は、ローラシア(後に北米とユーラシアに分裂する超大陸)起源の北方獣類、アフリカ起源のアフリカ獣類、南米起源の南米獣類(異節類/貧歯類)という3系統に分類されており、超大陸が分裂して3つの大陸になったことが哺乳類分岐の引き金になったと推測されています。ただし、分岐の順番は良くわかっていません。古地磁気学では、超大陸パンゲアが1億4800万〜1億3800万年前にローラシアとゴンドワナに分裂し、次いで1億500万年前にゴンドワナがアフリカと南米に分裂したという説が提唱されており、この順序に対応して、哺乳類の系統樹でもローラシア起源の北方獣類がまず分岐したという見方がやや有力ですが、決め手に欠けています。
岡田教授のグループは、3系統それぞれの代表としてヒト、アフリカゾウ、アルマジロを選び、併せて2万ヶ所のトランスポゾンについて詳しく比較することで、最終的に、68ヶ所が分岐の順番を決定するのに有用だと結論しました。ところが、3系統のうちどれが最初に分岐したかを割り出すと、これら68ヶ所のうち、22ヶ所がアフリカ獣類、25ヶ所が南米獣類、21ヶ所が北方獣類が最初に分岐したことを示していました。つまり、レトロポゾンのデータによれば、分岐の順番に先後関係が付けられないという訳であり、これをそのまま信じるならば、ほぼ同時に分岐したと考えざるを得ないのです(トランスポゾンのデータだけでは、分岐年代は推定できません)。そこで、岡田教授らは、ローラシア・アフリカ・南米が同時に分裂し、その時点で哺乳類の分岐が始まったと結論したのです。古地磁気のデータでは超大陸が分裂した時期に隔たりがありますが、生物学的に重要なのは大陸間の移動が可能かどうかです。論文では、ローラシアとアフリカをつなぐジブラルタル橋梁と、アフリカと南米をつなぐブラジル橋梁が、1億2000万年前に海面上昇によってほぼ同時に水没し、動物の往来が困難になって3つの系統に分岐したというアイデアが提案されています。
哺乳類の分岐に関する岡田教授らの主張は、必ずしも充分な証拠がなく、いまだ仮説の域を出ませんが、なかなかに興味深い説なので、今後の展開を見守っていきたいところです。
なお、質問文に述べられた2つの俗説のうち、アジア人(モンゴロイド)とダウン症(英語で Mongoloid という蔑称が使われることがある)の関係は根拠のない偏見ですが、白人(コーカソイド)の由来に関しては若干の真実を含んでいます。10〜12万年前にアフリカの熱帯付近に出現した初期のホモサピエンスは、強烈な紫外線を防ぐために肌の色は濃かったと推定されていますが、高緯度地方への移住が始まり、体内でビタミンDを合成するのに必要な紫外線が不足するようになると、色素が少ない変異体の方が生存に有利になって、肌の色の薄い人が増えてきたという訳です。実際、コーカソイドだけではなく、赤道から南方に移って定住したコイサン語族(かつてホッテントット/ブッシュマンと呼ばれていた部族)は、アフリカ黒人(ネグロイド)よりも色白で、紫外線量と肌の色に密接な関係があることを伺わせます。
【Q&A目次に戻る】

石英ガラスなど多くのガラスは、ヘリウムガスをわずかに透過させますが、窒素や酸素の分子はほとんど通しません。この性質が完全ならば、質問文にあるような現象が実際に起きることになります。
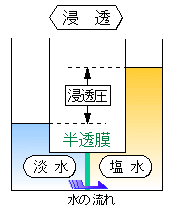
これは、浸透と呼ばれる現象の一例です。水は通すが塩は通さないような半透膜で淡水と塩水を分離していると、淡水側から塩水側へと水が自然に流れ込みます。溶液の場合は、浸透圧が力学的な圧力と釣り合うところで水の流入が止まります。しかし、ガラス瓶に入ったヘリウムガスの漏出の場合は、大気におけるヘリウムの分圧がきわめて低いので、外部への拡散がいつまでも続くことになります。
ヘリウムだけが漏れ出てしまい、外部から空気が侵入しないでほとんど真空になるという現象は、物理的には、それほど不思議なものではありません。最初に瓶の中にヘリウムだけを封入した段階で、酸素や窒素に関しては真空状態を作り上げたことになるので、ヘリウムだけが漏出して真空に近い状態になったとしてもおかしくないのです。問題は、それほど速やかにヘリウムを漏出されるガラスが現実にあるかどうかです。石英ガラスはヘリウムガスを通すと言われますが、これは、ガラスで防護された素材をヘリウムが汚染する危険性を指摘したもので、ガラス瓶に入ったヘリウムが自然に抜けてしまうというレベルではありません。
ヘリウムがガラスを透過する割合に関するデータは、次の論文にまとめられています。
F.J. Norton, 'Helium Diffusion Through Glass,' (Journal of the American Ceramic Society, 36(1953)90-)
この論文に記された実験では、ガラス瓶から漏出したヘリウムガスを質量分析器で測定するという方法が採用されています(質量分析器を使わなければわからないほど微量のガスしか漏れ出ないためです)。石英ガラス(シリカ100%)、バイコールガラス(米コーニング社製シリカ96%の高ケイ酸ガラス)、パイレックス(コーニング社製シリカ81%のホウケイ酸ガラス)、X線遮蔽用ガラス(主成分は酸化鉛でシリカは31%)など9種類のガラスについてのデータが出されており、そこから、ヘリウムの漏出は石英ガラスやバイコールガラスで多く、X線遮蔽用ガラスで少ないことがわかります。定量的なデータは、ヘリウム漏出量についての公式:
q = KStΔP/d
(q:漏出量(0℃、1気圧での体積)[cm
3]、S:表面積[cm
2]、d:ガラスの厚さ[mm]、t:時間[秒]、ΔP:内外の圧力差[cmHg])
に現れる浸透係数 K で与えられています。K の値は、ヘリウムの温度やガラスの種類によって何桁も異なりますが、ヘリウムが 0℃のとき、石英ガラスの 浸透係数 K は 5.3×10
-11 となっています。
このデータを使って、半径 10[cm]、厚さ 1[mm] の球形の石英ガラス容器に 0℃、1気圧(=76cmHg)のヘリウムガスを詰めたとき、ヘリウムが容器壁から抜け出て、圧力が100分の1気圧になってしまうまでの時間を求めてみましょう(温度は 0℃に保たれるとします)。容器内に残っているヘリウムの割合 x は、容器の容積(0℃、1気圧での体積で表した当初のヘリウム量に等しい)を V 、漏出した総量を q として、
x = (V-q)/V
で与えられます。大気のヘリウム分圧を 0気圧と置き、ヘリウム漏出量に関する公式を x についての微分方程式に書き直すと、
-dx/dt = (KS P
0/Vd) x
となります。ただし、P
0 は最初のヘリウムの圧力で、
容器内の圧力 P = xP
0
という関係式を使いました。この微分方程式を解けば、
x = exp ( -(KS P
0/Vd) t )
となります。ここで、x=0.01、S=4π×10
2 、P
0=76 などと置いて計算すると、圧力が100分の1に減少するまでの時間は、約120年と求められます(この数値は、ヘリウムを通しやすい石英ガラスの場合であり、パイレックスではその10倍、X線遮蔽用ガラスでは1万倍以上の時間が掛かります)。酸素や窒素の浸透係数は、石英ガラスの場合、ヘリウムより7桁以上小さいと見積もられているため、ヘリウムだけを封入した石英ガラスの容器に酸素・窒素が侵入することはなく、ヘリウムが抜け出る一方で自然に真空に近づいていきますが、厚さ1mmという比較的薄いガラスでも100分の1になるのに120年(10分の1なら60年)も掛かるとなると、その過程を簡単に確認することはできません。ヘリウムがずっと透過しやすい多孔質ガラスもありますが、これは酸素や窒素も通してしまうので、ヘリウムを封入しておいても、いつのまにか空気と入れ替わってしまうだけです。
この質問は2007年にいったん回答したものですが、最近になって読者から上掲の Norton の論文について教えられたので、大幅に改稿しました。
【Q&A目次に戻る】

観測結果によると、少なくとも太陽の120倍の質量を持つ恒星の存在が確認されていますが、こうした超重量級の恒星が形成されるプロセスは、まだ充分に解明されていません。
恒星は、重力作用で星間ガスが集まってできた円盤状の原始恒星系星雲の中で、さらに物質が凝集して誕生します。ところが、この凝集過程が進んでいる途中で原始恒星の輝きが増すと、放射圧によってガスを吹き飛ばしてしまうために、恒星はあまり成長できなくなるはずです。星雲が自転しておらず、物質分布が球対称の場合について計算すると、放射と重力は L/M 〜 2500 のときに釣り合うことがわかります。ただし、L と M はそれぞれ太陽を基準としたときの恒星の光度(luminosity)と質量です。L/M がこの臨界値を超えると放射の圧力が重力を上回り、恒星はそれ以上には成長できなくなります。主系列星のデータを使うと、M が約20のときに L/M が2500になるので、球対称のケースでは太陽質量の20倍が恒星質量の上限となると結論できます。星雲が自転している場合の計算は難しくなりますが、太陽質量の40倍が上限だという論文があります。ところが、実際には太陽質量の120倍もある恒星が見つかっているのですから、この議論はどこかが間違っていることになります。
この謎を解明すべく、コンピュータ・シミュレーションが繰り返されています。最近行われたシミュレーションでは、太陽の100倍の質量を持つ半径0.1パーセク(0.3光年)の原始恒星系星雲を初期状態として、それから何が起きるかが調べられましたが、その結果、物質分布がシンメトリックになると仮定して行った理論的な計算とは異なり、星雲は実に複雑な挙動を示すことが判明しました。シミュレーションによると、初期状態から3600年経過した時点で原始星が形成され、さらに1万7000年ほどスムーズに凝集が進みます。しかし、その後は不安定な振舞いが顕著になり、棒渦巻銀河に見られる腕のような構造が形成されます。約2万5000年経過した時点で L/M は2500を超えますが、重力による凝集は止まりません。星雲がいくつかに分断され、放射をすり抜けるようにして物質が凝集する領域が現れるからです。最終的には、2つの大きな恒星(それぞれ、太陽質量の41.5倍と29.2倍の質量を持つ)から成る連星系が形成され、そのまま安定した状態が続いたのでシミュレーションを打ち切ったとのことです。
このシミュレーションでは、個々の恒星は、自転する星雲についての理論的計算で求められた質量の上限(太陽質量の40倍)を大きく超えてはいませんが、これは、初期状態における星雲の質量を太陽質量の100倍に設定したためだと考えられます。最初の質量がそれよりも大きく、複数個の原始星が形成された後にいくつかが合体するケースを想定すると、理論的な上限を超えた巨大な恒星が形成されてもおかしくありません。ただし、凝集を妨げる要因には、放射だけではなく、恒星から物質が吹き出す現象である恒星風もあるため、恒星質量の上限がどうなるかを結論するには、恒星風の影響を含めた精密なシミュレーションを実施する必要があります。
この質問に関しては、以前の回答で一般相対論を元に上限を求めましたが、最近になって下の論文を読み、改めて答え直しました。
M.R. Krumholz et al., "The Formation of Massive Star Systems by Accretion," (Science 323 (2009) 754)
【Q&A目次に戻る】

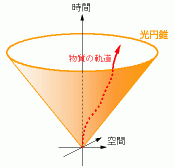
ブラックホールから物質が脱出できない訳を「強い重力に引っ張られて遠ざかれない」というように解釈すると、質量のない光子まで捉えられてしまう理由がわからなくなります。質問文にもあるように、幾何学的な構造のせいでシュヴァルツシルト面(事象の地平面)の外側には進めないと考えるのが妥当でしょう。
時空の幾何学的構造を考える際に、光円錐を使うとわかりやすくなります。光円錐とは、点光源から四方八方に放射された光が進む道筋を幾何学図形の表面として表したもので、重力が存在しない空間(ミンコフスキー空間)では、
(ct)
2 =
r2 (t:時間間隔、
r:3次元空間での間隔)
という式で定義される4次元円錐の形をしています。自然界の最高速度を持つ光は光円錐面に沿って進み、光より遅い速度でしか移動できない物質の軌道は光円錐の内側に入ります(空間を2次元にした図を右に記しておきます)。
ニュートン力学では、重力は空間を越えて一瞬で遠方の質量に作用すると仮定されていますが、一般相対論では、こうした遠隔作用の考えが否定され、重力源が周囲の時空をゆがませることによって作用を及ぼすと見なされています。重力による時空のゆがみは、光円錐の形に変化を与えます。ブラックホールの周辺では、時空のゆがみのせいで光円錐が中心の特異点に向かって傾いており、その表面に沿って進む光の進行も、重力の存在しない空間とは異なっています(図参照)。シュヴァルツシルト面のすぐ外側で放射された光は、ブラックホールから遠ざかろうとしても光円錐面の外縁の傾きが小さいためになかなか進めず、ゆっくりと時間をかけて遠方へと向かうことになります(このため、ブラックホールに落下する物体はシュヴァルツシルト面で止まって見えると言われることもありますが、実際には光量が急激に減少するため、すぐに暗くなって見えなくなるはずです)。光円錐の形からわかるように、ブラックホールに近づく光はそのまま飲み込まれていきます。
一方、シュヴァルツシルト面の内側では、光円錐全体が中心向きに傾いてしまうので、光であれ物質であれ、どのように動いたとしても中心に近づくようなルートしか存在しません。これが、ブラックホールから何も脱出できない理由です。
【Q&A目次に戻る】

太陽に関して言えば、地球の地震に相当する「日震」が観測されており、内部構造の研究に利用されています。
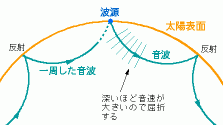
太陽の内部では深いほど温度が高く、振動波(音波)の速度が速くなります。このため、表面の波源から下方に向かって発射された音波は進行方向が上に向くように曲げられ、最終的には表面に到達してそこで反射されます。こうして表面での反射を繰り返しながら一周しますが、このとき、発射点に同じ位相で戻ってくるような振動のモードは、太陽表面の固有振動となります(右図)。対流層における乱れた対流は常に表面を揺さぶり続けているので、こうした固有振動は常時励起されています。この振動が日震です。1960年代に最初に観測された日震は周期約5分の基本振動で、現在では、太陽表面における明るさの局所的な変動パターンを元に多数の固有振動が調べられています。
上に述べたように、どのような振動のモードが固有振動になるかは、深さによる音速の変化によって決まります。したがって、固有振動数を測定することで、深度と音速の関係が求められます。太陽の内部は、エネルギー輸送を主に対流が担う外側の対流層と主に放射が担う内側の放射層、それに中心部の核から構成されることが恒星内部構造論から推定されていましたが、対流層と放射層の境界面がどこにあるかは、なかなか決定できませんでした。しかし、日震データの分析を通じて深度と音速の関係が判明したことにより、音速のカーブに変化が見られる場所(中心から太陽半径の約0.7倍の地点)として境界面の位置が確定されました。音速がわかれば、状態方程式を解いて圧力や温度が求められるので、内部構造についてかなり詳しく解明できます。
日震のデータからは、より局所的な情報も得られます。例えば、太陽表面の異なる地点における振動の相関から内部の動きを解析し、フレアや黒点の下でどのような流れが生じているかを調べることも可能です。こうした研究は1990年代から盛んになってきたもので、2006年に日英米共同で打ち上げられた太陽観測衛星「ひので」などによってデータ収集が進められています。
太陽以外の恒星でも「星震」の研究が始まっていますが、木星のようなガス惑星に関しては、固有振動の観測はきわめて困難です。ガス惑星の内部構造は、惑星磁場のデータなどを元に調べられていますが、必ずしも充分に解明されてはいません。
【Q&A目次に戻る】

小澤の不等式は、不確定性原理の拡張ではなく、測定における誤差と擾乱の間に成立する関係を表したものです。この点を誤解しなければ、量子力学の理解を深めるのに役立つ有用な式だと思います。
まず、不確定性原理について復習しておきます。粒子の位置と運動量の演算子をそれぞれ q, p 、それらの標準偏差をσ
q, σ
p と表すと、次の不等式が成立します:
σ
q σ
p ≧ h/4π (h:プランク定数)
ただし、物理量 A の標準偏差σ
Aは、
(σ
A)
2 = 〈( A -〈A〉)
2〉
によって定義されます(〈…〉は期待値)。不確定性原理の式は、位置と運動量の交換関係:
[ q, p ] = ih/2π
から厳密に導かれるもので、何ら修正の必要はありません。
量子論的な物理量の正確さに限界があることは、1927年にハイゼンベルクによって示唆されました。そこでは、位置の不正確さΔqと運動量の不正確さΔpの間に、ΔqΔp〜h のような関係式があると論じられています。この議論を踏み台にして、ワイルやケナードが数学的にきちんと導き出したのが、上に示した不確定性原理の式です。位置と運動量以外の一般的な物理量に関する不確定性原理は、ロバートソンによって導かれました。
しかし、ここで不確定性原理の解釈を巡ってブレが生じます。
ハイゼンベルクは、不正確さの関係式を導く際に、電子にガンマ線を照射して測定を行うという思考実験を取り上げました。この思考実験によると、電子の位置を測定しようとしても、ガンマ線に拡がりがあるために誤差が避けられないし、測定精度を上げようとしてガンマ線の波長を短くすると、大きな運動量を持つ光子が電子を散乱するために、今度は運動量に擾乱が生じてしまいます。この誤差Δq と擾乱Δp の間に ΔqΔp〜h という関係式が成り立つというのがハイゼンベルクの主張でした。ところが、論文の出版前に原稿を読んだボーアは、この解釈に疑義を呈しました。ハイゼンベルクの解釈は、人間の測定操作が状態を変えてしまうために正確な値が知り得ないというものなので、人間にはわからなくても粒子の位置と運動量そのものは正確に定まっていると考えることも可能です。これに対して、ボーアは、電子は波動性を持っているために、測定をするかどうかにかかわらず、位置と運動量は原理的に確定していないと喝破したのでした。物理学的に正当な不確定性原理の解釈は、ボーアの議論に基づくものです。
ハイゼンベルクは、それまで「電子は波動関数で表される波である」とするシュレディンガーの説を論破すべく立論を重ねていたので、電子の波動性を強調する立場には納得がいかなかったようです。出版された論文には末尾にボーアの異論が付記されたものの、1930年に著された非専門家向けの『量子論の物理的基礎(THE PHYSICAL PRINCIPLES OF THE QUANTUM THEORY)』では、再びガンマ線の思考実験に基づく不正確さの説明を持ち出しています。ハイゼンベルク本人がなかなか自分の解釈を改めようとしなかった結果、不確定性原理に関して、専門書にはケナードやロバートソン流の数学的に厳密な導出法が記される一方で、入門書や啓蒙書には誤差と擾乱に基づくハイゼンベルク流の杜撰な議論がまかり通るというブレが生まれたのです。
こうしたブレがその後半世紀以上も続いたのには、いくつか理由があります。測定における誤差や擾乱は、標準偏差と比べて明確に定義することが難しく、これらの関係式を求めるのはかなり面倒な作業になります。20世紀半ば過ぎまで不正確さの量子論的な限界に迫るような実験はほとんど行われていなかったので、労多くして功少ない課題に取り組もうとする人はなかなか現れませんでした。多くの物理学者は、さしたる根拠のないまま、測定誤差は標準偏差と同程度以上だと漠然と思っていたようです(小澤の議論を知るまで私もそうでした)。ところが、1980年代に入ると、レーザー光の同期や重力波の検出などに際して、量子限界が超えられるかどうかが現実的な問題として浮上してきました。ここで、誤差と擾乱に関する小澤の不等式が登場することになった訳です。
小澤の議論は、一般性をできるだけ失わないようにしながら、誤差と擾乱を定義するものです。詳しい議論は彼の論文
(例えば、小澤正直「不確定性原理・保存法則・量子計算」(日本物理学会誌、2004年3月号))に譲るとして、ここではポイントだけを紹介します。
まず、測定過程を対象と測定装置の量子論的な相互作用として一般化し、t=0 から t=T までの短い時間間隔T にだけ存在する相互作用項を考えます。対象と測定装置が測定を通じてどのように変化するかは、この相互作用項を導入したシュレディンガー方程式によって完全に記述されます。話を簡単にするため、測定装置で対象の位置 q を測定し、その際に運動量 p が擾乱を受ける場合を考えましょう(小澤の論文では一般的な物理量を扱っています)。運動量 p の擾乱Δp は、測定開始時(t=0)の運動量 p(0) と測定終了時(t=T)の運動量 p(T) の間のズレなので、標準偏差と同じように、両者の差の2乗平均の平方根として定義するのが妥当です。すなわち、
(Δp)
2 = 〈(p(T)-p(0))
2〉
となります。これは、きわめてわかりやすい定義です。一方、わかりにくいのが、位置の測定に伴う誤差Δq の定義です。誤差とは、測定開始時の対象の位置 q(0) と、測定終了時の測定装置の出力の間のズレと見なせます。そこで、その値が対象の位置の測定値として出力されるような測定装置の物理量 Q を考えることにします。Q としては、対象の位置を示すメーターに取り付けられた指針の位置を想定すればわかりやすいでしょう(ただし、測定装置の動作が量子力学によって記述されることを忘れないでください)。その上で、位置 q の測定に伴う誤差を次のように定義します:
(Δq)
2 = 〈(Q(T)-q(0))
2〉
この誤差の定義に異論のある人がいるかもしれませんが、ともあれ、この定義を採用した場合には、次の不等式が導かれます:
Δq σ
p + Δp σ
q + Δq Δp ≧ h/4π
これが小澤の不等式であり、誤差と擾乱に関する上の定義を認めるならば、一般的に導ける関係式(のはず)です
(すみません、ちゃんとフォローしていません m(_ _)m )。ガンマ線の思考実験によってハイゼンベルクが導いた式は、小澤の不等式における左辺第3項しかありません。
小澤の不等式の物理的な意味を理解するための例題として、対象を擾乱しない測定を考えましょう。2つの粒子AとBがあり、その重心が原点に固定されている(2粒子系が重心座標に関して固有値ゼロの固有状態となっている)とします。このとき、粒子Bの位置を測定すると、重心が原点に固定されていることから粒子Aの位置も判明しますが、測定操作は粒子Bに対して行っているので、粒子Aの運動量の擾乱Δp はゼロになります。もし、誤差と擾乱に関するハイゼンベルクの関係式 Δq Δp 〜 h が成り立っているとすると、(粒子Bの位置測定を介した)粒子Aの精密な位置測定は行えないことになります。しかし、小澤の不等式を使えば、Δp = 0 であっても、
Δq σ
p ≧ h/4π
という不等式が成り立つので、標準偏差σ
p が充分に大きいとすれば、測定誤差Δq がきわめて小さくなるような精密測定が許されます。この結果は、物理学者にとっては当たり前のことですが、不確定性原理をハイゼンベルク流に理解している初学者には目新しく感じられるでしょう。
小澤の不等式が重要な役割を果たすかもしれないと言われるのは、量子コンピュータに関する議論です。データを量子ゲートとレジスタの間でやりとりする際に、両者の相互作用に伴う擾乱と誤差の関係が問題になりますが、ここで小澤の不等式を適用して考えなければならないケースもあり得ます。
【Q&A目次に戻る】

人間が属している宇宙は、ほぼ一様等方な状態を維持したまま整然と膨張しているために、全宇宙に共通する宇宙時間が定義できるのです。
もし、ビッグバンが1回だけではなく、真空の相転移という形で何度も起こり、その際に生まれたベビーユニバースが互いに衝突するようなことがあれば、銀河の分布は一様ではなく、互いに近づいたり遠ざかったりと複雑な運動をするはずです。このとき、全体に共通する宇宙年齢は定義できません。しかし、WMAP(ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機)などの観測データによると、われわれの住む宇宙には(ダークマターに由来すると推測される揺らぎを除いて)異方性がほとんどなく、超銀河集団の流れといった特異的な状況は見られません。こうした宇宙は、全体が一様かつ等方だと仮定してアインシュタイン方程式を解く際に利用されるロバートソン・ウォーカー計量によって記述できます。この場合、一様に膨張する空間に対して静止している時計で計測される時間は、ロバートソン・ウォーカー計量に現れる時間座標と同じものになります。これが宇宙時間と呼ばれるものであり、特異的な(他の銀河と異なる)動きをしていない全ての銀河で通用する共通の時間となります。
この宇宙時間は、特殊相対論に登場する「観測者に固定された座標系の時間」とは異なっています。特殊相対論では、それぞれの観測者を原点とするローレンツ座標系が想定され、その座標軸は無限遠の彼方まで“まっすぐ”延ばせると仮定されていますが、こうしたリジッドな座標軸は、時間や空間が曲がっている一般相対論の世界ではあまり意味を持ちません。無理に特殊相対論の考えを持ち込んで、各銀河ごとに異なる時間を定義することも不可能ではありませんが、この時間軸をビッグバン近くまで延ばしていくと、特殊相対論に基づいて定義した時間座標と物理的な現実とのずれが顕著になって、時間座標として使い物にならなくなります。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
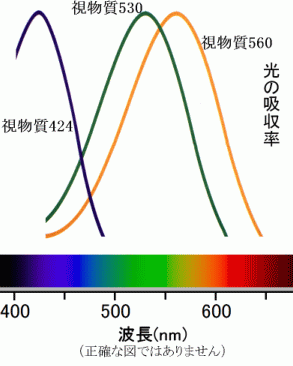 人間の視細胞(錐体細胞)には、ある範囲の波長の光を吸収して構造変化を起こす視物質(光受容タンパク質)が3種類存在しています。最も強く反応するのは、波長がそれぞれ560nm、530nm、424nmの光であり、それに応じて視物質560などと呼ばれますが、この波長だけに反応する訳ではありません。可視領域の広い範囲にわたって、2つ以上の視物質が反応します(図参照)。こうした反応は視神経を介して大脳視覚野に伝えられますが、このとき、各視物質がどの程度の割合で反応したかという組み合わせによって、色の知覚が成立します。例えば、500nmの光が眼に入射したとき、視物質424はほとんど反応せず、視物質530は光の吸収率が最大になる波長に比べて80%程度、視物質560は50%程度反応します(ここで言う吸収率とは、網膜に多数存在する視物質の中で、光を吸収して構造変化を起こすものの割合だと考えてかまいません)。この反応の組み合わせが、500nmの光に対する青緑という知覚を引き起こします。
人間の視細胞(錐体細胞)には、ある範囲の波長の光を吸収して構造変化を起こす視物質(光受容タンパク質)が3種類存在しています。最も強く反応するのは、波長がそれぞれ560nm、530nm、424nmの光であり、それに応じて視物質560などと呼ばれますが、この波長だけに反応する訳ではありません。可視領域の広い範囲にわたって、2つ以上の視物質が反応します(図参照)。こうした反応は視神経を介して大脳視覚野に伝えられますが、このとき、各視物質がどの程度の割合で反応したかという組み合わせによって、色の知覚が成立します。例えば、500nmの光が眼に入射したとき、視物質424はほとんど反応せず、視物質530は光の吸収率が最大になる波長に比べて80%程度、視物質560は50%程度反応します(ここで言う吸収率とは、網膜に多数存在する視物質の中で、光を吸収して構造変化を起こすものの割合だと考えてかまいません)。この反応の組み合わせが、500nmの光に対する青緑という知覚を引き起こします。
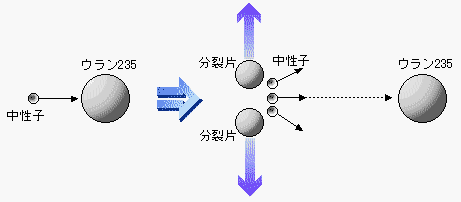
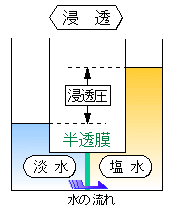 これは、浸透と呼ばれる現象の一例です。水は通すが塩は通さないような半透膜で淡水と塩水を分離していると、淡水側から塩水側へと水が自然に流れ込みます。溶液の場合は、浸透圧が力学的な圧力と釣り合うところで水の流入が止まります。しかし、ガラス瓶に入ったヘリウムガスの漏出の場合は、大気におけるヘリウムの分圧がきわめて低いので、外部への拡散がいつまでも続くことになります。
これは、浸透と呼ばれる現象の一例です。水は通すが塩は通さないような半透膜で淡水と塩水を分離していると、淡水側から塩水側へと水が自然に流れ込みます。溶液の場合は、浸透圧が力学的な圧力と釣り合うところで水の流入が止まります。しかし、ガラス瓶に入ったヘリウムガスの漏出の場合は、大気におけるヘリウムの分圧がきわめて低いので、外部への拡散がいつまでも続くことになります。
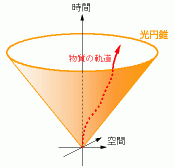 ブラックホールから物質が脱出できない訳を「強い重力に引っ張られて遠ざかれない」というように解釈すると、質量のない光子まで捉えられてしまう理由がわからなくなります。質問文にもあるように、幾何学的な構造のせいでシュヴァルツシルト面(事象の地平面)の外側には進めないと考えるのが妥当でしょう。
ブラックホールから物質が脱出できない訳を「強い重力に引っ張られて遠ざかれない」というように解釈すると、質量のない光子まで捉えられてしまう理由がわからなくなります。質問文にもあるように、幾何学的な構造のせいでシュヴァルツシルト面(事象の地平面)の外側には進めないと考えるのが妥当でしょう。
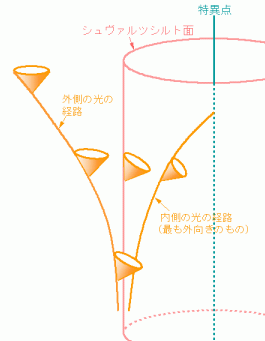
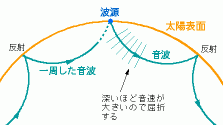 太陽の内部では深いほど温度が高く、振動波(音波)の速度が速くなります。このため、表面の波源から下方に向かって発射された音波は進行方向が上に向くように曲げられ、最終的には表面に到達してそこで反射されます。こうして表面での反射を繰り返しながら一周しますが、このとき、発射点に同じ位相で戻ってくるような振動のモードは、太陽表面の固有振動となります(右図)。対流層における乱れた対流は常に表面を揺さぶり続けているので、こうした固有振動は常時励起されています。この振動が日震です。1960年代に最初に観測された日震は周期約5分の基本振動で、現在では、太陽表面における明るさの局所的な変動パターンを元に多数の固有振動が調べられています。
太陽の内部では深いほど温度が高く、振動波(音波)の速度が速くなります。このため、表面の波源から下方に向かって発射された音波は進行方向が上に向くように曲げられ、最終的には表面に到達してそこで反射されます。こうして表面での反射を繰り返しながら一周しますが、このとき、発射点に同じ位相で戻ってくるような振動のモードは、太陽表面の固有振動となります(右図)。対流層における乱れた対流は常に表面を揺さぶり続けているので、こうした固有振動は常時励起されています。この振動が日震です。1960年代に最初に観測された日震は周期約5分の基本振動で、現在では、太陽表面における明るさの局所的な変動パターンを元に多数の固有振動が調べられています。