|
|
|
|
|
前節では、現代物理学の知見に基づいて、「空間−時間−物質−力」という古典的なスキームがいかに修正されなければならないかを示した。「空虚な空間の中に物質が存在し、これが外部から力を受けて時間とともに運動する」という描像は、もはや妥当ではない。現代物理学における《空間》とは、単なる空虚な入れ物ではなく、物理現象の担い手である場と一体化して、積極的に物理的プロセスに関与する。また、「流れる時間」というイメージも、人間が世界を認知するときの枠組みとして採用されているにすぎず、物理的な《時間》は、第4次元として空間同様の拡がりを持って存在している。さらに、《物質》についても、古典力学に見られるような自立的な──自己を他者から識別する根拠がそれ自身のうちにあるような──存在ではなく、場の変数の励起状態として定義される。その変化は、外部からの(非物質的な)《力》によって引き起こされるのではなく、ある経路に対する(経路積分の値としての)重みに差があるという形で自律的に生じる。古典的な物理学は、二元論(あるいは多元論)的な発想に基づいて、「空間の中に物質がある」「物質が力を受けて運動する」というスキームを用いていたが、現代物理学は、これらを全て一元論的な枠組みにまとめてしまったのである。
多くの人にとって、科学(特に物理学)によって記述される世界が「非人間的である」と感じられる大きな要因は、「空間の中で孤立する個物に対して外部から力が加わり、否応なしに一定の変化を押しつけられる」という描像があるからではないだろうか。まるでキューに突かれ壁に衝突しながら決まった動きを余儀なくされるビリヤードボールのように、自分が機械的に動かされ続ける存在であるとは、誰しも考えたくないだろう。しかし、現代物理学は、こうした素朴な機械論に基づく描像を、前時代的なものとして否定している。非因果的で自律的な変化を内包している量子過程Θrは、非人間的な機械論的なシステムとは一線を画すべきものである。
世界は、高次元φ空間における1つの量子過程Θrとして具現化されている。このことは、客観的な世界知に基づく存在論を展開する上で、本質的な重要性を持つ。
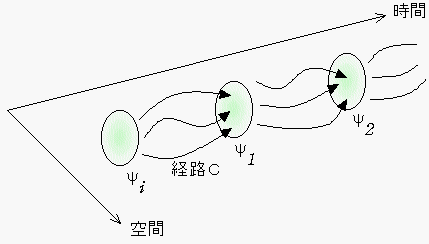
ここで、量子過程Θrの存在論的な地位について、コメントしておこう。Θrは、場の自由度に関する経路積分を元に、他と干渉しない歴史を抜き出すという形で数学的に構成されたものであり、それ自体が何らかの実体を直接的に表現するとは考えにくい。むしろ、人間の先験的概念では捉えることのできない世界の真実相を近似的に表すための形式的表現と見なすべきだろう。しかし、憶測によらない科学的な存在論を展開しようと志す場合は、たとえ形式的表現に過ぎないとしても、量子過程という概念を積極的に援用することが必要だと主張したい。理由の1つは、「空間内における物質の時間的変化」に関する記述のみが科学的だとする根本的な誤解を払拭しなければならないからである。「中枢神経細胞における膜電位の変動」を〈意識〉と同一視しようとする明らかに誤った言説を指して、科学的な議論の限界を喋々することは止めていただきたい。神経心理学の専門家には理解できないかもしれないが、神経系における協調的な興奮を、きわめて次元数の高い空間の内部に形成された単純な構築物として記述するスキームも、有り得るのだ。量子過程論に基づくこの新しいスキームは、確かに、「自然界の実態を直接的に反映したもの」と言えるような確固たる地位を獲得しているわけではない(し、そもそも、実態を直接的に反映するようなスキームを人間が作り上げることは不可能だろう)。しかし、少なくとも、「脳の存在」を自明な前提としてそこから議論を始めるような論法よりは、はるかに現実的な──客観的な記述として現実に応用する際の有効性の高い──スキームであることは確実である。こうした観点から、量子過程Θrを存在論的に有用な概念として援用していきたい。
量子過程Θrの際だった特徴は、きわめて次元数の高い空間内部に拡がっているという点である。デモクリトス流の原子論の場合、原子は、言ってしまえば空間の中にポツンと孤立している。しかし、量子過程は、こうした孤立した存在としてイメージすることができない。物質とも事象とも言えない形で、時間的・空間的な拡がりを有している。この特徴は、次章以降の議論展開において、きわめて大きな意味を持ってくる。
量子過程を直観的にイメージすることは、不可能に近い。そこには、実質的な無限が二重にも三重にも含まれているからである。第1に、量子論特有の無限次元ヒルベルト空間が登場する。非相対論的な量子力学では、座標qに対してψ(q)という(ノルムが有限の)複素関数の集合を考える必要がある。実数体で表される定義域qも、その上の複素関数の値域も、共に連続無限であり、ヒルベルト空間の元は、無限と無限を結びつける無限個の関数となる。さらに、相対論的量子力学になると、座標qの代わりに場の自由度φ(x)を考えることになる。φ(x)は、ミクロの側にもマクロの側にも際限がない。ミクロの方向で見ると、プランク長が自然界における最短の長さであり、それより間隔の小さな2点は原理的に区別できないという見方もあるが、現時点では、微小距離dxだけ離れている場の自由度φ(x)とφ(x+dx)は別々に扱わなければならないので、自由度の個数は無際限と言わざるを得ない。また、マクロの方向では、宇宙空間が無限に拡がっているという説も有力であり、そうなると、無限個のφを考える必要がある。無限個の自由度に対応する連続無限の定義域上の無限個の関数という“超絶的”なものを扱うことになるため、もはや直観は通用しないのである。
もっとも、上に掲げたような描像は、必ずしも現代物理学の常識として全ての研究者に馴染みのものになっている訳ではない。
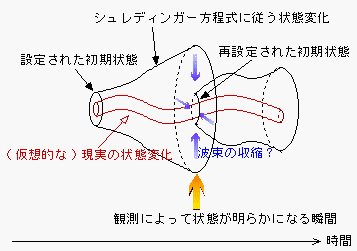 第1に、「無矛盾条件」を用いた量子過程の分割が実用的なものでないため、まだ、多くの研究者が、シュレディンガー方程式にしたがって時間とともに拡がり、観測によって状態が確定した段階で境界条件を再設定するような波動関数を使用している(右図)。こうした慣習が定着している背景には、「無矛盾条件」を現実のシステムに適用することが数学的に難しいことに加えて、応用の分野から量子力学に要求されるのが、多くの場合、初期条件を与えてその結果を予測する「初期値問題」だという事情がある。初期値問題を解く場合は、観測される時点での状態さえ正しく(確率的に)予測されるならば、中間段階でどのような状態になっているかをわざわざ考える必要はないのである。
第1に、「無矛盾条件」を用いた量子過程の分割が実用的なものでないため、まだ、多くの研究者が、シュレディンガー方程式にしたがって時間とともに拡がり、観測によって状態が確定した段階で境界条件を再設定するような波動関数を使用している(右図)。こうした慣習が定着している背景には、「無矛盾条件」を現実のシステムに適用することが数学的に難しいことに加えて、応用の分野から量子力学に要求されるのが、多くの場合、初期条件を与えてその結果を予測する「初期値問題」だという事情がある。初期値問題を解く場合は、観測される時点での状態さえ正しく(確率的に)予測されるならば、中間段階でどのような状態になっているかをわざわざ考える必要はないのである。
第2に、現時点での場の量子論の枠組みは、現実を記述するための完全な理論になっていない。「標準模型」と呼ばれ最も多くの支持を集めている素粒子論のモデル(量子色力学+電磁弱統一理論)では、同一時空点に複数の場の変数が割り当てられており、相互作用の形式も入り組んでいる。相互作用の形式をよりシンメトリックにした「大統一理論」は、1980年代初頭から繰り返し試みられている検証実験によってもその正当性が確認されず、データに適合するように理論を書き換えているうちに、かなり醜い模型に堕してしまった。また、「標準模型」「大統一理論」のいずれも、くりこみ理論が適用できないという理由で、重力相互作用だけを継子扱いにせざるを得ない。こうした閉塞状況を打開するため、「超ひも理論」など、場の量子論の枠組みを越える新しい理論体系を構築しようという試みが一部の学者によって押し進められているが、あまり成功しているとは言えないのが現状である。今後の展開次第では場の量子論の根幹が変更されかねない現階で、原理的な問題を考察するのはあまり建設的ではなく、優秀な研究者の関心を引きにくい。
(半導体デバイスの設計や新素材の開発などのために)量子力学を道具として利用している通常科学の従事者は第1の理由によって、また、根元的な理論を探求している物理学者は第2の理由によって、場の量子論に基づく科学的な世界像を構築することに積極的ではない。
しかし、たとえ多くの科学者に共有されるものでないとしても、現時点の科学的知見に基づく世界像を提出することは、哲学的に有意義な試みだと考える。古代ギリシャ以来、哲学者たちは、その時代における知見に基づいて、自然哲学の主張を展開してきた。確かに、その大半は、科学が発展する過程で実証的な見地から否定され、現在では忘却の彼方に葬り去られてしまっている。だが、こうした自然哲学の試みは、次の時代の先鋭な科学者に踏み台として利用されるならば、科学の発展に貢献し得るものである。例えば、「自然は真空を嫌う」というアリストテレスの有名な命題は、中世的ドグマの超克を目指すトリチェリら近世の科学者に、「人為的に空気を排出することによって真空を作る」という明確な目標を提供してくれた。ここで、トリチェリの真空がアリストテレスの真空とは概念的に全く別物だったという点は、さして重要ではない。アリストテレスによる自然学の体系があったからこそ、新しい学問を興すためには何をなすべきかが明確になったのである。
ついでに言えば、「超ひも理論」や「M理論」のような場の量子論を越える試みにおいても、多くの場合、「高次元空間で具現化された量子過程」という基本的な世界像は、細部に修正を加えるだけで維持できることが期待される。超ひも理論では、経路積分の変数を、時空点に割り振られた場の変数から「ひも」の変数に変更しているが、量子論的な揺らぎが「高次元空間内部に拡がった状態」という形で実現されているという点は、場の量子論と変わりない。しかも、時空をメッシュに切って各点を物理的な変数に置き換えるという(いささか場当たり的な)作業がなく、相互作用を通じて時空が二次的に派生してくるので、理論構成は場の理論よりもすっきりしていると言えるかもしれない。
次章では、ここで導入された「高次元空間で具現化された量子過程」というアイデアを武器に、《客観的世界》についての新たなアスペクトを探求する。
|
|
|
|
|
©Nobuo YOSHIDA