|
|
|
|
|
| 第3章.近代的土地利用の功罪 |
産業主義社会においては、産業の生産性を高めることが至上命題となる。経済学的には、産業に投入された資本に対して、どれだけの利得が得られたかによって、生産性が評価される(下図)。自由主義経済とは、投資対象をシフトすることによって、資本生産性を最大化するように図ることが、投資家の自由に任されている経済体制を意味する。
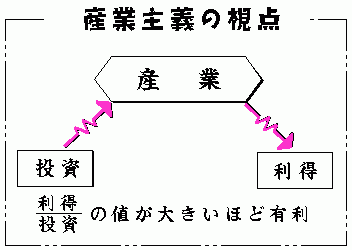
ただし、近代経済学では、投資や利得は市場価格によって数値化されるため、グローバルな観点からすると、不当な産業システムが実現されることも少なくない。特に、化石燃料や水資源などの環境財の変化は、収入/支出を表すバランスシートには記入されず、大幅に悪化して経済に影響を与える段階にならない限り生産性を左右しないので、産業構造の変化を促す圧力にならない。例えば、化石燃料は、太陽エネルギーの固定というプロセスの産物であり、人工的に同じものを作るには相当のコストが必要な“財”であるにもかかわらず、経済学的には、ストック(保有資産)として評価されず、採掘・運搬コストだけがカウントされる。このため、物理的に見ると、産業活動では、資源を蕩尽し廃棄物を環境中に排出する過程がかなりの部分を占めるにもかかわらず(下図)、生産性評価においてはほとんど無視されることになる。
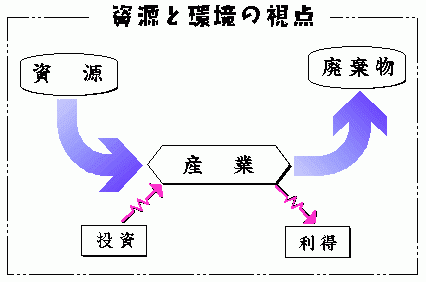
生産性を高めようとする近代化の流れの中で、その歪みが極端な形で現れたのが、近代的な土地の利用法である。限りある生産財として占有の対象とされてきた土地は、そこから最大限の収量を得ようとする活動が繰り広げられる場であった。文明の初期の段階では、森林の開墾や灌漑施設の設営という形で農業の収量を高める試みが中心であり、人口規模が小さいこともあって、事態はそれほど深刻なものとはならなかった。しかし、近代産業が勃興して以降は、安価な石油・石炭から得られる資材を大量に投入して土地の生産性をギリギリまで引き上げようとする努力が、全体的な展望のないままに過剰に推進されることになる。こうして、その土地が環境の中で果たしてきた機能が失われ、かえって人類の財産が減少するという皮肉な結果を招くケースが少なからず見受けられる。
この章では、土地を産業に役立てようとするあまり重大な環境破壊を引き起こした事例を考察する。
©Nobuo YOSHIDA