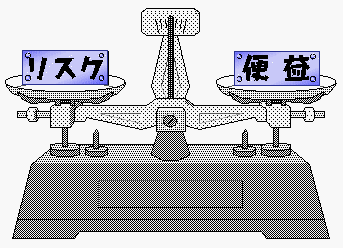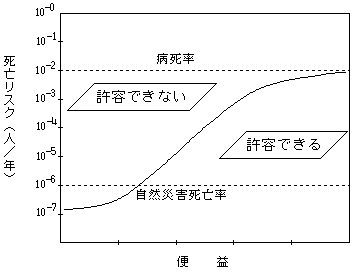§6.化学物質とどうつきあうか
20世紀には膨大な化学物質が合成され、産業や生活のさまざまな局面で活用されてきた。われわれの生活が、人間が作り出した化学物質によって豊かで便利なものになったことは、改めて指摘するまでもないだろう。
化学物質の積極的な利用が20世紀に急速に進んだ理由は、単純ではない。まず、2度の大戦が技術開発を促したことを指摘しなければならないだろう。例えば、第1次世界大戦において、ドイツは毒ガス兵器として利用するために塩素の研究を進めたが、その成果は、後にPCBやDDTなどの有機塩素化合物の開発に応用される。また、日本がゴムの産地を占領したために、アメリカで合成ゴムの開発に拍車が掛かったという事実もある。このほか、第1次世界大戦に疲弊したヨーロッパに代わって1920年代にアメリカが急成長を遂げたことも、化学産業の勃興と密接な関係を持つ。開拓者精神を受け継ぐアメリカは、やや保守的なヨーロッパ諸国とは異なり、有用な新技術を直ちに産業に取り入れて役立てることに貪欲である。当時の最先端技術者が生み出したエレクトロニクス技術や新素材をどこよりも積極的に利用したのは、新興国アメリカの産業人であった。また、消費者の立場にある多くの市民も、科学技術の成果として生活の利便性が向上することを期待していた。
化学物質に危険な側面があることが一般の人々に認識されるようになるのは、1960年代に入ってからである。1962年に出版されたレイチェル・カーソン著『沈黙の春 ( Silent Spring )』は、DDTのような化学物質を無節操に大量使用すると、生態系を破壊する危険があることを指摘した。『沈黙の春』は、ややもすると過度に感傷的・文学的な表現が鼻につくこともあって、農薬メーカーなどからの厳しい批判に晒された。しかし、DDTの過剰使用と生態系の異常の間に密接な因果関係があることは、その後の調査で実証され、カーソンは、環境問題のパイオニアとしての名声を獲得する。さらに、PCB・フロン・環境ホルモンと、有用だと思われていた化学物質の危うい側面が、次々に明らかにされていく。
DDTなどの農薬の危険性に関しては、「近代文明と環境問題−農業生態系」を参照してください。
化学物質が持つ危険性は、野生生物の生態系のように日々の生活と直接関わりないところにのみ現れるわけではない。日常生活の中でも、化学物質過敏症のように化学物質が危害を及ぼすことがある。もちろん、多くの化学物質は快適で便利な生活を送る上で不可欠あり、潜在的な場合も含めて危険性を持つ全ての化学物質を排除するというアイデアは非現実的である。こうした中で、われわれは、技術に潜む危険性を正当に評価する方法を模索しながら、「いかに化学物質とつきあうか」という命題を真剣に考えていかねばならない。
化学物質過敏症
大半の人には何の危害も生じない化学物質が、ある人にとっては激越な身体反応を引き起こすことがある。こうした症状は化学物質過敏症と呼称されるが、発症のメカニズムは十分には解明されていない。患者数はアメリカで人口の10%を超えるという説もあり、化学物質を日常的に使用する先進国で、大きな問題になりつつある。
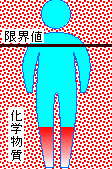 臨床的にはアレルギー反応と類似しており、特定の化学物質に対して感作が生じると、次回からは、安全基準を大幅に下回るきわめて微量な化学物質に接しただけで身体反応が生じる。こうした現象は、膨大な化学物質に曝され続けたために身体が耐えられる限界値を超えてしまった状況を表すと推測され、しばしば水がいっぱいになったコップに喩えられる(右図)。症状としては、頭痛・皮膚炎・喘息・下痢や便秘・運動障害・手足の冷えやしびれなどが報告されているが、個人差が大きく一律には捉えられない。原因物質もさまざまであり、ホルムアルデヒド・パラジクロロベンゼン(防虫剤)・トルエン(有機溶媒)・キシレン(有機溶媒)などがよく知られている。
臨床的にはアレルギー反応と類似しており、特定の化学物質に対して感作が生じると、次回からは、安全基準を大幅に下回るきわめて微量な化学物質に接しただけで身体反応が生じる。こうした現象は、膨大な化学物質に曝され続けたために身体が耐えられる限界値を超えてしまった状況を表すと推測され、しばしば水がいっぱいになったコップに喩えられる(右図)。症状としては、頭痛・皮膚炎・喘息・下痢や便秘・運動障害・手足の冷えやしびれなどが報告されているが、個人差が大きく一律には捉えられない。原因物質もさまざまであり、ホルムアルデヒド・パラジクロロベンゼン(防虫剤)・トルエン(有機溶媒)・キシレン(有機溶媒)などがよく知られている。
シックハウス症候群 : 建材に使用されるホルムアルデヒドなどが原因となって発症する化学物質過敏症で、新築ないしリフォームして間もない家に住む人に起きやすい。2001年に「室内空気対策研究会」によって行われた調査によると、対象になった4600戸のうち、ホルムアルデヒドでは27.3%、トルエンでは12.3%の家屋で、室内濃度が厚生労働省の定めた指針値を上回った。新築の住宅では化学物質の濃度が低くなる傾向が見られたが、これは、シックハウス症候群に配慮した建材が普及したためではないかと考えられる。学校内の建材や文房具から揮発した化学物質によって発症する化学物質過敏症は、特に「シックスクール症候群」と呼ばれ、不登校を生む原因の一つとされる。
杉並病 : 1996年に杉並区井草にゴミ中継所が稼働し始めてから、周辺住民数百人が悪心・発熱・体の痛み・皮膚の黒ずみや炎症など多様な症状を訴え、「杉並病」として社会問題化した。これは、プラスチックなどの不燃ゴミを圧縮する際に多種類の化学物質が放出され、その一部が化学物質過敏症を引き起こしたものと推定される。2000年4月に、都の設置した専門委員会は「中継所の排水から発生した硫化水素が健康被害の原因だと推定される」という調査報告を提出した。しかし、同年10月には、杉並区が、「環境調査によると、排出される化学物質は全て法令基準以下になっている」との理由で『安全宣言』を出している。これに対して、健康被害を訴える住民団体は強く反発している。
リスク・アセスメント
PCBやフロンなどの例を見てくると、技術者たちの犯した共通の失敗が明らかになってくる。簡単に言ってしまえば、長期的・広域的視野が欠落し、環境リスクへの配慮が欠けていたということになろう。ただし、開発に当たった技術者を直ちに批判することはできない。彼らは、従来品よりもすぐれた性能を持つ素材を開発することに全力を傾注し、充分な成果をあげたのだから。こうした新素材が開発された19世紀末から20世紀前半には、まだ、リスク・アセスメント(危険性の評価)を行う体制が整っておらず、好ましい性質を闇雲に追い求めることに手一杯で、その副作用にまで目が行き届かなかったことはやむを得ないのかもしれない。
当然のことながら、科学・技術の水準が向上し、研究・開発も組織化されている現在においては、過去の事例から教訓を引き出し、十全な対策を講じねばならない。ここで得られた教訓とは、長期的・広域的視野を持つリスク評価の重要性だろう。もちろん、フロンによるオゾン層破壊のように、製造を開始した当初の科学技術の知見では予想もされないような事態が発生するケースもあるだろう。だが、たとえ事前に予想できなかったとしても、生産を続けている限りは製品のリスク評価を継続して行うことによって、かなりの程度まで、リスクの軽減をはかることが可能になると思われる。
もっとも、リスクがあるとわかったからといって、単純に当該製品を斥ければよいというものでもない。PCBにせよフロンにせよ、最も好ましいと思われた性質が、裏を返せば、環境に多大な害悪をなす現況となっていた点に注意していただきたい。この2つについては、害悪が利益を上回っていたので、社会的な規制の対象になったが、常にそうなるとは限らない。良い例が自動車である。自動車は、日本だけで年間1万人を越える事故死者を出すほか、排ガスに含まれる汚染物質、特に窒素酸化物が大気汚染を増悪している。にもかかわらず、その経済的な役割がきわめて大きいため、社会で許容されているという現状がある。リスクを排除するだけでなく、諸々の要素を総合的に勘案するバランス感覚が必要なのである。
現実の社会では調整しなければならない要素が数多く存在するが、最も単純化された議論として、「利便性と安全性を秤にかける」という考えを取り上げてみよう。
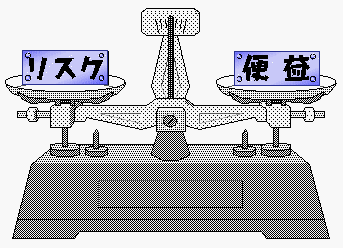
具体的には、縦軸に(安全性の裏返しである)リスクを、横軸に利便性を表す経済的な便益をとって、どの領域ならば社会的に許容されるかを考えてみればよい。リスクとは、一般には、被害の重大度とその発生確率の積として定義され、ガンのような潜伏期間の長い疾病を惹起する場合には、生存期間を含めた評価が必要になるはずだが、ここでは単純に年間死亡確率をとることにする。
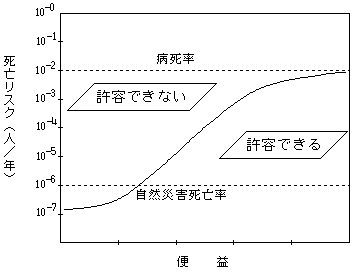
常識的に考えれば、この座標軸上に右肩上がりのグラフが描かれ、それより下が社会的に許容される範囲となるはずである(便益が大きければ、少々のリスクも許容されることになる)。ただし、リスクは無制限に容認されるわけではなく、社会的に合意されたある上限が存在すると考えられる。日本では、病気による死亡率(年間100分の1程度)あたりが、許容されるリスクの上限となるだろう。一方、自然災害による死亡リスクの1/10(年間1000万分の1程度)を下回れば、ほとんど社会的に問題とされなくなると考えられる。
現代日本で総合的に見て最も危険な製品といえば、間違いなく自動車であるが、このリスクが許容される範囲の上限付近に位置することになる。原子力発電所のリスクは、自動車を下回ると考えられるが、自動車と異なって火力発電所という代替物があるため、許容すべきかどうかの判断は難しい。
このように、リスクと便益を秤にかけて調整することによって、より安全で豊かな社会を実現できれば、実に喜ばしいことなのだが、このほかに考慮しなければならない要素も多く、単純に評価できないのが現状である。さらに、長期的・広域的なリスクを論じようとすると、あまりに不定性が大きくなって、議論が混迷する。例えば、フロンは、リスクがきわめて低い一方で、便益が大きくて、完全に許容範囲に入っていると思われたのだが、科学者のあずかり知らぬところで害悪を生んでおり、実際のリスクは予想以上に高かった。
一般的に言って、環境リスクの評価は、単なる急性毒性の判定とは異なって、膨大なファクターを考慮しなければならず、科学的に信頼できる数値をはじき出すのは、きわめて難しい。例えば、次に掲げる物質は、急性毒性がない(小さい)ためリスクは小さいと推定されていたが、環境中に蓄積されると大きな環境被害をもたらすことが判明している。ただし、どこまで使用(排出)規制をすべきかについては、現時点でも見解が分かれている。
-
二酸化炭素
-
二酸化炭素は、人間に対する化学毒性を持たないため、従来、排出規制の対象になることはなかった。1850年から1985年までの間に、森林を農地に転用したことにより115Gt、化石燃料の燃焼(および他の工業活動)によって200Gt(いずれも炭素原子換算)が大気中に放出されている。放出された二酸化炭素の多くは、光合成のために植物に吸収されたり、海水に溶け込むが、一部が残留することになる。1980年代では、年平均7Gtもの二酸化炭素が放出され、半分近くが大気中に蓄積されていると考えられている。
これほど大量の二酸化炭素を放出しながら、多くの学者がその悪影響を看過してきたのは、化学反応をもとに環境毒性の有無を判定していたためである。実際、有害とされる化学物質も、高温で二酸化炭素と水蒸気に分解できれば、完全にクリーンになったと見なされ、排気塔から自由に排出することが許されていた。
ところが、近年になって、二酸化炭素は、化学毒性ではなく、物理的な性質を通じて環境を破壊することが判明した。地表に到達した太陽光線は、いったん地面に吸収された後、波長の長い赤外線となって宇宙空間に放出される。このエネルギー収支に基づいて、大気温度が熱力学的に決定される。ところが、大気中の二酸化炭素は、他の気体分子よりも赤外線を吸収し、周囲の空気を暖める性質がある。このため、エネルギー収支の微妙なバランスが崩れて、地球規模で気温が上昇することになると予想されている。
こうした地球温暖化がどの程度の規模で起き、どれほどの影響を与えるかは、必ずしもはっきりしていないが、海面上昇や降水量の変化を通じて、多かれ少なかれ人間社会に打撃を与えることは確実である。
-
アスベスト(石綿)
-
アスベストとは、主にケイ酸からなる繊維性鉱物を綿のようにほぐしたものである。基本成分が岩石と同じものなので、化学的にきわめて安定で不燃である。また、形態が繊維状をしているので、隙間に多量の空気を含んでおり、密度が小さく保温性が高い。このため、断熱材・保温材として建築物に使用されることが多かった。
アスベストの危険性は、アスベスト鉱山に従事する労働者に肺の病気が多いことから、かなり以前から囁かれてはいたが、十分に認識されてはいなかった。なにしろ、岩石と同じ成分である。アスベストに中毒するようなら、土埃を吸っても中毒してしまい、人間は地上では生きられないはずだ・・・
だが、アスベストの毒性は、むしろ、化学的な安定性そのものに由来するものだった。壁や天井に断熱材として吹き付けられたアスベストは、そのままでは環境中に放出されることはないが、表面が剥離したり傷ついたりすると、そこから外部に飛散する。形状がきわめて細い繊維状であるため、そのまま空気中に漂い、呼吸の際に体内に入り込んで、最終的には繊維が肺胞に突き刺さった状態になる。人体は大概の物質を分解する能力を持っているのだが、アスベストは、岩石のように頑丈なので、酵素などでは分解することができず、そのまま肺を傷害し続ける。この結果として引き起こされるのが、アスベスト症と呼ばれる肺の病気である。さらに、長期にわたってアスベストに曝露されると、特殊な肺ガンを発症することが知られている。
フロンの場合は、化学的に安定である故に大気中に貯留することになったが、アスベストは、同じ理由で体内にとどまり続けて悪影響を及ぼすのである。
-
プラスチック
-
プラスチックは、可塑性を持つ高分子有機化合物の総称で、開発は19世紀後半から進められていたが、産業化されたのは、重合技術が進む1920年代以降である。プラスチックの中には、ポリ塩化ビニルなど化学的な毒性を有するものもあるが、近年は、消費者への配慮もあって、化学毒性のない(きわめて小さい)ものが開発されている。
プラスチックの長所は、(可塑性があって加工が容易なことに加えて)金属や木材のように腐ったり錆びたりしない点である。言い換えれば、生物による代謝や空気中の酸素による酸化をされにくいことであり、化学的な安定性の現れでもある。
ところが、最近とみに顕著になってきたように、こうした分解されにくい物質は、廃棄物としてゴミ問題を引き起こすことになる。生体反応を起こさないから毒性もなく腐食もしないので産業上の応用という点では実に好都合だったのだが、その同じ性質が、結果的に別の懸案を生み出したわけである。最近では、わざわざ、微生物に分解されやすいプラスチックが開発されてきている。
上で紹介した例は、危険性がかなり明確になっているものだが、現在なお、危険かどうかが判然としていないケースもある。最近話題になっている電磁汚染の問題を挙げておこう。電化製品や送電線から放射される電磁波が健康に悪影響を及ぼさないかどうかは、数十年間にわたる論争を経て、いまだに結論が出されない難問である。ここ数年、いくつかの研究成果は上がっているが、「被害が発生している証拠はない」という程度のデータしか集まっていない。電磁波が第2のフロンになるのか、あるいは、単なる杞憂で終わるのか、科学的にはいまだはっきりしないわけだが、この段階で、どのような対策をとるべきか、一考してみる価値はあるだろう。
©Nobuo YOSHIDA
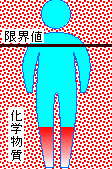 臨床的にはアレルギー反応と類似しており、特定の化学物質に対して感作が生じると、次回からは、安全基準を大幅に下回るきわめて微量な化学物質に接しただけで身体反応が生じる。こうした現象は、膨大な化学物質に曝され続けたために身体が耐えられる限界値を超えてしまった状況を表すと推測され、しばしば水がいっぱいになったコップに喩えられる(右図)。症状としては、頭痛・皮膚炎・喘息・下痢や便秘・運動障害・手足の冷えやしびれなどが報告されているが、個人差が大きく一律には捉えられない。原因物質もさまざまであり、ホルムアルデヒド・パラジクロロベンゼン(防虫剤)・トルエン(有機溶媒)・キシレン(有機溶媒)などがよく知られている。
臨床的にはアレルギー反応と類似しており、特定の化学物質に対して感作が生じると、次回からは、安全基準を大幅に下回るきわめて微量な化学物質に接しただけで身体反応が生じる。こうした現象は、膨大な化学物質に曝され続けたために身体が耐えられる限界値を超えてしまった状況を表すと推測され、しばしば水がいっぱいになったコップに喩えられる(右図)。症状としては、頭痛・皮膚炎・喘息・下痢や便秘・運動障害・手足の冷えやしびれなどが報告されているが、個人差が大きく一律には捉えられない。原因物質もさまざまであり、ホルムアルデヒド・パラジクロロベンゼン(防虫剤)・トルエン(有機溶媒)・キシレン(有機溶媒)などがよく知られている。