
「全ての素数の積」については初めて耳にしました。この手の話題はどうせζ(ゼータ/ツェータ)関数絡みのはずなので、関連する本をパラパラとめくればすぐにわかる……と思いきや、出ていない! インターネットで検索した結果、どうも質問にある結果は、「2ちゃんねる」の掲示板で新定理として提案されたもののようです。しかし、そこで示された「証明」なるものは、いろいろと問題をはらんでいて正当化できそうにありません。ともあれ、まずは議論のアウトラインを示してみます。
ζ関数に関しては
別の解答でも説明しましたが、もともとは次の級数で定義される関数のことです。
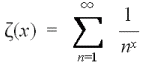
この級数は、xの実部が1より大きいときに収束します。ζ関数が素数と深くかかわっていることは、18世紀にオイラーによって示されました。特に、次の関係式は、ζ関数のオイラー積表示として知られています。
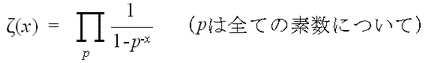
ζ関数がオイラー積で表されることの証明は多くの数論の本に書いてあります(厳密なことを言わなければ、高校レベルの数学の知識で理解できるはずです)。
さて、オイラー積で表されたζ(x)の対数を取ってからxで微分すると、次のようになります。
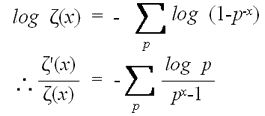
xとして適当な値を選ぶことで右辺の分母をうまくファクターアウトし、Σ(
log p) =
log(Π
p) という式を作れたならば、全ての素数の積をζ関数で表すことができますが、私はここから先に進めませんでした。
もっとも、全ての整数の積をζ関数で表すことならできます。ζ(x)を級数で表しておいて両辺をxで微分すると、次のようになります。
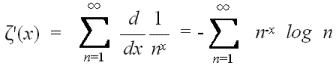
ここで、x=0 と置けば、
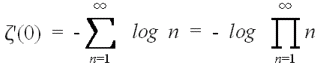
となり、ζ関数の特殊値を使えば、
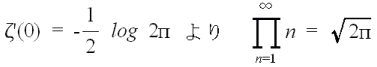
と求められます。
「何かおかしい」と感じた人は正常です。なぜ、だんだん大きくなる数の無限積が、たかだか2.5程度の数になるのか? これは、いわゆる正則化という数学的な方法論を用いたからです。
例えば、次のような簡単な式を考えましょう。
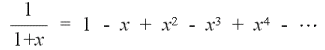
この等式は、級数が絶対収束する |x|<1 のときには完全に正しいものです。しかし、x=1 と置くと、右辺の級数は
1 - 1 + 1 - 1 + 1 - …
となって振動するので、収束しません。一方、左辺の関数の方は何の問題もなく1/2という値になります。つまり、級数の収束域から出ると、級数と関数は一致せず、上の等式は成り立たなくなるのです。とは言え、左辺の関数は、収束域で級数と一致するように定義された関数を域外にまで滑らかに拡張した−−数学の表現を用いると「解析接続」した−−ものなので、級数そのものの定義を拡張して収束域外でも値を持つようにしたと見なすこともできます。解析接続した関数を使って収束しない無限和の値を定義することは、「正則化」という数学的手法の一例です。ちなみに、上の等式で x=-2 と置くと、
-1 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + …
となります。ζ関数を使って全ての整数の積を求めた先の計算は、無限積に同様の方法を適用したものです。ζ関数による正則化は、一般に「ζ正則化」と呼ばれています。
ここで、最初の質問に戻りましょう。「全ての素数の積」ではありませんが、単純に計算したのでは値が定まらない無限和や無限積でも、正則化の方法によって有限の値にすることができます。これを、「何らかの物理的な現象と関連付けて考え」ることは可能でしょうか?
(以下の議論は少し専門的になります)
私の考えを言わせていただければ、正則化はあくまで人間が計算を行う際のテクニックであって、物理的な現象と直接結びつくものではありません。ζ正則化を場の量子論における「くりこみの手法」になぞらえる人もいますが、基本的な考え方が異なっています。場の量子論では、「くりこみ変換」(「くりこみ群」とも言う)という有限量だけを扱う変換理論があり、変換の極限で無限大が現れることが知られていますが、この無限大は理論の適用限界を逸脱して計算を行ったために生じた虚構で、物理的な世界にはもともと存在しないはずのものです。実際に計算するときには、有限なくりこみ変換があまりに難しく、積分範囲に無限大が現れる領域を含めた方が簡単なので、積分の定義を適当に変更するという一種の正則化によって有限化しています。しかし、そこには「観測される物理量の値が正則化の手法に依存してはならない」という厳格な条件が課せられます。正則化は人間のための計算テクニックにすぎないという前提があるからです。
ただし、物理現象に関する一般的なイメージが計算テクニックに依存している場合には、正則化の手法が物理現象と結びついているように見えることもあります。場の量子論の計算を行う際、しばしば結合定数による摂動展開が利用されます。この手法を使うことにより、場の相互作用がまるで素粒子の交換によって生じるかのように表されます。「物質の根元は素粒子である」というイメージは、摂動展開で計算することからもたらされたものです。ところが、結合定数のべき級数として表される摂動展開は、絶対収束しないことが示されています。つまり、この摂動展開自体が数学的にかなり危うく、何らかの方法で正則化しなければ、級数の和が定義できなくなるおそれがあるのです。そもそも、実際の物理量は結合定数の滑らかな関数になるはずですから、困難の原因は、べき級数に展開したことにあるはずです。したがって、摂動展開の正則化は、べき級数を解析的な関数で置き換える形で行うのが自然です。こうした正則化は、ζ正則化と関連づけられる可能性があります。もちろん、べき級数で表した時点で本来の物理現象から乖離した記述になっていたので、物理現象そのものが正則化と結びついている訳ではありません。しかし、正則化を通じて素粒子のイメージでは理解できない(非摂動論的な)効果が表面化してくるため、まるで物理現象が深いところで正則化とかかわっているかのような印象を与えることになるかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

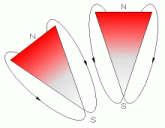
角錐の形をした磁石の側面同士を近づけると、それまで底面から頂点へと伸びていた磁力線が圧縮されて磁束密度(磁場の強さ)が増大します。さらに磁石を押しつけて接着させようとしたときに何が起きるかは、磁石の素材や磁石の近づけ方によって異なります。
1つの可能性は、磁石間のわずかな隙間に磁力線が閉じ込められるというものです。もともと磁石のN極同士、S極同士をくっつけようとしているのですから、強い反発力が働きます。磁気的なエネルギー密度は磁束密度の2乗に比例するので、隙間を完全になくそうとすると無限大のエネルギーを外から供給しなければなりません。このため、どうしてもわずかな隙間が残って、そこから磁力線が漏れ出てくることになります。
もう1つの可能性は、磁石の磁化が変化するというものです。強磁性体は、近隣のスピンが同じ向きに配向する性質を持っており、全体が磁化されていないときにも、内部には、スピンが同じ向きになった磁区(自発磁化の領域)がいくつも形成されています。磁石とは、外部磁場の作用で強磁性体全体を1つの磁区にしたものです。ところが、同じ向きの磁石を密着させると、側面にはN極からS極に向かう磁場が作用するため、この部分に磁石内部とは逆向きの磁区が形成されていきます。このとき、底面のN極から頂点のS極に向かう磁力線の一部は、この磁区を通るようになります。磁石を完全に密着させた場合には、磁力線は強磁性体内部で閉じてしまい、外部には出てきません。
いずれの場合にせよ、サッカーボール形の磁石から遠方へと磁力線が伸びることはなく、N極だけの磁石にはなりません。
【Q&A目次に戻る】

ゾウリムシの走電性は、繊毛の動きが細胞の膜電位によってコントロールされることで生じます。
細胞表面を覆う細胞膜には、イオンを能動的に輸送するイオンポンプや、特定のイオンしか通さないイオンチャネルが存在しているため、細胞膜の内側と外側ではイオンの組成が異なっており、その結果として、細胞の内外に電位差が生じています。この電位差は膜電位と呼ばれ、通常は、細胞内が負になるように分極しています。細胞が定常状態にあるときの膜電位が静止膜電位であり、静止膜電位に対して、より電位差が大きくなった状態を過分極、電位差が小さくなった(あるいは正負が反転した)状態を脱分極と言います。
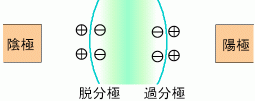
膜電位の変化は、さまざまな生化学的反応を引き起こすことが知られています。ゾウリムシの場合は、(イオンチャネルの透過性の変化などを介して)表面にある繊毛運動の向きを変える効果があります。繊毛運動は、ちょうど平泳ぎの腕のような周期的な動きを繰り返すことで、一定の向きに進む力を生み出しています。膜表面の分極が通常のときは前進させる向きに繊毛が動いており、過分極になるとこの動きが強められますが、脱分極状態になると、動きが停止したり逆に後退させる向きに動いたりするようになります。
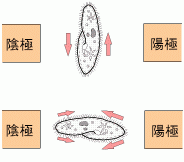
ゾウリムシのいる環境に電圧を加えると、陰極に近い側では外部電圧が膜電位と逆向きになるので脱分極に、陽極に近い側では過分極になります。このため、陰極に近い側の繊毛は後退の運動を、反対側の繊毛は前進の運動を行います。ゾウリムシが電場に対して垂直方向に向いているとき、この繊毛運動は体を回転させ陰極の方を向かせる作用を引き起こします。ゾウリムシが陰極を向いたとき、体の前部にある繊毛は(陰極に近く膜電位が脱分極になるので)後退の運動を、後部にある繊毛は前進の運動を行いますが、全体では脱分極による後退よりも過分極による前進の力が勝って、陰極に近づいていくことになります。
脱分極・過分極によるコントロールは、多くの生物に見られる一般的なものです。例えば、人間を含む脊椎動物では、細長い神経細胞の一端で生じた脱分極が軸索に沿って伝わる過程によって、感覚受容器から脳へ、あるいは脳から筋肉へと向かう神経信号を伝達しています。ゾウリムシは単細胞生物なので、いわば全身が神経細胞です。体の一部に熱や酸などのさまざまな刺激が作用すると、これがきっかけとなって脱分極が生じ、熱や酸を避けるような後退運動が引き起こされます。ゾウリムシのもともとの生活において、膜電位の脱分極・過分極は、外部刺激の受容に始まる一連の生化学的過程のワンステップにすぎないはずですが、人間が外から電圧を加えると、物理的に脱分極・過分極が生じて、走電性というゾウリムシにとっては何のメリットもない振舞いが見られるのです。
【Q&A目次に戻る】

Garrett Lisi が提案したのは、5つある例外型リー群の1つ「E8」によって、全ての物質粒子と相互作用(重力を含む)を統一的に記述する一種の究極理論です。究極理論の候補としては超ひも理論が有名ですが、この理論が10次元(あるいは、その発展形であるM理論が11次元)の時空を必要としているのに対して、 Lisi の理論は4次元の時空で記述できるというメリットがあります。
私は、 Lisi の理論の正当性を評価できるほどきちんと勉強していません。何人かの物理学者によって、この理論に大きな欠陥が存在することが指摘されたようですが、その批判が妥当かどうかもわかりません。ただし、個人的なことを言わせていただければ、私の趣味に合う理論でないことだけは確かなようです。
1970年代前半に確立された素粒子の標準模型は、SU(3)×SU(2)×U(1)という群で表されるゲージ対称性を持っています。この模型は実験結果と高い精度で一致しているものの、究極の理論と言うには群構造が複雑すぎます。そこで、こうした群を全て部分群として含むようなSU(5)やO(10)のような巨大な群によって素粒子間の相互作用を統一するという大統一理論が提案されました。 Lisi の理論は、素粒子の標準模型だけでなく、SO(3,1)という対称性を持つ重力理論も含めて、E8なる1つの群にまとめてしまおうというものです。さらに、ゲージ対称性という「束縛条件」があるシステムを量子化すると、反交換関係(フェルミオンの場が従う量子条件)を満たすゴーストが現れるという性質を利用して、フェルミオンである物質粒子の存在をも説明しようとしています(物質粒子がゴーストなのは変だと思いますが…)。つまり、基本的なアイデアは、物理法則が巨大な群によって記述されることを大前提として、そこから観測されている素粒子と対称性を全て導き出そうというものです。私は、このアイデアがどうにも気にくわないのです。
われわれが目にする3次元空間にはO(3)という対称性がありますが、この群は先験的に与えられたものではありません。3次元空間において「どの方向も特別ではない」という一般的な性質を認めれば、そこから導くことができるのです。言い換えれば、群の構造が基本的な物理法則として前提とされるのではなく、一般的な性質を表現するための手段として群が使われているのです。これは、物理現象の中に群の構造が“自然に”現れているケースと言えるでしょう。素粒子の標準模型にユニタリー群が現れる理由はよくわかりませんが、それに先立つゲルマンの八道説(u,d,sという3種類のクォークがSU(3)対称性を示すという理論)については、対称性の起源がはっきりしています。実は、3種類のクォークは、厳密な数学的対称性としてのSU(3)に従っていたわけではなく、似た性質を持つ3種類の粒子が存在することによる近似的な置換対称性(あるクォークを別種のクォークと置き換えても何も変わらないこと)を示していただけなのです。ユニタリー群と置換群の表現の間には密接な関係があるので、まるでSU(3)対称性があるかのように見えていたわけですが、これも、(似た粒子が存在するという)一般的な性質から自然に導かれる群でしょう。ゲージ対称性のような局所的な対称性に関しても、その起源を自然なものとして理解したいというのが、私の希望です。ところが、 Lisi の理論では、起源も何も理解しようのない巨大で複雑な群E8が、あらゆる物理現象の基礎にあるとされています。なぜ自然がこんな化け物のような対称性を持っていると仮定しなければならないのか、考え始めると気分が悪くなってきます。この段階で、 Lisi の理論を勉強しようという意欲はなくなりました。
もっとも、 Lisi 自身、自分の理論が正しい可能性は小さいとコメントしているようなので、ちょっと安心です(超ひも理論が正しい可能性はさらに小さいとも言っていますが)。付け加えて言えば、 Lisi はカリフォルニア大学サンディエゴ校から物理学のPhDを得ながら、研究所や大学には就職せず、サーフィンとスノーボード(および自然についての思索)に明け暮れているとのことで、何とも親近感を覚えてしまいます。
【Q&A目次に戻る】

こんにちアメリカやブラジルでガソリンの代替燃料として利用されているバイオ燃料は、トウモロコシのデンプンやサトウキビの糖分などから作り出したエタノールを添加したものですが、食物の供給不足を引き起こすほか、原料を栽培するために森林伐採が行われるといった問題もあり、決して環境負荷を小さくするものではありません。そこで注目されているのが、食用にならないセルロース(リグノセルロース)から作るセルロースエタノールです。
セルロースは、これまで農業廃棄物として処分されてきたトウモロコシの葉や麦ワラ、農作物として利用されていない雑草、果ては木屑や古紙の中にも含まれているため、原料の生産には費用がほとんど掛かりません。問題は、原料からエタノールを作り出すまでの工程です。この工程は、(1)絡まりあっているセルロースとリグニンの分離、(2)セルロースの加水分解による糖の生成、(3)発酵によるエタノールの産生−−の3段階に分かれており、いずれも技術的な障碍を抱えていますが、特に(2)のセルロースの分解が難しく、コストを押し上げる要因となっています。2004年のデータによると、エタノールの生産工程だけで1リットル当たり500円程度掛かる計算になります(これは当時の技術に基づく大ざっぱな見積もりで、新技術の開発により10分の1以下に低減できるという期待もあります)。また、時間を要する割に少量しか生産できないので、今の段階では、石油の代替燃料にはなりません。
セルロースの加水分解を効率的に行うためには、セルラーゼ(セルロースを加水分解する酵素)を利用する必要があります。セルラーゼを分泌する微生物としては、シロアリの腸に生息する原生生物などが知られていますが、これらをバイオリアクター内部で培養して高い酵素活性を維持することは、技術的に困難です。セルラーゼの遺伝子を酵母や大腸菌などに組み込む研究も進められていますが、工業的に充分な量の酵素を産生することはまだできません。高いセルラーゼ生産能を持つ糸状菌を利用する研究も、緒についたばかりです。酵素を使わずに高温の反応漕内部で分解することも可能ですが、生産効率は実用にならないほど低くなります。
悲観的なことばかり書いてきましたが、セルロースエタノールに関する研究開発は急ピッチで進められており、今後10年程度で商品化され、2030年までには石油に対抗できる燃料になると予測する研究者もいます。日本では、地球環境産業技術研究機構(RITE)と本田技研が積極的に開発を行っており、2006年には、エタノールの生産効率を従来の何倍にも高くする遺伝子組み換え細菌を作り出しています。
【参考文献】G.Stephanopoulos, 'Challenges in Engineering Microbes for Biofuels Production,' (Science 315 (2007) 801)
【Q&A目次に戻る】

私は化学結合の理論にはあまり詳しくありませんが、この質問はかなり有名なものらしく、アメリカのいくつかのサイトで解答されていました。ここでは、その内容をふまえてお答えいたします。
気体や液体に色が付いて見えるのは、特定の波長の光が吸収されるからです。光の吸収に関与する酸素分子のエネルギー準位は、(1)軌道電子によるもの、(2)2原子分子の回転によるもの、(3)2原子分子の振動によるもの−−の3タイプに分けて考えることができます。このうち、(2)の回転エネルギーはマイクロ波の領域に、(3)の振動エネルギーは、回転よりも2桁ほどエネルギーが高いものの可視領域から離れた赤外領域になるので、目に見える色とは関係ありません。
それでは、(1)の軌道電子の寄与はどうなるのでしょうか? 酸素分子には16個の電子がありますが、このうち4個はそれぞれの原子核の近くに強く束縛されています。4個は、酸素原子の2s軌道から作られるσ
2sとσ
2s*軌道を満たしています。6個は、酸素原子の2p軌道から作られる6つの分子軌道のうち、エネルギーの低いπ
x、π
y、σ
2p軌道を満たします。ここで重要な役割を果たすのが、残った2個の電子です。フントの規則によると、軌道電子は、「同一の軌道に入ることを避け、同等の軌道に1個ずつ入った電子はスピンが平行になる」という傾向があります。従って、2個の電子は、次にエネルギーの高いπ
x*とπ
y*に1個ずつ入って、スピン平行の状態になります。分子全体ではスピン1の三重項状態(
3Σ
g)となり、酸素分子は常磁性を示します。
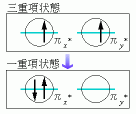
このように、酸素分子の基底状態は、エネルギーの等しいπ
x*とπ
y*に1個ずつ不対電子が入った状態です。基底状態の次にエネルギーの低い励起状態は、この2個の電子が同じ軌道に入ってスピン反平行になる(全スピン0の)一重項状態(
1Δ
g)で、基底状態とのエネルギーの差は、光の波長で1270ナノメートル相当です。ただし、全スピンの値が異なるため、光を吸収して基底状態(三重項状態)から一重項状態へと遷移することはありませんし、たとえ遷移が起きたとしても、赤外領域なので着色とは無関係です。また、これよりエネルギーの高い励起状態への遷移は紫外領域になるので、やはり目に見える効果はありません。可視領域に吸収線がないため、気体酸素は無色透明なのです。
ところが、液体酸素になると状況が変わります。液体では、分子同士が頻繁に会合するので、分子同士の相互作用を介して、1個の光子で2個の酸素分子を三重項状態(
3Σ
g)から一重項状態(
1Δ
g)へ遷移することが可能になります。この遷移は、エネルギーで言うと三重項と一重項のエネルギー差の2倍、波長で言うと1270ナノメートルの半分の630ナノメートルの光を吸収することで起こります。630ナノメートルの光はオレンジ色なので、これが吸収されたことにより、液体酸素は、オレンジ色の補色に相当する青に色づいて見えるわけです。
【Q&A目次に戻る】

風力発電は、再生可能エネルギーの中でも特に注目度が高く、EU諸国の他、アメリカ・インド・中国などで急速に導入が進められていますが、立地条件が適した地域は限られており、どこにでも建設できるというわけではありません。日本の場合、諸外国に比べて適地が少なく、むしろマイナス面が目立っているとも言えます。
電力供給という点から見て最大の障害になるのは、最後に上げられた「不安定で発電効率が悪い」ことです。大型の風車を回すには、最低でも秒速3メートルの風速が必要であり、年間を通じた平均風速が秒速6メートル程度なければ採算がとれないと言われています。デンマークで風力発電が普及した理由は、北海に突き出した半島状の国土を偏西風が吹き抜けるという自然環境が風車に適していたからです。ドイツで行われた研究によると、各地域に設置された個々の風車では発電量の変動が見られるものの、これは偏西風が部分的に蛇行した結果であり、ドイツ全体での風力発電量は年間を通じて安定していることが判明しました。西ヨーロッパ全域が風力発電に適しており、安定した電力供給が可能です。しかし、国土全体がモンスーン地域に属している日本では、風量・風向が季節によって変化するため、発電量の変動が大きく稼働率も低くなります。
「故障が多く、保守運用コストが高い」という問題もあります。最新式の風車は、コンピュータによって羽の向きを調節する精密機械になっていますが、大型発電所のように常時監視する体制がないので、不具合が放置され深刻な故障につながるリスクがあります。さらに問題となるのが、羽の破断やタワーの倒壊といった重大事故です。大型の風車は、秒速70メートルの風にも耐えられるように設計されているはずですが、実際には、それ以下の風速でしばしば事故を起こしています。強風と豪雨が重なると、想定以上の荷重が加わって破断・倒壊などの事故が引き起こされる危険性が生じますが、毎年のように台風が襲来する日本では、その確率がかなり高いと考えるべきでしょう。
「騒音」「景観の悪化」「電波の妨害」は、人間のいる場所に風車を建設するときに問題となります。特に深刻なのが、風切り音による騒音です。手元のカタログによると、750kWの風車の場合、200メートル離れた地点で45デシベルという住宅地で容認される騒音レベルになりますが、持続音なので、人によってはそれでもかなり不快に感じるかもしれません。アメリカでは、風車の建設計画に対して騒音を理由に地域住民が反対運動を起こしたケースもあり、住宅地の近くに建設するのは難しい状況にあります。米カリフォルニア州のウィンドファームのように、広大な砂漠や丘陵に1000基を越す風車の大群をまとめて建設するのが理にかなっていますが、日本では、そんな場所はなかなか見あたりません。山間部では風の流れが複雑になるため、発電量が安定せず、事故の確率も高まります。東京湾での洋上発電が提案されたこともありますが、漁業権の補償があまりに高額になるため見送られました。
風車そのものが自然環境の破壊になるという問題もあります。環境省は、国立公園内の風力発電施設の建設にかなり慎重です。生態系への悪影響を懸念する声もあります。2003年には、米アパラチア地方で、44基の風車が設置された風力センター近くで400頭のコウモリの死体が発見されましたが、風車のウィンドシアに巻き込まれたと見られています。ただし、このケース以外ではバードストライクの報告数はそれほど多くなく、絶滅危惧種の繁殖地でなければ、あまり心配する必要はないという見方が有力です。
なお、風車による大気の擾乱は、局所的な生態系に何らかの影響を与える可能性はありますが、せいぜい地上数十メートル程度での揺らぎなので、地球温暖化のような地球規模での異常気象への寄与は無視できると考えられます。
風力発電が温室効果ガスや汚染物質をあまり発生しないクリーンな発電方法であることは間違いありません。しかし、同時に、上のような問題点を抱えていることも事実です。問題点のいくつかは技術的な解決が可能であり、故障率や騒音の低減に関しては、すでにかなりの成果が上がっています。しかし、日本の国土がEU諸国ほど風力発電に向いていないという状況は、いかんともしがたいでしょう。むしろ、地熱発電や波力・潮汐力発電など、それぞれの地域の特性を生かした再生可能エネルギーと組み合わせる道を模索するべきでしょう。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
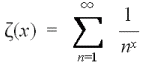
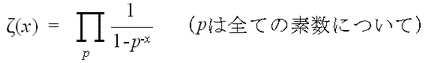
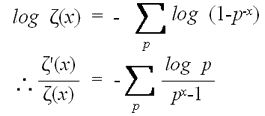
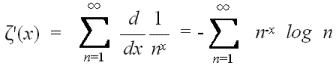
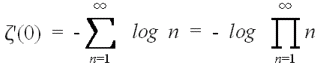
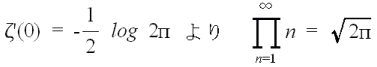
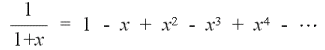
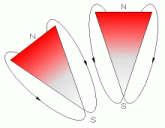 角錐の形をした磁石の側面同士を近づけると、それまで底面から頂点へと伸びていた磁力線が圧縮されて磁束密度(磁場の強さ)が増大します。さらに磁石を押しつけて接着させようとしたときに何が起きるかは、磁石の素材や磁石の近づけ方によって異なります。
角錐の形をした磁石の側面同士を近づけると、それまで底面から頂点へと伸びていた磁力線が圧縮されて磁束密度(磁場の強さ)が増大します。さらに磁石を押しつけて接着させようとしたときに何が起きるかは、磁石の素材や磁石の近づけ方によって異なります。
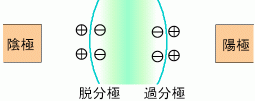 膜電位の変化は、さまざまな生化学的反応を引き起こすことが知られています。ゾウリムシの場合は、(イオンチャネルの透過性の変化などを介して)表面にある繊毛運動の向きを変える効果があります。繊毛運動は、ちょうど平泳ぎの腕のような周期的な動きを繰り返すことで、一定の向きに進む力を生み出しています。膜表面の分極が通常のときは前進させる向きに繊毛が動いており、過分極になるとこの動きが強められますが、脱分極状態になると、動きが停止したり逆に後退させる向きに動いたりするようになります。
膜電位の変化は、さまざまな生化学的反応を引き起こすことが知られています。ゾウリムシの場合は、(イオンチャネルの透過性の変化などを介して)表面にある繊毛運動の向きを変える効果があります。繊毛運動は、ちょうど平泳ぎの腕のような周期的な動きを繰り返すことで、一定の向きに進む力を生み出しています。膜表面の分極が通常のときは前進させる向きに繊毛が動いており、過分極になるとこの動きが強められますが、脱分極状態になると、動きが停止したり逆に後退させる向きに動いたりするようになります。
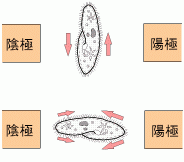 ゾウリムシのいる環境に電圧を加えると、陰極に近い側では外部電圧が膜電位と逆向きになるので脱分極に、陽極に近い側では過分極になります。このため、陰極に近い側の繊毛は後退の運動を、反対側の繊毛は前進の運動を行います。ゾウリムシが電場に対して垂直方向に向いているとき、この繊毛運動は体を回転させ陰極の方を向かせる作用を引き起こします。ゾウリムシが陰極を向いたとき、体の前部にある繊毛は(陰極に近く膜電位が脱分極になるので)後退の運動を、後部にある繊毛は前進の運動を行いますが、全体では脱分極による後退よりも過分極による前進の力が勝って、陰極に近づいていくことになります。
ゾウリムシのいる環境に電圧を加えると、陰極に近い側では外部電圧が膜電位と逆向きになるので脱分極に、陽極に近い側では過分極になります。このため、陰極に近い側の繊毛は後退の運動を、反対側の繊毛は前進の運動を行います。ゾウリムシが電場に対して垂直方向に向いているとき、この繊毛運動は体を回転させ陰極の方を向かせる作用を引き起こします。ゾウリムシが陰極を向いたとき、体の前部にある繊毛は(陰極に近く膜電位が脱分極になるので)後退の運動を、後部にある繊毛は前進の運動を行いますが、全体では脱分極による後退よりも過分極による前進の力が勝って、陰極に近づいていくことになります。
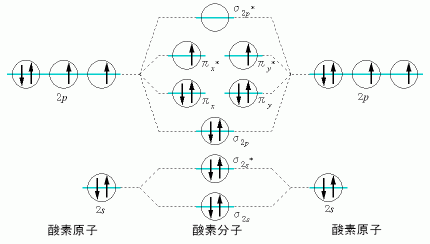
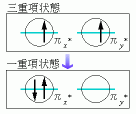 このように、酸素分子の基底状態は、エネルギーの等しいπx*とπy*に1個ずつ不対電子が入った状態です。基底状態の次にエネルギーの低い励起状態は、この2個の電子が同じ軌道に入ってスピン反平行になる(全スピン0の)一重項状態(1Δg)で、基底状態とのエネルギーの差は、光の波長で1270ナノメートル相当です。ただし、全スピンの値が異なるため、光を吸収して基底状態(三重項状態)から一重項状態へと遷移することはありませんし、たとえ遷移が起きたとしても、赤外領域なので着色とは無関係です。また、これよりエネルギーの高い励起状態への遷移は紫外領域になるので、やはり目に見える効果はありません。可視領域に吸収線がないため、気体酸素は無色透明なのです。
このように、酸素分子の基底状態は、エネルギーの等しいπx*とπy*に1個ずつ不対電子が入った状態です。基底状態の次にエネルギーの低い励起状態は、この2個の電子が同じ軌道に入ってスピン反平行になる(全スピン0の)一重項状態(1Δg)で、基底状態とのエネルギーの差は、光の波長で1270ナノメートル相当です。ただし、全スピンの値が異なるため、光を吸収して基底状態(三重項状態)から一重項状態へと遷移することはありませんし、たとえ遷移が起きたとしても、赤外領域なので着色とは無関係です。また、これよりエネルギーの高い励起状態への遷移は紫外領域になるので、やはり目に見える効果はありません。可視領域に吸収線がないため、気体酸素は無色透明なのです。