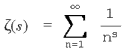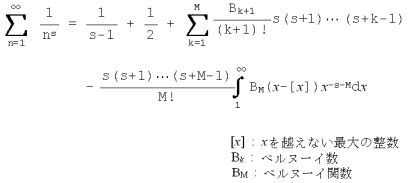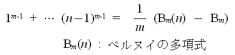環境問題を考える場合、基準とすべきは常に人間自身です。「地球に優しい」などと偽善的なスローガンを掲げる必要はありません。砂漠の緑化がサソリやタランチュラにとって深刻な環境破壊であるように、全ての生物種に好ましい環境など存在しないのですから、人間も、種の保存を最大の使命とする生物種として、自分たちの生存に適するように環境を作り替えていって、当然です。
それでは、直接的には人間の利益につながらない「森林・湿地の保全」や「生物多様性の維持」が重要課題とされるのは、なぜでしょうか。その理由は、環境における相互作用が人間の想像以上に複雑であり、自然界に存在する安定したシステムの助けを借りなければ、自分たちに適した環境を作り上げることができないからです。
人間は、これまでに何度も、自分たちに適した環境を作ろうとして失敗してきました。カザフスタンやウズベキスタンでは、荒地を沃野に変えようとするソビエト政権の方針に従って、運河による大規模灌漑が進められましたが、地面に浸透した水が地中の塩分を溶かして地表に残す塩類集積が進行し、開墾した耕地の多くを失う結果となりました。同様の現象は、インドのパンジャブ州や中国内陸部でも見られます。また、市場価値の高い穀類の単作を行ったため、収穫期には地表が剥き出しになり、有機物の含有量が多い表土が風や水の浸食作用によって失われる被害が多発しています。フィリピンやインドネシアなどの東南アジアでは、木材の輸出と耕地の拡大を目指して政策的に森林伐採が奨励されましたが、熱帯林では、有機物の大部分が植物体に蓄積されて土壌の腐植層はわずかしかない上、太陽光線にさらされると強い紫外線のせいで有機物が分解するため、植生を失った土地は急速に荒廃し、肥沃な耕地に作り替えることはできませんでした(木材の輸出も、供給過剰のために価格が下落して、期待したほど外貨を稼げずに終わりました)。熱帯林の伐採による荒廃地の拡大は、ブラジル、インド、サハラ以南のアフリカでも深刻な問題となっています。アメリカ中西部の穀倉地帯は、環境の変革に成功したケースのように見えますが、実は、数千年かけて蓄えられたオガララ帯水層からの地下水の汲み上げに頼っており、今のペースで水を消費し続けると、近い将来、深刻な水不足に直面すると言われています。
これらは、短期的には資本生産性を増大させることに成功したものの、持続可能な環境の創造に至らなかったケースだと言えます。自分たちにとって好ましい環境を作り上げようとしても、自然の仕組みを理解できるほどの知能を持たないわれわれ人間は、その状態をいつまでも持続させることができず、結果的に、自然破壊を加速させているのです。
人間が手を加えていない自然環境は、先の氷河期が終了して以降、ほぼ安定した状態を持続しています。これは、多様な生物種が存在することにより、多少の摂動に対しても適応することが可能だったからです。大規模な単作を行っている耕地は、洪水によって数日間水に浸されようものなら、農作物が全滅するでしょう。これに対して、アマゾンの浸水林では、洪水の際に多くの動植物が死にますが、水中でも生きられる生物がこれらの死骸を栄養にして繁殖し、数ヶ月にもわたる浸水期間を乗り越えます。水が引いた後は、水中生物が死んで、樹上などに避難していた動物の餌となります。豊かな生物多様性を持つ世界は、洪水、山火事、火山噴火、土砂崩れなどの災厄に遭遇しても、生態系が全面的に崩壊することなく、支配種の交代によって弾力的に対応できます。こうした安定したシステムは、気候変動や突発的な自然災害に対する緩衝帯の役割を果たしており、人間社会にとっても、必要不可欠な存在です。
さらに、生物種の豊富な森林や湿地は、周囲の環境を積極的に保全する機能も担っています。ラムサール条約が締結され、野鳥の飛来地となる湿地を守るための運動が世界的に盛んになっていますが、これは、単に野鳥が可愛いからというだけではありません。野鳥の飛来する湿地は、二枚貝やゴカイ、カニなどが豊富に棲息しており、これらの底生生物が、プランクトンの異常増殖による水質の悪化を防ぐ上で大きな役割を果たしていることが判明したからです。生活排水などに含まれるチッソやリンは、ケイ藻などの植物プランクトンを経て底生生物に摂取されます。その底生生物を食べた野鳥が、陸地に戻ってフンをすることにより、余分な栄養分が大地に還元されるのです。こうした巨大な物質循環を実現するシステムを人工的に作るのは、きわめて困難です。例えば、惜しくも干拓事業によって失われてしまった諫早湾の干潟が持っていた水質浄化能力は、建設費1000億円以上の浄化施設に匹敵すると言われています。また、日本各地で人工干潟を作る試みがなされましたが、その多くが失敗に終わっています。
自然界では、微生物から大型動物に至るさまざまな生物種が安定したシステムを形作っています(どの生物種が重要というわけではなく、生態系という1つのシステムが大切なのです)。地球環境が人間の生存に適した穏やかなものであり続けるために、その存在が欠かすことができません。農業・畜産業・養殖業などで人間にとって有用な生物だけを集めた人工的な環境を作ろうとしても、グローバルな物質循環などの面で自然の助けを借りなければ、持続可能なシステムを作ることはできません。こうしたシステムは、あくまで安定した自然環境を壊さないように、規模を限定して構築すべきでしょう。また、資源の状態に応じて収量をコントロールする「持続可能な漁業/林業」のように、自然と共生する産業のあり方も考えなければなりません。それができなければ、人間の文明は、数百年を経ずして崩壊することになるでしょう。
【Q&A目次に戻る】

リーマンのゼータ(ツェータ)関数ζ(s) が級数の形で
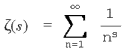
のように表されるのは、Re(s)>1 の範囲に限られます。質問にある式は、本来、級数の形で定義されない領域までζ関数を拡張したもので、数学的に正当な等式とは言えませんが、数の不思議さを教えるためにしばしば使われます。
導出法は省略しますが、上の級数は、Re(s)>1 の範囲で、次のように書き換えることができます:
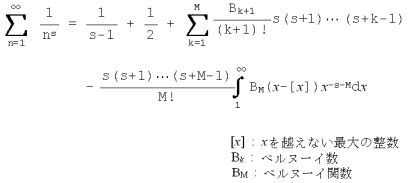
ここで、左辺の級数は Re(s)>1 以外の領域では絶対収束しませんが、右辺の積分は、Re(s)>1-M の範囲でも収束します。したがって、右辺をsの関数と考えると、充分に大きなMを選ぶことにより、sの全領域に解析接続することができます。Re(s)≦1 ではζ関数を右辺で定義することにすれば、ζ(s) は s=1 に1位の極を持ち、それ以外では正則な関数となります。特に、mを自然数として、 s=1-m 、M=m と置くと、積分の部分はゼロになるので、ベルヌーイ数の漸化式を使って変形し、
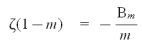
という関係を導くことができます。Re(s)=1-m≦1 なので、この関係式は、ζ関数が級数で表される領域を逸脱していますが、
仮に、級数で表されるとして m=1〜4 を代入すると、質問文にあるζ(0)〜ζ(-3)の式が得られます。
実際の級数和とζ関数の値とは何が違うのかをはっきりさせるために、自然数のべき和の公式を考えます:
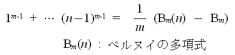
nを無限大にすると、左辺は、ζ関数を級数で表して s=1-m と置いたものに相当します。右辺の第2項は、解析接続によって定義されたζ関数の s=1-m での値です。それでは、右辺第1項は何でしょうか? 実は、この項は、n→∞で発散してしまうのです。つまり、Re(s)≦1 でのζ関数の値は、解析接続という数学的な手続きによって級数から発散する部分を除き、有限部分だけを評価したものだと言えます。
ζ関数には、この他にもいろいろと興味深い性質があります。詳しくは、次の参考書(高校数学をマスターしていれば理解できるはずです)を参照してください。
【参考】梅田亨ほか著『ゼータの世界』(日本評論社)
【Q&A目次に戻る】

人間の記憶は、脳におけるニューロン(神経細胞)同士の結合パターンに蓄えられると考えられます。ニューロンの数は1000億以上、シナプスと呼ばれるニューロンの結合部位は細胞当たり数千個ですから、
仮に、シナプスの有無によって1ビットの情報が表せるとすると、脳に蓄えられている情報量は、少なくとも100兆ビット、数万GB(ギガバイト)です。しかし、この推定値は、あまり意味がありません。神経興奮の頻度に応じてシナプスの伝達効率は大きく変化するので、単純に1ビットの情報を担っているとは言えません。また、成体の脳でも、新たにシナプスが形成されて神経組織の再構成が行われることが報告されており、可能な結合パターンを全て考えると、脳に蓄え得る情報量は遥かに膨大なものとなります。
何よりも、人間の記憶が、人工的な記録媒体に記録されているデータとは質的に異なることを理解しなければなりません。ハードディスクや磁気テープに記録されたデータそのものは単なるビット列に過ぎず、それをどのように利用するかは、データとは別に用意されたプログラムに依存します。これに対して、人間の記憶内容は、それ自体が意味を持っていると考えられます。
例えば、視覚的な記憶は、網膜に映じた2次元像を写真のように忠実に記録したものではありません。時間的な変化も含めてさまざまな特徴に分解され、各特徴ごとに連想が働くような形で記録されています。過去の体験を視覚的イメージとして想起しようとしても、記憶に焼き付いている一部を除いては、ぼやけた曖昧な映像しか得られません。しかも、しばしば欠落した部分が捏造されており、写真やビデオに比べると、正確さという点で著しく劣っています。しかし、その一方で、視覚的記憶は豊かな連想性を備えています。友人が微笑む光景から往時の心の揺らぎがありありと甦ったり、皿に載ったひとかけらの菓子のイメージが口の中にさまざまな甘い感覚を呼び起こしたりします。これは、経験内容の特徴を分析し、類似したパターンと関連付けながら記憶していくという人間の特性によるものです。パターンの関連づけといったアナログ的な作用に関しては、情報量がうまく定義できないので、「人間の記憶容量は何ビット」と答えることは、今のところ困難です。
【Q&A目次に戻る】

太陽は、白色矮星になる前に、いったん膨張して赤色巨星となり、さらに不安定化して爆発的に高温ガスを吹き出すようになります。太陽系の姿はこの段階で大きく変容し、現在とは全く異なるものになっています。
現在、太陽の中心部では、水素がヘリウムに変換される核融合が進行していますが、50億年もすると、中心部にはヘリウムが溜まって水素燃料が不足し、核融合の起きる領域が外層へと移動してます。この結果、重力と圧力の均衡が破れ、太陽は急激に膨張し始めます。これが赤色巨星と呼ばれる状態で、その大きさは現在の地球軌道ほどになり、水星と金星は飲み込まれて燃え尽きてしまいます。太陽は巨星化の過程でガスを吹き出して少し軽くなるため、地球は外側に移動し、かろうじて飲み込まれずに済みそうですが、それでも、強烈な放射に晒されて灼熱の世界と化します。
外層部の水素も燃え尽きると、ヘリウムの核融合が始まりますが、この段階で太陽は不安定な状態に陥り、表面から高温ガスが脈動的に周辺に吹き出すようになります。このガスの流れ(恒星風)は最大で秒速1000kmにも達し、天文ファンに馴染みの美しい惑星状星雲を形作るでしょう。木星や土星のようなガス惑星の大部分は、この恒星風で吹き飛ばされてしまいます。一方、表層部が失われた太陽では、2万度を超える高温の中心核が剥き出しになります。地球表面の岩石は、ここから放射される強い紫外線をまともに浴びてプラズマ化し、地球全体を靄のように覆うと考えられます。
こうした荒々しい段階は、数十万年程度で収まり、中心核が剥き出しになった太陽も、核融合の燃料がないために次第に冷えていきます。吹き飛ばされずに残った惑星の残骸も、冷たい塊となってその周囲を漂います。
【Q&A目次に戻る】

「密度行列の非対角項が消える」というのは、デコヒーレンス理論の1つの定式化にすぎません。具体的な状態変化に着目する定式化では、状態の収縮のような不自然な仮定を使わずに、射影定理と同等の結果を与えることができます。ただし、いかにして特定の現実が選択されるかについては、答える術がありません。
まず、1粒子系のような少数自由度系の量子状態について考えましょう。ある量子状態 |ψ〉を、物理量 A の固有状態 |a
s〉(正規直交系とする)で展開します:
|ψ〉= Σ
sc
s|a
s〉
c
s = 〈a
s|ψ〉
この場合、個々の |a
s〉が互いに直交するとしても、環境との相互作用を通じて異なる固有状態同士が干渉し得るので、物理的な状態が |a
s〉に分岐したわけではありません。A についての測定(ここでは概念的にやや曖昧な「観測」ではなく「測定」という語を用います)を行い、固有状態 |a
s〉に対応する固有値が得られて、はじめて |a
s〉という状態が物理的な意味を持つようになります。
この過程を理解するためには、量子力学的な測定が、ある固有状態を透過させるフィルターのようなものではなく、対象系と測定装置との物理的な相互作用であり、測定装置を含めた全体を変化させることを認識する必要があります。測定の過程において、物理的状態の時間変化は、対象となるシステムのハミルトニアン H
0 ではなく、測定装置と対象系を併せた全体系のハミルトニアン H
0 + H
1 に支配されます。理想的な測定の場合、対象系における固有状態の重みは変化しませんが、測定装置の量子状態Φが、対象系との相互作用を通じて変化すると考えられます。状態 |a
s〉が測定されたことを表す測定装置の状態を |Φ
s〉と記すと、観測による状態変化は、
|ψ〉|Φ〉→ Σ
sc
s|a
s〉|Φ
s〉
となります(状態ベクトルを並べて書いたものは直積を表すと理解してください)。これは、「測定によって特定の測定値が得られた状態」が、全ての測定値ごとに適当な重みをつけて重ね合わされた状態です。同じ物理量に関して続けて測定を行った場合、異なる測定結果を与える|Φ
s〉と|Φ
r〉(r≠s)は、H
0 + H
1 の下では干渉しないと考えられるので、系の状態は
Σ
sc
s|a
s〉|Φ
s〉
のままです。したがって、連続測定を行うと同じ測定結果が得られることになります。
ここで重要なのは、異なる測定結果を与える測定装置の状態が、外部からどのような操作を受けようとも干渉しない状態であり続けるということです。たとえ測定装置を含めた系の状態が Σ
sc
s|a
s〉|Φ
s〉という式で表されたとしても、「測定装置を測定する装置」をも含めたハミルトニアン H
0 + H
1 + H
2 の下では異なる|Φ
s〉の間で干渉が起きるとなると、上の議論は成り立たなくなり、それこそ、「想定装置を測定する装置を測定する装置を…」という無限連鎖に陥ってしまいます。
この連鎖を断ち切るロジックとして考案されたのが、多数の自由度から成る統計的なシステムにおけるデコヒーレンスです。ごく大ざっぱに言うと、多自由度系では、全てのサブシステムでコヒーレント(可干渉)な状態になっていなければ、全体として干渉は起きません。自由度がきわめて多数のときには、全てがコヒーレントになるよりも、どこか一部でコヒーレンスが破れる確率が圧倒的に高くなるので、外部からどのように操作しようとも、コヒーレンスを回復することは困難になります。自由度がきわめて多くなると、互いに干渉しない状態に自然に分岐していくことは、高エネルギー励起状態にある1つの強い(=固有振動数のきわめて小さい)振動子が多数の弱い振動子と頻繁に少量のエネルギーをやりとりしている場合など、いくつかの単純なケースで確かめられています。
多数の自由度から成る統計的システムでデコヒーレンスが起きるのが量子力学の一般的な性質だとすると、そのシステムが測定装置でなければならないという必然性はありません。量子力学の解釈において、測定の呪縛から逃れることは本質的な意味を持ちます。教条的な教科書は、状態を確定するための測定にこだわって、著しく窮屈な定式化を行っていますが、現実の世界では、「溶液の混合による色の変化」や「マイスナー効果による超伝導体の浮遊」のような定性的な振舞いを見ただけで量子状態が判定できるケースも多く、物理量の測定なしに状態を記述することは可能です。測定概念に基づく量子力学の解釈は、デコヒーレントになるものを測定装置に限定した特殊な考え方と見なすべきでしょう。
仮に、ある統計的システムで厳密なデコヒーレンスが起きたとすると、そのシステムを含む量子状態は、互いに影響を及ぼすことのない複数の状態に分岐します。全世界の状態を、デコヒーレントになったシステムの状態 |Φ
s〉と、それ以外の部分 |Ψ
s〉に分けて、
Σ
sC
s|Φ
s〉 |Ψ
s〉
と表すと、さまざまな添字 s で区別される |Ψ
s〉が表すのは、互いに無関係な別個の世界ということになります。
デコヒーレンス理論を解説した書物の中には、現実の物理的状態がいくつもの異なる世界へ分裂していくというイメージを与えるものもありますが、これは必ずしも適当ではありません。初期状態 |ψ
0〉から始まる系の変化を表す表式は、時間発展の演算子 U、密度行列ρを使って、一般に
〈ψ
0|U
+ρU|ψ
0〉
と書き下せますが、時間発展によって互いに干渉しない状態 |ψ
s〉に分岐していくとすると、これは、
Σ
sξ
s|〈ψ
s|U|ψ
0〉|
2
のように展開できます。この展開は、 |ψ
0〉から任意の状態に変化する過程が、|ψ
0〉から |ψ
s〉に変化する量子過程に、先験的な重みを付けて分割されたと解釈できます。状態ベクトルを正規化して遷移確率を定義すれば、ある初期状態から任意の状態に変化する確率1を、デコヒーレント状態へ分岐する確率 P
s に分割したことに相当します。つまり、量子力学とは、現実に起きる可能性のあるさまざまな量子過程に対して、先験的な確率を付与する理論なのです。ただし、特定の量子過程が「この世界」として実現したメカニズムを語ることはできません。
…と、このように説明すると、量子力学の本質がデコヒーレンス理論で見事に解明されたかのように見えますが、事態はそれほど単純ではありません。上の説明は、あくまで「何らかの統計的システムで厳密なデコヒーレンスが起きる」ことを前提としたものです。ところが、これまで行われた計算では、単純なシステムで近似的にデコヒーレンスが起きることが示せただけです。連続的な自由度があるシステムでは、固有値がごく僅かに異なる状態間の干渉が、難しい問題を引き起こします。デコヒーレンス理論はいまだ建設途上であり、もしかしたら、現在の理論形式のままでは数学的に正当化できないかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

紙1枚でα線が遮蔽できるというのは、原子核のα崩壊によって放出されるエネルギー4〜9MeV程度のα粒子の場合です。例えば、プルトニウム239は5.2MeVのα粒子を放出しますが、このエネルギーならば、空気中でも約4cm、アルミニウムの内部ならば0.02mm程度の飛程しかありません。しかし、α粒子のエネルギーが増加すると、飛程も非線形的に急増します。α粒子のエネルギーが1MeVから100MeVに増えると、飛程はほぼ1000倍になります。
物質に進入した荷電重粒子は、物質中の電子にエネルギーを与えることによって運動エネルギーを失っていきます。重粒子が電子を“跳ね飛ばしていく”過程を古典近似で考えると、電子に加わる力が重粒子と電子の間の距離で決まるのに対して、相互作用している時間は速度に反比例するため、電子が受ける力積(=運動量の変化)も速度に反比例します。従って、電子が受け取るエネルギーは重粒子の速度の2乗、すなわち運動エネルギーに反比例します。このことは、一定の距離を進む間に重粒子が失うエネルギーが、運動エネルギーに反比例することを意味します。実際には、量子論的な効果によってこの近似は大幅に修正されますが、エネルギーが数百MeV以下の範囲では、運動エネルギーが大きいほど進行距離あたりの喪失エネルギーが小さくなる点は、変わりません。このため、運動エネルギーの大きい粒子はあまり減速されず、エネルギーを失うにつれて減速率が急激に大きくなっていきます。
【Q&A目次に戻る】

太陽系近くの超新星爆発によって6500万年前に恐竜が絶滅したという説は、1954年にシンデウルフが提唱したもので、50年代後半から70年代にかけて、一部の科学者が賛同する論文を発表しました。しかし、この学説は、現在ではほぼ否定されています。6500万年前の地層に含まれるイリジウムが、小惑星ではなく超新星に由来するならば、この超新星は地球から0.1光年程度の距離で爆発したと推定されますが、それほど近くで超新星爆発が起こる確率は、10京年に1回程度でしかありません。また、検出された同位体の存在比も、超新星で生成される場合とは異なっています。
超新星が恐竜を滅ぼしたとする説は否定されましたが、宇宙に生きる生物にとって、超新星が脅威であることは変わりありません。超新星爆発は、太陽が1年間に放出する量の100億倍以上のエネルギーを数百日間で放出し、数十光年の拡がりを持つ星雲(超新星残骸)を形成するので、近くの恒星系に住む生物にとっては、致命的なダメージとなります。仮に超新星の光度が太陽の100億(=10
10)倍だとすると、超新星が地球−太陽間の10万(=10
5)倍の距離(10万天文単位=1.6光年)に出現したときには、地球に降り注ぐ光の量が2倍となって、地球環境は激変します。さらに、数十年後には、超新星から吹き出した高エネルギー粒子の流れが地球に到達します。地球上の生物が安泰でいられるのは、超新星が数十光年以上離れている場合でしょう。
将来、超新星爆発を起こすのは、単独の恒星ならば質量が太陽の8倍以上の大質量星に限られており、質量の小さい赤色矮星と異なって明るく輝いているので、簡単にそれとわかります。太陽系から20光年以内には、超新星爆発を起こしそうな危ない星はありません。連星系の場合は、白色矮星でも伴星からガスが流れ込んで質量が太陽の1.38倍になったときに超新星爆発を起こしますが、長時間にわたって安定した連星系でなければならないといった条件があり、観測によって特定することが可能です。まもなく超新星爆発を起こすことがほぼ確実なのは、地球から約2万光年彼方にあるさそり座U星で、現在の質量は太陽の1.37倍であり、このペースでいくと数千年以内に爆発するはずです。これより近くにも超新星候補は存在するはずですが、そもそも超新星は銀河系全体の中でも100年に1回程度しか現れない珍しいものなので、発見するまでにはかなり手間がかかります。
【Q&A目次に戻る】

福知山線事故の原因は、まだ完全には解明されていません。航空鉄道事故調査委員会による中間報告が9月6日に提出されているものの、運転士の心理状態などいくつかの重要な点に関して不明なままです。以下では、中間報告に基づいて私の考えをまとめておきます。
この事故は、次のような過程を経て起こりました:
- ○許容速度120km/h の区間から充分に減速しないまま、制限速度70km/h のカーブに進入した
- (1)カーブ進入して1秒弱の時点で運転士は常用ブレーキを操作したが、110km/h 以下に減速されることなく3秒ほど走行した
- (2)カーブ手前で適切に減速していないとブレーキが作動する新型ATS(ATS-P)、制限速度を超えるとブレーキが作動する改良型ATS(旧型ATSに速度照査機能を加えたもの)は、現場付近には設置されていなかった
- ○カーブでの遠心力により、片輪走行になって脱線した
- (3)車体を軽量化し空気バネで揺れを吸収する「ボルスタレス台車」を使用していたことが、横転の誘因になったとの見方もある
- ○脱線後に線路脇のマンションに激突、2両目は壁に巻き付くような形で潰れ、死傷者数を増やした
- (4)マンションは、カーブ手前の線路の延長線上にあり、線路の間隔は6m程度しかない
- (5)車体を軽量化したため、側面からの衝撃に弱く大破したとの見方もある
海外マスメディアは、マンションが線路のすぐ脇に建っていたという(4)の問題を大きく取り上げましたが、こうした光景は日本の大都市近郊ではごくふつうであり、そもそも線路脇の建造物に突っ込まないような安全策を講じるべきでしょう。一部の評論家は、(3)のボルスタレス台車の問題を重視しています。しかし、事故現場の半径304mの円軌道を時速120kmで走行したときの遠心力は 0.37G にも達するので、カント(遠心力を打ち消すための路面の傾き)が5°程度ならば、ボルスタレス台車でなくても重心が少し外側に振れただけで横倒しになったと思われます。したがって、事故の主因は、あくまで事故車両が制限速度を大幅に超過してカーブに進入したことであり、これにいくつかの条件が重なって被害を拡大したと言えます。
状況に応じて速度制御を行う装置(ATS-P や ATC など)が設置されていれば、事故が防げたと主張する人も少なくありません。こうした装置は、新幹線、大都市圏の地下鉄、首都圏のJRと私鉄では、大部分で導入されています。JR西日本でも、大阪環状線や阪和線で ATS-P を設置していますが、2001年度以降、整備のための予算が大幅に減額されており、導入が遅れていたことは否めないようです。旧型の ATS が使用されている路線は日本各地にまだ多く残っているので、JR西日本だけの問題ではありませんが、今回の事故は、安全対策を軽視したツケが回ってきたものと言えます。
最も重要な点は、運転士がなぜ40km/h 以上も制限速度をオーバーしたままカーブに進入するような無謀な運転を行ったかです。マスコミでは、JR西日本特有の厳しい「日勤教育」が心理的要因になったとする論調が多く見られました。事故を起こした運転士は、伊丹駅で起こした70mのオーバーランのため定刻より80秒遅れで発車しており、日勤教育で遅延を咎めらることを防ぐために、あえて制限速度を超過して遅れを取り戻そうとしたというものです。しかし、この運転士は、当日の朝に回送車を運転していた段階でもATSによる非常停止を起こしており、遅延が生じる以前から何らかの問題を抱えていたようです。勤務表を見ると、前日は23時14分まで10時間以上の業務をこなした後に派出所に宿泊し、当日は早朝6時21分から仕事を始めています。このため、疲労や睡眠不足のために意識レベルが低下していたのかもしれません。
私が気にかかるのは、事故が起きた直後に、JR西日本側が「時速133km以上でなければ脱線しない」と発表したことです。この数値は、鉄道総合技術研究所が試算したものですが、乗客数など脱線の要因となるさまざまなファクタが与えられておらず、あまり現実的ではありません(乗客が多いほど重心が高くなって脱線しやすくなります)。非現実的な数値であるにもかかわらず、「制限速度を超えても133km/h 以下なら危険はない」という“常識”がJR西日本社員の間に広まっていたとすると、睡眠不足で判断力の低下した運転士が、「わざわざ急減速しないで120km/h のまま惰性で走行してもかまわないのでは」と安易に考えた可能性があります。もしそうだとすると、「危険になる臨界点はどこか」という基本的な知識の欠如が、事故の引き金になったと考えられます。この点に関しては、おそらく、JR西日本以外の鉄道会社にも当てはまることでしょう。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA