 子供のときから疑問に思っていたことがあります。
子供のときから疑問に思っていたことがあります。
- 最低の温度は絶対零度(マイナス273.15℃)とのことですが、例えば、摂氏零度の氷も、冷凍庫に入れればそれ以下に冷やすことができます。本当に、絶対零度以下の温度はありえないのでしょうか?昔、理科の教師に絶対零度以下の温度はないと説明されましたが、どうも納得がいきませんでした。
- 温度の理論的な最高温度というものは果たしてあるのでしょうか?恐らく、ビッグバンの初めの瞬間が、この宇宙の実際の最高温度だったと思いますが、それはどのくらいの温度だったのでしょうか?
【古典物理】

絶対温度を直観的に理解するのに最もわかりやすい例となるのは、気体分子運動論でしょう。この理論では、気体分子がビリヤード球のように互いに衝突しながら空中を飛び回っていると仮定されています。シリンダーに閉じこめられた気体分子が繰り返し衝突することによってピストンに加えられる平均的な力を計算すると、気体の圧力p と気体分子の並進運動エネルギーK の間の関係式が得られます:
PV = (2/3)K (V:気体の体積)
実験的に得られている状態方程式
PV = nRT (n:モル数、R:気体定数、T:絶対温度)
と結びつけると、
K = (3/2)nRT
となります。この式によれば、絶対零度は、気体分子の持つ運動エネルギーがゼロとなり、完全に静止してしまう極限となります。従って、気体分子運動論の範囲では、絶対零度が実現され得る最低温度であり、それ以下の温度は存在しません。
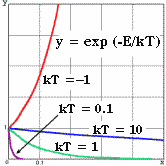
もう少し進んだ統計力学の理論によると、絶対温度T は、全エネルギーがシステムを構成する各部分にどのように分配されるかを決める量として定義されます。多数の自由度から成るシステムが熱平衡状態になっている場合、ある部分系にエネルギーEが分配される確率は、
exp (-E/kT) (k:ボルツマン定数)
に比例することが知られています
(規格化定数などの細かな議論は端折りました)。この式からわかるように、高温になるほど、部分系が大きなエネルギーを持つ確率が高くなります。逆に、絶対零度に近づく極限(T→0)では、エネルギーが最低値を取るような状態が圧倒的に高い確率で実現されることになります。古典論の範囲では、エネルギーに明確な下限はありませんが、量子論的なシステムの場合、エネルギーの下限を与える「基底状態」が定まっており、絶対零度では、全ての部分系が基底状態になっていると考えられます
(量子統計に関する細かな議論も端折っているので、厳密には正しくありません)。物体からエネルギーを奪っていって、絶対零度以下の温度にすることは、理論的に不可能です。
ただし、絶対温度がマイナスになることはあり得ないかというと、必ずしもそうではありません。例えば、部分系が E
1 と E
2(E
1 < E
2 )の2つのエネルギー状態を取る多数の部分系があるとすると、自然な熱平衡状態では、エネルギーの低い E
1 状態の系の方が多くなるはずです。しかし、人工的に E
2 状態が多くなるようにしてやると、式の上では E が大きいほど exp (-E/kT) の値も大きくなることになり、絶対温度はマイナスであると考えざるを得ません(グラフ参照)。こうした“不自然な”状況は、レーザー発振を起こすシステムなどで実現されています。
なお、絶対温度に理論的な上限はありません。標準的なビッグバン理論では、宇宙創成の0.01秒後には約1000億度、3分後には約10億度といった計算値が提出されていますが、ビッグバンの瞬間の温度は計算できません。宇宙が始まった瞬間の状態を記述するには、新しい理論が必要です。
【Q&A目次に戻る】

確かに、宇宙遊泳している2人の宇宙飛行士がキャッチボールをすると、ボールが持っている運動量を受け取るために、2人は互いに遠ざかってしまいます。ボールの交換によって、核力や重力のような引力が生じることはありません。相互作用のメカニズムを説明するのに「素粒子を交換する」という言い方を用いる場合がありますが、これは、直観的には理解不可能な量子論的な効果を表現するものです。
古典論において、電磁場はマクスウェル方程式に従う連続的な媒質のように表されます。ところが、量子論を適用して電磁場を量子化すると、電磁場が光子と呼ばれる粒子の集まりであるかのように振舞う(古典論の範囲では理解できない)ケースが出てきます。例えば、X線が電子によって散乱されるコンプトン効果の場合、電磁場によって振動させられた電子がX線を放出したと考えるよりも、1個の光子が電子にぶつかって跳ね飛ばされたと解釈した方が、散乱されたX線の散乱角と波長の関係などを簡単に説明できます。このように、量子論的な現象は粒子描像を用いるとわかりやすくなる場合があるので、場の量子論の入門書では、古典論との違いを強調して、場の振舞いを粒子のイメージに基づいて記述することが多くなっています。2個の電荷が電磁場を介して相互作用をしている状況は、古典論では、「一方の電荷が作る電磁場が他方の電荷に作用を及ぼす」となりますが、粒子描像を用いた量子論的な記述によると、「一方の電荷が放出する光子が他方の電荷に吸収される」と表されます。こうした光子のやりとりは相互に行われるので、簡略化した言い回しで「光子を交換する」と表現しても間違いではないでしょう。電磁場以外にも核力の場や重力場などがあり、これらを量子化したときに現れる粒子(粒子的な振舞いを実体化したもの)は、それぞれ、π中間子/重力子と呼ばれています(重力子はまだ観測されていません)。核力や重力が生じる過程を粒子描像に基づいて表すと、「核子(質量を持つ素粒子)がπ中間子(重力子)を交換する」ということになるわけです。
ただし、こうした粒子描像に基づく表現は、必ずしも適切なものではありません。実際、電磁的な現象の中で粒子描像によって本質的にわかりやすくなるのは、せいぜいコンプトン効果と光電効果くらいであり、大半の物理現象は、粒子描像によらずに記述できます。核力の担い手とされるπ中間子は、ウィルソンの霧箱内部にいかにも粒子のような軌跡を残しますが、核子や中間子の構成要素であるクォーク間の相互作用(強い相互作用)を担っているグルーオンになると、粒子描像が適用できるケースはほとんどありません。グルーオンや重力子は、自分自身と相互作用するという特異な性質を持っているため、1個の粒子として自存することができないからです。相互作用の説明として用いられる「素粒子を交換する」という表現は、「量子化された場を介して相互作用する」という内容を素朴に言い表したものだと思った方が良いでしょう。
【Q&A目次に戻る】

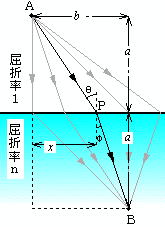
質問の小説(未読です)にも書かれているようですが、変分原理の最も簡単な例は、光の経路に関するフェルマーの原理で、「2点間を結ぶ光の経路は、その所要時間を最小にするものである」と表現されます。例として、2つの媒質の境界で光線が屈折する場合を考えましょう(ひとまず、均一な媒質中で光は直進するものとします)。図のAからPを通ってBまで光が進むのに要する時間は、(屈折率nの媒質中の光速が c/n になることより)、幾何学的距離をn倍した光学的距離、すなわち、AP+nPBに比例します。従って、フェルマーの原理を満たすのは、図のxを変えたときに光学的距離Sが最小(より一般的には極小)になるような経路となります。この条件は、Sをxで微分した値がゼロになるという形で表され、下に示すように、良く知られた屈折の法則(スネルの法則)を導きます。
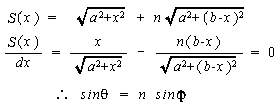
この議論を、屈折率が連続的に変化する媒質に拡張してみましょう。幾何学的距離は微小な線素 dl を積分したものであり、光学的距離は、dl に各点の屈折率を乗じて積分したもの、すなわち、
S = ∫n dl
となります。フェルマーの原理は、「Sが極小値を取る経路が光の進む道筋になる」ということですが、これを数学的に表現すると、(「導関数 = ゼロ」を一般化した条件として)「経路を僅かに変化させたときのSの1次の変化量(変分)がゼロ」となります(極大値となるケースは、他の条件によって排除されると仮定します)。この条件は、「経路のどの部分をいかに微小変形しようとも S の変分がゼロ」というきわめて強い制約であり、光が進もうとする全ての点で、ローカルな条件式が満たされていなければならないことを意味します。詳しい導出法は省略しますが、以下の式変形によって、「最終行の中括弧内 = 0」という光の進み方を決める微分方程式が導かれます:
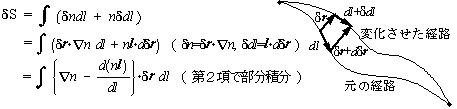
逆に、この微分方程式を満たすように進む光線に関しては、S の変分が常にゼロになるので、S が極小値を取ることが導かれます。
以上の議論から、次の2つの命題が等価であると結論されます。
「光は光学的距離S を極小にする経路を進む」
↓↑
「光はある微分方程式を満たすように進む」
多くの 科学者は、次のように解釈しています。
ある点に到達した光は、特定の微分方程式を満たすような形で、その先に進んでいく。こうした状況を、全体的な観点から再解釈すると、光学的距離S が極小になる経路を進んだことになっている。
同様の議論は、古典力学に従う質点系においても成り立ちます。1つの質点がポテンシャル内部を運動している場合、光学的距離に相当するのが作用積分S で、これは、質点が運動する軌道に沿ってラグランジアンL(多くの場合、「(運動エネルギー)−(ポテンシャル・エネルギー)」に等しい)を時間積分したものとして与えられます:
S = ∫L dt
さまざまな運動の仕方(経路)に対して作用積分S が求められますが、実現される運動は、S が極小値を取るものになります(ハミルトンの原理)。さらに、光の場合と同じように、「経路を僅かに変化させたときのS の変分がゼロ」という条件から、ローカルな微分方程式(=運動方程式)が導かれます。従って、次の2つの命題が等価になります:
「質点は作用積分S を極小にするように運動する」
↓↑
「質点は運動方程式を満たすように運動する」
質点の運動の場合でも、
標準的な 解釈は、「質点はローカルな運動方程式に従って運動するが、その状況を解釈し直すと、作用積分が極小になる運動が実現されたことになっている」というものです。
ただし、この解釈に異を唱える少数の科学者もいます(私もその一人です)。「作用積分は、単なる数学的な道具ではなく、現実に存在する何かと密接な関係を持っている」、あるいは、「世界は微分ではなく積分に従っている」という立場です。これは、時間的な因果律(原因は結果に先行する)を否定する立場なので、一般には受け入れられないものですが、SF作家だけではなく、そういう考え方をする科学者もいることを知ってほしいと思います。
【Q&A目次に戻る】

周期的な振動現象の分析には、フーリエ解析の手法が役に立ちますが、フーリエ成分として現れる高調波がどこまでリアルなものかは、扱っている現象の種類に依存します。例えば、(非線形性を示さない)媒質中を伝播する光の場合、フーリエ成分が混ざり合うような相互作用はないので、各成分をあたかも実在する波であるかのように取り扱うことが許されます。実際、吸収スペクトルを説明する際には、「振動数××Hzの波が吸収された」といった言い回しがなされ、光は、各成分波の(重ね合わせというより)集まりのようにイメージされています。
これに対して、交流回路の場合、一般に、各フーリエ成分を独立して存在する波として扱うことはできません。理想的なコイル・コンデンサ・抵抗器・電源しか含んでいない回路ならば、電流と電圧は線形な関係式で結ばれている──コイルでは V
ω=-iωLI
ω のように──ので、フーリエ成分ごとにキルヒホッフの法則を適用することができます。しかし、多くの素子は非線形であり、こうした簡単な関係式は成り立ちません。ダイオードの場合は、全電流の正負に応じて整流作用が働くのであって、個々の成分波ごとに整流するわけではありません。各成分波が混ぜ合わされてしまうので、フーリエ解析は1からやり直さなければならないのです。
非線形素子を含む交流回路でフーリエ解析がパワーを発揮するのは、波の歪みによる影響を高調波ごとに分析する場合でしょう。OA・FA機器は、高調波成分を含む電圧が加えられるとスイッチングなどに誤作動が生じやすくなるため、悪影響を与える高調波(通常は第5次以上の奇数次高調波)を測定して、高調波フィルタなどによって影響を取り除く必要があります。このような高調波は、「波の歪み」という定量化しにくい対象をイメージしやすいように実体的に表したもので、実在する波ではなく便利な数学的概念と見なすべきだと思います。
【Q&A目次に戻る】

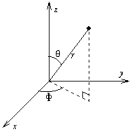
物質波の理論は、歴史的に見ると、ド・ブロイがかなり素朴な形で学位論文として1925年(執筆は1924年)に発表した後、(アインシュタインが比熱の理論との関係でコメントを加えたのを別にすると)他の学者がほとんど注目していないうちにシュレディンガーが集中的に研究し、翌1926年にシュレディンガー方程式の定式化を含む大論文にまとめてしまったため、ド・ブロイの物質波とボーアの量子条件を結びつけるという本格的な試みは行われませんでした。初学者向けの教科書で「ド・ブロイ波が定常波になる」という条件を置いて解説しているのは、初等数学だけを使ってエネルギー準位を求めるための苦肉の策であり、物理学的にはあまり正当なやり方とは言えません。
ボーアの原論文は難解でわかりにくい(簡単な解説を
別の回答で行っています)ため、ここでは、次の式で表されるボーア=ゾンマーフェルトの量子条件を考えることにします:
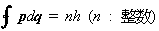
水素原子核の周りを運動している電子の運動に関して、この量子条件を正しく適用しようとすると、クーロン場でのラグランジアンを使って一般化運動量を求める必要があります。しかし、それでは話が難しくなるので、電子が、半径a、角速度|ω|の等速円運動を行っている場合に限ることにしましょう。このとき、軌道面がθ=π/2となる球座標(右上図参照)を使って運動を表すことにすると、
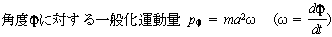
となり、ボーア=ゾンマーフェルトの量子条件は、
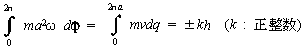
と表されます(正負の符号は、円運動が反時計回りか時計回りかに対応します)。最初の等号の右辺は、円軌道に沿った速度(v=aω)と座標(q=aφ)で左辺を書き直したもので、ド・ブロイによる物質波の条件式
|mv| = h/λ
を使えば、波長のk倍が円周に等しいという良く知られた条件を得ます。
ところで、上のボーア=ゾンマーフェルトの量子条件が意味するのは、角度φに対する運動量──すなわち、角運動量のz成分──が量子化され、磁気量子数が±kになるということです。細かい話は省略しますが、等速円運動なる条件を加えたことにより、角度θと動径rに対する運動量の量子数はゼロとなり、kは軌道角運動量の量子数と等しく、主量子数nより1だけ小さいことが示されます。このとき、シュレディンガー方程式の解となる波動関数の角度に依存する部分は、球面調和関数を使って表され、
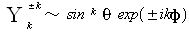
となります。φに依存する項の形から、波動関数は、磁気量子数の正負に応じて、反時計回り/時計回りの進行波解になっていることがわかるでしょう(波動関数全体には、エネルギーに依存する項 exp(-2iπEt/h) が掛かっていることを思い出してください)。つまり、ボーア=ゾンマーフェルトの量子条件をクーロン場内部で等速円運動を行う電子に適用すると、ド・ブロイ波長の整数倍が円周に等しくなるという結果を得ますが、そのときの波は、定常波ではなく進行波になっているのです。
それでは、初学者向けの教科書には、なぜ、ド・ブロイ波が定常波になると嘘が書かれているのでしょうか。おそらく、進行波についての説明を始めると、角運動量の量子化やら主量子数と角運動量量子数の関係やら、難しい議論が次々と出てきて収拾がつかなくなるからだと思われます。さらに、主量子数が1の基底状態は、磁気量子数がゼロになるため、上の議論では扱えません(1s状態を古典論における電子の等速円運動と結びつけるのは、そもそも無理があります)。何よりも、ボーア=ゾンマーフェルトの量子条件などという前時代的な代物を持ち出したくないため、いい加減な説明でお茶を濁したというのが真相でしょう。
【Q&A目次に戻る】

「影の…」という言葉は、現代物理学の超常識的な内容を一般人向けに紹介する書物でよく目にしまが、「影の光子」という言い回しは、おそらく、量子コンピュータの研究で有名なドイッチュが用いたものでしょう。
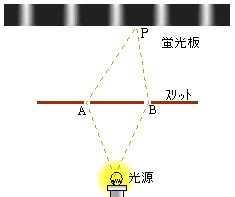
量子力学では、光は粒子性と波動性を併せ持っているとされます。二重スリット実験(ヤングの実験)で、光源から出てスリットを通り抜けた光は、通常の波動と同様に、背後のスクリーンに干渉縞を作りますが、「光は粒子だ」という立場からすると、この現象は、各スリットを通り抜けた光子が、干渉縞の明るい部分に集中し、暗い部分にはほとんど到達しない現象だということになります。しかし、粒子描像だけに基づいて考えた場合、スリットAを通り抜けた光子が暗い部分を避けて明るい部分に行こうとするのはなぜなのか、理解するのが困難です。量子力学では、スクリーン上の位置Pに光子が到達する確率は、
(Aを通り抜けた光子がPに到達する確率)
+(Bを通り抜けた光子がPに到達する確率)
+(Aを通り抜けた光子とBを通り抜けた光子の干渉項)
という形で計算され、干渉縞の暗い部分では、第3項が負になって第1,2項を打ち消しています。それでは、「Aを通り抜けた光子」に干渉してくる「Bを通り抜けた光子」とは何なのか? 古典的な粒子描像では、粒子は一方のスリットしか通り抜けられないので、光子がAを通り抜けているとき、「Bを通り抜ける光子」など実在しないはずです。
ドイッチュは、こうした状況を「多世界解釈」によって説明しようとしました。これは、ある初期状態から出発した宇宙が、多数の「平行宇宙」に分岐していくと考える立場で、二重スリット実験での干渉縞は、ある宇宙でスリットAを通り抜けた光子と別の宇宙でスリットBを通り抜けた光子が互いに干渉して作り出したと解釈されます。光子がAを通り抜けている宇宙から見ると、Bを通り抜けて干渉してくる光子は別の宇宙に属する「影の光子」だというわけです。
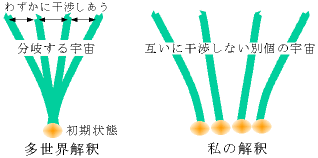
私は、個人的には、ドイッチュの解釈には賛成できません。ある初期状態に対して量子力学の計算を遂行すると、時間の経過とともに、異なる状態が実現されている「平行宇宙」に分岐していくような解が現れるのは事実です。しかも、こうした多数の宇宙は、分岐が完全ではなく、干渉現象を通じて互いに弱く影響しあっている──専門的な言い方をすれば、デコヒーレンスが完全でない──ため、現在の量子力学を全面的に信じるとすれば、わずかに干渉しあう平行宇宙の存在を認めざるを得ないでしょう。しかし、私は、分岐が完全でないように見えるのは、巨視的な物体に量子力学を適用する方法が確立されていないせいであり、平行宇宙の大多数は、本来、互いに干渉しない「別個の宇宙」と見なすべきだと考えます。こうした宇宙は、同じ初期状態を持つ異なる量子過程として区別して扱う──数学的には、経路積分の重み関数を分割して計算する──べきものであり、「この宇宙」として実現されているのは、ただ1つの量子過程であるはずです。互いに干渉しあう状態は、1つの宇宙における単一の実在を構成しており、二重スリット実験の場合には、光子がスリットAを通り抜ける過程とスリットBを通り抜ける過程の「重ね合わせ」が、こうした単一の実在になっていると考えます。ただし、これは「私の解釈」であり、異論を唱える人は大勢いるでしょう。
量子力学の解釈に関しては、いまだ物理学者の間で統一された見解はなく、1人の学者が書いた内容を真に受けるとバカを見ることがあります。
【参考文献】デイヴィッド・ドイッチュ著『世界の究極理論は存在するか』(朝日出版)
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
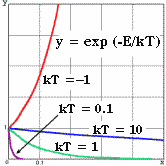 もう少し進んだ統計力学の理論によると、絶対温度T は、全エネルギーがシステムを構成する各部分にどのように分配されるかを決める量として定義されます。多数の自由度から成るシステムが熱平衡状態になっている場合、ある部分系にエネルギーEが分配される確率は、
もう少し進んだ統計力学の理論によると、絶対温度T は、全エネルギーがシステムを構成する各部分にどのように分配されるかを決める量として定義されます。多数の自由度から成るシステムが熱平衡状態になっている場合、ある部分系にエネルギーEが分配される確率は、
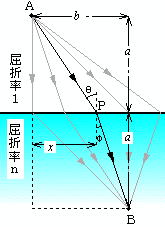 質問の小説(未読です)にも書かれているようですが、変分原理の最も簡単な例は、光の経路に関するフェルマーの原理で、「2点間を結ぶ光の経路は、その所要時間を最小にするものである」と表現されます。例として、2つの媒質の境界で光線が屈折する場合を考えましょう(ひとまず、均一な媒質中で光は直進するものとします)。図のAからPを通ってBまで光が進むのに要する時間は、(屈折率nの媒質中の光速が c/n になることより)、幾何学的距離をn倍した光学的距離、すなわち、AP+nPBに比例します。従って、フェルマーの原理を満たすのは、図のxを変えたときに光学的距離Sが最小(より一般的には極小)になるような経路となります。この条件は、Sをxで微分した値がゼロになるという形で表され、下に示すように、良く知られた屈折の法則(スネルの法則)を導きます。
質問の小説(未読です)にも書かれているようですが、変分原理の最も簡単な例は、光の経路に関するフェルマーの原理で、「2点間を結ぶ光の経路は、その所要時間を最小にするものである」と表現されます。例として、2つの媒質の境界で光線が屈折する場合を考えましょう(ひとまず、均一な媒質中で光は直進するものとします)。図のAからPを通ってBまで光が進むのに要する時間は、(屈折率nの媒質中の光速が c/n になることより)、幾何学的距離をn倍した光学的距離、すなわち、AP+nPBに比例します。従って、フェルマーの原理を満たすのは、図のxを変えたときに光学的距離Sが最小(より一般的には極小)になるような経路となります。この条件は、Sをxで微分した値がゼロになるという形で表され、下に示すように、良く知られた屈折の法則(スネルの法則)を導きます。
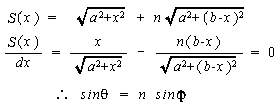
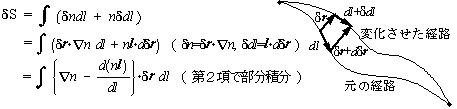
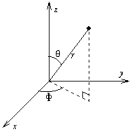 物質波の理論は、歴史的に見ると、ド・ブロイがかなり素朴な形で学位論文として1925年(執筆は1924年)に発表した後、(アインシュタインが比熱の理論との関係でコメントを加えたのを別にすると)他の学者がほとんど注目していないうちにシュレディンガーが集中的に研究し、翌1926年にシュレディンガー方程式の定式化を含む大論文にまとめてしまったため、ド・ブロイの物質波とボーアの量子条件を結びつけるという本格的な試みは行われませんでした。初学者向けの教科書で「ド・ブロイ波が定常波になる」という条件を置いて解説しているのは、初等数学だけを使ってエネルギー準位を求めるための苦肉の策であり、物理学的にはあまり正当なやり方とは言えません。
物質波の理論は、歴史的に見ると、ド・ブロイがかなり素朴な形で学位論文として1925年(執筆は1924年)に発表した後、(アインシュタインが比熱の理論との関係でコメントを加えたのを別にすると)他の学者がほとんど注目していないうちにシュレディンガーが集中的に研究し、翌1926年にシュレディンガー方程式の定式化を含む大論文にまとめてしまったため、ド・ブロイの物質波とボーアの量子条件を結びつけるという本格的な試みは行われませんでした。初学者向けの教科書で「ド・ブロイ波が定常波になる」という条件を置いて解説しているのは、初等数学だけを使ってエネルギー準位を求めるための苦肉の策であり、物理学的にはあまり正当なやり方とは言えません。
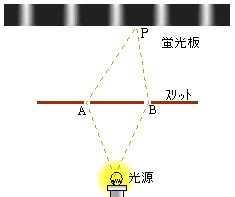 量子力学では、光は粒子性と波動性を併せ持っているとされます。二重スリット実験(ヤングの実験)で、光源から出てスリットを通り抜けた光は、通常の波動と同様に、背後のスクリーンに干渉縞を作りますが、「光は粒子だ」という立場からすると、この現象は、各スリットを通り抜けた光子が、干渉縞の明るい部分に集中し、暗い部分にはほとんど到達しない現象だということになります。しかし、粒子描像だけに基づいて考えた場合、スリットAを通り抜けた光子が暗い部分を避けて明るい部分に行こうとするのはなぜなのか、理解するのが困難です。量子力学では、スクリーン上の位置Pに光子が到達する確率は、
量子力学では、光は粒子性と波動性を併せ持っているとされます。二重スリット実験(ヤングの実験)で、光源から出てスリットを通り抜けた光は、通常の波動と同様に、背後のスクリーンに干渉縞を作りますが、「光は粒子だ」という立場からすると、この現象は、各スリットを通り抜けた光子が、干渉縞の明るい部分に集中し、暗い部分にはほとんど到達しない現象だということになります。しかし、粒子描像だけに基づいて考えた場合、スリットAを通り抜けた光子が暗い部分を避けて明るい部分に行こうとするのはなぜなのか、理解するのが困難です。量子力学では、スクリーン上の位置Pに光子が到達する確率は、
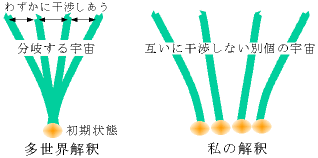 私は、個人的には、ドイッチュの解釈には賛成できません。ある初期状態に対して量子力学の計算を遂行すると、時間の経過とともに、異なる状態が実現されている「平行宇宙」に分岐していくような解が現れるのは事実です。しかも、こうした多数の宇宙は、分岐が完全ではなく、干渉現象を通じて互いに弱く影響しあっている──専門的な言い方をすれば、デコヒーレンスが完全でない──ため、現在の量子力学を全面的に信じるとすれば、わずかに干渉しあう平行宇宙の存在を認めざるを得ないでしょう。しかし、私は、分岐が完全でないように見えるのは、巨視的な物体に量子力学を適用する方法が確立されていないせいであり、平行宇宙の大多数は、本来、互いに干渉しない「別個の宇宙」と見なすべきだと考えます。こうした宇宙は、同じ初期状態を持つ異なる量子過程として区別して扱う──数学的には、経路積分の重み関数を分割して計算する──べきものであり、「この宇宙」として実現されているのは、ただ1つの量子過程であるはずです。互いに干渉しあう状態は、1つの宇宙における単一の実在を構成しており、二重スリット実験の場合には、光子がスリットAを通り抜ける過程とスリットBを通り抜ける過程の「重ね合わせ」が、こうした単一の実在になっていると考えます。ただし、これは「私の解釈」であり、異論を唱える人は大勢いるでしょう。
私は、個人的には、ドイッチュの解釈には賛成できません。ある初期状態に対して量子力学の計算を遂行すると、時間の経過とともに、異なる状態が実現されている「平行宇宙」に分岐していくような解が現れるのは事実です。しかも、こうした多数の宇宙は、分岐が完全ではなく、干渉現象を通じて互いに弱く影響しあっている──専門的な言い方をすれば、デコヒーレンスが完全でない──ため、現在の量子力学を全面的に信じるとすれば、わずかに干渉しあう平行宇宙の存在を認めざるを得ないでしょう。しかし、私は、分岐が完全でないように見えるのは、巨視的な物体に量子力学を適用する方法が確立されていないせいであり、平行宇宙の大多数は、本来、互いに干渉しない「別個の宇宙」と見なすべきだと考えます。こうした宇宙は、同じ初期状態を持つ異なる量子過程として区別して扱う──数学的には、経路積分の重み関数を分割して計算する──べきものであり、「この宇宙」として実現されているのは、ただ1つの量子過程であるはずです。互いに干渉しあう状態は、1つの宇宙における単一の実在を構成しており、二重スリット実験の場合には、光子がスリットAを通り抜ける過程とスリットBを通り抜ける過程の「重ね合わせ」が、こうした単一の実在になっていると考えます。ただし、これは「私の解釈」であり、異論を唱える人は大勢いるでしょう。