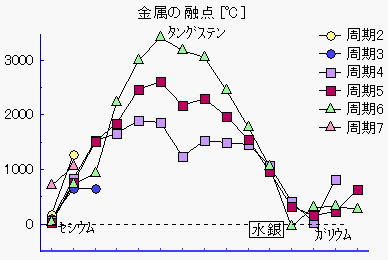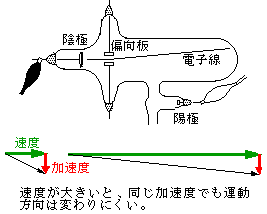
クルックス管は、陰極から飛び出した電子が直進することを示す教材として使われることが多いのですが、なぜ電子が引力を及ぼしている陽極に向かわずに真っ直ぐ進むのか、適切な説明なしに終わらしてしまうことがあります。ポイントは、陰極を飛び出した直後の加速度の大きさにあります。
陰極近傍の電場は、極面に垂直な方向を向いています。電子は質量が0.9×10
-30kgと小さいため、電気的な力が弱くても加速度はきわめて大きくなります。例えば、静止状態から1Vの電圧で加速した電子は、秒速600kmにもなります。陰極の近くで高速になった電子は、電気力線に沿った横向きの(比較的弱い)力を受けても、ほとんど向きを変えずに真っ直ぐ飛んでいきます。これは、速度が大きい場合は、同じ加速度を受けても、運動方向の変化が小さくなるためです(右図)。
ガラス管の底に到達した電子は、主に、ガラスの表面を通って陽極まで流れていきます。ガラス自体は絶縁体であり、電子が通り抜けることはできませんが、表面に汚れなどがあれば、それを伝って簡単に通電します。
【Q&A目次に戻る】

二酸化炭素は、もともと大気中の含有量が微量なので、人間の産業活動によって濃度が大きく変化していますが、酸素ははるかに大量にあるため、人為的な影響が表に現れにくくなっています。
地上付近の大気成分(水蒸気を除く)を示しておきます。
| 窒素 | 78.088*** |
| 酸素 | 20.949*** |
| アルゴン | 0.93**** |
| 二酸化炭素 | 0.04**** |
| ネオン | 0.0018** |
| ヘリウム | 0.000524 |
| メタン | 0.00014* |
| クリプトン | 0.000114 |
| 一酸化二窒素 | 0.00005* |
| 水素 | 0.00005* |
| 一酸化炭素 | 0.00001* |
(二酸化炭素は、地域的・季節的変動が大きい)
(出典:フリー百科事典 "Wikipedia")
二酸化炭素の濃度は、化石燃料の燃焼や吸収源となる森林の伐採によって、産業革命以前の280ppmから現在の360ppmへと30%ほど増加しており、このままの傾向が続けば、21世紀の終わりには500ppm以上になると予想されています。しかし、同じ量の酸素が減少したとしても、気体酸素の濃度を1000分の1程度変化させるにすぎません。産業革命以降の酸素濃度の変動を調べようにも、誤差に埋もれて正確なところは分からないのです。
酸素はきわめて反応性に富んだ元素で、生物のいない環境では、さまざまな酸化物の形で閉じこめられており、大気の主要な成分にはなれません。地球大気に大量の気体酸素が含まれているのは、20億年ほど前にシアノバクテリアが酸化物中の酸素を解放したことに始まり、その後は、各種の反応によって失われる分を、次の反応式で表される光合成を行う植物が持続的に供給しているからです。
CO
2 + H
2O → CH
2O + O
2
(CH
2O は、炭水化物を略記したものです)
酸素の供給源となるのは、主に海洋中の植物プランクトン(藻類など)です。陸上の植物は、光合成によって酸素を放出しても、自身が枯れたり食べられたりする過程で再び酸素を結合してしまう(上式の逆反応が起きる)ので、(泥炭になる一部の植物を別にすれば)酸素の循環しか行っていません。これに対して、海洋中の植物プランクトンは、0.1%ほどが海底に堆積して生物圏から失われる(上式右辺の CH
2O がなくなる)ので、逆反応によって打ち消されずに、酸素の供給を行うことができるのです。人類は、この堆積物の一部を掘り出して化石燃料として燃やしてしまい、過去の植物が放出した酸素を再び酸化によって消費しているわけです。
現在の酸素濃度は、植物プランクトンによる供給とさまざまな酸化反応(燃焼を含む)による喪失とのバランスの上に成り立っています。一般に、酸素濃度が増えると酸化反応が盛んになり、減ると抑制されるので、負のフィードバックが働くことになり、濃度は長期にわたって安定していました。産業活動による酸素消費は、自然界における酸化反応に比べてごく微量なので、酸素濃度を大きく変えるには至っていませんが、このまま大量の酸素消費を続けるとともに、化学汚染やオゾンホールによって海洋生態系を破壊し植物プランクトンを死滅させると、酸素濃度に影響が出てこないとも限りません。
【Q&A目次に戻る】

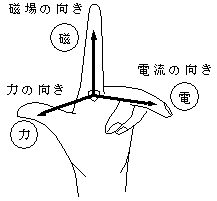
「それが自然界の法則だから」と言ってしまっては身も蓋もないので、この法則が奇妙に感じられる理由を考えてみたいと思います。
フレミングの左手の法則とは、左手の3本の指を直角になるように伸ばしたとき、電流が中指の向き、磁場が人差し指の向きを向いていたとすると、磁場から電流に作用する力は親指の向きになるというものです。ここで不思議なのは、なぜ、電流や磁場の向きと直交する方向に力が作用するかです。力学を勉強した人ならば、これと似たものとして、「コリオリの力」を思い出すでしょう。この力は、地球のような回転体の上で動いている物体に作用するもので、その向きは、回転軸と進行方向の両方に直交しています。ただし、コリオリの力は“真の力”ではなく、座標系が回転することによって運動方向がずれる効果を力の作用として表した“見かけの力”にすぎません。電流が磁場から受ける力は、現実に作用していると考えられるので、コリオリの力とのアナロジーは、作用する向きが似ている点に限られます。
本当のことを言うと、「磁場の向き」の定義に問題が隠されているのです。多くの人は、小学校の頃から、磁石のN極からS極に向かう磁力線のイメージに馴染んでいるため、磁場の向きを自明のものとして受け入れているでしょう。しかし、物理学では、向きを持ったベクトルとしては磁場を定義できないことが知られています。実際、空間の向きが全て反対になった──座標を(x,y,z)から(-x,-y,-z)に変換した──場合を考えると、電場や電流、力のベクトルは符号が逆になりますが、磁場は変化しません。磁場
Bとは、実は、通常のベクトルではなく、電磁場テンソルF
ijの成分であり、
B
x = F
yz, B
y = F
zx, B
z = F
xy
という関係で結ばれています。フレミングの左手の法則で、磁場は電流や力と直交しているように見えますが、電磁場テンソルの成分として考えると、電流および力と同じ“向き”になっているのです。
アインシュタインの相対性理論によると、磁場と電場は独立した量ではなく、座標系の変換によって互いに混じり合うことが示されます。電流とは電荷の運動であり、その平均速度と同じ速度で動く座標系から見ると、電荷は全体として静止していることになります。元の座標系で、電流はy方向に、磁場
Bはz方向に“向いて”いるものとしましょう。相対論の公式を使うと、電流とともに(y方向に)運動している座標系では、元の磁場B
z(=F
xy)の一部が電場E
xに変換され、静止している電荷に対してx方向の力を及ぼすことがわかります。この静電気的な力は、電荷が運動している座標系での「磁場から電流に作用する力」と同じものであり、「速度に直交する力」というわかりにくい表現を使わずに、その起源を理解することができます。
【Q&A目次に戻る】

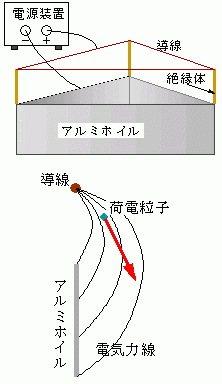
質問にあるのは、10月6日にフジテレビ系で放送された『100年後の超偉人たち(秘)ランキングSP』のことだと思います。肝心の番組を見ていないので、断定的なことは言えませんが、質問文や、この番組に関するBBSでのやり取りを読む限り、イオンクラフトの一種だと思われます。イオンクラフトは、電圧によってイオンを加速して空気の流れを作り出す機構で、これを元に、アルミホイルや導線を組み合わせて浮遊する装置を作ることも難しくありません。
最も簡単な浮遊型イオンクラフトは、右図のような構造をしています(形は丸でも三角でもかまいません)。導線が+極、アルミホイル(あるいは表面の大きな導体)が−極になるようにして数万ボルトの直流電源を接続すると、面積の小さい導線の周囲には電気力線が密に集まるために、強い電場が形成されます。実物を見たことがないので推測になりますが、おそらく、この強い電場によって導線付近の気体分子などから電子が奪われ、正に帯電した粒子が+極からの反発力を受けて運動するため、下向きの空気の流れが作り出されるのでしょう。また、導線の方も、荷電粒子からの反作用として上向きに力を受けることになります。極性を逆にした場合には、導線が−極になって粒子を負に帯電させ、同じ仕組みで下向きの流れを作り出します。このとき、電源を通って流れる電流はごく微弱なものになるため、磁気的な作用は関与していないはずです。
イオンクラフトは、機械的な駆動部分がなくても浮遊するので、新しい乗り物に応用できると期待する人もいるようです。しかし、数万ボルトの高電圧を用いても、作られる気流はそよ風ほどもなく、きわめて軽い(比重の小さい)物体しか浮き上がりません。より強力な電源を用いると、空気の絶縁破壊が起きて放電が始まるため、かなり危険です。機構が簡単なので何か応用があれば面白いのですが、今のところは、高校の文化祭などで物理部のデモンストレーションなどに使われる程度です。
【Q&A目次に戻る】

その通り、もし中性子の質量が実際の値よりもほんの少し小さければ、電子と陽子が接触すると中性子に変化してしまい、水素原子をはじめとする全ての物質は壊れてしまいます。そうした現象が起きないのは、われわれにとって幸いなことです。
中性子(n)が陽子(p)・電子(e)・ニュートリノ(ν)に変化する現象は、ベータ崩壊として知られており、次の反応式で表されます:
n → p + e + ν
anti
(反ニュートリノをν
antiと書きました)
この反応は、化学で言うところの“発熱反応”であり、外部からエネルギーを注入しなくても、自然に進行します。実際、真空中に置かれた中性子は、平均1000秒で3つの粒子に壊れてしまいます(原子核内の中性子は、強い相互作用を通じて陽子に変化できるので、ベータ崩壊しません)。発熱反応になるかどうかは、反応式両辺のエネルギーの大小によります。アインシュタインの関係式により、質量m の物体は、静止していても、mc
2 というエネルギーを有しています。質量がほぼゼロであるニュートリノを除くと、各粒子の質量は、次のようになります。
m
n = 1.67495 × 10
-27 [kg]
m
p = 1.67265 × 10
-27 [kg]
m
e = 0.00091 × 10
-27 [kg]
したがって、
m
nc
2 > m
pc
2 + m
ec
2
となり、中性子は3つの粒子に運動エネルギーを与えてベータ崩壊することができます。
しかし、陽子と電子が中性子に変わる反応:
p + e → n + ν
では、質量のエネルギーだけで比較すると、右辺の方が左辺より
Δmc
2 = 0.78 × 10
6 [eV]
だけエネルギーが大きくなっています([eV]はエネルギーの単位の一種です)。水素原子の基底状態のエネルギーは -13.5[eV] ですから、化学反応で得られる程度のエネルギーでは、陽子と電子を中性子に変えるには5桁も不足することがわかります。このため、軌道電子が中心部にある陽子に接近したとしても、両者が反応して中性子に変わり、物質が崩壊することは起きないのです。
【Q&A目次に戻る】

ラザフォードが原子核を発見して以来、原子の周りを回る電子がなぜ原子核に落ち込んでいかないかは、物理学者にとって大きな謎でした。地球を回る人工衛星が大気との摩擦でエネルギーを失って落下するのと同じように、電子も回転することで電磁波を放出してエネルギーを失い、軌道半径が小さくなって原子核と衝突するのが自然に思われたからです。
この謎に対するボーアの解答は、きわめて突飛なものです。彼は、電子が陽子の周りを半径aの等速円運動していると仮定しました。このときのエネルギーEは、簡単な計算より、
E = -e
2/2a
さらに、この円運動の振動数ν(=1/周期)は、ケプラーの第3法則よりaの3/2乗に逆比例しているので、
ν = k|E|
3/2
と表されます(kは簡単に計算できる定数)。ここで、ボーアは、エネルギーのやり取りは hνという固まり(エネルギー量子)を単位とするというプランク=アインシュタインの仮説に基づいて、電子は、自然状態からhν' というエネルギー量子をn個だけ放出して、エネルギーEの結合状態に達したと仮定しました。すなわち、
E = -nhν'
ただし、彼は、よくわからない理由で、ν'=ν/2 と置いています。この仮定に基づいて計算すると、
E = -nhk|E|
3/2/2
となるので、
-E ∝ 1/n
2
という関係式が得られます。これによれば、n=1 が最低エネルギー状態となり、それよりエネルギーの小さい状態には、振動数が特定の値に限られているエネルギー量子を放出して遷移することができないのです。エネルギーが−∞となる原子核と合体する状態への遷移も、同じ理由で禁じられます。
ボーアが提出した水素原子模型は、実験結果とほぼ完全に一致したため、自然界の基本原理を見事に剔抉したものと見なされ、その後、さまざまな改良が加えられます。細かな歴史的経緯は省略しますが、この模型がベースとなって、ボルン=ハイゼンベルグの行列理論ができあがったと言って良いでしょう。このように、成功した理論の出発点に位置しているため、ボーアの理論は、歴史的に高く評価されています。しかし、量子力学を勉強した後で見直すと、なぜ放出されるエネルギー量子が上の値に限られるのかなど、何を言っているのかよくわからない点が多々あります。電子が原子核に落ち込まない理由が正しく説明されるのは、ド・ブロイの定常波の理論を発展させた波動力学が完成されてからだと言うべきでしょう。
【Q&A目次に戻る】

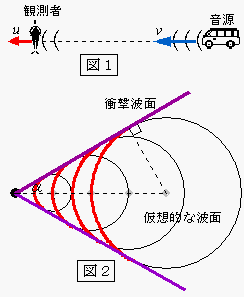
直線上を音源と観測者が運動している場合のドップラー効果の公式は、“音源が観測者に近づく速度”をv、“観測者が音源から遠ざかる速度”をu、音速をc、音源での振動数をf
0、観測される振動数をfとすると、
f = f
0 (c-u)/(c-v)
となります。音源が超音速で静止している観測者に近づいてくる場合、右辺分母が負になりますが、音は音源より遅れてやってくるので、この間に奇妙な現象が生じることはありません。また、衝撃波が通り過ぎた後は、観測者から遠ざかることになり、vは負になるので、通常のドップラー効果と同様に計算できます(v=2cならば振動数は1/3になります)。
それでは、音源が目の前を通り過ぎる瞬間に音の順番が逆になるかというと、そういうことも起こりません。音源から順次発射される波面が単純な球面波になると仮定すると、音源が超音速で動いている場合は、波面の順番が入れ替わるようにも見えます(図2)。しかし、実際には、音源が波面を追い越すことはできません。図で言うと、赤で描かれた部分の波面は実際には存在せず、無数の波面が圧縮されて、波面の包絡面となる部分に1つの衝撃波面(マッハ面)を形成します。衝撃波面は円錐状になっており、その頂角2αは、次式で与えられます。
sin2α = v/c
このように、音源が超音速で動いている場合に音の逆転現象は起きませんが、観測者が超音速になると、いろいろと面白いことが起きるはずです。もちろん、観測者が巨視的な物体で周辺の空気を乱してしまうと音の観測はできませんが、分子間隔程度のきわめて小さい装置を使うことによって空気の擾乱を無視できるほど小さく抑えるか
(これは技術的に困難でしょう)、あるいは、レーザー光照射などの手段により観測ポイントを超音速移動させながら空気の密度を測定することができるならば、波面を追い越していく過程での疎密の変化を捉えることが可能になるはずです。ちょうど音速の2倍で波面を追い越していったとき、観測される疎密の変化は、静止している観測者が捉える波形とは時間軸が逆になったものになるので、これを音として再現すると、テープレコーダを逆回転させたときの音になると考えられます。
【Q&A目次に戻る】

金属結晶は、自由電子の海の中に正電荷を持つイオンが浮かんでいるようなもので、金属結合には、主に、自由電子と陽イオンの間の静電気的な力が寄与していますが、内側の電子も無関係ではありません。金属の融点は、電子軌道の差によって、下は水銀の -38.9℃ から、上はタングステンの 3410℃ まで、かなりの開きがあります。周期律表に合わせて融点をグラフ化してみました
(族に関しては技術的な理由で左詰になっており、ランタン系列とアクチニウム系列は省略しています)。これからわかるように、水銀の融点が抜きん出て低いというわけではありません。セシウム(28.5℃)やガリウム(29.8℃)も、融点がかなり低くなっています。
金属の融点を大きく左右するのは、d軌道電子の状態だと言われています。d軌道が不完全な(“空いている”箇所が全て電子で満たされていない)遷移金属では、d電子が結合エネルギーを大きくするような寄与をするので、結晶は固く結びつき、一般に融点が1000〜3000℃程度に高くなります。逆に、d軌道が満たされている第12族の金属の場合、水銀だけでなく、亜鉛(419.6℃)とカドミウム(320.9℃)も低い融点を持っています。中でも水銀は、亜鉛やカドミウムよりも原子核の陽子数が多く、強いクーロン力によって軌道電子が核に引きつけられるため、金属結合に関与する自由電子を放出しにくくなり、亜鉛族の中でも、特に融点が低くなるのです。
常温で液体なのは確かに水銀だけですが、これは、「ほとんどの金属が常温で固体であるのはなぜか」と問い直した方がわかりやすいでしょう。ここで「常温」というのは、生物の生存に適した温度と考えられます(適していなければ、「なぜ水銀は液体なのか」と思い悩む生き物は存在しないはずですから)。地球上の生物にとっては、水が液体であることが生存にとって欠かすことができませんが、水分子同士を結合させる水素結合は金属結合に比べるとかなり弱いという特徴があります。メタンやアルコールなどの有機物でも同様で、やはり常温で液体か気体になります。水素結合が固体結晶の結合より弱いために、有機物はさまざまな化学反応を起こしやすく、複雑にして精妙な生化学現象を実現できるのです。水が液体であるような「常温」で大半の金属が固体になるのは、「生物の活動を支える物質の結合力は金属よりも著しく弱い」からだと言えるでしょう。
(グラフの作成には、Koichi Yoshioka氏のフリーソフト KyPlot ver2.0 を使用しました)
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
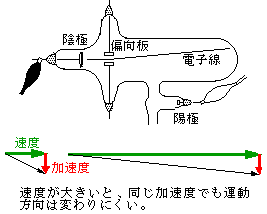 クルックス管は、陰極から飛び出した電子が直進することを示す教材として使われることが多いのですが、なぜ電子が引力を及ぼしている陽極に向かわずに真っ直ぐ進むのか、適切な説明なしに終わらしてしまうことがあります。ポイントは、陰極を飛び出した直後の加速度の大きさにあります。
クルックス管は、陰極から飛び出した電子が直進することを示す教材として使われることが多いのですが、なぜ電子が引力を及ぼしている陽極に向かわずに真っ直ぐ進むのか、適切な説明なしに終わらしてしまうことがあります。ポイントは、陰極を飛び出した直後の加速度の大きさにあります。
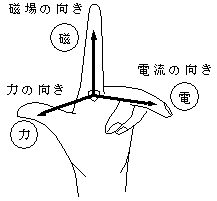 「それが自然界の法則だから」と言ってしまっては身も蓋もないので、この法則が奇妙に感じられる理由を考えてみたいと思います。
「それが自然界の法則だから」と言ってしまっては身も蓋もないので、この法則が奇妙に感じられる理由を考えてみたいと思います。
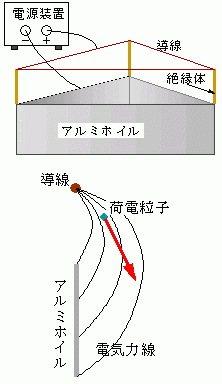 質問にあるのは、10月6日にフジテレビ系で放送された『100年後の超偉人たち(秘)ランキングSP』のことだと思います。肝心の番組を見ていないので、断定的なことは言えませんが、質問文や、この番組に関するBBSでのやり取りを読む限り、イオンクラフトの一種だと思われます。イオンクラフトは、電圧によってイオンを加速して空気の流れを作り出す機構で、これを元に、アルミホイルや導線を組み合わせて浮遊する装置を作ることも難しくありません。
質問にあるのは、10月6日にフジテレビ系で放送された『100年後の超偉人たち(秘)ランキングSP』のことだと思います。肝心の番組を見ていないので、断定的なことは言えませんが、質問文や、この番組に関するBBSでのやり取りを読む限り、イオンクラフトの一種だと思われます。イオンクラフトは、電圧によってイオンを加速して空気の流れを作り出す機構で、これを元に、アルミホイルや導線を組み合わせて浮遊する装置を作ることも難しくありません。
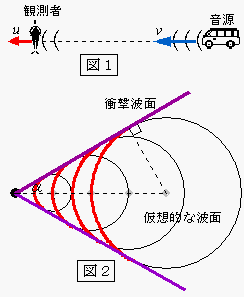 直線上を音源と観測者が運動している場合のドップラー効果の公式は、“音源が観測者に近づく速度”をv、“観測者が音源から遠ざかる速度”をu、音速をc、音源での振動数をf0、観測される振動数をfとすると、
直線上を音源と観測者が運動している場合のドップラー効果の公式は、“音源が観測者に近づく速度”をv、“観測者が音源から遠ざかる速度”をu、音速をc、音源での振動数をf0、観測される振動数をfとすると、