
この質問は、2つに分けて考えなければなりません。
まず、前半の部分について、お答えします。相対論では、ある座標系から速度vで運動する時計と物差しを見たときに、「時計はβ倍だけゆっくり進み、物差しは1/βに縮む」ことが示されています。ただし、βはローレンツ因子と呼ばれる量で、次式で定義されます:
β = (1-(v/c)
2)
-1/2
です。vが光速の87%になるとβは2なので、静止系の時計が1秒を刻む間に運動する時計は0.5秒しか進まず、運動する1mの物差しは静止系で計ると0.5mしかないことになります。従って、静止系で1秒間に30万km進む光の進行を運動している時計と物差しを使って計ると、0.5秒間に60万km進んでいることになる?? 光速で運動している座標系を考えれば、時計は進まずに物差しは無限小になるから、光の速さは無限大のはず???
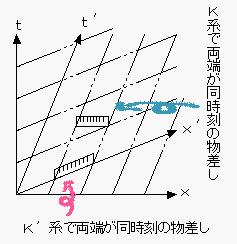
この議論がなぜおかしいかというと、「ある座標系で物差しの長さを計るときには、両端が同じ時刻のはずだ」という暗黙の前提が成り立っていないからです。運動している座標系で両端が同時刻になるように長さを計ったとしても、静止系から見ると、先端の位置を後端の位置よりも少し遅れて計っていることになります。従って、運動系の観測者が「物差しは1mだ」と言っても、静止系の観測者は、先端が少し遠くへ動いてから計ったので、「その値は過大評価で実際にはもっと短い」と考えることになります。これが、いわゆる“ローレンツ短縮”の起源であり、短いとされる割合は1/β
2になります。この部分を補正すると、運動座標系では静止座標系から見て時間と空間が同じβ倍だけ伸張していることが示されます。時間と空間の変化が同じ割合で起こるのですから、光の進行速度は、静止座標系から見ても運動座標系から見ても、同じ秒速30万kmになります。これは、座標系の速度vをcに近づける極限まで成立します。
質問の後半は、相対論の本質に関わるものです。「相対論は間違っている」と主張する論者は少なからずいますが、その多くが、相対論に現れるcを、実際に光が進む速度だと見なしています。しかし、光が本当にcで進行しているのか、厳密に測定されたわけではありませんし、相対論が成り立っているにもかかわらず「光の進行速度がcより小さい」ような理論も提唱されています。「マクスウェル方程式は巨視的には正しい」という経験則があるのでcイコール光の進行速度と置いていますが、相対論の論理構造を厳密に公理化すると、cは4次元幾何学における時間と空間の単位の換算定数にすぎないことが示されます。歴史的に、空間の単位1mは地球の子午線の4000万分の1、時間の単位1秒は地球の自転周期の86400分の1と恣意的に決めたために、c=30万km/sという値が必要となっていますが、実は、cとは、熱の仕事当量Jやボルツマン定数k(あるいは平方メートルと坪の換算定数3.3)と同様に、本来は同じ単位で計るべきものを別々の単位で表したときの換算定数として導入されるものなのです。ミンコフスキ空間で定義される4次元幾何学では、時間と空間はどちらも幾何学的な長さを表すものなので、同じ単位で表されるのが自然であり、仮に空間長も秒単位で表すものとすると、cは(常に1に等しいので)不必要になります。実際、基礎物理学を研究する物理学者の多くが、cを用いない“自然単位系”を使って計算式を見やすくしています。
【Q&A目次に戻る】
 回答篇59
回答篇59に記載されてある、量子サイズについてお尋ねした者ですが、回答が理解できません。結局、「波としての性質」とは、どういうことなのでしょうか?【現代物理】

電子のように自由度が少なく量子力学の効果が現れやすい対象は、(非相対論近似が使える範囲では)あたかも「波に導かれている」かのように運動することが知られています。特に有名なのが、二重スリットを使った干渉実験で、電子線を二重スリットに照射すると、光学におけるヤングの実験の場合と同様に、背後に置かれたスクリーンに強弱の干渉パターンが現れます。
小さな金属片に閉じこめられている電子の場合、電子の波長と金属の大きさが同程度になるようなエネルギー領域では、まるで金属内部に電子の定常波が存在しているかのような振舞いを示します。バスタブの中で水を大きく揺すると特定の周期・波長で振動を始めるように、金属内部の電子は、決まった波長(金属が完全な立方体である場合は、1辺の長さの半整数分の1)と、それに応じたエネルギーを持つことになります。このケースでは、二重スリット実験のように、定常波の干渉縞を視覚的に示す実験はなかなか難しいので、状態が離散的になるというのが、波動性が最も顕著に現れる例だと言えるでしょう。
状態の離散化を通じて微小な金属における電子の波動性を捉える実験は、すでに数多く実施されています。例えば、半導体に金属を蒸着して作るミクロの回路で、電子の通り道にくびれを作り、そこに電圧を加えて電流の流れ方を制御する場合、くびれ部分の電子の状態は離散的になるため、加えた電圧に応じて電流がなめらかに変化するのではなく、階段状に変化することが知られています。このとき、ちょうど水路を横断する向きに波が立っているのと同様に、くびれ部分に電子の波が生じていると考えられます。
【Q&A目次に戻る】

科学哲学と呼ばれる学問分野には、最先端科学の知見を認識論や存在論などの哲学的な議論に援用する「科学的哲学」や、『相対論の哲学』のように科学の成果を哲学的観点から基礎づける「科学の哲学」、科学者の研究手法を論じる「科学的方法論」、社会への応用に主たる関心を向ける「科学社会学」などが混在していますが、質問にあるラカトシュやローダンは、通時態に関する議論をベースに科学の実態を明らかにしようとする「科学史/科学哲学」(としか言いようのない分野)の研究者だと言えるでしょう。
学説の受容や消長などの時間的変化に基づく科学論の代表者としてしばしば名前を挙げられるのが、トマス・クーンです。彼が『科学革命の構造』で提唱した「パラダイム」という概念は、科学者によっても頻繁に使われており、さして斬新でもないアイデアを "new paradigm" と呼んで読者を混乱させるという困った傾向すら見られるほどです (J.Cohen, "The March of Paradigms," Sience 283(1999)1998-)。しかし、だからと言って、科学者たちが彼の業績を高く評価しているわけではありません。「クーンの主張は大ざっぱに言って正しい」という程度の受け止め方ですし
(一人の科学者が異なるパラダイムに則って研究したり、通常科学の範囲で革命的なアイデアが提出されたりするのは、“ささやかな”逸脱です)、「パラダイム」も、せいぜい“研究方法とセットになった総合的な学説”だと解釈しているようです。実際のところ、『科学革命の構造』には、パラダイムの厳密な定義はありません。クーンが挙げた多くの事例に合致するように最大公約数的な(きわめてルースな)解釈を採用すれば、確かに、パラダイムという概念は、学説の流れをわかりやすくまとめる上で有用です。それが、パラダイム論の唯一のメリットだと言ったら、怒られるでしょうか。
(ファイヤアーベントのような極端な論客を別にすれば)ラカトシュやローダンなどの科学史/科学哲学者の業績は、クーンの“大ざっぱな”科学論を精緻化しようという試みと言えなくもありません。ラカトシュの「研究プログラム」論は、学説群における不変性の高い「堅い核」の部分と容易に変化する部分を区別するものですし、ローダンは、受容における研究伝統の重要性を強調しています
(私は、ローダンの著書のうち『科学は合理的に進歩する』(サイエンス社)を斜め読みしただけなので、あまり口幅ったいことは言えませんが)。しかし、科学論を精緻化しようとすればするほど、多くの例外を許容しなければならなくなります。科学とは、さまざまな応用を担った実に多様な営みであり、単純な枠組みには収まりきらないからです。この分野で業績を上げる一番簡単な方法は、先行理論を厳格に適用すると説明できない事例があることを指摘し、そうした事例でも説明できる新しい理論を提唱することです。科学史をひもとけば、ある科学論に対する反例はいくらでも見つけられるので、簡単に本を1冊書くことができるというわけです。しかし、そうした“ためにする”議論に、どれほどの学問的価値があるかは、かなり疑わしく感じられます。
もし、ラカトシュやローダンの科学論が、本当に科学の実態を解明しているのならば、科学的な研究プロジェクトを開始するに当たって、組織の構成などに彼らの理論を参考にしてもおかしくないはずです。しかし、そんな話は聞いたことがありません。科学史/科学哲学者による議論の多くは、概念を厳格化すると、例外がポロポロと出てきて信憑性が失われますし、ルースに解釈すれば、説明としてはわかりやすくなっても、科学者に「なるほど、そうだったのか」と膝を叩かせるようなインパクトは期待できません。「パラダイム」とか「(不動の信念となる)堅い核」、あるいは「(行動を規制する)伝統」といった用語は、科学だけではなく、起業家や投資家の行動を説明するのにも使える便利な概念なので、社会学の分野に応用すれば良いという考え方もあります。確かに、これらの概念を使って、どんな歴史に関しても「大ざっぱに言って正しい」記述を容易に作り上げることができるでしょう。しかし、そうした曖昧さは、科学者がいたく毛嫌いするものです。
科学論文にその学説が最も頻繁に引用される哲学者は、カール・ポパーです(AAASのオンライン検索で "Karl Popper" という語句を含む論文は100篇見つかりました)。彼の「反証可能性」の議論は、他の哲学者や科学史家たちに厳しく批判されているにもかかわらず、多くの科学者の間で「唯一のまともな科学哲学」として高く評価されています。その理由は、ポパーのテーゼ──彼が実際に述べた形ではなく、現実の科学に適用可能なように読み替えたもの──が、科学を非科学から峻別する核心となる要素を正しく指摘しているからです。科学史/科学哲学の分野では、残念ながら、ポパーに匹敵する業績は、いまだ現れていないようです。
【Q&A目次に戻る】

宇宙を膨張させるエネルギーの起源に関しては、現在なお、完全に解明されたわけではありません。
当初のビッグバン理論では、膨張のエネルギーは、宇牛開闢の瞬間に与えられたことになっていました。最初の大爆発で大きな初速度を与えられ、その勢いで膨張を続けるというものです。こうした大爆発がどのようにして起きたかは全く説明されませんでしたから、正に、“神の一撃”とでも呼ぶべきものでしょう。
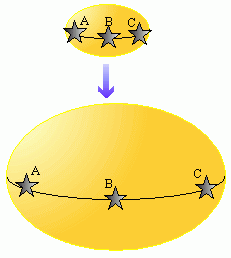
その後、宇宙初期に相転移が起きたという説が提出され、エネルギーの起源に1つの説明が与えられました。宇宙の始まりには、物質も何も存在しない状態にあったものの、途中で空間の状態が変化し、始まりの状態よりもエネルギーの低い真空と、空間からエネルギーを受け取って生まれた高エネルギー物質に分かれ、急激な膨張が生じたというものです。この説で、膨張宇宙の多くの謎が解決されたと考えられました。
ハッブルの原理によれば、遠方の銀河は、天の川銀河からの距離に比例する速度で遠ざかっていることになります。観測可能な最も遠い銀河は、後退速度がほぼ光速になっており、それより遠くの銀河を観測することは、原理的に不可能です。ただし、遠くの銀河ほど後退速度が大きくなっているからと言って、その分だけ加速されているわけではありません。この宇宙は、(エディントンの有名な比喩を使えば)膨らんでいる風船の表面のようなものです。風船の表面にある天体AからBとCを見ると、Cの方がBよりも2倍の速さで遠ざかっているように見えます。しかし、風船の膨らみ方は、どの部分でも同じであり、CがBよりも加速されているというわけではありません。むしろ、宇宙全体は、天体間の万有引力に引っ張られて膨張のスピードが減速されつつある──宇宙論研究者の大半が、そう考えてきました。
ところが、1998年に、宇宙全体の膨張速度は、遅くなるどころか、逆に加速されているという観測結果が報告されました。これが本当だとすれば、宇宙を加速膨張させるエネルギーがどこかに隠されているはずです。このエネルギーは、「ダークエネルギー」と呼ばれており、真空に含まれるエネルギーだとの見方が強いようですが、いまだに結論は出ていません。
【Q&A目次に戻る】

ヒッグス粒子は、クォークや電子などの素粒子に質量を与える粒子であって、重力と直接の関係はありません。こんにち支持されている場の理論によれば、電子という粒子は電子場の、クォークという粒子はクォーク場の励起状態だと考えられています。それと同じように、ヒッグス粒子もヒッグス場の励起状態に相当します。ところが、ヒッグス場は、電子場や電磁場(光子の場)とは異なり、電荷もスピンもないスカラーと呼ばれる場です。このため、ゼロとは異なる値で空間の中にベッタリと瀰漫した凝縮状態になることが許されます。われわれが真空と呼んでいる空間は、実は、その内部にヒッグス場が凝縮したものなのです。
ヒッグス場の凝縮がなければ、クォークも電子も質量を持たず、光速で飛び回ることになります。しかし、真空中にヒッグス場が凝縮していると、これと相互作用しながら──直観的に言えば、ヒッグス粒子が沈殿している中を掻き分けるようにして──進んでいかなければならないので、“動きにくさ”という意味での慣性が生じます。これが、質量の起源です。質量mを持った粒子は、最低でもmc
2という大きなエネルギーを持つことになり、対生成によって真空から簡単に作るというわけにはいかなくなります。こうして、ヒッグス場が凝縮していなければ光速でエネルギーを運び去っていたはずのさまざまな粒子が、光速よりも遥かに遅い速さでしか動けなくなり、空間に漂う物質として存在することが可能になります(厳密に言えば、CP対称性の破れによって、反粒子よりも粒子の数が多くなることが必要です)。こうした物質が多量に存在すると、重力場との相互作用が大きくなり、互いに引き合って凝集し、遂には恒星や銀河を作り上げていきます。
ヒッグス場はどのように凝縮しているのか、あるいは、そもそもヒッグス場というものが本当に存在しているのか──といった点については、完全には解明されていません。しかし、質量を生み出すこうした理論形式が正しいとすると、少なくとも、精密に観測されている近隣の銀河周辺までは、ヒッグス場は一様に凝縮していると考えられています。そうでなければ、場所によって電子や陽子の質量が違うことになってしまいますから。
【Q&A目次に戻る】

この宇宙はビッグバンという大爆発で始まったと考えられています。そして、必ずしも理由は明らかではありませんが、この大爆発直後には、原初的な物質(電子・陽子・光子のスープ)が、かなりの広範囲──もしかしたら宇宙全体──にわたって、ほぼ一様に分布していました。こうした状態から始まった後、わずかに密度の高い所に物質が重力で引き寄せられ、しだいに天体や銀河系が形成されていったので、宇宙に存在する物質は、どこか一箇所に集まっておらず、広大な空間内部に広くばらまかれたようになっているのです。
ただし、こうした「宇宙空間に物質が散らばった状態」は、長期間にわたって持続するものではありません。天体同士、銀河同士の重力作用によって、お互いが引き合って、次第に凝集していくからです。例えば、われわれの住む天の川銀河は、数百億年のうちに、アンドロメダ銀河を含む周辺の銀河群と合体すると予想されています。
銀河系の中心には巨大なブラックホールが存在していますが、星々がすぐにそこに落ち込んでしまうことはありません。中心のブラックホールなど銀河の内側からの重力と、外側にある物質からの重力、それに、銀河系が回転することによる遠心力がうまくつりあって、銀河系全体は、今のところ、ほぼ安定した状態を保っています。ただし、きわめて長い時間が経過すると、中心のブラックホールが、周囲の天体を全て飲み込んでしまうはずです。銀河同士の合体が、その動きに拍車を掛けることになるかもしれません。こうして、最終的には、いくつもの銀河が飲み込まれた超巨大ブラックホールが、宇宙の所々にポツンポツンと存在する状態へと変化していくはずです。
この宇宙がビッグバンで始まって以来、わずか100億年しか経過していません。宇宙は、まだ誕生して間もない“若々しい”状態にあるので、たくさんの星が宇宙空間に浮いているように見えますが、宇宙の長い長い歴史から見ると、それは、ほんの一瞬の出来事にすぎないのです。
【Q&A目次に戻る】

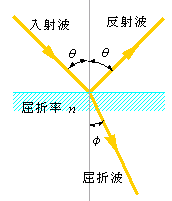
光は電磁波の一種なので、その反射・屈折に関する法則は、電磁気に関するマクスウェル方程式から導くことができます。単色平面波が平らの境界面に入射したときの反射波と屈折波の公式は、フレネルの公式として知られており、たいがいの電磁気学の教科書に書かれています。ただし、フレネルの公式は、電場・磁場の強さを複素誘電率を使って表したもので、少し専門的すぎるでしょう。ここでは、屈折率1・吸収率0の空気から屈折率n・吸収率0(誘電率ε=n
2)の水に向かって光が入射する場合についてだけ考えることにします。
入射波におけるエネルギー流の時間平均と、反射波におけるエネルギー流の時間平均の比は、反射率と呼ばれます。反射率R の値は、電場の向きによって異なっており、電場が入射面に垂直な成分に関しては、
R = sin
2(θ-φ)/sin
2(θ+φ)
平行な成分に関しては、
R = tan
2(θ-φ)/tan
2(θ+φ)
となります。ただし、入射角θと屈折角φの間には、
sinφ/sinθ = 1/n
という(よく知られた)関係があります。垂直入射(θ,φ→0)の場合には、2つの反射率はともに等しく、
R = (n-1)
2/(n+1)
2
です。2つの媒質に吸収がないと仮定しているので、エネルギー流の収支は一致することになり、屈折波のエネルギー流は、入射波に対して 1-R になります。
【Q&A目次に戻る】

電子レンジの扉に付けられている金属製のメッシュは、電磁波に対するシールドになっていると言われていますが、内部の料理が見える程度に可視光線は通しているのですから、本当に電磁波を遮蔽しているのか、不安に感じられるかもしれません。しかし、ことマイクロ波に関しては、ほとんど心配する必要がないと考えられます。
大ざっぱに言って、電磁波は、波長よりも充分に小さい穴は通り抜けられません。電子レンジで加熱用に用いられているのは、マグネトロンが作り出す2.45×10
9Hzのマイクロ波ですが、その波長は約12cmとなり、ミリメートルのオーダーの網目を通過することは、ほとんど不可能です(ただし、網目と同程度の距離までは飛び出してきます)。これに対して、可視光線の波長は1000分の1ミリ以下(400〜800nm程度)なので、扉の穴を楽々と通り抜けてきます。
電磁波が波長より充分に小さい穴を通れないことは、19世紀の終わり頃に、電磁波の方程式を使って証明されました。ただし、実際の計算は、フレネル回折の応用問題としてかなり高度なものです。ここでは、平らな金属に開いた直径a[m]の穴に対して波長λ[m]の電磁波が垂直に入射したとき、穴に入射した電磁波のエネルギーに対する回折波の全エネルギーの比r の公式を書いておきます:
r 〜 23×(a/λ)
4
(この式は、a<<λ という条件の下で導かれています)。a=λ/4 のときには、r は0.1以下になり、エネルギーの90%以上は穴を通過できずに反射されてしまいます。穴の径がさらに小さくなると、4乗の項が効いて、通り抜けられる電磁波は急激に減っていきます。電子レンジの場合は、マグネトロンから発射されるマイクロ波のエネルギーはかなり強大ですが、網目の大きさが波長の数十分の1なので、金属製のメッシュでほぼ完全に反射されると考えてかまいません。
電気用品安全法によると、電子レンジの安全基準は、扉を閉めて作動中の場合、器体の表面から5cm離れた地点での電力密度が1mW/cm
2以下となっています。国内で生産される電子レンジは、全てこの基準に適合しているはずなので、扉などが壊れていなければ、電子レンジの数cm以内に近づかない限り、漏洩マイクロ波の熱作用による障害のリスクは充分に小さいと見なせるでしょう。もっとも、低周波の影響に関しては、まだ未解明の部分があるため、完全に安心して良いとも言えませんが…
【Q&A目次に戻る】

一般的な見解によれば、物理学の理論は「物自体」を解明するものではなく、現象に適合するようなモデルでしかありません。例えば、固体の変形と応力を扱う弾性体理論では、現実の結晶構造を無視して固体を連続媒質と見なしていますが、それでも、原子間隔に比べて充分に大きなスケールで考える限りは、近似的な理論として充分に「役に立つ」ものです。同じように、現在、物質の本質に最も深く迫っているとされる素粒子論も、あくまで「役に立つ」ように構築された近似的な理論と考えるべきでしょう。実際、そこで使用される粒子場や確率振幅といった理論的な概念は、理論的な計算を進める上で便利な道具ではあっても、この世界の究極の姿を開示していると見なすには、あまりに数学的にすぎます。
ただし、だからと言って、物理学が「物自体」についての情報を何も与えないという訳ではありません。科学によって「物自体」に接近することは、かなりの程度まで可能なのです。
人間の素朴な認識が、世界の“似姿”ではないことは、近代以前から知られていました。色彩について言えば、これは、物そのものに備わった1次性質ではなく、知覚の様式に依存する2次的なものでしかありません。対象が示す「赤」という色は、反射光のスペクトルがある範囲にピークを持つような表面構造を持っていることの現れです。このように、人間の認識作用は対象に由来する情報にある種の変形を加えていますが、客観的な科学は、それがどのようなものかについての知見を与えてくれます。
カントは、『純粋理性批判』において、認識作用による情報の変形を解明することには、原理的な限界があるという見方を提出しました。彼によれば、理性的な推論は常に先験的な形式に則って行われるため、この形式の非現実性が露呈するような分野においては、必然的に誤った推論に導かれることになります(先験的誤謬推理)。例えば、空間について思索するとき、人間は「局所ユークリッド性を持つ空間」という限定的な直観形式を採用せざるを得ないため、空間が有限だと考えても無限だと考えても矛盾に陥るという訳です。人間の認識能力は、「物自体」に到達する遥か手前で限界に突き当たってしまう──これが、カントの基本的な世界観でした。
ところが、カントが提出した限界は、先験的な形式によらない理性的推論によって、いとも簡単に打破できることが、現代科学によって明らかにされました。空間に関しては、ユークリッド空間に基づいて思索しようとすると誤った結論にしか到達できませんが、テンソル解析のような数学的手法と、空間をゴム膜としてイメージする非先験的な直観によって、「果てはないが有限である」という相対論的宇宙モデルを構築することが可能になります。「現象は法則に完全に規定されているか否か」という別の誤謬推理に関しても、確率論的な量子過程を想定すれば、矛盾に陥ることはありません。数学的なモデルを用いた科学的推論に原理的な限界があるかどうかは、科学哲学が解明すべき重大なテーマですが、超準解析や非可換数論など新しい数学を次々と開発する科学者たちの旺盛な想像力を見る限り、限界は(あるとしても)素朴な世界認識の枠から遥か遠くに離れているようです。
もちろん、物理学で用いられるモデルは、「物自体」を直接的に開示するものではありません。しかし、人間の認識作用が行った情報の変形を補正するための手がかりは、確実に与えてくれるはずです。この手がかりを元に「物自体」にどこまで接近できるのか、はっきりしたことは言えませんが、宇宙の片隅に生まれたちっぽけな生命にしては、かなり良いところまで行くのではないでしょうか。
【Q&A目次に戻る】

まず、ブラックホールから説明しましょう。
太陽などの恒星が球形で安定しているのは、星を押しつぶそうとする重力と、内部から反発する圧力が釣り合っているからです。ちょうど、ゴムが縮む力と内部の空気圧が釣り合っている風船が、一定の形を保っているのと同じです。しかし、恒星も長い時間が経つと、燃料となる水素やヘリウムなどを使い尽くしてしまい、核融合のエネルギーで重力を押し返すことができなくなって、空気が抜けてきた風船のように、自分の重力でつぶれていきます(細かなことを言うと、超巨星過程や超新星爆発などの段階を経るのですが、ここでは省略します)。最終的に凝縮する質量が太陽の2倍程度までなら、星の残骸は中性子と呼ばれる粒子の塊(=中性子星)となって、それ以上はつぶれないのですが、もっと多量の物質が集まってくると、巨大な重力を押し返せる力は自然界には存在しないため、どこまでもつぶれていきます。この現象を「重力崩壊」と言います。重力崩壊が起きると、有限の質量が1点に集中し、密度が無限大の「特異点」が形成されます。「特異点」とは、既知の物理法則が成立しなくなる異常な点で、「空間に穴が開いた状態」とイメージする学者もいます。
ブラックホールには、巨大な質量を持つ1つの天体が自分の重力でつぶれてできたものと、星団の内部でいくつもの巨大天体が合体して形成されたものがあると考えられています。太陽の数倍から数十倍の質量を持つ前者のタイプは、われわれの住む天の川銀河の内部だけでも1000万〜10億個ほど存在すると言われており、現在までに、数十個の“ブラックホール候補”となる天体が発見されています。一方、後者の大質量ブラックホールは、大半の銀河の中心部に存在していると考えられます。天の川銀河の中心部でも、狭い範囲に太陽の数百万倍の質量が集中していることが判明しており、確証はないものの、まず間違いなくブラックホールでしょう。
ブラックホールの著しい特徴は、重力があまりに強大であるため、周辺にある物質だけでなく、近くの光源から発した光すら全て飲み込んでしまうことです。これが「ブラックホール」という名前の由来です。
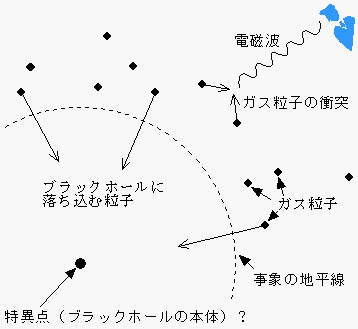
ブラックホールでは、中心にある特異点を取り囲むように「事象の地平線(event horizon)」と呼ばれる面が形成されています。太陽と同じ質量のブラックホールの場合、地平線の半径は約3kmになります。宇宙船でブラックホールに近づいていった場合、地平線を通過する瞬間には何事も起きないのですが、その内側に入ってしまうと、宇宙船はもちろんのこと、光であろうと何であろうと、もはや地平線の外に出ることはできません。あっという間に中心に引き寄せられ、その強大な重力の作用でバラバラに裂かれながら、“空間の穴”とでも言うべき特異点に吸い込まれてしまいます。なお、ブラックホール本体は光を発しませんが、周囲の物質が飲み込まれる過程で、粒子同士の衝突によって電磁波を放出するため、間接的にブラックホールを観測することが可能になっています。
ただし、上のようなブラックホールの説明に対して、異を唱える学者も少なくありません。中でも、物理法則が破綻する「特異点」の存在をうさん臭く感じる人が多いようです。ある学者は、特異点は現実には存在せず、重力崩壊を起こした天体がある大きさまで収縮すると、急速に冷やした水が瞬間的に氷になるように、通常の物質とは別の状態に突如として変化すると考えています。また、「超ひも理論」と呼ばれる極微の世界を扱う理論が、ブラックホールの謎を解明する鍵になると考える学者も少なくありません。いずれにせよ、特異点のようなブラックホールの本体に関しては、人類にとってまだ未知の領域と言って良いでしょう。
ダークマター(暗黒物質)に関しては、ブラックホール以上にわからないことだらけです。
ダークマターとは、恒星・惑星やガス雲などとは異なって、通常の方法では観測できない物質の総称です。ダークマターとしか呼びようのない物質が存在することは、すでに1930年代から銀河団の運動を元に推測されていましたが、1980年代における宇宙論(=宇宙全体の変化を扱う理論)の進展により、通常の物質よりもダークマターの方が大量にあるという見方が支配的になってきました。しかし、その正体は、今なおほとんどわかっていません。

銀河系内部に大量のダークマターが存在することは、その周囲を回る天体の速度v を調べることによって確証されました。銀河系の質量が、観測可能な円盤状の物質だけに担われているとすると、v は銀河中心からの距離r とともに小さくなるはずです(証明は省略します)。しかし、観測データは、v がr によらずにほぼ一定であることを示しました。これは、円板半径の2倍以上に拡がるハローの領域に大量のダークマターが存在することを意味します。銀河系に付随するダークマターは、ダークハローと呼ばれており、その一部は観測の難しい小質量の天体であると考えられていますが、それだけでは説明が付かないこともはっきりしています。
このほかにも、銀河形成のコンピュータ・シミュレーションにより、通常の物質とは異なるダークマターがなければ渦巻き銀河や銀河団の階層構造が形成されないことも、わかってきました。
宇宙全体に満ちているダークマターに関しては、理論も観測も未熟な状態です。最近、数十億光年彼方の銀河団の見かけの分布が予想値から少しずれているのは、ダークマターが重力の作用で光を曲げているからだという説が提出されましたが、研究はまだ緒についたばかりです。理論的な観点から、通常物質とダークマター、さらに(ダークマター以上に訳の分からない)ダークエネルギーを併せた宇宙のエネルギー密度は、臨界密度
ρ
c〜10
-29[g/cm
3]
に等しいと考えられています。最新のデータでは、このうち、通常物質の寄与は4%程度(恒星や光を放つガス雲は0.4%、光を発しない銀河間ガスが3.6%)で、23%がダークマター、73%がダークエネルギーだとされています。ただし、この数値は、将来の観測によって大幅に修正される可能性があります。
ダークマターの正体については、いくつかの説があり、基本的には、通常物質とほとんど相互作用しない素粒子だとの見方が一般的ですが、具体的なことは、ほとんどわかっていません。かつてダークマターの有力候補であったニュートリノという素粒子は、質量が小さすぎるなどの理由で、現在では候補からはずされています(エネルギー密度への寄与は0.1%程度だと推測されています)。ニュートラリーノやアクシオンといった未発見の素粒子ではないかという説もありますが、こうした素粒子自身の存在を疑う声も少なくありません。
【Q&A目次に戻る】

割り箸の中には、他には役に立たない廃材や間伐材などから作られているものもあります。例えば、高価な吉野スギは、家具材などに利用する角材を切り出した丸太の残りの部分といえども、捨ててしまうのはもったいないので、職人が端材ごとに加工して箸を作っています。しかし、こうしたものはごく一部であり、外食産業を中心に年間100億膳以上も利用される割り箸の大半は、原木の丸太か、大きめの木材から製造されています。これは、割り箸を工場で大量生産するに当たって、形の揃わない端材や細い間伐材を材料にしていたのでは、どうしても効率が悪くなるからです。
ただし、丸太を利用していると言っても、割り箸のためだけに伐採が行われるとは考えられません。実際、伐採や運搬のための費用を考えれば、1膳数円の割り箸に加工するのは経済行為として無意味です。主な用途が別にあって伐採した木材のうち、利用価値の低い部分から割り箸を作るのが一般的です。国産材の中では、シナ・カバ・ハンノキなどが割り箸の原材料となりますが、これらは、丸太の太い部分(直径28cm以上)を家具材や合板として利用し、14〜28cmの部分を割り箸に加工しているそうです。また、割り箸の過半は中国やインドネシアなどからの輸入材で作られていますが、割り箸のために木が伐採されているわけではありません。例えば、インドネシアのメルクシマツは、主に松ヤニを取る目的で伐採され、松ヤニ採取後のあまり使い道のない材木が割り箸用に回されているのです。
日本が東南アジアの木材を大量に輸入して森林破壊を押し進めたのは事実ですが、ここで問題にすべきは、建材や家具材として大量に利用される木材でしょう。割り箸の生産は、あくまで“隙き間産業”として行われているにすぎません。また、割り箸に加工されなかったとしても、せいぜいパルプ用のチップになる程度のものしか使っていないので、木材の利用法として、決して無駄の多いやり方とは言えません。バブル期に「使い捨て経済」の象徴的存在として批判されたこともある割り箸ですが、実際には、批判の大半は濡れ衣だったと考えて良いでしょう。
【参考文献】銀河書房編『割り箸で森が救えるか?』
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
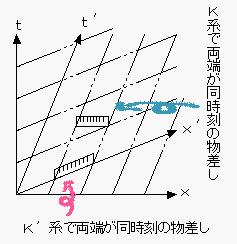 この議論がなぜおかしいかというと、「ある座標系で物差しの長さを計るときには、両端が同じ時刻のはずだ」という暗黙の前提が成り立っていないからです。運動している座標系で両端が同時刻になるように長さを計ったとしても、静止系から見ると、先端の位置を後端の位置よりも少し遅れて計っていることになります。従って、運動系の観測者が「物差しは1mだ」と言っても、静止系の観測者は、先端が少し遠くへ動いてから計ったので、「その値は過大評価で実際にはもっと短い」と考えることになります。これが、いわゆる“ローレンツ短縮”の起源であり、短いとされる割合は1/β2になります。この部分を補正すると、運動座標系では静止座標系から見て時間と空間が同じβ倍だけ伸張していることが示されます。時間と空間の変化が同じ割合で起こるのですから、光の進行速度は、静止座標系から見ても運動座標系から見ても、同じ秒速30万kmになります。これは、座標系の速度vをcに近づける極限まで成立します。
この議論がなぜおかしいかというと、「ある座標系で物差しの長さを計るときには、両端が同じ時刻のはずだ」という暗黙の前提が成り立っていないからです。運動している座標系で両端が同時刻になるように長さを計ったとしても、静止系から見ると、先端の位置を後端の位置よりも少し遅れて計っていることになります。従って、運動系の観測者が「物差しは1mだ」と言っても、静止系の観測者は、先端が少し遠くへ動いてから計ったので、「その値は過大評価で実際にはもっと短い」と考えることになります。これが、いわゆる“ローレンツ短縮”の起源であり、短いとされる割合は1/β2になります。この部分を補正すると、運動座標系では静止座標系から見て時間と空間が同じβ倍だけ伸張していることが示されます。時間と空間の変化が同じ割合で起こるのですから、光の進行速度は、静止座標系から見ても運動座標系から見ても、同じ秒速30万kmになります。これは、座標系の速度vをcに近づける極限まで成立します。
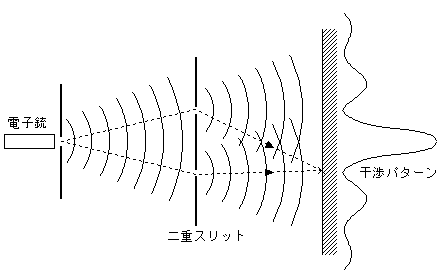
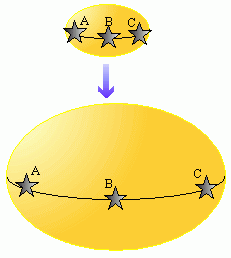 その後、宇宙初期に相転移が起きたという説が提出され、エネルギーの起源に1つの説明が与えられました。宇宙の始まりには、物質も何も存在しない状態にあったものの、途中で空間の状態が変化し、始まりの状態よりもエネルギーの低い真空と、空間からエネルギーを受け取って生まれた高エネルギー物質に分かれ、急激な膨張が生じたというものです。この説で、膨張宇宙の多くの謎が解決されたと考えられました。
その後、宇宙初期に相転移が起きたという説が提出され、エネルギーの起源に1つの説明が与えられました。宇宙の始まりには、物質も何も存在しない状態にあったものの、途中で空間の状態が変化し、始まりの状態よりもエネルギーの低い真空と、空間からエネルギーを受け取って生まれた高エネルギー物質に分かれ、急激な膨張が生じたというものです。この説で、膨張宇宙の多くの謎が解決されたと考えられました。
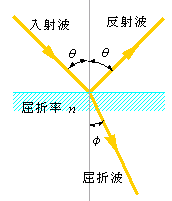 光は電磁波の一種なので、その反射・屈折に関する法則は、電磁気に関するマクスウェル方程式から導くことができます。単色平面波が平らの境界面に入射したときの反射波と屈折波の公式は、フレネルの公式として知られており、たいがいの電磁気学の教科書に書かれています。ただし、フレネルの公式は、電場・磁場の強さを複素誘電率を使って表したもので、少し専門的すぎるでしょう。ここでは、屈折率1・吸収率0の空気から屈折率n・吸収率0(誘電率ε=n2)の水に向かって光が入射する場合についてだけ考えることにします。
光は電磁波の一種なので、その反射・屈折に関する法則は、電磁気に関するマクスウェル方程式から導くことができます。単色平面波が平らの境界面に入射したときの反射波と屈折波の公式は、フレネルの公式として知られており、たいがいの電磁気学の教科書に書かれています。ただし、フレネルの公式は、電場・磁場の強さを複素誘電率を使って表したもので、少し専門的すぎるでしょう。ここでは、屈折率1・吸収率0の空気から屈折率n・吸収率0(誘電率ε=n2)の水に向かって光が入射する場合についてだけ考えることにします。
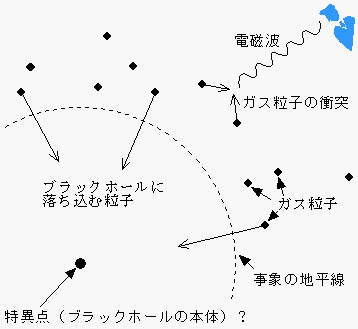 ブラックホールでは、中心にある特異点を取り囲むように「事象の地平線(event horizon)」と呼ばれる面が形成されています。太陽と同じ質量のブラックホールの場合、地平線の半径は約3kmになります。宇宙船でブラックホールに近づいていった場合、地平線を通過する瞬間には何事も起きないのですが、その内側に入ってしまうと、宇宙船はもちろんのこと、光であろうと何であろうと、もはや地平線の外に出ることはできません。あっという間に中心に引き寄せられ、その強大な重力の作用でバラバラに裂かれながら、“空間の穴”とでも言うべき特異点に吸い込まれてしまいます。なお、ブラックホール本体は光を発しませんが、周囲の物質が飲み込まれる過程で、粒子同士の衝突によって電磁波を放出するため、間接的にブラックホールを観測することが可能になっています。
ブラックホールでは、中心にある特異点を取り囲むように「事象の地平線(event horizon)」と呼ばれる面が形成されています。太陽と同じ質量のブラックホールの場合、地平線の半径は約3kmになります。宇宙船でブラックホールに近づいていった場合、地平線を通過する瞬間には何事も起きないのですが、その内側に入ってしまうと、宇宙船はもちろんのこと、光であろうと何であろうと、もはや地平線の外に出ることはできません。あっという間に中心に引き寄せられ、その強大な重力の作用でバラバラに裂かれながら、“空間の穴”とでも言うべき特異点に吸い込まれてしまいます。なお、ブラックホール本体は光を発しませんが、周囲の物質が飲み込まれる過程で、粒子同士の衝突によって電磁波を放出するため、間接的にブラックホールを観測することが可能になっています。
 銀河系内部に大量のダークマターが存在することは、その周囲を回る天体の速度v を調べることによって確証されました。銀河系の質量が、観測可能な円盤状の物質だけに担われているとすると、v は銀河中心からの距離r とともに小さくなるはずです(証明は省略します)。しかし、観測データは、v がr によらずにほぼ一定であることを示しました。これは、円板半径の2倍以上に拡がるハローの領域に大量のダークマターが存在することを意味します。銀河系に付随するダークマターは、ダークハローと呼ばれており、その一部は観測の難しい小質量の天体であると考えられていますが、それだけでは説明が付かないこともはっきりしています。
銀河系内部に大量のダークマターが存在することは、その周囲を回る天体の速度v を調べることによって確証されました。銀河系の質量が、観測可能な円盤状の物質だけに担われているとすると、v は銀河中心からの距離r とともに小さくなるはずです(証明は省略します)。しかし、観測データは、v がr によらずにほぼ一定であることを示しました。これは、円板半径の2倍以上に拡がるハローの領域に大量のダークマターが存在することを意味します。銀河系に付随するダークマターは、ダークハローと呼ばれており、その一部は観測の難しい小質量の天体であると考えられていますが、それだけでは説明が付かないこともはっきりしています。