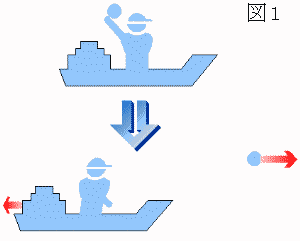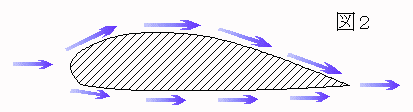原子力発電所は、きわめて多数の部分から構成されている巨大システムであり、各パーツごとに適材適所となるような材料が選ばれています。ここでは、強い放射能を帯びた核分裂生成物を伴う核燃料物質が、どのような素材で作られた防壁で取り囲まれているかを、最もポピュラーな原子炉である軽水炉(冷却材として水を使った原子炉)を例に説明しましょう。
酸化ウランの粉末である核燃料は、直径1cm程度の円柱形にし、高温でセラミック状に焼き固めます。これを燃料ペレットと呼びます。核分裂によって生じる放射性物質は、一部の気体を除いて、このペレット内部に閉じこめられることになります。
燃料ペレットは、多数まとめてジルカロイ(ジルコニウム合金)でできた被覆管の中に詰められます。燃料棒とは、被覆管にペレットを閉じこめた状態のものを指します。被覆管の素材としてジルカロイが使われるのは、ジルコニウムが、核分裂を引き起こす熱中性子(減速された中性子)をあまり吸収しないので、好都合だと考えられたからです。ただし、純粋なジルコニウムは、窒素と反応して腐食しやすくなるので、スズを混ぜて窒素の害を受けないようにしています。このほか、鉄やクロム、ニッケルなどが添加されており、組成によって、ジルカロイ−2とかジルカロイ−4などと呼ばれています。
燃料棒数百本を四角い束にして組み立てたものが、燃料集合体です。炉心部には、燃料集合体が100本以上もあり、核分裂の熱で溶融しないように冷却材である水に浸けられています。この炉心部全体を格納しているのが、高さが10m以上にもなる巨大な圧力容器(原子炉容器)です。加圧水型の原子炉では内部の圧力が150気圧以上になり、水の温度も300度を超えるという過酷な状況に耐えなければならないので、肉厚が20cm余りの鉄鋼(鉄−炭素系合金)できわめて頑丈に作られています。1979年に起きたスリーマイル島原発事故では、炉心溶融が起きて20トンもの部材が圧力容器の底に崩れ落ちていますが、ステンレス内張り炭素鋼製の容器がこの衝撃に耐えられたため、チェルノブイリ原発のような大惨事に至らずに済んでいます。
圧力容器や蒸気発生器を含む装置群を取り囲むのが、格納容器です。これは、鋼鉄製か、内側に鋼板を張ったコンクリート製です。
このように、原子力発電所の各パーツには、強度を十分に考慮した素材が用いられていますが、それでも、きわめて過酷な環境下で使用されるため、部分的に腐食したり脆くなったりすることがあります。
最近心配されているのが、圧力容器が、炉心部から飛び出してくる中性子を長期にわたって浴び続けた結果、しだいに脆くなるという現象(中性子脆化)です。運転中の原子炉では、核分裂の際に中性子が発生していますが、その中には、冷却水を通り抜けて圧力容器の壁に衝突するものもあります。このとき、中性子に衝突された鉄の原子が、規則正しく並んだ結晶配列の中からはじき飛ばされると、その部分に格子欠陥とよばれる配列の乱れが生じます。格子欠陥を多く含む金属は、粘り強さを失って脆くなります。これが、中性子脆化です。
中性子脆化が進むと、原子炉の圧力が高い状態で急激に温度が下がったとき−−例えば、ECCS(緊急炉心冷却装置)が作動して冷たい水が炉心部に高圧で注入されたとき−−に、圧力容器が破壊されやすくなります。材料試験の結果に基づく以前の計算では、中性子脆化は圧力容器の破壊事故につながるほど進行はしないとされていましたが、鋼材の中に銅などの不純物が含まれると脆化が促進されることが判明し、危険性を指摘する声が高まってきました。特に、旧ソ連製の原発では、アメリカの代表的な原子炉メーカーであるウェスティングハウス製のものに比べて、圧力容器壁が炉心部に近くて中性子を浴びやすい上に、材料の品質や溶接技術が悪く不純物の含有量が高くなっています。このため、圧力容器の強度がかなり低下しているという懸念があり、早急に手を打たなければならないと言われていますが、経済状態が悪化している中で、なかなか対策が進んでいないというのが現状です。
(中性子脆化に関しては、桜井淳著『原発のどこが危険か』(朝日選書)を参考にしました)
【Q&A目次に戻る】

非常に大きな問題ですので、ごく概略的にお答えいたします。
社会学的な議論で謂うところの「技術」とは、生産・流通・サービスなどの分野で見られる工学的応用の総称です。したがって、(「スポーツ選手が技術を磨く」というような場合とは異なって)「技術」の発達には、経済活動の中に技術が組み込まれるという社会的なプロセスが必要になります。このプロセスは、シーズ(seeds;種)とニーズ(needs;要求)なる概念を元に考えると、わかりやすいでしょう。大学や基礎研究所で行われる工学的研究の成果としてのシーズと、経済発展ないし願望充足のための社会的なニーズが結びついて、はじめて、新しい技術が経済活動に組み込まれ、生産性や利便性の向上が実現されることになるのです。
-
(技術革新のシーズとニーズについては、講義ノート「研究室からの技術革新」および「技術革新と市場戦略」参照)
具体的な技術発達の局面で、工学的なシーズと社会的なニーズのどちらが大きな役割を果たすかはケース・バイ・ケースです。一般に、産業構造を転換させるような「ジェネリック・テクノロジー」をもたらすブレイク・スルーは、地道な研究活動を通じて蒔かれた工学的シーズが、芽吹き花開いたものであることが多いようです。
-
(ジェネリック・テクノロジーについては、講義ノート「知的財産を守る」参照)
例えば、エレクトロニクス産業の隆盛をもたらす基礎技術となったトランジスタの発明は、ベル研究所で半導体の整流層の性質を調べていたバーディンとブラッテンによる理論的な研究の成果と言えるものです。当初は、信頼性と耐久性に欠けていたため、直ちに産業で利用されるには至らなかったのですが、ベル研で半導体の研究主任だったショックレーらがベンチャー企業を起こしてトランジスタの性能向上に尽力した結果、高価で大型の真空管に代わる整流装置を必要としていた電機産業のニーズに合致する品質に達しました。これが、エレクトロニクスが一大産業として発展していく契機となった訳です。
また、遺伝子組換作物の実用化やクローン動物の誕生などで注目を浴びているバイオテクノロジーも、基礎的な研究成果としてのシーズが先行する形で発展してきたものです。初期の段階では、大学を中心とする地道な研究を通じて、遺伝子を切断する制限酵素の発見や、切り出された遺伝子を標的細胞に導入するプラスミド法の開発がなされました。特に、プラスミド法を開発したスタンフォード大学のコーエンとボイヤーが、特許権を大学に委譲し、他の研究者がこの技法を安価に利用できるようにしたことが、バイオテクノロジーが発展する一つのきっかけになっています。その後、この技術が、医薬品の大量生産や農作物・家畜の改良に応用できるようになり、80年代後半から積極的に産業活動に組み込まれていきます。
一方、産業構造を転換するとまではいかないものの、社会に大きな影響を与える技術の発達もあります。こうした変化は、しばしば、社会的ニーズに応えるべく始められた製品開発において、既存技術の組み合わせや漸進的改良を行うことによって実現されています。例えば、携帯電話の普及は多くの人々のライフスタイルを一変させましたが、そこに使われている技術の大半は、実は、既に開発されていたものを使い回ししたに過ぎません(強力な小型電池は、新しい発明と言えなくもないのですが…)。多くの人が驚いた携帯電話の小型化(初期のものが肩に担ぐショルダー・フォンだったことを覚えていますか?)は、ポータビリティを求める社会のニーズに応えるために、回路をLSI化したり本体を折り畳み可能にしたりするなどの漸進的改良を加えていった結果なのです。
-
(携帯電話については、講義ノート「21世紀へ向けて」参照)
もっとも、現在のように技術が高度化・複雑化した状況の下では、シーズとニーズの関係は、必ずしも上の例のように単線的ではありません。現在では、直ちに製品化に結びつかない膨大な新技術が日々開発されており、その多くが学術論文や特許情報などの形で公開されています。各企業は、これらを巧みに組み合わせながら、特定階層の個別的なニーズに応える製品を生み出す努力を重ねています。カセットテープに代わって音楽録音のメディアとして普及してきたMDも、高音質と携帯性を求める音楽ファンの求めに応じて、さまざまな技術(レーザー制御、符号化、相変化などに関する諸技術)を組み合わせることによって作り上げられています。このほか、ハンディサイズのビデオカメラやGUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェイス)を持つパソコンなどにおいても、各界に分散して存在していた細かな新技術が結集されています。ジェネリック・テクノロジーの開発もさることながら、こんにちの企業に求められているのは、将来性を秘めたシーズを掻き集め、これらを適切に組み合わせてニーズと結びつけていく才覚でしょう。
ところで、シーズとニーズの相互作用を通じて発展する通常の産業技術と対照的なのが、国家主導の巨大技術です。これらには、特定の目的を実現するために莫大な資金が投入されていますが、製品化を指向しない地道な基礎研究によって生み出される工学的なシーズも、技術改良の方向性を定める社会のニーズもないため、技術開発のコスト・パーフォーマンスは著しく低くなっています。核融合炉、高速増殖炉、リニアモーターカーなど、現代技術の動向と乖離する分野に多くの税金が費やされていることは、憤るべき現実だと言わなければなりません。
【Q&A目次に戻る】

一口に空を飛ぶと言っても、飛行機とロケットでは、その飛行原理が全く異なります。ロケット(およびヘリコプター)が上向きの推進力によって上昇するのに対して、飛行機(プロペラ機・ジェット機とも)は、推進力を使って前進することによって浮き上がる力(揚力)を得るのです。
はじめに、比較的簡単なロケットの原理から説明しましょう。ロケットの推進力は、古典力学でお馴染みの「作用・反作用の原理」によって説明できます。
ボートに乗っている人間が、右向きのボールを投げる場合を考えましょう。このとき、ボールに加えた右向きの「作用」に対する「反作用」(反動)として、人間は左向きの力を受け、ボートは左側に進みます(図1参照)。
ロケットの場合は、ボールの代わりに燃焼ガスを噴射しています。ガスといえども質量を持っているので、勢いよく噴射すれば、投げられたボールと同じように、反作用でロケット本体に推進力を与えることができるのです。スペースシャトルをはじめとする通常のロケットでは、巨大なタンクの中に液体水素と液体酸素が詰められており、この二つを化学反応させてできる高温・高圧の水蒸気を後方に噴き出すことによって上昇します。もっとも(燃料そのものを含む)大質量のロケットを持ち上げるためには、大量のガスを噴射しなければならないので、巨大なタンクもあっという間に空になってしまい、途中で本体から切り離されることになります。
ロケットは、噴射の「反作用」を利用しているので、空気の希薄な大気圏外でも飛行できます。これに対して、空気の力を使って空を飛ぶのがいわゆる「飛行機」です(当然、空気のない所では飛ぶことはできません)。プロペラ機は、プロペラの回転によって、ジェット機は、空気取り入れ口から取り込んだ空気に燃料を混ぜて燃焼させることによって、それぞれ後方への気流を作り、その反作用でもって前進しています。ただし、この力だけでは、空を飛ぶことはできません。飛行機を空に浮き上がらせているのは、主翼に働く「揚力」と呼ばれる力です。
主翼の断面は、図2のような形をしています。飛行機が空気中を前進すると、翼の周りに気流が生じますが、翼の上面が下面より大きく湾曲しているため、上を回る空気の方が流れが速くなります。すると、流れが速いほど圧力が低くなるという流体の法則(ベルヌイの法則)によって、翼の上方の圧力が下方より低くなり、翼全体に上向きの力(揚力)が加わります。この力が、飛行機を空中で支えているのです。
18世紀末に気球が発明された後、より軽やかに空中を飛び回る飛行機の開発を夢見る技術者が数多く現れましたが、機械的に上向きの力を作って上昇しようとする試みはことごとく失敗しました。ライト兄弟の成功の秘訣は、実用化されたばかりのガソリン機関を前進のためだけに使い、あとは、揚力を作り出す翼の形状を工夫することに技術を傾注した点にあったと言えるでしょう。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA