
「アポロによる月着陸はNASAのでっち上げだ」という珍説は、これまで何度となく現れ、そのたびに科学者によって反駁されてきたものです。最近また、その内容を紹介するテレビ番組がゴールデンタイムに放送され、真に受けた視聴者もいたようですが、信憑性のある証拠は何ら提示されていません。
「旗がはためいている」現象は、確かに月面での作業を撮影した映像に映し出されています。しかし、別に不思議な出来事ではありません。この旗は、空気のない月面でだらりと垂れてしまわないように、ポールに対して直角に取り付けられた金属製の横棒から吊り下げられているものです(袋状になった旗の上端に横棒が通されています)。したがって、ポールを素早く動かせば、旗の端の部分は慣性のせいで少し遅れて動き始め、振り子のように平衡点を通り越してから元に戻るような運動をします。また、金属製の横棒がわずかに「しなる」こともあります。アームストロング船長の回想記には、月面は思ったより固くてポールが簡単に突き立てられず、ハンマーを使って打ち込んだと書かれていますから、かなり力を入れてポールを動かしていたはずであり、その途中で旗がヒラヒラするのは、自然な現象です。
クルーが離れた後も旗が波打っているように見える写真がありますが、これは、望遠鏡のように伸びるはずの横棒が完全に引き出せなかったため、旗に皺が寄ってしまったためです。NASAの説明(NASAホームページに掲載されたもの)によると、アポロ11号では偶然にそうなったのですが、12号以降は、視覚的な効果をねらって、横棒をわざと短くして旗がはためいて見えるようにしたとのことです。
質問にある太陽光の影響ですが、これは、ナイロン製の旗を翻らせるほど大きな圧力にはなりません。遠い未来には、差し渡し数kmの帆で太陽光を受けて宇宙空間を滑るように進む宇宙帆船が実用化されるかもしれませんが、今のところ、太陽光の圧力を実感させるような装置はないようです。
余談ですが、アメリカの国威発揚のためにアポロ11号のミッションの1つとして月面に据え付けた星条旗は、月着陸船に近すぎたため、発射の際にロケット噴射で吹き飛ばされてしまったそうです。
【Q&A目次に戻る】

熱を伝達する仕方に熱伝導・対流・放射の3種類があることはご存じだと思いますが、3番目の放射とは、電磁波による熱エネルギーの移動を意味します。一般に、有限温度の物体は必ず電磁波との間でエネルギーのやり取りをしており、高温の物体が周囲に熱放射を行う一方で、低温の物体は電磁波を吸収してエネルギーをもらっています。こうした過程を熱力学の枠内で定式化するためには、「電磁波の温度」を定義しておくのが好都合です。「熱力学の第0法則」によると、「熱は高温の物体から低温の物体に流れ、温度が等しくなると熱は流れない」ことになっているので、温度がTの物体と熱平衡にある電磁波の温度もTになるはずです。
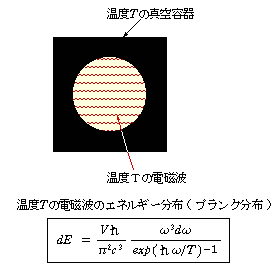
例えば、真空容器の温度を長時間Tに保っていると、その内側には、電磁波が温度Tの定常状態になると考えられます(右図)。19世紀後半から20世紀初頭に掛けての物理学者たちは、統計力学の法則をベースに、周波数に対するエネルギーの分布を使って熱平衡状態の電磁波の温度を定義しました。具体的な式は省略しますが、宇宙空間の温度は、背景放射(恒星が放射したものを除いたバックグラウンドの電磁波)のエネルギー分布にこの定義式を当てはめて求めています。
現在の宇宙は、約3Kというきわめて低温の状態になっていますが、これは、言ってしまえば、ビッグバンの余熱のようなものです。ビッグバンの瞬間には、宇宙はきわめて高温の状態にあり、高いエネルギーを持った電磁波に満ちあふれていましたが、こうした電磁波は、宇宙が膨張するにつれて拡がった空間に拡散し、急速に冷却されていったわけです。
【Q&A目次に戻る】
 別の回答
別の回答にも書いておきましたが、ホーンは音の大きさを表す古い単位で、現在では、デシベル(dB)を用いるのが一般的です。
物理学的には、音の大きさは音圧で定義し、デシベル単位で表します。具体的には、音圧が1[kHz]で0.00002[Pa]の音を基準の0[dB]とし、それ以外の領域では、音圧が10倍になると20[dB]だけ増加するように、音圧の常用対数を取っています。これが厳密な定義なのですが、人間の耳には同じ音圧でも周波数に応じて大きさが異なって聞こえるので、この分を聴感補正回路によって補正して、耳で聞いたときの実感に近いように音の大きさを定義し直すことがあります。この補正後の音の大きさを以前はホーン単位で表していたのですが、最近では、ややこしいことに、音圧による定義と同じデシベル単位で表します。補正の仕方によって、デシベルは、dB(A),dB(B),dB(C)に分類され、dB(A) が耳で聞いたときの実感に、dB(C) が音圧による定義に、最も近くなります。何も断りのない場合は、「デシベル」はdB(A) を意味する場合が多いようです。したがって、ホーンとデシベルの関係は、次のようになります:
ホーン = (聴感補正したときの)デシベル ≒ (音圧で定義した)デシベル
なお、ピンクノイズは、「1オクターブの範囲に含まれる音の強さが中心周波数に無関係なノイズ」のことで、オーディオ機器のテストによく用いられます。ですから、この質問に関しては、科学者よりもオーディオの専門家の方が詳しいことを教えてくれると思います。
【Q&A目次に戻る】

地球上に生息する動物の基本的なボディプラン(形態の設計)は、今から5〜6億年前のカンブリア紀にほぼ完成され、それ以来、大きな変化を受けずに現在に至っています。この点は、脊椎動物も節足動物(昆虫やクモの仲間)も変わりありません。
約35億年前に誕生して以来、生命は、真核生物から多細胞生物へと30億年近くかけてゆっくりと形態を複雑化してきましたが、6億年前、突然、きわめて多彩な動物種へと分化します。この「カンブリア爆発」がなぜ起きたかは進化論の謎の一つです(酸素濃度が高まって動物の運動量が増したという見方もあります)が、ともあれ、多くの動物がそれまでと異なる過酷な環境へと進出し、生物間の生存競争も熾烈なものになっていったことは確かです。数年前にNHKスペシャル『生命』で取り上げられて有名になった巨大肉食動物アノマロカリスが登場したのも、この頃です。
カンブリア紀に登場したボディプランは、生存競争に勝ち残るための生物たちの戦略として編み出されたものと考えられます。例えば、ピカイアと名付けられた生物は、アノマロカリスのような捕食者から素早く逃げるために、指令を体の各所に伝達する太い神経管と、全身を統括的に動かす際の支柱となる脊索を発達させました。現在のナメクジウオに似たこの生物が、魚類から爬虫類・哺乳類へと至る全ての脊椎動物の祖先となったわけです。
一方、別の生き残り戦略を採用したのが三葉虫などの仲間で、体を固い組織で覆って外敵に備えていました(もっとも、アノマロカリスは、強力な顎で三葉虫をバリバリと食っていたようですが)。その一部が陸に上がって、陸生の多足類(ムカデの仲間)になったと考えられています。こうした多足類の中で、体節が融合して頭部・胸部・腹部の3つの部分となり、さらに腹部の付属肢が退化して6本足になった生き物がいわゆる昆虫で、4〜3億年前に登場し、その後、爆発的に適応放散を行いました。恐竜たちが栄えた中生代には、すでに、ハエ・チョウ・ハチなどお馴染みの昆虫が現れています。
カンブリア紀には、この他にも、5つの眼で捕食者の襲来を見張っていたオパビニアや、体を縦にくねらせて素早く逃げ回ったオドントグリフスなど、奇妙きてれつなボディプランを持つ動物がたくさん現れました。しかし、その大半は、1億年以上にわたる生存競争に敗れ去り、現在に子孫を残すには至っていません。
【Q&A目次に戻る】

磁気レイノルズ数Rは、磁場が加わっている領域での導電性流体の運動を記述する際に使われる無次元の物理量で、特性長をL、代表的な流速をvとすると、
R = vL/ν = σμvL
で定義されます。ただし、νは流体の磁気粘性率で、ν=1/σμ(σ:電気伝導度、μ:透磁率)です。
σ=∞となる完全導体の場合、磁力線は流体に“くっついて”(frozen in)動いていくことが知られています(証明は、磁気流体力学の教科書を参照してください)。しかし、σが有限の場合、磁力線はある程度は引きずられるものの、流体に対して相対速度を持ち、束縛を逃れて拡散していくような振舞いを示します。磁気レイノルズ数Rは、こうした磁力線の拡散の程度を表すもので、Rが充分に大きければ、完全導体と同じように磁力線はあまり拡散せずに流体に引きずられていきます。このとき、流体は(外力と力学的な圧力を別にすると)磁力線の張力(B
2/μ)と磁気圧(B
2/2μ)に駆動されるように運動します。ただし、Rが大きいという条件が満たされるのは、νがきわめて小さくなるプラズマや、vやLが非常に大きくなる天体現象に限られます。
一方、Rが小さくなると、
τ 〜 RL/v
程度の緩和時間で磁力線が拡散していきます。Rが充分に小さいときには、磁場と流体が互いに引きずりあうような効果は目立たなくなります。
【Q&A目次に戻る】

ホーキングが虚数時間の概念を導入したのは、1984年に発表した宇宙の量子状態に関する論文においてですが、そこでは、必要な計算(経路積分)を確実に実行するための一種の方便として虚数時間を使っているような書き方がされています。量子力学の計算を行うには、ある時空領域での重力場をg
μν としたときの作用をS[g] として、関数積分(経路積分):
∫[dg] exp(iS[g])
を遂行しなければなりません。しかし、exp(iS) が振動する上に、積分領域がコンパクトでない(数学的に有限な範囲として定義できない)ので、この計算を実際に行うのは困難です。そこで、ある実関数f(x) を複素平面に解析接続した複素関数f(z) を考えるのと同じ要領で、時間軸を複素平面に拡張して虚数軸上の重力場g に対する作用S
〜 を導入すると、必要な積分は、
∫[dg] exp(-S
〜[g])
という形になり、被積分関数が振動せず、コンパクトでない領域からの寄与も小さくなるので、具体的に計算を実行することができます。ホーキングは、ごく簡単なモデルを使って、この計算法により初期宇宙の振舞いを説明できることを示しました。このようなやり方で重力場の量子効果を扱うことは、必ずしも理論的に正当化できない点が多々ある──例えば、解析接続しているのに、複素関数ではなく実関数を使っている点など──のですが、ホーキングは、重力場の量子論がほとんど未開発だった状況下で、あくまで「1つの提案」として虚数時間によるフォーマリズムを提唱した訳です。一般向けの啓蒙書(『ホーキング、宇宙を語る』など)では、虚数時間を考えることに物理的な意味があるような口調になっていますが、必ずしも根拠のある主張ではありません。
なお、1983年に初期宇宙の量子状態について論文を発表したヴィレンキンは、数式の上ではホーキングのと似た結果を得ていますが、こちらは、(質問文で2番目に上げられた)虚数時間を使ってトンネル効果の計算を行うという方法を採用したもので、物理的な発想はかなり異なっています。
【Q&A目次に戻る】

SFの世界では、夢のような技術(ワープ航法・タイムマシン・物質転送など)が科学的な用語を使って描かれています。しかし、現実の世界では、それらの多くは実現不可能です。物理学者が物質波レーザーと呼ぶものはあるにはありますが、理論的に提案されたばかりで実験データもほとんど集まっておらず、何らかの形で実用化できるという目途は立っていません。
レーザーとは位相が揃うように増幅された電磁波を意味し、多くの場合、高いエネルギー準位にある原子から光を誘導放出させることによって作り出しています。量子力学が示すように、物質を構成している電子や陽子も、量子効果によって波動的な振舞いを示すことはありますが、光とは物理的な性質が異なっている──きちんと言うと、光子がボーズ統計に従うのに対して電子や陽子はフェルミ統計に従う──ために、位相の揃った増幅波を作り出すことは困難です。2000年にアメリカや日本の物理学者が提案した「物質波レーザー」は、電子や陽子そのもののを放射するのではなく、半導体にエネルギーを注入したときにできるホール(正孔)と電子のペアを利用してレーザーのような波を作り出す技術のことです。クーロン相互作用によって束縛状態を作っているホールと電子のペアは、エクシトン(exciton) と呼ばれる1個の(ボーズ統計に従う)粒子のように振舞うため、光と同様に位相の揃った波として半導体内部を伝播させることができます。この現象は、半導体ポリマーを用いた光デバイスの開発などに応用できるという見方もありますが、現時点では、海のものとも山のものともわかりません。これ以外にもレーザーのように位相の揃った物質波になり得るものはいくつかありますが、いずれにせよ、これらを使って“空中に物質を顕現させる”ことは、いまだ夢物語です。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
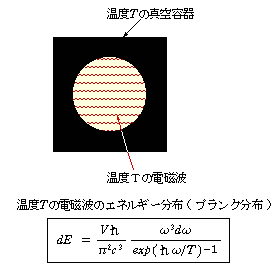 例えば、真空容器の温度を長時間Tに保っていると、その内側には、電磁波が温度Tの定常状態になると考えられます(右図)。19世紀後半から20世紀初頭に掛けての物理学者たちは、統計力学の法則をベースに、周波数に対するエネルギーの分布を使って熱平衡状態の電磁波の温度を定義しました。具体的な式は省略しますが、宇宙空間の温度は、背景放射(恒星が放射したものを除いたバックグラウンドの電磁波)のエネルギー分布にこの定義式を当てはめて求めています。
例えば、真空容器の温度を長時間Tに保っていると、その内側には、電磁波が温度Tの定常状態になると考えられます(右図)。19世紀後半から20世紀初頭に掛けての物理学者たちは、統計力学の法則をベースに、周波数に対するエネルギーの分布を使って熱平衡状態の電磁波の温度を定義しました。具体的な式は省略しますが、宇宙空間の温度は、背景放射(恒星が放射したものを除いたバックグラウンドの電磁波)のエネルギー分布にこの定義式を当てはめて求めています。