
古典論の範囲であらゆる電磁現象を記述するとされるマクスウェル方程式は、電磁場に関する1階の偏微分方程式群として表されているので、基本的には、電磁場(電界・磁界)は微分可能であることが理論的な要請となります。さらに、電磁場は電磁ポテンシャル(電位・磁気ポテンシャル)を微分したものとして表されるので、自然界がマクスウェル方程式に従っているならば、電磁ポテンシャルは2階微分が可能でなければならないはずです。
もっとも、こうした制限を厳密に課すと、実用的な計算にすら困難を来すので、通常は、超関数(distribution)と呼ばれる特殊な関数で表される程度の非解析性は、理論の中に取り込んでしまっています。
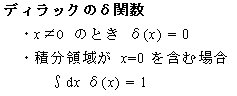
例えば、点電荷が作る電位は(電荷からの距離をrとすると) 1/r に、電界は 1/r
2 に比例し、電荷の置かれた点では発散して解析性が失われるはずですが、ディラックのδ関数という超関数の一種を使うことによって、実質的に解析的な扱いがなされています。また、質問にあった「微分係数が不連続になる」ケースは、面電荷が分布しているときに見られます。 x=0 となるyz面内に一様に面電荷が分布しているとき、電位は |x| に、電界のx成分は θ(x)-θ(-x) に線形に依存します(θ(x)は x>0のとき1、 x<0 のとき0 になる階段関数で、その微分はδ関数になります)。これも、本来なら x=0 で微分ができないはずですが、超関数を使って、あたかも解析的であるかのように計算を進めることが可能です。
ただし、超関数は、あくまで計算をスムーズに行うための便宜的な手段であって、現実に存在する物理量が超関数と同じ振舞いをしている訳ではありません。
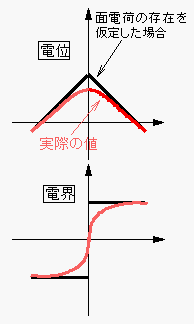
上の面電荷の例にしても、「(厚みのない)面上に電荷がなめらかに分布する」ことは現実にはあり得ず、電子のような点電荷が比較的狭い幅の中に分布していると考えられます。この場合、電位や電界は、(電子の存在する場所以外では)特異性のない“なまった”関数で表されるはずです(右図)。
多くの物理学者は、現実の自然界においてなめらかな関数で表せないのは、電荷を持つ素粒子の近傍の場だけだと考えています。電子やクォークなどでは、粒子に近づくにつれてさまざまな物理量が無限大に発散してしまい、自己エネルギーなどの物理量を計算することが不可能になります。こうした「発散の困難」を回避するために、くりこみ理論と呼ばれる計算法が開発されていますが、全ての問題が解消された訳ではなく、より完全な理論の登場が待たれています。
【Q&A目次に戻る】

磁気冷却法とは、磁気熱量効果を利用して冷却する方法で、通常は極低温を実現するのに利用されます。
磁性体に等温的に磁場を加えると、熱運動していた磁気モーメントを秩序配列に近づけようとして、熱を放出してエントロピーを下げるような変化が生じます。理想常磁性体の場合、磁場をB
1からB
2に増加させたときの放熱量ΔQは、次の公式で与えられます:
ΔQ = ΔS・T = nC(B
22−B
12)/2μ
0T
ただし、nは単位量中の磁性イオンの個数、Cはキュリー定数です。消磁過程では、同じ公式で吸熱量が計算されます。実際に用いられるのは、理想常磁性体ではないため、スピン間相互作用を考慮して、分母のTを
T−θ (θ:ワイス温度)
で置き換えなければなりません。
こうした性質を用いて実際に冷却を行うには、下のような「エリクソン・サイクル」(または、その改良型)を利用します。
磁性体が等温消磁過程で物体から熱を吸収、その熱を等温磁化を通じて熱浴に捨てるという過程を繰り返すことによって、物体を段階的に冷却することが可能になります。
磁気冷却を行う装置の性能は、使用される磁性体や装置の形状に大きく左右されるため、具体的にどの程度の強さの磁場を用いれば良いかは、一概には答えられません。極低温を実現するための実験装置では、6テスラ程度の汎用的な超伝導マグネットが使われることが多いようです。近年では、オゾン層破壊や地球温暖化をもたらすフロン/代替フロンなどの有害な冷媒を用いない「環境負荷の小さい」冷蔵庫として、常温付近で磁気冷却を利用する技術の開発が進められていると聞きます。例えば、2000年10月には、中部電力と東芝が磁性体としてガドリニウムを利用した大型冷蔵庫用冷却装置を試作しています。ただし、具体的に何テスラの磁場を加えたかは、プレス発表されていません。
磁気冷却の概略については、低温工学協会編『超伝導・低温工学ハンドブック』(オーム社)、川西・近角・櫻井著『磁気工学ハンドブック』(朝倉書店)などを参照してください。
【Q&A目次に戻る】

質問にあるアルミニウム化合物は、いずれも多様な結晶構造を持つことが知られています。
アルミナは酸化アルミニウム(Al
2O
3)の工業的な呼称で、α,γ,δ,η,χ,ρなどに分類されます。このうち最も安定した構造は六方晶系のα型で、コランダムあるいは鋼玉と呼ばれています。γ以下のものは格子欠陥のあるスピネル型で、結晶度の差などによって区別されます。
ムライトは、単鎖構造を持つアルミノケイ酸塩鉱物の総称です。アルミノケイ酸塩とは、ケイ酸塩においてケイ酸の一部がアルミニウムによって置換されたもので、
xM
2O
yAl
2O
3 zSiO
2 nH
2O
と表されます。AlO
4 および SiO
4 の四面体がOを共有してつながり、鎖状・層状・網状の骨格を作り出しています(多くの倍、隙間に陽イオンが入っています)。ムライトの化学式は
3Al
2O
3 2SiO
2 〜 2Al
2O
3 SiO
2
の幅を持っており、結晶構造も一定ではありません。
シリマナイトはケイセン(珪線)石とも呼ばれ、斜方晶系に属するアルミニウムケイ酸塩( Al
2O SiO
4 )の仲間です。斜方晶系のコウチュウ(紅柱)石、三斜晶系のランショウ(藍晶)石と多形をなしています。
より詳しい説明は、『化学大辞典』(共立出版)などをご覧ください。
【Q&A目次に戻る】

PDPは、現時点で「薄くて大きな画面を」という要求に応えられる唯一の商用ディスプレイであり、NECやフィリップスなど複数のハイテク企業が参入してしのぎを削っています。このため、製造技術も日進月歩ですが、ここでは、2〜3年ほど前の記事に基づいて解説することにします(A.ソベル「これからの薄型大画面ディスプレー」(日経サイエンス、1998年8月号)/日立化成テクニカルレポート)。
PDPの画素は3つのセルから構成されており、キセノンやネオンなどの不活性ガスが封入されている各セルは、1対の電極と蛍光体(赤・緑・青)を含んでいます。セル内部に定期的に放電させることにより、ガスの一部はイオン化してプラズマ(イオン化ガスと中性ガスの混合体)になっています。ここで、格子状に配置された電極に順次(適当な大きさの)電圧を加えていくと、交点に位置するセルに電場が生じて電子が加速され、これと衝突して励起された中性原子から紫外線が放出されます。この紫外線が蛍光体に当たると、3原色のいずれかの光が発せられることになります。この発光メカニズムは、基本的に蛍光灯と同じです。
PDPの欠点は、寿命が短いことです。もちろん、傷が付いて封入ガスが漏れ出せばディスプレイは発光しなくなりますが、それよりも、正イオンが陰極に衝突し、はじき出された原子がセル内部の別の部分に付着して、透過性をなくしたりショートさせたりする問題の方が深刻なようです。また、長時間にわたって使用し続けると蛍光体が劣化し、輝度が低下します。
PDPの製造に当たっては、ガラス基板上に電極や保護層などを形成した前面板と、ガラス基板に電極・保護層を形成した上に蛍光体層を形成した背面板を貼り合わせ、内部を排気した後に脇からキセノンなどの不活性ガスを送り込んで封入します。その後、周辺回路と接続し、シールド板などを取り付けてパネルが完成します。
【Q&A目次に戻る】

光速(あるいは亜光速)で運動する物体については、いろいろと直感に反することが起きますが、物理学的にきちんと解明すると、決して摩訶不思議な現象ではないことがわかります。
ご質問の件は、映像が光速でしか伝わらないことを考えれば、奇妙な点はありません。超音速で弾を発射するライフルで狙撃されたときに、被弾した後にパーンという発射音を聞くのと同様です。相対論で明らかにされたように、ロケットのように質量を持つ物体は光速では進めないので、発射の際の光が到達した少し後にロケット本体が到着することになります。ただし、ロケットの映像を実際に観測した場合、早送りのビデオのように船内でチョコマカと動く人の姿が見えるかというと、そうはいきません。こちらに向かってやってくる列車の警笛がかん高い高音になって聞こえるのと同じように、ドップラー効果によって光の波長が押し縮められ、静止物体では赤外線になるような光が可視光に変化するからです。赤外線領域では物体による放射の差はあまり大きくないので、飛来するロケットは、初めはぼんやりした光の塊のように見え、減速する(あるいは通り過ぎようとして相対速度が小さくなる)過程で次第に形がはっきりしてくるはずです。
なお、惑星に固定された時計では飛行に2年間掛かったことになっていますが、相対論によれば亜光速のロケット内部では時間はゆっくりと経過するので、ロケットの乗組員からすると、ほとんど一瞬のうちに惑星間航行をしてしまったことになります。これは、ロケットから見て惑星間距離がローレンツ短縮によって縮んでしまったためです。
【Q&A目次に戻る】

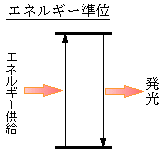
物質の発光は、一般に、高いエネルギー準位にあった電子が低い準位に遷移する際に生じます。物質が熱平衡状態にある場合、加えられたエネルギーは、電子の準位を押し上げるだけでなく、エネルギー分配則に応じて格子振動などに変換されるので、視覚に感じられるほど発光している物質は、高温状態になっているのがふつうです。ところが、熱平衡に達することなく、何らかのメカニズムで電子だけが高いエネルギー状態に励起されると、温度が低いままで光を発する現象が見られます。こうした現象(またはそのとき発せられる光)をルミネッセンス(luminescence)と言い、熱平衡にある発光体のような高温物体から発せられていないので「冷光」と呼ばれることもあります。電子だけを適当な準位に励起して他の部分にエネルギーを全く供給しないようにするのは技術的に難しいため、「冷たい光」とは言ってもある程度の温度上昇を伴うことが多いのですが、蛍の光などの生物ルミネッセンスは、エネルギー変換効率が高く発熱がほとんどありません。また、遅延蛍光のように、高エネルギー状態が準安定で、物質の温度が低下した後にゆっくりと発光することもあります。
特別な環境を整えれば、励起状態の原子数が基底状態にある原子数よりも多くなるような分布を実現することも可能です。レーザー光線は、こうした“反転分布”の状態から放射される一種のルミネッセンスです。レーザー光線は、励起状態と基底状態のエネルギー差に対応する特定の波長の強度だけが強くなっており、全ての波長にわたる光エネルギーの総量は、それほど大きくありません。したがって、青・赤・緑という3原色のレーザー光線を組み合わせれば、高温発光体の熱放射による白色光をフィルターなどで分光する場合に比べて、はるかに小さなエネルギーで任意の色の光を作り出すことができます。
【Q&A目次に戻る】

長さLの単振り子(質点振り子)の周期Tは、振幅が小さいという近似の下で、
T = 2π(L/g)
1/2 (g:重力加速度)
で与えられます。1901年に採択された標準重力加速度
g = 9.80665 [m/s
2]
はπ
2= 9.86960 と近似的に等しいので、L=1[m] の単振り子の半周期は、約1秒(正確には、1.0032秒)となります。
長さと時間の基本単位が振り子を通じて結びつけられることに、歴史的な理由があるかどうかは、はっきりしていません。
こんにち使われている単位系の元になっているのは、古代バビロニアの度量衡です。古代の長さの単位は、通常、人体を基準としています(フィートや尺など)が、バビロニアでは、成人男子の肘の長さに基づく倍肘長(0.992メートル)という単位が使われていました。これが各地に伝わり、後に1メートルとして標準化される単位の元になります。「1メートル」は、1799年にフランス科学アカデミーによって「子午線の北極から赤道までの長さの1000万分の1」として厳密に定義されますが、人間の肘長と地球の子午線の長さの比が単純な値になったのは、全くの偶然でしょう。
一方、時間の単位に関しても、バビロニア文明は、近代的な時−分−秒制の基礎を作りました。エジプトや中国など多くの古代文明では、日の出と日の入りを境として昼夜それぞれを6ないし12等分するという「不定時法」が採用されていました(当然、季節によって、また、昼と夜で単位時間の長さが異なります)が、バビロニアの天文学者たちは、早い段階で、昼夜の区別を設けずに1日を12等分するという「定時法」を利用するようになります。ここで使われたカプスという単位は、エジプトや中近東に伝えられ、季節によって伸び縮みしない時間概念のベースになります。さらに、天文学者らが用いていた60進法に基づいて、時間単位を1/60に分割していく方式も案出したとされています。
もっとも、こうして作り上げた時間単位を、振り子を通じて長さの単位と結びつける発想があったかどうかは、はっきりしません。古代における精密な時間測定は、振り子ではなく、専ら「クレプシドラ」と呼ばれる水時計によって行われていました。この水時計は、意外と正確なもので、古代エジプトの遺跡から発見された水時計には1日分の時刻目盛りが刻みつけられており、その誤差も、1日あたり十数分だったようです。もちろん、1日の24×60×60分の1が単位長さの振り子の半周期になるように、倍肘長の定義を調整した可能性もない訳ではありません(1倍肘長の単振り子の半周期は、1000分の1以下の誤差で1秒に一致します)。しかし、それを裏付ける証拠はなく、ダンネマンら科学史家の多くは、この一致は「単なる偶然」だと見なしています(ダンネマン『大自然科学史1』(三省堂))。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
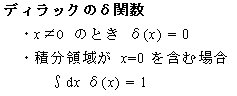 例えば、点電荷が作る電位は(電荷からの距離をrとすると) 1/r に、電界は 1/r2 に比例し、電荷の置かれた点では発散して解析性が失われるはずですが、ディラックのδ関数という超関数の一種を使うことによって、実質的に解析的な扱いがなされています。また、質問にあった「微分係数が不連続になる」ケースは、面電荷が分布しているときに見られます。 x=0 となるyz面内に一様に面電荷が分布しているとき、電位は |x| に、電界のx成分は θ(x)-θ(-x) に線形に依存します(θ(x)は x>0のとき1、 x<0 のとき0 になる階段関数で、その微分はδ関数になります)。これも、本来なら x=0 で微分ができないはずですが、超関数を使って、あたかも解析的であるかのように計算を進めることが可能です。
例えば、点電荷が作る電位は(電荷からの距離をrとすると) 1/r に、電界は 1/r2 に比例し、電荷の置かれた点では発散して解析性が失われるはずですが、ディラックのδ関数という超関数の一種を使うことによって、実質的に解析的な扱いがなされています。また、質問にあった「微分係数が不連続になる」ケースは、面電荷が分布しているときに見られます。 x=0 となるyz面内に一様に面電荷が分布しているとき、電位は |x| に、電界のx成分は θ(x)-θ(-x) に線形に依存します(θ(x)は x>0のとき1、 x<0 のとき0 になる階段関数で、その微分はδ関数になります)。これも、本来なら x=0 で微分ができないはずですが、超関数を使って、あたかも解析的であるかのように計算を進めることが可能です。
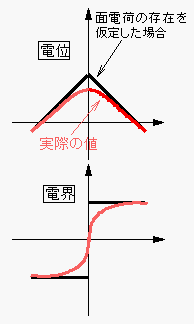 上の面電荷の例にしても、「(厚みのない)面上に電荷がなめらかに分布する」ことは現実にはあり得ず、電子のような点電荷が比較的狭い幅の中に分布していると考えられます。この場合、電位や電界は、(電子の存在する場所以外では)特異性のない“なまった”関数で表されるはずです(右図)。
上の面電荷の例にしても、「(厚みのない)面上に電荷がなめらかに分布する」ことは現実にはあり得ず、電子のような点電荷が比較的狭い幅の中に分布していると考えられます。この場合、電位や電界は、(電子の存在する場所以外では)特異性のない“なまった”関数で表されるはずです(右図)。
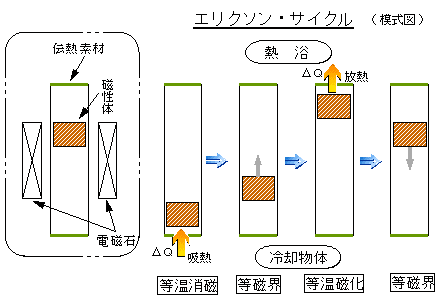
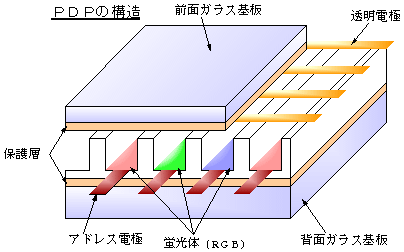
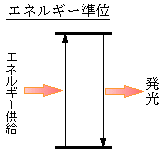 物質の発光は、一般に、高いエネルギー準位にあった電子が低い準位に遷移する際に生じます。物質が熱平衡状態にある場合、加えられたエネルギーは、電子の準位を押し上げるだけでなく、エネルギー分配則に応じて格子振動などに変換されるので、視覚に感じられるほど発光している物質は、高温状態になっているのがふつうです。ところが、熱平衡に達することなく、何らかのメカニズムで電子だけが高いエネルギー状態に励起されると、温度が低いままで光を発する現象が見られます。こうした現象(またはそのとき発せられる光)をルミネッセンス(luminescence)と言い、熱平衡にある発光体のような高温物体から発せられていないので「冷光」と呼ばれることもあります。電子だけを適当な準位に励起して他の部分にエネルギーを全く供給しないようにするのは技術的に難しいため、「冷たい光」とは言ってもある程度の温度上昇を伴うことが多いのですが、蛍の光などの生物ルミネッセンスは、エネルギー変換効率が高く発熱がほとんどありません。また、遅延蛍光のように、高エネルギー状態が準安定で、物質の温度が低下した後にゆっくりと発光することもあります。
物質の発光は、一般に、高いエネルギー準位にあった電子が低い準位に遷移する際に生じます。物質が熱平衡状態にある場合、加えられたエネルギーは、電子の準位を押し上げるだけでなく、エネルギー分配則に応じて格子振動などに変換されるので、視覚に感じられるほど発光している物質は、高温状態になっているのがふつうです。ところが、熱平衡に達することなく、何らかのメカニズムで電子だけが高いエネルギー状態に励起されると、温度が低いままで光を発する現象が見られます。こうした現象(またはそのとき発せられる光)をルミネッセンス(luminescence)と言い、熱平衡にある発光体のような高温物体から発せられていないので「冷光」と呼ばれることもあります。電子だけを適当な準位に励起して他の部分にエネルギーを全く供給しないようにするのは技術的に難しいため、「冷たい光」とは言ってもある程度の温度上昇を伴うことが多いのですが、蛍の光などの生物ルミネッセンスは、エネルギー変換効率が高く発熱がほとんどありません。また、遅延蛍光のように、高エネルギー状態が準安定で、物質の温度が低下した後にゆっくりと発光することもあります。