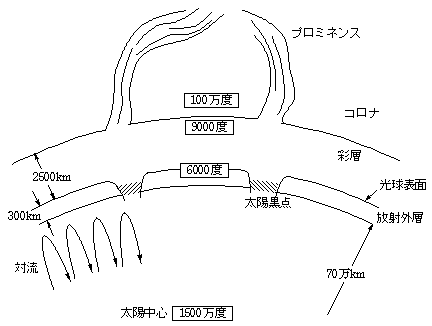光は電磁エネルギーとともに運動量を運んでいます(例えば、振動数νの光子に関するド・ブロイの公式では、エネルギーはhν、運動量はhν/cとなっています)。従って、光を吸収したり反射したりする物体は、電磁場の運動量の流れを変化させることになり、その反作用として圧力を受けることになります。
光圧の公式は、どの電磁気学の教科書にも書いてあるマクスウェルの応力テンソル(エネルギー運動量テンソルの空間成分)の式から導けます。真空中の応力テンソルは、
T
ij = E
iE
j + H
iH
j - δ
ij/2 (
E2 +
H2)
と表されます。ここでは、z方向に伝播する電磁波が、z>0 の領域に無限に拡がっている物体によって完全に吸収される場合を考えましょう。物体が受ける単位体積あたりの力のz成分F
z は、ローレンツ力に関する一般論(電磁気学の教科書を参照してください)より、
F
z = ∂
kT
zk - ∂
t(
E×
H)
z
で与えられます。圧力(単位
面積あたりの力)は、長時間平均を取ってから物体が存在する領域 z=0〜∞ にわたってF
z を積分すれば求められます。ここで、長時間平均を取ると第2項が消えること、および、z方向に伝播する電磁波では場のx,y依存性はないことを使って式を簡単化すると、光圧P の公式として、
P = ∫
0∞<F
z>
= 1/2(<
E2> + <
H2>)
が得られます。この式は、平面波による光圧が電磁波の平均エネルギー密度に等しいことを表しています。
このほか、内壁が反射体でできている空洞の場合は、いろいろな方向からやってくる電磁波について平均を取ることにより、光圧が平均エネルギー密度の1/3になることが示せます(詳しくは、電磁気学の教科書を参照のこと)。
通常の光の場合、エネルギー密度が希薄なので、光による圧力も、ごく微弱なものにすぎません。しかし、22世紀以降の壮大な夢として、レーザー光線かマイクロ波の光圧を利用して恒星間宇宙船を飛ばそうという計画もあります。金属薄膜で作った巨大な帆に基地から強力な電磁波を照射して運動量を与える「光帆船」のアイデアです。NASAは、夢に向かう第1歩として、地球周回軌道を直径100メートルの帆を使って航行する光帆船の実現可能性について検討を始めたそうですが、いつの日か、差し渡し数kmの巨大な帆を持った宇宙船が、アルファ・ケンタウリに向けて優雅に飛び立つかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

幾何光学が厳密に成り立つ場合、平行光線が障害物に当たると、その断面と同じ形のくっきりした境界を持つ影ができるはずです。しかし、実際には、光線が回り込んで、光と影の境目には複雑な強度分布が生じています。これが回折と呼ばれる現象で、障害物に比べて波長が長いほど強く現れます。回折される光の強度分布を計算することは、一般にきわめて難しい作業になりますが、幾何光学からのずれが小さいときには、近似的な計算が可能になります。特に、平行単色光を小さな開口部を持つ不透明スクリーンに当てたとき、充分に離れたところで光強度の方向分布がどうなるかという問題は、フラウンホーファ回折の演習として、光学の教科書にしばしば取り上げられています。
z軸方向に伝播する波数kの入射波の成分は、時間に依存する因子( exp(-iωt) )を別にして、
u = u
0 exp(ikz)
という表式(の実部)で表されます。ただし、u
0 は(複素)振幅です。
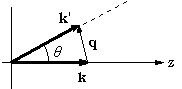
一方、開口部を通過した光線は、スクリーンから充分に離れたところでは、波数ベクトル
k'=
k+
q を持つ光線u
qの重ね合わせで近似することができます。ここで、開口部における場は、スクリーンがないときと同じだと仮定すると、次の境界条件が成立します:
u
0 exp(ikz) = ∫d
q u
q exp(i(
k+
q)
・r )
両辺を比較し、フーリエの逆変換の公式が適用できるとすれば、
u
q = u
0 ∫dS exp(-i
q・r )/(2π)
2
と表されます(積分は開口面で実行)。開口部が半径aの円であるときには、
u
q = u
0 ∫rdr∫dφ exp(-iqrcosφ )/(2π)
2
となります。ベッセル関数を使って積分を実行(数学公式集を参照)し、q=kθと置けば、θの方向に伝播する回折光強度(|u
q|
2に比例する)のθ依存性は、
(J
1(akθ)/θ)
2
(J
1は1次のベッセル関数)
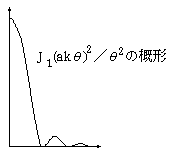
で与えられます。式の形から明らかなように、円形開口部を通過した光は、幾何光学に従う θ=0 の直進光が最も強くなるものの、開口部から広がっていくθ>0 の成分も含まれており、スクリーンから離れると次第に光の拡がりが大きくなっていくことがわかります。
数学的にもっときちんとした解説は、大学専門課程の光学の教科書に書いてあります。
【Q&A目次に戻る】

太陽の最外層となるコロナが太陽本体(光球)の表面より遥かに高温になっている原因は、現在なお完全に解明されているわけではありませんが、1970年代以降の人工衛星による観測を通じて、おおよそのメカニズムがわかってきました。
太陽の熱源となっているのは、中心部で進行している核融合反応であり、毎秒7億トンの水素がヘリウムに変化する過程で3.8×10
26ジュールの熱が生み出されます。この熱は、中心部の温度を1500万度にまで高め、対流によって光球の表面まで伝えられた後、極低温の宇宙空間に放射されていきます。このため、太陽の内部温度は、熱伝導の法則に則って中心からの距離とともに低下し、光球表面では6000度程度になります(表面から太陽半径の1%内側にはいると、温度は約5万度に上昇します)。通常の熱伝導が行われているならば、光球の外側にある彩層やコロナはそれより低温になるはずですが、実際には、彩層は5000〜9000度、コロナは100〜200万度になっており、熱伝導とは異なる加熱機構を想定しなければなりません。
1970年代初めまでは、こうした加熱機構の理論として、ビアマンらによる衝撃波仮説が受け入れられていました。これは、光球の表面でボツボツと煮えたぎるガス運動が乱流を引き起こし、その波動がコロナに伝わって衝撃波面を形成して熱を発生するというものです。ところが、1973年にスカイラブ衛星が撮影した太陽のX線像を解析したところ、コロナは一様ではなく、細いループ状の高温領域から構成されていることが判明しました。このループは正負の黒点をつなぐ磁力線とほぼ一致しており、コロナの加熱に磁場が大きく関与していることがわかります。衝撃波仮説は、磁力線に沿って熱が発生する理由を説明できないために否定され、代わって、磁気流体力学的な加熱機構が提唱されるようになります。
磁気を介した加熱を説明する理論として有力なのが、プラズマ波動の一種であるアルフヴェン波によるエネルギー伝達を仮定するものです。この理論によれば、光球内部の乱流によって生じたアルフヴェン波が、黒点から伸びた磁力線に沿ってコロナに伝わり、密度の変化に応じて圧縮波を作り出して周囲を加熱すると考えられます。このほか、フレアと呼ばれる磁気プラズマの爆発現象が重要な役割を演じているという説もあります。
コロナは、密度が3×10
-17g/cm
3ときわめて希薄であり、熱放射によって外部に熱を排出しにくい(放射による熱損失は密度の2乗に比例します)ため、上のようなメカニズムでエネルギーが注入されると、すぐに高温になってしまいます。これが、コロナがきわめて高温になっている理由です。ただし、総質量が小さいので、百万度を超すと言ってもエネルギーの総量は大したことはありません。
【Q&A目次に戻る】

結晶は、構造単位となる原子集団が周期的に配列したものであり、初等的な固体物理の教科書でエネルギー準位などを計算する際には、構造単位の繰り返しが無限に続くものと仮定されています。しかし、現実の結晶には、微量の異種原子が混入していたり、結晶境界が存在したりするため、一般に原子の配列には乱れが生じています。こうした乱れは、ランダムに現れることが多いのですが、場合によっては、安定な状態を作るように原子が自ら並べ替えを行うという「自己組織化」によって、結晶の格子定数(空間的周期)よりも大きなスケールで規則性が生じることがあります。こうした規則性を持つ構造が「超構造」と呼ばれます。ただし、「超構造」という用語に厳密な定義はなく、研究グループによってかなりニュアンスの違いがあるようです。
近年、応用面から特に注目されているのが、半導体表面の超構造です。シリコン原子は4つの「手」を持っていて、これが相互に結合(共有結合)してダイヤモンド型格子を構成していますが、結晶の表面にいる原子は、相棒がいないために手が余ってしまいます。こうした余った手(ダングリング・ボンド)がたくさんあると不安定になるため、表面近くの数層の原子層では、ダイヤモンド型格子からずれた「表面超構造」が形成されています。特に、微量の不純物が表面に吸着されると、これを取り込んだ特異な構造が作られ、半導体の物理的性質を大きく変化させることもあります。例えば、厚さ0.4mmのシリコンウェハに、表面のシリコン原子1000個に対して8個の割合でパラパラと銀原子を蒸着させると、ウェハの電気抵抗が、銀原子がないときよりも10%ほど低下するという報告があります(日本物理学会誌 54(1999)347-)。このとき、ウェハを構成する百万枚のシリコン原子層のうち、表面近くの2層ほどしか構造は変化していませんが、表面電子のエネルギー・スペクトルのシフトが、電気抵抗を大幅に減少させるのに寄与したと考えられます。こうした性質を利用して、エレクトロニクス分野の新素材が開発できないか、多くの研究者が注目しています。
このほか、性質の異なる有機分子膜を積み重ねて「積層超構造」を作る研究も進められています。こうした素材は、オプトエレクトロニクスでの応用が期待されています。
【Q&A目次に戻る】

これとほぼ同じ問いは、20世紀初頭の相対論の批判者によって提出され、物理学者から「剛体棒は存在できない」という実に単純な回答で切り替えされました。きわめて頑丈な未発見の素材があるのではないか──と疑問を持つかもしれませんが、この回答は素材にはよりません。このことは、相対論の公式を使って示せます。棒の先端に近い(静止)質量m の部分速度が速度v で運動していたとすると、その部分の有効質量(慣性)は、

となり、v が光速c に近づくにつれて無限大に増加します。宇宙空間に浮遊している状態で頑丈な長い棒を製造し、これを地球に差し込んで回転させ始めると、先端に近い部分の速度が増すにつれて慣性(加速されにくさ)が大きくなり、地球と同じ角速度で回転するように加速していくには、棒の根本に近い側から無限に増加する力を作用させなければなりません。どんなに頑丈な素材でできた棒も、内部の応力が無限に大きくなると必ず変形し、どこかで折れてしまうはずです。
ちなみに、棒を使わず赤道から自転軸に垂直に光を放出すると、(光は一定の速度c で進むので)その通り道はラセン状にねじれていきます。また、光源から充分遠方で光を捉える場合、到達地点の移動速度が光速を越えることもあり得ますが、これは物体が移動しているわけではないので、相対論と矛盾していません。
【Q&A目次に戻る】

金属の比熱は、主に2つの項からの寄与によって決定されます。1つは結晶格子の振動項で、絶縁体の比熱に関するデバイの理論によって記述されます。もう1つは、金属特有の自由電子の運動による項で、フェルミ・エネルギー(温度に換算してT
F〜数万度)以上のエネルギーを持つ電子が金属内部を自由に“飛び回る”ことに起因するものです。温度T のときの自由電子による比熱Cは、近似的に
C 〜 NkT/T
F (N:電子の総数)
となり、数百K程度では格子振動に較べて無視することができます。
デバイによる固体比熱の理論(1912)とは、格子振動による音波の中で特定振動数(デバイ振動数)以下の波動だけが励起されると仮定して比熱を求めたもので、かなり粗い近似ですが、比熱の測定値ををうまく説明できるものです(詳しくは、キッテル著『固体物理学入門』などを参照してください)。この理論によると、単原子格子のモル比熱は次の公式で表されます:
C = 3R D(θ/T)
ただし、θはデバイ温度(デバイ振動数を温度に換算したもの)で、数百K程度の大きさになります。また、D(x) はいわゆるデバイ関数で、
D(x) = 3x
-3∫dzz
4e
z/(e
z-1)
2 (積分区間:[0,x])
で与えられます。
T≫θという高温極限では(D(0)=1 より) C=3R となってデュロン−プティの法則に一致します。T≪θでは、(D(x)〜x
-3 より) C∝T
3 となります(比熱が絶対零度で0 に漸近する定性的な説明は、
別の回答をご覧ください)。デバイの公式は、比熱が小さい低温極限と一定値になる高温極限を結びつける内挿公式だと言えます。
質問にある推定式は、デバイ温度よりやや高い温度付近からデュロン−プティの法則( C = 6.0[cal/deg mol]に漸近していく(かなり狭い)範囲での実験式です。多くの金属では、デバイ温度が200〜400Kの範囲にあり、結晶構造が変化する相転移点付近を除いて、比熱の振舞いは似通っています。
【Q&A目次に戻る】

現代宇宙論の基礎になっているフリードマン模型は、アインシュタイン方程式を一様等方(宇宙はどの場所で見ても同じように見える)という条件下で解いたときに得られるもので、現在の密度(物質密度+真空のエネルギー)と初期条件によって定まる臨界密度との比(Ω=ρ/ρ
c)が1より大きいかどうかによって、3つのタイプに分類されます:
- Ω>1(閉じた宇宙):宇宙の空間的拡がり・全質量は有限で、有限時間内に宇宙は膨張から収縮に転じ、ビッグクランチによって消滅する。
- Ω=1(平坦な宇宙):宇宙の空間的拡がり・全質量は無限大で、宇宙の拡がりを表すスケール因子R(t)は、時間とともに
R(t)∝t2/3
という形で増大し続ける。
- Ω<1(開いた宇宙):宇宙の空間的拡がり・全質量は無限大で、宇宙の拡がりを表すスケール因子R(t)は、時間が充分に経過した時点では、近似的に
R(t)∝t
という形で増大し続ける。
これからわかるように、フリードマン模型によると、宇宙の全体的な振舞いは、Ωが「1より大きいか」「1以下か」で大きく変わり、「Ω=1」と「Ω<1」での差はそれほどでもありません(理論的には明確に区別されますが)。「平坦な宇宙」「開いた宇宙」いずれも、無限に膨張する過程で物質密度がきわめて希薄になり、質量あたりのエントロピーが極大値に漸近して、宇宙は所々に点在するブラックホールと、薄く瀰漫する超長波長の電磁波および低エネルギーのニュートリノだけの世界になっていく(最終的にはブラックホールも蒸発して消えてしまうかもしれない)と考えられています。
ただし、「無限宇宙」という考えに批判的な学者も少なくありません。「Ω≦1」の場合には、宇宙全体にわたって一様等方だという条件が成り立たず、トポロジカルに複雑な構造を取っている(例えば、宇宙全体がトーラス状になっていて、特定の方向に進むと短い距離を進んだだけで元の場所に戻ってきてしまう)という可能性もあります。現在の観測データでは「Ω=0.3」程度なので、フリードマン模型そのものを考え直した方が良い時期に来ているのかもしれません。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
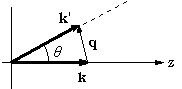 一方、開口部を通過した光線は、スクリーンから充分に離れたところでは、波数ベクトルk'=k+q を持つ光線uqの重ね合わせで近似することができます。ここで、開口部における場は、スクリーンがないときと同じだと仮定すると、次の境界条件が成立します:
一方、開口部を通過した光線は、スクリーンから充分に離れたところでは、波数ベクトルk'=k+q を持つ光線uqの重ね合わせで近似することができます。ここで、開口部における場は、スクリーンがないときと同じだと仮定すると、次の境界条件が成立します:
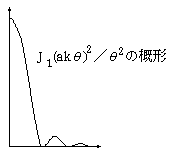 で与えられます。式の形から明らかなように、円形開口部を通過した光は、幾何光学に従う θ=0 の直進光が最も強くなるものの、開口部から広がっていくθ>0 の成分も含まれており、スクリーンから離れると次第に光の拡がりが大きくなっていくことがわかります。
で与えられます。式の形から明らかなように、円形開口部を通過した光は、幾何光学に従う θ=0 の直進光が最も強くなるものの、開口部から広がっていくθ>0 の成分も含まれており、スクリーンから離れると次第に光の拡がりが大きくなっていくことがわかります。