
�u�d�q�͔g�ł��藱�q�ł���i���邢�́A�ǂ���Ƃ����߂��Ȃ��j�v�Ƃ����̂�1920�`30�N��ɗ��s�����{�[�A��n�C�[���x���N�̉��߂ŁA�Θ_�I�ȋߎ��Ɋ�Â��ʎq�_---������ʎq�͊w---�̗���ł��B
����A�u�d�q�͔g���v�Ƃ����咣�́A�ʎq�͊w�̊�ՂƂȂ��̗ʎq�_�i���Θ_�I�ȗʎq�_�j�̒��ړI�ȋA���ł����A����������̗ʎq�_�̗������L�܂��Ă��Ȃ��̂ŁA�K��������ʓI�ł͂���܂���B
��҂̎咣�����y���Ȃ����R�Ƃ��ẮA�������̎���l�����܂��B
(1) ��̗ʎq�_�̎�e����r�I�ߔN������
��̗ʎq�_�́A1920�N��ɒ��ꂽ�ɂ�������炸�A�v���I�Ƃ��v���錇�ׂ�����������Ă���A60�N��O���ɂ͊��S�Ɍ����̎嗬����O��Ă��܂����B
���s�ɋt����Č����𑱂��Ă����ꕔ�̕����w�҂ɂ���āA���肱�Q�⎩���I�Ώ̐��̔j��̃��J�j�Y�������炩�ɂ���A�悤�₭70�N��Ɋ�b���_�Ƃ��ĔF�߂���Ɏ������̂ł��B
�ʎq�͊w�̖����Ƃ���鋳�ȏ��ɂ́A�i�����_�E�����t�V�b�c��V�A�Ȃǁj60�N��܂łɎ��M���ꂽ���̂����Ȃ肠��̂ŁA�������g���ĕ���������́A��ɂ��Ă̗������s�\���������悤�ł��B
(2) ���炭��������߂��ʗp���Ă���
�`����������Ə�̗ʎq�_�Ƃ�������Ȃ̂��A�f�B���b�N�ɂ���Q�ʎq���̗��_�ł��B
�ʎq�����ꂽ�g�������g���āA�d�q�E�z�d�q�Ȃǂ̗��q���������݂���V�X�e�����������̂ł����B
���݁A��Q�ʎq���̗��_�́A���{�I�Ɍ�肾�����Ƃ��ĖَE����Ă��܂����A80�N�㍠�ɂ͂܂��A����Ɋ�Â��ď�̗ʎq�_�����߂���l�����Ȃ�����܂���ł����i�f���q�����╨���̌����҂Ȃǁj�B
(3) ��̗ʎq�_�̐��Ƃ͏��Ȃ�
��̗ʎq�_�́A��̓I�Ȍv�Z���قƂ�ǂł����Z�p�I�ȉ��p���̂܂������Ȃ����_�ł���A�ǂ�Ȃɕ����Ă��A���̐��ʂɂ���Ċ�ƌ������ɏA�E�ł��铹�͂���܂���B
�����ʂɉ��p�ł��Љ�̖��ɗ��̂́A�Θ_�ߎ���p���邱�Ƃŋ�̓I�Ȍv�Z���\�ɂȂ����ʎq�͊w�̕��ł��B
���������������̂ŁA�ʎq�_�֘A�̌����J�����s���Ȋw�ҁE�Z�p�҂̈��|�I�����́A�ʎq�͊w�̊�b��g�ɕt���������ŁA��̗ʎq�_�́i���Ƃ������Ƃ��Ă��j�����Ȃ�ɂ��������Ă��Ȃ��l�����ł��B
��w�ŗʎq�_�̓���u����S�����鋳���ɁA��̗ʎq�_�ɂ��Ă낭�ɒm��Ȃ��l�����Ȃ肢��̂��A�����܂��B
(4) ���Ƃł���̗ʎq�_�̕��y�ɂ͔M�S�łȂ�
��̗ʎq�_�́A�a���������ォ�瑽���̌��ׂ�����Ă��܂����B
���̑啔����60�N��ɉ�������A70�N��ɑf���q�́u�W���͌^�v���m������܂������A�܂������ȗ��_�ƌ����ɂ͂قlj����i�K�ł���A����ɐ�ɐi�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��b��I�ȗ��_�ł��B
20���I�I�Ղ̑f���q�_�̌����҂́A�����I�ȏ�O�ɍl�Ă��ꂽ���Ȃ�Â߂��������_�̃X�|�[�N�X�}���ƂȂ�����A�|�X�g�W���͌^�������̎�ō���Č��`���邱�ƂɈӗ~��R�₵�܂����B
�������āA80�`90�N��ɂ͎����㗝�_�̌��i���Ђ����_�Ȃǁj�Ɋւ����ʌ����̏��������s���A���̈���ŁA�߂������Ɋ�b���_�Ƃ��Ă̖������I����͂��̏�̗ʎq�_�́A�����ĕ��y�ɐs�͂���K�v�͂Ȃ��Ɗ�����ꂽ�̂ł��傤�B
��̗ʎq�_�����ꂩ��Ђ�����Ԃ�\�����F���Ƃ͌����܂��A���́A��Ɋ�Â����R�ς��p��邱�Ƃ͂Ȃ��ƐM���Ă��܂��i���Ђ����_�ł��A�u�Ђ��̏�̗��_�i��N��Ԃ��Ђ���ɂȂ��̗��_�j�v���͍����ꂽ����������܂������A���̂ɂȂ�Ȃ������悤�ł��j�B
�������A��̕��ނɊւ���c�_���啝�ɕύX����A�����炭�̓X�J���[�ꂪ�p��X�s�m������\�����S���ς�肻���Ȃ̂ŁA���݂̏�̗ʎq�_�����̂܂܍L�߂邱�ƂɁA���Ƃ����͔M�S�ɂȂ�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�����ւ̃^�C���g���x���͌����I�ɂ͉\�ł��B
�@�������ASF�f��ɕ`�����悤�ɁA�ғ������u�Ԃɑ~�������悤�ɂȂ��Ȃ�A����҂��炷��Ƃ����Ƃ����Ԃɕʂ̎���ɓ�������Ƃ������A���Ԃ���g�^�C���}�V���h����邱�Ƃ͂ł��܂���B���㕨���w�̊�b�́A�����镨�����ۂ͏�ɐ�����A���I�ȉߒ����Ƃ����u��̗��_�v�ō\�z����Ă���A������щz���邱�Ƃ͕s�\���ƍl�����Ă��邩��ł��B�����ɍs����Ƃ͌����Ă��A�o���_�Ɠ����_�����ԘA���I�ȁg���E���h�ɉ����Đi�ނ�������܂���B
�@�����ɍs���^�C���}�V���Ƃ��ẮA�E���V�}���ʂ𗘗p����̂��ł��ȒP�ł��B�Ⴆ�A�S���N�ޕ��ɂ���V�́i�A���t�@�E�P���^�E���Ȃǁj�܂Ō�����80���ʼn�������ƁA�n���Ɏc�����l�ɂ͉F���D���A�҂���܂�10�N�|����܂����A��g���ɂƂ��đD�����Ԃ�6�N�����o�߂��Ă��܂���i����͑��Θ_�I���ʂ̌���ŁA��̓I�ȉ���́A�ْ��w���S�ƏK���ΐ����_�x��6-1-3�ōs���Ă��܂��j�B�F���D�̏�g���́A6�N���|����10�N��̒n���ɋA���Ă����̂ŁA4�N���̖����ɍs�������ƂɂȂ�܂��B���Ԃ��щz������ł͂Ȃ��A���w�]�������g���ƁA�X���[���[�V�����œ����p��������͂��ł��B
�@SF�I�ȁu���Ԃ���^�C���}�V���v�̃A�C�f�A�́AH.G.�E�F���Y�̌ÓT�I����w�^�C���}�V���x�ɗR������ł��傤�B�Ȋw�I�f�{�̂������E�F���Y�́A�����ɍs���ɂ͎��Ԃ�A���I�ɂ��ǂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ킩���Ă���A�u�����Ŕ�Ԓe�ۂ�����ɂ͌����Ȃ��悤�Ɂv���݂�������Ƌꂵ�������Ă��܂��B
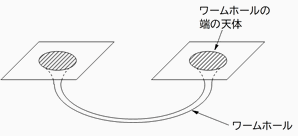
�@�ߋ��ɖ߂�^�C���g���x���ɂ��āA���Ă͕����@���ɂ���ċ֎~�����ƍl�����Ă��܂����B�ߋ��ɖ߂��Ȃ�A�u�e�E���̃p���h�N�X�v�Ȃǂ̃^�C���p���h�N�X�������Ă��܂�����ł��B����܂ł��܂��܂ȃp���h�N�X���l�Ă���A�ߋ��ɖ߂郋�[�g�����݂���A���Ƃ��l�Ԃ����Ȃ��Ă��������N����i��������_�ɂQ�̑������鎖�ۂ����N����j���Ƃ�������Ă��܂��B
�@�Ƃ��낪�A1988�N�A���Θ_�����̑�Ƃł���\�[���i�d�͔g�Ɋւ���ƐтŃm�[�x���܂���܁j���A���[���z�[���𗘗p���ĉߋ��ɖ߂��\�������邱�Ƃ������A�傫�Șb��ƂȂ�܂����BSF��Ƃ̊�z�ł͂Ȃ��A���m�ȕ����w���_�Ƃ��ĉߋ��ւ̃^�C���g���x�����_����ꂽ�̂ł��B
�@���[���z�[���Ƃ́A�A�C���V���^�C���������̉��ƂȂ蓾�鎞��\���ŁA�قȂ�n�_���V���[�g�J�b�g�Ō��ԒʘH�i����̒��H�����j���C���[�W���Ă��������B�\�[�����ďC�߂��f��w�C���^�[�X�e���[�x�ł́A�[���u���b�N�z�[���Ɍ����郊�A���ȃ��[���z�[�����o�ꂵ�܂����B
�@�ʏ�̃��[���z�[���́A��ԓI�ɗ���Ă�����̗̂��[�����������ɂȂ邱�Ƃ��z�肳��Ă��܂��B����ɑ��āA�\�[���̓E���V�}���ʂȂǂ𗘗p���ė��[�Ɏ��ԍ���t����A�g�^�C���g���l���h�ƂȂ蓾�邱�Ƃ������܂����B
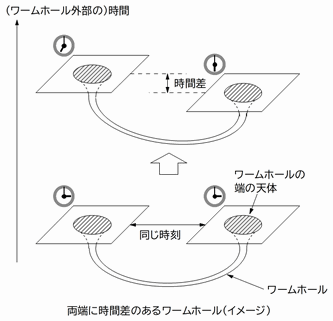
�@�\�[���̋c�_�ɑ��ẮA���낢��Ȕ��_������܂��B(1)�������������I�ȃ��[���z�[���͎��݂��Ȃ��A(2)�ʎq��炬�Ő������ɏ����[���z�[�������剻����Ƃ��Ă��A���I�Ȃقǔ���ȃG�l���M�[���K�v�ɂȂ�A(3)���Ƃ����剻�ł����Ƃ��Ă��A�����ɑ��݂��������Ȃ��G�L�]�`�b�N�����Ŏx���Ȃ���Έ�u�ʼn��Ă��܂��A(4)�G�L�]�`�b�N�����ʼn��Ȃ��悤�ɂ��Ă��A�������ʂ蔲���邱�Ƃ͕s�\�A(5)������ʂ蔲��������ƁA�ʎq���x���܂Ńo���o���ɔj��Ă��܂�---�ȂǂȂǁB�������A�ǂ̔��_������I�ł͂Ȃ��A�u�����I�Ɂi����Ɂj�s�\�v�Əؖ����ꂽ�킯�ł͂���܂���B
�@�����Ƃ��A�����I�ɕs�\�łȂ��ɂ��Ă��A�l�Ԃ����̂͂ǂ��l���Ă������ł��B�l�Ԃ����Ȃ����̂ɂ��ċc�_����Ƃ́A�����w�҂͉��Ė��ʂȂ��Ƃ�����̂��Ǝv����������܂��A����͗��_�����w�̍����Ɋւ����Ȃ̂ł��B���[���z�[�����g���ĉߋ��ɖ߂邱�Ƃ������I�ɉ\�Ȃ�A�^�C���p���h�N�X��r�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B����́A�w���@�ɂ���Ă��������̉��肪���ł���A�܂�A��ʑ��Θ_�ɂ͌��ׂ����邱�Ƃ̏ؖ��ɂȂ邩������܂���B�����炱���A�z�[�L���O���͂��߃g�b�v�N���X�̕����w�҂��^���ɋc�_���Ă���̂ł��B
�@���łɌ����Ă����ƁA�ʎq�R���s���[�^�̃A���S���Y���Œm����h�C�b�`�����A�ʎq�͊w�̑����E���߂Ɋ�Â��ƃp���h�N�X�͉���ł���Ƙ_���Ă��܂��BSF�ɂ́A���̋c�_�𗘗p������i������������܂����A���܂�ɓ˔�Ȏ咣�Ȃ̂ŁA�{�C�Ō������Ă��镨���w�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@
�u3�����g�[���X�\���ɂ��F���̗L���_�͊Ԉ���Ă���v�Ƃ����`���b�gGPT�̉��A�����w�̐��ƂƂ��Ăǂ����f���܂����H�@���̂����́A���L�̒ʂ�ł��i�ȗ��⏇�Ԃ̓���ւ�������܂��j�B�y���㕨���z
���R�����g�[���X�\���͕����I�ɂ͌����ɂ��肦�Ȃ��̂ł���A���������āA�R�����g�[���X�\���ɂ��F���̗L���_�͌��ł͂Ȃ��ł��傤���H
���m�`���b�gGPT�n�͂��A���̒ʂ�ł��B�R�����g�[���X�\���͐��w�I�ɂ͉\�ł����A�����I�ɂ͌������E�ɑ��݂�������̂ł͂���܂���B
���������āA�R�����g�[���X�\���ɂ��F���̗L���_�͕����I�ɂ͌��ł���ƌ����܂��B
���m�F�ł����A�������E�ɂ����Ċ��S�ȂR�����g�[���X�\�������݂��邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł��ˁB
���m�`���b�gGPT�n�͂��A���̒ʂ�ł��B�������E�ɂ����Ċ��S��3�����g�[���X�\�������݂��邱�Ƃ͕����I�ɕs�\�ł��邽�߁A�����I�ɂ͂��肦�܂���B
�������A���w�I�ɂ�3�����g�[���X�\�������݂��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���A���w�I�ȊT�O�Ƃ��ėL�p�ł��邽�߁A�Ȋw��Z�p�̕���ɂ����ĉ��p����邱�Ƃ�����܂��B
���Ȃ��A�������E�ɂ����ĂR�����g�[���X�\�������݂��邱�Ƃ͕����I�ɕs�\�Ȃ̂ł����H
���m�`���b�gGPT�n�������E�ɂ�����3�����g�[���X�\�������݂��邱�Ƃ��s�\�ł��闝�R�́A�w�I�Ȑ����Ɋւ��镨���I�Ȑ����ɂ���܂��B
�Ⴆ�A3�����g�[���X�\���́A�����ƊO������ʂł����A�Ȃ����Ă���悤�Ȍ`��������܂��B
����́A���̂̕\�ʂ��A���I�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ����G�C�u���n���E���[���̒藝�ɔ����邽�߁A�����I�Ȑ���ɂ������s�\�ł��B
�܂��A3�����g�[���X�\���́A�v�ʓI�����Ɋւ��Ă���������Ă��܂��B�Ⴆ�A3�����g�[���X�\���́A�\�ʐς�̐ς��L���łȂ��A������ɂȂ��Ă��܂��܂��B����́A�����I�Ȍ����ɂ����Ă͕s�\�ł��邽�߁A3�����g�[���X�\�������S�ɍČ����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�����̗��R����A3�����g�[���X�\���͕����I�Ȑ����ɂ������s�\�ł���A���w�I�ȊT�O�Ƃ��Ă̂ݑ��݂��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����Șb�A�`���b�gGPT�����������Ă���̂��A�����ς�킩��܂���B�����A�܂������̃f�^�������Ǝv���܂��B
�@�`���b�gGPT�͐����`�h�i�l�H�m�\�j�ȂǂƌĂ�܂����A���ۂɂ́A�m�\�͒�����قǂ��Ȃ��A���╶�ɂ�����Ɠ������̂��l�b�g��̖c��ȕ����̒�����T���o���A���̎��ӂ̌����m�����f������ɂȂ��ĉ��Ă��邾���ł��B���������āA(1)���x�ɐ��I�ȓ��e�A(2)���܂�L���łȂ��ŗL�����A(3)�������N�̏o����---�Ȃǂɂ��Ď��₷��ƁA�K�ɉ��������������������Ȃ����߁A�����Ⴂ�̓������������ł��B
�@�̓r���Ɂu3�����g�[���X�\���́A�����ƊO������ʂł����A�Ȃ����Ă���v�Ƃ�������������܂����A����̓g�[���X�ł͂Ȃ��u�N���C���̚�v�̐����ŁA�����Ȃ�A�m���Ɂu�����I�Ȑ���ɂ������s�\�v�ł��B�������A�����ɂ���u�G�C�u���n���E���[���̒藝�v�ɂ��ẮA�Ǖ��ɂ��Ēm��܂���B�\���͊w�Ŏg����u���[���̒藝�v�i�N���X�`�����E���[���������藝�j�Ȃ�킩��܂����A�u�G�C�u���n���v�Ƃ͉��ł��傤�B
�@�܂��A�u3�����g�[���X�\���́A�\�ʐς�̐ς��c������v�Ƃ���܂����A�g�[���X�Ȃ�ΗL���ɂȂ�͂��ł��B�`���b�gGPT���c�_���Ă���R�����g�[���X�́A�L���F���̃��f���Ƃ��Ē�Ă��ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����̉F����ԓ����ɑ��݂���R�����\���̂̂��Ƃ��Ǝv���܂����A�������߂��Ă��A���w�I�ɂ͊Ԉ�������e�ł��B
�@�`���b�gGPT�̊�ȉ��痣��āA�F�����f���̈�ʘ_�����b�����܂��傤�B
�@�����̏Z�މF�����L�����������A���݂̊ϑ��f�[�^����m��I�Ȃ��Ƃ͌����܂���B�f�[�^�ɂ��A�ϑ��\�Ȕ͈͂ŁA�F����Ԃ́s�قڊ��S�ȁt���[�N���b�h��Ԃł���A�s�قڊ��S�Ɂt��l�i�ǂ̏ꏊ�������j�������i�ǂ̕��������Ă������j�ł��B�������A�r�b�O�o���ȑO�ɁA�C���t���[�V�����ƌĂ��ߒ��ʼnF��������߂ċ���ɖc�������ƍl����A�S�̍\�����ǂ�Ȃ��̂ł����Ă��A�ϑ��ł���͈͓��Łs�قڊ��S�Ɂt���[�N���b�h�I����l�����ł��邱�Ƃ͐����ł��܂��B�ϑ��f�[�^�Ɂs�قځt�Ƃ������ۂ��t���ȏ�A�F���S�̂̊w�I�\���ɂ��Č��_�͏o���Ȃ��Ƃ����̂�����ł��B
�@�����A�F���S�̂��s���S�Ɂt���[�N���b�h�I�Ȃ�A�S�̍\���̌��͂������ɍi���܂��B�\���Ƃ��ẮA(1)�F���S�̂������̃��[�N���b�h��ԁA(2)��������ɂ͗L�������ʂ̕����ɂ͖����̃V�����_�[�A(3)�ǂ̕����ɂ��L���̃g�[���X�i���m�Ɍ����u���R�g�[���X�v�j---�Ȃǂ�����܂��B
�@��p���ɕ`���ꂽ�}�`�́A�\�ʂɉ����ĎO�p�`�̓��p���v��Ƙa��180�x�ɂȂ�ȂǁA�Q�������[�N���b�h�w�̖@���ɏ]���Ă���A�\�ʂ���������Ȃ�A��p����2�������[�N���b�h�I���ƌ����܂��B���������āA��p�����N���N���Ɗۂ߂��Ƃ��̕\�ʂ��A2�������[�N���b�h�I�ł��B���̂Ƃ��A��p���\�ʂ͊ۂ߂������ɗL���ł����A����ɐ����ȕ����ɂ͖����ɐL�����Ƃ��ł��܂��B���̂悤�ȋ�Ԃ��A��������ɂ͗L���i�����I�j�ŕʂ̕����ɂ͖����̃V�����_�[�ł��B
�@�����̋�ԓ����ŁA�N���N���ۂ߂���p���̗��[���Ȃ��ɂ́A��p�����I�ɐL�k������i���邢�́A�j�����肵�ē��ٓ_�����j��������܂���B�������A���w�I�ɂ́A�L�k�������Ɋۂ߂���p���̗��[���Ȃ����w�I�\�����l���邱�Ƃ��\�ł��B���ꂪ�A�Ǐ��I�ɂ͂ǂ��������������[�N���b�h�I�Ȃ̂ɁA�S�̂̑̐ς��L���ɂȂ�i���R�j�g�[���X�ł��B�F���S�̂��i��p���\�ʂ̂悤�ȂQ�����ł͂Ȃ��j�R�����g�[���X�ł���\���́A�ے肳��Ă��܂���B
�@���Ȃ݂ɁA�N���N���ۂ߂���p���̈���̒[���A�����ƊO�����t�ɂȂ�悤�ɗ��Ԃ��A���̏�Ԃł�������̒[�ɂȂ����̂��A�N���C���̚�ł��B�R�������[�N���b�h��ԓ����ŃN���C���̚����낤�Ƃ���ƁA�ǂ����ʼn�p�����������Ă��܂��̂ŁA�����ɃN���C���̚����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�F�����R�����g�[���X�Ȃ�A�Ⴆ�A�V�̖k�ɕ����ɂ���̂Ɠ����V�̂��A��ɕ����Ɂi���Α����猩�����̂Ƃ��āj�ϑ������\��������܂��B�������A�����ɂ��������V�̂́i�m���Ȏ���Ƃ��Ắj�������Ă��܂���B�F���S�̂����ۂɃg�[���X�Ȃ̂�������܂��A���̂Ƃ���A���������咣�����邾���̍����͂Ȃ��̂ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@��ʌ����̉�����ł͂��܂�ڂ����������Ă��܂��A����̈�ɃG�l���M�[�������߂��Ă���Ƃ��A�s���̗̈悪�Î~���Č�������W�n�i�Î~���W�n�j�t����́A�G�l���M�[�ɓ������������ʂ������Ƃ����Θ_���g���ē����܂��B
�@�̈悪�Î~���Ă��Ȃ��ꍇ�A�G�l���M�[�Ɗ������ʂ̓C�R�[���Ō��ꂸ�A�u�G�l���M�[�̂Q�悪�A���ʂ̂Q��Ɖ^���ʂ̂Q��̘a�ɓ������v�Ƃ����W�ɂȂ�܂��i��̃G�l���M�[�͂Ȃ����̂Ƃ���j�B
�u�G�l���M�[�́A���ʂƉ^���ʂɊ���U���Ă���v�ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��܂��B
�@�������ʂ͓������ɂ�����\�������ʂȂ̂ŁA�������ʂ��[���̕��̂́A��ɓ��������ĐÎ~�������܂���B
���̂��߁A�G�l���M�[�Ɗ������ʂ��������Ȃ�s�Î~���W�n�t�͑��݂��܂���B
����O���[�I���́A�������ʃ[���̗��q�ł���A�G�l���M�[�͉^���ʂƓ������Ȃ�܂��B
�@����ł́A�Ȃ����q��O���[�I���́i�����j���ʂ��[���Ȃ̂��Ƃ����ƁA����́A�Q�[�W�Ώ̐��ƌĂ�闝�_�I�����̋A���Ȃ̂ł��B
�Q�[�W�Ώ̐��������ɐ��藧�Ȃ�A�W���I�ȏ�̗ʎq�_�ł͎��ʂ��[���łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��ؖ��ł��܂��B
���q�̎��ʂ��[���Ƃ����̂́A�ϑ������ƌ��������A���_�I�A���ƌ��Ȃ��̂��K�ł��傤�B
�@���̐��E�ɃQ�[�W�Ώ̐����Ȃ����݂���̂��A�������̉�������Ă���Ă��܂����A�܂����_�͏o�Ă��܂���B
�������A�Q�[�W�Ώ̐��̑��ݎ��̂��^�������w�҂́i�قƂ�ǁj���܂���B
�Q�[�W�Ώ̐����Ȃ��ƁA�d�ׂ��ۑ����闝�R�������ł����A�f���q�����œd�ׂ̑��a�����ɕۂ���邱�Ƃ��ۏ���Ȃ�����ł��B
�Q�[�W�Ώ̐��̑��݂�F�߂Ȃ���A���q���킸���Ȏ��ʂ����Ƃ�����E�W���I���_���咣���镨���w�҂����܂����A�w�E�Ŏ�����Ă͂��܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@
�i�O��̉ɑ���lj�����ł��j
�@��b�I�Ȃ��Ƃŋ��k�Ȃ̂ł����AWheeler�̒x���I�������ɂ�����2�ڂ̃r�[���X�v���b�^�����O�����ꍇ���ǂ̂悤�ɉ��߂����낵���̂ł��傤���B
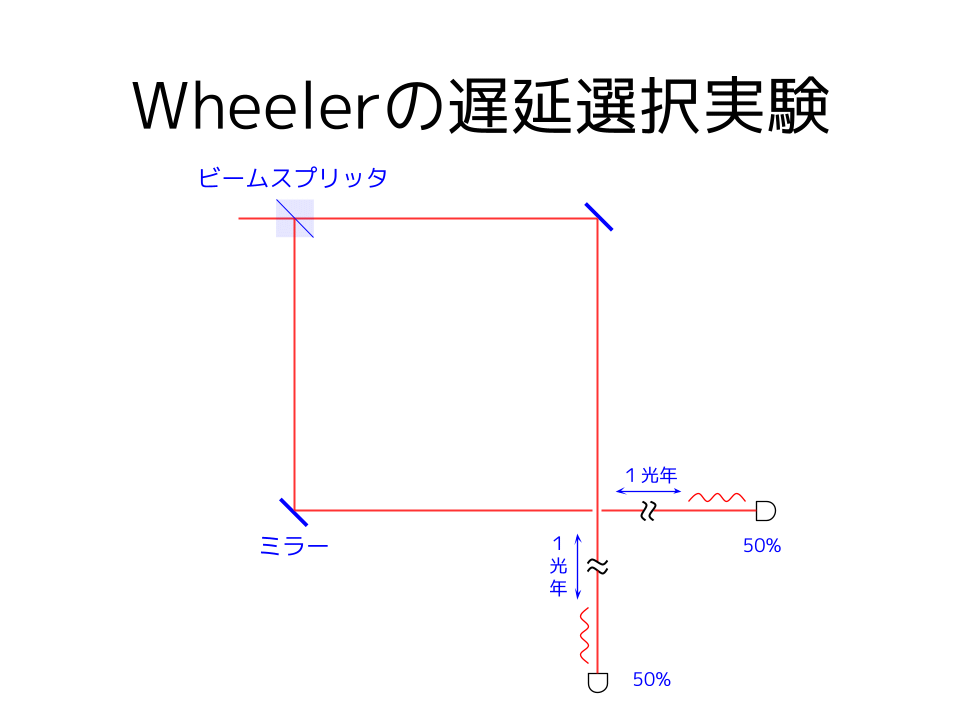
�@�搶�̒������q�ǂ������܂����B���͗��q�ł͂Ȃ��G�l���M�[�ʎq�̔g����Ԃ�`�d������̂ƃC���[�W���Ă���܂����A�ǂ����Ă��Z���T�[�ɓ��B�����u�Ԃɂ��ăC���[�W���邱�Ƃ��ł��܂���B�Y�t�摜�̂悤�Ɍ��H���������N������Z���T�[���m���F���K�͂ŗ���Ă����Ƃ��Ă��A�����̃Z���T�[�œ����Ɍ��q�����o���邱�Ƃ͂Ȃ��A�ǂ��炩����Ō��q�����o���ꂽ�瑼���ł͌����Č��q�����o���Ȃ��Ƃ����͕̂ς��Ȃ��͂��ł��B
�@�r�[���X�v���b�^�ɂ���ē�����50%�E50%�̋��x�ɕ�����ꂽ�g���A����̃Z���T�[�ł͌��q�ƂȂ�A�����̃Z���T�[�ł͔g���Ռ`�����������ĂȂ��Ȃ�̂������ł��Ȃ��̂ł��B
�@�搶�̋�ʂ�A�u���鑪�葕�u�Ō��q�����o���ꂽ����ƌ����āA���̏u�Ԃɉ������ꂽ�̈�ɂ܂ŗ��q�����e�����y�ڂ����Ƃ͂���܂���v�Ƃ���Ƃ���͂ǂ����߂�����ǂ��̂ł��傤���H�y���㕨���z

�@��̗ʎq�_�ɂ����āA�f���q�Ƃ́A����̒l�����G�l���M�[�ʎq���`�����ꂽ�i�قځj����ȏ�Ԃ��Ӗ����܂��B�������A�P�̌Ǘ������f���q�𐔎��ŋL�q����͓̂���A�`���I�ɓ����g�`�������ɑ����g�Ƃ��ĕ\�L���A���̑̐ϓ����ɑ��݂���f���q�����P�ɂȂ�悤�ɋK�i������̂���ʓI�ł��i�Ǘ��g��\���Q�ߏ�Ԃ��l����ꍇ������܂��j�B
�@�������������ɂ�����Ȃ��̂́A�������R�x�̗ʎq�_�����ɖ��ȑ㕨������ł��B�f���q�����ł́A��͎������u�Ƒ��ݍ�p���Ȃ���A���ɗ��q�I�ȐU�镑�������܂����A���̂Ƃ��A�ꂪ���ԂƂƂ��ɂǂ̂悤�ɕϓ����邩���v�Z����͕̂s�\�ł��B������n�_�ŏ�̒l�͗ʎq�_�I�ȗh�炬�������A�P���Ȕ����������ɂ͏]��Ȃ�����ł��B���̂��߁A�����g�`�������ɑ����g���`���I�ɍl���āA����̌��ۂ����N����m�����v�Z���邵������܂���B
�@����ł��A�����̑f���q���֗^����U�������Ȃ�A�`���_�ʼn����ʂ����Ƃ��ł��܂��B�������A�P�̑f���q�����o���ꂽ�ƌ��Ȃ����قǃG�l���M�[���x��Ⴍ���������ł́A�`���_�Ɋ�Â��C���[�W�͐��藧���܂���B���ہA�G�l���M�[���x���Ⴂ�����̏ꍇ�A�f�[�^�ɂ��Ȃ�̃���������A���_�ƌ��т���ɂ́A�m�C�Y���������߂̃f�[�^�������K�v�ɂȂ�܂��B
�@�i�O���Q&A�Ŏ��グ���j�X�J���[��̒x���I�������ł́A�ŏ���BBO�łQ�̌��q�������A���̂����̈�����i�̐}�ɂ�����D
0�Łj�ϑ��������ʂƂ̑��ւ��Ƃ邱�ƂŁA�iD
1�`D
4�œ�����f�[�^�́j�I�ʂ��s���Ă��܂��i�ڂ��������́A���_����ǂ�ł��������j�B���������I�ʂ��s���Ă��A�i�O���t�Ɏ������悤�Ɂj�����f�[�^�ɂ͑傫�ȃm�C�Y���܂܂�Ă���A���Ȃ̎ア�Ƃ���ł��ϑ��������q�����[���ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B�܂�A�u����Ō��q���ϑ������A�����ł͌����Ċϑ�����Ȃ��v�Ƃ������z�I�Ȓx���I���������s���̂́A�����ɂ͓���ƌ����܂��B
�@�r�[���X�v���b�^�ɂ���Č�������ꍇ�A�G�l���M�[���x���Ⴂ�ƁA�U�����������Q�̔g�ɕ������̂ł͂Ȃ��A�ɂ���ĕs���Ȕg�ɕ������͂��ł��B���������g�����q�J�E���^�[�̂悤�ȑ��u�Ƃǂ�ȑ��ݍ�p�����邩�A���_�I�ɋL�q���邱�Ƃ́i���R�x���������āj�ł��܂��A���������̈�������Ō��q���ϑ������m���������Ȃ�Ɛ�������܂��B
�@���q�̓G�l���M�[�ʎq���`�����ꂽ�����Ԃł����A���艻����Ȃ������ꍇ�͔g������Ċg�U���A����Ή_�U�������Ă��܂��܂��B�r�[���X�v���b�^�ŕ�������Ŋϑ����ꂽ�u�ԂɁA�����̔g��������̂ł͂���܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@
����́A�u�}�̂悤�Ȍ��w�n�Ŏ������s�����ۂɂǂ̂悤�Ȍ��ʂ������邩�H�v�ł��B�x���I��ʎq�����S�������Ȃǂɗp�����郁�^�z�E�_�o���E�������iBBO�j�ƁAWheeler�̒x���I�������̌��w�n��g�ݍ��킹���悤�Ȏ������u�ƂȂ��Ă��܂��B
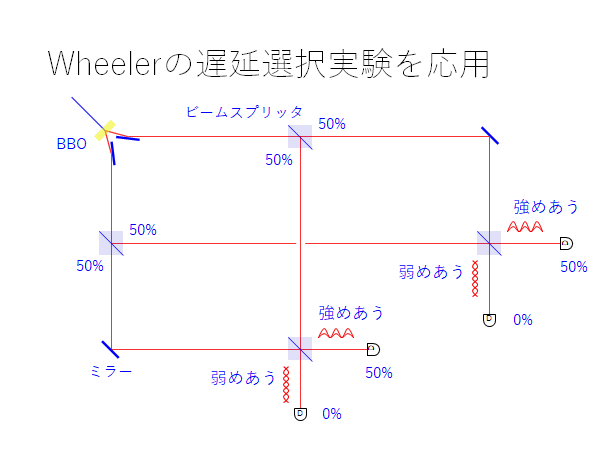
�@���̂悤�ɑ��u��g�ނƁA���߂����悤�Ɍ��H��ݒ肵���Z���T�[�ł̂��q2�𗼑��Ō��݂ɁA���邢�͌��q1���𗼑��œ����Ɂi�H�j���o����͂��ł��B����ŁA��߂����悤�Ɍ��H��ݒ肵���Z���T�[�ł͈�،��q�����o���Ȃ��͂��ł��B
�@�����ʼn����̃r�[���X�v���b�^�����O���Ƃǂ��Ȃ�ł��傤�H
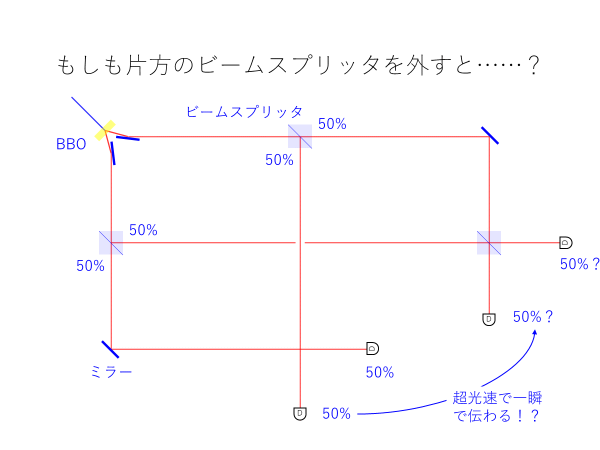
�@�r���̃r�[���X�v���b�^�œ��߁^���˂���m����50%�Ȃ̂ŁA���q2�����̃Z���T�[�Q�ɗ����Ƃ�����^�����Ƃ����Ȃ����Ƃ��A�ǂ��炩�Е��������Ȃ����Ƃ�����ł��傤�B�������A���͌��q�̕Е����������Č��o���ꂽ�ꍇ�ł��B���̏ꍇ�A�g���̎��k�ɂ���Ĉ�u�Ŋ����ׂ��������E�̃Z���T�[�S�̌��H�ォ����ł��邽�߁A��߂����Č��o����Ȃ������Z���T�[��50%�̊m���Ō��q�����o�����悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@���Ȃ킿�A���̃Z���T�[�Q�̃r�[���X�v���b�^�L�^���ɂ���ĉE�̃Z���T�[�Q�̌��q�����o�����^����Ȃ��𐧌䂵�܂��B������f�W�^���M���ł���0�^1�ɑΉ������邱�ƂŁA�������ʐM���\�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���܂����B
�@�����Ȃ�ɗގ��̃A�C�f�B�A�E�������Ȃ����ƒ��ׂĂ͌����̂ł�������炵�����̂͌����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
�@�B��
�������̎���/������̓��e�ɋ߂��Ǝv���܂����B�����ŎQ�l�{�Ƃ��ċ������Ă����u�ʎq�̂���݂����F���v���{�����Ă݂��̂ł����A�搶��web�y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă������w�n�Ƃ����ԈႢ�{�������u���ǂ̂悤�Ȍ��ʂƂȂ邩�͂����肵�����Ƃ͕�����܂���ł����B�y���㕨���z

�@�ʎq�͊w�̋c�_����Ƃ��ɔƂ������Ȍ�肪�A�d�q����q���A���ɔg�Ƃ��Ď��ɗ��q�Ƃ��Ĉ������Ƃł��B���ẮA�ʎq�͊w�Ƃ����Θ_�I�ߎ��Ɋ�Â����s���S�ȗ��_�����Ȃ��A���_�I�ȗ\����g���`���◱�q�`����p���ĉ��߂��Ă������߁A�����̍��������ݏo����܂����B�������A1970�N��Ɂi���̔����I�O�ɒ���Ă����j�u��̗ʎq�_�v�̐��������F�߂���ƁA�������������̎�͌�������̂��̂ɂ����Ȃ��ƍl����l�������Ȃ�܂����i���ׂĂ̕����w�҂��[��������ł͂���܂��j�B��̗ʎq�_�ɂ͗��q�Ƃ����T�O���܂܂�Ă��炸�A�g���ꌳ�_�ŋL�q����Ă��܂��B�d�q����q�͏�ɔg�ł���A�ɉ����āA�g�����q�̂悤�ɐU�镑�����Ƃ�����̂ł��B
�@����ɂ�������̏ꍇ�A�����`�d����ߒ��́A�d����̔g�����̂��̂��ƃC���[�W���Ă��܂��܂���B���̔g�����q�I�ɐU�镑���̂́A�דd���q�Ƒ��ݍ�p�������R�Ȕg�Ƃ��ē`����Ă����d���g���A�u�ԓI�ɃG�l���M�[�����Ƃ肷��ǖʂł��B���̂Ƃ��A���Ƃ肳���G�l���M�[�́A�ʎq�_�̖@���ɏ]���ăG�l���M�[�ʎq�ƂȂ�A�܂�ŗ��q�̂悤�ȉ�Ƃ��ēd���g���瑪�葕�u�ւƎn����܂��B���_�I�ɂ́A��̗ʎq�_�ɂ�����ۓ��_�ߎ��̍Œ�ŋL�q�����ߒ��ł���A���̏ꍇ�Ɍ����ė��q�I�ɂȂ�̂ł��B���������āA���鑪�葕�u�Ō��q�����o���ꂽ����ƌ����āA���̏u�Ԃɉ������ꂽ�̈�ɂ܂ŗ��q�����e�����y�ڂ����Ƃ͂���܂���B�}�̉����̃Z���T�[�Ō��q�����o���ꂽ�Ƃ��Ă��A�E���̃Z���T�[�ɂ����鑪�茋�ʂ͕����I�ȉe�����Ȃ��̂ł��B
�@���łɌ����Ă����ƁA�ʎq�_�Ō��q�̔g������g�����������Ƃ͂���܂���B��̗ʎq�_�ł́A���q�̈ʒu�̑���ɏ�̋��x���s�m�萫�W�����Ă���A��̋��x��ϐ��Ƃ���g��������`�����͂��ł����A���ۂɂ́A�v�Z�������ł��Ȃ��̂ŁA�g������g�����l����Ӗ�������܂���B
�@����ɂ�������́A�����ƉE���ɂ���Z���T�[���߂����āA���Ƃ��������ʐM���\���Ƃ��Ă��A�������ł��邱�Ƃ��m�F����͍̂���ł��B���̂��߁A����Ɠ��������͒N���s���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�����̃Z�b�g�A�b�v�́A1999�N�ɃX�J���[�炪��Ă����ʎq���������i����ɂ���x���I��ʎq�����S�������j�Ɗ�{�I�ɓ����Ȃ̂ŁA���̘_���iKim, Yoon-Ho; R. Yu; S.P. Kulik; Y.H. Shih; Marlan O. Scully, Phys.Rev.Lett.84:1-5,2000; arXiv:quant-ph/9903047v1�j�����ɐ����������Ǝv���܂�
�@�X�J���[��̎����ł́A���[�U�[�r�[�����Q��BBO�ɏƎ˂��邱�ƂŁA�ʑ������߂ł���Q�̉��Ȍ���L1��L2�����܂��iL1��L2�͂��̉����ŗp����L���ł����A���͌��_���Ɠ����ł��j�B
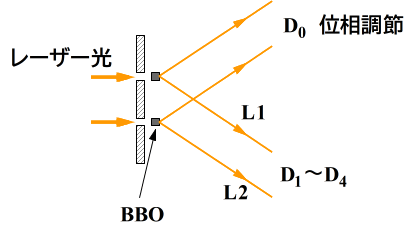
�@���̂Q�̌����̈ʑ����́ABBO�łQ�ɕ����ꂽ���̈���𑪒��D
0�Œ��ׂ邱�Ƃɂ��A�R���g���[���ł��܂��B�ǂ̂悤�ɃR���g���[�����邩�́A���_����ǂ�ł����������Ƃɂ��ďڂ��������͏ȗ����܂����A�ʒu�߂���D
0�łP���q�����肳���Ȃ�AD
1�`D
4�Ɏ���o�H�Ɂi�Q���q�ł͂Ȃ��j�P���q�i�ɑ�������ʎq�_�I�Ȕg���j�����荞�ƌ��Ȃ��܂��B���̂Ƃ��A�Q�̌���L1��L2�́AD
0�̈ʒu�ɉ������ʑ����������Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���╶�ɂ���悤�ȁu���q2�𗼑��Ō��݂Ɂv�Ƃ�����������s���̂́A���݂̎������x�ł͍���ł��B���茋�ʂ͏�ɑ傫�ȗh�炬���Ă���A���v�I�ȏ������s���āA�͂��߂ĈӖ��̂���f�[�^�ƂȂ�܂��B
�@��d�X���b�g�����ł́A��܂����������������Ċ��Ȃ����܂����A���̎����ł́A�r���Ƀr�[���X�v���b�^�[A��B��}�����āA���ꂼ��̉�܌�������ɂQ�ɕ������܂��B�X�J���[��́A�������������̈���̑g����������D
1��D
2�ő��肵�A�����̑g�́A���ꂼ��D
3��D
4�ŕʁX�ɑ��肵�Ă��܂��B���̃O���t�́A���ۂ̑��茋�ʂł��B�O���t�̉�����D
0�̈ʒu��\���Ă���AL1��L2�̈ʑ����ɑ������܂��B�r�[���X�v���b�^�[BS�ł̔��˂̍ۂɂQ�̌����̈ʑ���180�������̂ŁAD
1��D
2�Ɏ���o�H��Ώ̓I�ɂ��Ă����A����̎R�������̒J�̈ʒu�ɂȂ�A�Q�̑��茋�ʂ𑫂����킹��ƁA���Ȃ��������Ċ��炩�ȃJ�[�u�ɂȂ�܂��B���̂��Ƃ́A�r�[���X�v���b�^�[��}�����Ȃ���A���Ȃ̂Ȃ����ʂ������邱�Ƃ̌���ł��B
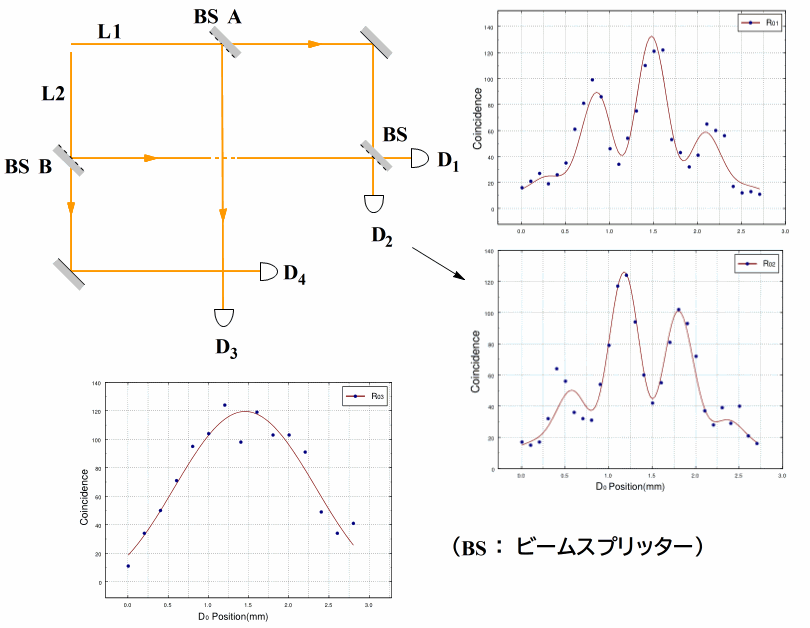
�@����̓��e���ĉ��߂���A�X�J���[��̎�����D
3��D
4�̎�O�Ƀr�[���X�v���b�^�[������ƁA����Ȃ������ꍇ�ɔ�ׂ�D
1��D
2�ł̑��茋�ʂ��ω�����̂ł͂Ȃ���---�ƂȂ�܂��B�������������͍s���Ă��܂��A����Ȃ������ꍇ�̑��茋�ʂ��A�Q�̌����ɂ��ÓT�I�Ȋ��Ȃƈ�v���Ă���̂ŁA�ω��͐����Ȃ��i���������āA�������ʐM�͍s���Ȃ��j�Ɨ\�z����̂��Ó��ł��傤�B
�@�uBBO����P�̌��q�����o����A�S�ʂ肠��o�H�̂ǂꂩ��ɐi������v�Ɖ��߂���ƁA���̎������ʂ͊�Ɋ������܂��B�������A�e�o�H��i�ނ͓̂d���g�i���m�Ɍ����A��̋��x�ɗʎq�_�I�ȕs�m�萫�����݂���d����̔g�j�ł���A�ŏI�I�ɑ��肳���i�K�ŁA�ʎq�_�̖@���ɏ]���ĂP�̌��q�ɑ�������G�l���M�[�����������ꂽ�ƍl����ƁA�s���ȓ_�͂���܂���B�X�J���[��́A�O���I�I�ȌÂ��ʎq�͊w�̔��z�Ɋ�Â��āA�u�o�H���m�肷��Ƃ��͗��q�I�A�m�肵�Ȃ��Ƃ��͔g���I�ɐU�镑���v�Ɖ��߂��ēǎ҂����Ɋ����܂����A����Ȗ�̂킩��Ȃ��c�_������K�v�͂Ȃ��̂ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�f�B���b�N�̗ʎq�����i�{�����������_���̌����W���������g���ĕ\�������j�������Ӗ����邩�ɂ��āA�����w�҂̈ӌ�����v���Ă���킯�ł͂���܂��A���́A�������ۂ̍���ɕ��ՓI�Ȕg�������邱�Ƃ̌��ꂾ�Ɖ��߂��Ă��܂��B�ȉ��A�������I�ȁi���������āA�����w�Ȃŕ������l�ȊO�ɂ͂�����Ƃ킩��ɂ����j���������܂��傤�B
�@��ʂɂQ�̕����ʂ�����ł���Ƃ́A���̂Q���݂��ɓƗ��ȕϐ��ł͂Ȃ��A�ˑ��W�ɂ��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�j���[�g���͊w�ł́A���q�̈ʒux�Ɖ^����p�i���ʁ~���x�j�͓Ɨ��ł���A���q���ǂ�Ȉʒu�ɂ��낤�Ƃ��A���̑��x�ɐ����͂Ȃ��C�ӂ̒l���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�ʎq�_�̏ꍇ�́A�ʒu�Ɖ^���ʂ͐[�����ݍ����Ă���A����ɒl�����߂��܂���B�^���ʂ����ʂƑ��x�̐ςŕ\���A���x���ʒu�̎��Ԕ����ŏ��������Ƃ͂����肷��悤�ɁA�ʒu�Ɖ^���ʂ�����Ȃ̂́A����u�Ԃ̈ʒu�Ƃ��̒���̈ʒu���Ɨ��łȂ����Ƃ��Ӗ����܂��B�܂�A�ʎq�_�I�ȑΏۂ́A�^��C�ӂ̑��x�Ŏ��R�ɔ�щ��闱�q�ł͂Ȃ��A��ԕω��ɋ�������������A���̂ł���ƍl������̂ł��B
�@��̓I�ɂǂ�Ȑ���ł��邩�́Apx-xp���������ɂȂ�Ƃ����������瓱����܂��B�Ⴆ�A���g�����̌𗬉�H�ɂ����ăR���f���T�[��R�C���̃C���s�[�_���X���������ɂȂ�̂́A�N�w�I�ɐ[���Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�d����d�������Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɐU�������邩��ł����A����Ɠ����悤�ɁA�ʎq�����Ɋ܂܂�鋕���P��i�́A�ʎq�_�I�Ȍ��ۂ������N�����̂��A�U�����鉽���ł��邱�Ƃ��������܂��B
�@�ʎq�_�̌v�Z�����Ă���ƁA
�@�@exp(iS/h)�@�iexp( )�͎w�����AS�͉�͗͊w�ň����Ƃ���́u��p�v�j
�Ƃ����t�@�N�^�[���p�ɂɓo�ꂵ�܂��B�o�H�ϕ��@�Ɋ�Â��莮�����s���ƁA���̃t�@�N�^�[�Ɋ܂܂�鋕���P��i���A�ʎq������i�ƌ��т����Ƃ��킩��܂��B
�@�ϐ����������̎w�����́A�ϐ��̑����ɔ����Ċ��l�����[�}���ʁi�������Ƌ����������Q�������ʁj�ɂ�����P�ʉ~������ł��B�ʎq�_�ł́A��ɕ��f�����Ƒg�ݍ��킹����������̂ŁA�I�C���[�̊W���F
�@�@exp(ix)=cos x + i sin x
���g���ĎO�p���ɒ����čl���邱�Ƃ��ł��܂��B���������āAexp(iS/h) �Ƃ����t�@�N�^�[�́A�u�v�����N�萔h��P�ʂƂ��ĕ\������p���ʑ��ɑ�������U�����q�v�Ɖ��߂ł��܂��B�ʎq���ʂɌ�����g���I�ȐU�镑���́A���̐U�����q�������炵�܂��B�f�B���b�N�̗ʎq�������A�������ۂ̍���ɂ���g�����ƌ��т����Ƃ̏؍��ƌ�����ł��傤�B
�@���ʎq�_�ɂ�����A�C���V���^�C���̊W���́A���q�̃G�l���M�[E��h�ˁi�ˁF�U�����j�ɓ������Ƃ������̂ł����A���̎��Ɏ������悤�ɁA�v�����N�萔h�́A�ʎq�_�ɂ����闱�q�`���i�Ⴆ�A���q�̃G�l���M�[E�j�Ɣg���`���i�g�̐U�����ˁj�����т���ʂł��Bh��P�ʂƂ��č�p��\���Ƃ́A���q�`���Ɣg���`�����L�q����̂ɁA�����P�ʌn���g�����Ƃɑ������܂��B���̒P�ʌn�ł́A�G�l���M�[�����Ԃ̋t���̒P�ʁi���b���̂P�Ƃ����悤�ȁj�������ƂɂȂ�܂��B��͗͊w�ɂ��ƁA�G�l���M�[�Ƃ́u���Ԃ��o�߂��Ă������@�����ω����Ȃ��v�Ƃ����������瓱�����ۑ��ʂł���A��Ɏ��ԂƑɂȂ��Č����ʂȂ̂ŁA�G�l���M�[�̒P�ʂ����Ԃ̋t���ɂȂ邱�Ƃ́A���͂ƂĂ����R�Ȃ̂ł��B
�@����̉ɂȂ��Ă��Ȃ���������܂��A�f�B���b�N�̗ʎq�����Ɋւ���i���̎��ȗ��́j���߂ƁA�v�����N�萔�́i�����̕����w�҂����ӂ���ł��낤�j�Ӗ��́A�ȏ�̂悤�Ȃ��̂ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@��ʑ��Θ_�ɂ��A����̓S���̂悤�ɐL�яk�݂�����̂ł���A�e�n�_�ɂ�����L�k�̓x������\���̂��A�v�ʃe���\���Ƃ��d�͏�ƌĂ���gij�ł��i�����ł́A�S���e���\���̓Y������ij�Ə������Ƃɂ��܂��j�Bgij�͎��ꏊ�ɂ���Ăǂ̂悤�ɐL�яk�݂��邩��\���ʂȂ̂ŁA�i���ٓ_�ȊO�ł́j�A���I�ɕω����܂��B
�@�������ɔG���Ƒ@�ۂ̊Ԋu�������I�ɕς�邽�߁A���ʂ����R�ł����Ȃ��Ȃ��Ĕg�ł��܂����A����Ɠ������A����̐L�яk�݂�\��gij���ꏊ�ɂ���ĈقȂ�ꍇ�ɂ́A���p�Ȃ��܂��B���̂悤�ɁA�p�Ȃ̓x������\�����b�`�e���\���́A�ꏊ�ɂ��gij�̈Ⴂ�ɗR������̂ŁAgij�̔����i�Q�K�����܂Łj���܂ޗʂƂ��Ē�`����܂��B���̂��߁Agij���A���I�ł����Ă��A�����l�ɔ�т�����ƁA���b�`�e���\���͕s�A���ɂȂ�܂��B
�@��ʑ��Θ_�̊�b�������ł���A�C���V���^�C���������ɂ��A���b�`�e���\���́A�G�l���M�[�^���ʃe���\���ƌ��т����A���ʃG�l���M�[���x�z�I�ȓV�̕����w�ł́A���ʖ��x�ƈ��͂����b�`�e���\�������肵�܂��B��Θf���̂悤�ɁA�����ł͖��x���L���A�O���ł̓[���Ȃ�A���b�`�e���\���͕s�A���ɂȂ�܂��B�v�ʃe���\��gij�͘A���I�ɕω�������̂́A���x�ɔ�т����邽�߁Agij�̔������s�A���ɕω����邩��ł��B
�@���Ώ̂Ȋ�Θf���̏ꍇ�A�A�C���V���^�C���������̉��ƂȂ�v�ʃe���\��gij�́A�f���O���ł́i���b�`�e���\�����[���ɂȂ�j�V�����@���c�V���g�̊O�����A�f�������ł͓������Ƃ����Q��ނ̉��ŋL�q����܂��Bgij�ɂ́A�f���\�ʂŘA�����Ƃ������E�������ۂ����A�ϕ��萔������̒l�Ɍ��܂�܂����A���b�`�e���\���ɂ�����������͂Ȃ��A�s�A���ɂȂ�܂��i�V�����@���c�V���g�̊O�����ɂ��ẮA�w���S�ƏK���ΐ����_�x��9.4�Ő������܂������A�������͓���̂ŏȗ����܂����j�B
�@�P����K�X�f���̂悤�ɁA���x�∳�͂��A���I�ɕω�����Ȃ�A���b�`�e���\�����A���ʂƂ��Ē�`�ł��܂��B�܂��A��Θf���ł����Ă��A�ڍׂɌ���Ζ��x�E���͂Ƃ��A���I�ɕω����Ă���Ɖ��肷��A���b�`�e���\�����i�}���ɕω�������̂́j�A���ɂȂ�܂��B
�y��L�z�@�lj����₪�����̂ŁA�����ɋL���Ă����܂��i������Ɖł��Ă��܂��j�B
�m����n�A�C���V���^�C���������̐��`���f����Rij���v�Z����ƁA���ʁ��O�̓V�̊O���ɂ����āARij���O�ƂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����A����͋ߎ��v�Z�ł��邽�߂ł��傤���B
�m�n�u���`���f���v�Ƃ́A��̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B���_�i����M�j�̎��͂ɂ�����i�ÓI�E���Ώ̂ȁj�v�ʃe���\�����j���[�g���̏d�͗��_�ɑ�������ߎ��ŕ\���ƁAg00�i����-���Ԑ����j�́A���_����̋���R���g���āA
�@g00��-1+2GM/Rc^2
�ƂȂ�܂��iG�F���L���͒萔�Ac�F�����j�B
�@���̋ߎ��ł̃A�C���V���^�C���������́Ag00�Ƀ��v���V�A�����i��ԍ��Wx,y,z���ꂼ��̂Q�K�����̘a����鉉�Z�q�j����p���������̂ɂȂ�܂��B���������̕������w�̎Q�l���ɏ����Ă���悤�ɁA1/R�Ƀ��v���V�A������p������ƁA���_�ȊO�ł̓[���ɂȂ�A���_�ł͔��U���܂��i�f���^���ɂȂ�܂��j�B�u���_�ȊO�Ń[���ɂȂ�v�Ƃ̓A�C���V���^�C���e���\�����[���ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ����A�������烊�b�`�e���\�����[���ɂȂ邱�Ƃ��킩��܂��B
�m����n�ȗ��e���\�����k�ē�����Rij�͓��R����̋ȗ��i�c�� or �p�Ȃ̒��x�j�f����ʂł����A�V�̂̎��ʂɂ���Ă��̊O���ɘc�݂����݂���i����ŏd�͂�������j�����ɂ����āARij���O�ƂȂ邱�Ƃ��C���[�W�ł��܂���B
�m�n���b�`�e���\���������Ӗ����邩�́A���͂��Ȃ������ł��B����̘c�݂�p�Ȃ��̂��̂ł͂Ȃ��A�ȗ��e���\����g�ݍ��킹�ē�����ʂȂ̂ł����A��̓I�ɉ����Ӗ����邩�Ɩ����ƁA�ԓ��ɋ����܂��B��ʑ��Θ_���c�_����ۂɁA�֗��Ȃ̂ł悭�g���钆�ԓI�ȕϐ��Ƃ����A�����l������܂���B�V�����@���c�V���g�̊O�����ŁA�Ȃ����b�`�e���\�����[���ɂȂ�̂��A�����ł͂Ȃ��C���[�W���g���Đ����ł���l������A�����Ăق������̂ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�f���q�̑��ݍ�p�����q�̌����ߒ��Ƃ��ĕ\�����̂́A�����ꕔ�̌��ۂɌ����܂��B���w�����̂悤�ɁA���͂̌��q���d�q�ɑ��Ď����I�ɍ�p���y�ڂ�������P�[�X�ł́A���q�̌������l���Ă��ߎ��ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�ʏ�́A�N�[�����|�e���V������p�����Θ_�I�Ȍv�Z�������s���܂��B
�@���q�̌����ɂ���đf���q�̑��ݍ�p���L�q�ł���̂́A�u�ۓ��_�v�ƌĂ��v�Z��@���ʗp����P�[�X�ł��B�ۓ��_�Ƃ́A�^�����������u�O������̍�p�v�Ɓu��p�̂Ȃ����R�^���v�ɕ������A���R�^�����Ă���ΏۂɊO������̍�p���J��Ԃ��u�ԓI�ɉ����Ɖ��肷��v�Z�@�ŁA���Θ_�I�ʎq�_�i�f���q�_�j�̏ꍇ�́A�f���q���^�����R�ɔ�щ��r���ŁA���X���q�⒆�Ԏq�Ȃǂ��z���E���o����ƌ��Ȃ����Ƃɑ������܂��B���̌v�Z�ߒ���}�ŕ\�������̂��A�L���ȁu�t�@�C���}���}�v�ł��B�Ⴆ�A�Ǝ˂��ꂽ�w�����z�����Ĕ��������d�q���U�����̏������w������˂���Ƃ����u�R���v�g���U���v�́A���̃t�@�C���}���}�i�}�P�j�ŕ\����܂��B
�@�������A�ۓ��_�͂����܂ŋߎ��I�Ȍv�Z�@�ł�������܂���B�t�@�C���}���}�����܂�ɂ킩��₷���̂ŁA�܂�Ő}�Ɏ����ꂽ�ʂ�ɑf���q����ь����Ă���ƌ������l�����܂����A�����ł͂���܂���B�ۓ��_�v�Z�Ɍ���鐔����}�ŕ\�����̂��t�@�C���}���}�ł���A�����̕����I�v���Z�X�Ƃ͈قȂ�܂��B
�@�ۓ��_�v�Z���ǂ��ߎ��ɂȂ�̂́A�R���v�g���ߒ���x�[�^����ȂǁA����̉ߒ��Ɍ����܂��B�d���I�ȑ��ݍ�p�̏ꍇ�A�ۓ��_�v�Z�́A���o�E�z���������q�̌����P�C�Q�C�c�ƂȂ鍀�����ׂĉ����鋉���̌`�ɂȂ�A���̋����̎��������ǂ��ꍇ�ɂ����ߎ��Ƃ��ė��p�ł��܂��B�R���v�g���U���̂悤�ɐ^�łQ�̑f���q���K�c���ƂԂ���P�[�X�ł́A�����̍������͒l���������Ȃ�A�����Ƃ���ɑ�������i���Ԃ̌��q���P�`�Q�j�����ŋߎ��Ƃ��Ďg�����ɂȂ�܂��B
�@�������A�����̑f���q�����ł́A�ۓ��_�v�Z�͑S���ߎ��ɂȂ�܂���B���ɁA�j�͂�q�b�O�X�@�\�i�d�q�Ȃǂ����ʂ��l�����郁�J�j�Y���j�Ɋւ��āA�ۓ��_�͖��͂ł��B�u�j�͂͒��Ԏq�̌����ɂ���Đ�����v�Ɛ��������ꍇ������܂����A����́g��g�h�ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��A���ۂɒ��Ԏq�̌������s���Ă���ƍl���Ă͂����܂���B
�@���w�����̃P�[�X�ł́A�f���q���K�c���ƏՓ˂���ꍇ�Ƃ͈قȂ�A�����Ɋւ��d�q�Ɍ��q�j����̓d���I�ȍ�p�����������܂��B���q�j�Ɠd�q���P������ꍇ�A�ۓ��_�̌v�Z�ɂ́A���Ԃɖ����̌��q�������t�@�C���}���}�i�}�Q�j������܂����A�������������������ׂĖ����ł��Ȃ���^���y�ڂ����߁A�������������܂���i�{���̂��Ƃ������A�����͂ǂ�ȉߒ��ł��������Ȃ��̂ł����A�R���v�g���U���̂悤�ȃP�[�X�ł́A�ŏ��̉������������W�߂�Ɨǂ��ߎ��ɂȂ�Ƃ�������Ȏ������̂ł��j�B
�@�������A�Î~�������q�j�Ɠd�q�Ɍ���ƁA����̃t�@�C���}���}�̊�^�����𑫂��グ��A�N�[�����͂Ƃ����L���̌��ʂ������邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���[�����c�͂ȂǃN�[�����͈ȊO�̑��ݍ�p�́A�דd���q�̉^���ɗR�����鑊�Θ_�I�Ȍ��ʂɑ������A���w�����̂悤�Ɍ��q�j���قƂ�Ǔ����Ȃ��P�[�X�ł́A�[���ɏ����Ȋ�^���������炵�܂���B���̂��߁A�ʎq���w�ł́A�����Ɍ��q�̑��݂�z�肷�邱�Ƃ͂����A���łɌ��q�̊�^���ꕔ�܂܂�Ă���N�[�����͂̃|�e���V�����i����сA�ꍇ�ɂ���Ă͈ꕔ�̎��C���ݍ�p�j�������g���Čv�Z���s���܂��B
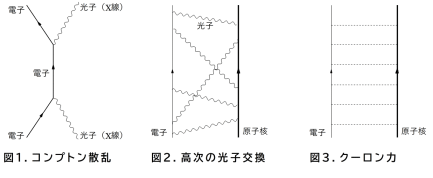
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�����e�B�E�z�[�����Ƃ́A��TV�ԑg���ł̃Q�[���Ɋւ��Ę_���ƂȂ������̂ł��B

�@���̃Q�[���ł́A���̂����R�̏������̂����A�P�Ɍi�i�������Ă���A�c��̂Q�͋���ۂł��B�Q�[���Q���҂́A����������ԂłP��I�т܂��B����ƁA�i��҂��A���̂Q�̂����̈���̔����J���Ē�����ł��邱�Ƃ���������ŁA�u�͂��߂ɑI�����������A�J���Ă��Ȃ�������̔��ɕύX���܂����v�Ɩ₢�����܂��B
�@�_�_�ɂȂ����̂́A�ύX���������i�i�Ă�m���������Ȃ邩�ǂ����ł��B������ƍl����ƁA�i��҂��J���Ă��Ȃ��Q�̔��̂ǂ��炩����ɂ����i�i�������Ă���̂ł�����A�ǂ���̔���I��ł��m����1/2�ɂȂ肻���ł��B
�@�c�_�m�ɂ��邽�߂ɁA�i��҂́A���炩���ߌi�i�̓���������m���Ă���A�K��������̔����J������̂Ƃ��܂��i�����łȂ��P�[�X�́A�Ō�ɍl�@���܂��j�B
�@�����������́A�m���ōl����ƍ������₷���̂ŁA�����̎��s�ɒu�������čl����̂��ߓ��ł��B���̃P�[�X�ł́A�����Q�[�����R����s�����̂Ƃ��܂��B�R�̏�������A,B,C�Ɩ��t���A�Q���҂��͂��߂ɑI���������A�Ƃ��܂��i���O�̕t�����ɔC�Ӑ�������̂ł������܂������A�C�ɂȂ�l�́A���s���X����ɂ��ĎQ���҂�A�`C��ʁX�ɑI�ԃP�[�X���l���Ă��������j�B
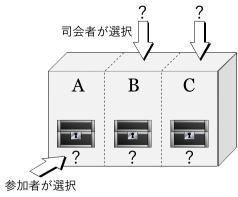
�@�i�i�́AA�`C�̂ǂꂩ�ɓ��������œ����Ă���͂��ł�����A�R����̎��s�̂����AA�ɓ����Ă���P�[�X���P����A�������AB���P����AC���P����ł��B���̂R�̃P�[�X���ꍇ�������܂��B
�@�i�i��A�ɓ����Ă���A�Q���҂�A�̔���I�ꍇ�AB��C�̂ǂ������������ۂȂ̂ŁA�i��҂́AB��C�̂ǂ��炩�������őI�т܂��B���������āA�i�i��A�ɓ����Ă���P����̂����A5000���B���A5000���C��I�т܂��i4997���5003������܂��A�������������ȃY��������̂��A�m���̕��@�_�ł��j�B���̂Ƃ��A�Q���҂�����ύX����ƁA�i�i���������ʂɂȂ�܂��B
�@�i�i��B�ɓ����Ă���P����̎��s�ł́A�i��҂͕K���i�i�̓����Ă��Ȃ�C�̔���I�т܂��B���������āA���̂P����̎��s�ł́A�Q���҂��A���łɑI��ł�����A����A�i��҂��I�Ȃ�������B�ɕύX����ƁA�Q���҂͌i�i���Q�b�g�ł��܂��B
�@�i�i��C�ɓ����Ă���P����ł��A�Q���҂͔���ύX����Όi�i����ɂ��܂��B
�@�ȏ���܂Ƃ߂�ƁA�R����̎��s�̂����A�P����͕ύX����ƌi�i�������A�Q����͕ύX����Όi�i���܂��B���������āA�i�i��m���́A�ύX����ƂQ�{�ɂȂ�܂��B
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA������ƍl�����Ƃ��̊m���v�Z���Ԉ���Ă������R�́A���炩�ł��B�i��҂̑I���������_���ł͂Ȃ����߁A�P���Ȋm���̍l�������K�p�ł��Ȃ������̂ł��B
�@�����܂ł́A�i��҂��i�i�̓����Ă������m���Ă���P�[�X�ł����A�m��Ȃ�������ǂ��Ȃ�ł��傤���H
�@�Q���҂�A��I�ьi�i��A�ɓ����Ă���P����ł́A�i��҂�B��C�̂ǂ����I��Ŕ����J���Ă��A���͋�Ȃ̂ŃQ�[���͕K�����s����܂��B���̂Ƃ��A�Q���҂��I����ύX����ƁA�i�i�������܂��B
�@�������A�i�i��B�ɓ����Ă���P����̃P�[�X�́A�����Ȃ�܂���B�P����̂�����5000��ł́A�i��҂�B��I�ьi�i�̂�������J���Ă��܂��̂ŁA���̎��_�ŃQ�[���͖����ɂȂ�܂��B�Q�[�������s�����̂́A�i��҂�C��I��5000��ł���A���̃P�[�X�ł́A�Q���҂����̑I����ύX����ƌi�i����ɂł��܂��B�i�i��C�ɓ����Ă���P����ł������ł��B
�@�܂Ƃ߂�ƁA�i��҂��i�i�̈ʒu��m��Ȃ��ꍇ�A�R����̎��s�̂����P����͖����ł���A�Q�[�������s�����Q����̂����A�ύX����ƌi�i�������̂��P����A�i�i����ɂł���̂�5000+5000���P����ŁA���ǁA�ύX���Ă����Ȃ��Ă��A�i�i����ɂ���m���͓����ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���Ԍn�ɂ�����E�B���X�̖����ɂ��ẮA���������ɏA��������A�͂����肵�����Ƃ͂킩���Ă��܂���B�������A�@�\�������痘�p���邾���łȂ��A�h��̖��ɗ��E�B���X������Ƃ�������������Ă���A����̌����ۑ�ƌ����܂��B
�@�E�B���X���ǂ̂悤�ɂ��Ēa���������͕s���ł����A�����j�̏����̒i�K�Ō��ꂽ�Ɛ�������܂��B�����̂�̍זE�̎��ɔ����Ċ����ɕ��o�����j�_�̂����A�唼�͒Z���ԂŎ��R�ɕ���������ł��܂����A�����ꕔ�̒f�Ђ��^���p�N���ƌ������Ĉ��艻���A���̐����̑�Ӊߒ��ɉ�����Ȃ��瑝�B���s���悤�ɂȂ邱�Ƃ����蓾�܂��B�����E�B���X���������Đ��܂ꂽ�̂Ȃ�A��ӁE���B���s������������A����ɐ������ăE�B���X�����X�ƌ����͂��ł��B
�@�����E�́A�^���ہi�o�N�e���A�j�A�Íہi�A�[�L�A�j�A�^�j�����Ƃ����R�̃h���C������\������Ă��܂��B���̂����A�ÍۂɊ�������E�B���X�ׂ�ƁA�^���ۂ�^�j�����Ƌ��ʂ��镪�q�\�������������̂�����̂ŁA�E�B���X�́A�R�̃h���C���ɕ������ȑO�A30���N�ȏ�O���瑶�݂����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B
�@�܂�A�����̂́A���\���N���̊ԁA��ʂ̈�`�q�f�Ђ�E�B���X�����݂�����̒��œ������������Ă����킯�ł��B�Ƃ���A�����̓E�B���X�ƂƂ��ɋ��i�����A�E�B���X�����̐����𗘗p����̂Ɠ����悤�ɁA�������E�B���X�𗘗p����\��������킯�ł��B
�@�����_�ł͂����肵�Ă���̂́A���������E�B���X�͏h��Ƒ��킸�ɋ������Ă���Ƃ������Ƃł��B���R�̂��ƂȂ���A�h��������Ɏ��ł����Ă��܂��悤�ȃE�B���X�́A�����ł��܂���B�l�ԂɊ�������E�B���X�̏ꍇ�A��C�����̂悤�ȋ��͂Ȋ����͂����E�B���X�́A���]�E�B���X�␅���я��v�]�E�C���X�Ȃǂ��������ł���A�������A�����l�͖Ɖu���l������̂ŁA���Ƃ��E�B���X���̓��Ɏc�����Ƃ��Ă��A�����Ԃɂ킽���ċx����ԂɂȂ舫�������܂���i�Ɖu�͂̐���������҂̏ꍇ�A�E�B���X���Ăъ��������я��v�]�ǂ��邱�Ƃ�����܂��j�B���̏�Ԃ́A���̋����ƌ����邩������܂���B���a�����̎ア�����̃E�B���X�́A�Ɖu�@�\�̑Ώۂɂ��Ȃ炸�A�̓��ɂ����Ɛ���Ԃŏh��Ƌ������Ă���̂��ӂ��ł��B
�@�E�B���X���h��ɂƂ��ėL�v�ɂȂ�P�[�X�͂قƂ�ǒm���Ă��܂��A���̉\�����������̂Ƃ��āA�ٔՔ����̍ۂɏd�v�Ȗ������ʂ����^���p�N���E�V���V�`�����Y�������`�q���m���Ă��܂��B���̈�`�q�́A���Ƃ��ƌ̂Ɋ����������g���E�B���X���ۗL���Ă������̂ł��B���g���E�B���X�Ƃ́A���������Ƃ��ɋt�]�ʍy�f���g���ďh��̐��F�̂Ɏ����̈�`�q��}�����A���ȑ��B���s���^�C�v�̃E�B���X�ł����A���B�זE�̐��F�̂ɑ}�����ꂽ��`�q���A���̂܂܌̂̃Q�m���ɑg�ݍ��܂�Ă��܂����Ƃ�����܂��B�q�g�Q�m���̐��p�[�Z���g���A�������ă��g���E�B���X������������`�q�f�Ђł���A���̑啔�����@�\���Ă��܂��A�V���V�`���̈�`�q�͗�O�I�ɋ@�\���Ă��܂��B���̈�`�q�������炵�����g���E�B���X�́A���ɗ��E�B���X�Ƃ��ďh��Ƌ������Ă��邤���ɁA�Ɨ����������ăQ�m���Ɏ�荞�܂�Ă��܂����̂�������܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�ӎ��Ɋւ���c�_�́A���������u�ӎ��Ƃ͉����v�Ƃ����₢�ɑ��Ċm���ȉ��Ȃ����߁A�N���A�J�b�g�Ȍ��_���o���܂���B���́A�ӎ��Ƃ͒����_�o�n�Ő��N����ʎq�_�I�ȋ������ۂ��ƍl���A������ԁi�ʎq�_�I�Ȏ��R�x�������ԁj�Ŗ��ڂȌ��т������������A��̂܂Ƃ܂���������ӎ����ƌ��Ȃ��܂����B�������A�������������͂����܂Ő����ł���A�u���ڂȌ��т��v���ǂ̒��x���Ƃ�������ʓI�Ș_�q�͂ł��܂���B
�@�����w�I�Ȋϓ_���炷��ƁA�j���[������V�i�v�X�͎��̂ł͂Ȃ��A�ꎞ�I�Ȉ��萫��ۂ����ʎq�_�I�ȏ�Ԃɂ����܂���B���������āA�����_�o�n���`���������̒i�K����̂̎���ɐ_�o�זE���j���܂ł��A�u���₩�Ɍ��т�����A�̏�ԁv�ƌ��Ȃ����Ƃ��\�ł��B�����A���������u���₩�Ȍ��т��v���P��̈ӎ����`������̂Ȃ�A���ꂱ���A�ꐶ�̑S�Ă̎��Ԃ��܂Ƃ߂Ĉӎ����邱�Ƃ����蓾��킯�ł��B
�@�����Ƃ��A�����܂ňӎ��͈̔͂��L���Ă��܂��ƁA�����_�o�n�Ƃ���ȊO�̑���A���邢�́A�����Ƒ��l�Ƃ������A�펯�I�ȋ��E����B���ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����Ŏ��́A�u�܂Ƃ߂Ĉӎ��������́v�ɂ��Ă̈�ʓI�ȏ펯�ƍ��v����悤�ɁA��]�A����ŋN����A���I�E�z�I�Ȑ_�o�����Ƃ�������ꂽ�������ۂ��A�ӎ��Ɠ��肷�邱�Ƃɂ��܂����B������H�ƌĂ�邱�������_�o�����́A�����������S�~���b�����������Ȃ��̂ŁA������܂Ƃ܂����ӎ��ƌ��т����킯�ł��B
�@�ӎ���_����ɓ������ẮA�����I�Ȃ��̂ɋc�_�����肵�Ă��܂��B�����ŕ����Ƃ����̂́A�G�l���M�[���ʎq�ꂪ���o������Ԃł��B���㕨���w�̊�{�I�ȕ����ςɂ��A�ꂪ�����錻�ۂ̒S����ł���A��̊O���ɑ���������̂͑��݂��܂���B
�@��ʂ̐l�́A�����w�̑Ώۂ͒P�Ȃ镨���ł����āA�S�Ƃ͕ʕ����Ǝv����������܂���B�������A���܂��܂ȕ������ۂׂ�ƁA���������ɑ��l���ɕx��ł���A���G�����Ȍ��ۂ������N�������Ƃ��킩��܂��B�����͐S�Ɠ����f�ނŐD��Ȃ���Ă���A���E�ɕ����ȊO�́g�����h�͕K�v�Ȃ��Ƃ����̂��A�����w�҂̒[����Ƃ��Ă̎��̎����ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�������ʂ͉^���������Ɍ���鎿�ʂŁA�����̊����i��������ɂ����j�ɊW���܂��B����A�d�͎��ʂ́i�j���[�g���́j�d�͖@���Ɍ���鎿�ʂŁA�Q�̕��̂̊Ԃɏd�͂���p����Ƃ��A���̑傫�������肵�܂��B���҂���������A�d�͂�������p����n�_�ŁA�����镨�̂����������x�ʼn^�����܂��B���̂��Ƃ́A�A�C���V���^�C������ʑ��Θ_���\�z����ۂɏo���_�Ƃ��܂����B
�@�������ʂƏd�͎��ʂ��قȂ�ꍇ�A�����Ɍ�����̂́A�d�ʌv�ő������d���i���d�͎��ʂɔ��j�������ł��A�f�ނɂ���ė����̉����x���Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B���̂ɍ�p����d�͂́A�d�͎���M�ɏd�͏�̋���g���悶�����̂ƂȂ�܂��B���������āA�d�͂�������p����n�_�ɂ�����^�������� f=ma �im�F�������ʁj�ɂ��A�d�͂ɂ�闎���^���̉����x�� a=(M/m)g �ƂȂ�AM��m���������i���ʂ̌W���Ŋ��Z�ł���j�Ȃ�A�����镨�̂͏d�͏���ł͓������d�͉����x�ʼn^�����܂��B�������A���f�ɂ���āi�z�q�ƒ����q�ƂŁA���邢�́A�ʏ�̕����ƈÍ������Ȃǂ̃G�L�]�`�b�N�E�}�^�[�ƂŁjM��m�̔䂪�قȂ�Ȃ�A�f�ނ��ƂɌŗL�̏d�͉����x�ʼn^�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�Q�̎��ʂ���v���Ȃ��Ƃ��Ɋϑ�����錻�ۂ́A�d�͉����x�ɍ����������x�ł����A���_�ɗ^����e���͐r��ł��B�����w�̊�{�ƂȂ�l�[�^�[�̒藝�ɂ��ƁA�Ώ̐�������A����ɉ������ۑ��ʂ����݂��邱�Ƃ�������܂��B���Ԃ��o�߂��Ă������@�����ω����Ȃ��Ƃ����Ώ̐��ɂ��ۑ��ʂ��G�l���M�[�ł���A�������A��Ԃ���i�ړ������Ƃ��̑Ώ̐��ɂ��ۑ��ʂ��^���ʂł����A���Θ_�ɂ��A���ԂƋ�Ԃ͕����ē��ꂳ�ꂽ������\������̂ŁA�G�l���M�[�Ɖ^���ʂ������Z�b�g�Ƃ��Ĉ����ׂ��ł��B�������ʂƏd�͎��ʂ́A�ǂ�����Î~���̂̓����ɒ~����ꂽ�G�l���M�[�̂��ƂŁA�O�҂́A���R�Ȏ���ŏd�͈ȊO�̗͂���p�����Ƃ��̊�����^���A��҂́A�d�͂̍����ł���Ȃ���������Ƃǂ̂悤�ɑ��ݍ�p���邩�����肵�܂��B�܂�A�������ʂƏd�͎��ʂ����������Ƃ́A�u�Q��ނ��鎿�ʂ��Ȃ�����v����v�Ƃ����s���Ȏ咣�ł͂Ȃ��A����Ƃ��̑Ώ̐��ɋN������ۑ��ʂ��ǂ̂悤�Ɋւ�邩�Ƃ�������I�ȗ��_�̌n�ɂ����āA���ƂȂ閽��Ȃ̂ł��B
�@���������āA�����������ʂƏd�͎��ʂ��قȂ�Ɣ���������A���㕨���w�����ꂩ����ւ���K�v���ɔ�����厖���ƂȂ�܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�����́A���Ƃ��Ƃ́A�����{�݂���R�����Ȃǂ̓`���a�����������Ƃ��A���̖͂�������߂ɍ������Ђǂ��Ȃ����Ƃ������A���[�J���ȃg���u���Ɏn�܂�A�l�Ԃ̊����悪�L�܂�ɂ�āA�������ɒn���S��i���Q�A���O�q���̖��j�A����ɂ͒n���K�͂ւƊg�債�Ă����܂����B�����F���ږ����n�܂�A���ꂱ���F���K�͂̊���肪�o�����邩������܂���B
�@�����Ƃ��A�F���̃X�P�[���͂���߂ċ���ŁA�l�Ԃ����X�̂��Ƃ���炩���Ă��A�ȒP�ɂ͔j��܂���B���z�̃G�l���M�[�o�͂́A100��kW�̌��q�F10����ɓ�����܂����A�F�����͍��G�l���M�[�̕��ː��ł���A�n��̕��˔\�����Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǗL�Q�ł��B�l�Ԃ́A�F���̈�p�Ɏ��������������ł������z���A�Ђ�����ƕ�炷�����Ő���t�ł��傤�B
�@�F���K�͂̊���肪����Ƃ���A����́A�l�ނƃG�C���A���̊ԂŔ�������\��������܂��B���ɁA�ΐ��̂悤�Șf�����e���t�H�[�~���O�ɂ���Ēn���Ɠ����悤�Ȋ��ɉ����ł����Ƃ���ƁA���̐��Ɍ��X�������Ă��������i����Ƃ���ł����j�ɂƂ��Ă͑���f�ł��B�l�ԂɂƂ��Đ�����̂Ɍ������Ȃ��_�f�́A�����������������ȑO�̏����̐����ɂ́A�v���I�Ȏ_����p�����ғł̃K�X�ł��B�܂��A��C�␅�̖R�����f���́A�C�ۂ����肵�y��̐Z�H���}�����Ă��܂����A�l�Ԃ��n���Ɏ����đ�ʂ̋�C�␅�����o���ƁA�~�J�◬���ɂ���ēy�낪�Z�H����A�����̐����������n�������܂��B�l�ԂɂƂ��ĉ��K�Ȋ������o�����Ƃ��A�n���O�����ɂƂ��ċ������������j��ɂȂ�̂ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�傫�����Ȃ����̂̉�]�́A�ÓT�����w�ł̓C���[�W�ł��Ȃ��T�O�ł����A�ʎq�_�ł́A�X�s���Ƃ����`�Ř_�����܂��B�������A�X�s���Ɖ�]���ǂ������W�ɂ��邩�́A�K���������m�ł͂���܂���B
�@�X�s���̊T�O���͂��߂Ē�Ă��ꂽ�̂́A1925�N�̃E�[�����x�b�N�ƃn�E�g�V���~�b�g�̘_���ł��B����́A��������ŃG�l���M�[���ʂ��Q�ɕ������Ƃ����[�[�}�����ʂ�������邽�߂ɁA�d�q�����]����Ɖ��肵�����e�ł����B�������A�ϑ����ꂽ�[�[�}�����ʂƍ��v������ɂ́A�\�ʂł̉�]���x���������Ă��܂��A���Θ_�̋A���ɔ�����ƃp�E����ɔᔻ����܂��B�p�E���́A�X�s���Ƃ͗��q�̉�]�ł͂Ȃ��p�^���ʉ��Z�q�̌ŗL�l�ł���A�ÓT�����w�̊T�O�ł͐��������Ȃ��ƍl���܂����B
�@�ʎq�_�ɂ́A�ÓT�_�I�ȉ�]�^���ɑΉ�����ʂ�����܂��B���q���ɑ��݂���d�q�͋O���p�^���ʂ������܂����A���̗ʂ́A���q�j�̎���Ńj���[�g���͊w�Ɋ�Â��Ď���^��������Ƃ��̊p�^���ʂƖ��ڂɊW���܂��B�܂��A�`���[���j�E���̂悤�ɁA�d���N�H�[�N�Ɣ��N�H�[�N�������������Ԏq�́A�����炭�Ђ���ɍג����L�тĉ�]���邽�߁A�X�s�����R�x�������܂��B�����́A�傫���������̂̉�]�Ȃ̂ŁA���Θ_�̐���ɂ���ď��������Ɨ\�z����܂��i�`���[���j�E���̃X�s���́A3�܂Ŋϑ�����Ă��܂����A���̏�͂܂��������Ă��܂���j�B
�@����ł́A�d�q�̂悤�ɑ傫�����Ȃ��ƍl�����闱�q�̃X�s���ɏ���͂Ȃ��̂ł��傤���H ���̖��ɂ́A�܂�������܂���B�܂��A�d�q�ɖ{���ɑ傫�����Ȃ����ǂ����́A���܂��m���ł��܂���B���炩�̓����\���������āA���ꂪ�X�s�����R�x�ݏo���Ă���\�����ے�ł��Ȃ��̂ł��B����ɁA�f���q�i�������q�ł͂Ȃ���{�I�ȏ�̗�N��Ԃƌ��Ȃ������́j�̃X�s�����ǂꂾ������̂��A�͂����肵�����_�͂���܂���B���݂̂Ƃ���A�X�s��1/2�̃N�H�[�N�ƃ��v�g���A�X�s��1�̃Q�[�W�{�\���̑��݂��m���ł���A�X�s��0�̃q�b�O�X���q������悤�ł��i�������ALHC�Ŕ������ꂽ�q�b�O�X���q�炵�����̂́A���͕������q���ƍl���錤���҂͏��Ȃ�����܂���j�B�X�s��2�̏d�͎q���A�܂��������Ă��Ȃ������ŁA�������݂��܂��B�������A����ȊO�̃X�s�������f���q�����݂��邩�ǂ����s���ł���A�X�s���̒l�ɏ�������邩���͂����肵�܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�����镶���l���A����̉Ȋw�m����������x�������܂܁A�����`���\���N����̖����Ƀ^�C���X���b�v����P�[�X���l���Ă݂܂��傤�B�l�ނ͂��łɐ�ł������Ί펞��̕��������ɂ܂Ō�ނ��A�����ɂ�镶���L�^�͂��ׂĎ���ꂢ����̂Ƃ��܂��B
�@����l�̉��⌚�����Ȃǂ̈�Ղ����@�ł���A���Ȃ�͂����肵�����Ƃ��킩��܂��B�����n�w���牽�炩�̓��A���̂����������ꍇ�A���̎���ɒY�f�̓��ʑ̔䂪���̊����ŕω����邱�Ƃ𗘗p���āA��r�I���m�ȔN�㑪�肪�\�ł��B�������A�Y�f�̓��ʑ̂��g����̂́A�������������N���x�ł��B����ȏ�ɂȂ�ƁA�Y�f�ɔ�ׂĐ��x�͗����܂����A���ː��J���E������ː����r�W�E����p�����N�㑪�肪�s���܂��B
�@��Ղ�������Ȃ������ꍇ�ł��A�n�w�����ɂ���āA������x�Ȃ玞��̓��肪�ł���͂��ł��B
�@����́A�n������敪�ŐV����E��l�I�E���V���i���ϐ��j�E���[�K�[�������ɕ��ނ���܂��B���[�K�[�������́A2018�N�ɍ��ۑw���ψ���ŏ��F���ꂽ����敪�ł��i���͍ŋ߂܂Œm��܂���ł����j�B4200�N�O���猻��E�ߖ����Ɏ��鎞��敪�ŁA�����Ƀ^�C���X���b�v�����l�́A���̎��ォ��ǂꂭ�炢��ɗ������ׂ邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�l�ނ̊����́A�n�w�ɂ��܂��܂ȍ��Ղ��c���܂��B�H�ꂩ��̔r�o���A���q�͔��d��j�����ɂ��c�����ː������Ȃǂ��n�w���猩�o����邩������܂���B�܂��A�l�ނ͑����̐�������ł�������̂ŁA���[�K�[�������w�̏㉺�Ő������̕��z���傫���قȂ�Ɨ\�z����܂��B�n�����g���Ȃǂ̋C��ϓ�������ɑ�K�͂ɂȂ����Ƃ���ƁA���̉e�����c�����͂��ł��B
�@���㕶�����h��������̒n�w���킩�����ꍇ�A���ː����ʑ̂ɂ��N�㑪�肪�\�ɂȂ�܂��B�茳�ɕ��ː�����킪�Ȃ��Ă��A��ɂǂ̒��x�̒n�w���d�Ȃ��Ă��邩�����邱�Ƃɂ��A��܂��ȔN���͐���ł��܂��B
�@�V�̊ϑ������p�ł��܂��B��͌n�����̍P���́A�S�̂Ƃ��ċ�͒��S�̎������]���Ă��܂����A���S����̋�����V�̂��Ƃ̌ŗL�^���ɂ���āA���z�n���猩���Ƃ��̓������ɍ�������܂��B���̂��߁A���݂̓V��Ɍ����鐯���́A����ƂƂ��ɏ������ό`����Ă����܂��B�Ⴆ�A���݂͂Ђ��Ⴍ�̌`�������k�l�����́A���\���N���o�ƁA�����������e�핔�����G���ɋ߂Â��A�����傫���܂�Ȃ���܂��B���݂̓V���f�[�^�𖢗��Ɏ����o���Ă���A�P���̑��ΓI�Ȉʒu�ω�����ɁA�N�������o����͂��ł��B
�@���z��f�������ԂƂƂ��ɏ������ω����܂����A�ω��̏ڍׂ͏[���ɉ𖾂���Ă��炸�A��قǒ������Ԃ��o���Ȃ��ƁA�o�N�ω��͂킩��Ȃ��ł��傤�B�Ⴆ�A���z�̌��ʂ́A���S���ŋN����j�Z�������̕ω��ɂ���đ��傷��Ɨ\�z����Ă��܂����A�����N���x�ł͔N�㑪��Ɏg���Ȃ��Ǝv���܂��i�����N�o�ƁA���݂Ƃ̈Ⴂ���͂����肵�܂��j�B
�@���ː�������V�̊ϑ��@��A���邢�́A���܂��܂ȉȊw�f�[�^�𖢗��Ɏ����o���Ȃ������ꍇ�A���m�ȔN�㑪��͍���ł����A���߂Ă͂����܂���B����̒n�}�����Q���Ă���A�͐�̈ʒu���ǂꂭ�炢�ړ��������Ƃ������n�`�ω����肪����ɁA�ǂ̒��x�̔N�����o��������傴���ςɌ��ς��邱�Ƃ͂ł��܂��B�������̎�ނ��ώ@�����݂Ƃ̈Ⴂ���l���邱�Ƃ��A���ɗ��ł��傤�B�ƒ{���쐶�������Ǝv���鐶����������A���݂ɂ��Ȃ�߂��i������������N���x�j�͂��ł����A�������Ƃ��Ȃ����A�����̂����Ă���A�K�v�Ȉ�`�q�ψق��~�ς���邾���̔N�����o�߂����ƍl�����܂��B
�@�܂��͊ώ@���邱�Ƃ���ł��i���̑O�ɁA�����Ő������т��i�������邱�Ƃ��K�v�ł����j�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���╶�ɂ���̂́A2013�N�ɃC���^�[�l�b�g�Ō��\���ꂽ C.B.Frey �� M.A.Osborne �̋����_��"THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?"�ł��B�u�A�����J�ɂ�����47%�̌ٗp�҂̎d�����R���s���[�^���icomputerisation; �Z���T�[��AI�ȂǏ��Z�p�����p����@��ւ̒u�������j����郊�X�N�������v�Ƃ����Z���Z�[�V���i���ȓ��e���������߁A�傫�Șb��ƂȂ�܂����B���͂ƌ����A�\�����ɂ��āu����Ȃ��Ƃ�����̂��ȁv�Ǝv�������x�ł��܂�C�ɂ��Ă��܂���ł������A���₪�����̂����������ɁA���_�����i�{��������45�y�[�W������̂ŁA�����Ɓj�ǂ�ł݂܂����B
�@���̘_���̓����́A702���̐E��ɂ��āu�R���s���[�^�������m���v���Z�o�������Ƃł��B�Ⴆ�A��D���ٖ̍D�t�A�X�|�[�c�̐R���A�ی��Ӓ�l�A���W�W��99-97���̊m���ŃR���s���[�^������邪�A�i�o���G�Ȃǂ́j�U�t�t�A���Ȉ�E�O�Ȉ�A���w�Z�̋��t�̏ꍇ�A�m����0.5�������ƌ��_����Ă��܂��B���ꂾ�������̐E��ɐ��l���A�T�C���ł����̂́AO*NET�Ƃ����A�����J�J���Ȃ��J�������I�����C���E�T�[�r�X�Ɋe�E��̏ڂ����J�����e���L����Ă������ƁA���̃f�[�^��J�����v�ǂɂ��ٗp�ƒ����̓��v�i2010�j�ƌ��т���ꂽ���Ƃł��B
�@���ɏd�����ꂽ�̂��AO*NET���܂Ƃ߂����ރf�[�^�ł��BO*NET�ł́A�E���̐��i�ނ��邽�߁A�������̍��ڂɑ��āA�E���𐋍s�����ł̏d�v���ƃ��x����������Ă��܂��B���������O*NET���ڂƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B�Ⴆ�A�u���̊�p���v�Ƃ���O*NET���ڂɑ��ẮA��i�d�����\�P�b�g�ɂ˂����ށj�|���i�I�����W��f�����ؔ��ɋl�߂�j�|���i��p�����g���ĐS����p���s���j�̂ǂ̃��x���ɓ����邩�������āA���ނ��s���Ă��܂��B�I�Y�{�[����́A�u���̊�p���v�u�I���W�i���e�B�v�u���́v�ȂǂX��O*NET���ڂ̃��x���ƃR���s���[�^���m�������т�����@���l�Ă��܂���
�@�R���s���[�^���m���́A���̂悤�ȃX�e�b�v�ŋ��߂��܂����B�܂��A70�̐E���I�сA�u�r�b�O�f�[�^�����p�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ����Ƃ��A�Ő�[�̃R���s���[�^����@��Ő��s�\�Ȃ悤�Ɏd�����e���w��ł��邩�v�Ƃ����₢�ɑ��āA���͎҂Ɂuyes/no�v�Łi��ςɊ�Â��āj�����܂��i�m���ɉł���E���I�悤�ł��j�B���̌��ʂ���ɁA�E�킲�ƂɂP�i�R���s���[�^���\�j���O�i�R���s���[�^���s�\�j�Ƃ������x����t���܂��B���ꂪ�A�R���s���[�^���m�������߂�T���v���f�[�^�ƂȂ�܂��B
�@���ɁA���v���w�̎�@�Ɋ�Â��āA�u���̊�p���v�Ȃǂ�O*NET���ڂɑ��郌�x����g�ݍ��킹���������肵�A�T���v���f�[�^�̃��x���ƌX������v����悤�ɁA�p�����[�^�����܂��B�ŏI�I�ɂ́A�������ē���ꂽ�����g���āA702�̐E��ɂ��ăR���s���[�^���m�������߂��킯�ł��B���̌��ʂ́A�T���v���f�[�^�Ɗ��S�Ɉ�v����킯�ł͂���܂���B�Ⴆ�A�u�E�F�C�^�[�^�E�F�C�g���X�v�́A��ϓI���f�Ɋ�Â����x�����O�i�R���s���[�^���s�\�j�ł����AO*NET���ڂ̎����狁�߂�ꂽ�R���s���[�^���m����94���ƂȂ��Ă��܂��B
�@���́A���̐��l���M���ł��邩�ǂ����ł��B�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�R���s���[�^���m���iprobability of computerisation�j�ƌ����Ă͂�����̂́A�����܂ŐE�����e�̕��ތ��ʂɊ�Â��ČX���������߂��ɉ߂��Ȃ��_�ł��B�_���̓r���ŁA���Y���_�̊C�O�ړ]����@��̒�����ȂǂɌ��y���Ă���̂ŁA�����Ɋւ���f�[�^�ƌ��т���̂��Ǝv���܂������A���������c�_�͂Ȃ��A�P�ɃR���s���[�^���\�^�s�\�ȐE��Ǝ������ރp�^�[�����ǂ����ׂĂ��邾���ł��B
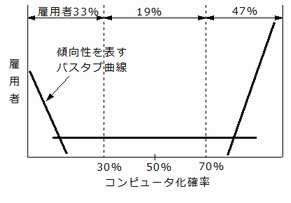
�@�ٗp���v�ƌ��т���ƁA�R���s���[�^���m���ɑ��ăv���b�g�����ٗp�Ґ��͂��ꂢ�ȃo�X�^�u�Ȑ��ƂȂ�܂��i�E�}�G�X������\���T���}�j�B�����M����ƁA�R���s���[�^������₷���E��Ƃ���ɂ����E��ɂ͂����蕪����A�R���s���[�^�����X�N�̍����i�R���s���[�^���m��70���ȏ�́j�E��ɏ]������l���A�S�ٗp�҂�47���ɒB����Ƃ������_������ꂻ���ł��B�������A����قnj����ȃo�X�^�u�Ȑ��ɂȂ�̂́A���x�������ɒ[�ɎU���₷��������O*NET���ڂƂ��đI��Ă��邱�ƁA����ɁAO*NET���ڂ̃��x�����ő�l�ɋ߂Â��L���͈͂ŃR���s���[�^���m�����ɒ[�Ȓl�ɂ��郂�f�����g���Ă��邱�Ɓ|�|�Ȃǂ��e�����y�ڂ������ʂł͂Ȃ����Ɛ�������܂��B
�@����A���\�̌���Ɖ��i�̒�����ɂ���ăR���s���[�^����̋@�킪���y����ɏ]���A�����̐E�ƂŘJ���҂������̋@��ɒu���������Ă������Ƃ͊m���ł��B�������A���̊��������̘_���Ŏ����ꂽ���l�ʂ�ɂȂ邩�ƌ����ƁA�����咣���邾���̉Ȋw�I�ȍ����͂���܂���B�_���ł́A���������������I���W�i���e�B���v�������E��قǃR���s���[�^������ɂ������Ƃ�������Ă��܂����A����́A�萫�I�ȋc�_�Ƃ��Ă͎��ɓ��R�̎咣�ŁA�T���v���f�[�^�Ƃ��ėp������ϓI���f�����̂܂ܔ��f����Ă���悤�Ɏv���܂��B�����������A�萫�I�ɂ͓�����O�A��ʓI�ɂ͍����̖R�������e�ŁA���ɒ��ڂ��ׂ��_���ɂ͎v���܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@����Ȑ��͏��߂Ď��ɂ��܂������A�C�ɂȂ��āu�A�_�@�m�\�v��Google�������Ă݂��Ƃ���A���Ȃ�̃y�[�W���q�b�g���܂����B�������������Ɠǂ���ł́A�l���x���ŔA�_�l�̍����ƒm�\�̍����ɒ��ړI�Ȉ��ʊW������Ƃ͍l�����Ȃ����̂́A��̃��x���Ō����ꍇ�A�i���̉ߒ��ŗ��҂̊Ԃɑ��ւ��������\��������܂��B
�@�����͐����̂��߂Ƀ^���p�N�����ӂ��܂����A���̉ߒ��Ő�����s�v�Ȓ��f��������̊O�ɏo���Ȃ���Ȃ�܂���B�A�_�iC
5H
4N
4O
3�j�͐��ɗn���Ȃ������ł���A�ނ�݂ɐ���r�o�ł��Ȃ����ނ���ނŗ��p����܂��B���ɍ������������Ō`���̐������A�_�ł��B����A�M���ނ◼���ނł́A�s�v�Ȓ��f�������͐��ɗn�����ĔA�ƂƂ��ɔr�o����̂���ʓI�ŁA���n���̔A�f�Ȃǂ��g���܂��B�זE�j�ɑ����܂܂��v�����̂��ӂ���ꍇ�́A��������A�_���������A�A�_�I�L�V�_�[�[�ɂ���Đ��ɗn���钂�f�������i�A�����g�C���j�ɂ��Ĕr�o���܂��B
�@�Ƃ��낪�A�l�Ԃ��܂ވꕔ�̗쒷�ނł́A��`�I�ɔA�_�I�L�V�_�[�[���������Ă���A�A�_��r�o���ɂ����̂ɂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A�v�����𑽂̂��܂ސH���𑱂���ƁA�����̔A�_�l�������Ȃ��ē�g�D��߂Ō��������܂��B���ꂪ�ɕ��̌����ƂȂ�܂��B�܂��A���A�_���ǂ̊��҂́A�������֘A�����⋕�����S�����A�A�H����t�@�\��Q�����₷�����Ƃ��m���Ă���A�A�_�����������ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B����A�A�_�ɂ́A�]���t�֖�ɂ����铧�ߐ��̏[�i��}��������ʂ�����A�������d���ǂ̐i�s��h���ȂǁA���܂��܂Ȍ`�Œ����_�o�n��ی삷�铭��������悤�ł��B����ɁA�������ߍ�p�Ɋւ��������A�A�_�̐����I�ȋ@�\�Ɋւ��ẮA�܂��s���ȓ_�������c����Ă��܂��B
�@�����I�@�\���͂����肵�Ă��Ȃ��̂ŁA�A�_�ƒm�\�̊Ԃɐ[���W������Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B�uIQ�̍����l�ɒɕ������������v�Ƃ�������������悤�ł����A���v�I�ɐM���ł���f�[�^�͌�����܂���ł����i�R���ő��肳�ꂽ�m�\�ƔA�_�l�̊ԂɎア���ւ�����ꂽ�Ƃ���1959�N�̕�A���Z�ł̌������ʂɂ��ƔA�_�l�ƒm�\�̊Ԃɑ��ւ͂Ȃ����w�Ɛ��тƂ͑��ւ��������Ƃ���1970�N�̕Ȃ炠��܂��j�B�����Č����A�u�ɕ��ɂȂ����̂̓v�����̂̑����ґ�ȐH������������v���u�ґ�ȐH�����ł���͎̂Љ�I�ɐ������Ă���؋��v���u�Љ�I�ɐ������邽�߂ɂ͍����m�\�����ɗ��v�c�c�Ƃ��������ʘA���ɂ���āAIQ�ƔA�_�l�ɑ��ւ������邩������܂��A���ĂɂȂ�Ȃ������ł��B
�@�������A�i���_�I�Ɍ���ƁA�A�_�I�L�V�_�[�[�̌����Ɨސl���̒m�\�̍����ɂ́A�W�����肻���ł��B
�@�q�g��ȁi�q�g���܂ޗސl���j���\������q�g�ȁi�q�g�A�`���p���W�[�A�S�����A�I�����E�[�^���j�ƃe�i�K�U���Ȃ̋��ʑc�悪�����E�̃T�����番���̂́A2400�`2800���N�O�ł��B�A�_�I�L�V�_�[�[�̈�`�q�����������̂́A���̕����̂��ƂŁA�q�g�Ȃł�1500���N�O�A�e�i�K�U���Ȃł�900���N�O�Ɛ��肳��܂��B����������`�q�ψق��q�g�Ȃƃe�i�K�U���Ȃő������ŋN�����̂́A���̕��������Ƀv���X�ɂȂ�������ƍl����̂����R�ł��B���݂̐l�ނ̓v�����𑽂̂��܂ސH����ۂ邽�߂ɔA�_�l�������Ȃ肷���A���܂��܂ȕa�C�ɜ��₷���Ȃ��Ă��܂����A�ސl���ɂƂ��ẮA�A�_�̐����I�@�\�̂��������ɗL���ɓ������̂����ʂ������͂��ł��B���ɏd�v���ƍl������̂��A�A�_�̎��R�_����p�ł��B
�@�̓��ɑ��݂��銈���_�f�́A��`�q������Ȃǂ̗L�Q��p���y�ڂ��܂��B�������������_�f�̎_����p��}������̂��R�_�������ł���A�����̐����ł́A�A�X�R���r���_�i�r�^�~���b�j�����p����܂��B�������A�쒷�ނȂǚM���ނ̈ꕔ�ł́A�A�X�R���r���_�̍����\�������Ă��܂��B�쒷�ނ͈�ʂɎ��㐶�������Ă���A�A�X�R���r���_�𑽗ʂɊܗL����ʕ����D��ŐH�ׂ邽�߁A�̓��ō����ł��Ȃ��Ă���肪�Ȃ������̂ł��傤�B
�@�Ƃ��낪�A�쒷�ނ̒��Ɏ��o�@�\�����コ����������L�߂���̂������ƁA����ς��܂��B
�@�M���ނ́A�����̑S�����ɓo�ꂵ���̂ŁA���ԂɊ������鋰���������悤�ɖ�s���ɂȂ�܂����B���̂��߁A���s���̋����i����сA���̎q���ł��钹�ށj�ɔ�ׂĎ��͂��キ�A����ɗD�ꂽ�k�o�������Ă��܂��B�����̐�Ō�A�����̚M���ނ����������s���ɕω����Ă����܂����A���͂͑��ς�炸�キ�A�����S��ނ̌���e�^���p�N���ɂ��S���F�̐F�o�����̂ɑ��āA�Q���F�̐F�o��������܂���ł����B�����������ŁA�쒷�ނ́A�ˑR�ψقɂ���ĂR�Ԗڂ̌���e�^���p�N������肾���A�R���F�̐F�o���l�����܂����B���͂����サ�����ƂŁA��ʂ̎��o�����헪�ɗ��p�ł���悤�ɂȂ�A���̏����������邽�߂ɑ�]�̎��o�삪���B�����ƍl�����܂��B���ꂪ�A�쒷�ނ̒m�\��i�������邫�������ƂȂ����̂ł��傤�B
�@���サ�����o�𗘗p���邱�Ƃŗ쒷�ނ̊����悪�L����A�������˂𗁂т���Ő������邱�Ƃ������Ȃ�܂������A�����Ȃ�ƁA���O���̍�p�Ŕ畆�̊����_�f�������܂��B�H������ێ悷��A�X�R���r���_�����ł͍R�_������������Ȃ��Ȃ�A���ʓI�ɁA�A�_�I�L�V�_�[�[�������čR�_����p�̂���A�_�����Z�x�ɂȂ����̂̕��������ɗL���ɂȂ�܂��B�܂�A�ˑR�ψقɂ���Č���e�^���p�N���̎�ނ��������Ƃ����P��̌����ɂ���āA�ސl���ɂ�����m�\�̌���ƔA�_�̒~�ς̗������n�܂����Ƃ����킯�ł��B�A�_���m�\���������錴���Ƃ͌����܂��A�A�_�ƒm�\�̕s�v�c�Ȋւ�荇���Ƃ����Ƃ���ł��傤���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�X�s�m�U�̒���́A���Z���̍��Ɂw�G�`�J�x��ǂ����������̂ŁA���̋@��Ɂw�G�`�J�x���ēǂ��A�w�m�����P�_�x�Ɓw�����_�x�̈ꕔ�ɖڂ�ʂ��Ă݂܂����i��������A�w���C�h�Ő��E�̑�v�z04 �X�s�m�U�x�i�͏o���[�V�Ёj���G���̖{�ł́A�w�ϗ��w�i�G�e�B�J�j�x�Ƃ����^�C�g���ɂȂ��Ă��܂����A�����ł́A��g���ɂŊ���e���w�G�`�J�x��p���܂��j�B�̂́A�X�s�m�U�͎����I�Ȗ��_�_�҂��Ƃ����A�悭����ᔻ�ɓ��ӂ��Ă��܂������A���߂ēǂݒ����ƁA�ނ���Ȋw�I�Ȉꌳ�_�̘g���ł����ɐM���m�ۂ��邩�Ƃ�������^���ɍl�����A���I�ȓN�w�҂������Ƃ̊����������܂��B
�@�Ȋw�́A�L���X�g���̂悤�Ɋ�Ղ�M�̊�ՂƂ���@���Ƃ́A�������悭����܂���B�Ȋw�͕��Ր����d�����A��ՂƂ����`�ł̖@���̔j���e�F���Ȃ�����ł��B�Ƃ��낪�A�X�s�m�U�́A�@���Ƃł���Ȃ���A��Ղ͂������̂��ƁA�_�ɂ��n���⍰�̎��݂�F�߂܂���B���̎v�z�̍������Ȃ��̂́A�u���̂̒P�ꐫ�v�ɂ��Ă̐M�O�ł���A���E�ɂ����邳�܂��܂ȏo�����́A�l�Ԃ̈ӎ����܂߂āA�B��̎��̂������ϗe���ƌ��Ȃ��܂��B���̍l�����́A�ʎq��i���邢�͗ʎq�_�I�ȃ��[�v��Ђ��j��B��̎��̂ƌ��Ȃ��A������o�����͂����ɐ����錻�ۂ��ƍl����A���㕨���w�҂̐��E�ςɒʂ���Ƃ������܂��B
�@�w�G�`�J�x�́A���������v�z��̌n�I�Ɏ��������̂ł��i�\���̓��[�N���b�h���_��͕킵�Ă��܂����A�u�ؖ��v�Ə̂������̂͌���������͂قlj����̂ŁA�_���I�ȋA���ł͂Ȃ��P�Ȃ�咣�Ƃ��Ĉ��p���܂��j�B
�@���̂̒P�ꐫ�́A���̃V���v���Ȗ���ɂ���ĕ\����܂��B
�u�_���̂����đ��ɂ́A�����Ȃ���̂����݂����Ȃ����A�܂��A�l���������Ȃ��v�i��P���藝�P�S�j
�����ň����Ƃ���̐_�Ƃ́A�L���X�g���I�ȑn�����Ղ��i��_�ł͂Ȃ��A���ꎩ�g�̖@���ɏ]���ĕϗe����B��̎��̂��Ӗ����܂��B
�@����ɁA���̒藝�̌n�Ƃ��āA���̖��肪�咣����܂��B
�u�������������Ǝv�҂��鎖���Ƃ́A�_�̑����ł��邩�A�łȂ���A�_�̑����̕ϗe�ł��邩�A���̂����ꂩ�ł���v�i�藝�P�S�̌n�Q�j
�������������Ƃ́i�P�������Č����j�����̂��ƁA�v�҂��鎖���Ƃ͐��_�̂��Ƃł��B���̎咣�́A�l�Ԃ��e�l���Ɨ��������̂ł͂Ȃ��A�B��̎��̂ł���_�̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��܈ӂ��܂��B
�@�f�J���g�́A�����Ɛ��_�̓_����܂������A���҂��֘A�����������I�ȗ��R���������Ƃ��ł����A���ʑ̂ő��ݍ�p����Ƃ������������ȋc�_�������o������܂���ł����i�X�s�m�U�́A�w�G�`�J�x��T���ŁA�َ��Ȏ��̂͑��ݍ�p�ł��Ȃ��Ƃ����l������ɁA�f�J���g�̋c�_���������ᔻ���Ă��܂��j�B���C�v�j�b�c�́A�َ��Ȏ��̂Ƃ����T�O��r�����A���i�h�_�Ɋ�Â�����I�Ȑ��E�ς̍\�z��ڎw�������̂́A���̎咣�͓���ŁA�����I�ȉ��߂͂ł������ɂ���܂���B����ɑ��āA�X�s�m�U�́A�����Ɛ��_�͒P��̎��̗̂L����قȂ鑤�ʂƂ��āA�����ɐ������܂��B
�@�X�s�m�U�́A�l�Ԃ̎��R�ӎu���ے肵�܂��B�u���R�̂����ɁA���ЂƂ��R�Ȃ��̂͂Ȃ��v�i��P���藝�Q�X�j�Ƃ����ϓ_����A���ׂĂ��@���I�ȕK�R���ɏ]���ƌ��Ȃ���܂��B�l�Ԃ̍s�ׂ��A�ӎu�������ł͂Ȃ��i��P���藝�R�Q�j�A���̖̂@���ɏ]�����K�R���Ƃ����l���ł��B
�@���������K�R���Ɏx�z����Ȃ���A�Ȃ����_�����ɉ��l�����o����悤�ɁA�X�s�m�U�́A�����I�Ȏv�l�����̖̂@���ƌ��т���c�_��W�J���܂��B
�u�����́A�������A����Ήi���̎p�̂��Ƃɔc������{���������Ă���v�i��Q���藝�S�S�̌n�Q�j
�u���_�́A���ׂĂ̐g�̕ϗe�A�܂��͎����̕\�ۑ����A�_�̊ϔO�ɊW����悤�ɂ����邱�Ƃ��ł���v�i��T���藝�P�S�j
�������A���́A���������咣�ɃX�s�m�U�̌��E�����܂��B�w�G�`�J�x�㔼�́A���̂̒P�ꐫ��F�߂���Ŋ����ӎu���ǂ̂悤�ɉ��߂��ׂ����A���Ȃ�`���I�Ȍ��������X�ƊJ���Ă��܂����A���܂�����͂�����Ƃ͎v���܂���B����l���w�G�`�J�x��ǂޏꍇ�A��P���Ƒ�Q�������ŏ[���ł��傤�B
�@��ʓI�Ȏv�z�j�ɂ��A�X�s�m�U�́A17-18���I�ɂ͔ᔻ�i�ƌ������͔l�|�j�̑ΏۂƂ���Ă������̂́A19���I�ɂ����鍇����`�I�Ȏ��R�ς̑䓪�ƂƂ��ɍĕ]�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B�������A�ߑ�Ȋw�ւ̒��ړI�ȉe�������������ǂ����́A���Ƃ������܂���B�ނ̍l�����ɁA�Ȋw�I���E�ςƒʒꂷ����̂����邱�Ƃ͊m���ł����A�A�C���V���^�C�����X�s�m�U��]���������Ƃ͎����ł��傤���A���������X�s�m�U��ǂ��Ƃ̂���Ȋw�҂��ǂꂾ������̂��A������ƐS���Ȃ��v���܂��i���{�l�Ȋw�҂́A��قǂ̕��D���ȊO�A�܂��ǂ�ł��Ȃ��ł��傤�j�B�ߑ�I�ȉȊw����������ۂ̍v���x�Ō����A�^���ʂ�^���G�l���M�[�Ȃǂ̃A�C�f�A���Ă����f�J���g��C�v�j�b�c�Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�܂���B
�@����ł��X�s�m�U�̎咣�����͓I�Ɋ�������̂́A�ؖ��ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ɐ��w�I�ɏؖ����ꂽ���̂悤�ȓ��X����_���A��̓I�ȍ������R�����ɂ�������炸�A���̂̒P�ꐫ���ΓI�Ȑ^���ƌ��Ȃ����M�ɖ����������ɁA�O�C�O�C�ƈ������܂�Ă��܂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B�u������o�����́A�P��̎��̂��K�R�I�Ȗ@���ɏ]���Ĉ����N�������ۂ��v�ƐM���Ă����Ƃ��Ă��A�����咣���邱�Ƃɑ����Ȃ�Ƃ����߂������o����̂́A�Ȋw�҂ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���R�Ȃ��Ƃł��傤�B�������A�����������߂�������o�����������Ȃ��X�s�m�U�̌����ɂ́A��͂�h�ӂ킸�ɂ͂����܂���B
�@���łɌ����A�v�z�ƂƂ��ẴX�s�m�U�ɂ́A�����Ƃ̗ގ������w�E�ł��܂��B�����́A�����@�̊J�c�Ƃ���銙�q����̑T�m�ł����A���̐��E�ς́A������������I�ȓ��e�ł��B�Ⴆ�A���E���P��̎��́i�_�ł͂Ȃ����j���琬��Ƃ��������́A�w���@�ᑠ�x��V���u��������v�Ŏ�����܂����A�l�Ԃ��Ɨ������̂ł͂Ȃ����̂̈�̌���i�����j�ł��邱�Ƃ��A��P���u�������āv���R���u�����v�Ō���܂��B���̌l�I�Ȋ��z�������A�X�s�m�U���������̎v�z�̕������ɍ����Ă��܂��i�u���Ԃ͗���Ȃ��v�Ƃ��u��Ԃɋ��E���Ȃ��v�Ƃ��������Θ_�I�ȁi�H�j�咣������܂����j�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�u���͂̊��ɂ���f�ނ�����p���āA�������g���ۂ��ƃR�s�[����v�Ƃ����Ӗ��ł̎��ȑ��B���\�Ȃ̂́A�����炭���������ł��B�������A�g���B�h�����������L���Ӗ��ʼn��߂���Ȃ�A�Y�����錻�ۂ͂���܂��B
�@�܂��A�E�B���X�̃P�[�X�B�E�B���X�́ADNA��RNA�̂悤�Ȋj�_�̒f�Ђ��^���p�N���ɕ���ꂽ���̂ŁA��ӂ⎩�ȑ��B���s��Ȃ��̂ŁA�����w�I�ɂ͐����̔��e�ɓ���܂���B�E�B���X�����B�ł���̂́A�����Ɋ��ĕK�v�ȋ@�\���ؗp���邩��ł��B�������A�E�B���X�̒��ɂ́A�傫�����~�N�����P�ʁA��`�q��^���ە��݂ɐ���i�咰�ۂ�4289�Ȃ̂ɑ��āA�p���h���E�B���X��2556�j������E�B���X�����܂����A�ۂɂ��A���ȑ��B�ł����ɂق��̐����̋@�\����đ�������̂��������Ă���A�ۂƃE�B���X�̈Ⴂ�͂���قǖ��m�ł͂���܂���B���ȑ��B�̊T�O���g�����āA�E�B���X���u�L���Ӗ��ł̎��ȑ��B�v���s���������ƌ��Ȃ����Ƃ��\��������܂���i���邢�́A���ȑ��B����̂����琶���ƌ����ׂ��ł��傤���H�j�B
�@���w�����ł́A���т����B�ɋ߂��U�镑���������܂��B�S�̐Ԃ��тƂ́A�����ɗn���o�����S�C�I�����_������A���_����P�S�iFe(OH)
2�j�A���_����Q�S�iFe(OH)
3�j���o�āA�I�L�V���_���S�iFeOOH�j�ȂǂɂȂ������̂ł����A����́A�������̌����^�����݂��鑽�E���̏�Ԃł��B�\�ʂɖh���щ��H���{�������i�ł��A�������ĐԂ��т��ł��͂��߂�ƁA���E���̂��߂ɐ����Ǝ_�f�����߂��ēS�̑f�n�ɒB���A����ɓS�̎_�����i�݂܂��B�Ԃ��т̕����͐Ǝ�Ń{���{���Ɣ��������邽�߁A���т����B���ēS��Z�H���Ă���悤�Ɍ����܂��B���ۂɂ́A�_�����A���I�ɋN���Ă��邾���ő��B�ł͂Ȃ��̂ł����A�u���т����т��Ăԁv�Ƃ����_�ő��B�ɋ߂����̂�����܂��B
�@������J���A���тƓ����悤�Ɂu�i�q���ׂ��i�q���ׂ��Ăԁv���Ƃɂ���Đ����錻�ۂł��B���������́A�������q���K�������������̂ł����A�ʏ�́A���X�ɔz��̗��ꂽ�i�q���ׂ����݂��܂��B�����������ׂ́A�U����Ă���Α債�Ĉ����͂��܂���B�������A�j���̓����������N�C�N�C�Ɖ��x���܂�Ȃ���ꍇ�̂悤�ɁA�ǂ����ɉ��͂��W�����ČJ��Ԃ��ό`�����ƁA���̕����Ɋi�q���ׂ��ړ����܂��B���傤�ǁA�O�~���̂��̂����͓̂���Ă��A�O�~�̕����オ���g���h�����Ȃ�ȒP�ɏꏊ��ς�����悤�ɁA���q�z��̗��ꂽ���������Ȃ珬���ȃG�l���M�[�ňړ��������邩��ł��B�����Ȃ�ƁA���̕����̋��x���ቺ���ĕό`���₷���Ȃ�̂ŁA�i�q���ׂ����������W�܂�₷���Ȃ�܂��B���̌��ʂ��A�ʏ�̋����Ȃ�Ας�����͂��̏����ȗ͂ŊȒP�ɔj�f����Ƃ����u������J�v���N����킯�ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���̒ʂ�A���ː����o��������p�ɂ��u���ː������v���N���܂��B���d�͋�ԂV����P�̗��q�i�����q�̂悤�ȗL���̎��������f���q����˔\�������q�j�j�����ː�����ꍇ�́A���q�̕���Ɋւ���^���ʕۑ��������ړK�p�ł��܂��B���̂Ƃ��A��������G�l���M�[�̒l�����ʌ����ɂ���Ċm�肷�邽�߁A�P�̗��q���Q�ɕ���Q�̕���Ȃ�A����O�̉^���ʂƕ����ɂ�����^���ʂ̘a���������ƒu�������ŁA�����̍ۂ̏��������߂��܂��B
�@���q�̕��ː�����̏ꍇ�A�A���t�@����Ȃ�A���Ȃ�傫�Ȕ������܂��B�x�[�^�����K���}����ɂȂ�ƁA�����͔�r�I�������Ȃ�܂����A����ł����w�����̃G�l���M�[���͂����Ƒ傫�ȃG�l���M�[���l�����܂��B���̂��߁A�������ŕ��ː�������������q�́A������u�z�b�g�A�g���v�̏�ԂɂȂ�܂��B�z�b�g�A�g���́A���̌��q�����傫�ȉ^���G�l���M�[�������Ă�����A���q�����ɂ���d�q�̃G�l���M�[��Ԃ��ُ�ɂȂ����肵�Ă���A�ʏ�ł͌����Ȃ����w�������N�������Ƃ�����܂��B
�@���ː������́A����������s���ꍇ�ɏd�v�ɂȂ�܂��B1960�N�A��ʑ��Θ_����\�z�����d�͐ԕ��Έځi���̐U�������d�͌�����̋����ɂ���ĕω�������ʁj�̌��؎������s���܂������A�����Ŗ��ƂȂ����̂��A���ː������̉e���ł����B���̎����ł́A���ː����q������o�����K���}���̐U�������A���x�ɂ���Ăǂ̂悤�ɕω����邩�����肳��܂����B���q�����S�ɌŒ肳��Ă���A���˒���̃K���}���̐U�����͊m�肵���l�ɂȂ�̂ŁA�����̈ʒu�����苗���̍����ɑ��葕�u��u���ĐU�������ϑ�����A�d�͐ԕ��Έڂ̑傫�����킩��͂��ł��B�������A���ۂɂ́A���q�͕��ː����������邽�߁A���˒���̃K���}���̐U�������A�g���������ꍇ�̌����ɏ]���ĕω����܂��B�d�͐ԕ��Έڂ̌��ɂ�1000������1�̐��x���K�v���������߁A�����҂͂��낢��ƍH�v���A�ŏI�I�ɂ́A���������ő��̌��q�ƌł��������邽�ߔ������N�����ɂ����S�̓��ʑ̂��g�p���邱�ƂŁA�d�͐ԕ��Έڂ̌��o�ɐ������܂����B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�v���X�`�b�N�́A��ɐΖ���������L�@�������ł���A�����̏ꍇ�A�����ɑ���e�a���������Ă��܂��B���̂��Ƃ́A�������������̐H��ɔ�ׂāA�v���X�`�b�N���̐H�킪�x�^�x�^������������z�����₷���A���Ƃ��̂ɋ�J�������邱�Ƃ�����킩��Ǝv���܂��B��ɂ��̐������A�����ɕ��o���ꂽ�v���X�`�b�N���댯�Ȃ��̂ɂ��Ă���̂ł��B
�@�_�C�I�L�V����`������APCB�ADDT�ȂǁA20���I�ɎЉ���ƂȂ����L�@�n���������̑������A���ɗn�����ɖ��ƍ�����₷���Ƃ��������������Ă��܂��B�������������������ɕ��o�����ƁA���ɗn���Ȃ����߂ɐ����Ŕ����g�U�����t�H�ƂȂ��Ă��܂ł��Y���܂��B��������ێ�E�z�������ꍇ�A�ق��̗L�ŕ����̂悤�ɔA�ɗn�����đ̊O�ɔr�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A���b�g�D�ɂǂ�ǂ�~�ς���Ă����u���̔Z�k�v���N�����܂��B���`�����₪�����_�o�n�ɔZ�k�����Ɛ_�o�����Q���܂����A�̑���牺���b�ɒ~�ς��ꂽ�_�C�I�L�V����PCB�́A�Ɖu�n��B�@�\�Ɉ��e�����y�ڂ��̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B
�@�v���X�`�b�N�́A�������ł���L�@�n����������\�ʂɋz�����܂��B�A�U���V��C���J�̂悤�ȁA�̎��b���̍����C���M���ނ̑̓��ɁAPCB��DDT���Z�k����Ă���Ƃ����f�[�^������A���̐N���o�H�͔������Ă��܂��A�C���ɕY���}�C�N���v���X�`�b�N����݂��Ă��邩������܂���B�܂��A�v���X�`�b�N�ƍ����Ďg���L�@�n�̓Y�����i��R�܂��܂Ȃǁj�́A�����̑̓��Ŏ��b�Ɉڍs���₷���̂ŁA���������ƂȂ�\��������܂��B
�@���W�܂̂悤�ȑ傫�ȃv���X�`�b�N���i���A�J����N�W���Ȃǂ̊C�m�����ɕ�H����ď�������l�܂点�邱�Ƃ�����܂��B�E�~�K���́A�C���ł���瓮���N���Q��C����H�ׂ�K��������A������ł��郌�W�܂̓G�T�Ɍ�����悤�ł��B�����قōs��ꂽ�����̉f���ɂ́A�E�~�K�������W�܂ɐH�����ĂȂ��Ȃ��������Ƃ��Ȃ����i���f���Ă��܂����B
�@������K���X�̏ꍇ�A�������ꂸ�Ɋ����Ɏc�����Ă��A��d���傫������ɒ��ނ̂ŁA�C�m����������ĐH�ׂ�P�[�X�͂���قǑ����Ȃ��Ǝv���܂��B�����́A�L�Q�ȃC�I�����邱�Ƃ�����܂����A���ɗn���Ċg�U���Z�x���[���ɒႭ�Ȃ邽�߁A�L������Ȃ炻��قNJ댯�ł͂���܂���i�D��Ȃǂɓh�z�����L�@�h�������������ƂȂ�ꍇ�͂���܂��j�B�܂��A�����͉���E�ė��p����r�I�e�Ղł���A���T�C�N��������ȃv���X�`�b�N�قǐ[���Ȗ��ɂȂ�ɂ����Ƃ������������܂��B�K���X�̏ꍇ�́A�g�̂��鐅���łׂ͍����ӂ��Ċp���ۂ��Ȃ�̂ŁA�C�m���������ݍ���ł��A�唼�͂��̂܂ܔr������܂��B
�@��Ɠ��������ł���Ȃ���A�ׂ��@�ۏ������߂ɔx�E�ɓ˂��h�����Ĕx����̌����ƂȂ����A�X�x�X�g�̂悤�ɁA���w�Ő��͂Ȃ��Ă����m�̊댯�����߂����������邩������܂��A���݂̂Ƃ���́A���̔Z�k�������N�����L�@���������ǂ����邩���A�i�ق̉ۑ肾�ƌ�����ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���̌`�Ƃ͉��ł��傤���H �ł��킩��₷���̂́A�ڂŌ������ŐG�����肵���Ƃ��̋��E�̌`�ł��傤�B�����������E�́A�u���������݂���̈�Ƒ��݂��Ȃ��̈�̋��v�ł͂���܂���B�ڂŌ���ꍇ�́A�������˂Ȃ������˂����̈�A��ŐG��ꍇ�́A�ڋ߂����Ƃ��ɓd�C�I�Ȑ˗͂��}�ɋ����Ȃ�̈�̂��Ƃł���A�ǂ�������ݍ�p�Ɋ�Â��Č��߂���̂ł��B�܂��A�ڂŌ�������Ƃ����ĕ��̌`�����ړI�ɔF�m�ł���킯�ł͂Ȃ��A�Ԗ��Ɍ������˂������ƂŐ������_�o�������]���o��ōč\���������ʂ��A�w�I�Ȍ`��Ƃ��ăC���[�W�����̂ł��B
�@���q�̌`�ɂ��Ă��A�����悤�Ȏ������܂��B���q�́A���S���ɂ���߂ď������ďd�����q�j������A���̎��͂Ɍy���d�q���L�����z����Ƃ����\���ɂȂ��Ă��܂��B�d�q�̏Ǝ˂�d���̈���Ȃǂɂ���Č��q�̏�Ԃׂ�ꍇ�A���ݍ�p�͎��́i�ʏ�͊O�k�j�ɂ���d�q�ɂ���Đ�����̂ŁA�f�[�^�Ƃ��ē�����̂́A���������d�q���ǂ̂悤�ɕ��z���邩�ł��B�������A�P�̓d�q�Ɋւ������͓̂���A�����̓d�q���֗^����v���Z�X��ʂ��đ�����s���̂ŁA���v�I�ȃf�[�^���������܂���B
�@���q�̌`�ׂ�ɂ́A���w�������ɂ�������̑���ɓd�q�r�[����p���铧�ߌ^�d�q�������̂ق��A�����^�d�q�������i�d�q�r�[�����Ǝ˂�������������o�����M���d�q�����o�j����^�v���[�u�������i�Z�j�������ɐڋ߂������Ƃ��̃g���l���d����J���`���o�[�̂���݂����o�j���p�����܂��B���ߌ^�̌������Ȃ�A�����q�̉摜���_�C���N�g�ɓ��邱�Ƃ��\�ł����A�����^�ɂȂ�ƁA���o���ꂽ�M�����R���s���[�^�ŏ����������ʂ��A���q�̌`��\���ʐ^�Ƃ��Č��\����܂��i�ڂŌ���Ƃ��A�Ԗ�����̐M�����]���o��ŏ������Ď��o����̂Ɠ��l�ł��j�B���������āA���q�̎ʐ^�ƌ����Ă��A�����́A����f�[�^�����Ƃɓ��v�I�ȓd�q���z���č\���������̂ł��B
�@���������̓d�q�������ʐ^�ł́A�i���`�Ƃ͌���Ȃ��܂ł��j�ۂ��������q���K���������z�Ă��邱�Ƃ�������܂��B���̊ۂ��������q�́A���̓����ɉ������l�܂��Ă���̈�ł͂Ȃ��A���ݍ�p�Ɋւ��d�q�����z����͈͂�\���ƌ��Ȃ��ׂ��ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���z�d�r�́A�������G�l���M�[�̈ꕔ��d�͂ɕϊ����鑕�u�Ȃ̂ŁA���˂�}���ċz�������M�ɂ���ꍇ�ɔ�ׂ�ƁA�d�C�g�[��ʂ��Č��G�l���M�[��M�ɕϊ�����Ƃ��̌����́A�y���ɒႭ�Ȃ�܂��B
�@���z�d�r�̌����i2018�N���݁j�́A�s�̕i��10����㔼����20�����������ł��B�s�̕i�̑唼�̓V���R���n�ŁA�ϊ������͍����i�ō��ŃZ���ϊ�����25�����x�j���R�X�g�������P�����V���R���͈ȑO�قǎg���Ȃ��Ȃ�A�������Ⴍ�Ă����i�̈����������V���R����A�����t�@�X�V���R�����嗬�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A����C���W�E���Ȃǂ̉������𔖖��ɂ����������n���J������Ă��܂����A�R�X�g�������A�f�ނɂ���Ă͓Ő�������̂ŁA�Z��p�Ƃ��Ă͕��y���Ă��܂���B�z��������̔g�����قȂ鉻�����n���z�d�r�̔��������w�ɂ��d�˂����������ڍ��W���^�ɂȂ�ƁA�ϊ������͂���ɍ����Ȃ�܂��i�ō���45���j�BNEDO�i�V�G�l���M�[�Y�ƋZ�p�����J���@�\�j�́A�����ڕW�Ƃ��āA2025�N�̕ϊ��������A�����^��30���A���������ڍ��W���^��50���Ƃ��Ă��܂��B
�@���z�d�r�̃����b�g�́A���̂܂܂ł͗��p���@�������鑾�z�����A�l�ԂɂƂ��Ďg������̗ǂ��d�C�G�l���M�[�ɕϊ�����_�ł��B�ď�́A�����ւ̓��˂�h���ŗ�[�ɗ��p���邱�Ƃ��\�ł��B�����I�ɂ́A�l�H�I�Ȍ������ɂ���āA���w�G�l���M�[�ɕϊ����铹�����ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�u���{�b�g�H�w�O�����v�́A�A�V���t�̒Z�ҏW�w���̓��{�b�g�x�i1950�N�j�Œ���A���ҁw�|�S�s�s�x�i54�N�j�Ŗ{�i�I�ɉ��p���ꂽ���̂ł��B�������A���{�b�g�H�w�iRobotics�j�ƌĂ�Ă�����̂́A�����͂܂��A�l�H�m�\�Ƃ����T�O�̂Ȃ����������ł��B���E�ŏ��̃v���O���������^�R���s���[�^EDVAC���ғ������̂�1953�N�ŁA����ȑO�ɍ��ꂽENIAC�́A�z���ƃX�C�b�`���ւ��ē���̃A���S���Y�������s����Ƃ������̂ł����B�`���[�����O���u�`���[�����O�E�e�X�g�v���l�Ă����̂�1950�N�A�}�b�J�[�V�[���l�H�m�\�Ƃ����p���������̂�1956�N�B���������āA�����ɉȊw�I�m���ɕx�ރA�V���t�Ƃ����ǂ��A���{�b�g�ɔ��f�͂�^����悤�ȋZ�p��z�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ł��傤�B
�@���{�b�g�H�w�O�����̑�P���́A�u���{�b�g�͐l�ԂɊ�Q�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƂȂ��Ă��܂��B�������A�l�ԂƂ͉����A�ǂ�ȓ��삪�u��Q��������v���Ƃɑ�������̂��A���{�b�g�����͂Ŕ��f���邱�Ƃ́A�����������s�\�ł��B�������A���̌������u�l�ԂɊ�Q��������悤�ȋ@�B������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����i���肫����ȁj�Z�p�җϗ��ɓǂݑւ��邱�Ƃ͉\�ł��B�������A�����̐��E�ł́A���܂��܂ȎE�����킪�ʎY����Ă���A���̌��������炳��邱�Ƃ͂��蓾�܂���B�ŋ߂ł́A��F���@�\�ɂ���ĕW�I�������I�ɒT�����U������AAI���ڂ̈ÎE�h���[���̊J�����i�߂��Ă��܂��B
�@����ł́A�A�V���t�ƃL�����x���́A�Ȃ����{�b�g�H�w�O�����Ȃ���̂�����̂ł��傤���B�����炭�A�Z�p�I�l�@�ƌ����������w�I�ȊS�������������炾�Ǝv���܂��B���ɁA�A�V���t�́A�w����ƒw偂̉�x���͂��߂Ƃ���~�X�e�������������M���Ă���A���̃W�������ɐV���𐁂����݂����Ƃ����ӗ~���������̂ł��傤�B�����Ŏv�������̂��A���{�b�g���ƍ߂�Ƃ��Ƃ����X�g�[���[�ł��B���{�b�g�́A�`���y�b�N�̋Y�ȁwR.U.R.�x�i1920�N�j�ŁA�@�B�ł���Ȃ���l�Ԃɑ��Ĕ��R���鑶�݂Ƃ��ĕ`����Ă���A�V���ȃ~�X�e����n�삷��ɂ͂����Ă��̑f�ނ������̂ł��B
�@�u�l�ԂɊ�Q�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������͓�����O�����āA�����Ėʔ������̂ł͂���܂���B�������A���̌����̉��Őv����Ȃ���A�Ȃ������{�b�g���E�l��Ƃ����|�|�Ƃ����~�X�e���́A�a�V�ŃX�������O�ł��B�O�����̏̓L�����x���ƃA�V���t�����͂��č�����̂�������܂��A�������Ƀ~�X�e�������グ���̂̓A�V���t�̎�r�ł��傤�i�L�����x���̏����́A��̂Ɂu�e���s���v�Ȃǂ�ǂL��������܂����A�ҏW�҂Ƃ��Ă͂Ƃ����������ƂƂ��Ắu���`��c�v�Ƃ��������ł��j�B���́A�O�����Ɋւ��āA�����ăL�����x���̖���t��������K�v�͂Ȃ��ƍl���܂��B
�@���łɁA�u�n�b�u���E�����[�g���̖@���v�ɂ��Ă��R�����g���Ă����܂��B
�@���̖@���́A�����̋�͂̌�ޑ��x�Ƌ����̊Ԃɔ��W������Ƃ������̂ł����A���͌�ޑ��x�̕����I�ȈӖ��ɂ���܂��B1910�N�ォ��20�N��ɂ����āA�X���C�t�@�[��n�b�u���ɂ��Q����́i�����͐��_���Ǝv���Ă����j�̊ϑ����n���I�ɍs���A�����̋�͂قnj��q�X�y�N�g�����傫�Ȑԕ��Έځi�g�����L�т�悤�Ȃ���j���������Ƃ��������܂����B���̂��ꂪ�����̉^���ɂ��h�b�v���[���ʂ��Ɖ��߂���ƁA�V�̐��͂Ƃ̊Ԃ̋������傫���Ȃ�قǍ����ʼn������邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�n�b�u���͂���Ɋϑ��𑱂��A1929�N�ɁA�h�b�v���[���ʂƉ��߂����Ƃ��̑��x�Ƌ�͂܂ł̋��������W�ɂ���Ƃ������ʂ\���܂����B
�@�������A���̂Ƃ��n�b�u���́A�h�W�b�^�[����Ă����F�����f���Ɋ�Â��A�����ł̎��Ԍo�߂��x���Ȃ邽�߂ɐԕ��Έڂ�������Ƃ������߁i����сA�������q�ɂ��U���̌��ʂƂ����A���݂ł͂�����Ɨ������Â炢�\���j�ɂ��ăR�����g���������ŁA�F���S�̂��c������Ƃ����A�C�f�A�ɂ͐G��Ă��܂���B
�@�Ƃ��낪�A�����[�g���̕��́A1927�N�ɁA�F���S�̂��c������Ƃ������_���\�z�A���̗��_�Ɋ�Â��āi����ȑO�ɒ�o����Ă����j�X���C�t�@�[��n�b�u���̊ϑ��f�[�^�����߂���_���\���Ă��܂����B���̘_���̓x���M�[�̃}�C�i�[�ȎG���Ɍf�ڂ��ꂽ���߁A�قƂ�ǂ̓V���w�҂��C�����܂���ł����B�n�b�u���̔��������Ԃ̎��ڂ��W�߂�1931�N�ɂȂ��āA�w�E�̑�䏊�������G�f�B���g���̊��߂Ń����[�g�����g���p���̂ł����A�n�b�u���̐V�����f�[�^�����\����Ă������炩�A�ϑ��f�[�^�̉��߂Ɋւ���L�q���폜���Ă��܂����̂ł��B���̂����ŁA�����ԁA�����[�g���̋Ɛт��ߏ��]������邱�ƂɂȂ����̂ł��B2011�N���ɂȂ��āA�폜�����������V���w�҂̊ԂōL���m����悤�ɂȂ�A�����[�g���̋Ɛт��ĕ]������܂����B
�@���������ƁA�n�b�u�������\�����f�[�^�ɂ́A�����s�R�ȓ_������܂��B�m�͂���܂��A�ǂ����A���W�Ɍ�����悤�Ɋϑ����ʂɏ�������������̂ł͂Ȃ����Ƌ^����̂ł��i���ɁA��N�̃n�}�\���Ƃ̋��������Łj�B����Ȏ��������̂ŁA�@���̖��̂�ύX����͎̂��R�Ȑ���s���ƌ�����ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���F���_�́A����ꂪ�����Ă����ԂR�����E���ԂP�����̉F���i�S�����F���j���A��荂�����̐��E�ɖ��ߍ��܂ꂽ���i�u���[���j�̂悤�Ȃ��̂��Ƃ����A�C�f�A�ɗR�����܂��B���̍l�������̂�1920�N�ォ�炠��܂����A���Ђ����_�ɂ���č��������E�̎������⑊�ݍ�p����̓I�ɘ_���铹�������Ƃ���A1990�N��ȍ~�ɂȂ��ĐϋɓI�Ɍ�������܂����B��\�I�Ȃ̂��A�T���E�����h�[���ɂ�郏�[�v�����]�莟�������F�����f���ł��B�������A�����I�ɓ����Ă���̒��Ђ����_�����̑ޒ��ɔ����A�ȑO�قǂ̐����͂Ȃ��悤�ł��B
�@���ۂ̐��E���������Ȃ̂ɁA����ꂪ�S�����F�������F���ł��Ȃ��̂́A������d���ꂪ���ׂĂS�����̓����ɑ�������Ă��邩�炾�Ƃ���܂��B�������A�d�͂͂S�������̊O���ɂ����ݏo���Ă���̂ŁA���������E�ɑ����̖��F�����������Ă���A���݂ɏd�͂��y�ڂ��\�����ے�ł��܂���B�����Ƃ��A�����h�[���̉F�����f���ɂ��ƁA���O���̏d�͖͂����牓������Ƌ}���Ɍ������邽�߁A���̉F���ɒ��ړI�ȉe�����y�ڂ����Ƃ͂���܂���B��͂ɂ́A�d���g�Ŋϑ��ł���V�̈ȊO�ɖc��ȏd�͌������݂��邱�Ƃ��A�F�������̕����̋ÏW�p�^�[������ӓV�̂̉^������\�z����Ă���A���̌��Ƃ��ă_�[�N�}�^�[����Ă���Ă��܂��B����ł́A�_�[�N�}�^�[�ł͂Ȃ��A�����̉F���̋ߗׂɂ��閌�F������̏d�͂��֗^����̂ł͂Ȃ����Ƃ̂��Ƃł����A���̖��F������̏d�͂͏������Ƃ��������h�[���̗��_�ʂ�Ȃ�A���̉\���͒Ⴂ�ł��傤�B�܂��A����F���_�ő�̓�ł���_�[�N�G�l���M�[���A���̖��F���ɋN�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�O���̖��F������e������\��������̂́A���F�����m�̏Փ˂ɂ���ăr�b�O�o����Ԃ�������Ƃ����P�[�X�ł��B�����Ƃ��A���̃A�C�f�A���A���ؓI�ȍ����͉����Ȃ��A�v�����ɋ߂��Ƃ����̂�����ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�����w�̋��ȏ��Ȃǂł́A�ʏ�A�ʎq��̔g�����͋c�_����܂���B�v�Z���邱�Ƃ��ϑ��ƌ��т��邱�Ƃ��ł����A���p�I�ɉ��̖������ʂ����Ȃ�����ł��B�������A���́A�u�f���q�Ƃ͉����v���l�����ŗL�p�Ȃ̂ŁA�����ď�̔g���������グ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�@�V�����f�B���K�[�̔g���͊w�ɂ��ƁA���q�i�d�q�ł͂Ȃ����z�I�ȑΏۂł��j�̔g�����́A���q�̈ʒu��q�Ƃ���ƃ�(q)�ƕ\����܂��B���̗��q���o�l�Ɍ��т��āAq=0 �ƂȂ�U�����S�̎���ŐU���� ν �̒P�U�����������ꍇ�A�G�l���M�[�� hν �̔������{�ɂȂ�܂��B����́A�P�U���������N�����́i�o�l�Ȃ�t�b�N�̖@���ɏ]���e���́j�ɂ���ė��q�̔g���U�����S�t�߂ɕ����߂��邽�߁A����̋���Ԃ��������I�ɂȂ蓾�邩��ł��B���̃G�l���M�[�́A��_�G�l���M�[��ʂɂ���A hν �Ƃ����G�l���M�[�ʎq���������݂���悤�ɃC���[�W�ł��܂��B
�@�}�N�X�E�F���d���C�w�ɂ�����d����̂悤�ɁA�����I�ȏ�́A�U�����Ȃ���`���Ƃ��������������܂��B�����ŁA������������A���q�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɃV�����f�B���K�[�̔g���͊w�ň������Ƃɂ��܂��傤�B��̋��x��Q�Ə����ƁA�g�����̓�(Q)�ƂȂ�܂��i��̋��x���ՂƏ����Ă��悢�̂ł����A�Ղƃ�������킵���̂ŁA��ʂ��₷���悤��Q�Ƃ��܂��j�B��́A Q=0 �ƂȂ�U�����S�̎���ŐU�����A����̋���Ԃ��������I�ɂȂ�܂��B��_�U���̎��ɃG�l���M�[���Ⴂ�̂́A�G�l���M�[�ʎq�i�����ꏊ�ŐU������Ƃ��̃G�l���M�[�Ɣg���ړ����邱�Ƃɂ��G�l���M�[�������������́j���P�������݂���P�[�X�ł��i�����w�I�Ɍ����Ȃ��Ƃ��������߂ɂ́A�J�荞�ݗ��_���K�v�ɂȂ�܂��j�B�ʎq�͊w�i�����q�̗ʎq�_�j�Ƃ́A�P�̃G�l���M�[�ʎq�𗱎q�ƌ��Ȃ��A������ꏊ�Œ�`������̋��xQ�̑���ɁA�G�l���M�[�ʎq�̈ʒuq���g���ď�̏�Ԃ��ߎ����闝�_�ł��B
�@�G�l���M�[�ʎq������������Ƃ��ɂ́A��ʂɁA���̊Ԃ̑��ݍ�p���l���Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���ݍ�p���[���Ɏア�Ȃ�A�܂����ݍ�p�����݂��Ȃ��Ƃ����ߎ��̉��ŕ����̃G�l���M�[�ʎq������ɓ������P�[�X��z�肵�A�������ɁA�G�l���M�[�ʎq�̑��ݍ�p�𒀎��I�Ɍv�Z������@���g���܂��B���̕��@���ۓ��@�ł��B�ۓ��@���g���ƁA�G�l���M�[�̉�ł���G�l���M�[�ʎq���������݂��A����炪�i�ʂ̑f���q���������Ȃ���j���ݍ�p���邩�̂悤�Ɉ����܂��B�ۓ��@�ɂ�����G�l���M�[�ʎq�́A���̂܂ܑf���q�Ɠ��ꎋ���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�ȑO�́A�ʎq��������ۂɂ͐ۓ��@���g���̂���ʓI�ł����B�ۓ��@���g���ꍇ�́A���ݍ�p���Ȃ����̂ƌ��Ȃ��Ƃ��납��X�^�[�g���܂����A���̒i�K�ł́A�������݂���G�l���M�[�ʎq�́A�����������R�ɔ�щ�闱�q�̂悤�Ɍ����܂��B���̂悤�Ȏ��R���q����щ���Ԃ�\�������̂��A�t�H�b�N��Ԃł��B���������āA�t�H�b�N��Ԃ��g���ꍇ�ɂ́A�ۓ��@�Ɋ�Â����q�`�����Öق̑O��ƂȂ�܂��B��̑��ݍ�p�́A�G�l���M�[�ʎq�i�����q�j���m�̑��ݍ�p�Ƃ��Ē����I�ɋߎ��v�Z���Ă����܂��B
�@�������A���݂ł́A�ۓ��@���ʗp���Ȃ������鏊�Ō������Ă��܂��B�Ⴆ�A�z�q�⒆���q�����̃N�H�[�N�ꂪ�ǂ��Ȃ��Ă��邩��_����Ƃ��A�܂����ݍ�p�����Ď��R�ɓ������N�H�[�N���l���A�����ɒ����I�ɑ��ݍ�p�̌��ʂ������Ă����|�|�Ƃ����c�_�͎g���܂���B�N�H�[�N�̎��͂ɃO���[�I����N�H�[�N�|���N�H�[�N�̏ꂪ�x�b�^���Ɗg���邽�߁A���ݍ�p������̂͌����ƑS����������A���̋ߎ��ɂ��Ȃ�Ȃ�����ł��B
�@���́A�ۓ��@�Ɋ�Â��c�_�i�Ⴆ�A�͂͑f���q���������邱�ƂŐ�����Ƃ��������́j�𑽗p����̂́A�u�f���q�����q�ł���v�Ƃ���������C���[�W���L�߂邽�߁A�D�܂����Ȃ��ƍl���܂��B���̂��߁A�ۓ��@�͂ł��邾���g�킸�A�o�l�Ɏ��t����ꂽ���q�̔g�����Ɠ����悤�ȃC���[�W�ŏ�̔g������\���悤�ɂ��Ă��܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���̖₢�ɑ��āA��ʓI�ȉ�^����͍̂���ł��B�ʓI�ȃP�[�X�Ō������Ȃ���Ȃ�܂���B
�@��Ƃ��āA�d���C�w���l���Ă݂܂��傤�B�I���O����m���Ă����d�C�E���C�E���Ɋւ��錻�ۘ_���A���̂S�̕������ɓ��������}�N�X�E�F���̓d���C�w�́A19���I�����w�̈�̓��B�_�ƌ����܂��B
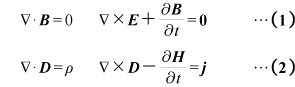
�i�L���̈Ӗ��́A�d���C�w�⑊�Θ_�̋��ȏ����Q�Ƃ��Ă��������B�ȉ����l�j
�@�Ƃ��낪�A20���I�ɓ����đ��Θ_�����������ƁA�}�N�X�E�F��������������ɊȌ��ɕ\�����Ƃ��\�ɂȂ�܂����B���Θ_�̍l�����ɏ]���ƁA���ԂƋ�ԁA�d�ז��x�Ɠd�����x�́A���ꂳ�ꂽ�P��̕����I�Ώۂł���A���ꂼ��S���x�N�g��x
μ�Aj
μ�iμ=0,1,2,3�j���g���ĕ\���̂��K�����Ƃ킩��܂��B�܂��A�d���C���ۂ̍����ɂ���̂��d���|�e���V����A
μ�ł���A�דd���q���������݂���^�̏ꍇ�A�d���|�e���V�����̔����Œ�`�����d����F
μν���d��
E�Ǝ���
B�̑���ɂȂ�܂��B
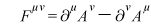
�@�P�����i�}�N�X�E�F����������(1)�ɑ����j��ʂɂ���ƁA�d���ꂪ�]���̂́A���̒P��̕������ł��i�}�N�X�E�F����������(2)�ɑ����B�W���́A�P�ʌn�ɂ���ĈقȂ�j�B

�@���̂悤�ɁA���Θ_�I�ȓd���C�w�́A���ԂƋ�Ԃ����ꂳ�ꂽ�Ώۂł��邱�Ƃ��I�ɕ\���Ă���A�]��������������߂ăV���v���Ȃ̂ŁA���E�̎��ԂɑΉ����Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A����������܂��B��Ɏ������悤�ȊȌ��Ȏ����g����̂́A�^�ɉדd���q���������݂���ꍇ�Ɍ����܂��B���q����\������镨�������݂���ꍇ�A�d�q�����q���ӂɑ�������邱�ƂɗR������U�d���ɂ�A�j�X�s���E�d�q�X�s���E�O���p�^���ʂȂǂ̌��ʂ������荇�������́A��������ʎq�_�I�Ȍ��ʂȂ̂ŁA�V���v���ȑ��Θ_�I�d���C�w�ł͈����܂���B
�@�}�N�X�E�F���d���C�w�́A�U�d���ɂ⎥���̌��ʂ��A�U�d���ⓧ�����Ȃǂ̌��ۘ_�I�ȕ����萔�ɋz�������ĕ\���Ă���̂ŁA�U�d�́E�����̂��܂ތ��ۂɂ��K�p�ł��A�����p���̍������_���ƌ����܂��B�������A�����܂Ō��ۘ_�I�ȋߎ����ł����Ȃ��A�U�d���ɂ⎥�����ǂ̂悤�ɋN���邩�́A�ʎq�_�����p����K�v������܂��B
�@��w�ŏK���ʎq�͊w�i�d�q�⌴�q�j�Ȃǂ̗��q��ΏۂƂ���ʎq�_�j�́A�U�d���ɂ⎥����������x�܂ň�������̂́A�����܂ŔΘ_�I�ȋߎ��ł���A���[�����c�Ώ̐������d���C���ۂ̎��ԂɑΉ������L�q�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B���Θ_�I�ȑΏ̐����I�ɕ\�������_�͗ʎq�d���C�w�iQED�j�ł����A�v�Z���ُ�ɓ���A�S�����p�I�ł͂���܂���B�܂��A�ʎq�d���C�w���ߎ��I�ȗ��_�ɂ������A���S�ȗ��_�͂܂��������Ă��܂���i�����炭�A�i���Ɋ������܂���j�B
�@�܂�A�}�N�X�E�F���d���C�w�A���Θ_�I�d���C�w�A�Θ_�I�ʎq�͊w�A�ʎq�d���C�w�́A���Ԃ��I�ɕ\�����A�K�p�͈͂������邩�Ȃǂ̓_�ŁA���ꂼ��꒷��Z�ł���A�ǂꂩ�����E�̎��Ԃɍł��������Ƃ͌����܂���B
�@������A�ʎq�_�̒莮���ɂ��Ă��q�ׂĂ����܂��B�ʎq�_��莮��������@�ɂ́A�����ʎq���ƌo�H�ϕ��@�̂Q������܂��B�����ʎq���̕������w�I�ɂ������肵�Ă���A�������Ȍ��Ŗ��ʂ�����܂���B����A�o�H�ϕ��@�́A�U��������̐ϕ��Ȃ̂Ŏ������邩�ǂ����������A�c�_�̌������Ɍ����܂��B���������G�ŁA��̓I�Ȍv�Z�͂Ђǂ��킩��ɂ������̂ł��B
�@�������A���ۂ̖{���ړI�ɕ\���Ă���̂́A�����炭�o�H�ϕ��@�̕��ł��B�����ʎq���́A���܂��܂ȉ����ςݏd�˂邱�ƂŌ����̂�₱������������A���̌��ʂƂ��ĊȒP�Ȑ����ŕ\����悤�ɂ������̂ł��傤�i���͂����l���܂��j�B�����_�ł́A�����ʎq���ƌo�H�ϕ��@�͂قړ����ł���A���ȏ��ł́A���w�I�Ɍ����Ȑ����ʎq���̕�����ɋL�ڂ���܂����A�������Ȍ�������Ƃ����āA���E�̎��Ԃ�\���Ă���Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@2018�N11��16���ɍ��ۓx�ʍt����ŏ��F���ꂽ�V������`�@�ɂ��ƁA�v�����N�萔�͌덷�̂Ȃ����m�Ȑ��l�Œ�`����A1�L���O�����́A����U�����i�l�͈ȉ��ɋL���j�̌��q�����G�l���M�[�������̂Q��Ŋ��������̂Ƃ���܂����B�V��`��2019�N5��20���ɔ�������A�����ɁA�L���O�������킪�p�~����܂��B
�@�V������`�̊�ɂȂ�̂́A�������1905�N�ɃA�C���V���^�C�����������̂Q�̊W���ł��B
�@�@���ʂƃG�l���M�[�̊W�� E = mc
2�@�im�F�Î~���ʁAc�F�����j
�@�@�U����ν�̌��q�̃G�l���M�[ E=hν �ih�F�v�����N�萔�j
SI�P�ʌn��p����Ȃ�A�]���ȌW����t���Ȃ��Ă��A�����̎��͂��̂܂ܐ��藧���܂��B���������āA1�L���O�����́A����U����ν
0�ƌ���c�A�v�����N�萔h��p���ė^�����܂��B
�@�@�L���O�����̒�`�@1[kg]=ν
0 × h/c
2�@�c(1)
�@�����́A1983�N�Ɏ��̒l���i�덷�̂Ȃ��j��`�l�Ƃ��č̗p����܂����B
�@�@���� c = 299 792 458 [m/s]
�@����A(1)�����L���O�����̒�`�Ƃ��ꂽ���Ƃɂ��ASI�P�ʌn�̐��l��������A���̎��́i��`�ɂ���āj�P���I�ɐ��藧�͂��ł��B�����ŁA�����_�ł̊ϑ��f�[�^����ɁA
�@�@�v�����N�萔 h = 6.626 069 57×10
-34 [Js]
�ƒ�`���A(1)�����t�ɉ����āA
�@�@�L���O�������`������̐U���� ν
0 = {(299 792 458)2/6.626 069 57}×10
34
�ƌ��߂��킯�ł��B
�@������v�����N�萔�́A�l�Ԃ�����ɒP�ʌn�����߂������ŕK�v�ɂȂ������Z�萔�ł��B�����悤�Ȓ萔�Ƃ��ẮA�M���J�����[�A�G�l���M�[���W���[���ŕ\���ۂɕK�v�ȁu�M�̎d�����ʁv��A�d���̒P�ʂ�d���Ԃɓ����͂��g���Ē�`�������߂Ɏg�킴��Ȃ��Ȃ����u�^��̓������v�Ȃǂ�����܂��B�����I�ȗ��_���\�z����ꍇ�A�����́A����ɂ���Ēl�����߂镨���萔�ł͂Ȃ��A�l�דI�Ɍ��߂����p�P�ʂ̊��Z���s�������̂��̂Ȃ̂ŁA�덷�̂Ȃ���`�l��^����̂��D�܂����͂��ł��B���ہA���ɓI�ȕ����w���_��ڎw���f���q�_�̌����҂́A�����Ɗ��Z�v�����N�萔�ih/2π�j��1�ɓ������ƒu�������R�P�ʌn���g���̂��ӂ��ł��B
�@�Ƃ��낪�A�v�����N�萔�Ǝ��ʂ������ẮA�����ǂ���`�ɂ��邩�Ɋւ��ċc�_���������܂����B���ɂȂ����̂́A�����w�̌����Ɖ��w�̎��p���̂ǂ�����d�邩�ł��B
�@���w�҂́A�`���I�ɁA�A�{�K�h���萔N
A�i���Ă̓A�{�K�h���� Avogadro number �ƌĂꂽ���A1969�N����A�{�K�h���萔 Avogadro constant �ɕύX�j����Ɏ��ʂ��l���Ă��܂����B���̍l�����ɂ��A�j��
12C�̃������ʁi���q�P�̎��ʂ�N
A�{�j���A������12�O�����ɓ������Ƃ���܂��i���݂ł́A�����x���������₷���V���R�����W�������Ƃ��ėp������悤�ł��j�B�������A���q�P�̎��ʂ������ɑ��肷��͓̂���̂ŁA�A�{�K�h���萔N
A���`�l�Ƃ��ė^���A
12C�̒P���q���ʂ����肵�������A�b���ȒP�ɂȂ�܂��B���̌��q�̎��ʂ́A
12C�̎��ʂƂ̔�𑪒肷�邱�Ƃŋ��߂��܂��B
�@�A�{�K�h���萔���`�l�Ƃ��ė^����ƁA1�L���O�����́A
12C��Si�̌��q���ʂ́~�~�{�Ƃ��Ē�`�����̂ŁA���ϓI�ɂ킩��₷���Ȃ�܂��B�������A���̏ꍇ�A�v�����N�萔�́A�A�{�K�h���萔�̂ق��A�d�q�̎��ʂ���\���萔�ȂǁA����ɂ���Ēl�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��萔�̑g�ݍ��킹�Ƃ��Ē�`����邱�ƂɂȂ�A�K�R�I�ɁA�덷���萔�ƂȂ�܂��B�����w�̌��n���炷��ƁA�A�{�K�h���萔�͂��Ƃ��Ɛl�Ԃ�����Ɍ��߂����́i���̎��ʂ����1�O���������߁A�����Ɋ܂܂�錴�q�����l�����̂��n�܂�j�ł���A���R�E�̊�{�萔�ł͂���܂���B����Ȃ��̂ɒ�`�l��^���A��{�I�ȕ������ۂ��L�q����̂ɕK�v�ȃv�����N�萔���A���܂��܂Ȓ萔�̑g�ݍ��킹�Ƃ��ĕ\���̂́A�{���]�|�̂悤�Ɏv����ł��傤�B
�@�A�{�K�h���萔�ƃv�����N�萔�̑���͂��܂��܂ȕ��@�ōs���Ă��܂����A���́A�Ȋw�Z�p�f�[�^�ψ���iCODATA�j���������镨���萔���g���ė��҂̑��茋�ʂ��r����ƁA����덷�Ƃ͉��߂ł��Ȃ��s��v�����݂��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B������������A�W���Z�t�\�����ʂ�ʎq�z�[�����ʂɊւ��闝�_�ɏC�����K�v�Ȃ̂�������܂���B���ꂾ���ɁA�Q�̒萔�̂ǂ�����`�l�Ƃ��邩�́A�T�d�ɍl����ׂ��ۑ�ł����B����̍��ۓx�ʍt����̌���́A���w�I�Ȃ킩��₷�������A�����w�I�Ȍ�����D�悳�������̂��ƌ����܂��B�����g�͕����w�҂̒[����Ȃ̂ŁA�D�܂������肾�����ƕ]�����Ă��܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�F���̔g�������l�@���鎎�݂́A����܂ʼn��s���Ă��܂����A���̂������{���ɐ��������ǂ����A�����ꂽ�킯�ł͂���܂���B
�@�����̎��݂Ƃ��ďd�v�Ȃ̂��A�h�E�E�B�b�g�ɂ��c�_�ł��B���_�������ʎq�͊w�ł́A���_�̉^�����L�q����j���[�g���̉^������������͗͊w�̎�@�Ɋ�Â��Ĉʒu�E�^���ʂ�ϐ��Ƃ���������n�ŏ��������A���̏�ŁA�ʒu�E�^���ʂ����Z�q�ƌ��Ȃ����Ƃŗʎq�_�Ɉڍs���܂��B���̂������A�����ʎq���Ƃ����܂��B�h�E�E�B�b�g�́A�܂��A��l�����ȉF���̐U�镑�����L�q����t���[�h�}�������������ƂɁA��͗͊w�̘g�g�݂ɓ��Ă͂܂�ϐ������߁A���̏�ŁA�����ʎq���̎�@�ɂ���āA�F���S�̂̔g�������������ׂ����������܂����B���ꂪ�A�h�E�E�B�b�g�������ł��B�h�E�E�B�b�g�������́A���_�̏ꍇ�̃V�����f�B���K�[�������ɑ���������̂ł����A���Ԕ����̍����Ȃ��Ƃ�����ȕ������ł��B
�@�u�����Ȃ���Ԃ���A�ʎq�_�I�Ȍ��ʂɂ���ĉF�����a������v�Ƃ����u������̑n���v�̘b�������Ƃ͂Ȃ��ł��傤���H �ꕔ�̕����w�҂́A�h�E�E�B�b�g���������g���A�u������̑n���v����㈂ł���Ǝ咣���Ă��܂��B�������A�F���̑傫�����[���̂Ƃ��ɔg�������ǂ���`���ׂ������s���Ȃ��߁A�����w�I�Ɋm���Ȏ咣�Ƃ͌����܂���B�h�E�E�B�b�g�������i���邢�́A��ʉ����ꂽ�z�C�[���[���h�E�E�B�b�g�������j�́A�g�����̕ω��������̂ł͂Ȃ��A�g�������������ׂ������������������̂��ƍl�����܂��B
�@�F���̔g�������c�_���������̎��݂́A�z�[�L���O�̃A�C�f�A�ł��B�ނ́A�t���[�h�}���F���ł͂Ȃ��A�r�b�O�o���ȑO�ɑ��݂����Ɛ��������h�E�W�b�^�[�F�����A�����ʎq���ł͂Ȃ��o�H�ϕ��i�����ʎq���Ƃ͕ʎ�̗ʎq���̎�@�j�ɂ���Ĉ������@���l���܂����B�������A�ʏ�̎��ԁE��Ԃ̂܂܂ł͐��w�I�ɂ�����Ƃ������ʂ������Ȃ����߁A���Ԃ������ɕύX�����v�Z���s���܂����B���̂����̐������ɂ��āA���͉��^�I�ł��B
�@�h�E�E�B�b�g�̎�@�ł��z�[�L���O�̎�@�ł��A�g�����̒��ɂ��܂��܂ȉF���̉\�����܂܂�܂��B���_�������ʎq�͊w�ł́A�ϑ����s�����Ƃɂ���āA�g�����Ɋ܂܂�邳�܂��܂ȉ\���̂����A�����ꂩ�̏�Ԃ��ϑ����ʂƂ��ē����܂��B�V�����f�B���K�[�������������ē�����g�����́A�ǂ̏�Ԃ��ϑ�����邩���m���I�ɗ\��������̂ł���A�ϑ����ꂽ��Ԃ�\���Ă͂��܂���B�Ƃ���ƁA�F���̔g�����͉���\���Ă���̂ł��傤���H
�@�z�[�L���O�́A���̂悤�ȈӖ��̋c�_�����Ă��܂��i���Ȃ�p���t���[�Y���܂����j�F�u�F���̏�Ԃ������ł��قȂ�ƁA�����ɑ��݂���m�I�����͑S���ʂ̂��̂ɂȂ�B����m�I�������ϑ�����F���́A�ނ炪���݂ł���悤�ȉF���Ɍ�����̂ŁA���̉F���̔g�����́A���Ɋϑ������F���̏�Ԃƈ�v����v�B���̎咣��ے肷�鍪���͂Ȃ��̂ŁA���̂Ƃ���A���̂悤�ɍl���Ă����܂�Ȃ��ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�����Ɠ���ő����肵���Ƃ��̕ω����قȂ�̂́A�l�Ԃ��m�o�ł�����g���͈̔͂����ƌ��ʼn������قȂ邩��ł��B
�@���̏ꍇ�A�l�Ԃ̉��͈͂�20Hz����20kHz���x�ŁA�ł��������͂P�b�Ԃ�2����̐U�������܂��B���ŕ������Ƃ��̊����𐳊m�ɍČ����邽�߂ɂ́A���̍ō��U�����̂Q�{�ȏ�ƂȂ�T���v�����O���[�g�i���x�𑪒肷��p�x�j�Ńf�[�^�����K�v������܂��B���j�I�ȗ��R�ɂ���āACD�ł�44.1kHz�ADVD�ł�48kHz�i���邢��96kHz�j�Ƃ����p�x�Ńf�[�^���̎悵�Ă��܂��B
�@�����Q�{���ɂ�����@�͂��낢�날��܂����A�ł��P���Ȃ����Ƃ��āA�L�^�������x�f�[�^��������ɓǂݏo���čĐ�����ꍇ���l���܂��傤�B���̂Ƃ��A�Đ�����鉹�̔g�`�́A�}�P�Ɏ������悤�ɁA���̌`�ɑ��Ď��ԕ����ɔ����ɉ����k�߂��܂��B����́A���̐U�������Q�{�ɂȂ������Ƃɑ�������̂ŁA���������������ɂȂ�܂��B
�@���̍����ς����ɍĐ����x���Q�{�ɂ���ɂ́A���������������U�����̔g�`��ς����ɁA�S�̓I�ȉ��̕ω������߂镔���������̎��ԂɈ��k����Ηǂ��͂��ł��B�A�i���O�g�`�̒P���ȗ�ŏ����A�}�Q�̂悤�ȕϊ������邱�Ƃł��B�������A�f�W�^�������Ŏ��ۂɂ��������ϊ����s�����߂ɂ́A���̍���Ɋւ��g�`���ǂ�قnjJ��Ԃ���邩���ׂ�Ƃ������w�I�ȑ��삪�K�v�ɂȂ�A���Ȃ���ł��B
�@����A���̏ꍇ�A�l�Ԃ̉��͈͂�400��Hz����800��Hz�ł��B����قǐU�������傫���Ȃ�ƁA���͂���̋��x���T���v�����O���Ăǂ̂悤�ɐU�����Ă��邩�ׂ邱�Ƃ͕s�\�ł��B
�@�K���A�l�Ԃ̎��o�́A�R��ނ̌���e�^���p�N�������ꂼ��قȂ�ш�̌��i������R���F�j���z�����邱�ƂŐF�����m����̂ŁA�U���̔g�`���̂��̂𑪒肵�Ȃ��Ă��A�R���F�ɑΉ�������̕��ϓI�ȋ��x���L�^���邾���ŁA�ڂŌ����Ƃ��̊������Č��ł��܂��B���{��DVD��n�f�W�����ł́A�P�b�Ԃ�30�R�}�Ƃ����p�x�łR���F�̋��x���f�[�^�����Đ����܂��B�P�R�}�����ɔ���Ƃ����P���ȂQ�{���ōĐ����Ă��A�R�}���Ƃ̂R���F�̋��x���ǂݏo�����̂ŁA�F�͕ω����܂���B
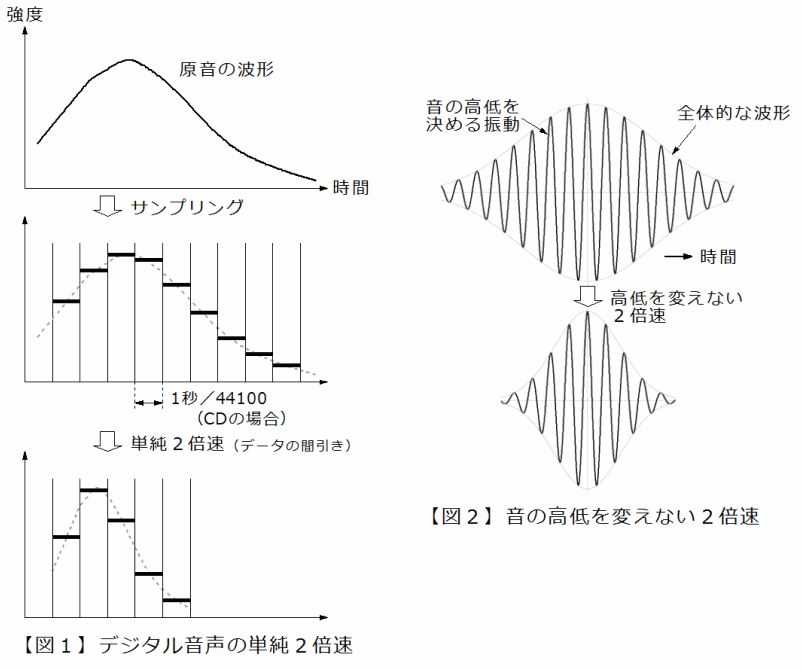
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�n�����g���Ƃ́A�P�ɋC�����㏸���邾���ɂƂǂ܂�܂���B���x���オ�邱�ƂŐ����̏����ʂ������A����ɉ����č~���ʂ��ω����܂��B�S�̓I�ɐ����̈ړ����_�C�i�~�b�N�ɂȂ�A����܂ō~���ʂ����������n��ł͂܂��܂��J�������A�������Ă����n��͂���Ɋ������i��ŁA�^���̑����ƍ����������s���Đ����܂��B�܂��A�C���̖c����嗤�X�̗͂Z���ɂ���ĊC���ʂ��㏸���A�C���̒Ⴂ�n��͐��v�����荂���̔�Q�����肵�܂��B
�@�l�ނɂƂ��čł��Ō��ƂȂ�̂́A�_�Ɛ��Y�ɑ傫�ȉe���������邱�Ƃł��傤�B�C���h�k����A�����J�������ȂǑѐ��w�i�n�����߂Ă���n�w�j����̟��ɗ����Ă���n��́A���݂ł��n�����ʂ̒ቺ�ɋꂵ�߂��Ă��܂��B���g�����i�s����ƁA���͂�n���������œy��̊�����h�����Ƃ͍���ɂȂ�A�k������n���}���ɑ�����Ɨ\�z����܂��B����ł́A���V�A��J�i�_�ȂǂŔ_�n�J����i�߂�Ηǂ����Ƃ����ƁA�����ȒP�ɂ͂����܂���B�n�����g���́A�������ʃK�X�ɂ���ĉF����Ԃւ̐ԊO�����˂��}������A����Βn�����z�c������ԂɂȂ邱�Ƃł���A���z����̌��ʂ͕ω����܂���B���������āA�k�n�ʐς�����̌��ʂ����Ȃ����ܓx�n���ł͌��������[���ɍs�����A��ܓx�n���قǂ̐��Y�ʂ͊��҂ł��Ȃ��̂ł��B
�@���Ă̖ҏ��͐��E�I�ŁA�I�}�[���ł́A�P���̍Œ�C����42���ƁA�l�Ԃ̐������s�\�ɋ߂����ɂȂ��������ł��B���������n��ɏZ�ސl�́A�^���ɈڏZ���l���Ă��邩������܂���B�������A����ȊO�̒n��̐l�ɂƂ��ẮA����������A�H�������ȂǎЉ�̊�Ղ��ێ��ł��邩�ǂ����̕����A���[���Ȗ��ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�`���̋^��ɒ[�I�ɓ�����Ȃ�A�d�͂���p����̂��A���ʂł͂Ȃ��G�l���M�[������ł��B
�@1907�N�A�A�C���V���^�C�������������i�����x�^���ɂ�銵���͂Əd�͕͂����I�ɋ�ʂł��Ȃ��Ƃ��������j�Ɋ�Â��Ĕ��������̂́A�G�l���M�[�Ǝ����ݍ�p����Ƃ������Ƃł��B�G�l���M�[�����݂���Ǝ��͂̎��䂪�݁A����̂䂪�݂��G�l���M�[�̈ړ��ɉe�����y�ڂ��|�|�����������݊W���d�͂̋N�����Ƃ����A�C�f�A�ł��i�����Ɍ����ƁA1907�N�ɔ��������͎̂��Ԃ̐L�яk�݂����ŁA���ԂƋ�Ԃ����c�݂��l����悤�ɂȂ�̂́A1912�N�ȍ~�ł��j�B
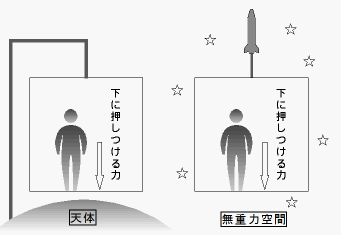
�@���̋c�_�Ɏg��ꂽ�̂��A�L���ȁu�G���x�[�^�̎v�l�����v�ł��B���Ȃ��́A���͂����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��G���x�[�^�̃J�S�ɕ����߂��A���ɉ���������悤�ȗ͂������Ă���Ƃ��܂��i�E�}�j�B���āA���̗͂̌����͉��Ȃ̂��H �G���x�[�^�̉����ɋ���ȏd�͌��������ďd�͂��y�ڂ��Ă���̂��A����Ƃ��A���d�͋�Ԃɕ����ԃJ�S�����P�b�g�Ȃǂŏ���Ɉ��������ĉ������̊����͂��������Ă���̂��|�|�����������Ӗ�����̂́A�J�S�����ł̕������ۂ����𗘗p�����ǂ�Ȏ��������Ă��A�Q�̉\���̂ǂ��炩����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@���̎v�l�����Ɋ�Â��āA�A�C���V���^�C���́A���̂悤�ɋc�_��i�߂܂��F�u�J�S�̏�����V��Ɍ����Č���������Ƃ���ƁA�J�S�������x�^�����Ă���ꍇ�A�V��Ŋϑ������Ƃ��Ƀh�b�v���[���ʂɂ���ĐU�������ω�����B���������ɂ��A�d�͂���p���Ă���Ƃ��ɂ��������ʂ������āA�U�������ς��͂����v�B�����x�^��������ꍇ�̉����x���d�͉����x�ɓ������ƒu���ƁA���̎��������܂��B
�@�@ν' = ν(1+Φ/c
2)�@�c(1)
�������Aν��ν'�͏��ƓV��ł̌��̐U�����B�܂��AΦ�͓V��ɑ��鏰�̏d�̓|�e���V�����ŁA�d�͉����x��g�A�V��̍�����H�Ƃ���ƁAΦ=-gH �ƂȂ�܂��B
�@���q�̃G�l���M�[�̓v�����N�萔h�ƐU����ν�̐ςȂ̂ŁA(1)���̗��ӂ�h���悶�����̂́A�G�l���M�[�̕ۑ����ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��܂��B���Ȃ킿�A�V��ɓ��B�����Ƃ��̌��q�̃G�l���M�[hν'���A���ɂ���Ƃ��̌��q�̃G�l���M�[hν�ɏd�̓|�e���V�����̉e�����悶���`
�@�@hν(1+Φ/c
2)�@�c(2)
�ɓ��������Ƃ������Ă��܂��B
�@����A�������ʂƏd�͎��ʂ�������m�ł���Ƃ����Ƃ��A�d�̓|�e���V����Φ�̒n�_�ŐÎ~���镨�̂̃G�l���M�[�́A���ʃG�l���M�[�ɏd�͂ɂ��ʒu�G�l���M�[mΦ���������l�Ȃ̂ŁA
�@�@mc
2(1+Φ/c
2)�@�c(3)
�ƂȂ�܂��B(2)����(3)��������ׂ�ƁA�d�̓|�e���V�����́A���ł����Ă����ʂ������̂ł����Ă��A�Ώۂ����G�l���M�[�ihν�܂���mc
2�j�ɓ����`�ō�p���邱�Ƃ��킩��܂��B�����������ʂݑ�ɂ��Č�����i�߁A�A�C���V���^�C���́A1915�N�܂łɁu�G�l���M�[�Ǝ���̑��ݍ�p���d�͂ł���v�Ƃ�����ʑ��Θ_���������܂��B
�@(3)���́A����ȑO�̍l�����ɂ��A���ʂ�W�J���āA��P����m�͊������ʁA��Q����m�͏d�͎��ʂƋ�ʂ��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�������A�A�C���V���^�C���́A�d�̓|�e���V����Φ���g������h�̂����ʂł͂Ȃ��G�l���M�[���Ƃ����������̗p���A���łɓ��ꑊ�Θ_�ɂ���āi�d�͂��Ȃ��Ƃ��́j�G�l���M�[�ɓ������Ƃ��ꂽ�������ʂ́A�d�͎��ʂƋ�ʂ���Ȃ��Ǝ咣���܂����B�u���q�̌��Ȃǂŕ\����镨���̗ʂɂ́A�d�͎��ʂƊ������ʂ̂Q��ނ�����A���҂͂Ȃ����������Ȃ�v�ƌ����Ă��A�S���킩��܂��A�u�d�͂Ƃ̑��ݍ�p�╨�̂̊����i��������ɂ����j�́A���̓����ɕ����߂�ꂽ�G�l���M�[�ɂ���Č��肳���v�Ƃ��������Ȃ�A�������肷��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�A�C���V���^�C���́A���Ԃ��Ԃ̂䂪�݂��g�̓`�d�ɉe�����y�ڂ����Ƃ������A�V�̂̎��͂Ō������܂��邱�Ƃ��܂����B���ʂ̂��镨�̂��d�͂Ői�H���Ȃ����邱�Ƃ́A�ʏ�͈�ʑ��Θ_�I�ȉ^�������������Ƃɐ�������܂����A��荪�{�I�ɂ́A�u�������g�ł���v�Ƃ����ʎq�_�̒m���Ɋ�Â��āA���Ɠ����悤�Ɏ���̂䂪�݂������g�̓`�d�ɍ�p�����ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B��ʂɁA�G�l���M�[���^�Ԕg�́A���ł��낤�ƕ����ł��낤�ƁA�d�͂̍�p���āA�����悤�ɐi�s�������ς��܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���́A�l�Ԃɂ�锭���̒��ɂ́A���R�ɗގ����̂Ȃ����̂����Ȃ肠��Ɗ����Ă��܂��B
�@�ÓT�I�Ȕ����ł́A�Ԏ��̂���ԗւ�����܂��B�ۂ��ē]���镨�̂Ȃ�A���R�E�ɂ���������܂��B�������A�Ԏ���t���邱�Ƃɂ���āA���ׂ������Q���̎ԗւ����ň��肵�����s�������ł��邱�Ƃ́A�l�Ԃɂ�铴�@�͂ɂ���Ă͂��߂Č��o���ꂽ�ƌ�����ł��傤�B
�@�ߑ�I�ȗ�ł́A���w�I�ȃA���S���Y���ƁA��������s����R���s���[�^�������邱�Ƃ��ł��܂��B�A���S���Y���Ƃ́A���������菇���������̒P���ȃX�e�b�v�Ƃ��đg�ݍ��킹�����̂ŁA���w�I�ȉ�@��R���s���[�^�E�v���O�����Ȃǂ��܂܂�܂��B���R�E�̏����ۂ��A�i���O�I�ł���̂ɑ��āA�A���S���Y���́i�P���ȃX�e�b�v�ɕ�������Ƃ����Ӗ��Łj�f�W�^���I�ł���A���ۓI�v�l�ɂ���č���܂��B
�@�A���S���Y�����@�B�I�Ș_�����Z�Ƃ��Ď��s����̂��A�R���s���[�^�ł��B�`���[�����O���ؖ������悤�ɁA�R���s���[�^�́A������_�����Z�����s�ł���̂ŁA�_�����Z�Ɋւ��閜�\�}�V���ƌ����ėǂ��ł��傤�B�l�Ԃ̔]�́A�A���S���Y���Ɋ�Â��Ďv�l����̂ł͂Ȃ��A�����܂Ńp�^�[���̗ގ����𗊂�ɃA�i���O�I�ȏ�����s���Ă��܂��B�R���s���[�^�Ɏ������̂́A���R�E�ɂ͑��݂��܂���B
�@�H�ƓI�ȑf�ނƂ��ẮA���݁A�����J�����i�߂��Ă��钴�i�q������܂��B�ʏ�̌����i�q���A�������q�z�J��Ԃ����̂ɑ��āA���i�q�́A���\�X�R�s�b�N�ȃX�P�[���œ������q�z��̃p�^�[�����J��Ԃ����悤�ȕ����ŁA�]���̕����ɂȂ��d�C�I�E���w�I�Ȑ����������Ɨ\�z����܂��B������A���R�E�ɂ͑��݂��Ȃ����̂ł��B
�@�������A�u���Ă��邩���Ă��Ȃ����v�Ƃ����c�_�͏�ɞB���ŁA�������ɂ���ẮA�ǂ�Ȕ����i�ł��A�ǂ����Ŏ��R���Ɠ����悤�Ȏd�g�݂��g���Ă���ƌ����܂��B�܂��A�ϋɓI�Ɏ��R��͕킵���Z�p�J�����i�߂��Ă���A�����̎d�g�݂����p�����@�ł���o�C�I�~���e�B�N�X�́A�Ԍ`�̌�������ƂȂ��Ă��܂��B�������A���̈���ŁA�l�ԃI���W�i���̋Z�p�����X�Ɛ��ݏo����Ă��邱�Ƃɂ��A�ڂ������Ă������������Ǝv���܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@����͓�����ł��B�I�N�@�Ɋւ��ẮA����i�L���X�g�I���j�݂̂Ȃ炸�A���{�̍c�I�i�_���V�c���ʋI���j�╧��i�߉ޓ��ŋI���j�̂悤�ɁA�ǂ̖����������������S�ɔ��z���Ă���A�����I�Ȃ��̂͂���܂���B�Ñ�G�W�v�g��̂悤�ɁA�P�N��365����1��1�����i���z�̉^�s���猩�āj�����͌��߂Ă��A���N���I�����N���ɂ͖��ڒ��ȗ������܂����A����ł͒ʗp���܂���B
�@�S�l�ނɂƂ��ďd�v�ȏo���������N�Ƃ��邱�Ƃ��ł���A���l���[���������邩������܂���B�������A�l�ގj�̏�ő傫�Ȏ����|�|�������s�̊J�n�A����̊l���A�o�A�t���J�Ȃǁ|�|�́A��������N�����ł�����̂ł͂���܂���B�l�ލŌÂ̕����́A�����炭�Ñチ�\�|�^�~�A�ŁA�V�����[���l���s�s���Ƃ����݂����̂͋I���O3000�N�ȑO���Ƃ���܂����A���̎n�܂�͞B���ł��B�܂��A���ɃV�����[���̈�Ղɂ����铯�ʑ̂̑���ȂǂɊ�Â��ĕ������ˋI�����߂��Ƃ��Ă��A���̌�̔��@�����ɂ���āA���Â���Ղ�������\��������܂��B
�@�V���w�I�E�n�������w�I�ȏo�����̂����A�l�ނɑ傫�ȉe����^������r�I�ŋ߂̂��̂ɂ́A�ŏI�X���̏I��肪����܂����A��P���N�O�Ƃ��������܂���B�n���[�a���̐ڋ߁i�m�����̍����ŌÂ̋L�^�͋I���O240�N�j�A����Ŋm�F���ꂽ���V�������i�e�B�R�̐�1572�N�A�P�v���[�̐�1604�N�j�A���z���_�����������}�E���_�[�ɏ����i1645�`1715�N�G���E�I�Ȋ��≻�̌����Ƃ����j�A�ϑ��j��ő�ƌ�����C���h�l�V�A�E�^���{���R�̕��i1815�N�j�A�L�j�ȗ��ő��覐Η����E�c���O�[�X�J�唚���i1908�N�j�Ȃǂ́A��̌��N�ɂ���قǂ̑厖���ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@���́A�X�I�ȗ�Ƃ��ăL���X�g�I����p���Ă����܂�Ȃ��Ǝv���܂��B���̗�́A�C�G�X�̐��܂ꂽ�N�����N�Ƃ�������Ȃ̂ɁA�ËL�^�̕s���S���������ŃY���Ă��܂��B���ۂ̐��N�Ƃ��ẮA�I���O4�N�Ƃ��������L�͂ł�����̂́A�I���O7�N�Ƃ��I���O12�N�Ǝ咣����l�����܂��B���̒��x�̓m��ȋI�N�@�Ȃ̂ł�����A�L���X�g���ȊO�̐l���A���Ďg�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����́A�`���I�ɁA�O���j�b�W�W�������p�����Ă��܂����B�O���j�b�W�W�����́A�V���w�I�ȍP���ϑ��Ɋ�Â��Č��肳��鎞���ŁA0���ƂȂ鎞���́A�o�x0�x�i����킸���ɂ��ꂽ�ꏊ�j�ɂ���O���j�b�W�V���䂩�猩���Ƃ��̑��z�̈ʒu����ƂȂ�܂��i���j�I�ɂ͐��߁i���̒��ԓ_�j��0���Ƃ���u�V�����v���������Ԃ������A20���I�����ɂȂ��āA���q�i���傤���G��̒��ԓ_�j��0���Ƃ���u��p���v�ɕύX����܂����j�B���݂́A���q���v���g���Ē�`���鋦�萢�E�����g���܂����A�����I�ɃO���j�b�W�W�����Ɠ������̂ƍl���Ă��܂��܂���B�n���̌`��͂قډ�]�ȉ~�̂ł���A�o�x�����Ō��Ēn�������w�I�ȍ���͂قƂ�ǂȂ��̂ŁA0���ƂȂ鎞�������߂����ǂ��ɂ��邩�A�C�Ӑ�������܂��B�C�M���X�̓V���䂪��ɑI�ꂽ�̂́A�P�ɁA�C�M���X�͊C�^�Ƃ�����ŁA�����̑D��肪�C�M���X�̕W�������g��������ɑ��Ȃ�܂���B
�@�����A�O���j�b�W�W�����́A������Ƃ������R�ŁA�֗��ȓ_������܂��B�C�M���X�ł̐��߂ɓ��t���ς��V�����́A�o�x180�x�ɂ������p���i�^�钆�̐��q�ɓ��t���ς��j�ƈ�v����̂ŁA�o�x180�x�t�߂ɓ��t�ύX����������邱�ƂɂȂ�܂����B�Ƃ��낪�A�^�̗ǂ����ƂɁA�o�x180�x�t�߂ɂ͗��n�����Ȃ��A���V�A�ɓ��ȂLjꕔ�n��������āA�n�����Ȃ̂ɓr���œ��t���ς��Ƃ������s�ւ������܂���B���݂ł́A���V�A�⑾���m���ו��ł̊���ɏ]���āA���t�ύX�������X�ŋȂ����Ă��܂����A�����ނˌo�x180�x�t�߂ɓ��ꂳ��Ă��܂��B���֗̕���������̂ŁA����Ƃ��O���j�b�W�W�����i�Ǝ����㓯�����萢�E���j���g��ꑱ����ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�����ʂ�\���ړx�Ɍ��_�����邩�ǂ����́A�ȒP�ɂ͓������܂���B���̗��R�́A�����ʂ����̐��i�����̂悤�Ȑ��w�I�T�O�Ƃ��Ă̐��j�ƑΉ���������̂����A���������B��������ł��B
�@�M�͊w�I�ȉ��x�ɂ́A��Η�x�i�뉺273.15���j�Ƃ����������z�肳��Ă��܂��B�������A������u���x�́A��Η�x�����_�Ƃ��锼�����̎����ŕ\�����v�Ɖ��߂���̂́A����������܂���B�M�͊w�I�ȉ��x�́A�����܂ŔM�̗����O��Ƃ��锼�o���I�ȊT�O�ł���A���w�I�Ȍ������͂Ȃ�����ł��B
�@���v�͊w�ɂȂ�ƁA���x�́A�������\������v�f�i�C�̕��q�^���_�ɂ����镪�q�Ȃǁj�ɂǂ̂悤�ɃG�l���M�[�����z����邩��\���ʂƂ��Ē�`����܂��B�����傴���ςɌ����A�S�Ă̗v�f���Œ�G�l���M�[��ԂɂȂ����ꍇ����Η�x�A�S�G�l���M�[�������荂���Ƃ��ɂ́A�u����̃G�l���M�[��Ԃɂ���v�f�����p�[�Z���g���v�ɂ���āA���v�͊w�I�ȉ��x�����߂��܂��B�Ƃ��낪�A����������`���̗p����ƁA���x�͐��Ɍ����܂���B���[�U�[���U�n�̂悤�ɁA�l�דI�ȑ���ɂ���āA�����G�l���M�[��Ԃɂ���v�f�̕��������Ȃ�P�[�X�������ł��邩��ł��B���̂悤�ȏꍇ�A���x�́A�`���I�Ƀ}�C�i�X�i��Η�x�ȉ��j�ɂȂ�܂��B
�@���v�͊w�I�ȉ��x�ɂ́A�u���̉��x���v�Ƃ����B�����������܂��B�C�̕��q�^���_�̏ꍇ�A���q���P�����Ȃ���Ή��x�͒�`�ł��܂��A���̕��q��������A���̃V�X�e���̉��x���`���邱�Ƃ́A�����I�ɉ\�ɂȂ�܂��B�������A���ꂪ�����I�ɈӖ��̂����`���ǂ����́A���Ȃ�^��ł��B�܂��A�����̉��x���z����Ƃ���Ƃ��ɂ́A�G�l���M�[���z�����߂���悤�ɁA�i�P�_�̉��x�ł͂Ȃ��j�K���Ȕ͈͂܂Ŋg�����Ƃ��̉��x���l���Ȃ���Ȃ炸�A�����ɒ�`����͍̂���ł��B
�@��Η�x�ɋ߂Â����Ƃ��ɂ́A�ʎq�_�I�Ȍ��ʂ����ɂȂ�܂��B���x�������ƂP�P�ɑΉ�����Ȃ�A�ǂ�Ȃɐ�Η�x�ɋ߂��Ă��A��x�Ƃ͈قȂ�C�ӂ̉��x������͂��ł��B�������A���ۂɂ́A�ʎq�_�I�ȕs�m�萫���\��邽�߁A���x�̒l���m��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�����ʂ̒l���m��ł��Ȃ��Ȃ錻�ۂ́A���x�ȊO�ɂ������܂��B��ԓ����ɂ�����Q�_�Ԃ̋����́A�����炭�v�����N���ȉ��ɂȂ�ƁA�l���m��ł��Ȃ��Ȃ�ƍl�����܂��B����́A�v�����N���ȉ��ɂ܂Őڋ߂�����ƁA�����Ȃ镨�����ۂ������Ă��Ă��Q�_�����ʂ��邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�A�����Ƃ����T�O���Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ邩��ł��B�����悤�ɁA����߂ĉ��������A�F�����₦���ĕ������ۂ������N���Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�Ȃ����Ԃ����݂���ƌ�����̂��A�^�₪�c��܂��B���������́A�u���R�E�ɖ�����E�����������邩�v�Ƃ����Â�����̖₢�Ƃ��֘A���܂��B
�@�����ʂ́A�������g���ĕ\���̂���ʓI�ł����A�����̕����I���E�ɂ�����ʂ́A�����̂悤�ɖ��m�Ȍ��E���߂���A������E��������_������ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����ʂ������ŕ\������̂ƌ��Ȃ��A���̏�Ō��E�����邩�ǂ������l��������A�����ʂ͂������������Ɠ��������������ǂ�����_��������A���R�E�̖{���ɔ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���͈Í����_�ɂ��Ă��܂�ڂ�������܂��A���̒m��͈͂Ō����A�ʎq�Í��́A���z�ʉ݂����p����Í��Ƃ͊�{�I�Ȏg�p�ړI���قȂ��Ă���̂ŁA���p�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�ʎq�Í��Ƃ́A�ʏ�A�ʎq���ʂ𗘗p���ĈÍ����𑗐M����Z�p���w���܂��i�ʎq�R���s���[�^��p���ĈÍ��������邱�Ƃ��u�ʎq�Í��v�ƌĂԂ��Ƃ�����悤�ł��j�B�����ňÍ����g�p����ړI�́A�T���h�����Ƃɂ���܂��B
�@�R���ʐM�̂悤�ɁA���M�҂Ǝ�M�҂͑��݂ɐM���ł�����̂́A�`���H�̓r���ő�O�҂ɖT���Ƒ傫�Ȕ�Q����������ꍇ������܂��B����������������邽�߂ɁA�T����Ɍ��m���ď��R�k��h���̂��A�ʎq�Í��ł��B
�@���M�ҁiAlice�j�����M�ҁiBob�j�ɏ����Í������đ���ꍇ�A�Í����ɉ����āA�Í�����ǂ��邽�߂̌��i�Í����j�����M����܂��B���̂Ƃ��A�Í����ƈÍ����̂ǂ��炩����ł��T��Ȃ���A��R�k���邱�Ƃ͂���܂���B�����ŁA���q�̕Ό���Ԃ̂悤�ȗʎq�_�I�ΏۂɁA�Í����ƂȂ������������邱�Ƃɂ��܂��i���q�́AAlice����Bob�ɑ���ꍇ�ƁA�ʂ̋@�ւ�Alice��Bob�o���ɑ���ꍇ������܂����A�����ł́A�O�҂�z�肵�܂��j�B�����A����T�悤�Ƃ��ĒN���iEve�j�����q���ϑ�����ƁA���̂��Ƃɂ���ĕΌ���Ԃ��s�t�I�ɗ�����܂��B���������āA���q�������i�K�ŕΌ���Ԃ��L�^���Ă����A�����������q�̕Ό���ԂƔ�r����A�T�ꂽ�i���邢�́A�ʂ̌����ŕΌ���Ԃ������ꂽ�j���Ƃ��������܂��B���̏ꍇ�́A����ꂽ�f�[�^���Í����Ƃ��ėp���Ȃ��悤�ɂ��āA�Í��ʐM�̃Z�L�����e�B��ۂ��܂��i�}�P�j�B
�@����A���z�ʉ݂̏ꍇ�A�Í��̓f�[�^�̉�₂�h�����߂Ɏg���܂��B
�@�㉿�̎x�����̂悤�ȏ�������s��ꂽ�Ƃ��A�]���́A��s�Ȃ菤�X�Ȃ�A���ꂼ��̋@�ւ��o�[�䒠�����L���A��L�̕����ɏ]���āA���̋@�ւɂ�������x�������I�ɂȂ�i�r���ŋ����������肵�Ȃ��j�悤�Ɏ�����e���L�����Ă��܂����B�������A����ł́A�S�Ă̏�����������I���ǂ������`�F�b�N����ɂ́A�ق��̏o�[�䒠�ƕt�����킹�Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�䒠�Ǘ����M���ł���@�ւ͋�s��N���W�b�g�J�[�h��ЂȂǂɌ����Ă���A����ȊO�̋@�ւƎ������ɂ́A������s�����s���鎆���̂悤�ȁg�����h������������������܂���ł����B
�@IT��p���Ă������������������悤�Ƃ����̂��A���z�ʉ݂ɂ�����u���b�N�`�F�[���̋Z�p�ł��B�ȒP�Ɍ����A�R���s���[�^���m�[�h�Ƃ��鉼�z�ʉݗ��p�̃l�b�g���[�N���\�z���A���̃l�b�g���[�N�����ōs����S�Ă̎���̋L�^���A�e�m�[�h�̃R���s���[�^�ɕۑ������邱�ƂŁA����̐��������m�ۂ���Ƃ������̂ł��B
�@�����Ƃ��ẮA���Ԃ�10�����x�̊Ԋu�ɕ������A���ꂼ��̎��ԓ��ɍs��ꂽ����̓��e���A�u�Í����v�̎�@�Ő��l�f�[�^�ɒu�������܂��B���̂Ƃ��A���l�����ꂽ������Ԃ̎���f�[�^���u���b�N�A�u���b�N�̎��n����u���b�N�`�F�[���ƌ����܂��i�}�Q�j�B�r�b�g�R�C���̏ꍇ�́A���������u���b�N�`�F�[�����A���z�ʉ݂̃l�b�g���[�N�ɎQ�����鎖�ƎґS�Ăŋ��L�ł���悤�ɂȂ��Ă���A�i�����I�ɂ́j�ߋ��ɂǂ̂悤�Ȏ�����s��ꂽ�����A���S�ɓ���������܂��B�ǂ�������̋@�ւ��䒠���Ǘ�����̂ł͂Ȃ��A������ peer to peer �����ŁA�䒠�����U�E���L�����̂ł��B
�@���l�f�[�^�ւ̒u���������u�Í����v�ƌ����܂������A�ǂ�Ȏ�������������킩��Ȃ�����̂ł͂���܂���B���l���g�����Ƃɂ���āA�R���s���[�^�ň����₷������ƂƂ��ɁA��₁i�f�[�^�̏��������j������ɂ��邽�߂̂��̂ł��B�e�@�ւ��ƂɌŗL�̑䒠������ꍇ�A�ߋ��̋L�^��������Ə��������āA���ۂɂ͍s���Ȃ������x�������������悤�Ɍ��������邱�Ƃ��A�s�\�ł͂Ȃ��ł��傤�B�������A�u���b�N�`�F�[���̏ꍇ�A����f�[�^���P�r�b�g�ł��ύX����ƁA�Í������ꂽ�Ƃ��̐��l�f�[�^���S���قȂ������̂ɂȂ�܂��B�u���b�N�`�F�[���̊e�u���b�N�́A�ȑO�̃f�[�^���ꕔ�܂ތ`�Ő��l������܂��̂ŁA�ߋ��̎���L�^���ق�̏�����₂���ɂ��A�S���Ǝ҂ɕ��U�E���L�����u���b�N�`�F�[����S�ʓI�ɏ��������Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɕK�v�Ƃ����J�͂����܂�ɋ���Ȃ̂ŁA�f�[�^�̉�₂͍s���Ȃ��Ƃ������Ƃł��i���ɂ́A���̕ӂ�̐������悭�����ł��Ȃ��̂ŁA�{���ɉ�₂�����Ȃ̂��A���M���Ȃ��̂ł����j�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�u���̓��m�̑��Α��x�͌������Ȃ��v�Ƃ��u�����͂����銵���n�œ����l�ɂȂ�v�Ƃ������i����j���Θ_�̋A���́A����̂䂪�݂�ϓ��A�d�͂̉e�������ƂȂ�Ȃ������͈͂ł������藧���܂���i���I�Ȍ�����������ƁA���ꑊ�Θ_�̌����ł��郍�[�����c�s�ϐ��́A����̂䂪�݂����W�ϊ��ŏ��������Ǐ����[�����c�n�ł̂ݐ��藧�Ƃ������Ɓj�B���L���͈͂ŋc�_����Ƃ��ɂ́A��ʑ��Θ_���g���K�v������܂��B
�@�c������F���ł́A�����`���r���ŋ�Ԃ��ǂ�ǂ�g�����Ă����܂��B���̂��߁A������E�̈��艓���ɂ���V�̂̌����A��Ԃ̖c���Ɍ����ǂ������A�ϑ��҂܂œ͂��Ȃ����Ƃ��N���蓾�܂��B�����������E���F���̒n�����ł���A���̔ޕ�����͌�������Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�n�����̔ޕ��͒������ʼn��������Ă���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�������A�������V�̂��A���̋߂��ɂ���V�̂ɑ��Č���葬�������Ă���킯�ł͂���܂��A�����`���ǂ̒n�_�ɂ����Ă��A�i�����͈͂Ȃ�j���ꑊ�Θ_���j�ꂽ�悤�ɂ͌����܂���B
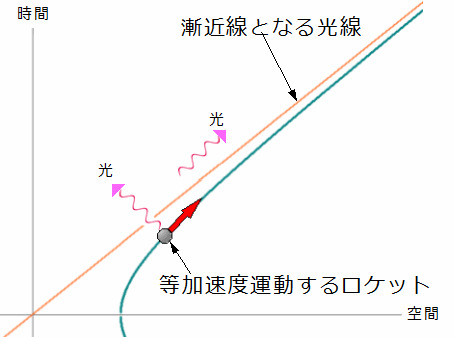
�@�c���F���Ƃ͏����Ⴄ�̂ł����A���̂悤�ȏ��l����ƁA�����̓C���[�W�ł���ł��傤�B���P�b�g�����R�ȃ��[�N���b�h��ԂŁi���Θ_�I�ȈӖ��ł́j�������x�^�������Ă���Ƃ��܂��B���P�b�g�͉�������ăX�s�[�h�������Ȃ�܂����A���Θ_�̐�����̂ŁA�����ȏ�ɂ͉����ł��܂���B���������āA���P�b�g�̋O�Ղ́A�}�̃O���t�̂悤�ɁA��������ɑQ�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�Q�ߐ��ƂȂ�����́A��������ė�������E�ł���A���̔ޕ�����͌����Č����͂��܂���B���������āA���̌����̈ʒu�����P�b�g����ɂƂ��Ă̒n�����ł���A���̌��������́A�܂�Œ������ʼn��������Ă���悤�Ɋ������܂��B�������A�O���猩��ƁA�������œ������̂͂Ȃ��A���Θ_�ɒ�G���錻�ۂ͉����N���Ă��܂���B
�@���P�b�g�ɏ���Ă���l���炷��ƁA�������郍�P�b�g�����ł́A�����镨�̂�����ɉ�������悤�Ȋ����͂���p���Ă���A���������F���S�̂Ɉ��̏d�͂���p���Ă��邩�̂悤�Ɋ������܂��B�n�����́A���������d�͂̍�p�Ő������ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�������A�n�����̋߂��ɍs���Ă݂Ă��A��Ԃ��ُ�����������킯�ł͂Ȃ��A���ꑊ�Θ_��������O�̂悤�ɐ��藧���Ă��܂��i���P�b�g�̊O���猩��ƁA�ӂ��̃��[�N���b�h��ԂȂ̂ł�����j�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�w�t�@�C���}�������w�x�̐����������킩��Â炭��������������ł����A�G�l���M�[�����W���A�Ƃ��Ƀ��[�����c�ϊ����Ă��܂��B
�@�Î~�������q�͉^���ʂ��[���Ȃ̂ŁA�G�l���M�[�iE
0�j�E�^���ʁip
0=0�j�Ǝ��ԍ��W�it�j�E��ԍ��W�ix�j�Ƃ����Q�̂S���x�N�g���̓��ς́AE
0t�ƂȂ�܂��i�\�L���ȒP�ɂ��邽�߁A��ԂɊւ��Ă�x���W�������l���邱�Ƃɂ��܂��j�B�����ŁA���q�����xv�ʼn^�����銵���n���l���܂��B���̊����n�̗ʂɂ̓_�b�V����t���ĕ\�����Ƃɂ���ƁA�G�l���M�[�E�^���ʂƍ��W�̓��ς͍��W�ϊ��ŕς��Ȃ��X�J���[�ʂȂ̂ŁA�@E
0t=E't'-p'x'�@�Ƃ����������藧���܂��B
�@�b���킩��ɂ����Ȃ����̂́A���̎���t�Ƀ��[�����c�ϊ��̌����Ă͂߂��̂ɑ��āAE
0�͂��̂܂c�������߂ł��B
�@�@
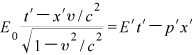
�@�t�@�C���}���́A�܂��A���̎��̗��ӂ�t'��x'�̌W�����r����E'��p'�����߁A����E'��p'�����xv�œ������q�̃G�l���M�[�Ɖ^���ʂł��邱�Ƃ܂��āA�^�����錴�q�̊m���U�������߂悤�Ƃ��Ă��܂��B�܂�A���xv�ʼn^�����錴�q�̊m���U���́A�Î~���錴�q�̊m���U�������[�����c�ϊ����邾���ŋ��߂���Ƃ����̂��A���̎咣�Ȃ̂ł��B
�@�@
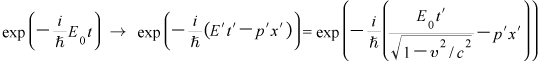
���̏�ŁAE'�ɑ��Ď��̋ߎ�����p���A�Θ_�I�Ȋm���U�����Ă��܂��B
�@�@
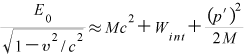
�@�����Ƃ��A�_�b�V����t����Ɣς킵���̂ŁA�r���ŏ���ɂ͂����Ă��܂����B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���Θ_�ɂ����Ď���i���Ԃ���ы�ԁj���Ȃ����Ă���Ƃ��䂪��ł���Ƃ����Ƃ��ɂ́A��������̂䂪�݂Ǝ����I�Ȃ䂪�݂�����܂��i���I�Ȑ��w�̗p����g���ƁA�ȗ��e���\���ŕ\�����̂���������̂䂪�݁A�X�J���[�ȗ��ŕ\�����̂������I�Ȃ䂪�݂ł��j�B���R�ȋ�Ԃʼn����x�^������Ƃ��Ɋϑ������̂́A���̂����A��������̂䂪�݂ł��B�O�p�`�̓��p�̘a��180�x�ƈقȂ�l�ɂȂ�̂́A�����I�Ȃ䂪�݂̌��ʂȂ̂ŁA�����x�^�����郍�P�b�g�����ł́A�ϑ��͂ł��܂���B
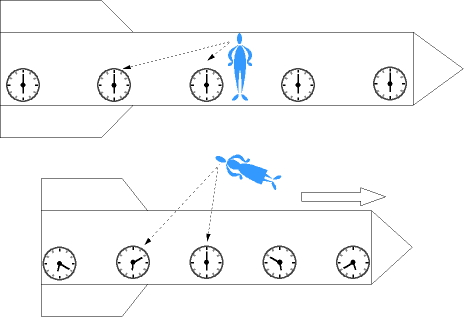
�@���Θ_�I�Ȍ��ʂƌĂ����̂̑����́A���݂ɉ^������ϑ��҂̊ԂŁA���Ԃ�����Ă��邱�ƂɋN�����܂��B����ȃ��P�b�g�̐i�s�����Ɏ��v����ׂ��ꍇ���l���܂��傤�B���P�b�g�̏���ɂƂ��āA�S�Ă̎��v���������Ă����Ƃ��Ă��A���P�b�g�̊O�ɂ���l���炷��ƁA��[�ɋ߂����v�قǒx��Ă���悤�Ɋϑ�����܂��i���v����ϑ��҂̂Ƃ���܂Ō������B����̂Ɏ��Ԃ��|����̂ŁA�ڂŌ��Ă����Ȃ�킯�ł͂���܂���j�B���P�b�g�̏�����炷��ƁA�O���̐l�́A���P�b�g�̒����𑪂�Ƃ��A��[���ƌ�[���̈ʒu���ɑ��肷��̂ł͂Ȃ��A��[���͏����O�̎����A��[���͏�����̎����ő��肵�Ă��܂��B���̂��߁A���������̏���Ă��郍�P�b�g���A�g���ۂ́h���������Z���ϑ�����邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A������u���[�����c�Z�k�v���N���闝�R�ł��i����ȊO�ɂ��A���P�b�g�����ƊO���Ƃō��W���݂��ɌX�����Ƃɂ����ʂ������܂��j�B
�@���P�b�g����������Ƃ��ɂ́A���Ԃ̂��ꂪ��[����̋����ɔ�Ⴗ��傫���łȂ��Ȃ�A���̌��ʂƂ��āA���P�b�g�����ł́A��[���ɔ�ׂČ�[���̎��Ԃ��������i�ނ��ƂɂȂ�܂��B���̕������������x���Ȃ�̂ŁA��Ԃ����̔}���ƌ��Ȃ����Ƃ��̋��ܗ�����[�ɋ߂��قǑ傫���Ȃ�A�^�ł������Ȃ����Đi�ނ��̂悤�Ɋϑ�����܂��B���̂��߁A���P�b�g�̏�����猩��ƁA����������Ԃ��䂪��ł��邩�̂悤�Ɋ������܂��B�������A����́A�����܂Ō�������̂䂪�݂ł���A���ۂɂ䂪��ł���i�X�J���[�ȗ����[���Ƃ͈قȂ�j�킯�ł͂���܂���B
�@��Ԃ����ۂɘc��ł��邩�ǂ������ϑ�����ɂ́A����߂Đ��x�̍����@�킪�K�v�ł��B�Ⴆ�A�n���̎�������l�H�q�������ł́A�قƂ�ǖ��d�͏�ԂɂȂ�܂����A�����Ɍ����ƁA�q�������ł����Ă��A�n������̋�������苗����艓���Ȃ�Ƃ킸���ɉ��S�͂�����A�t�ɋ߂��Ȃ�Əd�͂������āA���S�Ȗ��d�͂ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B���������d�͂̍���܂ő��肷��ƁA�����I�Ȃ䂪�݂����炩�ɂł��܂��B
�@���݂̊ϑ��f�[�^�ɂ��A�F����Ԃ͂䂪�݂̂Ȃ����R�ȃ��[�N���b�h��Ԃ��Ƃ���Ă��܂����A����́A��Ԃ̎����I�Ȃ䂪�݂����w�I�f�[�^�Ȃǂ��g���Ē��ڊϑ������̂ł͂Ȃ��A��͂��݂��ɉ������鑬�x����ɂ��ĉF���S�̖̂c���̎d���ׁA���̌��ʂ𗝘_�Ɣ�r���ē����ꂽ���_�ł��B
�@�����O�ɁA����̈�̋�͂̌ŗL�^���i�S�̓I�ȉ^������̂���j�����̕�������Ƃ���A�ϑ������͈͂̊O�ɋ���ȏd�͌�������A�ϑ�������͂͑S�āA�����Ɍ������ė������Ă���Ƃ����������ꂽ���Ƃ�����܂����B���C���̐ꂽ�G���x�[�^�����R��������Ƃ��A�����̐l�́A���d�͋�Ԃɕ�����ł���悤�Ɋ������܂����A���̐��ɂ��A�ϑ������͈͂̉F���S�̂��A���傤�Ǘ������̃G���x�[�^�����ɑ�������킯�ł��B�����������������ۂɎ����悤�ȉF���̗��_�I�ȃ��f�������Ȃ��̂ŁA���̐��͂��܂�x������܂���ł������A�\�����Ȃ��Ƃ͌����܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�v�����N���Ԃ����Ԃ̊�{�P�ʂ��Ƃ��闝�_�́A���܂���������Ă��炸�A�����܂ŗ��_�Ƃ̐����ł�������܂��A����ł��A�����̌����҂́A�M�ߐ��̍����������ƍl���Ă��܂��B���̗��R�́A���Ԃ��Ԃ̍\�������肷��悤�ȕ����萔�̑g�ݍ��킹���A�v�����N���ԁi���邢�́A�������Ԃ̒P�ʂɊ��Z�����v�����N���j�����Ȃ�����ł��B
�@�����萔�ɂ́A�l�Ԃ�����Ɍ��߂��P�ʂ𑊌݂Ɋ��Z���邽�߂̊��Z�萔�i�����A�v�����N�萔�Ȃǁj�A�r�b�O�o������̏�ԕω��ɂ���Ē�܂�����Ԓ萔�i�d�q��N�H�[�N�̎��ʂȂǁj�A�P�ʂ̂Ȃ��������̒萔�i���\���萔�Ȃǁj������܂����A���̂ǂ�Ƃ��قȂ閜�L���͒萔�Ɗ��Z�萔��g�ݍ��킹�č�����B��̎��������萔���A�v�����N���ԁi�v�����N���j�ł��B���̒萔���A�~�N���̋Ɍ��ɂ����鎞�Ԃ��Ԃ̍\���Ɗւ������͂����Ɨ\�z���t���܂��B�������A��̓I�ȗ��_���\�z���Ȃ�����A����ȏ�̋c�_�͂ł��܂���B���L���͒萔�ƃv�����N�萔�Ȃǂ�g�ݍ��킹�č��萔�Ȃ̂ŁA�ʎq�d�͗��_�ŏd�v�Ȗ������ʂ����͂��ł���A���Ђ����_��[�v�ʎq�d�͗��_�ł�����x�̋c�_���Ȃ���Ă��܂����A��������m��I�ł͂Ȃ��A�����̕����w�҂Ɏx������Ă����ł�����܂���B
�@����ɂ���̂́A�u���Ԃ��Ԃ��A�P�ӂ��v�����N���ԁi�v�����N���j�ł���悤�ȃu���b�N����\�z�����v�Ƃ����C���[�W���Ǝv���܂����A���ԁE��Ԃ́A����ȂɒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�����炭�A���ԁE��Ԃɂ́u�X�P�[���s�ϐ��v���Ȃ��A���Ԃ��Ԃ��g�債�Č����郂�j�^�[���g���ĕ������ۂ��f���o���ƁA����Ƃ���܂Ŋg�債���i�K�ŁA�����@�����傫���ς��ƍl�����܂��B
�@�X�P�[���s�ϐ��Ƃ́A���������������Ă��\�����ω����Ȃ��Ƃ��������ł��B���ԁE��Ԃ�\���̂Ɏg��������́A�܂��ɁA���̐�������������ł��B�Ⴆ�A�S���R���g���Đ�������\�����ꍇ�A�����I�ɃS���R��L������k�߂��肵�ĐV���Ȑ���������邱�Ƃ��ł��܂����A�������č�����������́A�ȑO�̐������Ɣ�ׂĐ��l�̊���U�肪�ς�邾���ŁA�����Ƃ��Ẳ�͓I�Ȑ����͓����ł��B��������Ŋ����`�����ꍇ�A�����\���Ȃǂ̐����́A��������L�яk�݂����Ă��ς��܂���B���������������A�X�P�[���s�ϐ��ł��B���݂̕����w���_�ł́A�X�P�[���s�ϐ��̂�������ɂ���Ď��ԁE��Ԃ�\�����߁A���Ԃ��Ԃɂ��X�P�[���s�ϐ�������ƍ��o�������ł����A�����̎��ԁE��Ԃ́A�����ŕ\�����悤�ȍ\���ł͂Ȃ��ƍl�����܂��B
�@����ł́A��̓I�Ɏ��ԁE��Ԃ͂ǂ̂悤�ȍ\�������Ă���̂ł��傤���H �z���ł���̂́A�Q�_�Ԃ̋��������������Ă����ƁA�v�����N���ԁi�v�����N���j���x�̃X�P�[���ȉ��ł́A�����I�ɋ�ʂ��邱�Ƃ��}���ɍ���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�����Ȃ�A�Q�̐��͓��������قȂ邩�̂ǂ��炩��������܂��A���ԁE��Ԃ̂Q�_�́A�����I�ȋ�ʂ�����ɞB���ɂȂ�A�~�N���̋Ɍ��ł͎��ʂ��s�\�ɂȂ�ƍl�����܂��B����Ɍ����A���ԁE��Ԃ͕����I�Ȏ��݂ł͂Ȃ��A�^�̎��݂̊W����l�Ԃ������ł���`�ŕ\�����߂ɕK�v�ȋ��\���Ƃ����\��������܂��B���������\�����������闝�_������܂����A�܂������r��ł��B
�@������ɂ���A�܂��킩��Ȃ����Ƃ��炯�ł���A�͂����肵�����Ƃ͌����܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@����ɂ���T�C�g�ł́A���[���[/�~���[�̎����ȂǁA20���I�ɓ����Ă���s��ꂽ���������������Љ��A���̂�����ɂ����Ă��A���Ȃɂ킸���ȓ����ω��������邱�Ƃ�������Ă��܂��B�Î~�G�[�e�������肷�闝�_�̗\�z���͗y���ɏ��������߁A�ʏ�́A�G�[�e���̑��݂�����������̂ł͂Ȃ��A���x�ω��ȂǂɋN������덷���Ɖ��߂���܂����A���Θ_�ł͊��Ȃ��S���ω����Ȃ��͂��Ȃ̂ŁA���̌��ʂ����Θ_�̔��ɂȂ�Ȃ��̂��A�C�ɂȂ�l������ł��傤�B
�@���_���猾���ƁA�قƂ�ǂ̕����w�҂́A���̓����ω��͒P�Ȃ�����덷�ł����āA���Θ_�ɑ��锽�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă��܂��B���̔w�i�ɂ́A�����ɂ�錟���ǂ̂悤�ɍs���ׂ����Ɋւ���A�����w�\�T�C�G�e�B�ł̈Öق̍��ӂ�����܂��B
�@���������A�����ɂ��덷���[���ɂ��邱�Ƃ́A�������Ƃ��ĕs�\�ł��B�g�G�[�e���̕��h�����o���悤�ƃ}�C�P���\�����ŏ��ɍs���������ł��A���Ȃ�傫�Ȋ��Ȃ̓����ω����ϑ�����Ă��܂����A����́A�������̑O��n�Ԃ��ʍs���邱�ƂȂǂɂ��U�����e�������\��������܂��B���������덷�����������邱�Ƃ��A�����ƂɂƂ��čł�����ǂ��d���ł��B�Ő�[�̑�^������ł��A�߂��Ƀg���b�N���ʂ�ƃf�[�^���������̂Ō�ʂ𐧌�����Ƃ��A������̒����͂ɂ���ĉ����킪�䂪�ނ̂ŕ���s���Ƃ��A���Ƃ����Č덷���Ȃ������Ƃ��܂����A���ۂɂ́A�����Ƃ�����Ђ˂�덷���ǂ����Ă��c���Ă��܂��܂��B�����ŁA�����w�ɂ����鐸�������̃f�[�^�ɂ́A�K���G���[�o�[�i�덷���ǂ͈̔͂܂ł��邩���A�f�[�^�|�C���g�̏㉺�^���E�ɐ����Ŏ��������́j��t���邱�Ƃ����K�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���v�I�Ȃ���ȊO�Ɋւ��āA�G���[�o�[�̒������ǂ����߂�Ηǂ����A�����͂���܂���B�����サ�炭�o���Ă���A�������l���G���[�o�[��傫���͂���Ă������Ƃ��������A�Ԉ�����f�[�^�����Ƃɘ_���������Ă��܂������_�Ƃ��������邱�Ƃ��A��������イ�ł��B
�@�덷�̓[���ɂł��Ȃ����Ƃ��l�����A�����f�[�^�́A�����܂ŗ��_�̌��̂��߂ɗp����Ƃ����̂��A�����w�҂̊�{�I�ȍ��ӎ����ł��B�G���[�o�[�͈͓̔��ŗ��_�̗\���l�ƈ�v���Ă���Η��_�̌��ɂȂ�A��v���Ă��Ȃ���Η��_���������Ƃ�����ł��B���[���[/�~���[�̎������ʂ́A�u���͐Î~�G�[�e���ɑ��Ĉ��̑��x�œ`�d����i�n���̉^���ɂ���āA�ϑ�����鑬�x���ω�����j�v�Ƃ������_�̗\���l�Ƒ啝�ɈقȂ�i�����̘_���ɂ́A�G���[�o�[��������Ə������܂�Ă��܂��A������덷�͈͂Ƃ���ƁA���Ȃ��ω����Ȃ��P�[�X���܂܂�Ă��܂��܂��j�̂ŁA���̔��ƌ��Ȃ���܂��B�t�ɁA���Ȃ̕ω�����Î~�G�[�e���ɑ���n���̑��x�����߂�ƁA�b��10�L�����[�g�����x�ƂȂ�A�V���w�I�Ȋϑ��f�[�^�i�n���͑��z�n����b��30�L���Ō��]���Ă��邱�ƁA����сA�V�̂̌��w���� ���ꂪ�Ȃ��̂ŐÎ~�G�[�e���̈���������ʂ��Ȃ����Ɓj�Ɩ������܂��B�����ω��������炷�����͔������Ă��܂��A�����̕�����Ȃ��덷�͂悭����̂ŁA���̃f�[�^�ƍ��v����悤�ȉ��炩�̗��_����o����Ȃ������́A�����w�҂̍��ӂɊ�Â��A�P�Ȃ�덷�Ƃ��ĖَE����܂��B
�@�����f�[�^�ɂ͌덷���t�����Ȃ̂ŁA�u�ϑ��l������̒l�ɂȂ�v���Ƃ������Ɏ������Ƃ͂ł����A���̂��Ƃ�B��̍����Ƃ���悤�ȗ��_�́A���܂Ōo���Ă����ł��܂���B���Θ_���A�u�����������Ɉ��ł���v���Ƃ������I�Ɏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ȃ�A���������_�ł���Ƃ͉i���ɔF�߂��Ȃ��ł��傤�B���Θ_�������w�҂ɔF�߂�ꂽ�̂́A�u�����������Ɉ�肾�v�Ƃ����������ʂ�����ꂽ����ł͂Ȃ��A���Θ_���瓱����邳�܂��܂ȋA���������I�Ɋm�F���ꂽ����ł��B
�@�Ⴆ�A���Θ_�̊�ɂȂ郍�[�����c�s�ϐ���O��Ƃ���ƁA�f���q�����̃p�^�[���Ɉ��̐������t�����Ƃ������܂��i�t�F���~�̗��_�j�B���݁A��^��������g���Ă��܂��܂ȑf���q���������ׂ��Ă��܂����A���̐�����j�邱�Ƃ����m�Ɏ����ꂽ�P�[�X�i�t�F���~�I�����������̑O��ŕω�����Ȃǁj�́A���܂�����܂���B�Ȃ��A����ȃG�l���M�[�őf���q���m���Ԃ��ĕ��G�Ȍ��ۂ������N�����Ă���̂ɁA��Ɉ��̐������̔��������N���Ȃ��̂�---�u���Θ_������������v�Ƃ����̂��ł��ȒP�ȉł���A����ȊO�̐����͌������Ă��܂���B
�@�����悤�ɁA�j����ɂ���ĉ�������G�l���M�[���A���Θ_���瓱�����A�C���V���^�C���̌��� E=mc
2 �ɏ]�����Ƃ��m�F����Ă��܂��B�j���������́A�d���C���ۂƂ͈قȂ鑊�ݍ�p�ɋN��������̂Ȃ̂ŁA���̌��ۂ��A�������������̏�ň��ɂȂ邱�Ƃ������Θ_�I�ȗ��_�Ő����ł���Ƃ͎v���܂���B
�@���Θ_�ɋ^���̖ڂ�������l�́A�����̏ꍇ�A�������Ƃ��������ᔻ���܂����A���̉���́A�����܂Ń��[�����c�ϊ��̎����ő��œ������߂̕X�I�Ȃ��̂ł���A���Θ_�̌����ł͂���܂���B�����̈�萫���m�F��������͍����������Ă��܂����A����́A���q���v�Ȃǂ̎����@��̐��x�����サ�Ă��邱�Ƃ������f�����X�g���[�V�����ł����āA���̎����ɂ���đ��Θ_�������悤�Ƃ������̂łȂ����Ƃ𗝉����Ă��������B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�M�́A�����Ă��܂��Ɓg�N�Y�h�G�l���M�[�ł���A�d���������ƒ�R�킪���M������A�^���G�l���M�[�����C�M�ɕς�����肷��悤�ɁA�i�ʂ̋@�\��p�ӂ��Ȃ��Ă��A���̃G�l���M�[�����R�ɓ]�����Đ�������̂ł��B���̂��߁A�d�M���K�X����������Ȃǂ̉��M���u�ł́A�킴�킴�p��i�]���ȗ�C����菜���A���Ȃ킿�A�O���炳��ɔM��������j���s���܂���B�������A���M�̌��������߂邽�߂ɁA�p����s���ꍇ������܂��B�ߔN�ACM�ŗǂ���������q�[�g�|���v�𗘗p�����g�[�́A���������M����ۂɊO�C�̔M�����p����̂ŁA���O�ɗ�C���̂Ă�V�X�e�����ƌ��Ȃ��܂��B
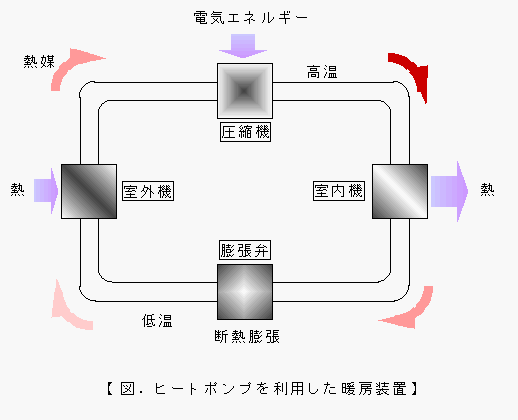
�@�q�[�g�|���v�ɂ��g�[�@��́A�ʏ�̗�[���������蔽�ɂ������̂ł��i�}�Q�Ɓj�B�܂��A�M�}�i�e�ՂɈ��k�E�c����������}���j��d�C�G�l���M�[�ʼn��M���A�����@��ʂ��ĕ����̒���g�߂܂��i�}�ł͎����@���璼�ڔM�����o�����悤�ɕ`���܂������A���ۂɂ́A������i�̔M�������s���āA���g�[���s���ꍇ�������悤�ł��j�B�����ɂȂ����M�}�́A���͂����C���������̂ŁA�c���ق��J�����Ēf�M�c��������ƁA�}���ɉ��x��������܂��B�������ĊO�C�����ቷ�ɂ����M�}�����O�@�ɑ��荞�ނƁA�O����M����荞�݂܂��B��[�̎��O�@����͔M�����o�Ă��܂����A���̒g�[�V�X�e���ł́A���O�@����O�C�������Ⴂ�╗���o�܂��B�������ĔM�}���z������ƁA�����@������o�����M�G�l���M�[�́A���k����̂ɗv����d�C�G�l���M�[�����傫���Ȃ�A�����I�Ȓg�[���\�ɂȂ�܂��B
�@���M���u�ƈقȂ��āA��p���u�́A�M��D���Ƃ����s���R�ȉߒ����������邽�߂ɁA���R�G�l���M�[�𓊓����Ȃ���Ȃ�܂���B�ʏ�́A���������G�l���M�[���M�ɓ]������̂ŁA�p�M�i�r�M�j���K�v�ƂȂ�܂��B�������A�]���ȔM���������Ȃ��悤�ɂ��ăG���g���s�[�̏�������Ԃ������ł���A�p�M���Ȃ��Ă���p���\�ɂȂ�܂��B
�@��̓I�ɂ́A�[���Ɋ����������z���ނ𐅑��ɋ߂Â��A�������������邱�ƂŋC���M��D���ė�p������@������܂��B�z���ނ̊����ɂ͔M�����g���邱�Ƃ������̂ŁA�ʏ�͗]���ȔM����菜���K�v������܂����A�M�����g�킸���Ԃ��|���Ċ��������邱�Ƃ��ł���A�p�M�Ȃ��̗�p���\�ɂȂ�܂��B
�@�ቷ�����̎����ł́A�����Βf�M�����Ƃ������@���g���܂��B�펥���̂ɋ���������������܂܉t�̃w���E���Ȃǂŗ�p����ƁA�X�s���Ɋւ��ẮA�����̂�������G���g���s�[�̏����ȏ�ԂɂȂ�܂��B���̌�Ŏ������菜���ƁA�����̂̎��M�G�l���M�[�̈ꕔ���X�s���ɂ����z�����̂ŁA���x���ቺ���܂��B�������A���̕��@�́A�����Ɏg���������ɒቷ�ɂ��邽�߂ɗ��p�������̂ŁA��K�͂ȗ�p�ɂ͎g���܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�嗤�̓v���[�g�e�N�g�j�N�X�ɂ���Ĉړ����܂����A���̍ہA���S�́E�R���I���͂Ȃǒn���̎��]���傫�ȉe�����y�ڂ��Ƃ͍l�����܂���B�n���\�ʂł́A�ꏊ�ɂ���ďd�͂Ɖ��S�͂��قȂ�܂����A���̌��ʂ͎�ɉ��������Ɍ���A�嗤���쓮����͂Ƃ͂Ȃ�܂���B�܂��A�嗤�ړ��̃X�s�[�h������߂Ēx���̂ŁA�R���I���͂̊�^�����S�ɖ����ł��܂��B���������āA�n���̎��]�͑嗤�ړ��ɉ��̉e�����Ȃ��͂��ł���A�u��ɂɑ嗤������A�k�ɂɂ͊C���L����v�Ƃ����́A�S���̋��R�ɂ���Ď������ꂽ�Ǝv���܂��B
�@�嗤�ړ��́A�����I�ȃ}���g���̏�ɍڂ����v���[�g�̓����ɂ���Ĉ����N������܂��B���傤�ǔM���̏�Ƀv���X�`�b�N�̔������������ׂ��悤�ȏŁA�㏸���Ɖ��~�����ǂ��ɐ����邩�ɂ���āA�嗤���W�܂����藣�ꂽ�肵�܂��B�㏸���Ɖ��~�����ǂ̂悤�ɂ��Ăǂ��ɂł��邩�́A�܂����S�ɉ𖾂ł��Ă��Ȃ��悤�ł��i�v���[���e�N�g�j�N�X�ƌĂ�闝�_�����ݓr��ł��j���A�����N�Ƃ����^�C���X�P�[���ŗ�������ω����Ă���A����ɉ����āA�嗤�̏W�܂�����ς��܂��B
�@���݂ł́A�n���C�Ƃ�������ڂ��������A�t���J�ƃ��[���V�A�i�C���h���嗤���߂肱��ł��܂��j�A��k�Ɉ���������ꂻ���ȓ�k�A�����J�Ƃ����Q�̒��嗤�ƁA�Ǘ�������ɂ���уI�[�X�g�����A�̗��嗤������܂��B�����́A�Q���N�قǂ܂��ɂ́A�p���Q�A�ƌĂ���̒��嗤���������Ƃ��m���Ă��܂��B�������A�̂�����������ł͂���܂���B�p���Q�A�́A�Q���T�疜�N�قǑO�܂łɁA�S���h���i��[�����V�A�ȂǕ����̑嗤���Փ˂��Ăł����ƍl�����Ă��܂��B�n���C�Ɋ�Â��f�[�^�ɂ��A����ȑO�ɂ��A�嗤�̕���E���̂��J��Ԃ���Ă������Ƃ��������Ă��܂��B������������E���̂ɉ��炩�̋K����������������Ζʔ����̂ł����A10���N�ȏ�O�̂��ƂɊւ��Ă͕s���ȓ_�������A���m�Ȃ��Ƃ������Ȃ��ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�l�H�I�Ȋj�Z���F�ł́A���x�▧�x�Ɋւ��锽���������ɂ₩�Ȃ��Ƃ���A�d���f�𗘗p���������i�d���f�|�d���f�A�d���f�|�O�d���f�A�d���f�|�w���E��3�Ȃǁj�����p����܂��B�����q���Ȃ��ꍇ�ł��A�z�q���z�d�q����o���Ē����q�ɕω����锽������Ċj�Z�����i�s���邱�Ƃ��\�ł����A�z�q�������q�ɕς�锽���͋N����m�������������߁A�G�l���M�[�ϊ������͂��܂荂���Ȃ�܂���B������x�ȏ�̌������v�������j�Z���F�ł́A�d���f�̂悤�ɕ��ς�蒆���q�̔䗦���������ʑ̂��A�j�R���Ƃ��Ă��炩���ߗp�ӂ��Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�@����A���z�Ȃǂ̍P���ł́A�j�R�����O�����狟���ł���j�Z���F�ƈقȂ�A�P�������ɒ~����ꂽ������R���Ƃ��āA�����ɂ킽���Ċj�Z�������������Ȃ���Ȃ�܂���B�r�b�O�o������ɂ́A�d���f��O�d���f����������܂����A�P�������ł́A�����͂��܂��܂Ȋj�����ɂ���Ă����ɏ����Ă��܂��A�����I�Ȋj�Z�����s�����Ƃ��ł��܂���B���̂��߁A���̘͂f���n�ɐ����������ł���قǂ̊��ԁi�����N�ȏ�j�ɂ킽���Ċj�Z�����s���ɂ́A���Ƃ��Ƒ�ʂɑ��݂���z�q�������g���Ċj�Z���𑱂���K�v������܂��B�����ŗ��p�����̂��App�`�F�C���ƌĂ�锽���ŁA�ŏ��ɁA�Q�̗z�q�ip�j����d���f���q�j�id�j�A�z�d�q�ie
+�j�A�j���[�g���m�iν�j������锽�����N���܂��i�z�q�̂����̂P�́A�z�d�q����o���Ē����q�ɕς���Ă��܂��j�B
p+p��d+e++ν
���̌�A�������Ăł����d���f���j�R���Ƃ��āA����Ȃ�j�Z�������i�������̕�����܂��j���i�s���܂��B
�@pp�`�F�C���́A���N����m���̏������z�q�������q�̕ϊ��ߒ����܂܂��̂ŁA���M�ʂ͂��܂�傫������܂���B���z�̏ꍇ�A���S���ł��P�����Z���`������0.3�~�����b�g���x�����Ȃ��A�l�̂ɂ�����P�ʑ̐ς�����̔��M�ʂ�菬�����Ȃ��Ă��܂��B���z���c��ȔM����o�ł����̂́A���ʂ�����߂ċ��傾����ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�t�@���f�����[���X�͂́A�Q�̕��q��������x����Ă���Ƃ��̕��q�ԗ͂̒��ŁA�d�ד��m�̑��ݍ�p�A�o�Ɏq���ݍ�p�ȊO�̂��̂̂����A��r�I�傫�Ȉ��͂��w���悤�ł����A�ǂ����A�����Ȓ�`������킯�ł͂Ȃ������ł��B
�@���q�ԗ͂́A�Θ_�I�ʎq�͊w�i���q�̗ʎq�_�j�ŁA�قڊ��S�ɋL�q�ł��܂��B�Q�̕��q���ڋ߂���ƁA���ꂼ��̕��q�Ɋ܂܂��d�q�ƌ��q�j�i���q�̋c�_�ł́A�_���q�Ɖ��肳��܂��j�́A���̑S�Ă̓d�q�^���q�j�Ɠd���C�I�ȑ��ݍ�p�����邽�߁A�[���ɗ���Ă���Ƃ��ɔ�ׂĔg������G�l���M�[���ʂ��ω����A����ɔ����ė͂��܂��B�������A���̕ω��̓R���s���[�^�łȂ���Όv�Z�ł��Ȃ��قǕ��G�ŁA�����N���Ă��邩�A�l�Ԃ̓��]�Ŋ��S�ɗ������邱�Ƃ͕s�\�ł��B�����ŁA���q��������x����Ă���Ƃ��́A�[���ɗ���Ă���Ƃ��Ɣ�ׂĔg���������������ω����Ă��Ȃ��Ɖ��肵�A���q���m���y�ڂ��͂�i�K�I�ɐ�������̂���ʓI�ł��B
�@���q���[���ɗ���Ă���Ƃ��A�Q�̕��q���d�ׂ������Ă���ꍇ�́A�����̂Q��ɔ���Ⴗ��N�[�����͂��x�z�I�ɂȂ�܂��B�d�ׂ͂Ȃ����̂́A�����q�̂悤�ɐ��d�ׂƕ��d�ׂ�������ēd�C�o�Ɏq���[�����g�����ꍇ�́A�P���ߎ��Ƃ��āA�����̂R��ɔ���Ⴗ��o�Ɏq���ݍ�p������܂��B
�@�d�ׂ��d�C�o�Ɏq���[�����g���Ȃ����q���m�̑��ݍ�p�ł́A�N�[�����͂��o�Ɏq���ݍ�p������܂���B���̂Ƃ��A�e���q�̔g�������ω����邱�Ƃɂ���Č����͂��A1/
r�̃x�L�i
r�͕��q�ԋ����j�œW�J����ƁA
r����r�I�������Ƃ��Ɏx�z�I�ɂȂ�̂́A��ʂɁA1/
r��6��̍��ł��i�u
r����r�I�������Ƃ��v�Ƃ����B���ȕ\�������܂������A���q�̑傫���Ɠ����x�܂Őڋ߂���ƁA�ʎq�_�I�Ȍ��ʂł�������˗͂��}�ɋ����Ȃ�̂ŁA���̗͂������ł�����x�ɂ͗���Ă���Ƃ����Ӗ��ł��j�B�t�@���f�����[���X�͂Ƃ������t�́A���̍������Ɍ��肳���ꍇ������܂����A�N�[�����́E�o�Ɏq���ݍ�p�E�����˗͈ȊO�̕��q�ԗ͂̑��̂Ƃ��Ďg����ꍇ������܂��B
�@1/
r6�̍������ɗR�����邩�́A�P���ł͂���܂���B�ł��킩��₷���̂́A�d�C�I�ɒ����̕��q�ł����Ă��A���q�Ɋ܂܂��d�q�^���q�j�Ԃ̓d�C�I���ݍ�p�ɂ���ēd�q�̈ʒu����o�Ɏq���[�����g���U�N����邽�߁A���̗U�N���[�����g���m�̑��ݍ�p�ɂ���Č����Ƃ����l�����ł��i���[�����g���U�N�����ߒ��́A�������茾���A���q�����̃v���X�ƃ}�C�i�X�̓d�ׂ������������Ƃœd�q���邱�Ƃł��j�B�������A����ȊO�ɂ��A1/
r6�̍��������炷���ʂ�����̂ŁA�t�@���f�����[���X�͂̋N���͂��Ȃ蕡�G���ƌ����Ă����܂��B
�@�Q�̕��q���������݂����ɉ����Ȃ���Ԃł́A�i�d�q�̌����c��łȂ��Ă��j�t�@���f�����[���X�͂̓��B�͈͖͂����ɂȂ�܂��B�������A����
r��6��ɋt��Ⴗ��t�@���f�����[���X�͂́A���������Ƌ}���ɗ͂��キ�Ȃ�i�t�Q��͂Ȃ������2�{�ɂȂ�Ɨ͂�1/4�ɂȂ�̂ɑ��āA�t�U��ł�1/64�ɂȂ�j�̂ŁA�����I�ɔ�r�I�ߋ����ł̂ݍ�p����ƍl���Ă��܂��܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�Ⴊ�a������ȑO�ɂ͎���튯�͑��݂����A�������邱�Ƃ��킩��Ȃ��܂܁u��̌`����ڕW�ɐi�����N�����v�ƍl����ƁA�m���ɕs�v�c�Ȃ��Ƃł��B�������A���ۂɂ́A�n����ɐ������o�ꂵ������������͂��܂��܂Ȍ`�ŗ��p����Ă���A��́A�����܂Ō��������シ��ߒ��Ō`�����ꂽ�튯�ɂ����܂���B
�@�n����ɐ����������ۂɏd�v�������̂́A�n�\�̉��x�������t�̂ł�������x�ɒႩ�����̂ɑ��āA�����ɍ~�蒍�����́A���z�̕\�ʉ��x�i6000K�j�ɑ�������G�l���M�[���z�������Ă������Ƃł��B���̂��߁A���G�l���M�[���q�ɂ��������ɂ���ĊC�����ɔ�r�I���q�ʂ̑傫������������������Ă��A���x���Ⴂ�̂ŔM�������ꂸ�ɒ~�ς���܂��B�����́A���Ɣ������ĉ��w�\����ω������镪�q�̃X�[�v���Œa�������̂ł���A����̂ɁA�����̐����́A�����������q��ϋɓI�ɗ��p����悤�ɂȂ����ƍl�����܂��i�����́A�C��̔M�����o���t�߂Œa�������Ƃ�����������܂����A�����������S�x�����Ȃ��A�p���I�ɃG�l���M�[�������ł�����Ԃ��Z���C��̔M�����A�����̐����ɕK�v�ȉ��w������S�ėp�ӂł����Ƃ́A���ɂ͎v���܂���j�B�ŏ��́A�����G�l���M�[���Ƃ��ė��p����Ɨ��h�{���������܂�A�u���Ɣ������ĉ��w�\����ω�������v���������R�[�h�����`�q�����Ɏ������̂ł��傤�B
�@���Ɣ������鉻�����́A������G�l���M�[��ȊO�ɂ��p�r������܂��B���������������������_���ȓˑR�ψقɂ���đ̂̂��������ō��o�������ɁA�M���`�B�n�ƌ��т��āA�����V�O�i���Ƃ��ė��p���鐶�������ꂽ�͂��ł��B���݂ł��A�Ⴊ�Ȃ��̂Ɍ����V�O�i���Ƃ��Ċ������\�͂��������́A���������݂��܂��B�����̐A���́A���������邩�ǂ����ɂ���čזE���B���x���R���g���[�����A���̌����ɉ����č���s���������ς��܂��i�����j�B�P�זE�����ł���~�h�����V�́A�ږт̕t�����Ɍ��Ǝ˂ɂ���Ċ������ω�����y�f�������Ă��邽�߁A���̂�����ɐi�ށu���̑������v�������܂��B�܂��A�_�j�͊Ⴊ�Ȃ��i�����Ă��n��ȋ@�\���������Ȃ��j�ɂ�������炸�A��Ƃ͈قȂ�튯�i�Ԗ��O����e��j�ɂ���Č����������A�P���̂������邢���Ԃ��������Z�����ōs���p�^�[����ω������Ă��܂��i�������j�B
�@���݂������邱���̌��n�I�Ȏ���튯���A�������I�Ɍ����W�߂�g��h�ɐi������ɂ́A(1)���Ɣ������鉻�����i����e�^���p�N���Ȃǁj��̕\�ʂɂ������̖��g�D�i�Ԗ��j�ɏW�ς���A(2)�������ʂɋ��S���̐_�o��ʂ��Č������̃V�O�i����`�B�ł���悤�ɂ���A(3)�Ԗ��̊O���ɏW���@�\���������ȑg�D���`������|�|�ȂǁA�������̏�������������邱�Ƃ��K�v�ł��B�X�̏����́A�ˑR�ψقɂ���ċ����I�ɖ�������邱�Ƃ����蓾�܂��B�Ⴆ�A�N���Q�ȂǓ����ȑ̑g�D���������͌����Ē������Ȃ��A���������g�D������`�q���ُ�𗈂��āA�̂̈ꕔ�����������邱�Ƃ��A�[���ɂ��蓾��ł��傤�B�������A�S�Ă̏����������ɖ�������Ċ�Ƃ��Ă̋@�\�����������̂͂���߂ċH����A���������ˑR�ψق����̂��A�ψقɂ���Ĕ��s���v�����z���Đ������т邽�߂ɂ́A��������ƂŐ��������啝�Ɍ��シ��̂łȂ���Ȃ�܂���B�������������ɂȂ����Ɛ��������̂��A�J���u���A�I�ɂ�����ߐH�҂̓o��ł���A�ߐH�҂��瓦���i���邢�́A�ߐH�҂��a��������j�ɂ́A��������Ƃ�����߂ėL���ɍ�p�����Ƃ����ł��B���́A��������ɔ�ׂē`�B���x�������A�������i�������̂ŁA��������Ă���A�ߐH�҂̐ڋ߂𑁊��Ɋ��m���Ĕ��邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A�J���u���A�I�ŋ��̓��H�b�ł���A�m�}���J���X���������Ă������A�����ɂT�̊�����I�p�r�j�A�Ƃ������������܂������A�����炭�A�C��ŏ�����グ�A�T�̊�ŃA�m�}���J���X�𑨂���Ƒ�}���œ����Ă������̂ł��傤�B
�@���łɌ����Ă����ƁA��̌`�����y���ɓ���̂��A���̌`���ł��B�P�Ȃ鈳�̓Z���T�[�Ȃ猴�n�I�Ȑ����������Ă��܂����A�U�������č����g�𑨂���@�\���ǂ̂悤�ɐi�����Ă����̂��A�ƂĂ��s�v�c�ł��i�X�e�B�[�����E�W�F�C�E�O�[���h�̃G�b�Z�C�Ŏ��グ���Ă��܂��j�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���z�n�̘f���ł́A�y���A�V�����A�ؐ��A�C�����ɗցi�j�����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�������A���̂����y���̗ւ������s�̖̂]�����ł����F�ł��閾�ĂȂ��̂ł���A����ȊO�̗ւ͊ŊȒP�ɂ͌����Ȃ����߁A�ŋ߂̃C���X�g�ł́A���܂�͂�����`���Ȃ��Ȃ����̂��ƍl�����܂��B
�@�f���̗ւ́A�q���ɑ��̓V�̂��Փ˂���Ȃǂ��ĕ����オ�����j�Ђ�o�������O��Ɋg���������̂��ƍl�����܂��B���ł��A�y���̗ւ́A�����ʂ��i�n���́j����1000���̂P�قǂ�����̂ŁA���z�n�̘f�����`������ď����o���������ɁA�q�����ӂ���قǂ̑傫�ȏՓ˂ɂ���Đ������j�Ёi��ɕX�j��o���W�܂��Ăł����Ɛ�������܂��i�����O�܂ŁA�ւ͐����N�O�Ɍ`�����ꂽ���肾�ƌ����Ă��܂������A���݂ł́A�嗬�̊w���łȂ��悤�ł��j�B���C�������O�́A�傫����1�Z���`����10���[�g���قǂ̕X�̉琬���Ă���A���x�┽�˗����傫�����߁A�ւ���̔��ˌ��ɂ���ēy���S�̖̂��邳�������قǂ�������ƌ����܂��B
�@����ɑ��āA���̘f���̗ւ́A�Ŗڗ����܂���B�ؐ��̗ւ́A�傫���������������~�N�����̐o���琬���Ă���A���m�ɂ͂킩��Ȃ����̂́A�����ʂ͓y���̂��̂ɔ�ׂĉ������������ƍl�����܂��B�C�����̗ւ��A����Ǝ��Ă��܂��B�V�����̗ւ́A�ؐ���肩�Ȃ�傫�Ȏ��ʂ������A�\�����q�������[�g���ɒB����傫���ł����A����ł��A�y���̗ւɔ�ׂėy���Ɋł��B�����̗ւ́A�����ԘI���ɂ���Ċϑ����\�ɂȂ�悤�Ȃ��̂ł���A�f���̎��͂ɋP���ւ����݂���悤�ȃC���X�g��`���ƁA�������Č���������Ă��܂��܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�u�X�|�b�g���C�g���_�v�Ƃ������t�́A���̎���ŏ��߂Ēm��܂����B�l�b�g�Ō��������Ƃ���A���̗��_�́A�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�̃u���b�h�E�X�R�E���������̂ŁA�u�F���́A�ߋ����疢���Ɏ���S�Ă̎��Ԃ����Ă���A���݂Ƃ́A�ړ�������́g�X�|�b�g���C�g�h�ɏƂ炵�o���ꂽ����̈悾�v�Ƃ����咣�̂悤�ł��B
�@���̂����A�O�i�́u�F�����S�Ă̎��Ԃ�����v�́A�����w�҂ɂƂ��Ă͒ʏ�̍l�����ŁA�u�u���b�N�F���_�v�ƌĂ�Ă��܂��B���Ƃ��Ƃ́A���Θ_�𐔊w�I�ɒ莮�����邽�߂Ƀ~���R�t�X�L�[��1907�N�ɒ����A�C�f�A�ŁA�����A�A�C���V���^�C���͂��̍l���������Ă��܂������A1910�N��㔼�Ɉ�ʑ��Θ_���\�z����ߒ��ŁA���ꂪ���ΐ������̕K�R�I�Ȍ��ʂł��邱�ƂɋC�����A��N�́A��ʐl�����̍u���ł��ϋɓI�Ɏ��グ��悤�ɂȂ�܂����B�u���b�N�F���_�ɂ��A�u���݁v�ɑ������鎞���͑��݂��܂���B���ꂼ��̎��Ԃɂ���l�������ɂƂ��Ắu���܁v���ɋ��ʂ���u���݁v���ƍ��o���Ă��邾���ŁA�����I�ɂ́A�����鎞���������ł��B
�@�u���b�N���_�͕����w�҂ɂƂ��Ēʏ�̍l�����ƌ����܂������A����ɔ�����l���F���Ƃ�����ł͂���܂���B�Ⴆ�A�f���q�_�̌����҂Ƃ��Ă��m����|�[�L���O�z�[���́A���g�̃L���X�g���M�Ɋ�Â��āA�u���b�N�F���_�ɉ��^�I�ȍl���������Ă��܂��B�������A��̓I�Ȏ��Ԙ_���Ă���ɂ͎����Ă��܂���B
�@�X�|�b�g���C�g���_�́A�u���b�N�F���_�ɂ�����g���������Ԃ�O��Ƃ��Ă��܂����A�g�X�|�b�g���C�g�h�Ƃ����A�C�f�A��p���邱�ƂŁA���݂𑼂̎��������ʂ��܂��B�������A�X�|�b�g���C�g���I�Ȍ��ۂƍl����ƁA���Θ_�Ɩ�������悤�Ɏv���܂��B���Θ_�ł́A���[�����c�ϊ��Ƃ������ԂƋ�Ԃ������荇���ϊ����{���Ă������@�����ω����Ȃ����Ƃ��v������܂��B�Ƃ��낪�A�X�|�b�g���C�g�������ɑ��݂��錻�ۂŁA�����@���ɏ]���ďƎ˂����̈悪�ߋ����疢���ֈړ�����̂Ȃ�A�X�|�b�g���C�g���ړ������镨���@�������[�����c�ϊ��ɑ���s�ϐ������Ƃ͍l�����܂���B�҂̃X�R�E�́A���̘_���ŁA�����̃X�|�b�g���C�g���_�i�]���̃X�|�b�g���C�g���_�̉��ǔŁj�����Θ_�I���Ǝ咣���Ă��܂����A�_����ǂތ���A���[�����c�s�ϐ��������Θ_�I�ȗ��_�ɂȂ��Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��i�����g�킸�Ɍ��t�Ɛ}�����Ő��������_���Ȃ̂ŁA�������lj��ł��������M�͂���܂��j�B
Bradford Skow, "Relativity and the Moving Spotlight," (The Journal of Philosophy 106 (2009): 666-678)
(http://web.mit.edu/bskow/www/research/timeinrelativity.pdf �œ����)
�@�u���b�N�F���_�ł́i�X�|�b�g���C�g���_�Ɠ������j�u�^���͂��łɌ��܂��Ă���v���ƂɂȂ�A���̒��Ől�Ԃ̎��R���ǂ̂悤�ɉ��߂��邩���N�w�I�Ȗ��ɂȂ�܂��B���́A�u�^���͎����Ƃ��Č��܂��Ă��邪�A�����@���ɂ���Č��݂̏�ԂɋK�肳����ł͂Ȃ��v�Ƃ����ϓ_����A�u���b�N�F���_�Ǝ��R�ӎu�������\���ƍl���Ă��܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�m���ɁA�R���I���͂͌������̗͂ł�������܂���B�Ȋw�҂́A�b���ȒP�ɂȂ�̂ň��ՂɃR���I���͂�p�������ł����A�F�����猩���ꍇ�́A�R���I���͔����ő䕗�̉Q���ǂ�������ɂȂ邩���������K�v������܂��B
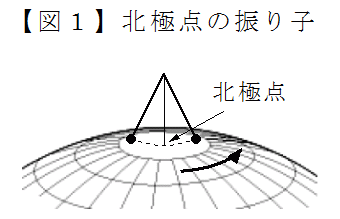
�@�܂��A�R���I���͂��ǂ̂悤�Ȃ��̂��m�ɂ��邽�߂ɁA�k�ɓ_�Ƀt�[�R�[�̐U��q��ݒu���A�F���i�n���̌��]���x�Ɠ����X�s�[�h�œ��������n�j���猩�ē����U���ʓ��������^��������ꍇ���l���܂��i�}�P�j�B�n�ʂ��������ɓ����Ă��邽�߁A�U��q���U�����S���牓�������Ă����i������ɉ^������j�Ƃ��́A�n�\����́A�����肪�������ɃJ�[�u��`���悤�Ɍ����܂��B�t�ɁA�U�����S�ɖ߂�i�k�����ɉ^������j�Ƃ��ɂ́A�n���̎���̉�]���x���x�����ܓx�n���Ɉړ����邽�߁A�n�ォ�猩���������̑��Α��x������ɒx���Ȃ�悤�ɋO�����Ȃ���܂��B���������āA�n�ォ�猩���Ƃ��̐U��q�̉^���́A�i��n�ɑ��鑊�ΓI�ȁj�^�������ɑ��ĉE�����ɋȂ����Ă����܂��B���������ω��������N�����������̗͂Ƃ��đz�肳���̂��A�R���I���͂ł��B
�@�t�[�R�[�̐U��q���ɓ_�ɒu���ƁA��ɏ�猩���Ƃ��̎��]���E���ɂȂ邽�߁A�k�ɓ_�̏ꍇ�Ƃ͋t�ɁA�R���I���͂́A�^�������ɑ��č������ɋȂ���悤�ȗ͂ƂȂ�܂��B
�@�ɓ_�ɒu�����t�[�R�[�̐U��q�̏ꍇ�́A�F�����猩��ƁA�����ʓ��ŐU��q�^�����邾���ł����A��C���ۂ̏ꍇ�́A��C���̂��n���\�ʂƂƂ��ɓ������߁A�b���������G�ɂȂ�܂��B��C����n�ɑ��Ċ��S�ȐÎ~��Ԃɂ���Ƃ��́A�d�́E���S�́E���͌��z�Ȃǂ��S�Ēނ荇������ԂɂȂ�A��C�͒n���\�ʂƓ������x�Œn���̎������]���܂��B���������C�̏�Ԃ��ω����A��C���i�䕗�j�̂悤�Ȉ��͂̒Ⴂ�n�_���������ꍇ���l���܂��B�b���ȒP�ɂ��邽�߂ɁA��C���̎��͂̑�C�̏�Ԃ́A�ߎ��I�ɓ��S�~��ɂȂ���̂Ƃ��܂��B
�@�܂��A�k�����ɂ����āA�n�\���猩���Ƃ��̑�C�̉^�����l���܂��i�}�Q�j�B��C�������݂���ꍇ�A��C�͈��͌��z�ɉ����ē����o���܂����A���̂Ƃ��A�^�������ɑ��ĉE�����ɋȂ���悤�ȃR���I���̗͂��������߁A��C�̗���͉E�ɋȂ���Ȃ����C���ɐڋ߂��邱�ƂɂȂ�A���ʓI�ɁA�������̉Q�������܂��B���ꂪ�A�ӂ��̐����̎d���ł��B
�@�������ۂ��A�F�����猩��Ƃǂ��Ȃ�ł��傤���i�}�R�j�H ��C���̖k����C�������ꍞ�ޏꍇ�A���ܓx�ł͒n���̎���̉�]���x����ܓx�����x�����߁A�C���͒�C���̓��������x��āA���ΓI�ɐ��̕��ɃJ�[�u���܂��i����́A�k�ɓ_�ɒu���ꂽ�t�[�R�[�̐U��q�̏ꍇ�Ɠ����ł��j�B���l�ɁA��C���̓삩�痬�ꍞ�ދC���́A���Ƃ��Ǝ����̕����������ɂ�葬�����x�œ����Ă������߁A��C���ɑ��ē��̕��ɂ���Ă����܂��B�������āA�n�\���猩���Ƃ��Ɠ����悤�ɁA�^�������ɑ��ĉE�����ɋȂ����Ă����A�ŏI�I�ɍ������̉Q���`������̂ł��B
�@�씼���ł̑�C�̗���́A��ɏ�猩���Ƃ��̉�]�̌������t�ɂȂ�̂ŁA���E���t�ɂȂ��čŏI�I�ɉE�����̉Q�ƂȂ�܂��B
�@�������āA�k�����̑䕗�͍������A�씼���̑䕗�͉E�����ɂȂ�̂ł��B
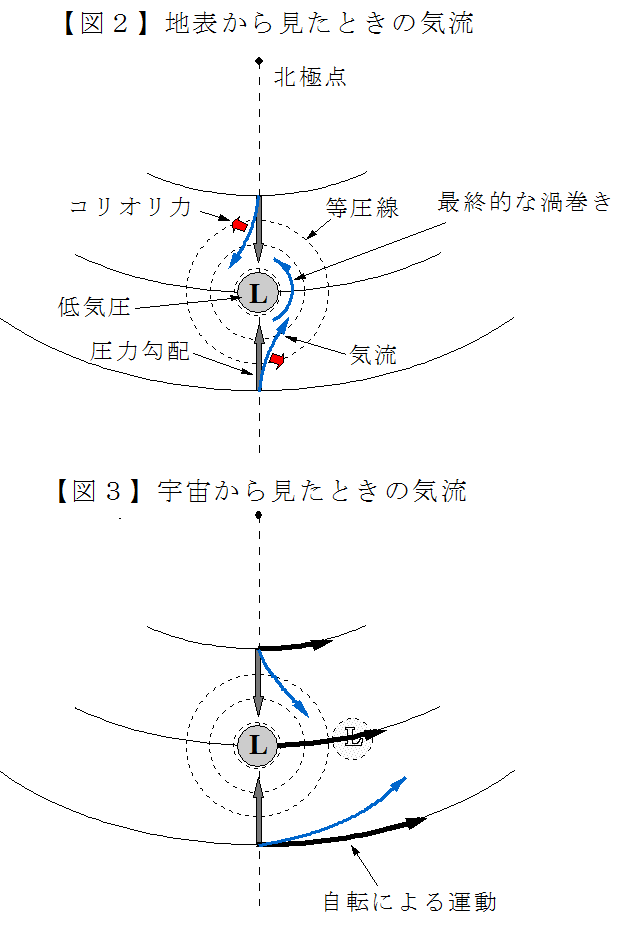
�y�Q�l�����z���������イ�@�Q�O�O�Q Vol.18 No.10�@�䕗�͂Ȃ��������H�@���s���Ȋw�ف@�֓��g�F
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�ʓI�Ȃ��Ƃ������A�������Ђ����_�i�����_�j�ɑ��Ĕᔻ�I�ȗ��R�Ƃ��āA�������̋�̓I�ȍ����������邱�Ƃ��ł��܂��B
- �����E�ϑ��œ�����f�[�^�ɂ���Ďx������Ă��Ȃ� �F ���Ђ����_�Ƃ́A�Ђ����_�ɒ��Ώ̐����ۂ������_�ł��B�Ђ����_�́A���Ƃ��ƒ��Ԏq���Ђ��̂悤�ȐU����������Ƃ������G�l���M�[�����̃f�[�^�Ɋ�Â��Ē�Ă��ꂽ���̂ł����A���Ԏq���N�H�[�N���_�Ɋ�Â��������q�ł��邱�Ƃ��m���ɂȂ�ƁA�N�H�[�N�Ȃǂ̑f���q���Ђ��ƌ��Ȃ����_�Ƃ��čĒ�Ă���܂����B�������A�f���q���Ђ��ł��邱�Ƃ����������f�[�^�͂Ȃ��A�܂��A�Q�[�W�{�\����d�͎q���Ђ��́i�x�N�g���Ȃ����e���\���I�ȁj��N��Ԃł���Ƃ����咣���A�����̒i�K�ɗ��܂��Ă��܂��B���Ώ̐��Ɋւ��Ă��A���Ώ̐��p�[�g�i�[����������Ă��Ȃ��̂ŁA�����I�����͉�������܂���B
- ���_�Ƃ��Ė������ł��� �F �f���q���Ђ��ƌ��Ȃ���̂́A�����܂Őۓ��_�ߎ������藧�͈͂ł̕`���ł��B�Ђ��`���ɗ���Ȃ������ȗ��_�ɂ���ɂ́A���ݍ�p���Ǐ��I�ł͂Ȃ��P�����I�Ȋg��������u�Ђ��̏�̗��_�v���\�z���Ȃ���Ȃ�܂���B�������A�����������_�͂��܂��\�z����Ă��炸�AM���_�Ɋ�Â��莮�����A�\�z�̒i�K�ɗ��܂��Ă��܂��B���Ђ����_�����_�����w�҂̒��ڂ��W�߂��̂�1985�N������ł����A���ꂩ��30�N�ȏ�o�̂ɂ��܂��Ɋ�b���_���ł��Ă��Ȃ����Ƃ́A���_�̐��������^���̂ɏ[���ȗ��R�ł͂Ȃ��ł��傤���B
- ���w�I�Ȏ�@�ɋ^�`������ �F ���Ђ����_�̌v�Z�ɂ́A�c�F�[�^���������ƌĂ���@���g���܂��B���̎�@�́A�ʏ�̌v�Z�ł͔��U���鋉���̘a��L���Ȓl�Ƃ��ċ��߂���̂ł����A��͐ڑ��ł͂Ȃ��A�����܂ŗL���ɂ��邽�߂̃e�N�j�b�N�Ȃ̂ŁA�ǂ̒��x�̐M���������邩�͂����肵�܂���B
- �ؖ�����Ă��Ȃ��\�z���������� �F�ʎq��̗L������AdS/CFT�Ή��Ȃǂ́A�����ȏؖ��̂Ȃ��\�z�ɂ����܂���B�ɂ�������炸�A���Ђ����_�́g����h�Ƃ��Č��`����邱�ƂɁA�������킵���������Ă��܂��܂��B
�@�����������R�ɉ����āA�������Ђ����_���D���ɂȂ�Ȃ��ő�̗��R�́A�u�Ȋw�͑Q�i�I�ɐi������v�Ƃ����Ȋw�j�̏펯�ɔ����邩��ł��B�f�p�ȂЂ����_�̓A�m�}���[�ƌĂ�闝�_�I�Ȗ��������邽�߁A�A�m�}���[���Ȃ��悤�Ȍ`�����̗p����K�v������܂��B���̌��ʁA���Ђ����_�́A���������̗v������`�����قڈ�ӓI�Ɋm�肵�Ă��܂��g�]�T�̂Ȃ��h���_�ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A�ߑ�ȍ~�̉Ȋw�̐i�����ڂ݂�ƁA�����Ȃ芮�S�ȗ��_�����ꂽ�P�[�X�͂قƂ�ǂ���܂���B���_�����������܂łɁA�����̉Ȋw�҂��f�[�^�Ɋ�Â��Ă��܂��܂ȁi��Ɍ����܂ނ��Ƃ��킩��j�������Ă��A���ꂼ��̉����́u�����Ƃ����v���J��Ԃ����ƂŁA�����������`�ɋ߂Â��Ă������̂ł��B�T�^�I�ȗႪ�A�n�h�����͌^�ł��B�Q���}���̃N�H�[�N�����A�t�@�C���}���̃p�[�g���͌^�A�n�����암�̃J���[���R�x���_�AMIT�̃o�b�O�͌^�A�암�̂Ђ����_�ȂǁA���܂��܂ȃA�C�f�A�����X��Ă���A�����𐠂荇�킹�邱�Ƃ��K�v�ł����B���_�̌`���ɗ]�T���Ȃ��A���̉����Ƃ̐��荇�킹������Ȓ��Ђ����_�́A���������Q�i�I�Ȑi�������狑��ł��܂��B
�@����Ɍ����A���R�E�������Ȑ��w�ɏ]���Ă���i�Ⴆ�A���j�^�����������I�ɐ��藧�j�Ƃ������z�ɁA�ǂ����Ă�����߂܂���B�ʎq�_�����v�I�ȗ\�������s���Ă��Ȃ��ȏ�A�������ۂ������ȕ������ɏ]�����Ƃ��m�F���ꂽ�P�[�X�͂Ȃ��A�����܂ŁA�����̎��R�x��������铝�v�I�Ȍ��ۂ̖@�����𖾂炩�ɂ��������ł��B���̒i�K�ŁA���w�I�Ɍ����Ȍ`��������b���_�������o���̂́A�l�ނɂ͑�������Ƃ����C�����܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@
�u�������Ђ����_�������Ȗ�v��ǂ݁A�ے�I�Ɏ~�߂Ă邱�Ƃ�������܂����B���A�Ђ����_�ƌ��т����z���O���t�B�b�N�F���_�Ƃ������̂�����܂��B����ɂ��Ă͂ǂ����l���ł��傤���H�y���㕨���z

�@�z���O���t�B�b�N�F���_�́A�Q�̃A�C�f�A�����Ƃɂ��Ă��܂��B
- �������̈قȂ�Q�̕����w���_�����S�ɓ����ɂȂ�P�[�X������
- �����̉F�����L�q���闝�_���O���̃P�[�X�ɊY�����A����ꂪ�R������ԂƎv���Ă��鐢�E�́A�{���́i�u�{���́v�Ƃ����������͑Ó��ł͂Ȃ���������܂��j�Q�����Ȃ̂�������Ȃ�
���Ђ����_�̌����҂ɂ́A���̂Q�����ɔF�߂�l�������悤�ł����A���́A��P�̃A�C�f�A�Ɋւ��Ă͗e�F������̂́A��Q�̃A�C�f�A�͐M���Ă��܂���B
�@�������̈قȂ镨���w���_�������ł���P�[�X�Ƃ��čŏ��Ɍ��������ꂽ�̂��A�T�����̔��h�E�W�b�^�[�iAdS�j����ƂS�����̋��`�ꗝ�_�iCFT�j�������ł���Ǝ咣����AdS/CFT�Ή��ŁA���Ђ����_�̌�����ʂ��āA1997�N�Ƀ}���_�Z�i�ɂ���Ĕ�������܂����B�������A���Ђ����_�̘g���Ŕ������ꂽ�ƌ����Ă��A�K���������Ђ����_�������I�ł��邱�Ƃ��Ӗ����܂���B���������Ή��W�́A�����܂Ő��w�I�ȓ������i�o�ΐ��ƌĂ��^�C�v�̊W�j�ł���A���Ђ����_�́A�Ή��W�����߂̐��w�I�ȃ��f���Ƃ��Ďg��ꂽ����������ł��B���ہAAdS/CFT�Ή�����ʉ��������܂��܂ȑΉ��W������������Ă��܂��i�������A�������́A�K�����������ɏؖ����ꂽ��ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�ߎ��I�ȊW��������܂���j�B���̊W���g���ƁA�ۓ��_�ߎ������藧�����v�Z������ȏ�̗��_���A���ȒP�Ɍv�Z�ł���d�͗��_�ɕϊ����邱�Ƃ��ł���̂ŁA�ߎ��������߂邽�߂̐��w�I�e�N�j�b�N�Ƃ��Ė��ɗ����܂��B���̂��߁A�����I�ȕ����n�������������_�̕���ł��A����Ɍ������i�߂��Ă��܂��B
�@���ꂾ���Ȃ�A�V���Ȍv�Z��@���J�����ꂽ�ɂ����܂���B�������A���Ђ����_�̌����҂́A����Ɉ���i�߂āA�������E�ł������ȑΉ��W�����藧���Ă���ƍl���A���̃A�C�f�A�Ɋ�Â��āA�F���ɑ���V���Ȍ�������悤�Ƃ��Ă��܂��B���ꂪ�A�z���O���t�B�b�N�F���_�ł��B�����Ƃ��A���Ђ����_�̑��̎咣�Ɠ��l�ɁA�z���O���t�B�b�N�F���_�̐�������������̓I�ȃf�[�^�͂Ȃ��A�킸���ɁA�u���b�N�z�[���̃G���g���s�[���n���ʂ̕\�ʐςɔ�Ⴗ�邱�ƂƊ֘A�Â����邾���ł��B�u���b�N�z�[���E�G���g���s�[���\�ʐςɔ�Ⴗ�闝�R�́A�z���O���t�B�b�N�F���_���g��Ȃ��Ă������\�Ȃ̂ŁA�z���O���t�B�b�N�F���_�́A���̒i�K�ł́A�����炵�������̂Ȃ��咣�ƌ��킴��܂���i�������A���������_�ł���\���͔ے�ł��܂��j�B
�@���Ƃ����s�̕����w���_���������̈قȂ�ʂ̗��_�Ɗ��S�ɓ������Ƃ��Ă��A�����ɉF���ς�ύX���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������܂��B�Ⴆ�A���_�n�̃j���[�g���͊w�́A�ʏ�́A�R������Ԃ̓����𗱎q���^�����Ă���Ƃ����`���Ō���܂����A�n�~���g���`����p����ƁA��Ԃ̘g�g�݂͑S���قȂ������̂ɂȂ�܂��B��ʓI�ȃj���[�g���͊w�ł́AN�̎��_�̉^����Ԃ́A3����������N�̈ʒu���W�ŋL�q����܂����A�n�~���g���`���̏ꍇ�A�e���_�̈ʒu�Ɖ^���ʂ̐��������W���Ƃ���6N�����̋�Ԃ�z�肵�A���鎞���ɂ�����S�Ă̎��_�̉^����Ԃ́A���̋�ԓ����̂P�_�ŕ\����܂��B����ł́A���E��6N������Ԃƌ��Ȃ���̂��Ƃ����Ɓc���ۂɂ́A�u���̐��E�͎��_�n�̃j���[�g���͊w�Ō����ɋL�q�ł���v�Ƃ����O���藧���Ȃ��̂ŁA�u�R������Ԃ͌��z�ł���A�{���̐��E��6N������Ԃ��v�Ƃ����咣�ɂ͖���������܂��i�������A��̗ʎq�_�ɂȂ�ƁA��������Ԃ̎��ݐ������Ȃ�M�ߐ���ттĂ��܂��j�B���Ђ����_�̌����҂́A�u���̐��E�����Ђ����_�Ō����ɋL�q�ł���v�Ƃ����O��̉��ł��܂��܂ȋc�_��W�J���Ă��܂����A���̑O����^���ƁA�ނ�̎咣�̑������������Ɍ����Ă��܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�A�C���V���^�C���̈�ʑ��Θ_�ɂ��A�d�͏�Ƃ́A�G�l���M�[�����ݏo������̂䂪�݂̂��Ƃł��B��ԓ����ɓV�̂����݂���ꍇ�A���̎��ʃG�l���M�[�ɂ�鎞��̂䂪�݂́A�A�C���V���^�C���������ɏ]���Ăǂ��܂ł��g�����Ă��܂��B�V�̂��痣���ɂ�āA�䂪�݂������炷�����I�ȉe���̓j���[�g���̏d�͗��_�ɑQ�߂��܂����A�t�ɁA�V�̂ɋ߂Â��ƁA�j���[�g�����_����̂��ꂪ�傫���Ȃ�܂��B���ɁA�u���b�N�z�[���ł́A�߂Â��ɂ�Ď���̂䂪�݂��ɒ[�ɑ傫���Ȃ�A����Ȗʂ��������ł́A���ł���������ɂ����i�߂Ȃ��悤�Ȏ���\���ɂȂ�܂��B���̕Ȗʂ��u���ۂ̒n���ʁv�ƌĂ����̂ł��B�n���ʂ̓����Ɉ��ݍ��܂ꂽ��������������o����Ă��A���̌��͓������ɂ����`���Ȃ��̂ŁA�n���ʂ̊O�ɂ͏o���܂���B
�@���̂悤�ɁA�u���b�N�z�[������͌�������o����܂���B�������A����̂䂪�ݎ��̂́A���S���疳���̔ޕ��܂ŘA���I�Ɋg�����Ă���̂ŁA�u���b�N�z�[���̏d�͂́A�O���ł��ϑ�����܂��B�u���b�N�z�[�����^������ƁA���͂̂䂪�݂́A�u���b�N�z�[���Ɉ���������悤�ɕϓ����܂��B�Q�̃u���b�N�z�[�����A���n���`���A�Ƃ��ɏd�S�̎������]���Ă���ꍇ�́A�䂪�݂������I�ɕϓ����邽�߁A�U������g�Ƃ��Ċg�����Ă����܂��B�d�͔g����o����ƃG�l���M�[�������邽�߁A�Q�̃u���b�N�z�[���͏������ڋ߂��A����ɔ����Č��]�����͒Z���Ȃ�̂ŁA�d�͔g�̐U�����͑傫���Ȃ��Ă����܂��B���F��⒆���q�̘A���n�ł́A�Q�̓V�̂��Փ˂���ƌ������������A���̍ۂ̎��ʈړ��ɂ��]�g�������܂����A�u���b�N�z�[���ł́A�݂��̒n���ʂ��Z�����ĂP�ɂȂ�A���̊O�����猩��Ǝ��ʂ̈ړ����Ȃ��Ȃ邽�߁A�d�͔g�͓ˑR�X�g�b�v���܂��B
�@2015�N�ɍŏ��Ɋϑ����ꂽ�d�͔g�́A�Z���ԂŐU�������}��������ɁA�ˑR�A�g�����ł���Ƃ����p�^�[�������������Ƃ���A�u���b�N�z�[�����m�̍��̂Ɗm�F����܂����B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�V�˂ƌĂ��l�̑����́A�����˔\�̎�����ł���A����̕���ȊO�ł́A���ȉ��̔\�͂��������Ȃ��P�[�X�����Ȃ�����܂���B���_�����w�̕���Ō����A�f�B���b�N��p�E���́A���w�I�ȗ��_���\�z����ۂɌ��O��̍˔\�����܂������A�l�t�������Ɋւ��ẮA�R�~���j�P�[�V������Q�ƌ��Ȃ���Ă��d���Ȃ����x�ł����B���������V�˂����́A��啪��ł͈��|�I�ȋƐт��グ�Ă�����̂́A�u�l�ގj��̓V�ˁv�ƌĂԂɂ͑��������Ȃ��悤�Ɋ������܂��B
�@���������]������̂́A���E�S�̂��������铧�O�����r�W�����������A�����������ۂ𑍍��I�ɔc��������ŁA���̃r�W�������x���闝�_���\�z���邱�Ƃ̂ł���l�ł��B���G�Ȏ��ۂ̔w��ɂ���A�����Ŕj����ɂ́A�����ʂ̊w����Ȃ��C�������u���\�̓V�ˁv�^�C�v�ł��邱�Ƃ��K�v�ł��B�������A���낢��ȕ���ɏ������˔\�����鑽�|���˂̐l�ł͂Ȃ��A��т������E�ς̉��ɂ�����m�𑍍����悤�Ƃ���u�m�̋��l�v�łȂ���Ȃ�܂���B����ȓV�˂ȂǑ��݂��Ȃ��ƌ����Ă��܂�����܂łł����A���z�̋߂��ɂ���l�Ƃ��āA�A���X�g�e���X�A���I�i���h�E�_�E���B���`�A�����̖������������Ǝv���܂��B���ɁA�����́A���{�ɂ���قǂ̎v�z�Ƃ������̂��Ƌ��Q����قǁA���E��[�����߁A���̖{�����ɂ߂悤�Ƃ����V�˂ł��B�咘�w���@�ᑠ�x�́A�����v�z�Ɋւ���m����O��Ƃ�������Ȃ��̂ŁA�e�Ղɉ��߂ł�����̂ł͂���܂��A����ɂ��ʗp����m�̕�ɂƌ����ėǂ��ł��傤�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�u���b�N�z�[���ɂ́A�傫�������āA���z���ʂ̐��{���琔�\�{���x�Ƃ����P���T�C�Y�̂��̂ƁA���z���ʂ̐��\���{�ȏ�Ƃ���������u���b�N�z�[���̂Q��ނ�����܂��B�O�҂́A�县�ʍP�����j�Z���R�����g���ʂ�������ɏd�͕�����N�����Č`������邱�Ƃ��킩���Ă��܂����A�����̋�͒��S�Ɍ������҂̃^�C�v���ǂ̂悤�ɂ��Ēa���������́A�悭�킩���Ă��܂���B���̖�肪���Ȃ̂́A(1)�r�b�O�o������10���N�ȉ��Ƃ�����r�I���������ɁA������u���b�N�z�[���̑��݂����؋������邱�ƁA(2)���z���ʂ̐��炩�琔���{�Ƃ������ԃT�C�Y�̃u���b�N�z�[�����A�����킸�������������Ă��Ȃ����Ɓ|�|�Ƃ������ϑ��f�[�^�̐��������邽�߂ł��B���̐��������邽�߁A�K�X�̋z����u���b�N�z�[�����m�̍��̂ɂ���ăR���X�^���g�Ɏ��ʂ��������A������u���b�N�z�[���ɐ��������ƊȒP�ɐ������邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă��܂��B
�@�T�C�G���X�y�d�q�n�ł́A���������ϑ��f�[�^�̐����Ɋւ���������������A�u���b�N�z�[�����ǂ̂悤�ɐ����������Ƃ����_������_���Ă��܂��B�O���ł́A�u���b�N�z�[���̍��̂ɂ���Đ������d�͔g��2015�N�Ɋϑ����ꂽ���Ƃ����ƂɁA�u���b�N�z�[�����m�����X�ɂԂ����Ď��ʂ��������Ă������\�����Љ�Ă��܂����B�������A���̃��J�j�Y�������ŁA�P���T�C�Y����o�����Ē�����u���b�N�z�[���ɂ܂Ő����ł��邩�ǂ����́A���炩�ł͂���܂���B
�@�ԑg�̌㔼�ŏЉ�ꂽ�K�X�z���̃��J�j�Y���ɂ��ẮA�b��[�܂肷���āA���Ȃ�킩��ɂ��������Ǝv���܂��B
�@�u���b�N�z�[���ƌ����Ă��A��Ɏ��͂̃K�X��V�̂����ݍ���ł����ł͂���܂���B�u����ȏd�͂Ō�����O�ɏo���Ȃ��v�Ƃ����C���[�W�Ō���܂����A���������C���[�W�����藧�͎̂��ۂ̒n���ʂ̋ߖT�Ɍ����Ă���A�[���ɉ�������A�ߎ��I�Ƀj���[�g���̏d�͗��_�����藧�V�̂ƌ��Ȃ��܂��B���z�̂P00���{�̎��ʂ����u���b�N�z�[���ł����Ă��A�V�����@���c�V���g���a��300���L�����[�g�����x�ŁA���z���a�i�����̑傫���j�̂S�{���X�A�����̌��]���a��20���̂P��������܂���B����قǃR���p�N�g�Ȃ̂ŁA���ۂ̒n���ʂɋ߂Â��̂́A���\�����ւ�ł��B��������u���b�N�z�[���ɋ߂Â��Ǘ��V�̂Ȃ�A�����́A�P�v���[�̖@���ɏ]���đȉ~�O����o�Ȑ��O����`���čĂщ�������A��O�I�Ɏ��ۂ̒n���ʂɋ߂Â������̂��������ݍ��܂�܂��B�K�X�̏ꍇ�A���x����������ƁA�c�����悤�Ƃ���X�����������S���ɂȂ��Ȃ��W�܂��Ă��Ȃ��̂ŁA��͂���ݍ��܂��ʂ͌����܂��B
�@����ł́A�u���b�N�z�[���Ɉ��ݍ��܂��K�X�͂ǂ̂悤�ɉ^������̂��Ƃ����ƁA���ꂪ���Ȃ������ł��B���n�f���n�~�Ղ̂悤�Ƀj���[�g���̗��_�����Ōv�Z���ł���ꍇ�ł����Ă��A���C�ɂ���ĉ�]�̃G�l���M�[���������ʂƁA�M�^���ɂ���Ċg�U���悤�Ƃ�����ʂ����邽�߁A�����ȒP�ɓ��͏o�܂���B���z�n�̏ꍇ�A���ʂł͑��z���S�̂�99.8�p�[�Z���g�ȏ���߂�̂ɑ��āA�p�^���ʂɂȂ�ƁA�ؐ��̌��]�p�^���ʂ��S�̂̂R���̂Q�قǂ��߁A���z�̎��]�p�^���ʂ͂Q�`�R�p�[�Z���g��������܂���B���z�̎��]�p�^���ʂ��������̂́A���z���`�����ꂽ��Ō������ꂽ���ʂ�����܂����A���z�ɕ����i��ɃK�X�������f��������j���W�܂�ۂɁA���̕����Ƃ̑��ݍ�p�ʼn�]�G�l���M�[�����������̂��������S�ɗ��������炾�Ɛ�������܂��B�������A���̉ߒ����R���s���[�^�E�V�~�����[�V�����ōČ�����̂́A�e�Ղł͂���܂���B
�@�u���b�N�z�[���ɃK�X���������ޏꍇ�̋c�_�́A���n���z�n�~�Ղɔ�ׂĊi�i�ɓ���Ȃ�܂��B��������u���b�N�z�[���Ɍ������ė������ރK�X�́A���ۂ̒n���ʕt�߂ł́A�����߂��܂ʼn�������Ă��܂��i���ۂ̒n���ʂ���̒E�o���x�������ɓ��������Ƃ��v���o���Ă��������j�B���̂��߁A�K�X���\�����錴�q���������Ԃ��肠���ăC�I��������A�v���Y�}��ԂɂȂ�܂��B�v���Y�}���u���b�N�z�[���̎��͂���]����ƁA�Q�d���ƂȂ��č~���~�Ղɐ��������̎�������܂����A���̎�������I�ł͂Ȃ��A�̂������܂��悤�ɓ����Ă��܂��B���������āA�_�C�i�~�b�N�ɕϓ����鎥������������߂��܂ʼn������ꂽ���Θ_�I�ȉדd���q���^������Ƃ����A����߂Ă�₱��������`�������������Ȃ���A�K�X�̐U�����͂킩��܂���B�������A�o�b�N�O���E���h�ƂȂ鎞��́A�u���b�N�z�[���̏d�͂ł䂪��ł��܂����A�~���~�Ղ�����o����鋭�͂�X���̉e��������܂��B�������茾���ƁA�v���Y�}�������K�X�͉Q�����悤�Ƀu���b�N�z�[���ɐڋ߂��A���̂������Ȃ�̂��̂��A���������̎��͐��ɉ����ău���b�N�z�[�����琁���o���悤�ɉ^������͂��ł��B�������A��̓I�ȃV�~�����[�V�����́A���낢��Ȑ�����t�����`�ł����s���Ă��炸�A�����A�[���Ȓm���͎����Ă��܂���B
�@�T�C�G���X�y�d�q�n�ŏЉ�ꂽ�̂́A�R���s���[�^�E�V�~�����[�V�����ł͂Ȃ��A���V�������̏Ռ��g�ɂ���ăK�X����������A���̉e���Ńu���b�N�z�[���ɗ������ރK�X�������邱�Ƃ��������f���v�Z�̂悤�ł��i���e�͂悭�킩��܂���j�B�u���b�N�z�[���Ɉ��ݍ��܂��K�X���P�N�Ԃő��z���ʂ�0.1�{���x�ɂȂ�Ƃ������Z���Љ��Ă��܂������A���I�ȃK�X���Ƃ���Ɛ��l���傫������̂ŁA�ǂ̂悤�ȏ������ł̌v�Z�Ȃ̂��A�����������ׂĂ݂�K�v������܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�^�̃}�N�X�E�F���d���C�w�͈̔͂ł́A�O�����ꂪ���̐i�s�ɉe�����y�ڂ����Ƃ͂���܂���B����́A�u���`���v�ƌĂ�鐫���ɗR�����܂��B
�@�����܂ޓd���C���ۂ́A�}�N�X�E�F���������ɂ���ċL�q����܂����A���̕������́A�d��⎥��Ɋւ��ĂP���������ɂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�d��
E�̔��U�́A�d��ρ���g����
�@�@
divE=ρ�@�i�^��̗U�d����1�ƒu����L���P�ʌn�̏ꍇ�j
�ƕ\����܂��B���̂R�̕����������l�ł��B���̂��߁A�d��
E���A�d�ׂ����݂��Ȃ��Ƃ��̓d��
E1�ƁA�d��ρ�����d��
E0�ɕ����āA���ꂼ�ꂪ�A
�@�@
divE1=0
�@�@
divE0=ρ
�Ƃ����������i����сA���̃}�N�X�E�F���������j�������̂Ƃ��Ĉ����܂��B���̂悤�ɁA�d�ׂ�d�������݂���Ƃ��̃}�N�X�E�F���������̉��i��̗�ł�
E0�j�ɑ��āA�d�ׁE�d�����Ȃ��Ƃ��̉��i��̗�ł�
E1�j�������Ă��A���́i�d�ׁE�d�������݂���j�}�N�X�E�F�������������Ƃ����̂��A�d���C���ۂ̓����ł��B
�@�O���̓d�ׁE�d���i���ˌ��̐i�s��W���Ȃ��ʒu�ɂ�����̂Ƃ���j�ɂ���ĊO������
B0�������Ă���^��̈�Ɍ������˂��ꂽ�ꍇ�A���̓d����́A�O���d�ׂ̑��݂��Ȃ��i���������āA�O����������݂��Ȃ��j�}�N�X�E�F�������������Ă��܂��B���̂��߁A���ˌ��́A����̉e�������ɒ��i���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�������A�������˂���̂��^��ł͂Ȃ��U�d�̂̂悤�Ȕ}���̏ꍇ�́A�O������ɂ���ėU�d���E���������ϓ�����̂ŁA���̐i�s�͉e�����܂��i���C���w���ʁj�B
�@�܂��A�}�N�X�E�F���d���C�w�́A�����܂ŋߎ��I�ȗ��_�ł����āA�����ɐ�������ł͂���܂���B�d���C�Ǝア���ݍ�p�ꂷ�郏�C���o�[�O���T�������_�ɂ��A�d����́A�x�[�^����Ȃǂ������N�����ア�j�͂̏�ƈ�̉����Ă���A�{���A����`�ȑ��ݍ�p���s�����̂ł��B�ア���ݍ�p�́A���̖��̒ʂ���Ɏキ�A�ʏ�̓d���C���ۂɂ͂قƂ�lje����^���Ȃ����߁A�d���C�������o���Đ��`�ȕ������ɏ]���Ƌߎ����Ă��邾���ł���A����߂Đ����ȑ�����s���A����`�Ȍ��ʂ�������͂��ł��B�܂��A��ʑ��Θ_�ɂ��A����̃G�l���M�[�͎�����ق�̂킸���ɘc�߂�̂ŁA���̌��ʂ�ʂ��Ă����̐i�ݕ��ɉe���������܂��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�F���D���ōs��ꂽ�����Ƃ́A�����炭�A���́gDancing Droplets�h�̉f�����Ǝv���܂��B
http://www.physicscentral.com/explore/sots/episode1.cfm
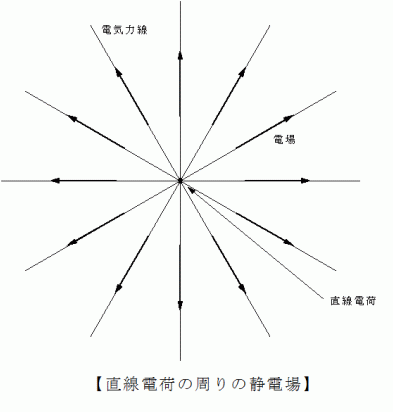
�@���̎����ł́A�i�C�������̕҂ݖ_�C�ŕ��ɑѓd�����ĐÓd������o���A���ɑѓd�������H�����͂ɔ���ē��������Ă��܂��i�ڂ����́A��L�y�[�W�̉����ǂ�ł��������j�B
�@���̉^�����̂��̂𗝘_�I�ɉ�͂���͓̂���̂ŁA�[�̂���҂ݖ_�̑���ɖ����ɒ����������l���A�����ɓd�q����l�ɕ��z���Ă���Ɖ��肵�܂��B���̉���̉��ł́A�d�C�͐��͒������琂���ɐL�т�̂ŁA�d��̋����i���d�C�͐��̖��x�j�͒�������̋����ɔ���Ⴕ�܂��i�}�Q�Ɓj�B���̐Ód��̎���ɁA�i���H�ł͗U�d���ɂ��N���Ĉ��������ɂȂ�̂Łj�_�d�ׂ��^������ꍇ���l���܂��傤�B���ۂɂ́A�����d�ׂɕ��s�ȑ��x����������܂����A�ȒP�̂��߁A�����d�ׂɐ����Ȗʓ��ł̉^���Ɍ��肵�܂��B���S�͂ɂ��^���ł́A���S�̎���Ɋp�^���ʂ��ۑ������i���ʐϑ��x�����ɂȂ�j�̂ŁA�_�d�ׂ́A���S�̎�����Ȃ���A���S�ɋ߂Â��Ƒ����A��������Ƃ�����蓮�����ƂɂȂ�܂��B

�@�_�d�ׂ̋O���́A�^����������ϕ����邱�ƂŁA���߂��܂��B�d��̋��������S����̋����ɔ���Ⴗ��̂ŁA�^���������̌`�͔�r�I�ȒP�ɂȂ�܂����A�������͓I�ɐϕ����ċO�������߂邱�Ƃ͂ł��܂���B���S�͂���p����ꍇ�A���̂́A���Ȃ���߂Â����艓����������Ǝ����I�ȉ^�������܂����A�����I�ł͂����Ă��O���͕Ȑ��ɂȂ炸�A�����I�ȉ�͊��ł��\����Ȃ��̂ŁA�O�������߂�ɂ́A���l�ϕ����s���K�v������܂��B�����ł́A�G�l���M�[�Ɗp�^���ʂ�����l�̂Ƃ��̋O�����A�}�����Ă����܂��i���l�ϕ��́A�����x�v�Z�T�C�g�ikeisan.casio.jp�j�𗘗p���čs���܂������A����ȊO�̕����́A���Ȃ��G�c�Ɍv�Z���������Ȃ̂ŁA���܂�M�p���Ȃ��ł��������j�B�͂������̂Q��ɔ���Ⴗ��P�v���[�^���ł͑ȉ~�O���ɂȂ�܂����A�P��ɔ���Ⴗ��ꍇ�́A�Ԃт�̂悤�ȕ��G�ȋO���ɂȂ�܂��B����ł́A���������O����`���^�����A�点��^���ƌĂ̂ł��傤�B
�@�҂ݖ_�̏ꍇ�́A�[�̕����œd�C�͐��̌������ς�邽�߂ɁA�[�ɋ߂Â������H�������߂����悤�ȓ����������܂��B���̂ق��A��C��R�␅�H�̗U�d���ɂȂǂ����邽�߁A�����̉^���͂��Ȃ蕡�G�ŁA�����ŕ\�����Ƃ͕s�\�ł��B
�@�Ȃ��A���̃P�[�X�ł͎����̂��߂ɐÓd���p�ӂ��܂������A�F����Ԃɂ͒��I�ȐÓd��͂قƂ�ǂ���܂���B���z���琁���o�����z���́A�d�q��z�q�Ȃljדd���q����\������Ă���A�d�ꂪ����Ƃ����ɂ���炪�����ēd�ׂ𒆘a����̂ŁA����̕ω��Ȃǂɔ����Đ����铮�I�Ȃ��̈ȊO�́A�d�ꂪ�����ł��Ȃ�����ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

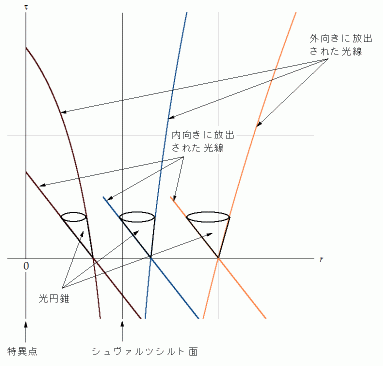
�@�u���b�N�z�[���́A�펯�ɔ�����V�̂Ǝv���Ă��܂����A���̎��͂Ō����ǂ̂悤�ɓ`��邩�𗝉�����ƁA�ϑ��҂��ǂ�Ȍ��i�����邩�A���ϓI�ɑ����邱�Ƃ��ł��܂��B��ԍ��W���i�P�̎������ȗ������j�Q�����ŁA���ԍ��W��c�{���ċ�ԍ��W�Ɠ����P�ʂŕ\�����Ƃɂ���ƁA�d�͂��Ȃ��ꍇ�A�_����������o�������́A�����_�Ƃ��Ő��̌X����45���̉~���ʂ�i�݂܂��B���̉~�������~���ł����A�u���b�N�z�[���̎��͂ł́A�����d�͂̂��߂ɁA���̉~�����}�P�̂悤�ɂЂ��Ⴐ���`�ɂȂ邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�V�����@���c�V���g�ʂ̓����ł́A���~���̑��ʂ��S�Ē��S�������悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA���Ƃ��O���Ɍ����Č��˂��Ă��A���S���痣��邱�Ƃ͂ł����ɓ��ٓ_�ɗ�������ł����܂��B�܂��A�V�����@���c�V���g�ʂ̂����O���ŊO�����ɕ��o���ꂽ���́A�ʂ���Ȃ��Ȃ�����邱�Ƃ��ł����A���Ԃ��|���āi��������Ac���x�����x�Łj�i�݂܂��B
�@�O���̊ϑ��҂��u���b�N�z�[���Ɏ��R�������Ă������̂�����ꍇ�A�V�����@���c�V���g�ʂ�����u�ԂɎp�������̂ł͂Ȃ��A�ʂɋ߂Â��ɂ�ĕ��̂���̌����Ȃ��Ȃ�����Ă��Ȃ��Ȃ邽�߂ɁA�������Ɍ��ʂ��������ď����Ă����܂��i����ɁA�X�y�N�g�����ω�����̂ŁA�F�������ς��܂��j�B
�@�u���b�N�z�[���ɗ������ފϑ��҂��������邩���A���~�������Ƃɐ������邱�Ƃ��ł��܂��B���~���̌`�������悤�ɁA�V�����@���c�V���g�ʂ̊O����������ɂ͂ӂ��Ɍ����i�߂�̂ŁA���̖ʂ��z���Ă��A�w��Ɋg���鐯��́A���炭�̊ԁA���̂܂܌��������܂��B�������A���~�������S�����ɂЂ��Ⴐ�Ă���̂ŁA���Ƃ��������鑼�̕��̂��V�����@���c�V���g�ʂ̓����ɂ������Ƃ��Ă��A�O������ϑ��҂Ɍ������Ă���Ă�����̗ʂ͏��Ȃ��Ȃ�܂��B���ɁA���S�ɂ�����ٓ_�i���u���b�N�z�[���̖{�́H�j����͌��͑S�����Ȃ��̂ŁA�����Ɍ������ė�������l�ɂƂ��Ă��A���S���͊��S�Ȉł̒��ɉB��Ă��Č����Č����܂���B
�@���ɁA���Ԋu�ɏc����g�F���D�̑����������Ƀu���b�N�z�[���ɗ�������ł������Ƃ��܂��傤�B���̂Ƃ��A�u���b�N�z�[���ɋ߂��F���D�̕����傫�ȉ����x�ɂȂ邽�߁A����F���D�̃p�C���b�g���炷��ƁA�O���̑��������Ɉ���������Ă����܂��B�V�����@���c�V���g�ʂ��z����ƁA�F���D����O�����ɕ��o���ꂽ���́A���~�����������ɂЂ��Ⴐ�Ă���̂Łi�O�����ł͂Ȃ��j�������ɂ������Ɓic�ȉ��̑��x�Łj�i�ނ悤�ɂȂ�܂��B���̂Ƃ��A�㑱�̉F���D�́A���������S�ɗ�������ߒ��ŁA�O�̉F���D������ɔ��˂������ɏo��̂ŁA�O���̉F���D���V�����@���c�V���g�ʂ��z����ƁA���������Ȃ��Ȃ�킯�ł͂���܂��A���ʂ��}���Ɍ����Ă����̂ŁA�O�̉F���D�͂������ɔ��Â��Ȃ�p�������Ă����܂��B�O�������ł͂Ȃ��A�������������̌��ʂ������đS�̂ɈÂ��Ȃ�A�킸���ɁA�w�ォ��܂���������Ă�����������Ō�܂Ō��������܂��B���ꂪ�A�u�T�C�G���X���� �u���b�N�z�[��03 -�v�ŁA�u�F���̑S�Ă�����ɏW�܂��Ă����A�₪�ĂP�_�ɏW�܂��ď����Ă����v�Ɛ����������i�ł��B
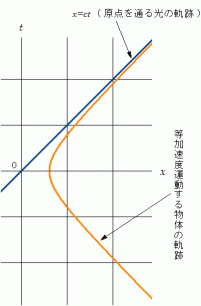
�@�u���b�N�z�[���ɓ��������Ă͂߂�ɂ́A�������x�^��������ϑ��҂��l����Ƃ킩��₷���ł��傤�B���̉����x�ʼn^������ϑ��҂́A�}�Q�̂悤�ɁA�������Ɍ����ɑQ�߂���O�Ղ�`���܂��B���̋O�Ղ́A�}�Q�Ō����� x=ct �̌����ƌ����Č����Ȃ��̂ŁA���̌�����荶�̗̈悩��o�����́A�ϑ��҂ɓ��B���܂���B���������āA x=ct ���A���̐悩��̏��͌����Ă���Ă��Ȃ��u���̒n�����v�ƂȂ�܂��B�������x�^������ϑ��҂��猩��ƁA�w��͏��̒n�����ɋN������ÈłƂȂ�A�S�V�Ɉ�l�ɕ��z���Ă������X�́A�O���ɏW���Ă��܂��B���������ɂ��A�������x�^������ϑ��҂́A���̏d�͉����x�����݂���d�͏�����̊ϑ��҂Ɠ����Ȃ͂��Ȃ̂ŁA�d�͏�����̊ϑ��҂��A�����悤�Ȍ��i�����܂��B���ꂪ�A�u���b�N�z�[�����s�w�ɂ����t�ϑ��҂�������i�Ǝ��Ă��邱�Ƃ́A�����ɂ킩��ł��傤�i�u���b�N�z�[���̒n���ʂ͋��`�����Ă���̂ŁA�S���������i�ɂ͂Ȃ�܂���j�B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@EM�h���C�u�Ȃ���̂ɂ��ẮA�Ǖ��ɂ��Ēm��Ȃ������̂ŁAWikipedia ���͂��߁A�������̃T�C�g�ŏ����W�߂܂����B����ɂ��ƁA�}�C�N���g�𖧕e����Ŕ��˂����邱�Ƃɂ���Đ��͂ݏo���Ƃ���鑕�u�ŁA�F����Ԃɂ����镬�o�܂�K�v�Ƃ��Ȃ����i���u�ɂȂ�Ɗ��҂���l������炵���̂ł����c�B
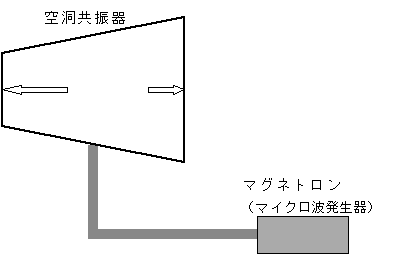
�@���Ƃ��Ƃ́A�C�M���X�̏���ƂɍݐЂ��Ă����Z�p�� Roger Shawyer����2001�N���ɍl�Ă����A�C�f�A�ŁA�}�̂悤�ɗ���ʂ̑傫�����قȂ���U��Ƀ}�C�N���g����͂���ƁA���ꂼ��̒�ʂɍ�p������ˈ����قȂ�͂����Ƃ������̂ł��B�ނ�2008�N�ɍs���������ł́A��ʂ̔��a��16cm��12cm�̋��U���850W�̃}�C�N���g����͂����Ƃ���A�傫����ʂ��珬������ʂɌ�������16�~���j���[�g���̐��͂��������������ł��B�����̓g���f���Ȋw�Ƃ��ĒN���C�ɂ��Ȃ��������̂́A2010�N�ɁA������ Juan Yang ���A�uEM�h���C�u���u��2.45GHz�̃}�C�N���g����͂���ƁA����d��80�`2500W�ɑ���70�`720�~���j���[�g���̐��͂��������v�Ƃ����������ʂ\����������A���ڂ���l�������Ă��܂����B
�@�����̎������u�͋�C���ɒu����Ă������߁A�u�}�C�N���g�ɂ���Ĕ��������M���Η��������N�����A�͂Ƃ��č�p�����v�Ƃ����^�����c��܂������A2014�N�ANASA�̌����`�[�� Eagleworks �ɑ�����Z�p�� Paul March �����^�Ŏ������s���A���͂���p���邱�Ƃ��m�F�������߁A��R�A���ړx���A�b�v���܂��B�������ANASA�`�[�����������������͂́A30�`50�}�C�N���j���[�g���Ƃ̂��ƂŁA�����̎������ʂƂ͑啝�ɈقȂ��Ă��邱�Ƃ��C�ɂȂ�܂��iNASA�`�[���̌��_���̓l�b�g��Ō�����Ȃ������̂ŁA���̐��l�͑������ł��j�B�u�Ȋw�̏펯�ɔ����闝�_���x�����錋�ʂ������̎����`�[���ɂ���ē���ꂽ���A���肳�ꂽ���l�͉������قȂ�v�Ƃ����́A���Ă̏퉷�j�Z�������̂Ƃ��Ɠ����ŁA�u���������Ȃ�Α唭�����ƍl���đ����̃`�[�������������݁A���炩�̋��R�Ń|�W�e�B�u�Ȍ��ʂ��Ƃ��낾�������\�����v�̂�������܂���B
�@�������ʂ������Ȃ��̂��Ƃ��Ă��A���̌����͑S���킩��܂���BM.E. McCulloch �����_�I�ɉ𖾂����Ƃ����b���������̂ŁA"Testing quantised inertia on the emdrive" �Ƒ肳�ꂽ�_���iarXiv:1604.03449v1 [physics.gen-ph] 6 Apr 2016�j��ǂ�ł݂܂������A�M���ł�����̂ł͂���܂���B���̘_���ł́AEM�h���C�u�ɂ����鐄�͂̋N�����E�����[���ʂ��Ƃ���Ă��܂��B�E�����[���ʂƂ́A�z�[�L���O���\�������u���b�N�z�[���̏����Ɗ֘A�������ʂŁA�����x�^��������ϑ��҂��猩��ƁA���������ɂ���ďd�͌��z�������A���̉e���Ŏ���ɂ����钷���̊���ω����ď�̊�U�������łȂ��Ȃ錋�ʁA�^�L�����x�̃G�l���M�[���z�����悤�Ɍ����邱�Ƃł��i�������G�ōς݂܂���j�B McCulloch �́A�ȑO�ɁA���̌��ʂ̉e���ʼn�������镨�̂̊������ʂ��ω�����Ƃ������_�\���Ă��܂������A����ɁA���q�̊������ω����邽�߂ɕ��ˈ��̍���������Ɛ������Ă��܂��B�������A��i�̎咣�Ɏ���ߒ��Ń��W�b�N�̔��i���U������̌��q��������E�����[���ʂɂ��Ă̐��������m�łȂ��j������A�ǂ��������Ȏ咣�Ƃ͎v���܂���B�������ʂ̕ω���\�����ɂ́A�����̕���ƕ��q�ɂ���߂ċ���Ȑ��i�P�́A�n�����猩�ĉF����Ԃ̖c�����x�������ɓ������Ȃ�n�_�܂ł̋����j���܂܂�Ă���A���҂��������������āAEM�h���C�u�Ƃ����l�ԃX�P�[���̑��u�ő���ł���悤�ɂȂ�Ƃ��������ɂ́A���Ȃ薳��������܂��B
�@�l�b�g��ɃA�b�v���ꂽEM�h���C�u�̎����f��������ƁA�}�O�l�g�������܂ނ��܂��܂ȑ��u�����t�����Ă���A���炩�̐U�������`�F�b�g���ʁi���~�߂ɂ���ĉ^����������ɐ����������ʁj�������N�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���㕨���w�ɂ�����d�v�Ȏ����i�F���w�i���˂̑����d�͔g�̌��o�Ȃǁj�ł́A�m�C�Y�̏����ɔ���ȘJ�͂���₳��Ă���AEM�h���C�u�̎����ł��ꂾ���̔z�����Ȃ��ꂽ���ǂ����A���X�^�킵���Ǝv���܂��B�����������畨���w�̏펯���唭���Ȃ̂�������܂��A���̂Ƃ���A�^�ɎȂ������ǂ��Ƃ����̂����̌����ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���w�E�̒ʂ�ŁA�������肵�Ă��܂����B�ʑ����x��c���܂��i�d�ł�����A���̍ۂɒ������܂��j�B�������A�u�����ȏ�̈ʑ����x���������g���������̉��ƂȂ�v�Ƃ��������ł����āA�����ȏ�ŏ���G�l���M�[���`���Ƃ����킯�ł͂���܂���B�Ⴆ�A�g���g���ĐM���𑗂낤�Ƃ���ƁA�p���X�ɂ���ăf�W�^���M�������Ȃ���Ȃ�܂��A���̏ꍇ�A�p���X�͌Q���x�œ`�d����̂ŁA�������܂���B
�@�����ɂ́A�����ɃN���C�����S���h���������ɏ]����͂���܂���B�f���q�̏�́A���Ƃ��ƕ��U�̂Ȃ��g���������ɏ]���Ă���A�S�Ă͌����œ`�d���܂����A�u�Q�[�W�Ώ̐��̔j��v�ƌĂ�錻�ۂŎ��ʍ���������ƁA�q�b�O�X��̂悤�ɁA�ߎ��I�ɃN���C�����S���h���������ɏ]���P�[�X���o�Ă��܂��B�������A���̏ꍇ�ł��A���ۂɊϑ������̂́A��̗�N��Ԃł���f���q���Q���x�ʼn^������ߒ������ł��B
�@�ʑ����x���������ɂȂ邱�Ƃ́A���S�ɑ��Θ_�̘g�Ɏ��܂��Ă���A���̖�������܂���B�w���S�ƏK���ΐ����_�x�́u��4-3-6 �������^���ƃ^�L�I���v�ŋ������Ă������悤�ɁA���������R�E�̍ō����x���ƍl������̂́A�������肵�Ȃ��Ɓu�������ߋ��ɉe�����y�ڂ����Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ������ʗ��ɖ������邩��ł����āA���ΐ������ƈ�w���邩��ł͂���܂���B�u��6-3 ���Θ_�̌����͉����H�v�ł́A�u�����s�ϐ����������ƍl����̂͑��Θ_�ɑ���ő�̌�����v�Ƃ܂Ō����Ă����܂����B���Θ_�̊�{�I�Ȍ����͂����܂Ń��[�����c�Ώ̐��ł���A�N���C�����S���h���������́A���[�����c�Ώ̐������鑊�Θ_�I�ȕ������ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@���x�[�O�ϕ��́A�m���_�������ɒ莮������Ƃ��Ɏg������̂ł����A�����܂Ő��w�I�Ȍ�������Nj�����Ƃ��ɏd�v�ɂȂ�̂ł����āA���v�͊w��o�ϊw�Ȃǂ̐����I�ȕ�����܂߂āA���p�ɂ͂قƂ�ǕK�v�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�����ȋc�_�Ń��x�[�O�ϕ��̂悤�Ȓ��ې��w�̊T�O���g����̂́A�����I�Ȏ��ۂ��������グ��ƁA�m���Ƃ����T�O��������ƒ�`�ł��Ȃ�����ł��B�Ⴆ�A�C�ے��ɂ��~���m���̗\��́A�ߋ��ɓ����悤�ȋC�ۏɂȂ����Ƃ��̍~���ʂ����Ƃɍs���Ă��܂����A�����Ȃāu�����悤�ȁv�ƌ����̂��B����������܂��B���������B�������c�����܂܂ł͐��w�I�ȋc�_��W�J���ɂ����̂ŁA�܂��m���𐔊w�I�ɒ�`������ł��܂��܂Ȓ藝���Ă����A�������ɁA���̒藝�������̎��ۂɓ��Ă͂߂�Ƃ����_�@�������킯�ł��B���w�I�ɒ�`���ꂽ�m���ɂ́A��̓I�ȓ��e����������܂���B�P�ɁA�S�Ă̕����W���ɑ��Ĕ�l�̑��x���^�����Ă���A�݂��ɑf�ȕ����̕����W��������Ƃ��A�����̘a�W���̑��x�͊e�����W���̑��x�̘a�ɂȂ�Ƃ������@�������藧�ꍇ�ɂ́A���x�̋K�i���ɂ���Ċm������`�����Ƃ��������ł��i�ȒP�Ɍ����A�����ĂP�ɂȂ�0�����̒l�Ȃ牽�ł��m�����Ƃ������Ɓj�B
�@���x�[�O���x�Ƃ́A�������̎��ϐ��ɑ��Ē�`�������@�I���x�ŁA�ʐς�̐ς̊T�O���g���������̂ƌ����ėǂ��ł��傤�B���x�[�O�ϕ��́A�����f�p�Ɍ����Ă��܂��A���[�}���ϕ��ɂ������ԋ��ϖ@�̋�Ԃ��A������ԂɌ��肹�����x�[�O���x���^����ꂽ�̈�Œu���������ϕ��ł��B�K�i�����ꂽ���x�[�O���x���m���ƌ��Ȃ���̂ŁA���x�[�O�ϕ��́A�m���Ɗ��̐ς𑫂����킹��v�Z�ƂȂ�A���Ғl�Ȃǂ̓��v�I�ȗʂ����߂邱�Ƃɑ������܂��B
�@���x�[�O�ϕ����g�������b�g�́A�m���ɋ�̓I�ȓ��e���Ȃ��̂ŁA�����ɐ��w�I�ȋc�_�����ŁA���܂��܂Ȓ藝��������_�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���[�}���ϕ��ł́A�ϕ���Ԃ����ɂ���Ɍ����삪���邽�߁A��d�ϕ��̏��������ւ����邩�ǂ����ȂǁA���w�I�ɔ����Ȗ�肪���������ł����A���x�[�O�ϕ��Ȃ�A�������������r�I�e�Ղɍ����ł��܂��B
�@�����A���w�I�Ɍ����ȋc�_�����p����łǂ�قǖ��ɗ����A���������^��ł��B���Ȃ荂�x�ȗ��_�����w�ł��A���x�[�O�ϕ��̒藝��p���Ă͂��߂ĉ����ł���悤�ȏ�ʂɏo��������Ƃ͂���܂���B�ϕ��̏���������ւ����Ȃ��P�[�X�͗ǂ�����܂����A���x�[�O�ϕ��ɂ�����t�r�j�̒藝�Ȃǂ������o�������A�Ȃ�����ւ����Ȃ������I�ȃC���[�W��p���čl��������L�v�ł��B���x0�̗̈悪�����I�Ȍ��ʂ��y�ڂ��Ȃ����Ƃ��A���x�[�O���x�ŋc�_������A��̓I�ɂǂ̂悤�ȃP�[�X�ɑ������邩���������������͂�����܂��B���x�[�O���x��x�[�O�ϕ��́A�����܂ŋc�_�̍ŏI�I�Ȏd�グ�Ɏg���c�[���ł����āA���H�I�ȏ�ʼn��p���ɑΏ�����ۂɂ́A���ɗ����Ȃ��Ƃ����̂����̎����ł��B
�@�m���_�̉��p�Ŗ��ɂȂ�̂́A�ނ���A�����Ȑ��w�Ƌ�̓I�Ȏ��ۂ�������ƌ��т����邩�Ƃ����_�ł��B�Ⴆ�A�������̂����Ƃ��炵�������u���ƁA���v�I�ȕ������ۂɊւ��ăx���̕s�����̐�����������ɂ�������炸�A�ʎq�_�I�Ȍ��ۂł́A���̕s���������藧���Ȃ��Ƃ����������ʂ������Ă��܂��B�����ŁA����̂P�ł��镨���@���̋Ǐ������j��Ă���Ƃ������c�_���o�Ă���̂ł����A���́A��荪�{�I�ȑO��ł��鑪�x�̔�l������ɂ��ׂ����ƍl���܂��B�܂��A�����̐l�Ԃ��֗^���錻�ۂv���w��p���ė\������ꍇ������܂����A�l�Ԃ̍s���K�͂͂������̗��h�ɕ�����邱�Ƃ������̂ŁA���v�I�Ȍ��ۂł����Ă����S�Ɍ��藝�����藧���܂���B���Z�H�w�̕���Ŋm���ߒ��Ɋւ��錵���ȕ��������g�����g��̑ł����̂Ȃ��h�\�������Ă��A�����Α�͂���ɂȂ�킯�ł��B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�u���b�N�z�[���̌��ۂ��L�q�����ʑ��Θ_�ɂ́A���W���ǂ̂悤�ɑI��ł����܂�Ȃ��Ƃ�������������܂��B�u�V���o���c�V���g���a����̂ɖ����ɋ߂����Ԃ�������v�̂́A�V�����@���c�V���g�ʕt�߂œ���̍��W�n��I�ꍇ�̂��ƂŁA�n������u���b�N�z�[�����ϑ�����Ƃ��ɁA���̍��W�n��I�ԕK�R���͂���܂���B�������A�ǂ̂悤�ȍ��W�n���̗p���Ă��A���N���镨�����ۂ͓���ł��B�u���b�N�z�[���Ɉ��ݍ��܂��ϑ��҂��炷��ƁA���R��������ߒ��ł́i�����͂�ʂɂ��āj�d�͂͑S��������ꂸ�A�V�����@���c�V���g�ʂ�ʉ߂���ۂɂ��A�����N���܂���B�L�����Ԃ̂����Ƀu���b�N�z�[���̒��S�ɓ��B���܂��B�u�����ɋ߂����Ԃ�������v�Ƃ́A����̂䂪�݂̂����ŁA�V�����@���c�V���g�ʂ�ʉ߂��钼�O�ɔ����������A���܂ł��ʂ̋߂����痣���ꂸ�A�����̊ϑ��҂ɓ��B����̂ɒ������Ԃ������邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�ƌ����Ă��A�u���b�N�z�[���Ɉ��ݍ��܂�镨�̂��A�V�����@���c�V���g�ʕt�߂ɂ����Ƃւ���Č�����̂ł͂Ȃ��A�ʂ�ʉ߂���ߒ��Ō��ʂ��}������̂ŁA�ϑ��҂��炷��ƁA���̂��Â������Ă����悤�Ɍ�����͂��ł��B
�@�u���b�N�z�[���̊ϑ��́A���͂Ɍ`�����ꂽ�~���~�Ղ̕��������ݍ��܂��ۂɕ��˂����w���Ȃǂ̓d���g�ɂ���čs���܂��B�u���b�N�z�[���Ɍ������ė������镨���́A�V�����@���c�V���g�ʂ̂��Ȃ��O�Ō݂��Ɍ������Փ˂��d���g����˂���̂ŁA�����ʂ̋ߖT�ɗ��܂�Ƃ������ʂ͂قƂ�nj���܂���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�I�[�����`�I�L�g���E��(Aurantiochytrium)�ɂ��Ă͂��܂�m��Ȃ������̂Ńl�b�g�Ō������Ă݂܂������A�ǂ����A���ϕi�p�̍��@�\���Y����v�����g�̌��݂ɒ��肷��i�K�ŁA�����Ԃ�q��@�̃o�C�I�R���Ɋւ��ẮA��������Ƃ��Ă����Ȃ��ɂȂ肻���ł��B
�@�I�[�����`�I�L�g���E���́A�}�g��w�̌����`�[�����I�[�X�g�����A�Ŕ�����2010�N�ɕ������ނł��B�����ȑ��B�͂������A�T�v�������g�Ƃ��Đl�C�̂���h�R�T�w�L�T�G���_�iDHA�j�Ȃǂ̃�-3������ɎY������_�����ڂ���܂����B�������A�N�����t�B�������������������s��Ȃ��]���h�{�����Ȃ̂ŁA�Y�f�������̃G�T��^���Ȃ���Ȃ炸�A�����ɖ����̑�ʐ��Y�������ł���킯�ł͂���܂���B�}�g��w�u���ރo�C�I�}�X�E�G�l���M�[�V�X�e���������_�v�̃z�[���y�[�W������ƁA�{�g���I�R�b�J�X�Ȃǂ̌��������ނƑg�ݍ��킹��A���������ƒY�����f���Y���ɍs���V�X�e�����\���ƋL����Ă��܂����A�\�z�i�K�ɗ��܂��Ă��܂��B���肵�����B�̂��߂ɔ|�{�^���N�𝘝a��������������o���̂ɉ��w���������肵�Ȃ���Ȃ炸�A�����_�ł̓R�X�g�����Ȃ荂�����̂��l�b�N�ł��B
�@���o�V���̋L���ɂ��ƁA�}�g��w���x���`���[�̑��o�C�I�e�N�m���W�[�Y���A�����{��k�ЂŔ�Q�����n��̕������ƂƂ��āA�{�錧�������s�ɃI�[�����`�I�L�g���E���̔|�{�^���N10���������H������݁A2018�N�t����ғ������@�\���𒊏o�E�������ĉ��ϕi���[�J�[�Ȃǂɒ���\�肾�����ł��i2015�N7��30���t���o�d�q�Łj�B���o�r�W�l�X�Łu���ނ̒��������B�œ��{���Y�����ɂȂ�H�@2�̑����n�C�u���b�h���B���A�R�����������E�Ɂv�ƃu�`�グ���L���i2015�N10��15���t���o�r�W�l�Xonline�j���炷��ƁA���Ȃ��ނ�����ۂ��܂��B�z������ɁA�x���`���[�r�W�l�X�ł͎��ڂ��W�߂邽�߂Ɏ��ƖڕW��傰���ɐ������邱�Ƃ�����A�o�C�I�R���̘b�͂�������o�Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z

�@�u��C���m�o�ΏۂƂ���Ȃ��̂͐i���̌��ʂł���v�Ƃ����l�����́A��{�I�ɐ������Ǝv���܂��B�O�J���̋c�_�͓r���̐�����[�܂��Ă���̂ŁA�����킩��ɂ����̂�������܂���B
�@G�^��n�i���F��j�ł��鑾�z�̃X�y�N�g����460nm�i�ΐF�j�t�߂Ƀs�[�N�������̕��˂ŕ\����܂����A��C����300nm�ȉ��̒Z�g�������啝�ɃJ�b�g�����̂ŁA�n�\������ł́A�����オ�������i400�`800nm���x�j�A�c��̑啔�����ԊO���ɂȂ�܂��B���������˂𗘗p����ꍇ�A�ԊO���͑�C�␅�����߂�M���Ƃ��ĊԐړI�ɖ𗧂Ă����A�����w�������N�����₷���g���̒Z�����́A���������s�����߂̃G�l���M�[���Ƃ��āA�܂��A����e�̂���Ēm�o���邽�߂ɁA���ړI�ɗ��p���Ă��܂��B����e�̂́A�����z������ƍ\���ω����N�����^���p�N���ł���A�~�h�����V�̂悤�ȒP�זE�����ɂ���������̂ŁA�T�����Y����������������邽�߂ɁA�i���̂��Ȃ葁���i�K���痘�p���ꂽ�ƍl�����܂��B�������A���̒i�K�ł́A�܂��u��C�����F�������v�ƔF������悤�Ȓm�o�͐������Ă��܂���B
�@�����̎��o���}���ɐi������̂̓J���u���A�����̎����ŁA���̍��A����e�̂��g�D�����ꂽ�g��h�����������o�ꂵ�܂����B��̐i���𑣂����v���������͂͂����肵�܂��A�ߐH�W���d�v�Ȗ������ʂ������Ƃ�������������܂��B�ߐH�҂ɂƂ��Ă͉a��f���������邽�߁A�a�ƂȂ鐶���ɂƂ��Ă͕ߐH�҂��瓦��邽�߂ɁA���@�\�Ȏ��o�튯�������Ƃ��L���ɍ�p����̂ŁA���������������x�z�I�ɂȂ����Ƃ����킯�ł��B���̏ꍇ�A�����ɑ��݂���a��ߐH�҂����F���邱�Ƃ��d�v�ł���A�r���̔}���i�J���u���A�I�̐����ɂƂ��Ă͐��j�Ɋւ�����͕s�K�v�Ȃ̂ŁA�}���͔F�m����Ȃ����F�����ȑ��݂ɂȂ����ƍl�����܂��B�ߐH�W�́A���̌���i���̓������肷��d�v�ȃt�@�N�^�[�ł��葱�����̂ŁA�i���̉�������ɂ���l�Ԃ��}���i��C�j��F�m���Ȃ��̂ł��傤�B
�@�ȏ�̋c�_���琄���ł���悤�ɁA�ߐH�W�������͂̔}���Ɋւ���f�[�^���d�v�Ȑ���������ꍇ�A�ނ�ɂƂ��Ĕ}���́g������h�͂��ł��B�n���ɂ͑��݂��Ȃ������ł����A���ɁA�m�������������V����������Ƃ��܂��傤�B�x�h�{�����i�C��̕��V�����́A���͂ɉh�{�����L�x�ɂ��邽�߂ɑf�����������K�v���Ȃ��A���̑���A�����≖���Z�x�̂悤�Ȕ}���Ɋւ���f�[�^�̕��������̏�ŏd�v�ɂȂ�܂��B���������āA�x�h�{��Ԃ̊C�ɏZ�ޒm�I���V�����́A���͂̐��̏�Ԃ�������悤�Ȋ��o�튯��i�������Ă���Ɨ\�z����܂��B
�@���鐶���ɂƂ��āg������h���̂��ʂ̐����ɂ́g�����Ȃ��h�Ƃ����́A��̓I�Ȏ�����g���čl���邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A�R�E�����́A�����̖ڂ�邽�߂ɖ�s���ɂȂ��������̚M���ނƓ����悤�Ɏ��o���ア���ʁA�����g���g���Ď��͂̕��̂�F�m���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�l�Ԃɂ͕s�����Ɍ����鉌���A�ނ�ɂ͓����Ɏv����ł��傤�B�܂��A�C�k�̂悤�ɚk�o�̔��B���������́A�����̍��Ղ̂悤�ȉߋ��̏���m�o���Ă���A���Ԏ������̊g����������E���g������h�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�y�p���`�ڎ��ɖ߂�z
©Nobuo YOSHIDA
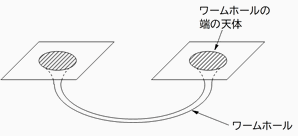 �@�ߋ��ɖ߂�^�C���g���x���ɂ��āA���Ă͕����@���ɂ���ċ֎~�����ƍl�����Ă��܂����B�ߋ��ɖ߂��Ȃ�A�u�e�E���̃p���h�N�X�v�Ȃǂ̃^�C���p���h�N�X�������Ă��܂�����ł��B����܂ł��܂��܂ȃp���h�N�X���l�Ă���A�ߋ��ɖ߂郋�[�g�����݂���A���Ƃ��l�Ԃ����Ȃ��Ă��������N����i��������_�ɂQ�̑������鎖�ۂ����N����j���Ƃ�������Ă��܂��B
�@�ߋ��ɖ߂�^�C���g���x���ɂ��āA���Ă͕����@���ɂ���ċ֎~�����ƍl�����Ă��܂����B�ߋ��ɖ߂��Ȃ�A�u�e�E���̃p���h�N�X�v�Ȃǂ̃^�C���p���h�N�X�������Ă��܂�����ł��B����܂ł��܂��܂ȃp���h�N�X���l�Ă���A�ߋ��ɖ߂郋�[�g�����݂���A���Ƃ��l�Ԃ����Ȃ��Ă��������N����i��������_�ɂQ�̑������鎖�ۂ����N����j���Ƃ�������Ă��܂��B
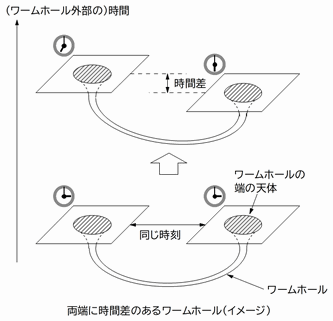
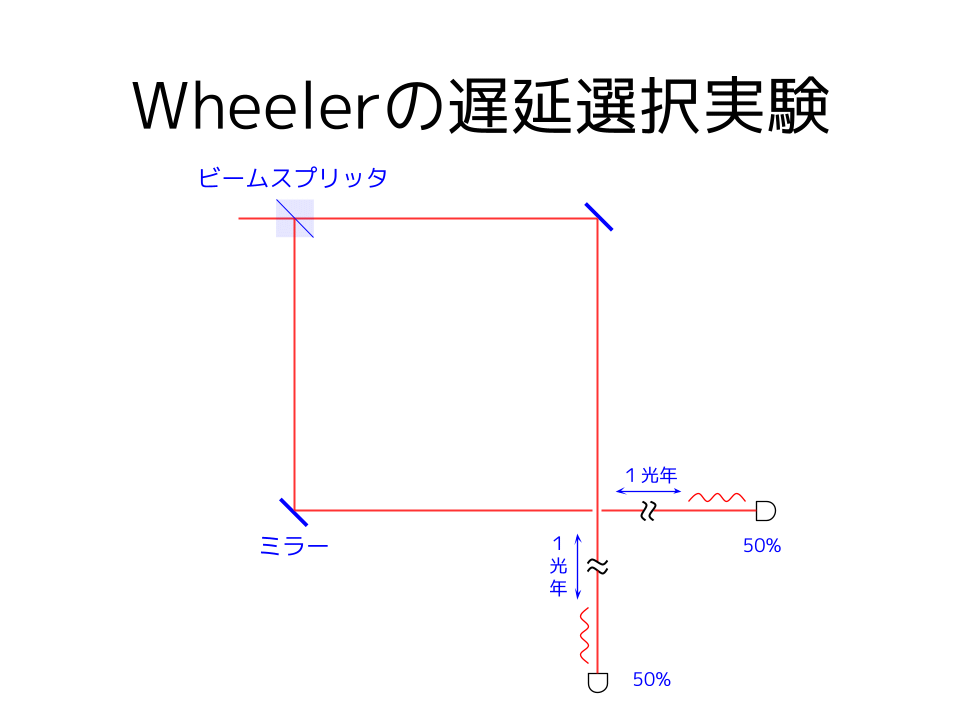
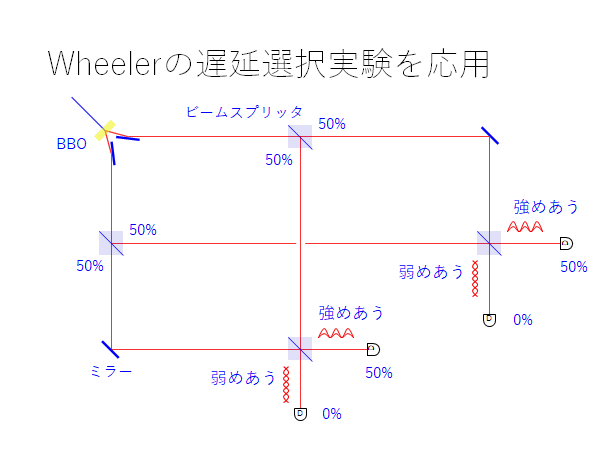
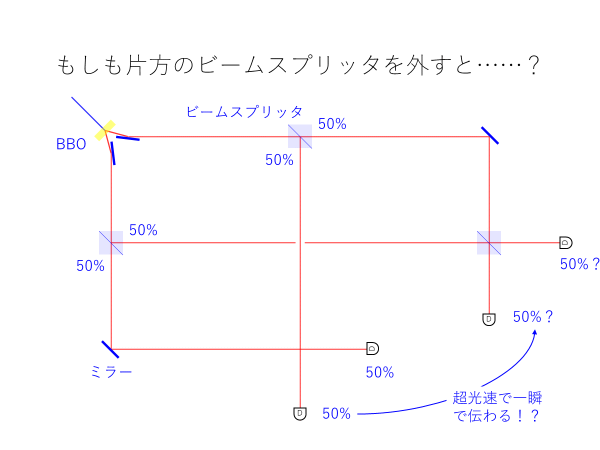
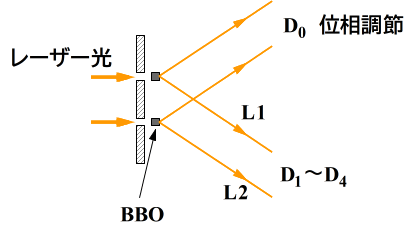
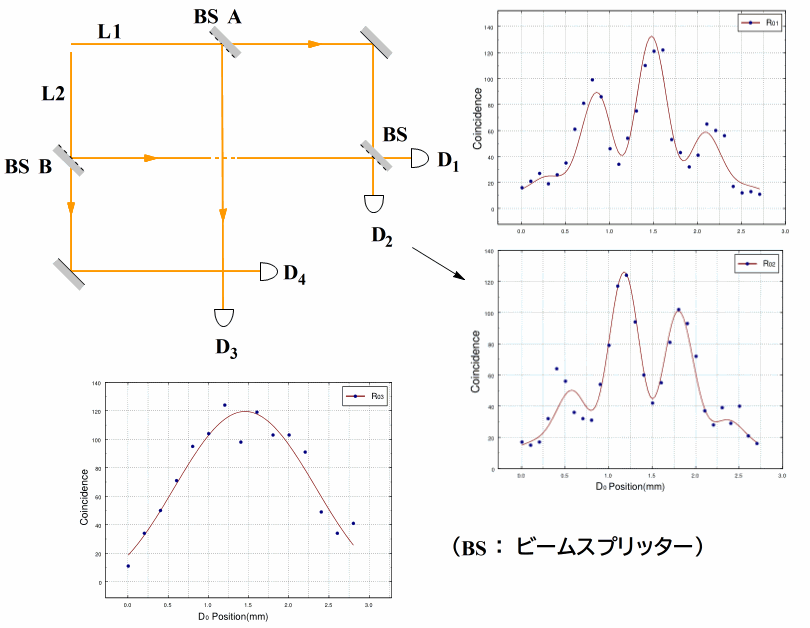
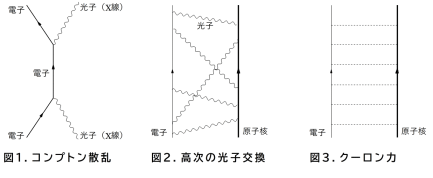

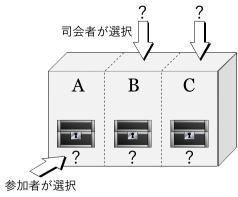 �@�i�i�́AA�`C�̂ǂꂩ�ɓ��������œ����Ă���͂��ł�����A�R����̎��s�̂����AA�ɓ����Ă���P�[�X���P����A�������AB���P����AC���P����ł��B���̂R�̃P�[�X���ꍇ�������܂��B
�@�i�i�́AA�`C�̂ǂꂩ�ɓ��������œ����Ă���͂��ł�����A�R����̎��s�̂����AA�ɓ����Ă���P�[�X���P����A�������AB���P����AC���P����ł��B���̂R�̃P�[�X���ꍇ�������܂��B
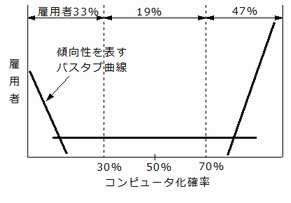 �@�ٗp���v�ƌ��т���ƁA�R���s���[�^���m���ɑ��ăv���b�g�����ٗp�Ґ��͂��ꂢ�ȃo�X�^�u�Ȑ��ƂȂ�܂��i�E�}�G�X������\���T���}�j�B�����M����ƁA�R���s���[�^������₷���E��Ƃ���ɂ����E��ɂ͂����蕪����A�R���s���[�^�����X�N�̍����i�R���s���[�^���m��70���ȏ�́j�E��ɏ]������l���A�S�ٗp�҂�47���ɒB����Ƃ������_������ꂻ���ł��B�������A����قnj����ȃo�X�^�u�Ȑ��ɂȂ�̂́A���x�������ɒ[�ɎU���₷��������O*NET���ڂƂ��đI��Ă��邱�ƁA����ɁAO*NET���ڂ̃��x�����ő�l�ɋ߂Â��L���͈͂ŃR���s���[�^���m�����ɒ[�Ȓl�ɂ��郂�f�����g���Ă��邱�Ɓ|�|�Ȃǂ��e�����y�ڂ������ʂł͂Ȃ����Ɛ�������܂��B
�@�ٗp���v�ƌ��т���ƁA�R���s���[�^���m���ɑ��ăv���b�g�����ٗp�Ґ��͂��ꂢ�ȃo�X�^�u�Ȑ��ƂȂ�܂��i�E�}�G�X������\���T���}�j�B�����M����ƁA�R���s���[�^������₷���E��Ƃ���ɂ����E��ɂ͂����蕪����A�R���s���[�^�����X�N�̍����i�R���s���[�^���m��70���ȏ�́j�E��ɏ]������l���A�S�ٗp�҂�47���ɒB����Ƃ������_������ꂻ���ł��B�������A����قnj����ȃo�X�^�u�Ȑ��ɂȂ�̂́A���x�������ɒ[�ɎU���₷��������O*NET���ڂƂ��đI��Ă��邱�ƁA����ɁAO*NET���ڂ̃��x�����ő�l�ɋ߂Â��L���͈͂ŃR���s���[�^���m�����ɒ[�Ȓl�ɂ��郂�f�����g���Ă��邱�Ɓ|�|�Ȃǂ��e�����y�ڂ������ʂł͂Ȃ����Ɛ�������܂��B
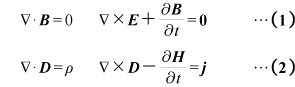
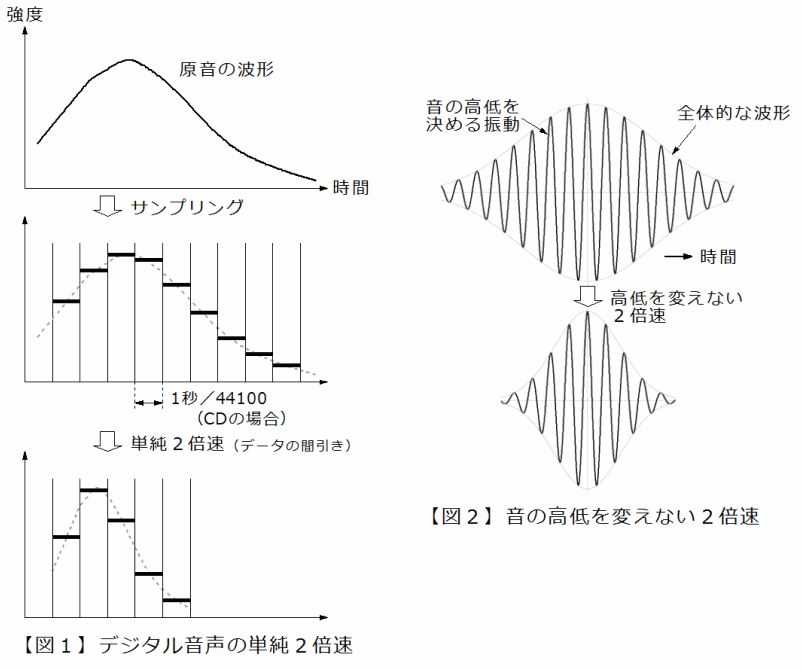
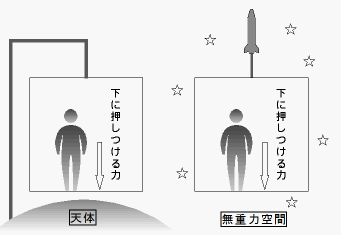 �@���̋c�_�Ɏg��ꂽ�̂��A�L���ȁu�G���x�[�^�̎v�l�����v�ł��B���Ȃ��́A���͂����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��G���x�[�^�̃J�S�ɕ����߂��A���ɉ���������悤�ȗ͂������Ă���Ƃ��܂��i�E�}�j�B���āA���̗͂̌����͉��Ȃ̂��H �G���x�[�^�̉����ɋ���ȏd�͌��������ďd�͂��y�ڂ��Ă���̂��A����Ƃ��A���d�͋�Ԃɕ����ԃJ�S�����P�b�g�Ȃǂŏ���Ɉ��������ĉ������̊����͂��������Ă���̂��|�|�����������Ӗ�����̂́A�J�S�����ł̕������ۂ����𗘗p�����ǂ�Ȏ��������Ă��A�Q�̉\���̂ǂ��炩����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@���̋c�_�Ɏg��ꂽ�̂��A�L���ȁu�G���x�[�^�̎v�l�����v�ł��B���Ȃ��́A���͂����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��G���x�[�^�̃J�S�ɕ����߂��A���ɉ���������悤�ȗ͂������Ă���Ƃ��܂��i�E�}�j�B���āA���̗͂̌����͉��Ȃ̂��H �G���x�[�^�̉����ɋ���ȏd�͌��������ďd�͂��y�ڂ��Ă���̂��A����Ƃ��A���d�͋�Ԃɕ����ԃJ�S�����P�b�g�Ȃǂŏ���Ɉ��������ĉ������̊����͂��������Ă���̂��|�|�����������Ӗ�����̂́A�J�S�����ł̕������ۂ����𗘗p�����ǂ�Ȏ��������Ă��A�Q�̉\���̂ǂ��炩����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
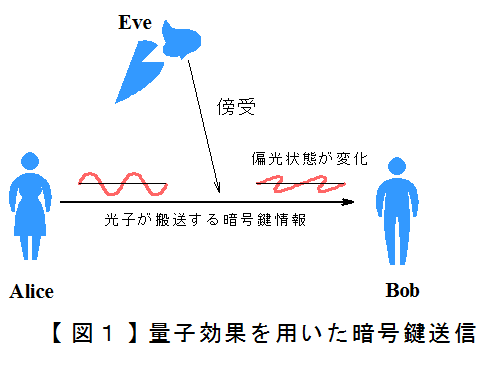
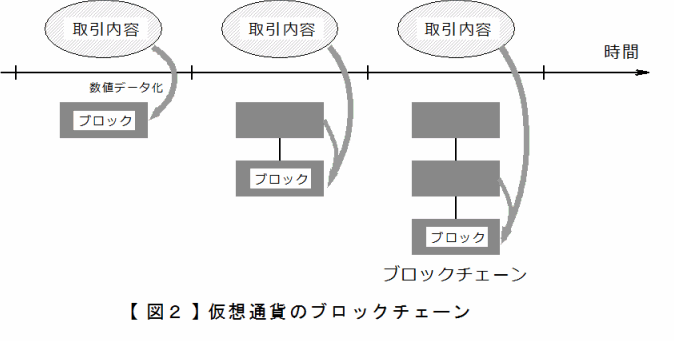
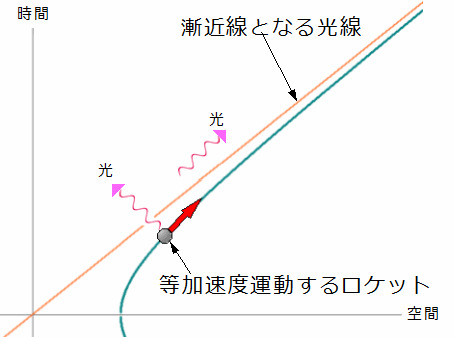 �@�c���F���Ƃ͏����Ⴄ�̂ł����A���̂悤�ȏ��l����ƁA�����̓C���[�W�ł���ł��傤�B���P�b�g�����R�ȃ��[�N���b�h��ԂŁi���Θ_�I�ȈӖ��ł́j�������x�^�������Ă���Ƃ��܂��B���P�b�g�͉�������ăX�s�[�h�������Ȃ�܂����A���Θ_�̐�����̂ŁA�����ȏ�ɂ͉����ł��܂���B���������āA���P�b�g�̋O�Ղ́A�}�̃O���t�̂悤�ɁA��������ɑQ�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�Q�ߐ��ƂȂ�����́A��������ė�������E�ł���A���̔ޕ�����͌����Č����͂��܂���B���������āA���̌����̈ʒu�����P�b�g����ɂƂ��Ă̒n�����ł���A���̌��������́A�܂�Œ������ʼn��������Ă���悤�Ɋ������܂��B�������A�O���猩��ƁA�������œ������̂͂Ȃ��A���Θ_�ɒ�G���錻�ۂ͉����N���Ă��܂���B
�@�c���F���Ƃ͏����Ⴄ�̂ł����A���̂悤�ȏ��l����ƁA�����̓C���[�W�ł���ł��傤�B���P�b�g�����R�ȃ��[�N���b�h��ԂŁi���Θ_�I�ȈӖ��ł́j�������x�^�������Ă���Ƃ��܂��B���P�b�g�͉�������ăX�s�[�h�������Ȃ�܂����A���Θ_�̐�����̂ŁA�����ȏ�ɂ͉����ł��܂���B���������āA���P�b�g�̋O�Ղ́A�}�̃O���t�̂悤�ɁA��������ɑQ�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�Q�ߐ��ƂȂ�����́A��������ė�������E�ł���A���̔ޕ�����͌����Č����͂��܂���B���������āA���̌����̈ʒu�����P�b�g����ɂƂ��Ă̒n�����ł���A���̌��������́A�܂�Œ������ʼn��������Ă���悤�Ɋ������܂��B�������A�O���猩��ƁA�������œ������̂͂Ȃ��A���Θ_�ɒ�G���錻�ۂ͉����N���Ă��܂���B
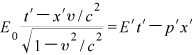
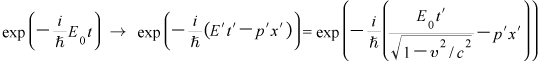
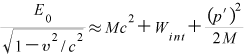
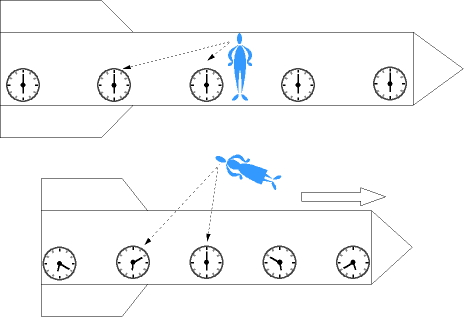 �@���Θ_�I�Ȍ��ʂƌĂ����̂̑����́A���݂ɉ^������ϑ��҂̊ԂŁA���Ԃ�����Ă��邱�ƂɋN�����܂��B����ȃ��P�b�g�̐i�s�����Ɏ��v����ׂ��ꍇ���l���܂��傤�B���P�b�g�̏���ɂƂ��āA�S�Ă̎��v���������Ă����Ƃ��Ă��A���P�b�g�̊O�ɂ���l���炷��ƁA��[�ɋ߂����v�قǒx��Ă���悤�Ɋϑ�����܂��i���v����ϑ��҂̂Ƃ���܂Ō������B����̂Ɏ��Ԃ��|����̂ŁA�ڂŌ��Ă����Ȃ�킯�ł͂���܂���j�B���P�b�g�̏�����炷��ƁA�O���̐l�́A���P�b�g�̒����𑪂�Ƃ��A��[���ƌ�[���̈ʒu���ɑ��肷��̂ł͂Ȃ��A��[���͏����O�̎����A��[���͏�����̎����ő��肵�Ă��܂��B���̂��߁A���������̏���Ă��郍�P�b�g���A�g���ۂ́h���������Z���ϑ�����邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A������u���[�����c�Z�k�v���N���闝�R�ł��i����ȊO�ɂ��A���P�b�g�����ƊO���Ƃō��W���݂��ɌX�����Ƃɂ����ʂ������܂��j�B
�@���Θ_�I�Ȍ��ʂƌĂ����̂̑����́A���݂ɉ^������ϑ��҂̊ԂŁA���Ԃ�����Ă��邱�ƂɋN�����܂��B����ȃ��P�b�g�̐i�s�����Ɏ��v����ׂ��ꍇ���l���܂��傤�B���P�b�g�̏���ɂƂ��āA�S�Ă̎��v���������Ă����Ƃ��Ă��A���P�b�g�̊O�ɂ���l���炷��ƁA��[�ɋ߂����v�قǒx��Ă���悤�Ɋϑ�����܂��i���v����ϑ��҂̂Ƃ���܂Ō������B����̂Ɏ��Ԃ��|����̂ŁA�ڂŌ��Ă����Ȃ�킯�ł͂���܂���j�B���P�b�g�̏�����炷��ƁA�O���̐l�́A���P�b�g�̒����𑪂�Ƃ��A��[���ƌ�[���̈ʒu���ɑ��肷��̂ł͂Ȃ��A��[���͏����O�̎����A��[���͏�����̎����ő��肵�Ă��܂��B���̂��߁A���������̏���Ă��郍�P�b�g���A�g���ۂ́h���������Z���ϑ�����邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A������u���[�����c�Z�k�v���N���闝�R�ł��i����ȊO�ɂ��A���P�b�g�����ƊO���Ƃō��W���݂��ɌX�����Ƃɂ����ʂ������܂��j�B
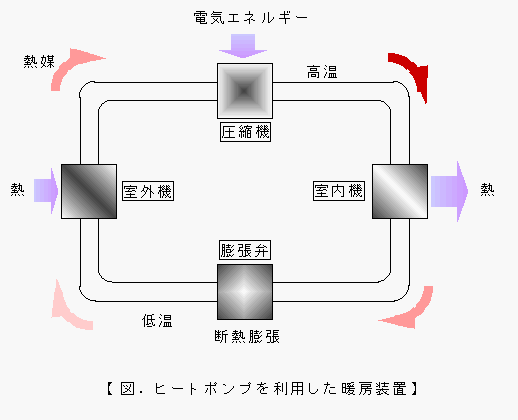 �@�q�[�g�|���v�ɂ��g�[�@��́A�ʏ�̗�[���������蔽�ɂ������̂ł��i�}�Q�Ɓj�B�܂��A�M�}�i�e�ՂɈ��k�E�c����������}���j��d�C�G�l���M�[�ʼn��M���A�����@��ʂ��ĕ����̒���g�߂܂��i�}�ł͎����@���璼�ڔM�����o�����悤�ɕ`���܂������A���ۂɂ́A������i�̔M�������s���āA���g�[���s���ꍇ�������悤�ł��j�B�����ɂȂ����M�}�́A���͂����C���������̂ŁA�c���ق��J�����Ēf�M�c��������ƁA�}���ɉ��x��������܂��B�������ĊO�C�����ቷ�ɂ����M�}�����O�@�ɑ��荞�ނƁA�O����M����荞�݂܂��B��[�̎��O�@����͔M�����o�Ă��܂����A���̒g�[�V�X�e���ł́A���O�@����O�C�������Ⴂ�╗���o�܂��B�������ĔM�}���z������ƁA�����@������o�����M�G�l���M�[�́A���k����̂ɗv����d�C�G�l���M�[�����傫���Ȃ�A�����I�Ȓg�[���\�ɂȂ�܂��B
�@�q�[�g�|���v�ɂ��g�[�@��́A�ʏ�̗�[���������蔽�ɂ������̂ł��i�}�Q�Ɓj�B�܂��A�M�}�i�e�ՂɈ��k�E�c����������}���j��d�C�G�l���M�[�ʼn��M���A�����@��ʂ��ĕ����̒���g�߂܂��i�}�ł͎����@���璼�ڔM�����o�����悤�ɕ`���܂������A���ۂɂ́A������i�̔M�������s���āA���g�[���s���ꍇ�������悤�ł��j�B�����ɂȂ����M�}�́A���͂����C���������̂ŁA�c���ق��J�����Ēf�M�c��������ƁA�}���ɉ��x��������܂��B�������ĊO�C�����ቷ�ɂ����M�}�����O�@�ɑ��荞�ނƁA�O����M����荞�݂܂��B��[�̎��O�@����͔M�����o�Ă��܂����A���̒g�[�V�X�e���ł́A���O�@����O�C�������Ⴂ�╗���o�܂��B�������ĔM�}���z������ƁA�����@������o�����M�G�l���M�[�́A���k����̂ɗv����d�C�G�l���M�[�����傫���Ȃ�A�����I�Ȓg�[���\�ɂȂ�܂��B
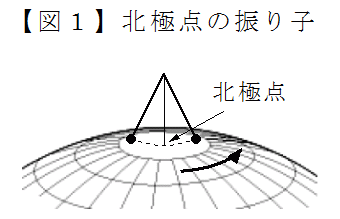 �@�܂��A�R���I���͂��ǂ̂悤�Ȃ��̂��m�ɂ��邽�߂ɁA�k�ɓ_�Ƀt�[�R�[�̐U��q��ݒu���A�F���i�n���̌��]���x�Ɠ����X�s�[�h�œ��������n�j���猩�ē����U���ʓ��������^��������ꍇ���l���܂��i�}�P�j�B�n�ʂ��������ɓ����Ă��邽�߁A�U��q���U�����S���牓�������Ă����i������ɉ^������j�Ƃ��́A�n�\����́A�����肪�������ɃJ�[�u��`���悤�Ɍ����܂��B�t�ɁA�U�����S�ɖ߂�i�k�����ɉ^������j�Ƃ��ɂ́A�n���̎���̉�]���x���x�����ܓx�n���Ɉړ����邽�߁A�n�ォ�猩���������̑��Α��x������ɒx���Ȃ�悤�ɋO�����Ȃ���܂��B���������āA�n�ォ�猩���Ƃ��̐U��q�̉^���́A�i��n�ɑ��鑊�ΓI�ȁj�^�������ɑ��ĉE�����ɋȂ����Ă����܂��B���������ω��������N�����������̗͂Ƃ��đz�肳���̂��A�R���I���͂ł��B
�@�܂��A�R���I���͂��ǂ̂悤�Ȃ��̂��m�ɂ��邽�߂ɁA�k�ɓ_�Ƀt�[�R�[�̐U��q��ݒu���A�F���i�n���̌��]���x�Ɠ����X�s�[�h�œ��������n�j���猩�ē����U���ʓ��������^��������ꍇ���l���܂��i�}�P�j�B�n�ʂ��������ɓ����Ă��邽�߁A�U��q���U�����S���牓�������Ă����i������ɉ^������j�Ƃ��́A�n�\����́A�����肪�������ɃJ�[�u��`���悤�Ɍ����܂��B�t�ɁA�U�����S�ɖ߂�i�k�����ɉ^������j�Ƃ��ɂ́A�n���̎���̉�]���x���x�����ܓx�n���Ɉړ����邽�߁A�n�ォ�猩���������̑��Α��x������ɒx���Ȃ�悤�ɋO�����Ȃ���܂��B���������āA�n�ォ�猩���Ƃ��̐U��q�̉^���́A�i��n�ɑ��鑊�ΓI�ȁj�^�������ɑ��ĉE�����ɋȂ����Ă����܂��B���������ω��������N�����������̗͂Ƃ��đz�肳���̂��A�R���I���͂ł��B
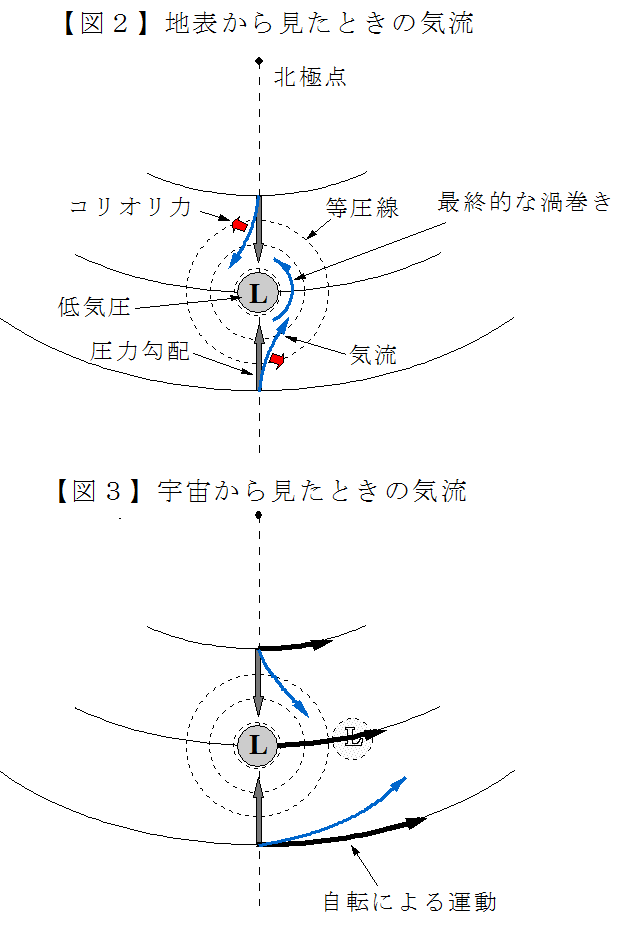
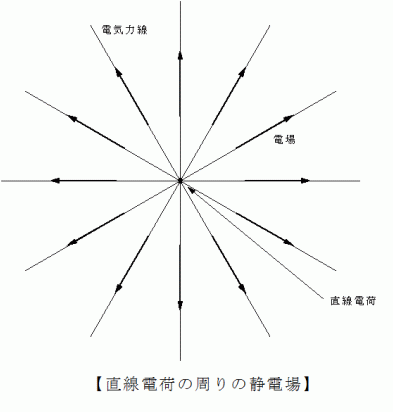 �@���̎����ł́A�i�C�������̕҂ݖ_�C�ŕ��ɑѓd�����ĐÓd������o���A���ɑѓd�������H�����͂ɔ���ē��������Ă��܂��i�ڂ����́A��L�y�[�W�̉����ǂ�ł��������j�B
�@���̎����ł́A�i�C�������̕҂ݖ_�C�ŕ��ɑѓd�����ĐÓd������o���A���ɑѓd�������H�����͂ɔ���ē��������Ă��܂��i�ڂ����́A��L�y�[�W�̉����ǂ�ł��������j�B
 �@�_�d�ׂ̋O���́A�^����������ϕ����邱�ƂŁA���߂��܂��B�d��̋��������S����̋����ɔ���Ⴗ��̂ŁA�^���������̌`�͔�r�I�ȒP�ɂȂ�܂����A�������͓I�ɐϕ����ċO�������߂邱�Ƃ͂ł��܂���B���S�͂���p����ꍇ�A���̂́A���Ȃ���߂Â����艓����������Ǝ����I�ȉ^�������܂����A�����I�ł͂����Ă��O���͕Ȑ��ɂȂ炸�A�����I�ȉ�͊��ł��\����Ȃ��̂ŁA�O�������߂�ɂ́A���l�ϕ����s���K�v������܂��B�����ł́A�G�l���M�[�Ɗp�^���ʂ�����l�̂Ƃ��̋O�����A�}�����Ă����܂��i���l�ϕ��́A�����x�v�Z�T�C�g�ikeisan.casio.jp�j�𗘗p���čs���܂������A����ȊO�̕����́A���Ȃ��G�c�Ɍv�Z���������Ȃ̂ŁA���܂�M�p���Ȃ��ł��������j�B�͂������̂Q��ɔ���Ⴗ��P�v���[�^���ł͑ȉ~�O���ɂȂ�܂����A�P��ɔ���Ⴗ��ꍇ�́A�Ԃт�̂悤�ȕ��G�ȋO���ɂȂ�܂��B����ł́A���������O����`���^�����A�点��^���ƌĂ̂ł��傤�B
�@�_�d�ׂ̋O���́A�^����������ϕ����邱�ƂŁA���߂��܂��B�d��̋��������S����̋����ɔ���Ⴗ��̂ŁA�^���������̌`�͔�r�I�ȒP�ɂȂ�܂����A�������͓I�ɐϕ����ċO�������߂邱�Ƃ͂ł��܂���B���S�͂���p����ꍇ�A���̂́A���Ȃ���߂Â����艓����������Ǝ����I�ȉ^�������܂����A�����I�ł͂����Ă��O���͕Ȑ��ɂȂ炸�A�����I�ȉ�͊��ł��\����Ȃ��̂ŁA�O�������߂�ɂ́A���l�ϕ����s���K�v������܂��B�����ł́A�G�l���M�[�Ɗp�^���ʂ�����l�̂Ƃ��̋O�����A�}�����Ă����܂��i���l�ϕ��́A�����x�v�Z�T�C�g�ikeisan.casio.jp�j�𗘗p���čs���܂������A����ȊO�̕����́A���Ȃ��G�c�Ɍv�Z���������Ȃ̂ŁA���܂�M�p���Ȃ��ł��������j�B�͂������̂Q��ɔ���Ⴗ��P�v���[�^���ł͑ȉ~�O���ɂȂ�܂����A�P��ɔ���Ⴗ��ꍇ�́A�Ԃт�̂悤�ȕ��G�ȋO���ɂȂ�܂��B����ł́A���������O����`���^�����A�点��^���ƌĂ̂ł��傤�B
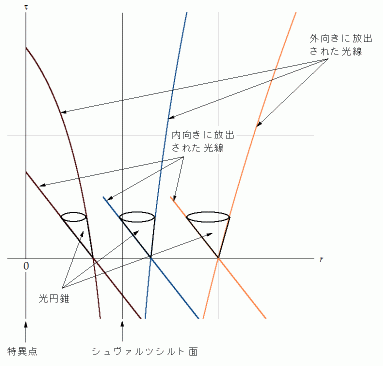 �@�u���b�N�z�[���́A�펯�ɔ�����V�̂Ǝv���Ă��܂����A���̎��͂Ō����ǂ̂悤�ɓ`��邩�𗝉�����ƁA�ϑ��҂��ǂ�Ȍ��i�����邩�A���ϓI�ɑ����邱�Ƃ��ł��܂��B��ԍ��W���i�P�̎������ȗ������j�Q�����ŁA���ԍ��W��c�{���ċ�ԍ��W�Ɠ����P�ʂŕ\�����Ƃɂ���ƁA�d�͂��Ȃ��ꍇ�A�_����������o�������́A�����_�Ƃ��Ő��̌X����45���̉~���ʂ�i�݂܂��B���̉~�������~���ł����A�u���b�N�z�[���̎��͂ł́A�����d�͂̂��߂ɁA���̉~�����}�P�̂悤�ɂЂ��Ⴐ���`�ɂȂ邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�V�����@���c�V���g�ʂ̓����ł́A���~���̑��ʂ��S�Ē��S�������悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA���Ƃ��O���Ɍ����Č��˂��Ă��A���S���痣��邱�Ƃ͂ł����ɓ��ٓ_�ɗ�������ł����܂��B�܂��A�V�����@���c�V���g�ʂ̂����O���ŊO�����ɕ��o���ꂽ���́A�ʂ���Ȃ��Ȃ�����邱�Ƃ��ł����A���Ԃ��|���āi��������Ac���x�����x�Łj�i�݂܂��B
�@�u���b�N�z�[���́A�펯�ɔ�����V�̂Ǝv���Ă��܂����A���̎��͂Ō����ǂ̂悤�ɓ`��邩�𗝉�����ƁA�ϑ��҂��ǂ�Ȍ��i�����邩�A���ϓI�ɑ����邱�Ƃ��ł��܂��B��ԍ��W���i�P�̎������ȗ������j�Q�����ŁA���ԍ��W��c�{���ċ�ԍ��W�Ɠ����P�ʂŕ\�����Ƃɂ���ƁA�d�͂��Ȃ��ꍇ�A�_����������o�������́A�����_�Ƃ��Ő��̌X����45���̉~���ʂ�i�݂܂��B���̉~�������~���ł����A�u���b�N�z�[���̎��͂ł́A�����d�͂̂��߂ɁA���̉~�����}�P�̂悤�ɂЂ��Ⴐ���`�ɂȂ邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�V�����@���c�V���g�ʂ̓����ł́A���~���̑��ʂ��S�Ē��S�������悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA���Ƃ��O���Ɍ����Č��˂��Ă��A���S���痣��邱�Ƃ͂ł����ɓ��ٓ_�ɗ�������ł����܂��B�܂��A�V�����@���c�V���g�ʂ̂����O���ŊO�����ɕ��o���ꂽ���́A�ʂ���Ȃ��Ȃ�����邱�Ƃ��ł����A���Ԃ��|���āi��������Ac���x�����x�Łj�i�݂܂��B
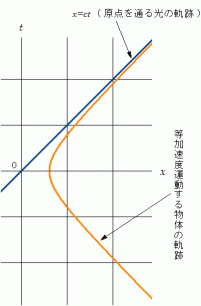 �@�u���b�N�z�[���ɓ��������Ă͂߂�ɂ́A�������x�^��������ϑ��҂��l����Ƃ킩��₷���ł��傤�B���̉����x�ʼn^������ϑ��҂́A�}�Q�̂悤�ɁA�������Ɍ����ɑQ�߂���O�Ղ�`���܂��B���̋O�Ղ́A�}�Q�Ō����� x=ct �̌����ƌ����Č����Ȃ��̂ŁA���̌�����荶�̗̈悩��o�����́A�ϑ��҂ɓ��B���܂���B���������āA x=ct ���A���̐悩��̏��͌����Ă���Ă��Ȃ��u���̒n�����v�ƂȂ�܂��B�������x�^������ϑ��҂��猩��ƁA�w��͏��̒n�����ɋN������ÈłƂȂ�A�S�V�Ɉ�l�ɕ��z���Ă������X�́A�O���ɏW���Ă��܂��B���������ɂ��A�������x�^������ϑ��҂́A���̏d�͉����x�����݂���d�͏�����̊ϑ��҂Ɠ����Ȃ͂��Ȃ̂ŁA�d�͏�����̊ϑ��҂��A�����悤�Ȍ��i�����܂��B���ꂪ�A�u���b�N�z�[�����s�w�ɂ����t�ϑ��҂�������i�Ǝ��Ă��邱�Ƃ́A�����ɂ킩��ł��傤�i�u���b�N�z�[���̒n���ʂ͋��`�����Ă���̂ŁA�S���������i�ɂ͂Ȃ�܂���j�B
�@�u���b�N�z�[���ɓ��������Ă͂߂�ɂ́A�������x�^��������ϑ��҂��l����Ƃ킩��₷���ł��傤�B���̉����x�ʼn^������ϑ��҂́A�}�Q�̂悤�ɁA�������Ɍ����ɑQ�߂���O�Ղ�`���܂��B���̋O�Ղ́A�}�Q�Ō����� x=ct �̌����ƌ����Č����Ȃ��̂ŁA���̌�����荶�̗̈悩��o�����́A�ϑ��҂ɓ��B���܂���B���������āA x=ct ���A���̐悩��̏��͌����Ă���Ă��Ȃ��u���̒n�����v�ƂȂ�܂��B�������x�^������ϑ��҂��猩��ƁA�w��͏��̒n�����ɋN������ÈłƂȂ�A�S�V�Ɉ�l�ɕ��z���Ă������X�́A�O���ɏW���Ă��܂��B���������ɂ��A�������x�^������ϑ��҂́A���̏d�͉����x�����݂���d�͏�����̊ϑ��҂Ɠ����Ȃ͂��Ȃ̂ŁA�d�͏�����̊ϑ��҂��A�����悤�Ȍ��i�����܂��B���ꂪ�A�u���b�N�z�[�����s�w�ɂ����t�ϑ��҂�������i�Ǝ��Ă��邱�Ƃ́A�����ɂ킩��ł��傤�i�u���b�N�z�[���̒n���ʂ͋��`�����Ă���̂ŁA�S���������i�ɂ͂Ȃ�܂���j�B
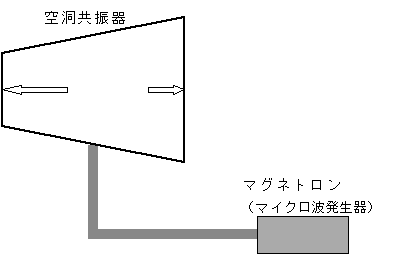 �@���Ƃ��Ƃ́A�C�M���X�̏���ƂɍݐЂ��Ă����Z�p�� Roger Shawyer����2001�N���ɍl�Ă����A�C�f�A�ŁA�}�̂悤�ɗ���ʂ̑傫�����قȂ���U��Ƀ}�C�N���g����͂���ƁA���ꂼ��̒�ʂɍ�p������ˈ����قȂ�͂����Ƃ������̂ł��B�ނ�2008�N�ɍs���������ł́A��ʂ̔��a��16cm��12cm�̋��U���850W�̃}�C�N���g����͂����Ƃ���A�傫����ʂ��珬������ʂɌ�������16�~���j���[�g���̐��͂��������������ł��B�����̓g���f���Ȋw�Ƃ��ĒN���C�ɂ��Ȃ��������̂́A2010�N�ɁA������ Juan Yang ���A�uEM�h���C�u���u��2.45GHz�̃}�C�N���g����͂���ƁA����d��80�`2500W�ɑ���70�`720�~���j���[�g���̐��͂��������v�Ƃ����������ʂ\����������A���ڂ���l�������Ă��܂����B
�@���Ƃ��Ƃ́A�C�M���X�̏���ƂɍݐЂ��Ă����Z�p�� Roger Shawyer����2001�N���ɍl�Ă����A�C�f�A�ŁA�}�̂悤�ɗ���ʂ̑傫�����قȂ���U��Ƀ}�C�N���g����͂���ƁA���ꂼ��̒�ʂɍ�p������ˈ����قȂ�͂����Ƃ������̂ł��B�ނ�2008�N�ɍs���������ł́A��ʂ̔��a��16cm��12cm�̋��U���850W�̃}�C�N���g����͂����Ƃ���A�傫����ʂ��珬������ʂɌ�������16�~���j���[�g���̐��͂��������������ł��B�����̓g���f���Ȋw�Ƃ��ĒN���C�ɂ��Ȃ��������̂́A2010�N�ɁA������ Juan Yang ���A�uEM�h���C�u���u��2.45GHz�̃}�C�N���g����͂���ƁA����d��80�`2500W�ɑ���70�`720�~���j���[�g���̐��͂��������v�Ƃ����������ʂ\����������A���ڂ���l�������Ă��܂����B