
現代的な宇宙論で宇宙の複数性が議論されるのは、次のような論拠があるからです:
-
(1) もっともらしい基礎方程式に複数の宇宙が存在するような解がある。
-
1980年頃まで宇宙論の基礎として使われていた最も単純なアインシュタイン方程式からは、宇宙の複数性は導けません。しかし、素粒子論の知見を元にして真空状態の変化を記述する項などを付け加えると、母宇宙の微小部分がインフレーション的な急膨張を起こして、多数の宇宙が生成されるような解も存在することになります。この他にも、(母宇宙ではなく)われわれの住む宇宙の一部が新たなインフレーションを起こすという理論や、インフレーションとは別のメカニズムで多数の宇宙が生成したり、1つの宇宙が破壊と再生を繰り返したりする理論も提案されています。宇宙全体を記述する基礎方程式として何が正しいのかは、いまだはっきりしていませんが、有力な理論のいくつかが複数の宇宙の存在を支持していることは確かです。
-
(2) 実験および観測データは宇宙の複数性を否定しない。
-
宇宙がいくつも生成されたとしても、個々の宇宙は互いに相互作用をしていないため、「この宇宙」以外の宇宙を直接観測することはできません。ただし、多重生成のしかたによっては背景放射の分布に独特の揺らぎが現れるため、これを元に間接的に検証することは可能です。現時点では、宇宙の複数性は肯定も否定もされていません(一部の科学者は肯定的なデータが見いだされると主張していますが、多数意見ではありません)。
-
(3) 宇宙の複数性を仮定することで説明できる現象がある。
-
われわれが住む「この宇宙」には、素粒子の質量比など少なからぬ点で生命の発生に都合の良いように物理定数の値が定まっています。素粒子論によれば、こうした物理定数の多くは、ビッグバンの直後における真空の相転移がたまたまある形で起きたことによって決まるものであり、その値に理論的な必然性はないとされています。それでは、宇宙はなぜ生命を生み出すためにあつらえられたかのような器であるのでしょうか? この説明として、宇宙はきわめてたくさん存在しており、その中で生命を胚胎しやすい条件が揃った所にのみ知的生命が誕生し、「宇宙はなぜこうなのか」と考えているのだという見方があります。大部分の宇宙は生命の存在しない不毛の世界であるものの、そんな宇宙についてはそもそも認識する主体がいないという訳です。
以上の論拠は、いずれも科学的な学説の当否を決めるにはあまりに薄弱ですが、少なくとも、この問題について議論をしてみる価値があると科学者に感じさせるだけのものは持っています。近い将来に議論が決着することはないにしても、科学者たちは一種の知的挑戦として宇宙の複数性について論じているのです。私自身は、積極的に宇宙が数多く存在するとは主張しないものの、その可能性は否定できないと考えています。
一方、「この宇宙」とは全く異なる世界については、議論のきっかけになるようなかすかな論拠すら見いだされていません。時間と空間の枠組みを超越するような理論を提案できれば話が始まるのですが、今の段階では、科学者が取り組むだけの条件が整っていないと言わざるを得ません。
【Q&A目次に戻る】

こうした問題は、推測ではなく実際に計算してみることが大切です。シリウスからやってくる光について、数値を入れてみましょう(それぞれの数値は、ネットで検索すれば簡単に調べられます)。
シリウスは連星ですが、そのうちの明るい方(シリウスA)の絶対等級は1.47です。絶対等級mは天体を仮に地球から32.6光年の距離に置いたときの見かけの等級で、細かな補正を別にすれば、天体が放射する全エネルギーFの対数の1次関数として表されます。式で書けば、
m = -2.5 log F + (定数)
あるいは、
F = 10
-m/2.5×(定数)
となります。太陽の絶対等級は4.8なので、シリウスは、太陽の 10
(4.8-1.47)/2.5 ≒ 21.5 倍 のエネルギーを放出していることがわかります。太陽の放出エネルギーは、3.9×10
26 [W] であり、そのうちの47%が可視光線です。シリウスにおける可視光線の割合を厳密に求めるにはプランク分布を考慮しなければなりませんが、ここでは、話を簡単にするために、シリウスでも放出エネルギーの約50%が可視光線だとしましょう。すると、シリウスが放出する可視光線のエネルギーは、
3.9×10
26 [W]×21.5×0.5 ≒ 4×10
27 [W]
と求められます。
ここで、光量子論の仮定を使いましょう。光量子論では、波長がλのとき、光子1個当たりのエネルギーが hc/λ で与えられます(h はプランク定数、c は光速)。理論的には必ずしも正しくないのですが、細かなことを言わずに、放出エネルギーを光子1個当たりのエネルギーで割ることで、光子数を定義しましょう。可視光線の波長は0.4〜0.7μm ですが、桁がどうなるかを知りたいだけなので、0.5μm と置いてしまいます。 このとき、光子1個当たりのエネルギーは、
6.6×10
-34[kg m
2/s]×3.0×10
8[m/s] / 0.5×10
-6[m] ≒ 4×10
-19[kg m
2/s
2]
なので、1秒間に放出される光子数は、
4×10
27 / 4×10
-19 = 10
46[個]
と求なります。
この膨大な数の光子は、シリウスを中心に四方八方に飛び散っていきます。シリウスから地球までの距離Rは、8.6光年 ≒ 8×10
16mです。シリウスから見ると、地球上にいる人間の瞳孔など無限小に思えるかもしれませんが、きちんと計算できます。瞳孔の半径rは約1.5mmなので、全天に占める瞳孔の割合は、瞳孔の面積(πr
2)を半径Rの球の表面積(4πR
2)で割った値、すなわち、
πr
2 / 4πR
2 ≒ (1.5×10
-3)
2/4×(8×10
16)
2 ≒ 10
-40
です。シリウスから地球までの間に光子が吸収されないとすると、1秒間に放出される10
46個の光子のうち、10
6個が地球上にいる人間の目に飛び込んでくることになります(実際には、大気中で何割かが吸収されます)。網膜の感度からすれば、これは感知するのに充分な個数です。だからこそ、夜空にシリウスがくっきりと見えるのです。
【Q&A目次に戻る】

ダークマターが不均一な分布をしている場合、重力レンズ効果のせいで楕円銀河の長軸の向きに見かけ上の偏りが生じます。ここからダークマターの質量分布を推定することが可能になります。
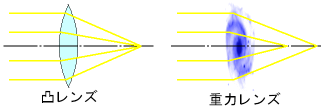
まず、重力レンズについて簡単に説明しておきましょう。重力レンズ効果とは、一般相対論の効果で重力源の周囲の空間が歪むために光線の方向が曲げられることで、屈曲の向きは凸レンズと似ています。ただし、凸レンズの場合、レンズの周辺部に入射した光線を中心付近の光線よりも大きな角度で曲げるために、レンズ軸に平行な光線を1点に集める作用があるのに対して、典型的な重力レンズでは、中心付近よりも周辺の方が重力が弱いので屈曲角が小さくなります。この結果、重力レンズによる像は、ビンの底を通して何かを見たときのようにゆがんでいます。Strong lens 効果と呼ばれる強い作用の場合、球形の天体(銀河や星)が複数個に分裂したり、アーク状やリング状に変形して見えます。それほど重力が強くないときでも、球形の天体は重力源に対して円周方向に伸びたようにゆがむことになります(Weak lens 効果)。
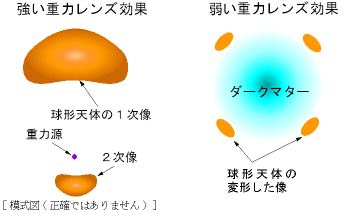
ダークマターが集中している領域の周囲に球形の銀河が存在する場合、重力レンズ効果のせいで、これらは長軸が円周方向に向いた楕円のように見えます。従って、ある領域で楕円形をした銀河の長軸が一方向に揃っているときには、近くの重力源による重力レンズ効果である可能性があります。たとえ、もともと(重力レンズの変形を受ける前から)楕円体または円盤状の銀河だったとしても、この場合の長軸方向の分布はランダムで偏りがないと考えられるので、もし分布に偏りが観測されるとすれば、重力レンズ効果の現れだと推測できます。
実際の観測では、銀河の長軸方向の分布に関して空間的な相関を調べ、広い範囲で見るとランダムに分布しているのに狭い範囲では一方向に偏っているように見える領域を探し出します。その上で、こうした偏りを生み出すような質量分布を計算し、それに対応する天体が光学的に観測できないときは、目に見えないダークマターが存在すると仮定します。このようにして求めたダークマターの分布はかなり不均一であり、宇宙は、ダークマターまで含めても、質量が少ない空洞領域が至る所に存在するスポンジのような構造をしていることになります(こうしたデータは、2000年に複数のグループによって発表されました)。ただし、重力レンズ効果に基づく議論は、まだ不確定要素が多く信憑性に欠けるため、他のデータと突き合わせて整合性を検討している段階です。
【Q&A目次に戻る】

多くの鳥は仲間の鳴き声を模倣する習性があります。人工的な環境で飼育されている九官鳥が人間の言葉を真似するのも、この習性の現れです。
九官鳥の鳴き方に関する論文は見つかりませんでしたが、カナリアの囀りに関する研究は良く知られています。カナリア(及びその他の鳴く鳥)の囀りは、シラブル(音節)と呼ばれる音のユニットを一定の方式で連ねるようにして構成されています。カナリアの場合、持続時間と周波数変調の異なるいくつものシラブルを生まれつき身につけており、あるシラブルを何回も繰り返すことで1つのフレーズを作り出しています。フレーズのパターンは、主に仲間の囀りの模倣を通じて身に付けることが判明しています。ただし、仲間から引き離して単独で育てた個体でも、パターン数が少なく単調ではあるものの野生の個体と似たフレーズを囀るようになるので、部分的には遺伝的要素が絡んでいると思われます。
カナリアの学習能力を調べるために、生後25日の幼鳥を仲間から引き離して自然界にはないフレーズ(例えば、シラブルの音程が連続的に低くなるグリッサンドのようなフレーズ)を2時間おきに繰り返し聞かせる実験を行ったところ、過半数の幼鳥がこれを模倣した囀りを行うようになり、一部の個体は成熟後も人工的なフレーズを持つ囀りを維持したという報告があります。同様の学習能力は、ダーウィンフィンチやヌマウタスズメでも報告されており、フレーズの模倣は多くの鳥に共通する性質だと言えます。
囀りは、主にテリトリーを主張したり交尾相手を呼び寄せたりするために繁殖期の雄が行うものであり、同じ地域に生息する同一種ではフレーズが共通している方が(差別化を図れるなどの点で)好都合なので、仲間のフレーズを模倣する学習能力が備わったのだと推測されます。同様の学習能力は、鳴き声をコミュニケーションに利用する鳥にも見られます。一般的に言って、どのようなシラブルが利用可能かは発声器官の構造によって決まりますが、シラブルをいかに組み合わせてフレーズを作るかは、模倣を中心とする学習によって後天的に獲得されるという訳です。
野生の九官鳥は、森林で小規模な群れを作って生活しています。仲間同士で鳴き交わしによるコミュニケーションが行えるように肉厚で自由に動かせる舌が発達しており、カナリアやスズメよりも多くのシラブルが利用可能です。鳴き方のパターンはかなり複雑であり、囀り声(whistles)、泣き叫ぶような声(wails)、金切り声(screeches)、のどを鳴らすような声(gurgles)を組み合わせています。こうした鳴き方のパターンは模倣を通じて身に付けると推定されており、同一グループに属する九官鳥が同じような鳴き方をするのに対して、空間的に隔たった地域に生息する個体同士では鳴き方に共通性がないとのことです。
人間に飼育されている九官鳥は、仲間と鳴き交わすことのない環境で育てられているため、鳴き方を模倣する習性が人間や動物の声などに対して適用されることになります。フレーズを模倣する鳥は他にもいますが、九官鳥は舌が厚く人間の声に近いシラブルを操ることができるので、人語を喋っているように感じられるのです。
【参考文献】T. J. Gardner et al., 'Freedom and Rules: The Acquisition and Reprogramming of a Bird's Learned Song,' Science 308 (2005) 1046、英語版 Wikipedia より "Hill Myna" の項
【Q&A目次に戻る】
 下の回答
下の回答の追加としてお答えします。
物理学的な因果律が成立していない場合、未来の状態は過去の状態によって完全に定まっていないことは確かですが、これは必ずしも「未来が決定されていない」ことを意味しません。「過去と未来は実在せず、ただ現在だけが存在する」という立場からすると、因果律によって規定されていない未来は不確定になります。しかし、相対論を全面的に信頼するならば、時間は空間と同じように拡がりであり、現在と同じように過去及び未来も存在するはずです。この場合、(量子論的な非因果性の帰結として)未来は過去に完全に束縛されていないにもかかわらず、未来が過去と同じように決定されていると考えても、何の矛盾もありません。例えば、観戦しているサッカーの試合でどちらのチームが勝利するか、現在の物理的状態だけでは決定できない(つまり、現在においては決定されていない)としても、2時間後の未来においては確定しているはずです。この「2時間後の未来」を、空間的に遥か隔たった地点と同じように「存在しているがアクセスできない」領域と見なせば、試合の勝敗は「未来における事実として決定している」と解釈されます。こうした「非因果的な決定論」については、哲学の分野でも充分に議論されてはいませんが、1つの明確な主張だと言えるでしょう。
【Q&A目次に戻る】

「因果」はもともと仏教用語で、原因と結果の結びつきを表す概念として用いられます。「因果律」とは原因と結果の結びつきに法則性があるというもので、「ある結果が起きるのには必ず原因がある」「原因は結果に先んじる」といった解釈が一般的だと思います。
ただし、物理学で言うところの「因果律」は、こうした一般的な解釈とは少し異なっています。物理学的な因果律とは、「ある時刻での状態が与えられれば、それ以外の時刻での状態が完全に定まる」というもので、物理的な過程が原因と結果という具体的な出来事に分節されるとか、原因は結果より前に起きるといった内容は含んでいません。
物理学的因果律の簡単な例として、放物運動を考えましょう。一様な重力場の中で放り投げられた物体は、放物線を描く運動を行います。ここで、放り投げた直後の物体の位置と速度を与えると、その後、どのような軌道を描くかが完全に決定されるので、この位置と速度を初期条件と呼び、しばしば「軌道は初期条件によって決定される」という言い方をします。しかし、実は、軌道を決定するのに必要な位置と速度は、運動の途中であってもかまわないのです。どの時刻であろうと、そのときの位置と速度さえ与えられれば、初期条件を含めて他の全ての時刻の位置と速度が一意的に決定されます。このように、ある時刻の運動状態(質点運動の場合は位置と速度)を与えると他の全ての時刻の状態が定まるとき、「物理学的因果律が成り立つ」と言います。ニュートン力学は、物理学的因果律が厳密に成り立つ理論体系です。
電磁場のように空間のあらゆる場所で値を持つ量に関しては、ある時刻における全空間での状態(場の強度とその時間微分)が与えられると全時刻・全空間での状態が定まることが、物理学的因果律が成立する条件です
(*1)。電磁場の状態変化を記述するマクスウェル電磁気学でも、ニュートン力学と同じく物理学的因果律が厳密に成り立っています。
(*1)細かいことを言うと、必ずしも全空間での状態が与えられる必要はありません。物理的な作用は光速以下のスピードでしか伝播しないので、有限な空間領域に作用を及ぼし得る範囲は限られます。ある時刻においてこの範囲内の状態が与えられれば元の空間領域の状態が完全に決定される場合、物理学的因果律が成り立っています。また、話をわかりやすくするために「ある時刻における状態」と言っていますが、正確に言えば「時刻」ではなく「空間的超平面」です。以上の注意は、無限遠の状態を考えるときに重要になります。
ニュートン力学やマクスウェル電磁気学で物理学的因果律が成立しているのは、これらの理論が、コーシーの境界条件に対して一意的な解を持つような微分方程式で記述されるからです。ある時刻の状態を境界値とする解がただ1つだけ存在するならば、その解によって全ての時刻の状態が表されることになり、物理学的因果律の条件が満たされる訳です。原子から構成されている物質を連続体で近似する連続体力学では(近似が破綻するせいで)物理学的因果律が成立しなくなる場合もありますが、ニュートン力学やマクスウェル電磁気学のような古典物理学の基礎理論では、一般に物理学的因果律が成り立っています
(*2)。
(*2)アインシュタインの一般相対論も古典物理学に含まれますが、ブラックホール特異点を含む領域では、特異点に落ち込んだ情報が完全に消滅してしまうので、(未来の状態から過去の状態が決められるという)厳密な物理学的因果律は成り立っていません。また、時間が過去から未来へと1次元的に伸びているのではなく、未来から過去に戻るようなループ状の時間軸が形成された場合に因果律がどうなるかは、良くわかっていません。
量子力学になると、古典物理学と異なって厳密な物理学的因果律は成立しません。これは、量子系には量子ゆらぎと呼ばれる非因果的なゆらぎが存在するからです。
量子ゆらぎが存在すると、古典物理学のように物理量の値を確定することができません。質点運動の場合、位置と速度の量子ゆらぎが共にゼロになるような状態は、原理的に存在しないことが示されています。電磁場に関しても、場の強度に量子ゆらぎが現れます。ニュートン力学やマクスウェル電磁気学でも、位置と速度のような境界値が確定していなければ微分方程式の解を1つに限定できませんが、量子力学の場合も同じく、物理量の不確定性のために一意的な時間変化を求めることができません。ただし、古典物理学の場合、こうした非因果性は、境界値を確定できない人間の無知に由来すると見なされるのに対して、量子力学では、量子ゆらぎを持つ物理的なシステムそのものの性質だと考えられています。通常の量子力学の定式化では、量子ゆらぎを含む状態を定義するのに波動関数が用いられます。波動関数の時間変化はシュレディンガー方程式で与えられますが、この方程式は物理的な状態の時間変化を正確に記述するものではなく、現実の状態とシュレディンガー方程式の解はずれていきます(シュレディンガー方程式の解は何を表しているのかという「解釈問題」には、ここでは踏み込みません)。ほとんどの物理学者は、こうした非因果的な振舞いは物理の本質であり、いつか量子力学を超える因果的な理論が構築されるとは考えていません。
物理学的因果律の不成立は、哲学的観点からすると受け容れやすい性質ではないかと思います。実際、今日の夕食に何を食べるかもビッグバンの瞬間に既に決まっていたというのは、あまり面白い話ではありません。古典物理学では、ある時刻の状態に対して(グリーン関数によって定義される)積分変換を施すことによって別の時刻の状態を表わせますが、これは取りも直さず、時刻の違いは単に数学的な表現の違いにすぎないことを意味します。つまり、物理学的因果律が厳密に成り立っている場合、そもそも時間軸というものが物理的に存在しているとは言えないのです。そんな奇矯な解釈をするよりも、物理学的因果律は成立していないと考えた方が、はるかに素直な世界観ではないでしょうか。
【Q&A目次に戻る】

一定周期で大量発生する「周期ゼミ」がいる理由は進化論的に説明されていますが、その周期がなぜ13年または17年という素数になるのか、もっともらしい理論が提唱されてはいるものの、明確な結論が出ている訳ではありません。
卵から孵化したセミの幼虫は、通常、2〜8年間を地中で過ごします。天敵の少ない地中で木の根から樹液を吸って徐々に成長、充分に大きくなったところで地上に姿を現して羽化し、短期間で交尾を行って一生を終えます。ほとんどのセミが毎年羽化するのに対して、周期ゼミは同じ時期にいっせいに羽化するという特徴があります。北米に生息する100種類以上のセミのうち、4種類が13年周期、3種類が17年周期の周期ゼミです。同じ年に羽化する周期ゼミは、ブルードというグループに分類されます。17年ゼミには12のブルードがあるので、17年間のうち12年はいずれかのブルードがどこかで羽化していますが、各ブルードは異なる生息地に棲み分けをしているので、ある地区だけ見ると、17年ごとにいっせいに17年ゼミが現れることになります。
周期ゼミが生存競争で有利になる理由は、次のように説明できます。北米大陸は、東南アジアや中南米に比べてセミが生息するには厳しい環境であり、もともとセミの個体数はあまり多くありません。緯度が高く根から摂取される樹液の養分も不十分なため、羽化可能な大きさまで成長するのに年数も掛かります。こうした環境では、バラバラに羽化すると1匹だけ目立ってしまい、鳥やスズメバチなどの天敵に狙われやすくなります。また、交尾できる確率も低下します。そこで、いっせいに羽化することによって、数で圧倒して集団を守り、併せて交尾の確率を高めているのです。ふつうの昆虫ならば、個体数の増加に対応して捕食者の数も増えるはずですが、セミは交尾する短期間だけ地上に現れ、その後はすぐに姿を消すので、捕食者が増える間がないのです。この時期をはずれて羽化した個体は子孫に遺伝子を残せないため、羽化がシンクロナイズする遺伝子集団だけが自然選択されることになる訳です。
このように、セミが一定の周期でいっせいに羽化する現象は進化論によって説明可能です。それでは、その周期が13年、17年という素数になる理由は何なのでしょうか? 吉村仁は著書『素数ゼミの謎』の中で、周期が素数ならば交雑が起こりにくくなることを指摘しています。例えば、12年ゼミ、13年ゼミ、15年ゼミという3種類の周期ゼミが同一の地域に生息していた場合、12年ゼミと15年ゼミは60年に1回同じ時期に羽化して交雑が生じますが、13年ゼミは、12年ゼミとは156年に1回、15年ゼミとは195年に1回しか交雑しません。異なる遺伝子を持つセミが交雑すると、孵化率が低下するなどの不都合が生じたり、周期が乱れていっせいに羽化することによるメリットが享受できなくなったりするため、繁殖率が低下すると考えられます。たとえ当初は同じ個体数でスタートしたとしても、12年ゼミと15年ゼミの繁殖率が低下して個体数が減り始めると、13年ゼミは、他のセミとの生存競争において圧倒的に有利な立場を獲得します。
交雑が起きるとき少しでも数が多い方が圧倒的に有利になる理由は、数字を使った簡単な考察からわかります。100匹のセミが生息できるだけのキャパシティを持つ環境があったとしましょう。ここに、60匹の13年ゼミ(オス30匹、メス30匹))と40匹の15年ゼミ(オス20匹、メス20匹)がいて、同時に羽化したとします。すると、30匹いる13年ゼミのメスのうち40%の12匹は15年ゼミのオスと交尾するので、13年ゼミの純血種を残せるのは18匹のメスだけとなります。一方、20匹の15年ゼミのメスのうち、純血種を残せるのは40%の8匹だけです。仮に交雑で生まれた卵が全て孵化せず、純血種の卵だけが孵化して100匹というキャパシティを満たすとすれば
(交雑によって生まれた生存率の低い個体が生息環境の一部を占める可能性は無視します)、その内訳は、18匹のメスが産んだ13年ゼミの卵と8匹のメスが産んだ15年ゼミの卵からの幼虫(数の内訳は69匹と31匹)となるはずです。つまり、交雑前は 3:2 だった比が交雑後は 9:4 に変化し、15年ゼミは13年ゼミの半分以下に減っているのです。このように、1回の交雑ごとに個体数は2乗に比例して変化するため、数が少ない方は急速に淘汰されていきます。
吉村は『素数ゼミの謎』の中で、現存する周期ゼミの羽化周期は前回の氷河期の際に固定されたものであり、その値は、北米南部ではもともと12〜15年、北米北部では14〜18年だったが、周期が素数のもの以外は淘汰されたと推測しています。これが、周期ゼミの中で13年ゼミと17年ゼミだけが現存する理由だ−−と言えそうにも思えますが、どうでしょう。
この推測はいかにももっともらしいのですが、1つ気になります。なぜ、もともとの羽化周期を、南部で12〜15年、北部で14〜18年と推測したのでしょうか? これらの数値からは、素数の11と19が除かれています。素数の羽化周期を持つセミが生存競争で有利になるとするならば、なぜ11年ゼミや19年ゼミが存在しないのか、説明できなければなりません。もちろん、11年ゼミの方が13年ゼミより交雑による繁殖率低下の影響を受けやすいのは確かですし、19年も土中にいるとモグラに食われたり菌類に寄生されたりするリスクが高まるので19年ゼミより17年ゼミの方が有利なのかもしれませんが、それにしても仮説の検証は必要です。
そもそも、13年ゼミと17年ゼミが生き残ったのは単なる偶然だと考えることも、無理ではありません。仮に羽化周期に関する吉村の推測が正しいとして、南部では周期12〜15年という4種の周期ゼミのうちの1種だけが、北部では同じく5種のうちの1種だけが偶然に生き残ったとします(似た生物が同一の環境内に複数生息する場合、個体数のランダムな変動を経て1種だけが生き残るという過程は、自然界にしばしば見られることです)。このとき、生き残ったのが他でもなく13年ゼミと17年ゼミである確率は、1/4×1/5=1/20、すなわち5%となります。実は、確率5%というのは、偶然か偶然でないかのボーダーとされる数値です。確率1%未満なら「偶然ではない」と言ってもかまわないでしょうが、確率5%の出来事が偶然に起きるというのは、良くあることです(厳密に言うと、これは母集団として何を考えるかという問題であり、北米の周期ゼミ以外に周期性を持つ生物がどれほどいるかを議論しなければなりません)。13と17という素数に幻惑されて、ありもしない原因を探し出してしまった可能性もないとは言えません。
素数ゼミに関する科学的な結論を導くためには、セミが土中に留まる期間と気候の相関関係や、交雑したときの繁殖率の低下などについて、より定量的に解明する必要があります。とは言っても、セミの生態自体が必ずしも明らかにされていないので、結論が出るまでにはまだ時間が掛かりそうです。
【参考文献】吉村 仁 著『素数ゼミの謎』(文藝春秋)
【Q&A目次に戻る】

雷光(稲妻)がどのようにしてジグザグに進んでいくのか、まだ完全に解明できたわけではありませんが、次のような仮説が提唱されています。
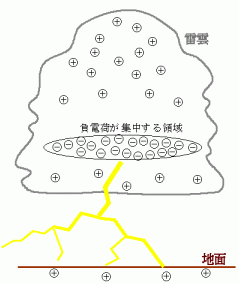
急激な上昇気流によって形成される積乱雲のような雷雲では、通常、雲の上部がプラスに、下部がマイナスに帯電するとされています(帯電のメカニズムに関しては、
別の回答に説明があります)が、より詳しく見ると、単純な2極構造ではなく、地上から約6kmの高度に負電荷が集中的に集まる領域があり、その上下に正電荷が広く分布するという3極構造になっています。雷雲内部の電荷分布を考えると、負電荷領域の境界部分で最も電位差が大きくなるはずであり、この場所で雷放電の最初のステップが始まると考えられています。
ここで重要なのは、気球や航空機による観測で測定された電位差がせいぜい20万ボルト/メートルで、空気の絶縁破壊を起こすほど大きくないという点です。つまり、雷とは、巨大な電位差で絶縁が破れていきなり放電するという現象ではないのです。かなり信憑性の高い仮説によれば、まず、宇宙線などによって気体分子から電子が弾き出され、これが負電荷領域の境界付近に生じている電場によって加速されていきます。こうして光速の数%以上で運動するようになった電子が、さらに他の気体分子に衝突して次々と電子を弾き出し、電子の数が指数関数的に増大するという「電子なだれ」が起きて、大量の電子の流れが始まります。この電子流自体は、そう長く持続しません。高速になった電子はほぼ直進しますが、雷雲内部やその周辺の電場は複雑に変化している上に、電流によって電位差が中和されるため、何十メートルか進んだところで電子の流れはいったん終息します。しかし、電子流の先端部には電子が集まってくるので、これが(自身が誘起したものも含む)周辺電場に加速されて再び高速の電子の流れを作ります。こうした過程が繰り返され、結果的に、ジグザグに進む断続的な電子流の連なりとなります(ただし、ジグザグの経路が形成される具体的なメカニズムは明らかではありません)。これが先駆放電と呼ばれるものです。この断続的な電子流が通った道筋は、イオン化された気体分子と電子がふんだんに存在して電流が流れやすくなっており、一種の導線の役割を果たします。この“導線”が地面の近傍に達すると、その瞬間に雷雲と地面が短絡(ショート)したことになり、ジグザグになった先駆放電の道筋に沿って帰還雷撃と呼ばれる大量の電流が流れます。この大電流によって加熱された気体が発する可視光が雷光であり、気体が膨張して発生する音が雷鳴です。
もっとも、現実に起きている雷は、上の単純化した説明では捉えきれないほど複雑です。稲妻の大部分は雷雲と雷雲の間で生じていますが、その中には、空中でくるりと宙返りするような形のものも観察されています。こうした奇妙な放電路が形成される理由は、良くわかっていません。
【参考文献】J.R.ドワイヤー「稲妻から出るX線を追え」(日経サイエンス 2005年8月号 p.48)
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
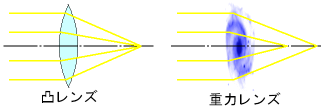
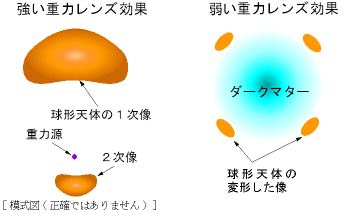 ダークマターが集中している領域の周囲に球形の銀河が存在する場合、重力レンズ効果のせいで、これらは長軸が円周方向に向いた楕円のように見えます。従って、ある領域で楕円形をした銀河の長軸が一方向に揃っているときには、近くの重力源による重力レンズ効果である可能性があります。たとえ、もともと(重力レンズの変形を受ける前から)楕円体または円盤状の銀河だったとしても、この場合の長軸方向の分布はランダムで偏りがないと考えられるので、もし分布に偏りが観測されるとすれば、重力レンズ効果の現れだと推測できます。
ダークマターが集中している領域の周囲に球形の銀河が存在する場合、重力レンズ効果のせいで、これらは長軸が円周方向に向いた楕円のように見えます。従って、ある領域で楕円形をした銀河の長軸が一方向に揃っているときには、近くの重力源による重力レンズ効果である可能性があります。たとえ、もともと(重力レンズの変形を受ける前から)楕円体または円盤状の銀河だったとしても、この場合の長軸方向の分布はランダムで偏りがないと考えられるので、もし分布に偏りが観測されるとすれば、重力レンズ効果の現れだと推測できます。
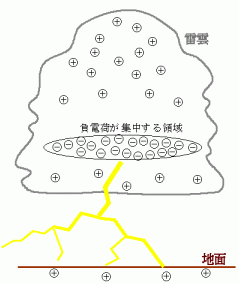 急激な上昇気流によって形成される積乱雲のような雷雲では、通常、雲の上部がプラスに、下部がマイナスに帯電するとされています(帯電のメカニズムに関しては、別の回答に説明があります)が、より詳しく見ると、単純な2極構造ではなく、地上から約6kmの高度に負電荷が集中的に集まる領域があり、その上下に正電荷が広く分布するという3極構造になっています。雷雲内部の電荷分布を考えると、負電荷領域の境界部分で最も電位差が大きくなるはずであり、この場所で雷放電の最初のステップが始まると考えられています。
急激な上昇気流によって形成される積乱雲のような雷雲では、通常、雲の上部がプラスに、下部がマイナスに帯電するとされています(帯電のメカニズムに関しては、別の回答に説明があります)が、より詳しく見ると、単純な2極構造ではなく、地上から約6kmの高度に負電荷が集中的に集まる領域があり、その上下に正電荷が広く分布するという3極構造になっています。雷雲内部の電荷分布を考えると、負電荷領域の境界部分で最も電位差が大きくなるはずであり、この場所で雷放電の最初のステップが始まると考えられています。