
多くの初等的な物理学の教科書では、ローレンツ変換の公式を、「相対性原理」と「光速度不変の原理」という2つの前提から導いています。このうち、相対性原理の方は、力学の幾何学化に相当するものです。物体の運動を「動いている」「止まっている」といった力学的な概念ではなく、時空内部の軌道(trajectory)──あるいは世界線──という幾何学的な概念で表し、軌道を決定する力学法則は座標系に依存しないものと仮定されます。ただし、相対性原理(あるいは4次元幾何学)だけでは、相対性理論を構築することはできません。もう1つ、何らかの前提を要請することによって、はじめて変換公式を含む理論体系が与えられるのです。1905年の論文でアインシュタインが掲げ、現在でも多くの教科書で採用される「光速度不変の原理」は、あくまでヒューリスティック(発見法的)な議論を行うために要請されるものであり、いささかアドホックな仮定です(実際、光速度が一定にならないにもかかわら相対論的である理論が、いくつも提案されています)。ローレンツやポアンカレは、「マクスウェル方程式を不変にする」という前提の下で変換公式を導いていますが、マクスウェル方程式を特別扱いする物理的な根拠はありません。「物理的な伝達速度には、全ての慣性系で共通する最大値がある」とすると、かなり一般的になりますが、何を言っているのかわかりにくいのが問題です。
形式的には、こうした物理的な議論をするよりも、数学的な前提から出発して体系化した方が、すっきりします。まず、「世界は4次元(より一般的にはn次元)多様体である」と宣言し、その上で天下り的に、「この世界においては、標準形で
Q(
x) = -(x
0)
2 + Σ(x
k)
2
と表される2次形式で計量が与えられる」とすれば、後は数学的な議論だけで、相対性理論を構築することが可能です(線形性は計量の定義に含まれています)。例えば、因果律が成り立つならば、物理的な現象は Q=0 で与えられる“円錐面”の外側に伝わることがないので、「全慣性系に共通の最大速度がある」という性質が導けます。さらに、光がこの速度で伝播すると仮定すれば、光速度不変性が得られます。計量を用いた数学的な前提が原理的なのか、これとは別の物理的な原理を要請すべきかは、現在の科学的知見の範囲では、何とも言えません。議論の出発点に何を採用するかは、科学者・教育者のセンスないし好みにまかされています。
【Q&A目次に戻る】

「
時間に関する5つの問題」の4番目──未来は決まっている──という結論は、以下のような考えから漠然と未来は決まっていないのだろう信じていた私にとっては大変ショックでした。どこが妥当でなかったのかご指摘いただけないでしょうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
熱湯と氷が入っていたグラスを、十分な時間放置した後にできたぬるま湯の状態をAとします。これに対して、個々の“粒子”の位置は全く同じで運動量だけが反対の状態をA
-1とします。ここでもし未来が一意的に決まっているなら、Aは際立った変化を示さないでしょうけれど、A
-1は、均質化の仮定を全く逆に辿って、やがて熱湯と氷に分離するにちがいありません。
Aは決して特別なぬるま湯ではなく、他のどうでもいいぬるま湯ともはや本質的に区別はできないはずです。したがってA
-1の状態もまた、Aと等しい確率で実現されることが期待できます(極言すれば、ぬるま湯のうち半分はAで残りの半分はA
-1であるべきです)。
にもかかわらず、「ぬるま湯を観察していたら熱湯と氷に分離した」という経験はありませんし、人からもあまり(というか全然)聞いたことがありません。これは、未来が一意に決まっているのではなく、A
-1から再び熱湯と氷が形成されることが滅多に起こらないためなのではないでしょうか?【古典物理】

私が「未来は決まっている」と書いた根拠は、相対性理論において、時間が空間と同等の“拡がり”として扱われていることです。過去・現在・未来の区別もありません。従って、未来は、過去が「決まっている」、あるいは、山の向こうに何があるか「決まっている」のと同じように、「決まっている」と考えられるのです。質問にあるのは、「こうした時空の中で、変化の向きが決まっているのはなぜか」という(私の主張とは別の)問題ですが、これはこれで興味深いテーマなので、ここでお答えしたいと思います。
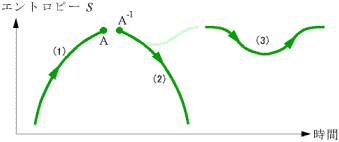
「熱湯+氷」の状態と「ぬるま湯」の状態を区別する良く知られた指標が、エントロピーSです。ごく単純化して言えば、エントロピーはシステムの乱雑さを表す量であり、「熱湯+氷」は(個々の水分子に分配されるエネルギーが均一ではなく大きな偏りがあるために)エントロピーが低い状態で、「ぬるま湯」はエントロピーが高い状態です。時間とともにエントロピーがどのように変化するかグラフに描くと、「熱湯+氷」から「ぬるま湯」の状態Aに変化する過程は(1)の軌道で、Aを時間反転した状態A
-1から「熱湯+氷」に変化する過程は(2)の軌道で表されます。(1)のタイプの軌道と(2)のタイプの軌道は、さまざまな初期条件に対する運動方程式の解として同じ数だけ存在するので、
水分子の運動が原理的に可能な過程の中からデタラメに選ばれるとすると、両者は同じ確率で実現されるはずです。
しかし、現実に、(2)で表されるような変化が実現されることはありません。実は、エネルギー一定という条件下で実現可能な過程の圧倒的多数は、AでもA
-1でもなく、エントロピーの高い「ぬるま湯」の状態付近をウロウロしているだけでなのです
(厳密に言えば、「有限時間の範囲で」という条件が付きます)。ごくまれにエントロピーが低い状態に移行する軌道があっても、その大多数は、(3)のようにすぐに高エントロピー状態に逆戻りするものです。A
-1に限りなく近い状態であっても、運動量にほんのわずかのずれがあるだけで、途中から(2)のそばを離れ、(3)タイプのエントロピー増大の軌道に転じるのです(薄い色で描いた軌道)。(2)の過程が実現することは、確率的に見て、ほとんどありません。
それでは、確率的には(2)と同程度に生起しにくい(1)タイプの過程が実現するのは、なぜでしょうか。その理由は、宇宙開闢の瞬間が、途轍もない低エントロピー状態になっていることにあります。宇宙の始まりに関する理論は、ホーキングらの努力にもかかわらず未完成ですが、おそらく初期宇宙は揺らぎのない完璧な世界であり、そのエントロピーは、理論的な最低値に近い値を取ると思われます。この結果、世界で生起する大多数のプロセスは、時間軸上で初期宇宙に近い側(便宜的に「過去」と呼ばれています)のエントロピーが低くなるような(1)のタイプの軌道を描くことになるのです。ビッグバンとともに宇宙が始まって約100億年が経過していますが、熱力学的に見た宇宙の寿命は10
40年──100億年の100億倍の100億倍の100億倍──程度になるとの説もあるので、現在は、まさに宇宙開闢の“直後”であり、宇宙全体のエントロピーはまだまだ低く、そこかしこでエントロピーが急増する過程が繰り広げられているのです。
【Q&A目次に戻る】

各元素の原子量は、IUPAC(国際純正および応用化学連合)の原子量委員会で表にまとめられていますが、その値には、測定誤差とは別の不確定な部分が残されています。例えば、炭素Cの原子量は 12.0107(8) と記されており、有効数字の最後の桁に括弧内の数字程度の不確かさがあることが示されています。この不確かさの原因は、表の前に次のように説明されています。
The atomic weights of many elements are not invariant, but depend on the origin and treatment of the material.
( "not invariant" は「不変でない」というより「一定でない」と訳した方が良いと思います)
入手可能な元素の試料は、通常は、いくつかの同位体が混じったものです。炭素の場合、 C
12 だけから成るならば、原子量は(定義により)12のはずですが、C
13 が1%ほど混じっているため、 12.01… という数値になっています。問題は、この同位体組成が必ずしも一定でない点です。IUPAC原子量委員会が与えている数値は、「地球起源で天然に存在する物質中の元素」のものですが、それでも、炭素、水素、酸素など多くの元素では、地球上の物質の同位体組成に違いがあり、不確定さをなくすことが困難です。
化学反応に関してほとんど差のない同位体の組成が変動するのは不思議に思われるかもしれませんが、質量が異なるために、物理的な振舞いに差が生じ、結果的に同位体の含有量が変わってくるのです。例えば、地球上の水循環の過程において、水分子の質量数の差によって蒸発や凝結の速度に違いが生じるため、海水温や気象条件によって、水素・酸素の同位体組成が変動することが知られています。
このほか、人為的な原因によっても同位体組成が変動します。塩素やウランの場合、市販の試料の中に、同位体分別が不適切で同位体組成が変動した物質が見つかることがあるそうです。
【Q&A目次に戻る】

視覚や聴覚は、もともと、自然環境の中で生存に有利になるような情報を得るために特化された器官です。このため、人間が文化的・社会的な活動を行うのに必要な情報を的確に集めるとは限りません。
視覚データに基づく情報処理では、比較的単純なパターン・マッチングを通じて、特徴を抽出する作業が行われます。例えば、相似形のまま次第に大きくなる対象を見いだした場合、(両眼視差など他のデータとも照らし合わせた上で)空間的に近づいてくる物体として認知する傾向があります。また、丸い点が2つ並んでいるときに、動物や人間の目のように見えることがあり、心霊写真の錯覚を生む元になっていますが、これは、本来、夜間に目を光らせて動き回る捕食動物を把捉するために役に立つ能力です。知的に成熟した人間は、パターン・マッチングを行うための型(テンプレート)をきわめて多数用意しており、これを使って、例えば、群衆の中から簡単に知人を見つけることができます。しかし、テンプレートに合致しないような視覚データが入力されると、適切な特徴分析ができず、重大な内容を見落とすことも少なくありません。通り魔殺人のような異常な事態に直面した人が、核心となる場面の映像的な記憶を欠いていることがあるのは、そのためです。
聴覚も、もともとは、枝を踏みしめる音や鳴き声などの音声パターンを分析して、状況判断に必要な情報を取得するための装置です。しかし、聴覚データは、リアルタイムで聴覚野に送られ持続的に分析が行われるため、単純なパターン・マッチングにとどまらず、パターンがいくつも連なった(分節的な)音列を使うことによって、大量の情報をコードすることが可能になります。これが言語の起源です。文字で表された文を読む場合には、音読する際の口や舌の筋肉の動きを内的にイメージすることによって、視覚的な記号列を聴覚的なデータに変換し、その上で持続的な処理を行っています。
当然のことながら、単純な視覚的パターンで表現できるような情報は、視覚データとして与えた方が容易に取得されます。三国志時代の勢力分布を覚えるには、長ったらしい文章を読むよりも、魏・蜀・呉が鼎立する様子を表した歴史地図を見る方が効果的でしょう。場合によっては、こうした視覚的パターンに、より複雑な情報を結びつけることもできます。最近の映画はストーリー重視のせいか印象的なシーンが減りましたが、古典的な作品は、『戦艦ポチョムキン』のオデッサ階段の場面(民衆弾圧のために降りてくる軍隊の足だけが描かれる)のように、シンボリックな表現(オデッサ階段のシーンは権力の非人間性を表す)として記憶に刻み込まれるショットに溢れています。とは言っても、さまざまな要素が複雑に組み合わされているため、ワンショットで提示可能な視覚的パターンに還元できないケースも、また限りなくあります。『アンナ・カレーニナ』における自殺直前のアンナの心境は、俳優が曖昧な表情を浮かべるだけの映画よりも、驚異的な表現力で延々と内面描写を続けるトルストイの文章の方が、心に迫ります。
画像・映像と文章は、情報を得るためのメディアとして、補完的な関係にあると言えるでしょう。どちらのメディアが情報を取得しやすいかは、情報の内容に依存しており、一般的な優劣は付けられません。特に、何かを学習する際には、一方に頼るよりも、両者を組み合わせるのが効果的だと考えられています。単に文章を黙読するだけではなく、映像・音声の教材を積極的に利用し、場合によっては声を出したり何らかの動作を行ったりして、異種感覚を同時に刺激するのが、良い結果を生むようです。
【Q&A目次に戻る】

「雷雲の中では鉛直方向に電荷の分離が起きており、下層部に蓄積された負電荷が放電されると稲妻になる」という説明は、多くの参考書に書かれていますが、なぜ電荷の分離が起きるかきちんと説明している文献は、ほとんど見あたりません。実は、いまなお、電荷の分離が生じる過程が完全に解明されたわけではなく、不明な点が数多く残されているのです。ここでは、最新の文献で「最も有力な説」とされているものを紹介します。
湿度の高い空気塊が気流に乗って上昇すると、凝結した水滴が衝突・合体を繰り返しながら成長していき、高度を増すうちに、氷結して比較的大きなアラレの粒子になります。こうしたアラレ粒子は、-10〜20℃で水分を多く含んだ領域に入ると、付近に多量に存在する小さな氷晶と頻繁に衝突します。ここで、適当な条件が整っていると、衝突した粒子間で電荷が移動して、氷晶が正に、アラレ粒子が負に帯電すると考えられています。
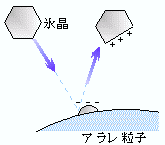
電荷が移動する過程は、次のように説明されます
(これは、1978年に高橋劭が発表した着氷電荷生成理論に基づくものです)。小さな氷晶が固く凝固したアラレの表面にぶつかると、衝突のエネルギーが熱に変換され、熱容量の小さな氷晶の表面がわずかに溶けて、薄い水の膜ができます。液相では水分子が解離して OH
- と H
+ になりますが、H
+ が氷の結晶に入り込んでつなぎ止められるのに対して、 OH
- は速やかに水中に拡がっていくため、水膜はわずかに負に帯電しています。この水膜が氷晶からアラレ粒子の表面に飛び散って氷結するため、アラレ粒子は負の、氷晶は正の電荷を帯びるようになるわけです。ただし、温度が高くてアラレ粒子の表面が溶けていると、衝突の際に OH
- を過剰に含む水分が飛び散るため、逆に、アラレの方が正に帯電することもあります。充分に強い上昇気流によって空気塊が高高度の低温領域にまで吹き上げられないとカミナリが起きにくいのは、そのためです。
上昇気流が弱まると、大きくなりすぎたアラレ粒子は落下を始めますが、小さな氷晶は高高度の領域に留まるので、雲の上方には正に帯電した粒子が、下方には負に帯電した粒子が集まり、雷雲特有の電荷の分離が生じます。電荷の分離にはエネルギーが必要ですが、これは、上昇気流によって供給されたことになります。
電荷分離に関する上の理論は、低温の風洞内に着氷棒を設置した実験で定性的に成り立つことが確かめられているものの、定量的には、雷雲内部の電荷分布を説明することができません。水滴に溶け込んでいる不純物や、氷表面の結晶構造が関与している可能性も指摘されています。カミナリの発生を予測できると災害防止にも役立てられるので、現在、雷雲中の電荷分布の実測、風洞などを用いた実験、氷表面の物性に関する理論的研究が精力的に続けられています。
【参考文献】『大気電気学概論』(日本大気電気学会編、コロナ社)
【Q&A目次に戻る】

30年ほど前には、コンピュータが進歩すれば天気も相場も高い精度で予想できるようになると考える学者がいました。しかし、コンピュータの性能が大幅に向上した現在でも、なかなかうまくいきません。
それでも天気に関しては、1週間程度の短期的な予報はかなり的中するようになりました。これは、天気図のパターンを分類し、過去のデータと比較して予想することが可能だからです(ただし、大気循環モデルなどに基づく数値的な計算の信頼性は乏しく、6ヶ月以上の長期予報は、ほとんど当てになりません)。
これに対して、株や為替の相場を売買に役立てられる精度で予想するのは、不可能に近いと言えるでしょう。天候の変化が気圧・降水量・気温・風向など比較的少数の数値パラメータと強い相関を持っているのとは異なり、相場に関与するパラメータの数が膨大なものになる上、数値だけでは評価できないケースが多々あるためです。例えば、損切りで製品を出荷している場合は売上高が増加しても企業業績としては低迷していますし、あまり儲かりすぎると不安になって売りに転じるといった投資家心理が働くこともあります。「総弱気は買い、総強気は売り」などの相場師の格言もありますが、こうした状況をパターンごとに分類したり数値的なモデルで表すのは、現実問題として困難です。
なお、相場に関する信頼に足る数学的なモデルが存在していないので、「相場がカオス的な振舞いをするため予測困難だ」という主張は正当ではありません。
数学的に可能なのは、経済が順調に推移している(=経済成長は続いているが構造変動は表面化していない)ような状況下で、数百億円以上の多額の資金を運用する際に、多数の投資対象から最適な組み合わせを選び出すことでしょう。このとき、利得の期待値を予想するために、円のレートなどの少数のパラメータと企業業績の相関関係が利用されますが、あくまで「円高になったときは××程度の利得が、円安のときは○○程度の利得が期待される」のように組み合わせ全体の利得/損失が求められるだけです。もちろん、戦争やテロ、革新的な技術開発、経済制裁の発動など、予想外の事件が出来して、多大な損失を被る可能性も否定できません。
20世紀末にアメリカを中心として「金融工学」と呼ばれる学問が急激に普及し、高等数学を利用すれば確実な資産形成が可能になるという楽観的な見方が生まれたこともあります。有名な例が、オプション取引に関するブラック=ショールズの公式で、この式を使えば、理論的にはリスクのない取引が可能になると言われました。ブラック=ショールズの公式を解説した教科書が、高度に専門的な数学の用語に満ちあふれ、一般の経済人にはあまりに難解だったこともあって、何か深遠な意味のある公式だと思われたのかもしれません。しかし、私が解説をパラパラと見た限りでは、複雑そうに見えるのは確率微分方程式の一般論を論じている部分だけであり、肝心の経済学的な前提は驚くほど単純化されているようです。例えば、市場価格が幾何学的ブラウン運動に従う(価格の対数が正規分布する)といういささか疑わしい仮定が採用されており、大数の法則が成り立たないような異常事態──自然界ではまず起こらないが、情報が不均等に伝播する人間社会では十分に起こり得る──の下では、公式が役に立たなくなる可能性があります。そもそもブラック=ショールズの公式は、変数変換すると熱伝導方程式と同じ形になるものであり、複雑怪奇な人間の活動を熱と同程度に単純化していると言ったら言い過ぎでしょうか。それかあらぬか、ブラック=ショールズの公式を提唱・展開しノーベル経済学賞を受賞したショールズとマートンが参加していたロング・ターム・キャピタル・マネジメントは、1998年に破綻しています。
【Q&A目次に戻る】

人間が自己と環境の空間的な位置関係を認知するに当たっては、2つの視座を用いています。1つは、特定の物体が自分に対してどの位置にあるかを見る自己中心的な視座であり、もう1つが、外界を表す地図上で自分がどこに位置しているかを見る外界中心的な視座です。実は、この2つの視座は、、脳の異なる部位で処理された情報に基づいており、両者を調和させるには、かなり高度な作業が必要になります。
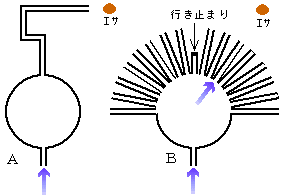
迷路の学習をさせたラットの場合、脳に微小電極を刺入して神経活動をモニターした結果、迷路内のある場所に来ると特定のニューロンが興奮することが判明しています。また、トールマンの古典的な実験(1948)では、図のAのセットアップでエサの位置を覚えさせたマウスをBの迷路に入れたとき、多くのマウスがエサへの最短で到達できる通路を選択したことが報告されています。こうしたことから、ネズミには、外界中心的な視座で自己および他の物体の位置関係を把握する能力があると推測されます。外界における物体の配置を表す地図は、一般に「認知地図」と呼ばれており、必ずしも現実空間での物体配置と幾何学的に同型ではありませんが、おおまかの位置関係は再現されています。人間の場合、馴染みの場所に関する記憶は側頭葉の海馬に格納されており、必要に応じて記憶を呼び出しながら、認知地図を構成しているものと考えられます。
一方、自己中心的な視座を構成する情報は、これとは異なる神経回路で処理されています。微小電極を刺入したサルに物体を提示する実験を通じて、方向や距離の情報を選択的に処理するニューロンが存在することが明らかにされましたが、人間にも同様に、視覚入力から空間的な情報を抽出する処理系が備わっており、「眼前に見える物体を掴むのに手をどれくらい伸ばせば良いか」といったことを判断するために利用されています。
異なる情報源から構成された自己中心的視座と外界中心的視座を調和させる作業は、大脳連合野で無意識のうちに行われていますが、決して簡単なものではありません。実際、町中を足早に歩いているとき、自分と環境の空間的な関係がどのように捉えられているか深く内省すると、自分の後方へと流れていく周囲の光景と、固定された環境の中を移動している自己のイメージが、必ずしも1つにまとまらず、異質なままで絡み合うように表象されている状況が感じられるのではないでしょうか。通り慣れた街路をそぞろ歩く場合、認知地図は周辺の比較的狭い範囲に限られ、目立つ建物や特徴的な看板などの“ランドマーク”を目にするたびに、記憶が呼び覚まされて地図が更新されていきます。ただし、認知地図の精度や更新の仕方には個人差が大きく、曲がり角など重要なポイント付近しか記憶に留めていない人もいれば、鳥瞰図のような広範囲にわたる幾何学的地図を脳裏に描いている人もいるでしょう。この差が、方向感覚の鈍さ/鋭さとなって現れると思われます。
自己中心的な情報が少ないとき、認知地図の内部に自分を定位できなくなることは、誰しも体験することです。地下鉄から交差点付近の出口に辿り着いたとき、何回か訪れた場所でも、どの道がどこに向かっているかわからなくなるのは、ごくありふれた現象です。また、デパートなどの閉鎖的なビル内部を歩き回っていると、当初は、鉄道の線路などとの位置関係を正しく把握していても、何度か角を曲がるうちに90°ないし180°ずれてイメージするようになることもあります。こうした錯覚を解消するには、意識的に遠方のランドマークに着目するのが効果的でしょう。
【参考文献】『方向オンチの科学』(新垣紀子著、講談社ブルーバックス)、『街角を曲る 人と空間の認知心理学』(大山俊男著、近代文芸社)
【Q&A目次に戻る】

質問にあるのは、おそらく、耐候性鋼を用いた橋梁だと思われます。
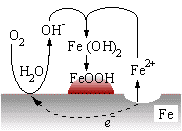
鉄の赤錆とは、水中に溶け出した鉄イオンが酸化され、水酸化第1鉄(Fe(OH)
2)、水酸化第2鉄(Fe(OH)
3)を経て、主にオキシ水酸化鉄(FeOOH)になったものですが、これは、いくつかの結晶型が混在する多孔性の状態であり、水分と酸素が透過して鉄の素地に達してしまうので、腐食は止まりません。鉄の構造物は、年0.02-0.08mm程度の割合で断面が減少し、強度不足に陥ります。こうした事態を避けるには防錆塗装を行うのが一般的ですが、10〜20年に1回の割合で塗り直しをしなければならず、建物によってはその費用がかなり高くつくため、腐食が進行しない耐候性鋼を用いることが多くなってきました。
金属で腐食の進行を抑制する役割を果たすのが、緻密で密着性の高い安定した錆(酸化物)の層です。例えば、ステンレスの場合は、クロムを含む厚さ数nmの酸化膜が表面に形成され、それ以上は錆が成長しません。戦前にUSスチール社で開発された耐候性鋼は、炭素鋼に微量の銅やクロムなどを添加したもので、表面の赤錆の内側に安定したマグネタイト(Fe
3O
4; 黒錆)の層が形成され、腐食の進行を抑えると言われています(通常の鉄でも、錆コブの内側などで赤錆が還元されて黒錆になっていますが、鉄の素地から剥離してくるため、腐食を食い止めることはできません)。建造物に使用された耐候性鋼の場合、数年〜10年で安定した錆の層が形成され、その後、100年以上にわたって防錆効果を維持するそうです。
耐候性鋼の建造物は、安定錆の層が形成される過程で表面に赤錆が生じ、錆汁がコンクリート床や橋脚を汚すため、一般にあまり見栄えが良くありません。また、排水・通気性の悪い部分や、海に近く塩分の多い地域では、耐食性が不十分になります。このため、従来は、塗り直しに手間のかかる山間部の橋梁など一部でしか利用されていませんでした。しかし、現在では、チタン・ニッケル・モリブデンなどを適度に添加し耐食性を大幅に向上させた鋼材が開発されたほか、錆汁による汚れを防ぐための表面加工や安定錆の成長を促進する表面処理も行われるようになっており、鋼橋全体の15%以上が耐候性鋼を使用するに至っています。
【参考文献】パンフレット「耐候性鋼の橋梁への適用」(日本鉄鋼連盟・日本橋梁建設協会)、『初歩から学ぶ防錆の科学』(藤井哲雄著、工業調査会)
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
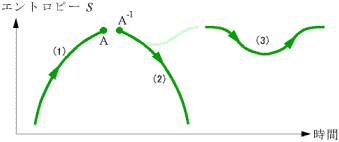 「熱湯+氷」の状態と「ぬるま湯」の状態を区別する良く知られた指標が、エントロピーSです。ごく単純化して言えば、エントロピーはシステムの乱雑さを表す量であり、「熱湯+氷」は(個々の水分子に分配されるエネルギーが均一ではなく大きな偏りがあるために)エントロピーが低い状態で、「ぬるま湯」はエントロピーが高い状態です。時間とともにエントロピーがどのように変化するかグラフに描くと、「熱湯+氷」から「ぬるま湯」の状態Aに変化する過程は(1)の軌道で、Aを時間反転した状態A-1から「熱湯+氷」に変化する過程は(2)の軌道で表されます。(1)のタイプの軌道と(2)のタイプの軌道は、さまざまな初期条件に対する運動方程式の解として同じ数だけ存在するので、水分子の運動が原理的に可能な過程の中からデタラメに選ばれるとすると、両者は同じ確率で実現されるはずです。
「熱湯+氷」の状態と「ぬるま湯」の状態を区別する良く知られた指標が、エントロピーSです。ごく単純化して言えば、エントロピーはシステムの乱雑さを表す量であり、「熱湯+氷」は(個々の水分子に分配されるエネルギーが均一ではなく大きな偏りがあるために)エントロピーが低い状態で、「ぬるま湯」はエントロピーが高い状態です。時間とともにエントロピーがどのように変化するかグラフに描くと、「熱湯+氷」から「ぬるま湯」の状態Aに変化する過程は(1)の軌道で、Aを時間反転した状態A-1から「熱湯+氷」に変化する過程は(2)の軌道で表されます。(1)のタイプの軌道と(2)のタイプの軌道は、さまざまな初期条件に対する運動方程式の解として同じ数だけ存在するので、水分子の運動が原理的に可能な過程の中からデタラメに選ばれるとすると、両者は同じ確率で実現されるはずです。
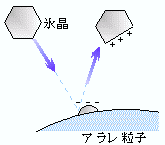 電荷が移動する過程は、次のように説明されます(これは、1978年に高橋劭が発表した着氷電荷生成理論に基づくものです)。小さな氷晶が固く凝固したアラレの表面にぶつかると、衝突のエネルギーが熱に変換され、熱容量の小さな氷晶の表面がわずかに溶けて、薄い水の膜ができます。液相では水分子が解離して OH- と H+ になりますが、H+ が氷の結晶に入り込んでつなぎ止められるのに対して、 OH- は速やかに水中に拡がっていくため、水膜はわずかに負に帯電しています。この水膜が氷晶からアラレ粒子の表面に飛び散って氷結するため、アラレ粒子は負の、氷晶は正の電荷を帯びるようになるわけです。ただし、温度が高くてアラレ粒子の表面が溶けていると、衝突の際に OH- を過剰に含む水分が飛び散るため、逆に、アラレの方が正に帯電することもあります。充分に強い上昇気流によって空気塊が高高度の低温領域にまで吹き上げられないとカミナリが起きにくいのは、そのためです。
電荷が移動する過程は、次のように説明されます(これは、1978年に高橋劭が発表した着氷電荷生成理論に基づくものです)。小さな氷晶が固く凝固したアラレの表面にぶつかると、衝突のエネルギーが熱に変換され、熱容量の小さな氷晶の表面がわずかに溶けて、薄い水の膜ができます。液相では水分子が解離して OH- と H+ になりますが、H+ が氷の結晶に入り込んでつなぎ止められるのに対して、 OH- は速やかに水中に拡がっていくため、水膜はわずかに負に帯電しています。この水膜が氷晶からアラレ粒子の表面に飛び散って氷結するため、アラレ粒子は負の、氷晶は正の電荷を帯びるようになるわけです。ただし、温度が高くてアラレ粒子の表面が溶けていると、衝突の際に OH- を過剰に含む水分が飛び散るため、逆に、アラレの方が正に帯電することもあります。充分に強い上昇気流によって空気塊が高高度の低温領域にまで吹き上げられないとカミナリが起きにくいのは、そのためです。
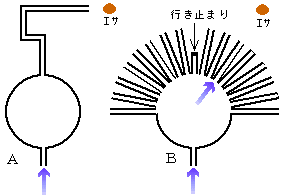 迷路の学習をさせたラットの場合、脳に微小電極を刺入して神経活動をモニターした結果、迷路内のある場所に来ると特定のニューロンが興奮することが判明しています。また、トールマンの古典的な実験(1948)では、図のAのセットアップでエサの位置を覚えさせたマウスをBの迷路に入れたとき、多くのマウスがエサへの最短で到達できる通路を選択したことが報告されています。こうしたことから、ネズミには、外界中心的な視座で自己および他の物体の位置関係を把握する能力があると推測されます。外界における物体の配置を表す地図は、一般に「認知地図」と呼ばれており、必ずしも現実空間での物体配置と幾何学的に同型ではありませんが、おおまかの位置関係は再現されています。人間の場合、馴染みの場所に関する記憶は側頭葉の海馬に格納されており、必要に応じて記憶を呼び出しながら、認知地図を構成しているものと考えられます。
迷路の学習をさせたラットの場合、脳に微小電極を刺入して神経活動をモニターした結果、迷路内のある場所に来ると特定のニューロンが興奮することが判明しています。また、トールマンの古典的な実験(1948)では、図のAのセットアップでエサの位置を覚えさせたマウスをBの迷路に入れたとき、多くのマウスがエサへの最短で到達できる通路を選択したことが報告されています。こうしたことから、ネズミには、外界中心的な視座で自己および他の物体の位置関係を把握する能力があると推測されます。外界における物体の配置を表す地図は、一般に「認知地図」と呼ばれており、必ずしも現実空間での物体配置と幾何学的に同型ではありませんが、おおまかの位置関係は再現されています。人間の場合、馴染みの場所に関する記憶は側頭葉の海馬に格納されており、必要に応じて記憶を呼び出しながら、認知地図を構成しているものと考えられます。
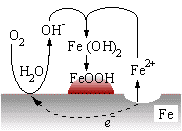 鉄の赤錆とは、水中に溶け出した鉄イオンが酸化され、水酸化第1鉄(Fe(OH)2)、水酸化第2鉄(Fe(OH)3)を経て、主にオキシ水酸化鉄(FeOOH)になったものですが、これは、いくつかの結晶型が混在する多孔性の状態であり、水分と酸素が透過して鉄の素地に達してしまうので、腐食は止まりません。鉄の構造物は、年0.02-0.08mm程度の割合で断面が減少し、強度不足に陥ります。こうした事態を避けるには防錆塗装を行うのが一般的ですが、10〜20年に1回の割合で塗り直しをしなければならず、建物によってはその費用がかなり高くつくため、腐食が進行しない耐候性鋼を用いることが多くなってきました。
鉄の赤錆とは、水中に溶け出した鉄イオンが酸化され、水酸化第1鉄(Fe(OH)2)、水酸化第2鉄(Fe(OH)3)を経て、主にオキシ水酸化鉄(FeOOH)になったものですが、これは、いくつかの結晶型が混在する多孔性の状態であり、水分と酸素が透過して鉄の素地に達してしまうので、腐食は止まりません。鉄の構造物は、年0.02-0.08mm程度の割合で断面が減少し、強度不足に陥ります。こうした事態を避けるには防錆塗装を行うのが一般的ですが、10〜20年に1回の割合で塗り直しをしなければならず、建物によってはその費用がかなり高くつくため、腐食が進行しない耐候性鋼を用いることが多くなってきました。