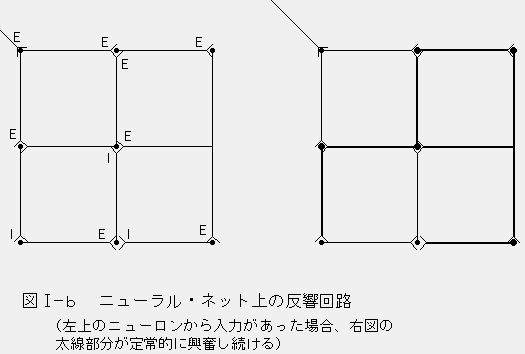《反響回路》と《観念》
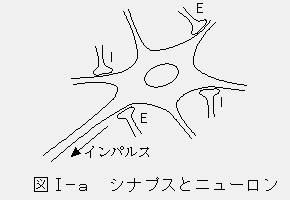 哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なまじ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解しやすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニューロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播していく過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナプスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じて、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図I‐a)。
哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なまじ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解しやすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニューロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播していく過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナプスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じて、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図I‐a)。
さて、適度に単純化したニューロンのネットワーク・モデルを想定し、ある興奮バターンが入力された場合を考えてみよう。このとき、回路上を伝達される信号は興奮性シナプスを介して伝わっていき、充分長い時間が経過した後には、全ての興奮が収まるか、または、周期的な興奮バターンが生じると予想される(図I−b)。後者のケースは、ネットワークの一部分をなす閉回路上を信号が繰り返し周回する《反響回路》が形成されることに対応している。こうしたモデル理論に見られる特徴を現実の大脳神経系にも敷術した場合、《反響回路》による(準)安定状態の発生を客体化作用における《観念》と結びつける発想は、きわめて自然である。
神経系に見られる《反響回路》と、認識過程で援用される《観念》とが類似しているのは、何よりも安定性という点においてである。すなわち、人間の思考はどこまでも生成流転を続ける訳ではなく、しばしば流れを止めて――「これは机だ」「あそこにいるのはポチだ」というように――諸事象を統括する観念を措定し、これを転機として新たな思考の流れを生み出している。このとき、個々の《観念》が瞬時のうちに変形されるほど脆弱であったり、ひとたび忘却するともはや再現するのが困難な1回限りのものであったとすると、思考は足を下ろすための立脚点を失ってしまうだろう。対象認識で利用される観念には、このような(状況の変化に対する)安定性が要求されることになる。ところが、神経系のモデルに見られる《反響回路》は、(最も理想的なケースでは)半永久的に周期的な興奮のバターンを示すことに加えて、ネットワークの配線やシナプス効率が変化しない限り、―定範囲の入力に対して同一の反響回路が形成されるという特徴があり、上の要求を基本的に満たしていると考えられる。
《反響回路》と《観念》の類似性は、さらに次の諸点においても指摘できる:
- 《反響回路》は、ネットワーク内部に特殊な配線があるときに限って実現される稀なケースであり、可能な入力バターン全てにわたって異なる反響回路を用意するのは困難なため、各安定状態に対して最終的にそこに収束していく入力バターンの数は一般に膨大なものとなる。ところが、こうした状況こそ、通常の対象認識において《観念》が導き出される過程と共通しているのである。実際、客体化作用によって対象を把握する場合は、いくつかの「弁別要素」の組によって一意的に判断を下すのではなく、複数の判定規則を(輪郭線の解析に曖昧な点が生じたのでテクスチュアに関する情報を活用するというように)状況に応じてストラテジックに適用しているため、特定の《観念》を引き出すトリガーとなる入力バターンには、《反響回路》の場合と似た冗長性が存在している。認識過程においては、こうした冗長性は、範型と若干の異同がある対象を認定する場合に重要となる。
- 《反響回路》は、閉じた部分での周回的な興奮バターンを示すだけではなく、開放された興奮性シナプスを介して周辺部へもシグナルを発信しており、これを受信した部位が、新たな興奮バターンを生み出すことも可能である。こうした状況を認識論の概念を使って読み換えれば、「それぞれの《観念》は、そこに端を発する特定の認識過程を随伴する」と表現できる。このような現象は、日常的には《観念》に由来する連想として実感されるもので、およそ思考と名付けられる過程には必ず含まれていると言っても過言ではない。例えば、幼児が「玩具」の《観念》に「自分を楽しませてくれるもの」という一般的な性質を付随させて把握するのも、《観念》に由来する連想の一種と解釈される。
- 《反響回路》は、部分的に重複させたり、「入れ子」状に構成することもできるが、これと類似した性質を《観念》の中に見いだすのは容易である。
《反響回路》と《観念》の類似性は、“強化”の概念を導入することによって、より完全なものとなる。すなわち、現実の神経系では、頻繁に信号が到達するシナプスは(おそらく細胞骨格レベルでの構造上の変化によって)信号伝達の効率を漸進的に高めていくため、繰り返して形成される《反響回路》は、次第に興奮しやすくなる傾向にある。このことは、人間の思考において、成長とともに《観念》が言わば「―人歩き」しはじめる状況と対応している。実際、幼い子供の場合は、何らかの《観念》を想起するためには、具体的な知覚情報がなければならないが、経験を積むにつれて当該《観念》が強化されるため、ごく僅かなキューによって想起が可能になり、遂には、言語的な連想だけで観念を操れるようになる。この段階に達すると、《観念》は純粋に言語的な意味連関に基づくネットワークを構成するようになり、知覚情報を整理する過程としての客体化の作用からは乖離する。しかし、このことによって《観念》そのものが変質する訳ではなく、当初に有していた諸性質の多くがなお保持されることは論をまたない。
【項目リストに戻る】
【表紙に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
info@scitech.raindrop.jp
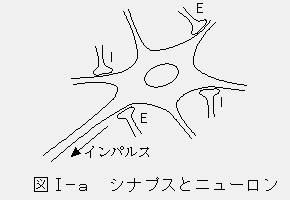 哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なまじ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解しやすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニューロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播していく過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナプスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じて、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図I‐a)。
哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なまじ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解しやすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニューロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播していく過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナプスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じて、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図I‐a)。