認知過程における《客体化》
人間による認知過程は、外界からの知覚情報が脳の各部位でさまざまな処理
を受けることによって成立している。このため、たとえ正常な意識の下で直感
的な知覚に即した対象認識を行ったとしても、外界の状態がそのまま模写され
ている訳ではなく、言わば認知のフィルターを通して変形された像となってい
る。仮に、高速フーリエ変換を行うコンピューターとして作動する脳を想定す
れば、その意識内部において目の前にありありと小石が見えたとしても、現実
に“存在する”のはその運動量の方なのであって、座標空間の中に定位されて
いる姿は、実は、フーリエ変換を通して見た“虚像”にすぎない。素朴な(だ
が、必ずしも正鵠を射ていない)理解に従えば、こうした《認知のフィルター》
の介入が、いわゆる《物自体》の認識を不可能にしていると言えよう。
しかし、当然のことながら、認知過程における変形によって本来の姿が跡形
もなく歪められてしまうとは考えられず、対象認識は多かれ少なかれ外界の状
況を反映しているはずである。もし、《認知のフィルター》が単なる情報の変
換を行う機構にすぎないならば、手持ちの対象認識に対して逆変換を施すこと
によって、外界に関する“真の”情報が得られると期待できよう。いくつかの
限られた認知については、こうした変換/逆変換の対応関係を見いだすことが
可能である。具体的には、視覚的認知における《色彩》を思い起こすとわかり
やすいだろう。物理学の知見に従えば、人間の網膜に投射される光線は幅広い
連続的なスペクトルを有しているが、光を受容するタンバク質(=ロドプシン)
の吸収帯のピークが赤/青/緑に対応する3つしかないため、視知覚として現
れる像はこの3原色から構成された色彩に限られることになる。物理的には波
長がなめらかに変化しているはずの虹が、いくつかの色の帯として見えるのは、
こうした理由による。したがって、視知覚をもとにして“真の”世界を再構成
するためには、直感的な色の区分に依拠する判断を「括弧でくくった」上で、
光学的な計測によって求められる波長の値を個々の視覚像に重ねるようにして
イメージすれば良い。このほか、触覚や嗅覚などに由来する知覚像においても、
いくつかの性質に関しては、《色彩》の場合と同様に《認知のフィルター》に
よる情報の変形を取り除くことが可能である。
それでは、このような逆変換を通じて、人間は《物自体》の世界にどこまで
も漸近していけるのだろうか。ここで問題となるのは、
- 認知過程において本来の情報がどこまで簡約化されているか
- 認識を成立させるための《カテゴリー》は充分に多様であるか
の2点である。
(i)については、「解像力の乏しいTV受像機では物が良く見えない」という
自明の理を取り上げているだけなので、説明を要しないだろう。これに対し
て、(ii)はより原理的な問題を議論の対象とする。すなわち、はたして人間には
情報の簡約化を補償して《物自体》の世界を(ある程度)復元するだけの知的
能力があるのか――という問題である。確かに、もし思考の「型」となる《カ
テゴリー》自体が貧困ならば、手持ちの知識をどのように組み合わせても、所
詮は人間の思考の枠組みを越えられないだろう。いささか突飛な警え話によっ
て、この間の事情を説明しよう。こんにちNTTなどで使用されているような
電話回線用のディジタル交換機が突如として意識に目覚めたとしても、「彼」
にはこの世界の何たるかがほとんど理解できないだろう。実際、電話交換機の
内部状態としては、呼び出し待ちや回線の探索作業などいくつかの限られたバ
ターンしか存在せず、しかも、各状態間での遷移――呼び出された回線の探
索を終了して通話状態に移るといった――が行われるためのキューはあらか
じめ設定されている。このため、(意識を持っている)交換機が認識を展開す
るに当たっての「型」ないし《カテゴリー》も、ごく僅かの種類しか用意でき
ないことになる。例えば、特定の呼び出し番号を(交換機にとっての)ある概
念と見なすと、この概念を含む認識過程は、当該番号の回線を探り出して接続
するか、探索に失敗して「その番号は使われていません」というメッセージを
送り返すか――という2つの《カテゴリー》に限定されてしまう。いかに多
数の回線を処理できる能力を持った交換機であっても、認識を組み立てる道具
立てがこのように乏しければ、複雑な世界情勢について思索するのはそもそも
不可能であろう。もちろん、人間の脳は、きわめて多数の内部状態を有する情
報処理マシンであり、その能力はディジタル交換機とは比較にならないほど巨
大である。しかし、《認識》が成立するためには、単に脳の内部で複雑な情報
の変換が行われるだけでなく、これを適当な《カテゴリー》をもとに分節する
作業がなされなければならない。もし、そのときに援用される《カテゴリー》
自体がきわめて貧困ならば、《認知のフィルター》を取り除こうとしてさまざ
まな逆変換の作業を試みたとしても、結局は人間に許された思考の領域を脱す
ることはできず、《物自体》への接近は不可能となる。これが、(ii)で提示した
問題である。
結論から先に言えば、対象の認知によって成立する《存在者》の認識に関す
る限り、人間が用いている《カテゴリー》は種類の面でも機能面でもきわめて
貧しく、しかも、外界の状況よりも人間の側の都合を優先して規定されている。
したがって、こうした《カテゴリー》に基づく存在認識が直接的に外界と対応
しているとは到底考えられず、この枠組みの中で《実在》についの議論を展開
することは不毛だと言わざるを得ない。この点について、以下の論述でより詳
しく見ていこう。
《実体化》作用と存在認識
幼少の頃を思い起こせば、誰しも自分が徹底した“実在論者”として振舞っ
ていた記憶があるだろう。すなわち、幼児にとっては、玩具にせよ母親にせよ、
その基本的な現れ方が変化することは予想されておらず、玩具は常に喜びをも
たらし、母親は常に慈しんでくれる存在であり続けると感じられるのである。
このように「認識対象は、自分との関係における基本的な性質を不変に保つ」
とする見解が、おそらく最も素朴な《実在論》だろう。もちろん、日常経験を
積み重ねていくうちに、素朴な実在論は、現実によって手厳しく裏切られるこ
とになる。実際、玩具はしばしば壊れて思い通りに動かなくなるし、母親が時
に激しく叱責して体罰を科す場合もある。こうした体験を通じて、人は、不変
な性質を備えているのが、外界の対象ではなく心の中の《観念》の方だと、い
やでも気づかされるのである。しかし、不変的な《観念》を通じて対象を把握
するという思考法それ自体が、成長と共にそう簡単に失われる訳ではあるまい。
ここでは、外界からの複雑な知覚情報を状況に応じて分節し、その中で安定な
部分を適当な《観念》によって統括する認知の方略を、《客体化》と呼ぶこと
にし、幼稚な実在論的世界観を脱したかに見える成人においても、存在認識が
成立するための鍵として《客体化》の作用が機能していることを示したい。
《客体化》の方略とは、簡単に言えば、全体の中から部分としての「もの」
を抽出していく手法である。例えば、網膜に映じる光学的な像が、2次元方向
にべったりと拡がっているのに対して、認知された視知覚においては、「机」
や「椅子」などが個別的な存在として浮き上がるように把握できるが、これ
は、《客体化》を通じて、それぞれの対象物を背景から抜き出す操作が無意識
のうちに行われるからである。少し内省すれば簡単に納得できるように、《客
体化》とは、用意されたテンプレートと照合する単純なバターン認識に還元で
きるものではなく、無数の細かな判定規則の組み合わせから成る総合的な作業
である。個々の規則としては、「同一の形態が時間とともに僅かに異なった位
置に提示される場合は、同じ物体の移動として統括できる」というごく基本的
なルールから、破損を免れた手がかりをもとに残骸から元の物体を再構築する
ための経験的な推定法に到るまで、さまざまなものがある。しかも、このよう
な膨大な数のルールは、状況に応じてストラテジックに――すなわち、それ
ぞれの適用法をあらかじめ定めておくのではなく、(「このケースではまず輪
郭線の分析を」、「このケースでは運動の変化に着目して」というように)各
時点で最適な手順を考案しながら――適用されている。このような作業を通
じてはじめて、対象を個別的な「もの」として把握する《客体化》が実行され
るのである。
上に述べたような《客体化》が対象を認識する過程で実際に行われている証
拠は、常に対象を名指しできるという人間の基本的能力のうちに見いだされる。
もちろん、単に「名指し」と言っても、「犬」や「レストラン」のように抽象
性の高い名辞を用いる場合から、「(わが家の)ポチ」とか「(3丁目の)来々
軒」といった具体的な固有名詞を使う場合までさまざまであるが、これらの用
法を峻別する必要性はない。なぜなら、たとえ固有名詞を用いようとも、そも
そも名指しを行う時点で対象にかかわる情報をかなりの程度まで捨象してい
る――「わき腹に泥をつけて裏の土手を歩いていた3時14分のポチ」を名指し
する固有名詞は存在しない――以上、抽象性/具象性の差異は、単なる程度
問題にすぎないからである。このように考えると、「名指し」とは、対象を(多
かれ少なかれ)抽象化された「もの」として観念的に取り扱う操作であること
がわかり、その背後に、全体の情報の中から適当な規則によって部分を抜き出
す《客体化》の作用を指摘できる。逆に言えば、《客体化》の基本的な特徴は、
音韻記号として表わされる名辞の存在を別にすれば、「名指し」の中に集約さ
れている。したがって、《客体化》を説明するのに、「あらわに名辞を用いな
い名指し」という発想をなぞって、「(必ずしも言語化されていない)《観念》
によって知覚情報の特定部分を統括する過程」と表現することが許されよう。
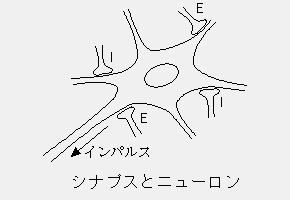 哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が
成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なま
じ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解し
やすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニュー
ロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の
回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播してい
く過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性
の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接
続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の
場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナ
プスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じ
て、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図)。
哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が
成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なま
じ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解し
やすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニュー
ロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の
回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播してい
く過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性
の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接
続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の
場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナ
プスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じ
て、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図)。
さて、適度に単純化したニューロンのネットワーク・モデルを想定し、ある
興奮バターンが入力された場合を考えてみよう。このとき、回路上を伝達
される信号は興奮性シナプスを介して伝わっていき、充分長い時間が経過した
後には、全ての興奮が収まるか、または、周期的な興奮バターンが生じると予
想される。後者のケースは、ネットワークの一部分をなす閉回
路上を信号が繰り返し周回する《反響回路》が形成されることに対応している。
こうしたモデル理論に見られる特徴を現実の大脳神経系にも敷術した場合、《反
響回路》による(準)安定状態の発生を《客体化》作用における《観念》と結
びつける発想は、きわめて自然である。
神経系に見られる《反響回路》と、認識過程で援用される《観念》とが類似
しているのは、何よりも安定性という点においてである。すなわち、人間の思
考はどこまでも生成流転を続ける訳ではなく、しばしば流れを止めて――「こ
れは机だ」「あそこにいるのはポチだ」というように――諸事象を統括する《観
念》を措定し、これを転機として新たな思考の流れを生み出している。このと
き、個々の《観念》が瞬時のうちに変形されるほど脆弱であったり、ひとたび
忘却するともはや再現するのが困難な1回限りのものであったとすると、思考
は足を下ろすための立脚点を失ってしまうだろう。対象認識で利用される《観
念》には、このような(状況の変化に対する)安定性が要求されることになる。
ところが、神経系のモデルに見られる《反響回路》は、(最も理想的なケース
では)半永久的に周期的な興奮のバターンを示すことに加えて、ネットワーク
の配線やシナプス効率が変化しない限り、―定範囲の入力に対して同一の《反
響回路》が形成されるという特徴があり、上の要求を基本的に満たしていると
考えられる。
《反響回路》と《観念》の類似性は、さらに次の諸点においても指摘できる:
- 《反響回路》は、ネットワーク内部に特殊な配線があるときに限って実
現される稀なケースであり、可能な入力バターン全てにわたって異なる《反
響回路》を用意するのは困難なため、各安定状態に対して最終的にそこに
収束していく入力バターンの数は一般に膨大なものとなる。ところが、こ
うした状況こそ、通常の対象認識において《観念》が導き出される過程と
共通しているのである。実際、《客体化》作用によって対象を把握する場
合は、いくつかの《弁別要素》の組によって一意的に判断を下すのではな
く、複数の判定規則を(輪郭線の解析に曖昧な点が生じたのでテクスチュ
アに関する情報を活用するというように)状況に応じてストラテジックに
適用しているため、特定の《観念》を引き出すトリガーとなる入力バター
ンには、《反響回路》の場合と似た冗長性が存在している。認識過程にお
いては、こうした冗長性は、範型と若干の異同がある対象を認定する場合
に重要となる。
- 《反響回路》は、閉じた部分での周回的な興奮バターンを示すだけでは
なく、開放された興奮性シナプスを介して周辺部へもシグナルを発信して
おり、これを受信した部位が、新たな興奮バターンを生み出すことも可能
である。こうした状況を認識論の概念を使って読み換えれば、「それぞれ
の《観念》は、そこに端を発する特定の認識過程を随伴する」と表現でき
る。このような現象は、日常的には《観念》に由来する連想として実感さ
れるもので、およそ思考と名付けられる過程には必ず含まれていると言っ
ても過言ではない。例えば、幼児が「玩具」の観念に「自分を楽しませて
くれるもの」という一般的な性質を付随させて把握するのも、《観念》に
由来する連想の一種と解釈される。
- 《反響回路》は、部分的に重複させたり、「入れ子」状に構成すること
もできるが、これと類似した性質を《観念》の中に見いだすのは容易であ
る。
《反響回路》と《観念》の類似性は、《強化》の概念を導入することによっ
て、より完全なものとなる。すなわち、現実の神経系では、頻繁に信号が到達
するシナプスは(おそらく細胞骨格レベルでの構造上の変化によって)信号伝
達の効率を漸進的に高めていくため、繰り返して形成される《反響回路》は、
次第に興奮しやすくなる傾向にある。このことは、人間の思考において、成長
とともに《観念》が言わば「一人歩き」しはじめる状況と対応している。実際、
幼い子供の場合は、何らかの《観念》を想起するためには、具体的な知覚情報
がなければならないが、経験を積むにつれて当該《観念》が強化されるため、
ごく僅かなキューによって想起が可能になり、遂には、言語的な連想だけで《観
念》を操れるようになる。この段階に達すると、《観念》は純粋に言語的な意
味連関に基づくネットワークを構成するようになり、知覚情報を整理する過程
としての《客体化》の作用からは乖離する。しかし、このことによって《観念》
そのものが変質する訳ではなく、当初に有していた諸性質の多くがなお保持さ
れることは論をまたない。
以上、《客体化》の作用を、神経系の議論と比較しながら長々と議論してき
たが、その主たる目的は、認識過程の実態的な解明ではなく、人間の思考様式
がいかに制限されているかを示すことである。実際に、これまでの議論で使わ
れた《反響回路》の説明は、あまりに単純化されたモデルに依拠しているため、
脳神経系のようなきわめて複雑なシステムに適用できるか疑わしい。現実の神
経系は、シナプスの効率が時間と共に変化するなど、ここでは無視されている
多くの特徴を持っており、果して周期的な信号の伝達を示す(準)安定状態が
生じるかどうかは明らかでないからである。しかし、このような単純なモデル
が、多くの点で人間の観念的な思考と類似性を持っているという事実は、認識
能力に存する限界を見極める上で示唆的である。
【項目リストに戻る】
【表紙に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
info@scitech.raindrop.jp
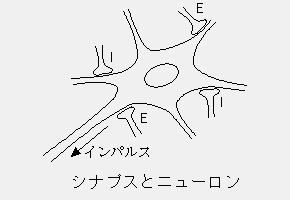 哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が
成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なま
じ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解し
やすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニュー
ロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の
回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播してい
く過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性
の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接
続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の
場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナ
プスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じ
て、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図)。
哲学者は、繰り返し、刻々と変化する知覚をもとにして普遍的な《観念》が
成立する契機は何かという疑問を表明してきたが、この問題については、なま
じ観念論的な議論をするよりも、神経生理学の枠組みの中で考える方が理解し
やすいだろう。よく知られているように、人間の脳の基本的な機能は、ニュー
ロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを中継点として構成するネットワーク状の
回路に担われており、電気化学的な“興奮”がこの回路上を次々と伝播してい
く過程を通じて諸々の精神的作業が遂行される。シナプスには興奮性と抑制性
の2種類があり、興奮性シナプス(E)にインバルスが到達すると、これに接
続しているニューロンを興奮させる作用が生じるが、抑制性シナプス(I)の
場合は反対に興奮を抑えようとする。通常、1つのニューロンには複数のシナ
プスが結合しており、各シナプスからの興奮性/抑制性作用のバランスに応じ
て、当該ニューロンが興奮するか否かが決定される(図)。