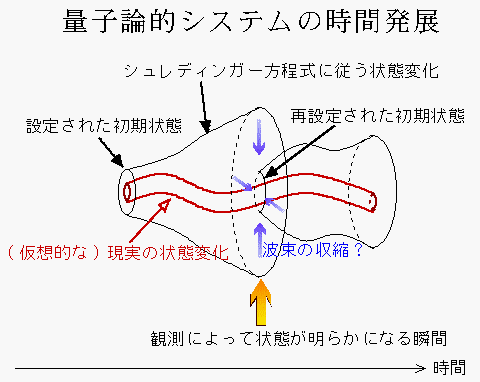「時間が流れない」という主張への批判
《未来》や《過去》も《現在》と同様に実在すると見なす立場は、物理学的に容認できる唯一の時間観だと考えられる。にもかかわらず、―般の人の目には、この見解はきわめて奇異で非常識なものと映るに相違なく、これに対してさまざまな批判が寄せられるであろう。ここでは、こうした批判のいくつかを筆者なりに予想し、それに対して改めて反論を加えてみたい。
-
■素朴な批判
-
人間は、生き生きとした実存の直感をもとにして、《現在》とそれ以外の時刻を区別することができる。その存在資格において《過去》や《未来》が《現在》と同等であるとは、到底信じられない。
-
□反論
-
「生き生きとした」実感が時間軸上のどの時刻にあったとしても、論理的に矛盾は生じない。実際、こうした感覚は、脳神経が特定の興奮バターンを描いたときに派生するものと考えられ、当該パターンが《過去》あるいは《未来》の任意の時刻に誰かの脳内部で生じた場合は、そこで実存の直感が得られているはずである。それでも納得できず、自分という人間は《現在》にのみ生きており、《過去》や《未来》において《現在》と同様に笑ったり泣いたりしている自己が生きているとは信じられないと主張する者もあるかもしれないが、その場合は次のように考えられたい。すなわち、空間的に隔たった人間が自己とは別個の存在で生の実感を共有できないことを誰も怪しまない。それと同様に、時間的に隔たった人間は、たとえ肉体の生物学的な連続性があったとしても、実存としては截然と分かれた他者にすぎない。したがって、《過去》あるいは《未来》の自己の存在があまりによそよそしく共感が持てないと思われても、それは当然なのである。
-
■情報理論的な批判
-
統計力学によれば、情報の欠如を表す量であるエントロビーは、孤立系においては単調に増大するため、情報は時間の経過とともに次第に失われていくはずである。したがって、低エントロビー状態にあった《過去》の記憶は必然的に忘却の淵に沈んでいき、逆に《現在》よりも少ない情報量で記述できるはずの《未来》の方が容易に予想できなければならない。ところが、現実には、《過去》の事件は何らかの痕跡を残すため、その事実内容に関して高い信憑性を持った言明を提出するのはそれほど困難ではないが、《未来》の事跡を《現在》の中に見いだすのは不可能であり、単なる予測を越えて「来たるべき事実」について語る手段は存在しない。卑近な例を挙げると、われわれは自分がいつ生まれたかを知っているが、いつ死ぬかとなると確実なことは何もわからないのが実状である。このように、《過去》と《未来》の情報に関する熱力学の主張が観察事実と食い違っているのは、統計力学に含意されていない物理的な事情によって《過去》と《未来》の間で情報の確定度が本質的に異なっているためであり、両者を同等に取り扱う時間観は首肯しがたい。
-
□反論
-
現実の世界には、統計力学がそのまま適用できるような孤立系はまれであり、表面上の矛盾が生じてもおかしくはない。例えば、摩擦のある振動系ではエントロピーが単調に増大して非可逆的に静止状態に漸近していくが、これほど単純なシステムは、現実にはほとんど存在しない。特に、生物個体の場合は、生命維持のため食物として高分子化合物を摂取し続ける以上、いわゆる「負のエントロピー」が継続的に流入している開放系に相当するため、エントロピーが極大となる《死》に到達するまでの間に(初期状態よりも高度に組織化されたものも含めて)さまざまな中間状態を経ていくのはきわめて当然の事態である。したがって、こうした生物体の一種である人間にとっても、《未来》が《現在》より情報量が有意に乏しい訳ではなく、どのような中間状態を経ていくか――自分がどのような運命を辿るか――予言できなくても不思議はない。
ただし、《現在》に《過去》の痕跡が残っている理由を説明するには、相互作用の具体的な形式に言及する必要がある。現実の世界には、結晶や高分子のように量子効果によって安定化された構造があり、その中に《過去》の出来事が「刻み込まれる」ことによって、周囲に生じる変動に抗して(ある程度の期間は)痕跡が維持される。生命現象においては、脂質の疎水基を内側に向い合わせにした二重の膜構造(脂質二重層)が水中で安定な構造をとり、脂質分子の置換やタンバク質分子などの透過があっても二重層自体は破壊されにくいため、この二重層によって形成されている細胞膜のトポロジカルな構造は、(膜タンバク質や微小管からの作用もあって)細胞の応力変形や生体分子の代謝過程を通じて保存される傾向にある。したがって、生体器官における多数の細胞の相互的な位置関係のようなトポロジーの中に《過去》の情報が刻み込まれるならば、この《エングラム(記憶痕跡)》は生体活動のタイムスパンから見て相当に長い期間にわたって安定に保たれる。これが、(素朴に解釈された)統計力学の予想に反して《過去》の記憶が保存されるメカニズムである。
-
■物理学的な批判
-
量子力学における観測過程のフォーマリズムは、(基礎過程に関する)物理学理論の中で、唯一、時間に対する取り扱いが他と異なっており、シュレディンガー方程式に則って滑らかに変化してきた波動関数が、観測を行った瞬間に、非連続的・非因果的に特定の(分散のない)状態に収縮したように表される。これを素直に解釈すれば、人間を含む巨視的装置によって観測が行われる瞬間が《現在》を表し、波動関数の形で確率振幅だけが与えられる状態は変更可能な《未来》を、波動関数が収縮して確定した状態は変更不能な《過去》を、それぞれ表現していることになる。
-
□反論
-
観測過程における非連続的な変化は、かつては《波束の収縮》と呼ばれ、観測を行う知的存在が物理系に影響を及ぼす過程ではないかと主張する人も現れたほどミステリアスだったが、現在では、こうした変化が物理的なプロセスとして生起しているのではないという点は了解されている。
量子論的なシステムでの時間発展を、シュレディンガー方程式に従う連続的・因果的変化と、観測過程における非連続的・非因果的な変化に分けるという分類法は、量子力学が定式化された初期の頃から行われてきた(J.von Neumann : "Mathmatische Grundlagen der Quantenmechanik" (Springer,1932))。しかし、この分類は、時間を引数とする関数φ(t)(不要な引数・添字は省略した)によってシステムを記述しようとするときに必要になる便宜的なものであって、理論的必然性に基づいて要請される訳ではない。量子力学においては、理論に内在する本質的な非因果性のために、状態の変化を完全に跡づけるような方程式は存在せず、あくまで系の統計的な振舞いを予測することだけが可能になっている。従って、シュレディンガー方程式の解として与えられる波動関数φ(t)は、ある時刻で系の状態の近似的な表現になるように設定されていたとしても、そこからの時間間隔が開くにつれて、現実の状態からのずれが拡大していく。そこで、観測によって系の状態が明らかになった場合は、それを新たな初期条件として波動関数を再設定しなければならない。この結果、表現の上では、観測を行うたびに波動関数が収縮するように見えることになるのだ(下図参照;ただし、「現実の状態」は模式的に描いている)。
観測に関する上の解釈の妥当性は、技術開発の現場で検証することができる。すなわち、もしシュレディンガー方程式に従わない《波束の収縮》が現実に起きるならば、量子効果を利用した各種測定装置(量子干渉計など)はその効果をまともに受けるため、この過程が装置に及ばす影響を勘案しない限り測定時の動作が保証されないはずである。ところが、実際には、開発・設計の段階でこうした効果は無視されているにもかかわらず、量子デバイスはきわめて良い精度で機能することが知られている。これは、《波束の収縮》が現実に生起する物理的なプロセスではないことを示す。
このように、量子力学においても、(観測前の)未定の状態にある《未来》と、(観測によって)状態が確定した《過去》とが、物理的に峻別されている訳ではない。もちろん、今後に解決が委ねられている量子力学固有の問題――特に、「現実の状態」を想定することの理論的正当化――は数多くあるが、少なくとも、量子力学が《過去》と《未来》の間にくさびを打ち込むものでないという結論は揺るがないだろう。
ここまでの議論を総合すれば、こんにちの物理学的な時間観として、《過去》から《未来》まで同じように実在していると見なす「拡がった時間」という見解が妥当であると結論できる。物理学に馴染みのない読者の中には、この議論があまりに常識はずれだと感じられ、そこに到る論証を一種の詭弁だと断じる者もいるだろう。しかし、この結論そのものは、物理学の専門家にとっては“当り前”にすぎて、一時的にせよこれを否定した論述を進めること自体、ひどく苦痛に感じられる程なのである。その理由は、次のようなものである。
第1に、相対性理論によれば、時間と空間は1つの多様体を構成する要素として局所的には同質であり、ただ境界条件(時間の始点にはビッグバンがあるが、空間的には周期的または漸近的境界条件に従っている)と次元数(時間が1次元で空間が3ないしそれ以上の次元から成る)によってのみ区別される。従って、空間の中にさまざまな地形や構造物が「事実として」存在しているように、《過去》あるいは《未来》に向かう時間軸に沿っていろいろな事象が並列的に存していると考えても、何ら奇妙な点はない。《未来》に何か訪れるか分からないのは、ちょうど扉の向こう側に何があるか知る方法がないのと同じなのである。
第2に、現在の物理学のパラダイムには、何か「になる(to become)」過程を記述する概念枠が存在せず、理論の取り扱いの対象となるのは、物理量がある値「である(to be)」ような状態に限られることを指摘したい。物理学の理論とは、状態を指定する適当なデータを与えればあとは自律的に結論を導出できる機械的なモデルであり、ある科学的命題が実在的か否かは、(理論の正当性を別にすれば)これを求めるのに使ったデータの確実性のみに依存している。このため、日常的な文脈で「《未来》の状態は未定である」と主張しても、これを科学的に解釈しようとする局面では、単にインプットすべきデータが得られないという状況説明に落着するだけで、未定の状態を予言する理論形式を構成することは現代科学のパラダイムにおいては不可能である。有り体にに言えば、物理学的な理論の内部では、対象の実在性に差をつける手がかりがないのである。それだけに、一般の物理学者にとっては、現行の物理学の枠組みを根本的に否定してまで《過去》と《未来》とが《実在度》において《現在》と異なっているとは主張できないのだろう。
【項目リストに戻る】
【表紙に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
info@scitech.raindrop.jp